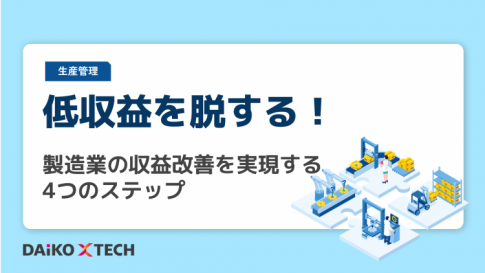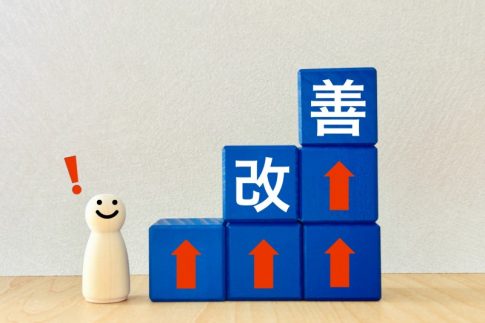2025年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、全企業で「熱中症対策」が義務化されました。
これからの暑い季節、労働者の安全と健康を守るために、職場における熱中症対策の強化が必要です。
本記事では、熱中症対策の義務化の対象や、今回のルール変更で具体的に企業はどのような対応をする必要があるのかについて解説していきます。
目次
2025年6月1日から義務化された熱中症対策

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が企業の義務として施行されました。
これまで努力義務にとどまっていた熱中症予防措置が、法的な責任として位置づけられました。
6月から熱中症対策が義務化となる作業内容

熱中症対策の義務化対象は、以下の表に示す環境条件と作業時間の両方を満たす場合です。
|
項目 |
条件 |
|
環境条件 |
WBGT値28℃以上または気温31℃以上 |
|
作業時間 |
連続1時間以上または1日4時間以上 |
|
対象範囲 |
全業種・屋内外問わず |
WBGT値(暑さ指数)とは
WBGT値は1954年にアメリカで開発された熱中症予防指標で、単純な気温とは異なる包括的な暑さの評価基準です。
WBGT値は、以下の3つの要素を総合的に評価して算出されます。
- 湿度:発汗による体温調節への影響度
- 輻射熱:日射や機械設備からの放射熱
- 気温:大気中の温度
気温とWBGT値の違い
気温が25℃でも湿度が高い環境では、WBGT値が28℃に達する場合があります。
これは人体が実際に感じる暑さをより正確に表現するためです。
製造業の工場内では、機械設備の稼働により輻射熱が発生するため、一般的な気温よりもWBGT値が高くなる傾向があります。
熱中症対策義務化の対象
製造業では以下のような作業環境が義務化の対象となる可能性があります。
- 機械設備周辺での作業:生産機械からの発熱により室温が上昇する環境
- 溶接・鋳造作業:高温の金属加工による輻射熱が発生する作業場
- 乾燥工程:製品の乾燥・焼成により高温多湿となる作業環境
- 倉庫・物流作業:空調設備が限定的で熱がこもりやすい環境
- 屋外での荷役作業:直射日光下での製品搬出入作業
熱中症対策の罰則規定
2025年6月1日から施行された改正労働安全衛生規則により、熱中症対策を怠った事業者には厳格な罰則が適用されます。
熱中症対策の義務に違反した法人には労働安全衛生法第122条により50万円以下の罰金が科されます。個人への処罰とは別に、法人としての責任も問われる両罰規定となっています。
行政処分
罰則に加えて、都道府県労働局長または労働基準監督署長から使用停止命令等の行政処分を受ける可能性があります。
具体的には作業の全部または一部停止、建設物の使用停止などが命じられ、事業運営に重大な影響を与えます。
工場の熱中症対策が重要な理由

工場は一般的なオフィス環境と比較して、熱中症リスクが格段に高い作業環境です。
2023年の職場における熱中症死傷者1,106人のうち、製造業は建設業に次いで多くの事故が発生しており、その背景には工場特有の構造的要因が深く関わっています。
製造業では屋内作業であっても、複数の環境要因が重なることで危険な高温環境が形成されます。
これらの要因を正しく理解し、適切な対策を講じることが、従業員の安全確保に欠かせません。
以下では、工場が熱中症の高リスク環境となる4つの主要な構造的要因について詳しく解説します。
熱が伝わりやすい建築構造である
工場の多くは金属製の屋根や壁を採用しており、外部からの熱が内部に伝わりやすい構造です。
特に夏場は、屋根の表面温度が70℃以上になることもあり、輻射熱が屋内に直接影響します。
断熱材が不十分な場合、熱がそのまま室内に侵入し、作業環境の温度上昇を招きます。
こうした構造的な特徴が、工場内の熱中症リスクを高める大きな要因です。
空調が効きにくく熱がこもりやすい
工場は広い空間や高い天井を持つことが多く、空調の冷気が全体に行き渡りにくい傾向があります。
加えて、大型設備や保管物が空気の流れを妨げ、換気が不十分になりがちです。
そのため、外気温や内部の熱源の影響を受けやすく、熱や湿気がこもりやすい環境が生まれます。
結果として、従業員の体温調節が難しくなり、熱中症の危険性が増加します。
出入口が広く室内温度の維持が難しい
工場では大型の出入口が設けられていることが多く、頻繁な開閉によって外気が流入しやすい環境です。
そのため、冷房や換気による温度管理が難しく、外部の高温が室内に直接影響します。
特に夏場は、外気の流入によって室温が上昇しやすく、安定した作業環境の維持が困難です。
機械熱によって室温が上昇する
工場内では多くの機械や設備が稼働しており、その運転によって大量の熱が発生します。
特に成型機や電気炉など高温を扱う設備がある場合、室温の上昇が顕著です。
さらに、密閉性の高い空間ではこの熱が逃げにくく、作業者の体温も上がりやすくなります。
機械熱は工場独特のリスク要因であり、熱中症対策の重要なポイントです。
企業に求められる熱中症対策

企業に求められる熱中症対策の重要性を理解し、具体的な行動へとつなげるためには、まず「見つける」「判断する」「対処する」の3つのステップが不可欠です。
これらを押さえることで、職場の安全性を高め、従業員の健康を守る最善策を講じましょう。
1.見つける
熱中症対策の第一段階は、症状の早期発見体制の構築です。
企業は熱中症の自覚症状がある作業者や、異変を発見した者からの報告を受ける明確な体制を整備する必要があります。
報告体制では、担当者や連絡先を事前に定め、関係作業者への周知を徹底することが重要です。
単に報告を待つだけでなく、事業者は積極的な発見に努める責任があります。
推奨される具体的な取り組みとして、以下のような例が挙げられます。
- 管理監督者による定期的な職場巡視と声かけ
- 二人一組で作業する「バディ制」の導入
- 作業者の体調変化を検知するウェアラブルデバイスの活用
- 作業者と管理者間での定期的な双方向連絡
これらの措置により、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの初期症状を見逃さず、重篤化を防ぐ体制を構築できます。
2.判断する
熱中症の疑いがある作業者を発見した際の迅速かつ的確な判断体制の整備が義務づけられています。
企業は事業場ごとに緊急連絡網、緊急搬送先の医療機関の連絡先および所在地を事前に作成し、関係作業者に周知する必要があります。
判断段階では、熱中症の重篤度を適切に評価し、必要な措置を決定する能力が重要です。
また、軽度の症状であっても「大丈夫だろう」という自己判断は禁物で、専門的な基準に基づいた客観的な評価が重要です。
特に製造業では、作業環境の特殊性により症状が急激に悪化する可能性があるため、迷った場合は救急隊要請や医療機関への相談を優先するといったように、判断基準を明確化することが必要です。
#7119(救急安全センター)の活用も推奨されており、専門家からの指示を仰ぐことで適切な判断ができます。
3.対処する
異常が確認された場合は、事前に定めた手順に従い、速やかに対処します。
作業者を安全な場所に移動させ、身体を冷やし、水分・塩分を補給しましょう。
必要に応じて医療機関への搬送を行い、経過観察も徹底します。
これらの対応手順は、全従業員に周知し、緊急時に誰もが適切に行動できるよう教育を徹底することが重要です。
特に重要なのは、本人が「大丈夫」と申し出ても異変を感じた場合は救急隊を要請することです。
製造業では機械設備の停止や作業中断が生産に影響するため、対処手順には代替要員の確保や作業継続の判断基準も含めることが実務上重要です。

- この記事を監修した人
- SMB向け業務システムのセールスエンジニアとしてキャリアをスタート。
400社以上の企業さまの販売管理・会計・給与システム導入に関与。
その後、さまざまなBtoB向けソリューションの企画・販促に携わり、SEO、MEOにも精通。
多くの企業さまの課題とその解決策をわかりやすくご紹介します。
- DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
マーケティング推進部 - 三上 哲章