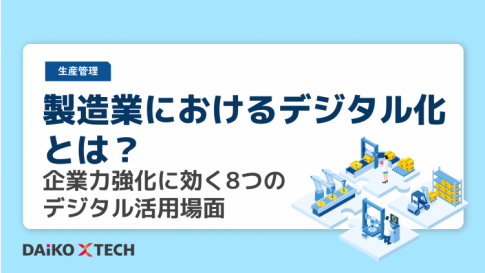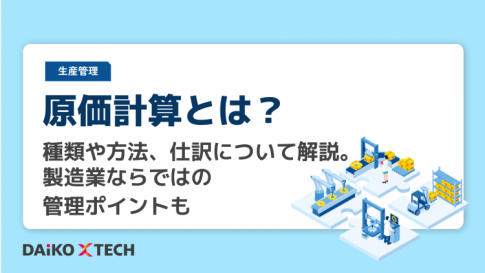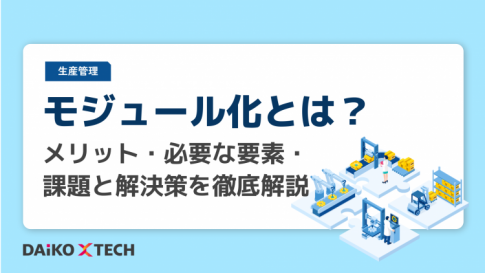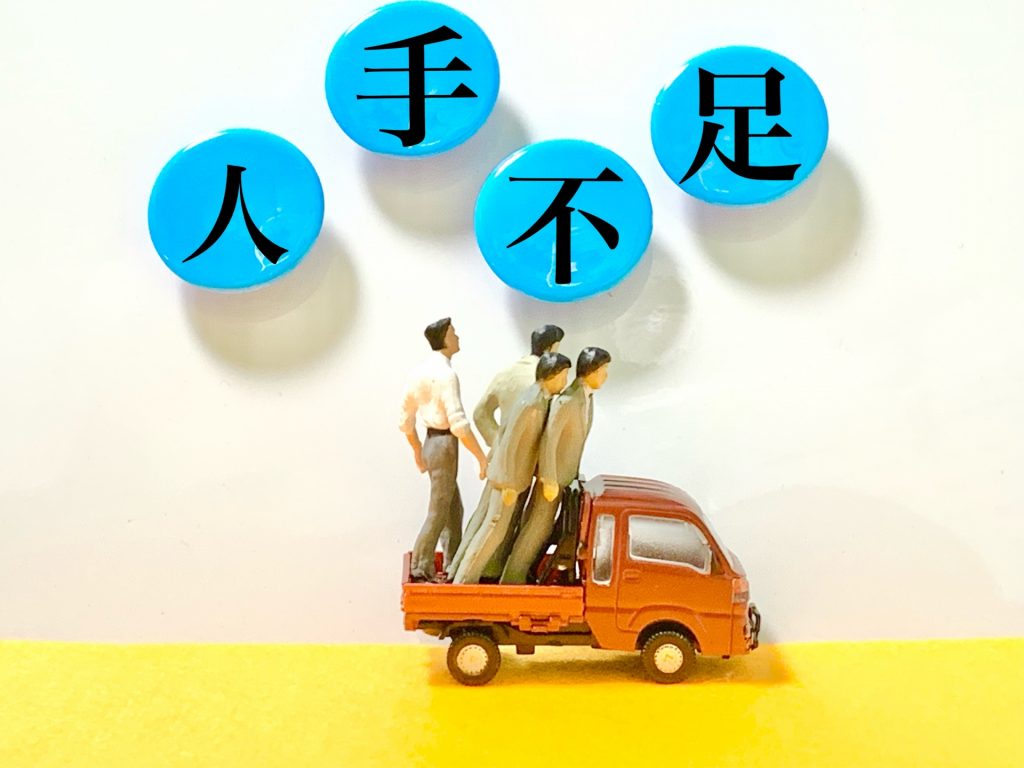
現在、多くの業界で人手不足が深刻な問題となっています。
製造業においても、人手不足によって競争力やお客さま満足度が低下する課題を解消しなければなりません。
企業の利益を向上させるためにも、人手不足解消の打開策が必要です。
本記事では、製造業の人手不足解消のためにDX(デジタルトランスフォーメーション)を用いた具体的な打開策を詳しく解説します。
製造業が人手不足に陥る原因と、人手不足に伴って生じる影響も併せて解説します。
また、DXを行うことで人手不足を解消した事例もご紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
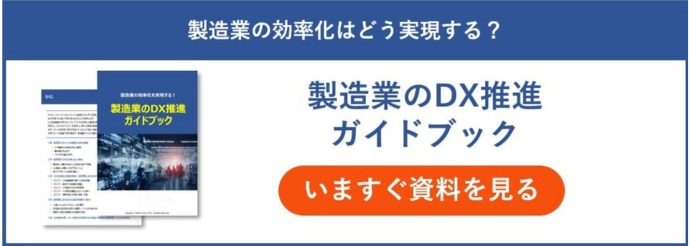
製造業では、人手不足により人材確保が難しい状況が続いています。
まずは有効求人倍率と労働人口の推移を確認して、人手不足の実態を把握しましょう。
目次
有効求人倍率は1.67倍
厚生労働省が実施した「一般職業紹介状況」調査によると、令和6年度における製造業の有効求人倍率は1.67倍でした。
なお具体的な職種としては、生産ラインなどで製造業に従事する「生産工程従事者」の有効求人倍率が1.67倍であり、求職者1人に対して1件以上の求人がある状況です。
その他の、製造業に関わる職種の有効求人倍率は次のとおりでした。
|
職種 |
有効求人倍率 |
|
製造技術者(開発) |
2.18倍 |
|
製造技術者(開発を除く) |
0.83倍 |
|
生産設備制御・監視従事者(金属製品) |
1.07倍 |
|
生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) |
2.11倍 |
|
機械組立設備制御・監視従事者 |
0.83倍 |
|
製品製造・加工処理従事者(金属製品) |
2.19倍 |
|
製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
1.85倍 |
|
機械組立従事者 |
0.74倍 |
|
機械整備・修理従事者 |
4.45倍 |
|
製品検査従事者(金属製品) |
1.15倍 |
|
製品検査従事者(金属製品を除く) |
1.88倍 |
|
機械検査従事者 |
1.18倍 |
|
生産関連・生産類似作業従事者 |
0.95倍 |
引用元:一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について|厚生労働省
上記のように製造業の職種によっては、有効求人倍率が2倍を超えるケースもあります。
全職業の有効求人倍率は1.25倍が平均なため、製造業は人手不足の状態であることがわかります。
製造業の新規求人数は減少
2024年のものづくり白書によると、製造業の新規求人数は減少していることがわかります。
2020年コロナ禍の影響を受けて大幅に減少した後、2021年には一転して増加に転じました。
しかし、2022年中頃以降は再び減少傾向になっています。
製造業の新規求人数も2022年には増加幅が縮小し、2023年はマイナスになりました。
2024年2月では、対前年同月比で-8.7%と求人が減少していることがわかります。
さらに、2024年11月のマイナビキャリアリサーチのレポートによると、2024年9月の製造業の新規求人数は7.8万人で前月比5.9%で増加、前年同月の8.6万人と比較すると7.8%減少しています。
増減がありつつも、製造業の新規求人数は減少傾向が続いています。
人手不足にもかかわらず新規求人数を増やせない原因には、原材料の高騰により利益が出しづらく、採用に予算を回せない状況があります。
また、地方に生産拠点を置いている企業も多く、過疎化により若年就業者数自体が少ないため募集しても人が集まらないのが現状です。
製造業が人手不足に陥っている原因

近年、製造業では人手不足に陥っており、人材獲得や生産性の向上が課題となっています。
人手不足の原因としては以下3点が挙げられます。
- 少子高齢化に伴う労働人口減少
- 人材の流動化が主流となった
- 教育体制が整っていない
少子高齢化に伴う労働人口減少
現在は少子高齢化に伴う労働人口減少の影響で、日本全国で人手不足が課題となっています。
労働力となる若年層・労働年齢層が減少しているため、採用難が続いている状況です。
また高齢者が増えているため、シニア採用を取り入れている企業も多いですが、組織の次世代を担う若手層の獲得が難航しています。
「2024年版 ものづくり白書」によれば、2002年から2023年にかけて製造業で就業する人材の推移は次のように変化しました。
|
年次 |
若年就業者(34歳以下)数 |
高齢就業者(65歳以上)数 |
|
2002年 |
384万人 |
58万人 |
|
2023年 |
259万人 |
88万人 |
参照元:2024年版 ものづくり白書|経済産業省・厚生労働省・文部科学省
製造業における若年就業者数は、約20年間で125万人減少し、高齢就業者は30万人増加しています。
高齢就業者だけでなく若年就業者を獲得しなければ、組織は長期的に成長できません。
製造業だけでなく、日本全体で少子高齢化による労働人口の減少が課題となっています。「国立社会保障・人口問題研究所」が公表する「2024年版人口統計資料集」によると、年齢別の人口は次のように変化する見込みです。
|
年次 |
人口(1,000人) |
||
|
0~14歳の人口 |
15~64歳の人口 |
65歳以上の人口 |
|
|
2020年 |
15,032 |
75,088 |
36,027 |
|
2025年 |
13,633 |
73,101 |
36,529 |
|
2030年 |
12,397 |
70,757 |
36,962 |
|
2035年 |
11,691 |
67,216 |
37,732 |
|
2040年 |
11,419 |
62,133 |
39,285 |
|
2045年 |
11,027 |
58,323 |
39,451 |
|
2050年 |
10,406 |
55,402 |
38,878 |
|
2055年 |
9,659 |
53,070 |
37,779 |
|
2060年 |
8,930 |
50,781 |
36,437 |
|
2065年 |
8,360 |
48,093 |
35,134 |
|
2070年 |
7,975 |
45,350 |
33,671 |
引用元:「2024年版人口統計資料集」表2-7年齢(3区分)別人口および増加率の将来推計:2020~70年|国立社会保障・人口問題研究所
労働人口である15~64歳の人口は2020年で約7,509万人ですが、2040年には約6,213万人、2050年には約5,540万人、2070年には約4,535万人と減少していく見込みです。
同調査によると、1920〜2020年までに国内の労働力は次のように変化しました。
|
年次 |
労働力総数(1,000人) |
労働力の割合(%) |
|
1920年 |
25,866 |
72.8 |
|
1940年 |
32,661 |
71.1 |
|
1960年 |
44,384 |
67.4 |
|
1980年 |
57,231 |
64.0 |
|
1990年 |
63,595 |
63.1 |
|
2000年 |
66,098 |
61.1 |
|
2010年 |
63,699 |
57.8 |
|
2020年 |
68,121 |
62.9 |
|
2022年 |
69,020 |
62.5 |
引用元:「2024年版人口統計資料集」表8-1性,労働力状態別人口および割合:1920~2022年|国立社会保障・人口問題研究所
1920年には人口のうち72.8%が労働力でしたが、2022年には62.5%まで労働力が減少しました。
製造業だけでなく日本国内全体で、労働力が減少しているため、業界を問わず人手不足に悩まされています。
また、2024年のものづくり白書でも、若年就業者の割合の推移が示されています。
2002年〜2004年は製造業・非製造業ともに30.0%超でしたが、2023年には製造業・非製造業ともに25.0%程度となっており、あらゆる業種で若年就業者割合の低下は深刻であることがわかります。
今後も労働力は減少していく見込みであり、優秀な人材を確保する採用力と定着率を向上させる施策が求められます。
人材の流動化が加速した
従来の終身雇用は崩壊しつつあり、現在では転職が当たり前になりました。
人材の流動化が加速し、ひとつの企業で長く就業しない人材が増えています。
さらにダイバーシティが拡大している現在では、フリーランスや在宅ワークなどの働き方が多様化しています。
企業に生涯を捧げるのではなくライフワークバランスを重視する労働者も増えました。
人手不足を解消するためには、労働者が長く働きたいと思える魅力的な組織づくりと、働きやすい職場体制を整えることが大切です。
教育体制が整っていない
モノづくりを行う中小企業では、OJTによる教育体制を取り、先輩社員の仕事を見て覚える昔ながらの教育をしている企業も少なくありません。
前述した通り人材の流動化が加速した現在では、十分に技術継承が行われずに若年就業者は他の企業へ転職してしまいます。
OJTでの教育では、一人の技術者を育てるのに長い年月を要することが欠点です。
結果としてベテラン社員だけが残り、ベテラン社員の退職とともに技術継承ができなくなってしまった企業も存在します。
また、人手不足も続く中、効率的でコストの掛からない教育体制を整えることは急務です。
タブレットなどを活用したeラーニングや熟練作業者の作業を映像化した技術訓練など、教育の面でもIoT機器を積極的に導入していく必要があります。
製造業が人手不足に陥ることで生じる影響

製造業が人手不足に陥ることで生じる影響は、次のとおりです。
- 競争力が低下する
- 事業縮小や撤退のリスクが高まる
- 従業員の負担が増加する
- お客さま満足度が低下する
人手不足によって生じる影響を確認して、対策を講じるべきか検討しましょう。
競争力が低下する
人手不足に陥ることで、企業の競争力が低下します。
人手不足によって生産性が低下すると、十分な品質を担保した製品を製造できず、生産ラインの縮小化や生産量減少につながるリスクがあります。
品質が低下し生産量が減少すれば、競合他社に市場シェアを奪われてしまいかねません。
また、新人作業員に対して十分な教育をする時間と労力を確保できなければ、組織内のスキル・ノウハウが属人化してしまいます。
次世代にスキルやノウハウを継承できず、属人化した生産工程で製品を製造し続ければ、将来的に生産量と品質が低下し、競争力の低下につながります。
事業縮小や撤退のリスクが高まる
人手不足になると、事業縮小や撤退のリスクが高まります。
人手不足の影響から生産性が悪化し利益率が下がってしまうと、設備投資へ回す資金も確保できません。
設備投資もできなくなると、生産性を向上させるきっかけを作ることすら難しくなってしまう可能性もあります。
さらに競争力は下がり現状維持どころか生産ラインの縮小、最終的には撤退につながってしまいかねません。
人手不足の状態が解消されなければ、生産力はさらに低下し、結果的に事業縮小や撤退のリスクが高まってしまいます。
従業員の負担が増加する
十分な人手を確保できていない場合は、従業員の負担が増加するため対策が必要です。
従業員1人ひとりの負担が増加すれば、疲れやストレスを溜め込み、モチベーションが低下します。
さらに離職や休職が増え、さらに人手が不足する悪循環に陥ることもあります。
人手不足の職場では長時間労働や休日出勤といったオーバーワークが発生しやすくなり、人材の定着・採用が難しくなるため、根本から問題を解決する必要があります。
お客さま満足度が低下する
人手不足の状態では生産性が低下し、品質の確保・向上が難しくなるため、お客さま満足度の低下へとつながります。
品質の低い製品を市場に流通させた場合、企業のブランドイメージも低下しかねません。
また、人手不足によって管理業務に費やすリソースが不足すると、市場ニーズや在庫数の調査を行えず、機会損失が生じるリスクもあります。
DXで製造業の人手不足を解消する打開策

製造業の人手不足への対策として、DXは有効です。
DXは、人手不足の組織でも作業を自動化・効率化し、限られたマンパワーでも業務を遂行できるよう業務改善を実現できます。
DXで製造業における人手不足を解消する具体的な打開策は、次のとおりです。
- 作業を自動化する
- 現場作業を可視化する
- 市場分析やバックオフィスにもICTを取り入れる
- ノウハウをデータベース化する
各打開策を参考に、自社で取り入れるべき施策を検討しましょう。
作業を自動化する
設備や機材のDXによって作業を自動化させれば、限られた人員でも十分な生産量を確保でき、従業員の負担軽減が可能です。
さらに、AIを搭載した設備を導入すれば簡単な作業を機械化でき、限られたマンパワーを有効活用して高品質な製品を製造できます。
業務の効率化によって労働時間を削減できるため、生産性の向上や従業員の定着率向上も見込めます。
現場作業を可視化する
人手不足の環境では、品質管理や生産管理が疎かになる可能性があります。
生産計画を立案しても、計画どおりに作業が進まなければ納期遅れや品質の低下につながります。
限られた人手でも品質管理・生産管理を徹底し、高品質な製品を期限内に納品するために、DXで現場作業を可視化しましょう。
生産管理システムなどを活用して現場作業の進捗状況や作業時間、不良やミスの発生を可視化すれば、現場の無駄を省けます。
さらに効率的な作業手順へ改善したり、不良やミスが多い作業を洗い出したりと、生産性を高める対策を講じることも可能です。
市場分析やバックオフィスにもICTを取り入れる
市場分析やバックオフィスにもICTを取り入れることで、コストの削減と業務効率の向上が期待できます。
バックオフィスとは、お客さまと直接的にコミュニケーションを取らない経理や人事、労務、総務などのことです。
市場分析やバックオフィスにICTを取り入れれば、少ない人数で業務を遂行し、人件費を削減できます。
データ活用による高度な市場分析を行うことで生産性とサービス品質向上を図り、市場ニーズを満たした製品・サービスの提供も期待できます。
ノウハウをデータベース化する
人手不足解消におけるDXでは、自動化だけでなく知識やノウハウのデータベース化も重要です。
人手不足の環境では、新人作業員へのスキルやノウハウの教育が難しく、技術の継承が滞ってしまいがちです。
しかし、熟練した技術者のノウハウをデータベース化すれば、人手不足の環境でも新人作業員へスキルやノウハウを伝達し、技術が継承できずに失われてしまう事態も回避できます。
データベース化の一例として、熟練技術者の作業内容の映像化が挙げられます。
効果的な方法としては、VRを活用した学習システムの確立です。
まず熟練技術者の視線の動きなどを追跡し、作業手順を映像マニュアルとして保存します。
学習者は、まず熟練技術者の視線の動きをPC画面上で学ぶことができます。
次に、VRゴーグルを装着して仮想空間に入り、学んだ視線の動きを実践します。
教育する側の目線では、学習者の視線の動きを確認して、所要時間や手順を熟練技術者の作業と比較し評価や指導が可能です。
従来の先輩の動きを現場で見て覚えて実践するOJTによる教育よりも、よりタイムリーで確実に作業を習得できます。
熟練技術者の動きを映像化すると、ノウハウをデータベース化できるだけでなく、後に作業効率の分析や現場改善にも活用できるメリットもあります。
ノウハウをデータベース化すれば、人的コストをかけなくても熟練の技術者のノウハウを新人に継承できるため、教育効率も高まります。
製造業における人材不足解消の事例

本章では製造業においてDXにより人材不足を解消した事例をご紹介します。
テレワーク導入で社員の定着率が向上した事例
兵庫県の金属加工会社では、テレワークを導入し社員の定着率が向上しています。
本社が地方にあるために人材確保が困難であること、介護や子育てで離職するケースを解消する目的でテレワークを導入しました。
2020年コロナ禍の半年前にテレワーク導入を開始していたことから、人材不足解消のために積極的に取り組んできたことが伺えます。
テレワークを導入するにあたって、はじめにコミュニケーションのDXに取り組んでいます。
クラウドシステムを積極的に活用し、予定表やチャット機能、情報共有をリモート環境で行うことから始めました。
テレワーク導入の取り組みにより、社員の働きやすさが向上したことで定着率向上を実現しました。
2024年11月には、タブレット連動型の自走式ロボットを活用し、テレワークでも会議や視察を行える環境を整えています。
タブレット連動型の自動式ロボットは、ネットワーク環境が整っていれば自由に室内を動き回ることができます。
来客対応や、現場作業者の手を煩わせずに生産ラインの様子をチェックしたり、営業部署でのデモンストレーションに活用可能です。
本事例ではテレワークの導入だけではなく、IoTやAIを活用した工場内の生産性向上にも取り組んでいます。
テレワークを促進しているため、必然的に少人数で現場を回さなければいけません。
小型センサーの活用により、工場内の人の流れを計測して、工数を削減し少人数での工程管理を実現しました。
さらに機器のデータ、工場内の環境データを取得し、照明や空調等の効率的な制御も進めています。
DXを進めるにあたって、従業員へは人的コストの削減ではなく、業務支援であることを伝えることで、従業員満足度の高いDXを継続しています。
ITの活用により業務を効率化した事例
京都府の部品加工・装置開発会社では、ITの活用により多品種少量生産のアルミに特化した24時間無人化システムを実現しています。
前身の鉄工所は自動車部品の量産を行っており売上の9割を占めていたものの、試作開発を伴う多品種少量生産へ経営方針を転換しました。
方針転換の理由は、前身の鉄工所では常に納期や人手不足との戦いで、「機械が人に使われているようだ」と危機感を持ったためとのことです。
借りていた機械設備なども全て返却し、量産体制を全て終了させました。
毎回試作品を作り、少量の生産を行うと一般的には属人化の面が強くなると見られがちですが、本事例では職人の技術や思考をデータベース化し、加工技術を標準化しました。
また、情報のデジタル化も進め、社内ネットワークによる情報の一元管理、進捗管理など効率的な独自の生産モデルを確立しました。
現在では受注から部品製作・納品までIT技術を駆使しています。
NC旋盤やマシニングセンタにも早くから目を付け、導入していることにも注目です。
本事例では「機械が24時間無人で加工生産を行い、人は人にしかできない知的労働へ」と業務体系を大きく変革させました。
現在ではシステムエンジニアの採用にも力を入れています。
大幅なDXにより人手不足を解消し、若手の採用・定着ができる企業となりました。
製造業の人手不足を解消するためDXを促進しよう

全国的に人手不足の状況が続いており、製造業でも人材獲得と業務の効率化が求められています。
製造業における人手不足の解消には、DXの推進が有効です。
AIを活用した業務の自動化や、テクノロジーを活用した新たな価値の創造など、企業に付加価値を与える施策としてDXを進める企業も増加しています。
下記のホワイトペーパーでは、DX推進が高まる背景や製造業でDXが進まない理由を詳しく解説しています。
DXの推進方法も併せて解説しているため、人手不足を解消する打開策としてぜひ確認してみてください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
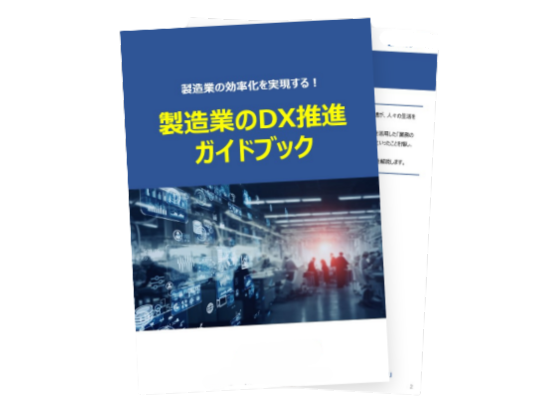
製造業の効率化を実現する!
製造業のDX推進ガイドブック