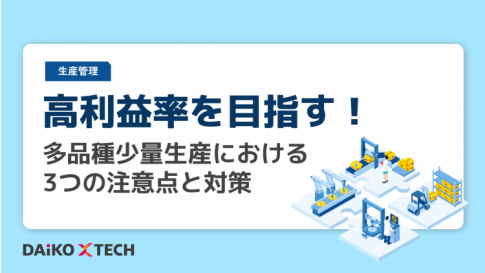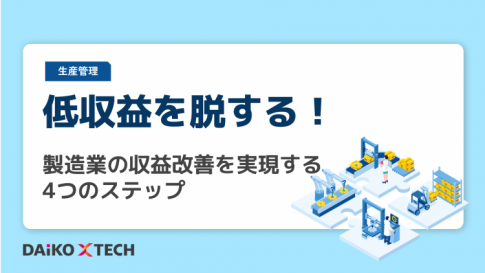製造業を経営する上で、自社の健全性を図る指標として利益率は重要な項目です。
利益率が低い業種は、製品やサービスを販売しても企業の利益が上がりづらく、経営難に悩むリスクがあります。
製造業の利益率を低下させる要因と、目指すべき目安を確認して、利益向上に向けた対策を実施しましょう。
本記事では、製造業の利益率の目安について詳しく解説します。
利益率が低下する要因と改善ポイントをあわせて解説するため、ぜひ最後までご覧ください。
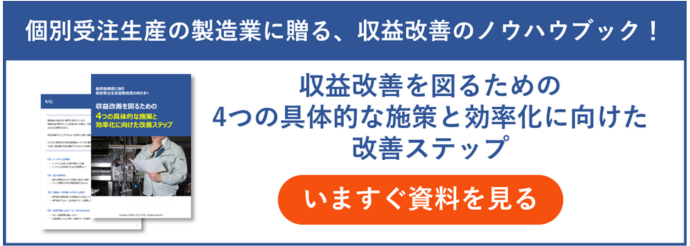
目次
製造業の平均営業利益率

製造業の利益を向上させるために、自社の利益率を把握しておくことが重要です。
利益率とは、売上高に対する利益の割合であり、材料費や人件費などの諸経費を差し引いた割合を意味します。
どれだけ売上高が高くても、高額な諸経費が発生している場合は、企業の手元に残る純利益は低いです。
利益率が高いほど優れた収益性を確保できるため、売上高に対する利益の割合を増やす試みが必要です。
なお、経済産業省の調査によると製造業の営業利益率は、中小企業・大企業とも4.0%でした。
参照元:1.中小企業の売上高営業利益率|商工業実態基本調査|経済産業省
一般的に利益率は5%前後が標準とされるため、製造業の平均利益率は少し低い傾向にあります。
製造業では、製品や材料の管理費や仕入コスト・人件費・エネルギーコストがかかり、その高騰によって利益率が圧迫されます。
製造業の利益率を向上させるためには、諸経費などの出費を減らす施策が求められます。
製造業の各種利益率と計算方法

経済産業省企業活動基本調査によると、2022年度の製造業の利益は次のとおりでした。
|
営業利益 |
1,564,181,000円 |
|
経営利益 |
2,774,246,800円 |
|
純利益 |
216,4,479,000円 |
|
売上高 |
32,042,829,100円 |
参照元:経済産業省企業活動基本調査 / 統計表一覧-確報(データ) 2023年企業活動基本調査確報ー2022年度実績ー|政府統計の総合窓口
売上高のうちどれだけ利益があるかを算出することで、利益率を求められます。
そのため、企業の業績を確認する際は、営業利益・経営利益・純利益・売上高を把握しておくことが大切です。
また利益率は大きく分けて、下記の5種類に分類されます。
- 売上高総利益率(粗利益率)
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 自己資本経常利益率(ROE)
- 総資本経常利益率(ROA)
下記利益率の特徴と計算方法を確認して、自社の利益率を算出しましょう。
売上高総利益率(粗利益率)
売上高総利益率(粗利益率)は、売上高のうちどれだけ企業の利益があるかを示した一般的な利益率です。
企業が提供するサービスや製品によって、「どれだけの利益を生んだか」を算出します。
製造業では、売上高から製造原価を差し引いた売上総利益を売上高で割ることで、売上高総利益率を算出できます。
売上高総利益率の計算式は、次のとおりです。
|
売上高総利益率(%)=売上総利益÷売上高×100 |
経済産業省が公表した「中小企業実態基本調査」によると、2021年から2022年における製造業の売上高総利益率は、次のとおりでした。
|
年度 |
売上高総利益率平均値 |
|
2022年度 |
20.3% |
|
2021年度 |
21.4% |
参照元:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年度決算実績) 確報 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
参照元:中小企業実態基本調査 令和4年確報(令和3年度決算実績) 確報 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
売上高営業利益率
売上高営業利益率は、売上高から製造原価だけでなく販売費や管理費などを差し引いた営業利益がどの程度あるかを表した指標です。
具体的には、事業活動によってどの程度利益が生じているか、事業の収益性を把握する際に活用されます。
売上高営業利益率の計算式は、次のとおりです。
|
売上高営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100 |
なお営業利益は、売上高から原価・販売費・管理費を引くことで求められます。
経済産業省が公表した「2023年経済産業省企業活動基本調査速報」によると、2021年から2022年度における製造業の売上高営業利益率は、次のとおりでした。
|
年度 |
売上高営業利益率平均値 |
|
2022年度 |
4.9% |
|
2021年度 |
5.7% |
産業省:2023年経済産業省企業活動基本調査速報(2022年度実績)調査結果の概要|経済産業省
売上高経常利益率
売上高経常利益率は、営業利益率からさらに営業外損益を差し引き、売上高に占める経営利益の割合を表した数値です。
つまり企業の事業活動によって得る収益全体の利益率を表すもので、複数の収入源がある場合にはすべての収益を合算して求めます。
営業利益が主力事業の収益性を表すのに対して、経常利益は企業全体の収益性を表す指標です。
なお、経常利益を求める際に差し引く営業外損益とは、貸付金の受取利息や借入金の支払利息など、企業の財務活動によって生じる損益を指します。
売上高経常利益率の計算式は、次のとおりです。
|
売上高経常利益率(%)=経常利益÷売上高×100 |
なお経済産業省が公表した「2023年経済産業省企業活動基本調査速報」によると、2021年から2022年度における製造業の売上高経常利益率は、次のとおりでした。
|
年度 |
売上高経常利益率平均値 |
|
2022年度 |
8.7% |
|
2021年度 |
9.0% |
産業省:2023年経済産業省企業活動基本調査速報(2022年度実績)調査結果の概要|経済産業省
自己資本経常利益率(ROE)
自己資本経常利益率は、「Return On Equity」を略して「ROE」とも表記する利益率の一種です。
自己資本経常利益率(ROE)は、企業が資本をどれだけ効率的に活用し、利益を上げているかを表しています。
経常利益から、資産売却益や損害賠償費用などの「特別損益」と「法人税」などの各種税金を差し引くことで、自己資本経常利益率(ROE)を求められます。
経常利益から特別損益と各種税金を差し引いた値を「当期純利益」と呼び、主に経営者より投資家が企業の業績を調べる際に利用するケースが多いです。
自己資本経常利益率(ROE)の計算式は、次のとおりです。
|
自己資本利益率(%)=当期純利益÷自己資本×100 |
総資本経常利益率(ROA)
総資本経常利益率は、「Return On Assets」を略して「ROA」とも呼ばれる、利益率の一種です。
ROAは、企業の総資本をどれだけ有効活用し、利益を生み出しているかを図る指標です。
総資本とは、どのような方法で資本を集めたかを表し、総資産は資本を活用してどのような資産を得たかを意味します。
そのため、総資本は総資産と同額になり、総資本経常利益率を総資産経常利益率と呼ぶケースもあります。
総資本経常利益率は、財務構成に関わらず対象期間中に得た企業の総資産を把握するために、使用する数値です。
自社の業績を、企業規模や財務構成が異なる同業他社と比較する際に、総資本経常利益率が活用されます。
総資本経常利益率の計算式は、次のとおりです。
|
総資本利益率(%)= 当期純利益÷総資本×100 |
製造業における業種別の平均利益率

製造業全体の粗利益率は、2022年度20.3%・2021年度21.48%ですが、業界内にはさまざまな職種が存在しており、各職種で利益率が異なります。
先ほど解説した製造業全体の利益率をまとめると、次のとおりです。
|
項目 |
平均 |
|
売上高総利益率 |
20.3% |
|
売上高営業利益率 |
4.9% |
|
売上高経常利益率 |
8.7% |
産業省:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年度決算実績) 確報 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
産業省:2023年経済産業省企業活動基本調査速報(2022年度実績)調査結果の概要|経済産業省
次の業種別に各利益率の平均値・中央値を解説するため、製造業全体の利益率と比較しましょう。
- 食料品製造業
- 飲料・たばこ・飼料製造業
- 衣服・その他の繊維製品製造業
- 家具・装備品製造業
- パルプ・紙・紙加工品製造業
- プラスチック製品製造業
- ゴム製品製造業
- 非鉄金属製造業
- 金属製品製造業
- 一般機械器具製造業
- 電気機械器具製造業
- 情報通信機械器具製造業
- 輸送用機械器具製造業
食料品製造業
食品製造業の平均利益率は、次のとおりです。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
39.6% |
36.8% |
|
売上高営業利益率 |
-10.1% |
-5.4% |
|
売上高経常利益率 |
-5.4% |
-2.0% |
|
自己資本経常利益率 |
-8.3% |
2.6% |
|
総資本経常利益率 |
-6.1% |
-2.6% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
飲料・たばこ・飼料製造業
2022年度の飲料・たばこ・飼料製造業の利益率は、次が平均値・中央値でした。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
44.1% |
43.0% |
|
売上高営業利益率 |
-16.5% |
-11.7% |
|
売上高経常利益率 |
-8.6% |
-4.4% |
|
自己資本経常利益率 |
-40.1% |
-6.3% |
|
総資本経常利益率 |
-4.2% |
-2.2% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
衣服・その他の繊維製品製造業
衣服・その他の繊維製品製造業では、次の数値が平均値・中央値です。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
45.0% |
37.2% |
|
売上高営業利益率 |
-13.7% |
-7.8% |
|
売上高経常利益率 |
-6.2% |
-2.8% |
|
自己資本経常利益率 |
9.2% |
8.7% |
|
総資本経常利益率 |
-7.0% |
-2.8% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
家具・装備品製造業
家具・装備品製造業の利益率は、次のとおりです。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
41.6% |
37.7% |
|
売上高営業利益率 |
-9.0% |
-4.7% |
|
売上高経常利益率 |
-4.4% |
0.1 |
|
自己資本経常利益率 |
32.4% |
7.6% |
|
総資本経常利益率 |
-4.3% |
0.3% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
パルプ・紙・紙加工品製造業
2022年度のパルプ・紙・紙加工品製造業における利益率の平均値・中央値は、次のとおりでした。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
39.1% |
30.1% |
|
売上高営業利益率 |
-9.9% |
-6.0% |
|
売上高経常利益率 |
-4.9% |
-1.2% |
|
自己資本経常利益率 |
29.4% |
5.8% |
|
総資本経常利益率 |
-3.7% |
0.0% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
プラスチック製品製造業
プラスチック製品製造業の利益率は、次のとおりです。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
38.6% |
32.1% |
|
売上高営業利益率 |
-5.7% |
-1.7% |
|
売上高経常利益率 |
-1.8% |
0.3% |
|
自己資本経常利益率 |
-2.2% |
6.4% |
|
総資本経常利益率 |
-1.1% |
0.3% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
ゴム製品製造業
2022年度のゴム製品製造業における利益率は、次のとおりでした。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
39.8% |
33.4% |
|
売上高営業利益率 |
-5.0% |
-3.7% |
|
売上高経常利益率 |
-2.9% |
-1.3% |
|
自己資本経常利益率 |
17.2% |
15.2% |
|
総資本経常利益率 |
-3.8% |
-0.5% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
非鉄金属製造業
非鉄金属製造業の利益率は、次の数値が平均値・中央値です。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
28.7% |
23.8% |
|
売上高営業利益率 |
-7.3% |
-6.3% |
|
売上高経常利益率 |
-6.0% |
-3.7% |
|
自己資本経常利益率 |
28.0 |
-4.0% |
|
総資本経常利益率 |
-4.6% |
-2.4% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
金属製品製造業
金属製品製造業の利益率は、次のとおりです。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
40.4% |
34.5% |
|
売上高営業利益率 |
-11.0% |
-5.1% |
|
売上高経常利益率 |
-6.0% |
-1.4% |
|
自己資本経常利益率 |
11.3% |
3.8% |
|
総資本経常利益率 |
-6.1% |
-1.7% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
一般機械器具製造業
2022年度の一般機械器具製造業における利益率は、次のとおりでした。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
38.6% |
33.3% |
|
売上高営業利益率 |
-9.0% |
-4.3% |
|
売上高経常利益率 |
-4.8% |
-0.2% |
|
自己資本経常利益率 |
27.1% |
4.7% |
|
総資本経常利益率 |
-2.9% |
-0.1% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
電気機械器具製造業
電気機械器具製造業では、利益率の平均値・中央値が次のような数値でした。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
39.3% |
33.8% |
|
売上高営業利益率 |
-14.3% |
-5.2% |
|
売上高経常利益率 |
-9.4% |
-4.1% |
|
自己資本経常利益率 |
-16.6% |
5.8% |
|
総資本経常利益率 |
-11.7% |
-4.4% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
情報通信機械器具製造業
情報通信機械器具製造業の利益率の平均値・中央値は、次のとおりです。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
48.5% |
41.5% |
|
売上高営業利益率 |
-16.5% |
-4.1% |
|
売上高経常利益率 |
-7.7% |
0.5% |
|
自己資本経常利益率 |
-14.1% |
0.7% |
|
総資本経常利益率 |
-5.8% |
0.4% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
輸送用機械器具製造業
輸送用機械器具製造業の利益率は、次の数値が平均値・中央値です。
|
項目 |
平均値 |
中央値 |
|
売上高総利益率 |
48.6% |
41.3% |
|
売上高営業利益率 |
-10.7% |
-4.9% |
|
売上高経常利益率 |
-6.0% |
-1.8% |
|
自己資本経常利益率 |
32.5% |
3.9% |
|
総資本経常利益率 |
-4.8% |
-2.0% |
参照元:小企業の経営指標調査 製造業 業種別|日本政策金融公庫
一般的な営業利益率の目安
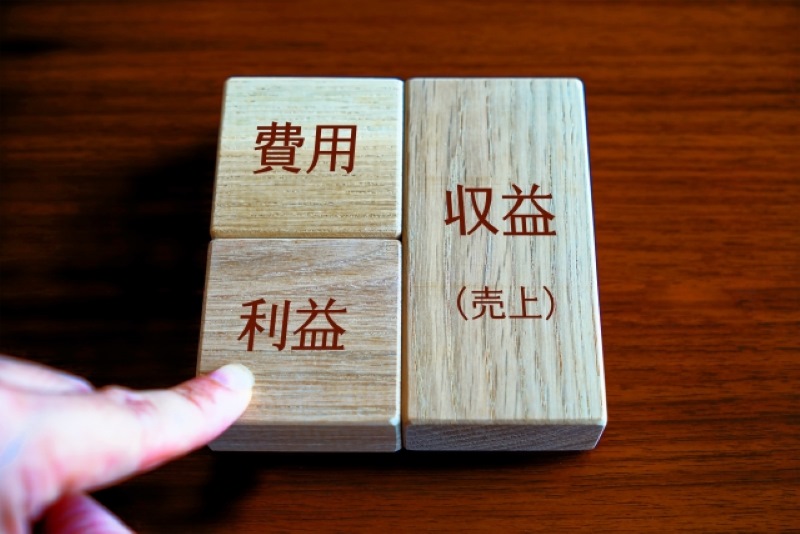
営業利益率は、高すぎても低すぎても危険なため、適切な目安を理解しておく必要があります。
営業利益率が低すぎる場合は、経営が赤字化するリスクが高く、業績不振に陥りやすいです。
反対に高すぎる場合は、従業員に負担がかかりすぎていたり顧客満足度が低かったりと、収益性が低下するため注意しなければなりません。
営業利益率の適正な水準目安は、次のとおりです。
|
営業利益率 |
企業の状態 |
|
0%以下 |
危険 |
|
0~5% |
一般的 |
|
5~10% |
優良 |
|
10~15% |
超優良 |
|
15%以上 |
要注意 |
営業利益率0〜5%程度が一般的であり、5〜15%まで高めれば収益性が高く、企業の業績を向上させやすいです。
しかし利益率が15%以上ある場合は、何かしら不満やトラブルを抱えている可能性があり、離職率の増加や顧客離れにつながりかねません。
一般的な営業利益率の目安を参考に、無理のない経営戦略を立案しましょう。
製造業の利益率が低下する要因

製造業の利益率が低下する要因は、次のとおりです。
- 業務を効率化できず生産性が低い
- 原材料費などコストが高い
- 売上高と原価の管理ができていない
自社の課題や改善点を見直して、利益率の低下を防ぎましょう。
業務を効率化できず生産性が低い
業務を効率化できず生産性が低いと、利益率が低下します。
生産性が高い場合は、製品の生産スピードが高く、人件費や材料費など無駄なコストを削減しているケースが多いです。
無駄な作業時間を短縮し、不良やロスを削減することで、業務の効率化へつながります。
製造業における生産性は、下記のQCDを重視することが大切です。
- Quality(品質)
- Cost(コスト)
- Delivery(納期)
また生産管理が疎かになり、各部門の連携や現場の情報収集・分析ができていない場合、生産性が低下します。
原材料費などコストが高い
どれだけ業務効率が優れていても、原材料費などコストが高い場合は、利益率が低下します。
原価率が適切でない場合は、製品を販売しても企業の手元に残る利益が少なく、収益性が低下します。
原価が高くともその分製品の販売価格が高いと、利益率を向上できます。
製品の販売価格を上げられない場合は、原材料費などコストを削減して、利益率を向上させましょう。
売上高と原価の管理ができていない
売上高と原価は、どちらも利益率に影響する要素です。
生産管理や経理業務を最適化することで、利益率の低下を防げます。
反対に売上高と原価の管理が疎かになっている場合、適切な生産量や販売価格を見極められません。
製造業の利益率を改善するためのポイント

利益率を低下させる要因がわかっても、改善する方法を知らなければ、現状の課題を解消できません。
製造業の利益率を改善するためのポイントは、次のとおりです。
- 売上を向上させる
- 余分なコストを削減する
- 業務効率を向上させる
各改善ポイントを参考に、自社の利益率を向上させましょう。
売上を向上させる
利益率を改善するには、売上を向上させる必要があります。
売上が高いと必然的に利益率が向上するため、マーケティング活動や営業活動で売上を伸ばしましょう。
新規顧客獲得・既存顧客開拓によって、製品の販売数を増やせば売上の向上へとつながります。
また製品の価格設定を見直すことで、製品1台あたりの売上を向上させ、利益率の向上へとつながります。
余分なコストを削減する
製造業では人件費や設備費など、余分なコストを削減する施策が必要です。
業務を効率化し、余分な作業を削減すれば、従業員の負担を軽減できます。
さらに業務の効率化により、長時間労働の防止や従業員の補填を行えば、残業や休日労働による割増賃金の支払いを軽減できます。
また材料を原価の低いものに変えることで、余分なコストを削減させることが可能です。
QCDを意識して、不要なコストカットを実現することで、利益率の向上へつながります。
業務効率を向上させる
生産性を向上させ利益率の増加を目的とするなら、業務効率の向上が効果的です。
業務効率を向上させれば、余分なコストを削減し生産性の向上へとつながります。
製造業でDXを実現すれば、リアルタイムでの生産管理や作業の自動化により、業務効率を向上できます。
システムや設備などを導入し、作業手順の見直しや不良率の低下を実現できれば、利益率の低下を防ぐことが可能です。
自社の課題や改善の目的を明確化して、必要なシステム・設備を導入しましょう。
製造業の利益率を向上させるためDXを促進しよう

製造業の利益率を向上させるために、業務効率を向上させて余分なコストを削減する取り組みが効果的です。
DXを促進して、生産管理システムやAI・IoT技術を搭載した設備を導入すれば、無駄な作業時間やコストを削減し、作業工程・手順の見直しをスムーズに実施できます。
原価と売上高・良品率を意識して、QCD向上を目指しましょう。
下記のホワイトペーパーでは、リードタイムの短縮・設計の標準化・情報共有の改善・生産管理の改善など、製造業の収益改善を行う施策を解説しています。
生産管理が難しい理由やシステム導入に伴う業務フローの見直し方も解説しているため、利用率を向上させたい方はぜひチェックしておきましょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
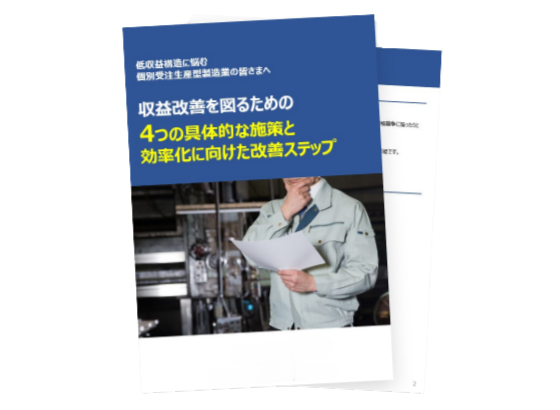
リードタイムの短縮、設計の標準化、情報共有の改善、生産管理の改善.... 個別受注生産の製造業に贈る、収益改善のノウハウブック!
収益改善を図るための4つの具体的な施策と
効率化に向けた改善ステップ