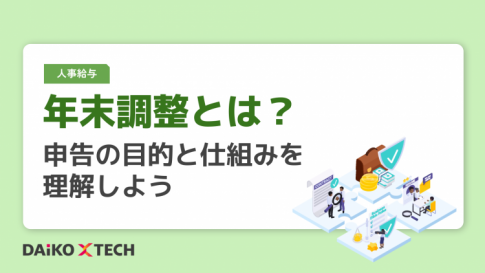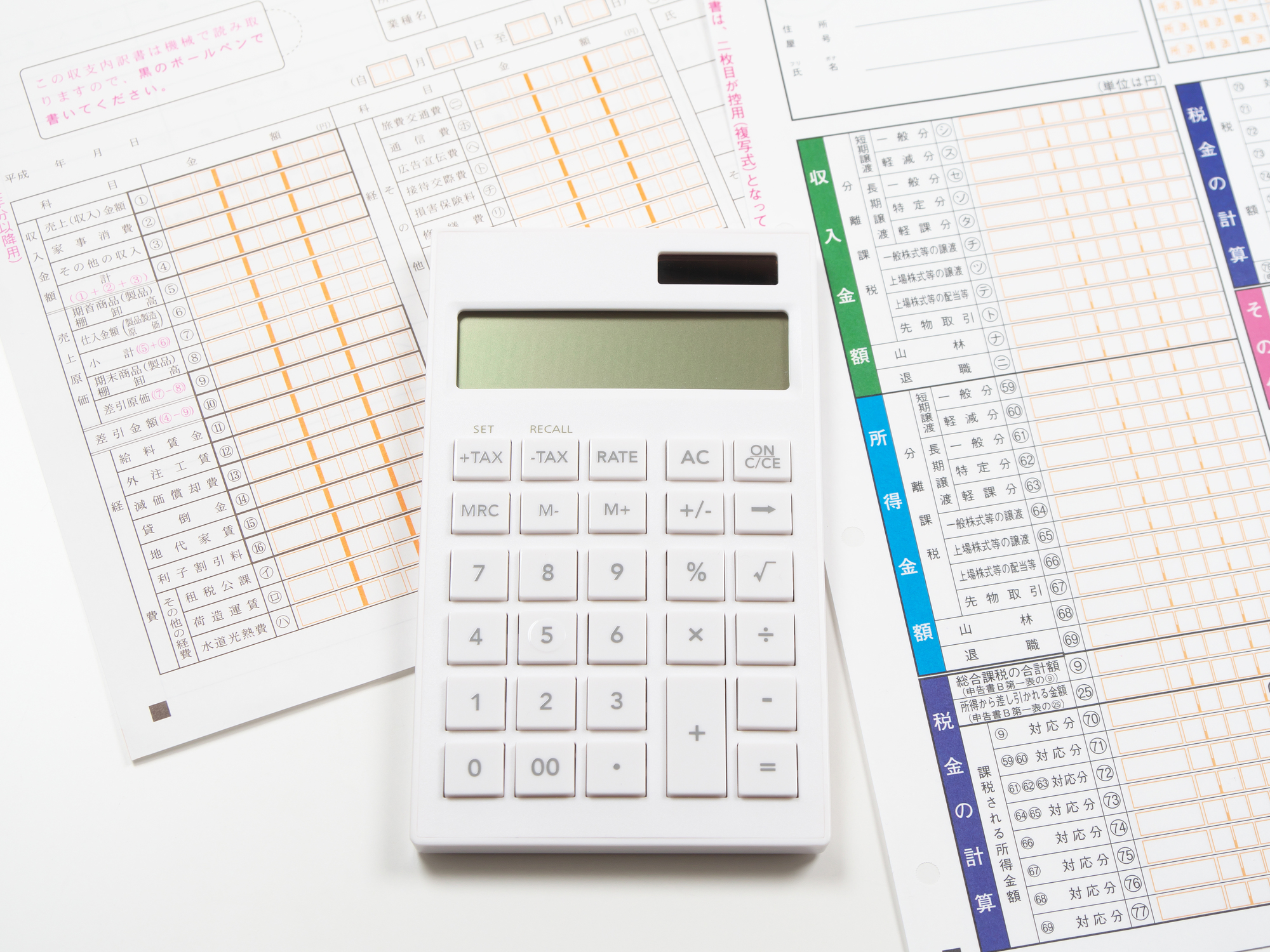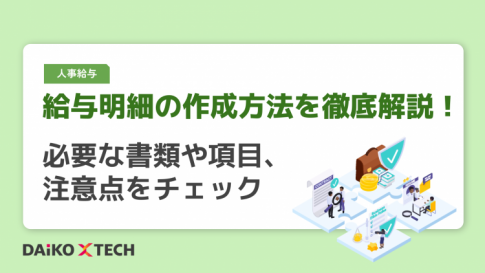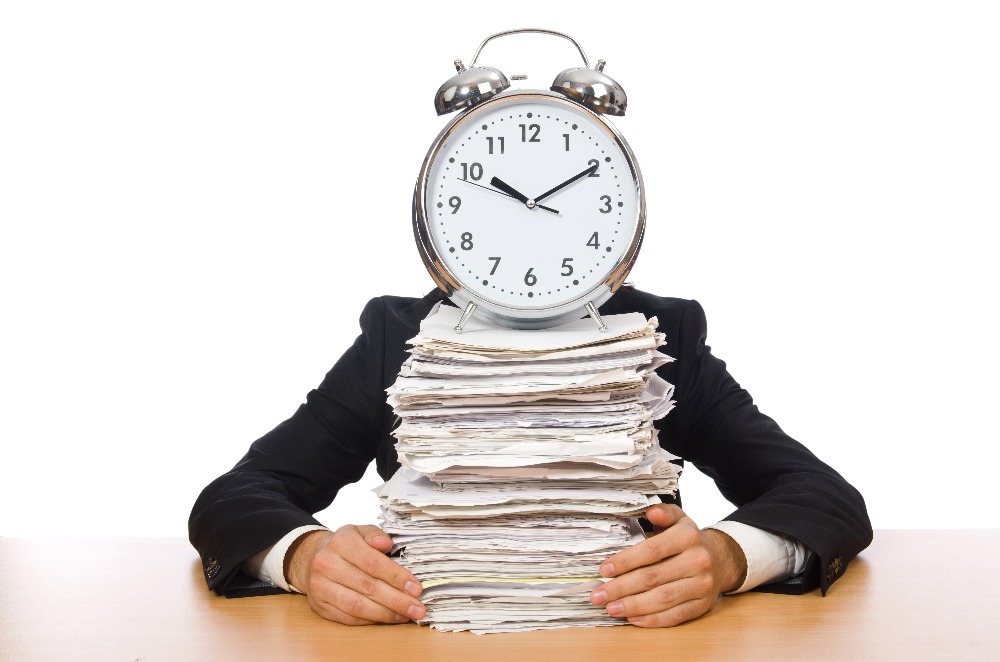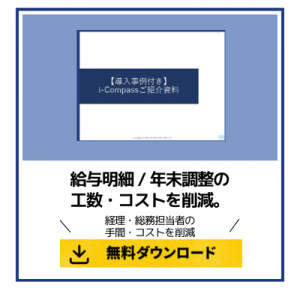給与計算は、会社経営において欠かせない業務です。さまざまなルールのもと計算する必要があり初心者には負担が大きいものの、ミスが許されないため、大きなプレッシャーを感じる人は少なくありません。
給与計算を担当する初心者に向けて、覚えておくべきルールと手順をご紹介します。
給与計算の手順やリスク・対処法をあわせて解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
初心者が覚えておくべき給与計算の基本知識

初心者が給与計算する場合は、次の基本知識を押さえておきましょう。
- 給与に含まれる項目
- 給与の決め方
- 給与の計算方法
それぞれの基本知識を押さえておけば、スムーズに給与計算できます。それぞれの基本知識を確認しておいてください。
給与に含まれる項目
給与計算の際は、給与に含まれる項目を覚えておく必要があります。
一般的な正規雇用における給与に含まれる項目は、主に次のとおりです。
|
項目 |
概要 |
|
基本給 |
ベースとなる給与。月々の変動がない |
|
各種手当 |
通勤手当・役職手当・資格手当・家族手当・住宅手当など、福利厚生によって支給される手当 |
|
割増賃金 |
残業代・深夜割増賃金・休日割増賃金など、法定労働時間以外の働きに対して支給される賃金 |
基本給をベースに各種手当や割増賃金を加算していき、支給する給与総額を計算します。
原則として、基本給は昇給や減給がない限り変動しません。
また各種手当は、従業員の住まいや家族構成、役職などによって変動します。
企業が設ける法定外福利厚生によって、各種手当の有無が異なるため、自社が設置している福利厚生の種類を確認しておきましょう。
割増賃金は、労働基準法によって法定労働時間外の労働が認められた場合に、支払いが義務付けられています。
そのため、法定労働時間を超えて労働した従業員に対しては、割増賃金を支払わなければなりません。
給与の決め方
従業員の給与は、大きく分けて次の3要素で決まります。
- 基本給
- 手当・割増賃金
- 賞与
基本給と福利厚生による諸手当、法定外時間労働を行った際の割増賃金の他に、賞与も給与に含まれています。
また、給与の内訳は課税支給額と非課税支給額に分類され、所得税や住民税が課税される対象が多いと手取りの給与額が減少します。
従業員の手元に振り込まれる給与は、総支給額から保険料や税金を差し引いた金額です。
そのため給与計算の際は、社会保険料や各種税金を差し引いて、手取りの金額を求める必要があります。
給与の計算方法
給与の計算方法は、次のとおりです。
|
総支給額-控除額=差引支給額 |
基本給に諸手当と割増賃金を加算した総支給額から、保険料や税金などの控除額を差し引いて、従業員に支給する手取り金額を算出します。
例えば、総支給額が25万円で控除額が4万5,000円の場合、差引支給額は次のとおりです。
|
総支給額25万円-控除額4万5,000円=差引支給額20万5,000円 |
初心者が押さえておくべき給与計算におけるルール

初心者が給与計算する際は、次の基本的なルールを押さえておきましょう。
- 賃金支払い5原則
- 最低賃金ルール
- 割増賃金の要件
それぞれのルールを押さえておけば、従業員の給与を正確に計算できます。
賃金支払い5原則
賃金支払い5原則とは、労働基準法第24条で定められている給与支払いに関する5つのルールです。
- 通貨で支払う
- 直接本人に支払う
- 賃金の全額を支払う
- 毎月1回以上支払う
- 一定の期日を定めて支払う
参照元:賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。|厚生労働省
給与はポイントや金券ではなく、原則は現金で支払わなければなりません。
支払い方法は現金手渡しでなくとも、労働者の同意があれば銀行振り込みで対応できます。
また、労働者の同意がある場合はデジタル給与による賃金支払いが、2023年4月から解禁されました。
家族や組織を経由して従業員に給与を支払うのではなく、雇用している企業から労働者本人に直接支払う必要があります。
給与は毎月1回以上のペースで給与日を定めて、全額支払いましょう。
賃金支払い5原則を遵守しない場合は、30万円以下の罰金が課せられるため、注意してください。
最低賃金ルール
給与は、最低賃金法で定められた地域別の最低賃金ルールを守らなければなりません。
最低賃金とは、雇用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。
2024年10月に最低賃金が値上げされ、今後も制度が改正される度に、最低賃金を下回らないよう賃金体系を設定する必要があります。
|
主な都道府県 |
最低賃金(2024年10月改正) |
|
全国平均 |
1,055円 |
|
北海道 |
1,010円 |
|
東京都 |
1,163円 |
|
大阪府 |
1,114円 |
|
広島県 |
1,020円 |
|
福岡県 |
992円 |
|
沖縄県 |
952円 |
最低賃金ルールは、基本給と諸手当に適用されますが、以下の手当に関しては対象外です。
- 皆勤手当
- 家族手当
- 通勤手当
最低賃金ルールを守らなかった場合は、50万円以下の罰金に課せられるため、地域別の最低賃金を下回らない賃金設定が必要です。
割増賃金の要件
給与計算の際は、割増賃金の要件を押さえておきましょう。
割増賃金の種類は、次のとおりです。
|
種類 |
適用条件 |
割増率 |
|
時間外(時間外手当・残業手当) |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合 |
25%以上 |
|
時間外労働が限度時間(1カ月45時間・1年360時間)を超えた場合 |
25%以上 |
|
|
時間外労働が1カ月60時間を超えた場合 |
50%以上 |
|
|
休日(休日手当) |
法定休日(週1日)に勤務させた場合 |
35%以上 |
|
深夜(深夜手当) |
22時から5時までの間に勤務させた場合 |
25%以上 |
給与計算の際は従業員の勤務時間と日数を確認して、割増賃金を算出する必要があります。
特に月の残業時間が60時間を超えた労働に関しては、割増賃金を50%以上として計算するため、割増率を間違えないよう注意してください。
初心者が給与計算をスムーズに行うための準備

初心者が給与計算をスムーズに行うための準備は、次のとおりです。
- 給与計算のタイミングを決定
- 就業規則・給与規程の作成
- 従業員情報の把握
- 勤怠状況の確認
給与計算を円滑に進められるよう、上記の準備を徹底しましょう。
給与計算のタイミングを決定
従業員に支払う給与を正確に計算するために、給与計算のタイミングを決めておくことが大切です。
月次給与は毎月の締め日まで働いた労働時間を基に、支払う給与を計算します。
締め日から給与支払い日までの期間が短い場合、給与計算が間に合わない可能性があるため要注意です。
締め日から給与支払い日までの期間で、給与を計算するタイミングを決めて、不備がないかチェックする余裕をつくりましょう。
給与計算のタイミングが決まれば、明細書の作成や給与振り込みを支払い日までに間に合うよう手続きできます。
就業規則・給与規程の作成
従業員が10人以上いる企業では、就業規則・給与規程が必要です。
従業員の勤務ルールや労働条件について記載した就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出するよう労働基準法醍89条・90条で義務付けられています。
また就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」が設けられています。
「絶対的必要記載事項」
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、交替制勤務に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、締め日と支払い日、賞与関する事項
- 退職や解雇に関する事項
参照元:1 就業規則に記載する事項 2 就業規則の効力|厚生労働省
絶対的必要記載事項の中に、賃金の計算や支払いに関する事項が含まれているため、給与規程を作成しなければなりません。
給与規程は、従業員の給与を計算する方法について明記するため、予め準備しておきましょう。
従業員情報の把握
従業員情報を把握しておけば、給与の計算がスムーズに行えます。
従業員の勤続年数や役職によって基本給が、居住地や家族構成で諸手当が変わります。
従業員ごとに基本給と手当の金額が変わるため、給与計算を正確に行えるよう、従業員の情報を把握しておきましょう。
勤怠状況の確認
給与計算を正確に行うには、勤怠状況の確認を徹底する必要があります。
従業員の労働時間や出勤日数によって割増賃金が変わるため、勤怠情報を基に給与計算を行います。
勤怠管理が疎かになっている場合は、割増賃金を反映できずに給与計算の精度が低下するため要注意です。
給与計算をスムーズに実施するために、勤怠管理システムを活用して、従業員の勤怠情報を正確に管理しましょう。
給与計算の手順

給与計算の手順は、次のとおりです。
- 総支給額を計算する
- 控除額を計算する
- 差引支給額を計算する
- 金融機関への振り込み、明細書を作成する
- 社会保険料・各種税金を振り込む
1.総支給額の計算
従業員に支給する手取り額を算出するには、まず総支給額を計算する必要があります。
給与は大きく分けると、毎月変動しない固定的な給与(基本給や通勤手当など)と、変動的な給与(残業手当や休日手当など)の2種類あります。
固定的な給与は雇用契約書や就業規則に則り算出しますが、変動的な給与は別途計算しなければなりません。
割増賃金は、「残業時間×1時間あたりの賃金×割増率」の計算式で算出します。
従業員の給与を計算する際には、まず割増賃金や諸手当を含む総支給額の計算が必要です。
2.控除額を計算する
総支給額を計算した後は、控除額を計算しましょう。
給与計算は「総支給額-控除額=差引支給額」の計算式で求められるため、総支給額から差し引く控除額を計算しておく必要があります。
控除額の内訳は、大きく分けて次の2種類です。
- 保険料
- 税金
各控除額の計算方法を確認して、総支給額から差し引く値を計算しましょう。
保険料の計算方法
保険料の計算方法は、次のとおりです。
|
保険料の種類 |
計算式 |
|
雇用保険料 |
月支給額合計×保険料率 |
|
健康保険料(介護保険料) |
標準報酬月額×保険料率 |
|
厚生年金保険料 |
標準報酬月額×保険料率 |
雇用保険料は、労働者と事業主が折半で支払うものであり、労働者の負担は次のとおりです。
|
事業の種類 |
労働者負担 |
事業主負担 |
|
一般の事業 |
6/1,000 |
9.5/1,000 |
|
農林水産・清酒製造の事業 |
7/1,000 |
10.5/1,000 |
|
建設の事業 |
7/1,000 |
11.5/1,000 |
健康保険料率は、保険組合によって設定されているため、全国保険協会のサイトから保険料率を確認しておきましょう。
参照元:令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
なお、厚生年金保険料率は2017年以降、18.3%に固定されています。
標準報酬月額は、例えばその年の4〜6月の給与を基に、従業員ごとの1カ月単位での支給額を算出したものです。
標準報酬月額は、健康保険や雇用保険など社会保険料を計算する際に使用します。
税金の計算方法
給与は、所得税や住民税などの税金が天引きされた状態で、従業員の手元に支払われます。
所得税では源泉徴収、住民税は特別徴収と呼ばれ、毎月の納付額を年末調整によって正しい金額に調整する仕組みです。
所得税は、課税所得に対して次の税率を掛け合わせて計算します。
|
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000円から1,949,000円まで |
5% |
0円 |
|
1,950,000円から3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
|
3,300,000円から6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
|
6,950,000円から8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
|
9,000,000円から17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
|
18,000,000円から39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
|
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
住民税は、前年の所得を基準に計算する所得割と、一定の所得がある方に定額の負担が発生する均等割があります。
|
税金の種類 |
所得割(標準税率) |
均等割(年額) |
|
森林環境税 |
ー |
1,000円 |
|
道府県民税 |
4% |
1,000円 |
|
区市町村民税 |
6% |
3,000円 |
3.差引支給額を計算する
総支給額と控除額を計算した後は、差引支給額を計算しましょう。
総支給額から控除額を差し引いた金額が、従業員の手元に残る差引支給額です。
4.金融機関への振り込み、明細書を作成する
差引支給額を計算できたら、金融機関への振り込みや明細書の作成に移ります。
給与規程で定められた支払い日に従業員の口座へ給与を振り込めるよう、金融機関で手続きしておきましょう。
また、給与を支払った証明として明細書を作成し、従業員へ交付しておいてください。
給与計算は、明細書の作成にかかる時間や労力を考慮して、支払い日までに手続きを終えられるようスケジュールを調整しましょう。
5.社会保険料・各種税金を振り込む
控除した社会保険料や税金は、期日までに納付する必要があります。
毎月10日ごろに前月分の保険料が確定し、20日ごろに日本年金機構から事業所へ「保険料納入告知書」が送付されます。
保険料納入告知書に記載されている納付期日までに社会保険料や各種税金を振り込む必要があるため、次のいずれかの方法で納税しましょう。
- 口座振替
- 金融機関の窓口
- 電子納付(Pay-easy)
初心者が給与計算する際に注意するべき3つのリスク

初心者が給与計算する際は、次の3つのリスクに注意する必要があります。
- 労務リスク
- 税務リスク
- 情報漏えいのリスク
それぞれのリスクを確認して、給与計算で損失を生じさせないよう対処してください。
給与計算ミスのリスク
給与計算の際は、計算ミスのリスクに注意しなければなりません。
具体的には、次のような労務リスクが想定されます。
- データの転記・入力ミス
- 出退勤の打刻忘れ
- 複雑化した勤務体系によるデータ処理のミス
- ヒューマンエラーによる計算ミス
手作業で給与計算を行う場合は、計算ミスや給与・勤務データの転記・入力ミスのリスクがあります。
また従業員がタイムカードや勤務管理システムでの打刻を忘れたり、テレワークやフレックスタイム制度など複雑化した勤務体系でデータ処理が煩雑化したりすると、正確な給与を計算できません。
勤務管理を徹底し給与計算のミスを防止するために、複数人でのチェックやシステムの導入によるヒューマンエラーへの対策が必要です。
税務リスク
給与計算を間違えると、社会保険や所得税の納税額が不足する税務リスクが発生します。
社会保険料や所得税の計算を誤ると、実際に納税するべき金額より少なくなり、後ほど追徴課税される可能性があります。
さらに税務署からの税務調査を受けた場合は、書類の作り直しや対応で通常業務が圧迫されるので注意が必要です。
情報漏えいのリスク
給与計算をする過程で、個人情報や給与情報を扱うため、それらの情報漏えいには細心の注意を払う必要があります。
情報を漏えいした従業員は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、またはその両方が課せられるリスクがあるため、適切に給与情報を管理しなければなりません。
また情報を漏えいした企業は、1億円以下の罰金が科せられ社会的な信用を失う可能性があります。
給与計算でミスが起きた際の対処法

給与計算でミスが起きた際は、発覚した段階で即座に謝罪しましょう。
給与計算のミスは、従業員の生活に直接影響するため、ごまかしや隠ぺいをせずに早急な対応が求められます。
また、給与計算のミスを防止するために、次のような対処法が効果的です。
- 保険料率の改定に対応するため、年間スケジュールを作成する
- ダブルチェック制度を導入して、入力・転記ミスを防止する
- チェックリストを作成して、入力・転記ミスを防止する
- マニュアルを作成して、月額変更届の提出漏れ防止する
- 給与計算システムを導入して、計算のミスを防止する
給与計算システムや勤怠管理システムを導入すれば、ヒューマンエラーの回避につながります。
給与計算のミスが起きないよう、マニュアルやチェックリストを作成し、DX促進しましょう。
初心者でも安心して給与計算できるようDXを促進しよう

初心者が給与計算する際は、覚えておくべき基礎知識と手順を把握しておきましょう。
給与計算の際は、労務リスクや税務リスク、情報漏えいのリスクに対処する必要があります。
当社では、給与計算の自動化だけでなく、健康経営や企業価値向上までを包括的に支援するソリューションを提供しています。
給与計算に関連する主な当社取り扱いソリューションは、次のとおりです。
- 人時革命
- 勤次郎
- SuperStream
- GLOVIA iZ
なお、給与明細のWeb配信には「i-Compass」がおすすめです。
下記のボタンから、給与明細の工数やコストを削減する「i-Compass」の導入事例を確認できます。
給与計算を円滑化するために、導入事例を確認してお気軽にご請求ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓