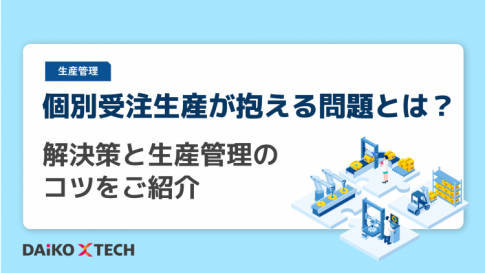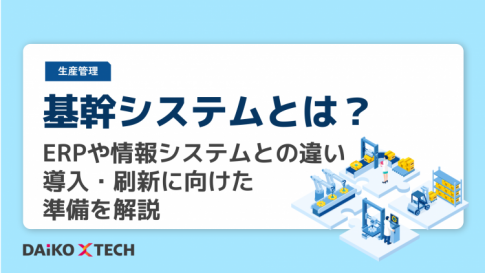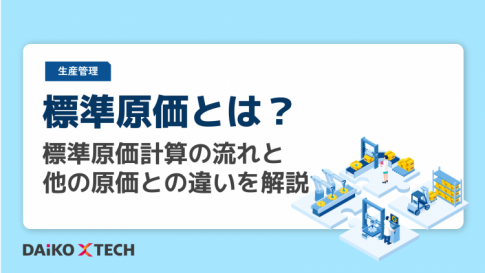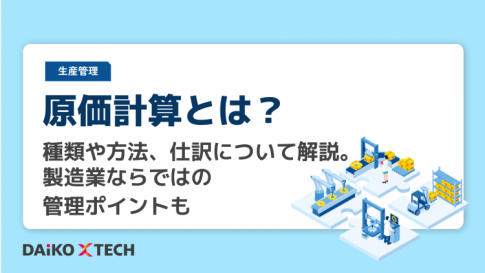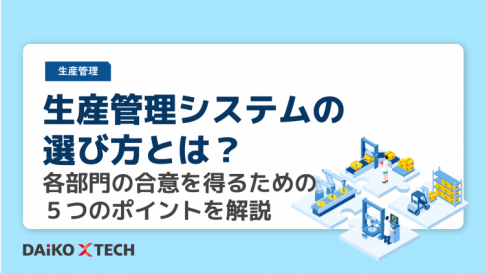トレーサビリティとは、製品材料から消費者の手元に届くまでの履歴を把握する仕組みです。適切にトレーサビリティを取ることは品質管理に欠かせないため、さまざまな業種で導入されています。
製造業においては、原材料調達から、加工や組立、販売までを追跡できるようにしなければなりません。
本記事では、トレーサビリティを支える仕組みやメリット、デメリット、効果的に活用する方法を解説します。
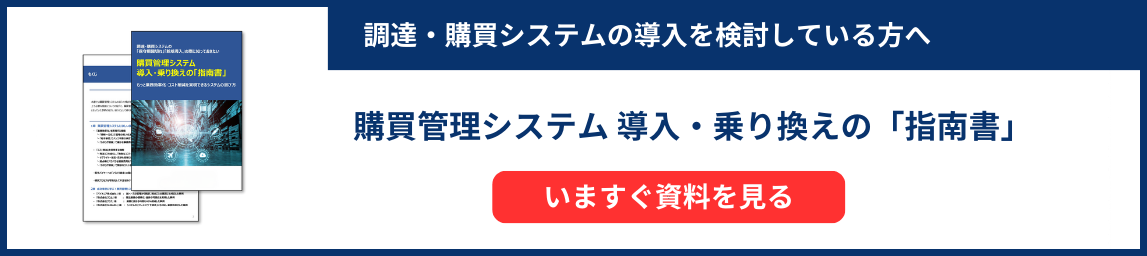
目次
トレーサビリティとは

トレーサビリティとは、Trace(追跡)とAbility(能力)を組み合わせた造語で、製品の原材料の調達から、加工、販売、消費までを追跡できる状態をさします。
業界によってトレーサビリティの定義は異なるのが特徴です。例えば、製造業の場合、原材料の調達から加工、組立、販売の各工程で製造者、仕入先、販売元などの情報を記録して、履歴を追跡できる状態とされています。
トレーサビリティの導入で、不具合が起きそうな部品を事前に排除できたり、データ分析を活用し、効率的な生産や品質管理ができたりするのが主なメリットです。
トレーサビリティの種類

トレーサビリティには大きく2種類あります。
- チェーントレーサビリティ:企業間の移動を把握
- 内部トレーサビリティ:工程内の移動を把握
それぞれ解説していきます。
チェーントレーサビリティ:企業間の移動を把握
チェーントレーサビリティとは、企業間の移動を把握する仕組みです。原材料の調達から加工、組立、販売の各工程で製造者、仕入先、販売元などの情報を記録して、履歴を追跡できるようにします。手元の商品がどこから来たのかがわかるため、消費者が安心しやすい特徴があります。
内部トレーサビリティ:工程内の移動を把握
内部トレーサビリティとは、工程内の移動や作業内容を把握する仕組みです。企業や工程など、作っている場所を限定して追跡できるため、品質や生産管理がしやすくなるのが特徴です。
例えば、生産効率が悪くなった場合、原因追及や不具合が発生した際にどの工程で品質に原因があったかを確認する手段として役に立ちます。
結果として、内部トレーサビリティの導入は、業務効率化や品質向上に役立つ仕組みと言えます。
トレーサビリティを支える3つの仕組み

トレーサビリティを支える仕組みは以下の3つです。
- バーコードやICタグによる個体識別
- IoTデバイスやセンサーによるリアルタイムデータ収集
- ロットトレースによる生産ロットの追跡管理
それぞれ詳しく解説します。
バーコードやICタグによる個体識別
トレーサビリティを実現するには、個々の部品や製品を一意に識別する必要があるため、バーコードやICタグを用いるのが一般的です。
バーコードは安価で導入しやすいですが、ハンディターミナルなどの読み取るための装置を用意しなければなりません。一方でICタグは、非接触で大量の情報を読み取りできるため、高度なトレーサビリティに使われるケースが多いです。
IoTデバイスやセンサーによるリアルタイムデータ収集
IoTデバイスやセンサーによるリアルタイムデータ収集もトレーサビリティを支える仕組みの一つです。
IoTは、Internet of Thingsの略で、さまざまな製品がインターネットにつながることでデータ収集や制御を可能にする技術です。製造現場にIoTデバイスを設置して、製品の位置情報や品質データなどを記録します。リアルタイムでデータが送られ、トレーサビリティシステムと連携が可能です。
ロットトレースによる生産ロットの追跡管理
トレーサビリティには、ロットトレースが使われています。ロットトレースとは、生産ロットごとに追跡管理を行える仕組みです。
ロットトレースには、製造現場で使われた材料や工程、日時などの情報が紐づけられています。万が一、リコールや不具合が発生した場合に、対象ロットの洗い出しをすぐに行えます。さらには、ロット単位での可視化ができるため、品質管理をきちんと行えるのが特徴です。
消費者にとっても、製品が問題なく作られていることが一目でわかるため、安心してもらいやすい効果もあります。
トレーサビリティシステム導入のメリット5つ
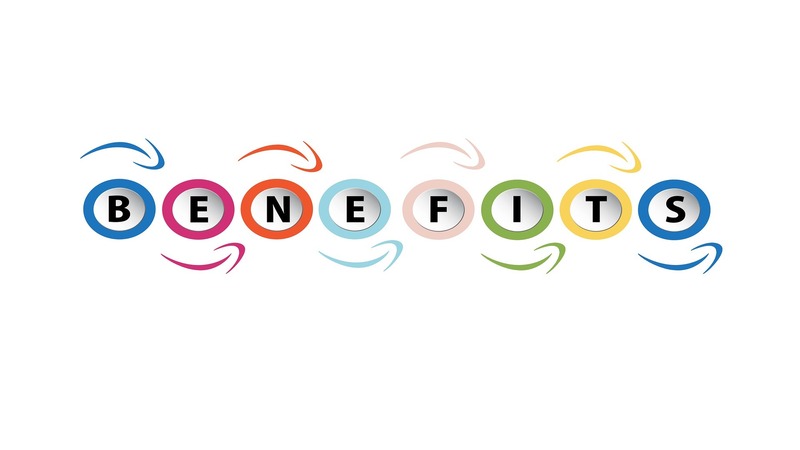
トレーサビリティシステムを導入するメリットは以下の5つです。
- 品質が向上する
- 迅速な不具合対応ができる
- 製造工程の見える化により業務効率化が図れる
- お客さま満足度が向上する
- 規制への対応を迅速に行える
品質が向上する
トレーサビリティの導入で、工程の各段階で詳細な品質データを記録し管理できるため、不良品の発生した際に原因を素早く特定し、適切な対策を講じられるのがメリットです。
さらに、工程間の品質を定量的に把握できると、生産数にばらつきがあった工程の最適化や品質向上を実現できます。この結果、不良品の発生頻度を大幅に低減でき、品質そのものを向上できる効果も期待できます。
迅速な不具合対応ができる
問題のある製品のロット番号や流通経路、製造された時期などを即座に把握できるのも、トレーサビリティシステム導入のメリットです。
万が一、不具合が発生しても、リコールの範囲をすぐに特定でき、被害を最小限に防げます。リコール対応は企業やブランドのイメージに大きく影響するため、迅速で適切な対応を行わなければなりません。
製造工程の見える化により業務効率化が図れる
トレーサビリティシステム導入で、製造工程の見える化が可能なため、進捗状況や在庫状況をリアルタイムで把握できるのがメリットの一つです。
工程の見える化によって得られる効果は以下のとおりです。
- ボトルネックや遅延している工程をすぐに特定ででき、対策を講じやすい
- 問題が発生していなくても、危険な場所や問題となりそうな部分を特定して、改善しやすい
- 在庫数の適正化
- リードタイム短縮
結果、生産計画の最適化がしやすくなり、業務効率化につながります。
お客さま満足度が向上する
トレーサビリティの導入で、お客さまのデータを蓄積でき、マーケティングに活かせるのがメリットです。
お客さまが求めている情報を貯められるため、より満足してもらえるような改善がしやすくなり、お客さま満足度の向上が期待できます。
一例として、部品メーカーでは、製品ごとの使用状況やお客さまからの問い合わせ履歴をシステムに記録することで、お客さまが求めている改善ポイントや要望を正確に把握し、次回の製品改良やサービス向上に反映させられます。
また、お客さまごとにカスタマイズされたサポートや提案がしやすくなり、より満足度の高い取引関係を構築できます。
こうしたマーケティングを活用した継続的な改善は、お客さまの信頼感を高め、長期的な関係性の維持にもつながっていくため、トレーサビリティシステム導入の効果は大きいです。
規制への対応を迅速に行える
製品の安全性や品質に関する規制は年々強化される傾向にあり、特にグローバル展開している企業にとっては、各国の規制対応が非常に重要です。
トレーサビリティの導入で、製品に使用されている部品の調達先、製造工程に関するデータを一元管理し、必要な証明書や報告書を迅速に提出できます。
また、万が一、品質問題が発生した場合も、原因特定や影響する範囲をスムーズに把握でき、規制当局からの調査にも適切に対応ができるのも大きなメリットです。
規制対応はどの企業も行わなければ、信頼性やブランド力が低下してしまいます。企業の継続した成長のためには、トレーサビリティシステムを導入し、迅速に適切な規制対応を行っていきましょう。
トレーサビリティシステム導入の課題3つ

トレーサビリティシステムは導入する必要がありますが、簡単に導入できるものではありません。導入の主な課題は以下の3つです。
- データの整合性を確保するのが難しい
- 外部への情報漏えいリスクが高まる
- 導入コストがかかる
それぞれについて解説します。
データの整合性を確保するのが難しい
トレーサビリティの導入には、時間と費用がかかるのが大きな課題の一つです。特に、製造工程が複数の工場やサプライヤにまたがる場合、データの収集・統合には多大な労力が必要です。
例えば、自動車部品メーカーでは、各部品の製造元や加工履歴を正確に記録・管理しなければなりません。しかし、手動入力やシステム間のデータ連携にミスが生じると、トレーサビリティ情報に矛盾が発生し、問題解決が遅れる可能性があります。
さらに、古いシステムや異なるフォーマットのデータを統合するには追加の開発コストが発生することもあります。データ整合性の確保は、簡単にはできないため、システム導入時にの大きな課題です。
外部への情報漏えいリスクが高まる
トレーサビリティシステムは、製品の図面や製造に関する機密情報を多く扱っています。外部に情報が漏えいすると企業だけでなく、お客さまの個人情報が危険にさらされる可能性があります。必ずセキュリティ対策を講じなければなりません。
トレーサビリティシステムは、製品の図面や製造に関する機密情報を多く扱っています。特に、製品の詳細な仕様や製造工程に関するデータは、競合他社や悪意のある第三者にとって貴重な情報資産です。
例として、精密機器メーカーでは、サプライチェーン全体で共有すべきデータが多く、その過程でサイバー攻撃の標的になるリスクが高まります。また、外部ベンダーやパートナー企業とのデータ連携においても、不正アクセスや情報漏えいが発生する可能性があります。
トレーサビリティシステム導入による情報漏えいリスクを低減するためには、強固なセキュリティ対策やデータ暗号化技術の導入、定期的な監査などの体制を構築する必要があるのも、大きな課題です。
導入コストがかかる
専用のシステムやソフトウェアを導入する必要があるのもトレーサビリティシステム導入の課題の一つです。
例えば、電子部品メーカーがトレーサビリティシステムを導入する場合、既存の生産管理システムとの統合やデータ収集のための専用デバイス導入が必要になるため、費用が発生します。
また、新しいシステムを導入すると、発生する主な費用は以下のとおりです。
- 従業員への研修費用
- 運用体制の整備
- 導入後もシステムの保守アップデート
これらのような費用が発生するため、トレーサビリティの導入には多大なコストがかかるのが課題です。
トレーサビリティを効果的に活用する4つの方法

トレーサビリティを効果的に活用する方法は、以下の4つです。
- 導入の目的を明確化する
- 生産に関わるすべての関係者と協力体制を築く
- 継続した改善を行っていく
- 専門的な知識をもった企業と連携する
導入の目的を明確化する
トレーサビリティを効果的に活用するには、導入目的の明確化が重要です。どのデータを収集し、どのように活用するのかを明確にすることで、適切なデータを選び、システムの費用対効果を高められます。
製造業では、不良品発生時の原因特定や法規制対応を目的としてデータを収集するケースがあります。一方で、目的があいまいなままだと、システムを導入してデータを集めても適切に活用されず、導入効果が実感できないまま終わる可能性があり、避けなければなりません。
まずは、目的を明確にし、全社で共通認識を持つことがトレーサビリティシステム活用の第一歩です。
生産に関わるすべての関係者と協力体制を築く
トレーサビリティを効果的に活用するには、生産に関わるすべての関係者との協力体制が欠かせません。
システムの導入には、部品供給者、製造業者、流通事業者、さらには最終消費者まで、すべての段階でデータの正確な記録と共有が必要です。一例として自動車部品メーカーでは、サプライヤから部品が納品される際に正確なロット情報や品質データが共有されていなければ、完成品の品質保証が難しくなってしまいます。
関係者間で合意形成を行い、共通の目標を設定し、データの透明性を確保することで、効果的なトレーサビリティの運用が実現できます。
継続した改善を行っていく
トレーサビリティシステムは導入して終わりではなく、定期的に効果や機能を評価し、改善を繰り返すことが重要です。
例えば、製造現場で新たな工程や設備が導入された場合、トレーサビリティシステムも合わせて調整する必要があります。また、市場やお客さまのニーズは常に変化しており、応じたシステムもブラッシュアップしていかなければなりません。
短期的な運用効果の確認だけでなく、中期、長期的な視点で改善プランを策定し、継続的にシステムを進化させることがトレーサビリティの効果的な活用につながります。
専門的な知識を持った企業と連携する
トレーサビリティの導入には、高度な専門知識が必要です。
初期設計から運用、改善までを一貫してサポートできる専門企業と組むことで、予期しないトラブルや運用上の課題にも迅速に対応できます。特にサイバーセキュリティ対策やデータ統合の問題は、専門家の知識がなければ適切に解決できないことがあります。
信頼できるパートナー企業を選定し、協力しながら導入を進めることがトレーサビリティの効果を最大にするための近道です。
トレーサビリティシステムを導入してお客さま満足度を向上させよう

製造業でトレーサビリティシステムを導入することは、品質向上や製造工程の見える化、お客さまの満足度向上、迅速な規制対策などさまざまなメリットをもたらします。
しかし、データの整合性を合わせるために多くの費用がかかることや、情報漏えいリスクに対応する必要があるなどの課題が多くあり、導入するのは簡単ではありません。
目的や課題、運用体制を明確にし、段階的な導入を進めることで、お客さま満足度が向上する効果的なトレーサビリティシステムを導入できるでしょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
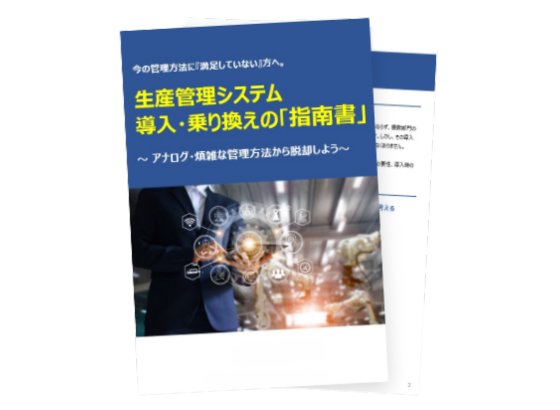
今の生産管理方法に不満がある、という方へ。
生産管理システム 導入・乗り換えの「指南書」