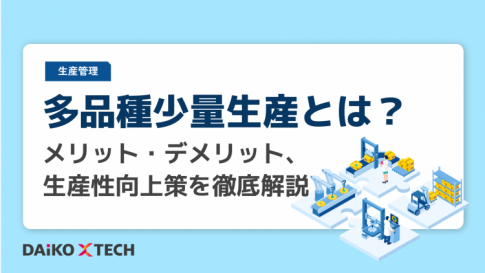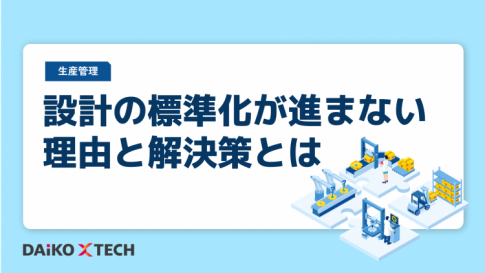QCDはモノづくりにおいて重視される「品質・コスト・納期」のフレームワークです。モノづくりを行う現場のみで活用されるのではなく、製造業にかかわるあらゆる職場で効果的な考え方でもあります。
本記事では、QCDのフレームワークを業務に活用するメリットや、業務への活用方法をご紹介します。
さらに、時代に合わせて多様化するQCDの種類や、製造業で活用される他のフレームワークについても解説します。
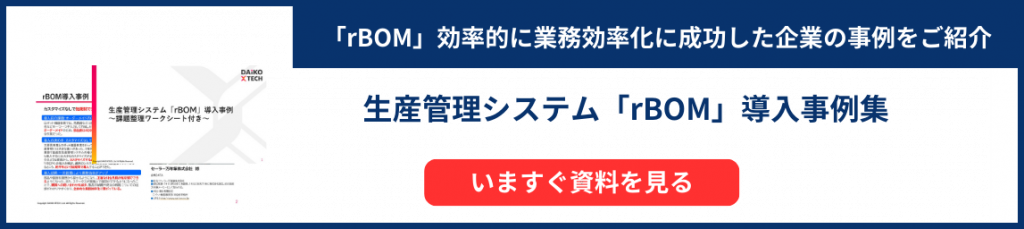
目次
QCDフレームワークとは?

QCDフレームワークとは、製造業で用いられる「Q:品質」「C:コスト」「D:納期」を重視する考え方を、モノづくり以外の業務やマネジメントにも活かすことを指します。
本章では、QCDの考え方の基本や、フレームワーク自体の概要についても解説します。
QCDとは?
QCDとは、品質(Quality)・コスト(Cost)・納期(Delivery)をバランスよく意識してモノづくりを行う考え方のことです。
顧客満足度(CS)や安全性の観点から品質が最優先ではあるものの、他の要素を軽視していては利益を確保できないため、QCDのバランスが重要です。
コストばかり重視してしまうと、品質が著しく下がったり、人手不足で納期遅延を発生させてしまったりといったリスクがあります。
納期ばかり重視してしまうと、納期に間に合わせるために時間がかけられず品質が落ちてしまったり、納期遵守のため深夜残業や休日出勤を繰り返し必要以上に人件費が掛かってしまったりするリスクがあります。
したがって、QCDを考慮する際には、それぞれの要素をバランスよく意識して行う必要があります。
QCDについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。
フレームワークとは?
フレームワークとは、課題達成や問題解決のために用いられる考え方の枠組みのことを言います。
ビジネスにおいて、フレームワークが用いられるのは、課題や問題に対して論理的に取り組めるメリットがあるためです。
多くの場合、個人の思い込みや感情論ではビジネス上の問題解決や課題達成はできません。
また、フレームワークの多くがチーム内で共有されるため、多角的な視点によってより多くの問題解決や課題達成につながる効果もあります。
QCDのフレームワーク活用のメリット

前章で、QCDのフレームワークはビジネス上の課題達成や問題解決のために活用されることを解説しました。
本章では、QCDのフレームワークを活用するメリットについて解説します。
具体的には、以下のメリットが挙げられます。
- 企業の利益につながる
- 顧客満足度(CS)が向上する
- 従業員満足度(ES)が向上する
以降で詳しく解説します。
企業の利益につながる
まず、QCDのフレームワークを活用するメリットとして、企業の利益につながることが挙げられます。
課題に対してのQCDのバランスの取り方を意識できれば、無駄なコストを抑えつつ魅力的な製品やサービスを提供できるからです。
例えば営業部門で新規受注するにあたって、価格に対して求められる品質や掛かるコスト、納期を意識するようにQCDフレームワークを導入します。
すると、受注数のみ重視するのではなく、「納期に間に合うような人員体制で、品質を担保できるような見積設定なのか」といった利益を出せる営業が可能になり、企業全体の利益につながります。
顧客満足度(CS)が向上する
顧客満足度(CS)の向上もQCDフレームワークを活用するメリットの一つです。
モノづくりだけでなく、サービスの提供や顧客対応においても、QCDの3要素は重要なためです。
一定の品質が保たれ、費用がかかりすぎず、納期が守られる製品やサービスは、顧客満足度も高くリピート率も向上します。
また、顧客対応においてもQCDフレームワークを活用できれば、できる限り早く、かつ正確に、コストを抑えつつ業務を行い、結果として顧客の要望にも応えられるため、顧客満足度(CS)の向上にもつながります。
従業員満足度(ES)が向上する
従業員満足度(ES)が向上するのもQCDフレームワーク活用のメリットの一つです。
事前にQCDを考慮してモノづくりやサービスを開始すれば、過剰な残業や頻繁な休日出勤といった無計画なマネジメントが削減できるためです。
間に合わなければ残業や休日出勤させれば良いといった考え方は、労働基準法違反となりうるだけでなく、従業員の離職率悪化にもつながりかねません。
顧客の要望した納期と現場の生産能力とを厳密に計算して、高品質な製品やサービスを提供できるようになれば、労働環境が快適になり、従業員満足度(ES)の向上にもつながります。
QCDのフレームワークを業務に活用する方法

本章では、QCDのフレームワークを自分自身、またはチーム単位での業務に活かす方法について解説します。
具体的には、以下の方法で行います。
- 事前に業務の認識合わせをする
- 問題解決や業務改善に役立てる
- 業務の優先順位づけを行う
以降で詳しく解説します。
事前に業務の認識合わせをする
QCDのフレームワークを業務に活用する際は、事前の業務の認識合わせに活用するのも効果的です。
あらゆる業務において、求められる品質と掛けるべき労力、納期を確認するのは重要です。
個人で判断するのではなく、事前に依頼者や関係各所との認識を合わせておきましょう。
認識合わせを怠ると、以下のように認識のズレからトラブルになってしまうリスクがあります。
|
とにかく納期に間に合わせるために急いだが、品質が良くなかったためクレームになった。 先方は品質にこだわってほしく、相談してもらえれば納期を延ばせたのに、と不満を持っていた。 |
よって、QCDのフレームワークは業務上、当事者同士での事前の認識合わせの際に有効活用できます。
問題解決や業務改善に役立てる
問題解決や業務改善に役立てるのもQCDフレームワークの有効的な活用方法です。
クレームなど、問題が起きた際に品質、コスト、納期のうち何が問題なのか、どうバランスを取るべきかを検討するのが解決や改善につながりやすいためです。
しかし注意すべきなのは、自社の中だけで片付けないことです。
例えばクレームの原因が品質であったとして、「品質を優先するとコストが上がるため次回以降は価格を大幅に上げる」といった独断での判断は顧客の信用を失いかねません。
QCDのバランスを変更する際には、顧客や関係各所との協議の上進めていきましょう。
業務の優先順位づけを行う
業務の優先順位づけを行う際にもQCDフレームワークが有効活用できます。
ビジネスにおけるさまざまな場面で優先順位づけは重要ですが、QCDのフレームワークを用いることで、何を優先すべきかが見えやすくなるためです。
例えば、新しいプロジェクト立ち上げの際にも、優先事項を決める際に役立ちます。
- 正確性を求めるため、時間を掛けて分析するべきか
- 予算の上限を考慮して、予算内でできる限りの品質に留めるべきか
- 開始日をずらせないため、一時的に人員補充を行ってでも納期を優先すべきか
以上のように、プロジェクトを進めるにあたっても事前にQCDフレームワークを用いて優先順位を決めておくと、スムーズにプロジェクトが進みます。
QCDの多様化

QCDは、近年ではさらに発展しており、品質、コスト、納期だけでなく他の要素も同様に重視すべきであるといった考えが広まっています。
本章では、QCDの考え方を元にして、さらに他の要素を加えたQCDの多様化について、具体例を挙げながら解説します。
QCDの多様化について具体的には、以下のような考え方があります。
- 安全性を意識する:QCDS
- サービスを意識する:QCDS
- モチベーションを意識する:QCDSM
- 環境を意識する:QCDE
- 開発や経営を意識する:QCDDM
以降で詳しく解説します。
安全性を意識する:QCDS
QCDSは2種類あり、まずはQCDの考え方に安全性(Safety)を加えたQCDSを解説します。
特に、危険作業が多い現場や、切削や圧縮など誤作動や作業ミスにより重大な事故になりかねない業務では重視して取り入れるべき考え方です。
危険を伴う現場で作業する従業員にとって、自身の安全性が担保されずに「品質」「コスト」「納期」といった項目ばかりを重視されている状況では安心して働けません。
安全性を意識する職場づくりのためには、5S活動による現場の整備も重要ですが、未然防止の考えを元に将来起こりうるリスクを想定した職場環境作りを行いましょう。
安全性を軽視した経営は従業員の離職につながるため、QCD同様に安全性を重視して、バランスを取りながらビジネスを構築していくのが重要です。
サービスを意識する:QCDS
もう一つのQCDSは、QCDの考え方にサービス(Service)を加えた考え方です。
顧客サービスを重視する業種で採用される傾向にあります。
質の高い製品を提供できたとしても、他社へのコミュニケーションやサービス対応が粗雑であれば、売上にはつながりません。
例えば、営業先の新規開拓や新製品の発売、既存商品の販路拡大などではQCDにプラスしてサービスを重視すると効果的です。
また、サービスにおいてもバランスが重要です。
過剰な割引により売上を上げたとしても、利益を圧迫してしまいコストとの調整が難しくなり、さらにはコストを掛けられなくなってしまった結果、品質も落ちてしまうといったリスクがあります。
よって、QCDSにサービスを追加する場合にもバランスを重視するのが重要です。
モチベーションを意識する:QCDSM
QCDSMは、先述したQCDS(安全性、サービスの両方)にプラスしてモチベーション(Morale)を加えた考え方です。
従業員の高いモチベーションは、生産性の向上や現場改善につながります。
しかし、従業員にモチベーションを上げるよう強制しても、思うような効果は上がりません。
モチベーションを上げるためには、経営者や管理職が改善や生産性の向上による従業員自身のメリットを伝える必要があります。
- 生産性が向上し利益が上がれば業績が向上し、給与アップにつながる
- 改善活動を行えば、ヒューマンエラーが減り業務上の心理的負担を軽減できる
以上のようなメリットを繰り返し伝えることによって、従業員も高いモチベーションで作業を行えます。
したがって、従業員自身が高いモチベーションで従事できるような環境づくりを続けながら、QCDSMをバランス良く意識する必要があります。
環境を意識する:QCDE
QCDEは、QCDに環境(Environment)を加えた考え方です。
企業活動において、環境への配慮に対する社会的責任があります。
排水や排気ガス、廃棄物などで地球環境を汚染するリスクがある事業では、特に意識すべき考え方です。
環境に配慮した事業にはコストが掛かるため、特にコストと環境は大きな関係性があります。
QCDEもバランスが重要ではあるものの、コストのために環境配慮の優先度を下げるような調整は行うべきではありません。
環境配慮のためのコストは必須として、効果測定を行いながら必要以上のコストが掛かっている場合にはバランスを取る、といった考えで調整を行いましょう。
開発や経営を意識する:QCDDM
QCDDMは、QCDに開発(Development)と経営(Management)を加えた考え方です。
主に原材料の調達で重視されます。
SDGsの持続可能な開発目標を達成するためには、調達段階でのサプライヤ選定が重要です。
QCDを兼ね備えているサプライヤを選択するのはもちろん、以下のように開発、経営面でも評価を行います。
- 開発:技術力や開発力を評価する。SDGsへの取り組み状況はもちろん、提案力や改善活動、サポート状況なども考慮する。
- 経営:財務状況の安定性やリスク管理、コミュニケーション能力などの経営能力を考慮して評価する。
製造業で活用される他のフレームワークとは?
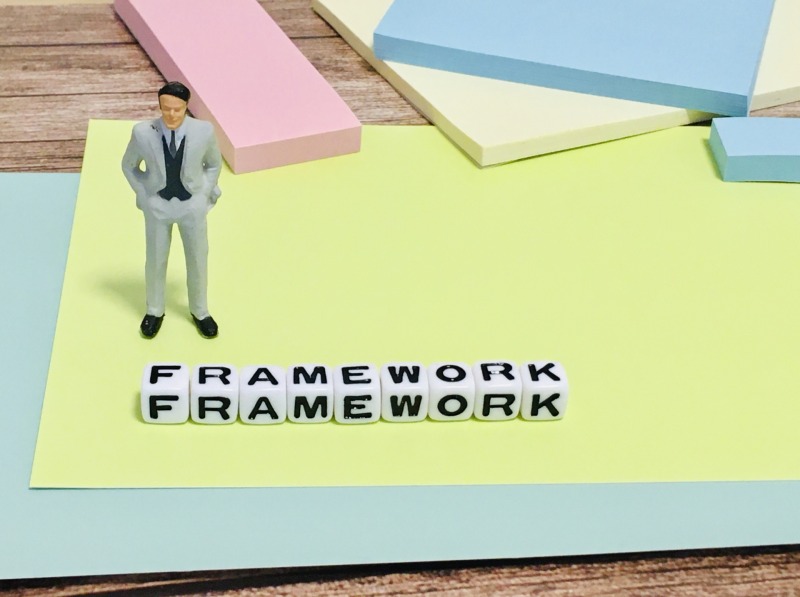
製造業では、QCDの他にもさまざまなフレームワークが活用されています。
本章では、モノづくりだけでなく、マネジメントやプロジェクトでも活用できる以下のフレームワークをご紹介します。
- 5W1H
- ECRS
- QCストーリー
- なぜなぜ分析
- 特性要因図
以降で詳しく解説します。
5W1H
5W1Hは、状況整理に役立つフレームワークです。
具体的には、以下の情報を整理して、問題解決や課題達成のための状況整理を行います。
- When:発生時間、期間などの情報
- Where:発生箇所の詳細情報
- Who:担当者、取引先など関係者の情報
- What:具体的な内容、状況の情報
- Why :原因または目的の情報
- How:方法や手段の情報
特に、管理職が部下に報告を求める際に、5W1Hで状況整理をさせると客観的なデータを収集できます。
ECRS
ECRSはムダ取りや業務改善に効果的なフレームワークです。
具体的には、以下のように業務のムダを省けないかといった観点で検討します。
- 排除(Eliminate):作業自体をなくせないか
- 結合(Combine):分かれている作業を結合できないか
- 交換(Rearrange):作業自体、または作業場所を交換できないか
- 簡素化(Simplify):複雑な作業を見直して簡素化できないか
特に長年習慣として行っている作業や業務は、追加作業や機械の入れ替えなど状況の変化によりムダ作業が発生している可能性があるため、ECRSのフレームワークを元に見直しを行います。
QCストーリー
QCストーリーも問題解決や課題達成の際に活用されるフレームワークの一つです。
具体的には、以下の8つのステップを行います。
【問題解決型】
- テーマ設定
- 現状把握・目標設定
- 計画作成
- 要因解析
- 対策検討・実施
- 効果測定
- 標準化
- 反省と未然防止
【課題達成型】
- テーマ選定
- 目標設定
- 計画作成
- 方策立案
- シナリオ実施
- 効果測定
- 標準化
- 反省と未然防止
以上のように、直面している問題を解決するのか、対応するべき課題を達成するのかによってステップが異なることが特徴的です。
なぜなぜ分析
問題解決の際にはなぜなぜ分析のフレームワークが有効です。
問題の発生源の特定のために活用します。
特定の事象が発生した原因を「なぜ」が出なくなるまで繰り返して深掘りする分析方法です。
以下の記事でもなぜなぜ分析について解説しておりますので、ぜひご一読ください。
特性要因図
特性要因図も、問題解決の際の要因分析に役立つフレームワークです。
問題が生じた際の要因をあぶり出すために作成される図のことで、完成した図が魚の骨に似ているにていることから「フィッシュボーン図」とも呼ばれます。
特性要因図は、発生した問題について、思いつく限りの要因を漏れなく書き出します。
要因がいくつか絡み合っている場合に有効です。
特性要因図についても、以下の記事で解説しておりますので、ぜひご覧ください。
QCDのフレームワークはモノづくりだけでなく、マネジメントやプロジェクト運営にも有効

本記事では、モノづくりにおいて重視されるQCD「品質・コスト・納期」のフレームワークについて業務に活用するメリットや、業務への活用方法をご紹介しました。
また、時代に合わせて多様化するQCDの種類や、製造業で活用される他のフレームワークについても解説しました。
QCDのフレームワークは、モノづくりの経営で考慮するだけではなく、業務上のマネジメントや問題が発生した際の解決策、課題の整理にも活用できます。
問題解決や課題達成のためには、フレームワークだけではなく、部門間での情報の適切な管理や共有も重要です。
以下のホワイトペーパーでは、弊社の提供する生産管理システム「rBOM」活用事例や、自社の課題を整理できるワークシートを掲載しているため、ぜひご一読ください。