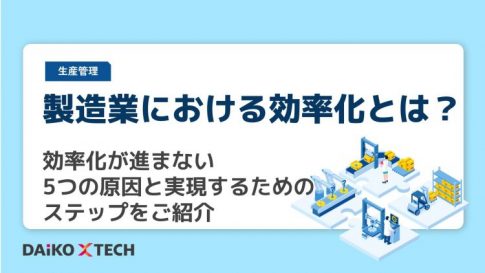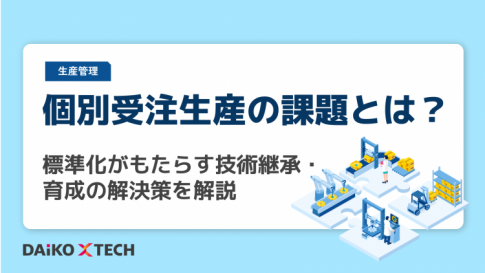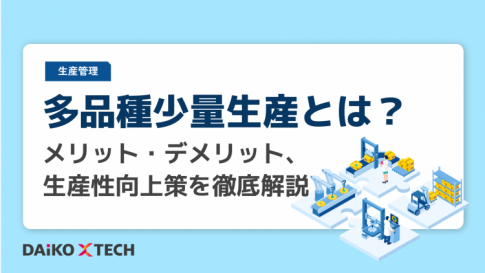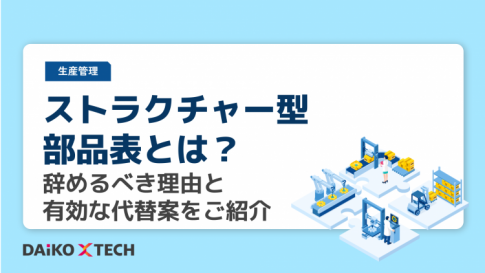CMMSとは、設備の安定稼働と保全業務の効率化を支援する設備保全管理システムのことです。製造業をはじめとする多くの企業にとって、生産設備の安定した稼働は、事業継続と競争力を左右する重要な要素です。
しかし、設備の老朽化や予期せぬ故障、さらには熟練保全担当者の退職による技術継承の課題など、設備保全を取り巻く状況は年々複雑化しています。
こうした背景から注目されているのが、CMMSの導入です。CMMSは、保全業務の可視化・自動化・最適化を実現するツールとして、設備管理の効率向上とコスト削減に貢献します。
本記事では、CMMSの意味・役割から、主な機能、導入によるメリット、選定ポイントまで、企業の設備管理や工場運営に携わる方に役立つ情報をわかりやすく解説します。
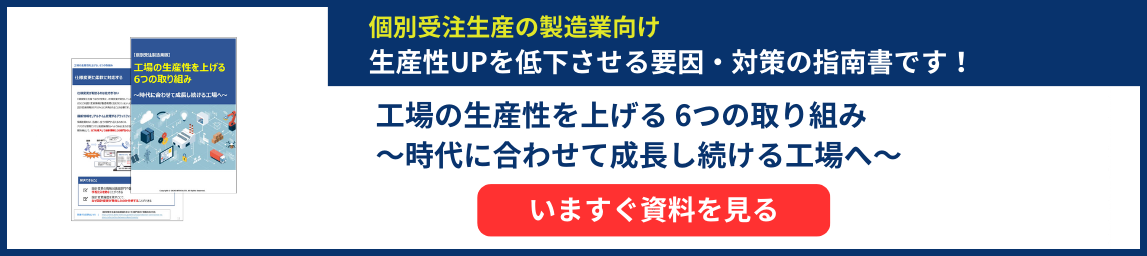
目次
CMMS(設備保全管理システム)とは

CMMSを理解するためには、まずその定義、目的、解決できる課題、主な利用対象者、そして関連システムとの違いを把握することが重要です。
CMMSの定義と目的
CMMS(Computerized Maintenance Management System:設備保全管理システム)とは設備の安定稼働を最大化するために保全業務を支援し、蓄積された保全データを分析することでコストを最小化しながら効果的な保全業務を実現するITシステムです。
具体的には、日々の設備点検や部品の在庫管理、保全計画の策定・進捗管理といった一連の保全管理業務をサポートする役割を担います。
CMMSの重要な目的の一つは、設備がどのような状況にあるのかを正確に把握し、それを可視化することです。従来の手作業やExcelによる管理では限界があった情報の一元化とリアルタイムな共有を可能にし、保全業務全体の最適化を目指します。
過去の故障事例や対処方法を容易に参照できるようにして、経験の浅い保全担当者でも迅速かつ正確な復旧作業を行えるように支援するのも、CMMSの重要な目的です。
CMMSが注目されている理由
CMMSが注目されている背景には、製造業を取り巻く環境の変化があります。
- 設備の高度化・複雑化により、従来の経験と勘に頼った保全では限界が生じている
- IoTやAI技術の発展により、設備の状態をリアルタイムで監視し予知保全を実現できる環境が整ってきた
- 人材不足が深刻化する中、限られた人員で効率的に保全業務を遂行する必要性が高まっている
- コロナ禍を経て、リモートワークやデジタル化の重要性が再認識され、クラウド型CMMSの普及が加速している
これらの要因が複合的に作用し、CMMSへの関心と導入が急速に拡大しています。
CMMSの主な利用対象者と業種
CMMSは設備保全に関わる幅広い部門の担当者が利用します。
- 保全担当者・技術者
- 保全部門管理者
- 生産管理者・工場管理者
- 在庫管理者
- 経営層
現場の作業員から経営判断を行うマネジメント層まで、それぞれの立場で必要な情報をCMMSから得て活用できます。
主な対象業種として、CMMSは、物理的な設備やインフラが事業運営に不可欠なあらゆる業種で活用されています。
- 製造業全般
- 食品・飲料製造業
- 化学工業、製薬業
- 上下水道・ユーティリティ
- エネルギー産業
- 建設業
- 運輸・物流業
- 石油・ガス・鉱業 など
設備が重要な役割を果たす多くの分野で導入が進んでいます。
CMMSの主要機能とできること

CMMSは、設備保全業務を多角的に支援するためのさまざまな機能を有しています。以下、主要な機能について詳しく解説します。
設備台帳管理
設備台帳管理は、CMMSの中核となる機能であり、保全対象となる全ての設備に関する情報を一元的に管理します。
- 機器の名称
- 型式
- メーカー
- シリアル番号
- 設置場所
- 導入年月日
- 資産番号
- 分類コード など
基本情報としてこれらが登録され、仕様情報、履歴情報、関連情報も管理されます。
設備を親子関係で階層的に管理し、大規模なプラントや複雑な装置群の構成を分かりやすく表現できます。設備台帳は、単なるリストではありません。各設備の「デジタルなカルテ」としての役割を果たし、他の機能が効果的に機能するための基盤です。
保全計画管理と予防保全
保全計画管理機能は、設備の故障を未然に防ぎ、安定稼働を維持するための予防保全(Preventive Maintenance:PM)活動を計画・実行・管理する上で不可欠です。
定期点検、部品交換、オーバーホールなどの保全作業の実施計画を策定し、過去の保全実績や設備の推奨メンテナンスサイクルに基づいて保全カレンダーを作成します。
予算や生産計画、設備の重要度、故障リスクなどを考慮して、保全計画の優先順位付けや実施時期の調整が可能です。時間基準(例:3ヶ月ごと)、使用量基準(例:1000時間稼働ごと)、あるいは特定のイベント発生をトリガーとして、予防保全のための作業指示を自動的に発行する機能もあります。
作業指示管理
作業指示管理は、保全作業の依頼から完了までの全プロセスを追跡・管理するCMMSの中心的な機能です。故障修理や定期点検、改良工事などのあらゆる種類の保全作業に対して作業指示書を作成・発行し、以下の安全上の注意点などが明記されます。
- 作業内容
- 対象設備
- 作業場所
- 担当者
- 期限
- 必要な部品や工具
発行された作業指示の進捗状況をリアルタイムで追跡でき、作業の遅延や滞留を早期に把握し、対策を立てることが可能です。
- 実際にかかった作業時間
- 使用した部品
- 交換部品のシリアル番号
- 作業内容の詳細
- 故障原因
- 処置内容 など
作業完了後は上記を記録し、正確な保全履歴が蓄積されます。
点検管理と保全履歴管理
タブレットやスマートフォンを利用して、現場で日常点検や巡回点検の結果を直接入力できます。これにより、紙の点検表が不要になり、転記作業やそれに伴うミスが削減可能です。
設備ごと、点検種類ごとに標準的な点検項目やチェックリストを事前に登録・管理でき、オフライン環境での入力に対応しているシステムもあります。
保全履歴管理では、過去に実施されたすべての保全作業の履歴を設備ごとに一元的に記録・管理します。
- 故障発生日時
- 停止時間
- 故障現象
- 原因
- 要因
- 処置内容 など
上記の内容を詳細に記録します。蓄積された保全履歴は、将来の保全計画の最適化や故障トレンドの分析に活用されます。
部品・在庫管理
適切な部品・在庫管理は、保全作業の迅速性とコスト効率に直結するものです。CMMSは、保全に必要な交換部品や消耗品(MRO品)の在庫を最適化する機能を有しています。
保管場所ごと、部品ごとに現在の在庫数、安全在庫数、発注点などをリアルタイムで管理・表示します。
在庫数が発注点を下回った場合にアラートを通知したり、自動的に発注要求を作成したりする機能を持つシステムがあるのも重要な点です。
データに基づいた在庫管理により、不必要な過剰在庫を削減し、同時に作業時に必要な部品が不足する事態を防ぎます。
レポート・分析機能
CMMSに蓄積された膨大な保全データは、レポート・分析機能を通じて、保全業務の改善や経営判断に役立つ貴重な情報へと変わります。
設備稼働率、平均故障間隔(MTBF)、平均修理時間(MTTR)、保全コスト実績、作業員の作業負荷状況など、主要なKPIに関する定型レポートを容易に作成・出力可能です。
主要なKPIや保全状況をグラフやチャートで視覚的に表示するダッシュボード機能により、状況を一目で把握できます。マクロな視点での効果測定から、現場の改善活動に役立つミクロな分析まで幅広く対応します。
設備ごとの修理コスト分析や故障傾向の分析で、適切な保全計画の策定や、将来的な設備投資の最適化など、経営層の意思決定をサポートできるのも特長的です。
図書管理(ドキュメント管理)
設備保全業務には、多種多様な技術文書や資料が不可欠です。CMMSの図書管理機能は、これらの情報を一元的に整理・保管し、必要な時に容易にアクセス可能にします。
Word、Excel、PDFといった一般的な文書ファイルに加え、写真、図面、動画、作業手順書、安全データシート(SDS)、メーカーの取扱説明書、保証書など、さまざまな形式のファイルを管理できます。
過去に発生した故障やトラブルの事例、その対処方法などを文書や画像、動画として蓄積・共有するのは非常に重要です。経験の浅い保全担当者でも迅速かつ正確な対応が可能で、技術伝承にもつながります。
CMMS導入のメリット:なぜCMMSが必要なのか?

CMMSを導入することは、企業にとって多岐にわたる具体的なメリットをもたらします。以下では主要なメリットについて詳しく解説します。
設備稼働率の向上とダウンタイム削減
CMMS導入による直接的かつ重要なメリットの一つが、設備稼働率の向上と予期せぬダウンタイムの削減です。CMMSは、予防保全(PM)や、IoTセンサーやAIと連携した予知保全(PdM)の計画と実行を支援します。
これにより、設備の突発的な故障を未然に防ぎ、計画外の生産停止を大幅に削減できます。
設備に故障が発生した場合でも、CMMSに蓄積された過去の修理履歴や対応手順、関連図書などを迅速に参照できるため、復旧までの時間(MTTR)を短縮可能です。
CMMSは設備のダウンタイムを記録・分析し、その原因や傾向を明らかにします。特に頻繁に停止する設備やボトルネックとなっている箇所を特定し、集中的な対策を立てられます。
メンテナンスコストの最適化と削減
計画的な予防保全により、大規模な故障やそれに伴う高額な緊急修理の発生を抑制可能です。小さな問題が大きくなる前に対処することで、修理費用そのものを低減します。
部品在庫の適切な管理によって、過剰在庫に伴う保管コストや廃棄ロスを削減します。また、必要な部品を適時に調達できるため、緊急手配による割増コストも回避できるのも特長的です。
作業指示の自動化やスケジューリングの最適化、移動時間の削減(モバイル対応による)などにより、保全担当者の作業効率が向上して無駄な残業や人員コストを抑制できます。
経験や勘に頼った過剰なメンテナンスを避け、データに基づいて本当に必要な時期に必要な作業のみを行うため、不要な部品交換や作業コストを削減します。
保全業務の効率化と標準化
CMMSは保全業務のプロセス全体をデジタル化し、標準化して大幅な効率向上を実現します。点検項目、修理手順、安全確認事項などをCMMS上で標準化し、だれでも一定の品質で作業を行うことが可能です。
これにより、個人の経験やスキルへの依存度を低減し、作業のバラツキをなくします。
設備情報や保全履歴、作業指示、図面などの情報がCMMSに一元化され、関係者間でリアルタイムに共有されます。
部門間の連携がスムーズになり、情報の伝達ミスや確認作業の手間が削減可能です。紙ベースの作業指示書、点検記録、報告書などを電子化して、書類の作成、配布、保管、検索にかかる手間とコストを大幅に削減します。
- 現場で作業指示の確認
- 点検結果の入力
- 写真や動画の添付
- 作業完了報告 など
スマートフォンやタブレットからCMMSにアクセスし、上記を行えるようにすれば、事務所との往復や二重入力の手間が省けることで作業効率の大幅な向上が期待できます。
資産寿命の延長
CMMSを活用した計画的かつ適切なメンテナンスは、設備の物理的な寿命を最大限に引き出すことにつながります。
代表的なのが、定期的な点検や部品交換、センサーデータなどに基づく予知保全です。設備の劣化を早期に発見し、適切な処置を施して、大きな損傷や機能停止に至る前に対処できます。
CMMSに蓄積された稼働データや保全履歴を分析すると、各設備に最適なメンテナンスサイクルや部品交換時期を見極められます。
これにより、過度な使用による早期劣化や、逆に不必要な早期交換を避けることが可能です。設備の長寿命化は、新規設備への投資を遅らせられるため、企業のキャッシュフロー改善に大きく貢献します。
コンプライアンス対応と安全性向上
多くの産業において、安全基準や環境規制、品質基準など、遵守すべきさまざまな法的・業界的要件が存在します。
CMMSの役割は、これらのコンプライアンス対応を支援し、作業環境の安全性を向上させる上で重要です。
- 保全作業
- 点検結果
- 使用部品
- 作業担当者 など
上記のすべての情報がCMMSに正確に記録され、容易に追跡可能です。監査時などに必要な情報を迅速に提出でき、規制当局への説明責任を果たせます。
安全手順や作業標準をCMMSに登録し、作業指示に組み込むと、すべての作業員が定められた手順に従って作業実施を徹底しやすくなります。作業ミスや事故のリスクを低減し、法令で定められた定期点検や検査のスケジュールをCMMSで管理して、実施漏れを防ぐことが可能です。
データに基づいた意思決定支援
CMMSは保全活動に関する膨大なデータを収集・蓄積し、分析可能な形で提供することで、勘や経験に頼るのではなく客観的なデータに基づいた意思決定を支援します。
- どの設備が最も故障しやすいか
- どのような故障が頻発しているか
- 修理にどれくらいのコストと時間がかかっているか など
上記のデータを分析して、保全リソースの最適な配分や予防保全計画の見直しなど、より効果的な保全戦略を策定できます。
設備の修理履歴や維持コスト、残存寿命予測などのデータを基に、設備の修理、オーバーホール、更新(リプレース)といった投資判断を、より客観的かつ経済合理的に行えます。
主要なKPI(設備稼働率、MTBF、MTTR、保全コストなど)を可視化し、目標値との比較や時系列での変化を追跡すると、継続的なパフォーマンス改善が可能です。
技術継承と人材育成のサポート
製造業をはじめとする多くの現場では、熟練技術者の高齢化や退職に伴う技術・ノウハウの継承が大きな課題です。熟練技術者が持つ修理手順やトラブルシューティングのコツ、過去の対応事例などを、文書、画像、動画といった形でCMMSに記録・蓄積できます。
貴重な知識やノウハウが組織の資産として共有され、特定の個人に依存する状態を解消します。
CMMSに登録された標準作業手順書やチェックリストを参照すれば、経験の浅い作業員でも、一定の品質で安全に作業を遂行可能です。これにより、OJT(On-the-Job Training)の効果を高め、早期の戦力化を支援します。
過去の故障事例や修理履歴をCMMSで容易に検索・参照できるため、類似のトラブルが発生した際に、迅速かつ適切な対応方法を見つけ出せます。
TPM(全員参加の生産保全)活動の推進とCMMSの役割
TPM(Total Productive Maintenance)は、生産部門を含む全従業員が参加して設備の効率化を図る活動です。CMMSは、TPM活動を支援する強力なツールとなります。
CMMSにより設備の稼働状況や故障履歴が可視化されると、現場作業員も設備の状態を把握しやすくなり、自主保全活動への参加意識が高まります。また、改善活動の成果をデータで示せるため、TPM活動のモチベーション向上にもつながるのも特長的です。
さらに、CMMSに蓄積されたデータを分析すると、改善の優先順位付けや効果測定が容易になってTPM活動のPDCAサイクルを効果的に回せます。
自社に最適なCMMSの選び方

CMMS導入の効果を最大限に引き出すためには、自社の状況や目的に最適なシステムの選定が不可欠です。以下で選定における重要なポイントを解説します。
導入目的の明確化と課題の整理
CMMS選定の最初のステップは「なぜCMMSを導入するのか」「CMMSで何を解決したいのか」という導入目的を明確にすることです。現状の設備保全業務における課題を具体的に整理します。
例えば以下のような具体的な目標を設定します。
- 設備の突発故障による生産ライン停止時間を現状から20%削減する
- 年間メンテナンスコストを10%削減する
- 保全作業の属人化を解消し、若手への技術継承を促進する
現在の設備保全業務のフローを分析し、非効率な点や問題が発生しやすい箇所、情報共有のボトルネックなどをリストアップします。例えば紙ベースの記録による情報の散逸や点検漏れの発生、部品在庫管理の不備、修理履歴の活用不足などが挙げられます。
保全部門だけでなく、生産部門、IT部門、経営層などの関連する部署の担当者と目的・課題を共有してCMMS導入に対する共通認識と期待値の熟考が重要です。
必要な機能の洗い出しと優先順位付け
導入目的と現状課題が明確になったら、次にそれらを解決するためにCMMSにどのような機能が必要かを具体的に洗い出し、優先順位を付けます。自社の課題解決に不可欠な機能をリストアップします。
例えば、設備のダウンタイム削減が最優先であれば、予防保全計画機能や予知保全(PdM)連携機能が重要です。コスト管理が重要であれば、詳細な修理履歴管理や部品在庫管理機能が必要です。
洗い出した機能に対して「必須」「重要」「あればなお可」といった形で優先順位を付けます。予算や導入期間の制約の中で、どの機能を重視するかを判断する基準です。
機能が多すぎても使いこなせずコストが無駄になる可能性がありますし、逆に必要な機能が不足していては導入目的を達成できません。
自社の業務フローや管理対象となる設備の特性、保全担当者のスキルレベルなどを考慮し、バランスの取れた機能要件の定義が重要です。
操作性(UI/UX)とモバイル対応の確認
CMMSは、保全担当者や現場作業員が日常的に使用するシステムであるため、その操作性(UI:ユーザーインターフェース、UX:ユーザーエクスペリエンス)は導入成功を左右する非常に重要です。
画面が見やすく、操作方法が分かりやすいか、専門的なIT知識がない現場の担当者でも直感的に使える設計になっているかを確認します。
スマートフォンやタブレット端末からのアクセスや操作がスムーズに行えるかは、特に現場での利用を想定する場合に不可欠です。
点検結果の入力、作業指示の確認、写真の添付などがモバイルデバイスで容易に行えるかを確認します。オフライン環境での入力に対応しているかも重要な点です。
システムが複雑で使いにくいと、現場の担当者にとって大きな負担となり、入力ミスや利用敬遠につながりかねません。実際にシステムを操作できるデモンストレーションを依頼したり、無料トライアル期間を利用したりして、複数の担当者で操作性を評価するのがおすすめです。
他システム(ERP、MES等)との連携性
CMMSを単独のシステムとして運用するだけでなく、企業内ですでに稼働している他の基幹システム(ERP:統合基幹業務システム、MES:製造実行システム、SCADA:監視制御システムなど)と連携させると、より高度な設備管理や全社的な情報活用が可能です。
ERPとの連携では、CMMSの保全コスト情報をERPの会計システムと連携させると、正確な原価計算や予算実績管理が可能です。
MES/SCADAとの連携では、MESの生産計画データやSCADAからの設備稼働状況・センサーデータをCMMSに取り込むと、生産状況に合わせた保全計画の調整や、設備の状態に基づいた予知保全の精度向上が期待できます。
連携対象システムとの間でデータをやり取りするためのAPIが提供されているか、仕様は公開されているかを確認します。
標準機能で連携できない場合、どの程度のカスタマイズが必要になるか、コストと期間を見積もるのも重要です。
ベンダーのサポート体制と導入実績
CMMSの導入と運用は、システムを提供するベンダーとの長期的なパートナーシップを意味します。そのためベンダーのサポート体制や導入実績は、ソフトウェアの機能と同等、あるいはそれ以上に重要な選定ポイントです。
サポート体制の確認として電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ手段が提供されているか、対応時間(平日のみ、24時間365日など)やレスポンスの速さはどうかを確認します。
技術的な問題解決支援、操作方法の指導、システム障害時の対応など、サポートの範囲も重要です。
自社と同じ業種や、近い事業規模の企業への導入実績が豊富にあるかを確認します。これにより、ベンダーが自社の特有な課題やニーズを理解している可能性が高まります。具体的な導入事例や既存顧客からの評価を参考にし、可能であれば、実際に導入している企業にヒアリングするのも有効です。
費用対効果とTCO(総保有コスト)の検討
CMMS導入には相応のコストがかかります。そのため初期費用だけでなく、運用にかかる費用も含めた総保有コスト(TCO)を算出し、導入によって得られる効果(ROI)と比較検討が不可欠です。
初期費用としては以下があります。
- ソフトウェアライセンス料(オンプレミス型の場合)
- クラウドサービスの初期設定費用・月額/年額利用料(クラウド型の場合)
- サーバー等のハードウェア購入・構築費用(オンプレミス型の場合)
- システム導入支援・コンサルティング費用
- カスタマイズ費用、データ移行費用
- 初期トレーニング費用 など
運用費用としては以下が発生します。
- クラウドサービスの月額/年額利用料(クラウド型の場合)
- ソフトウェア保守契約料(オンプレミス型の場合)
- ハードウェア保守費用
- IT担当者の人件費
- 追加トレーニング費用
- バージョンアップ費用 など
これらのコスト要素を考慮し、3年〜5年程度の期間でTCOを算出します。
定量的効果として設備稼働率の向上による生産量増加やダウンタイム削減による損失回避額、メンテナンスコストの削減額、在庫コストの削減額などを試算します。定性的効果として作業品質の向上や安全性の向上、コンプライアンス遵守、技術継承の促進、従業員の満足度向上なども考慮に入れます。
CMMS導入で実現する設備保全の未来

CMMSの導入は、単なる業務のデジタル化に留まらず、設備保全のあり方そのものを大きく変革する可能性があります。IoT技術との連携によって設備の状態をリアルタイムで監視し、AI技術を活用した高度な予知保全が可能です。故障をゼロに近づける「ゼロダウンタイム」の実現も夢ではありません。
CMMSに蓄積されたビッグデータを活用すれば、設備の最適な更新時期の予測や省エネルギー運転の実現、保全コストの更なる削減など、より戦略的な設備管理が可能です。
AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術との組み合わせにより、遠隔地からの保全支援や、より効果的な技術トレーニングの実現も期待されています。
CMMSは製造業をはじめとする多くの企業にとって、競争力を維持・向上させるための必須のツールとなりつつあります。自社の課題と目的を明確にして最適なCMMSを選定・導入することで、設備保全業務の効率化と高度化を実現し、持続可能な成長を支える強固な基盤の構築が期待できるものです。
本記事を参考にして、CMMSを活用した設備保全の変革着手に役立ててください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
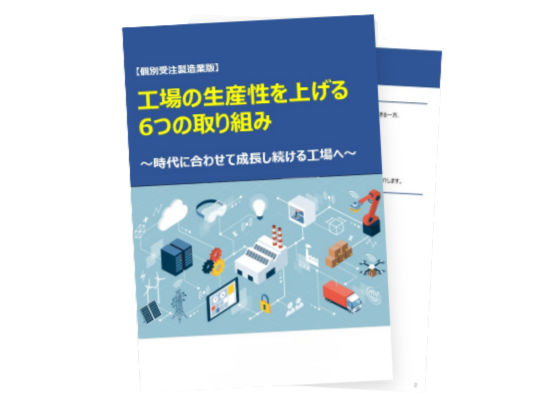
個別受注生産の製造業向け 生産性UPを低下させる要因・対策の指南書です!
工場の生産性を上げる 6つの取り組み
~時代に合わせて成長し続ける工場へ~