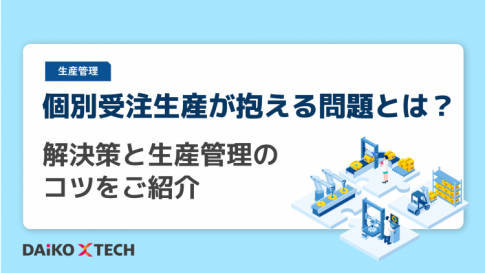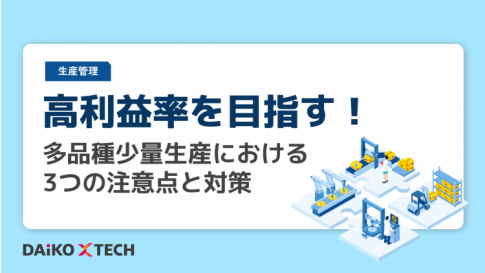歩留まりを向上させれば、利益率・顧客満足度を向上させられます。
生産プロセスにおける課題を解消し、適切な生産計画を立てるために、歩留まり向上につながる施策を実行しましょう。
本記事では、歩留まり向上につながる改善策例を6選ご紹介します。
歩留まり向上が求められる理由から具体的な改善プロセスまで詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
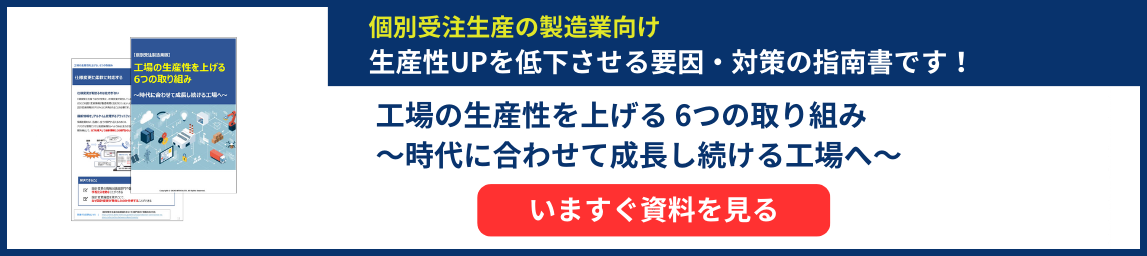
目次
歩留まり向上とは?

歩留まり向上とは、生産数における良品の数を増やすことです。
そもそも歩留まりとは、生産された製品のうち良品として認められる割合を意味し、投資した原材料のうち良品として納品できる割合を導き出す際に活用されます。
歩留まりが高ければ、良品の数が増えるため、利益率も高まります。
より高い歩留まり率を目指すことを、歩留まり率向上と呼びます。
歩留まり向上は、ただ良品の数を増やすのではなく、生産数における良品数の割合を増やす取り組みです。
そのため、歩留まり向上を実現すれば、生産性が向上し利益率の増加が期待できます。
歩留まり率を求める計算式については、こちらの記事を参考にしてください。
歩留まり率の計算式とは?低下する原因と改善する方法を徹底解説
歩留まり向上が求められる理由

歩留まり向上が求められる理由は、下記のとおりです。
- 収益性を把握するため
- 現状の課題を追求するため
- コスト削減により利益率を向上させるため
- 品質向上により顧客満足度を高めるため
- 適切な生産計画を立てるため
それぞれの理由を確認して、歩留まり向上につながる施策を実行すべきか検討しましょう。
収益性を把握するため
歩留まりは、製造工程における原材料や部品がどれだけ製品になったかを示す指標です。
歩留まりが低ければ原価率が高くなり、収益性の低下につながるため、定期的に歩留まり率を測定して生産プロセスの改善が求められます。
歩留まりを正確に把握することで、実際の利益構造を明確にでき、事業の採算性を評価できます。
そのため、収益性を把握するための参考として、歩留まりの管理・改善を徹底しましょう。
現状の課題を追及するため
歩留まりの低下は、製造工程における潜在的な課題を示す指標です。
例えば、設備の不具合・作業員のスキル不足・原材料の品質バラつきなどが起きると、歩留まり率が低下します。
歩留まりを分析すれば「どの工程でロスが発生しているか」「不良の原因は何か」など課題の原因を特定でき、改善施策の優先順位を明確化できます。
生産効率を向上させるためには、現状の課題を可視化し根本的な原因を追及する必要があるため、歩留まり向上が求められるのです。
コスト削減により利益率を向上させるため
歩留まりを改善すれば、直接的にコスト削減へとつながります。
不良品率を減らせれば、廃棄コストや再加工コストを削減できるため、原価が低下します。
さらに、同じ原材料・同じ生産時間でより多くの製品を出荷できるため、生産効率が上がり利益率を改善できるのです。
競争が激しい市場では、歩留まり改善によるコスト最適化が、価格競争力の強化にもつながります。
品質向上により顧客満足度を高めるため
歩留まりの向上は、品質の安定化とも深く関係しています。
不良率の高い製品は顧客からのクレームや返品につながり、企業の信頼を損ねるリスクがあります。
一方で、歩留まりが高い状態は、品質基準を満たした良品を継続的に供給できている証拠です。
品質の安定は顧客満足度を高め、リピート受注やブランド価値の向上につながります。
品質を向上させて顧客満足度を高めるためにも、歩留まり向上が欠かせません。
適切な生産計画を立てるため
歩留まり率を把握すれば、適切な生産計画を立てられます。
歩留まりは「投資した原材料のうちどれだけ良品を生産できたか」を示す指標なので、生産計画を立てる際に歩留まりを考慮しなければ、必要な原材料の数量や生産ラインの稼働計画にズレが生じてしまいます。
結果として、納期遅延や過剰在庫につながるため、利益率・顧客満足度が低下するリスクがあります。
生産計画を立てる際は、生産性向上と経営全体のリスクヘッジを実現するために、歩留まり向上を重視しましょう。
歩留まり向上につながる改善プロセス

歩留まりを高めるために、場あたり的な対策ではなく、下記のプロセスで改善施策を進めましょう。
- 歩留まり低下の原因を把握する
- 製造業における7つのムダを理解する
- 不良データを収集・分析する
- 5M+1Eで歩留まり低下の原因を追及する
1.歩留まり低下の原因を把握する
歩留まり向上のためには、まず歩留まりが低下している原因を把握する必要があります。
不良の発生状況や工程内でのロスを数値で明らかにし、「どこで・何が・どのくらい」発生しているかを可視化しましょう。
改善すべき領域の優先度を整理でき、効率的な改善活動につながります。
2.製造業における7つのムダを理解する
歩留まり低下の背景には、多くの場合「ムダ」が潜んでいます。トヨタ生産方式で定義された「製造業における7つのムダ」は、以下のとおりです。
- 過剰生産のムダ
- 手待ちのムダ
- 運搬のムダ
- 加工そのもののムダ
- 在庫のムダ
- 動作のムダ
- 不良・手直しのムダ
上記のムダを意識して、歩留まりを押し下げる要因を探しましょう。
3.不良データを収集・分析する
不良発生の実態を把握するためには、データに基づく分析が欠かせません。
不良の発生件数・不良率・発生場所や時間帯・担当ラインなどを記録・収集し、統計的手法を用いて傾向を分析しましょう。
感覚や経験に頼るのではなく、データを根拠に不良原因を特定すれば、説得力の高い改善策を実行できます。
4.5M+1Eで歩留まり低下の原因を追及する
歩留まり低下の要因を追及する際は、5M+1Eのフレームワークを活用しましょう。
5M+1Eとは、下記の6要因から品質低下の原因を探る品質管理のフレームワークです。
- Man(人)
- Machine(機械)
- Material(材料)
- Method(方法)
- Measurement(検査・測定)
- Environment(環境)
それぞれの原因を追及して、歩留まり向上につながる改善策を考案・実行しましょう。
Man(人)
Man(人)は、作業者に焦点を当てて不良発生の要因を追及する項目です。
作業者のスキル不足やミスは、不良発生の要因です。
Man(人)の不良を軽減するには、教育訓練や作業標準を整備して、人に起因するムラを抑えましょう。
Machine(機械)
Machine(機械)は、機械が起因で生じる不良を特定する項目です。
設備の老朽化や調整不足は、製品の品質にバラつきを引き起こします。
Machine(機械)の不良を軽減するには、定期的なメンテナンスや予防保全の実施が不可欠であり、IoTやセンサーを活用した管理体制も効果的です。
Material(材料)
Material(材料)は、原材料が原因で引き起こる不良を特定する項目です。
原材料の品質が安定しなければ、製品の品質も安定しないため、原材料の品質を維持・向上させる取り組みが欠かせません。
仕入先の選定や受入検査の強化により、原材料段階での不良流入を防止しましょう。
Method(方法)
Method(方法)は、製造方法や工程設計による不良要因を特定する項目です。
製造方法や工程設計に問題がある場合、歩留まりは大きく低下します。
Method(方法)の不良を避けるために、作業標準の見直しや工程改善・作業動作の最適化を徹底しましょう。
Measurement(検査・測定)
Measurement(検査・測定)は、製品の検査・測定による不良を特定する項目です。
検査方法が不適切であれば、不良を見逃したり逆に良品を不良として判断したりと、不良発生率が高まります。
Measurement(検査・測定)での不良発生率を抑えるためには、検査精度の向上や測定機器の定期校正が効果的です。
Environment(環境)
Environment(環境)は、製造環境が起因して生じる不良を特定する項目です。
温度や湿度・作業場の照明や清浄度などの環境要因も、製造品質に影響を与えます。
環境条件を安定させることは、不良低減と歩留まり向上に直結します。
歩留まり向上につながる改善策例6選

歩留まりを高めるためには、単発的な取り組みではなく、現場全体で継続的に改善を進めていく必要があります。
製造業では、品質・コスト・納期のQCDが企業競争力に直結するため、歩留まり改善は「利益率向上」と「顧客満足度向上」を実現するために欠かせません。
歩留まり向上につながる改善策は、下記の6つです。
- 従業員教育によるスキル向上・意識改善
- 業務の標準化による属人化の防止
- 生産プロセスのリアルタイム管理
- 生産プロセスの最適化
- 設備・器具の定期的なメンテナンス
- 品質管理の徹底
自社の課題に照らし合わせ、適切な解決策を実施しましょう。
従業員教育によるスキル向上・意識改善
歩留まりを改善するには、現場で作業を担う従業員のスキルと意識を改革する必要があります。
作業者が十分に訓練されていなければ、工程標準を守れなかったり、不良品を見逃したりするリスクが高まります。
作業者の知識や技能が不足していると、品質のバラつきや不良発生につながるため、製品知識や工程手順を習熟する研修・スキルアップが必要です。
そのため、基本的な作業手順や品質基準に関する教育を定期的に実施し、現場で求められるスキルを確実に身につけさせましょう。
歩留まり向上につなげるために重要なポイントは、「不良を出さない」という意識の共有です。
従業員一人ひとりが品質の担い手である認識を持ち、日常の小さな異常にも敏感になり、不良の早期発見や再発防止につながります。
定期的な研修やOJTによるスキル教育を行い、作業基準や品質目標に対する理解を深めましょう。
また、「不良を出さない」という意識を全員で共有することで、現場全体の品質意識が高まります。
そのため、定期ミーティングやeラーニングを実施して、従業員のモチベーション向上・品質向上を目指す意識改善を行いましょう。
業務の標準化による属人化の防止
属人化された作業は、人によって品質に差が出やすく、歩留まりを不安定にします。
ベテラン作業者は問題なく行える作業でも、新人作業者が担当すると不良が増える可能性もあるため、業務の標準化が欠かせません。
歩留まりを向上させるために、作業手順をマニュアルや動画で明確化し、誰が担当しても同じ品質を確保できる仕組みを整えましょう。
また、標準作業書の定期的な見直しや、作業手順の改善を継続することで、標準そのものをより実用的かつ効率的なものへ進化させましょう。
属人化を排除すれば、作業のムラやバラつきが減少し、再現性の高い生産体制を実現できます。
業務の標準化により属人化を防止できれば、不良率の低減だけでなく、生産計画の安定化や人員配置の柔軟性向上などの副次的な効果も得られます。
生産プロセスのリアルタイム管理
歩留まりを改善するうえで、問題が発生した後に対応するのではなく、異常を「即時に把握する」仕組みが重要です。
近年ではIoTやセンサー技術の進化により、生産設備の稼働状況や不良発生傾向をリアルタイムで監視できる体制が整いました。
温度や湿度などの環境条件をセンサーで監視し、基準から外れた場合にアラートを出す仕組みを導入すれば、不良が発生する前に対処できます。
また、生産ラインに設置されたカメラやAI画像認識技術を用いることで、目視検査では見逃してしまうような細かな不良も自動的に検知できます。
リアルタイムで異常を把握し、すぐに改善行動を取れる体制を構築すれば、不良の拡大や工程全体への影響を最小限に抑えて、歩留まりの安定性を高められるのです。
また、データを蓄積・分析すれば、将来的な予防保全にも活かせます。
生産プロセスの最適化
現状の工程をそのまま維持するのではなく、無駄を排除し最適化していく取り組みも歩留まり改善に効果的です。
具体的には、生産プロセスの最適化により下記のような効果を得られます。
- 作業順序を入れ替えて、業務効率を向上させることで作業時間が短縮される
- 設備配置を変更し作業者の移動距離を減らして、業務負担軽減と生産性向上を図る
- 工程の中でボトルネックな箇所を改善すれば、生産フローの流れがスムーズになり、不良の発生も抑えられる
生産プロセスの最適化には、トヨタ生産方式で知られる「カイゼン」の考え方が有効です。
カイゼンでは、小さな改善を積み重ね、継続的に無駄を減らしていくことで、歩留まりだけでなく、生産効率全体を引き上げます。
また現場の従業員が意見を出し合いながら、能動的に現状の課題を解消する取り組みを実施するボトムアップ型の活動である点が特長です。
継続的に生産プロセスを最適化すれば、コスト削減と品質向上の両立が期待できるため、歩留まり向上につながります。
設備・器具の定期的なメンテナンス
設備や器具の故障や調整不良は、不良品の発生を増加させる典型的な要因です。
例えば、プレス機の摩耗や射出成形機の温度異常を放置してしまうと、製品精度は大きく乱れます。
設備・器具によるトラブルを未然に防ぐには、定期的な点検やメンテナンスが欠かせません。
設備メーカーの推奨サイクルに基づく保全だけでなく、現場で得られる実績データを活用した予防保全を実施しましょう。
さらに、IoTによる「状態監視型保全(CBM)」を導入すれば、故障の兆候を早期に察知し、計画的に修理や交換ができます。
定期メンテナンスを徹底して、突発的なライン停止を防ぎ、生産の安定性と歩留まりの向上を実現しましょう。
また、予兆管理システムや設備保全管理システムを導入すれば、異常発生前にメンテナンスを計画的に実施でき、生産ロスを抑えられます。
品質管理の徹底
歩留まり改善には、品質管理の徹底が欠かせません。
最終製品の検査を強化するだけではなく、工程ごとの品質チェックを徹底することが大切です。
品質管理を強化するには、QC七つ道具や統計的品質管理(SQC)などの手法を活用し、工程ごとのデータを継続的にモニタリングしましょう。
不良が発生した場合は迅速にフィードバックを行い、再発を防止する仕組みを構築することが大切です。
また、品質管理は検査部門だけの役割ではなく、製造・技術・購買など部門を横断して取り組みましょう。
組織全体で品質意識を高めれば、不良の発生源を根本から減らし、長期的な歩留まり改善を実現できます。
歩留まり向上のために現状把握と改善策の実施が必要

歩留まり向上のためには、現状の課題を把握し、改善につながる施策を実施する必要があります。
まずは現状の課題を把握するために、製造業における7つのムダや5M+1Eを意識して、改善点を探りましょう。
改善策を実施して歩留まり向上につながれば、収益性を確保するだけでなく、コスト削減による利益率の向上が期待できます。
組織の利益率を向上させ、顧客満足度を高めるためにも、歩留まり向上につながる施策を実施しましょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
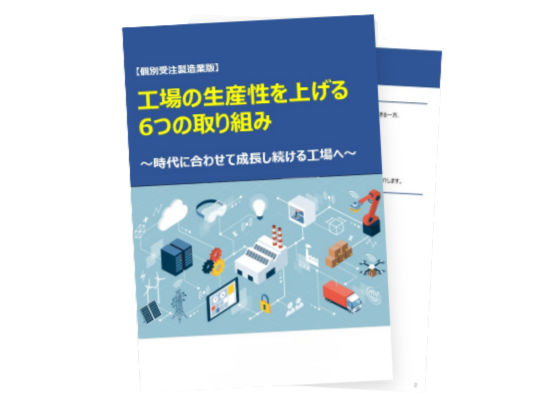
個別受注生産の製造業向け 生産性UPを低下させる要因・対策の指南書です!
工場の生産性を上げる 6つの取り組み
~時代に合わせて成長し続ける工場へ~