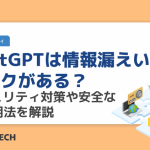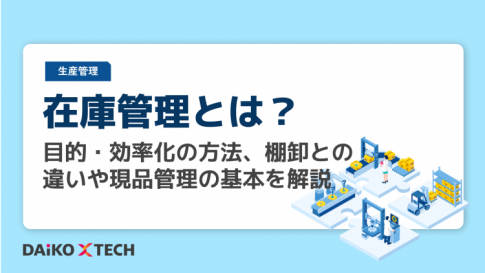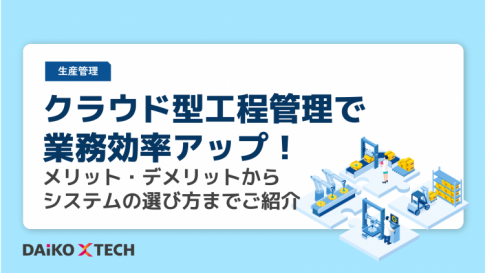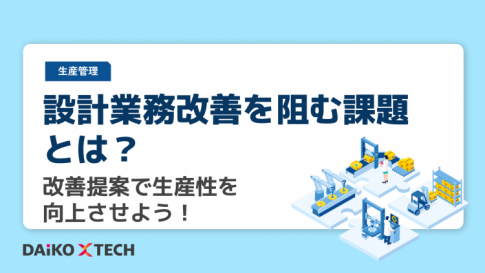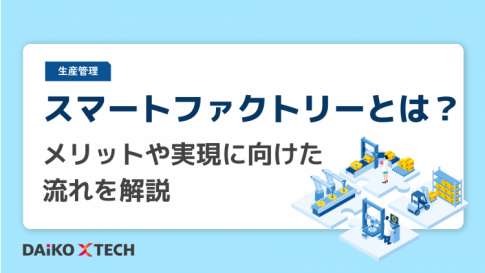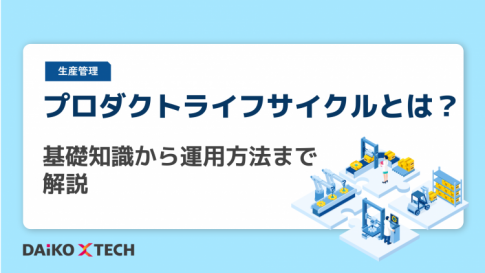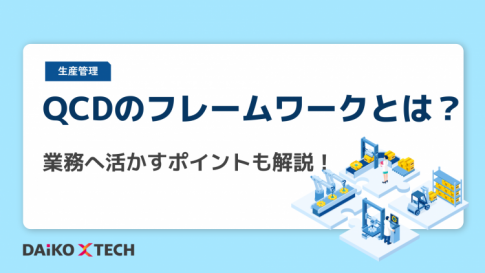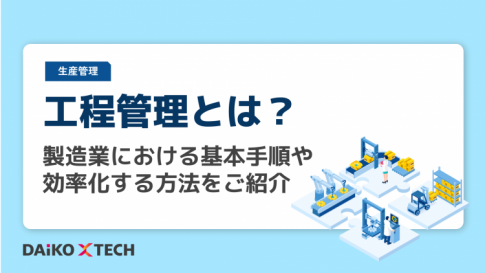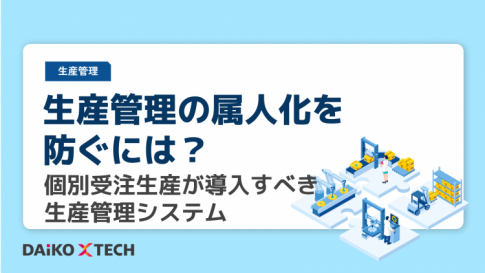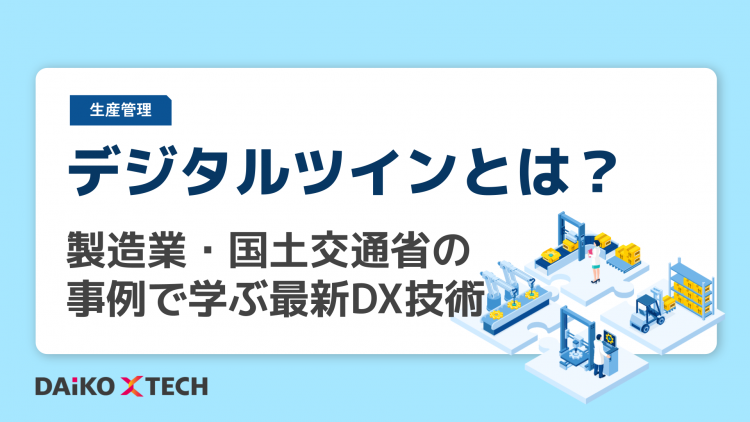
デジタルツインとは、工場や都市といった現実世界をそのまま仮想空間に再現する技術です。単なる3Dモデルではなく、IoTセンサーやAIと連携しながらリアルタイムで情報を反映し続けるのが大きな特長であり、生産性向上やDX推進の鍵として注目されています。
「生産性を上げたいが、何から着手すれば良いのかわからない」「最新のDX技術を導入したいが、効果が見えにくい」といった、製造業、建設業、自治体、スマートシティ政策などに携わる方が抱える課題の解決策として、デジタルツインが注目されています。
本記事では、デジタルツインの基礎から、製造業の具体的事例、国土交通省の取り組み、導入を成功させるための実践ステップまでを網羅的に解説します。
製造業の「業務効率化」「人材不足」「納期短縮」についてお悩みではありませんか?
大興電子通信では製造業界のDX化と主な対策がわかる「製造業のDX推進ガイドブック」を無料配布していますのでぜひご活用ください。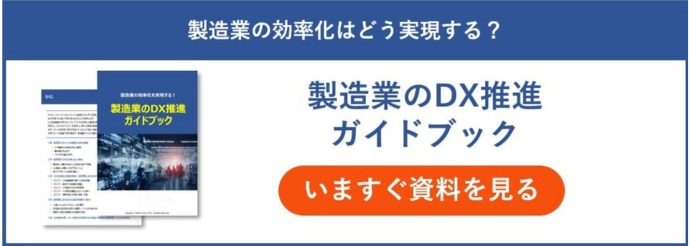
目次
デジタルツインとは?

デジタルツインとは、現実のモノや環境をそっくりそのまま仮想空間に再現し、リアルタイムで同期させる仕組みです。
従来の3Dモデルやシミュレーションとの大きな違いは、リアルタイム性と双方向性です。IoTセンサーやカメラから得られたデータが常に仮想空間へ反映され、AIによる分析結果が現実世界へフィードバックされます。つまり、デジタルツインは一度作ったら終わりの静的なモデルではなく、常に成長し続ける生きたシステムです。
デジタルツインにより、現実では難しい試みを仮想空間で安全に検証することが可能になりました。製造業においては、新しい生産ラインを稼働させる前に稼働率や故障リスクを仮想空間で検証できます。都市開発や国土交通省が推進するスマートシティでは、防災シミュレーションや交通渋滞の緩和策を事前に検証し、社会課題の解決に役立てています。
参照記事:製造業におけるデジタルツインとは?注目される理由や大手企業の取り組み事例を解説
デジタルツインとシミュレーションやメタバースとの違い

デジタルツインとシミュレーション、メタバースは、いずれも仮想空間を活用する技術として混同されがちです。しかし、それぞれの目的とリアルタイム性、双方向性には明確な違いがあります。
それぞれの違いを理解しておきましょう。
シミュレーションとの違い
過去を検証するのがシミュレーション、現実を最適化するのがデジタルツインです。
シミュレーションは、想定された条件下で仮に起きうる結果を予測する、一方向の分析モデルです。過去データや理論モデルを基に未来を試算する点に強みがあるものの、現実の変化を反映する仕組みは持ちません。
一方、デジタルツインは現実世界と連動してデータをリアルタイムに更新し、仮想空間で再現します。例えばある大手企業では、製造現場の人やモノの動きを常時データ化し、仮想空間上で状況を把握しています。
メタバースとの違い
メタバースもまた3D仮想空間を用いますが、目的は人が交流し、体験するための環境づくりにあります。そこでは現実の制約がなく、空を飛ぶ、ファンタジーの世界を探索するといった非現実的な体験が中心になります。
対してデジタルツインは、現実の出来事を正確に再現し、改善や維持に活かすための実務的な仕組みです。つまり、メタバースは体験の拡張、デジタルツインは現実の再現と最適化が目的であり、似て非なる存在です。
共通する技術と今後の可能性
デジタルツインとシミュレーション、メタバースには、3Dモデリング・IoTデータ・AI解析といった共通の技術基盤があります。近年はこれらを統合して、メタバース上でデジタルツインを運用する試みも進みつつあります。
将来的な構想として現実味を帯びてきているのは、企業や自治体がデジタル空間上で実社会の状況を再現・共有し、より迅速に意思決定できる時代の到来です。技術の融合が進むことで、デジタル空間が現実の拡張機能としての進化が期待されています。
デジタルツインの課題

デジタルツインは、都市や産業の高度化を支える中核技術として注目を集めています。しかし、その普及が進む一方で、導入と運用の現場ではいくつもの壁が立ちはだかっています。
デジタルツインの課題について、解説します。
データの統合と標準化が進まない
デジタルツインを成立させる前提条件は、現実のあらゆる情報を一元的に統合することにあります。しかし実際には、IoTセンサー、CAD/BIM、SCADA、ERPなど、企業や自治体が持つデータは形式も粒度も異なっており、連携に膨大な工数がかかります。多くの組織では部門間でデータが分断され、リアルタイムでの共有ができていないのが現状です。
国土交通省が推進する都市デジタルツイン、PLATEAUでは、3D都市モデルの標準化とオープン化を進めており、異なるシステム間のデータ連携を可能にする基盤づくりが行われています。
このような標準化の動きが、民間の製造・建設分野にも波及していくことが期待されます。しかし、データが統合されなければ、デジタルツインは部分最適の仮想空間止まりです。
セキュリティとプライバシーリスクが高い
デジタルツインは、現実空間と同等の情報を扱います。そのため、サイバー攻撃やデータ漏えいが発生すれば、被害は仮想空間にとどまらず、現実の社会インフラや生産活動にも波及しかねません。特に、工場の稼働データや都市の交通・電力情報など、機密性の高いデータを扱う場合はセキュリティ対策の欠如は致命的です。
近年では、ネットワークを階層的に管理する従来型の防御から、すべての通信を検証するゼロトラストアーキテクチャへの移行が進んでいます。アクセス制御、暗号化通信、AIによる異常検知を組み合わせた多層防御の設計が必要です。デジタルツインは現実と直結しているがゆえに、安全な仮想化が前提条件になります。
導入コストがかかり人材が不足している
デジタルツインの構築には、IoT設計、クラウド運用、AI解析、3Dモデリングといった複数領域の知見が求められます。このような横断的スキルを持つ人材はまだ限られており、特に中小企業では確保が難しいのが現状です。
また、センサー設置やシステム統合にかかる初期費用、クラウド運用やデータ保守のランニングコストも高く、PoC(概念実証)段階で止まるケースが多いです。重要なのは、すべてを一度に導入するのではなく、スモールスタートで実証→効果検証→拡張という段階的アプローチをとる点にあります。
成功している企業は、最初から全体最適を目指さず、解くべき現場課題を明確に定義してから着手しています。
デジタルツインの事例

製造業は、いまやデジタルツイン活用の最前線にあります。生産効率化や品質向上、リードタイム短縮など、データに基づいた成果を挙げる企業が次々と現れています。
成功している企業に共通するのは、最新技術を単なるシステム導入として扱わず、経営と現場を結ぶDX基盤として位置づけている点です。明確な目的設定のもとでPoC(概念実証)を重ね、効果を確認しながら全社展開している地道な積み重ねが成果を生んでいます。
実証都市と工場を融合した次世代モデル構築
ある自動車関連プロジェクトでは、スマートシティ構想と工場のデジタル化を一体的に進めています。仮想空間上に都市と生産施設を再現し、人やモノの動きをシミュレーションすることで、設計・運用・物流を最適化しています。
工場で得たデータを都市の開発にも活かすフィジカルとデジタルの循環モデルを構築し、製造とまちづくりの融合を目指しているのが特長です。
製造現場の見える化と省エネ最適化
別の製造企業では、IoTとAIを活用して工場全体をデジタルツインで再現しています。生産設備の稼働状況やエネルギー使用量をリアルタイムに監視し、省エネと品質安定化を同時に実現しています。
仮想空間上で複数の条件を試行できるため、現場改善のスピードが格段に向上しており、データを活用した現場力強化が注目されている事例です。
ロボット稼働を仮想空間で検証し導入期間を短縮
産業用ロボットを扱う企業では、クラウド上でロボットの挙動をデジタルツイン化しています。実機導入前に仮想空間で動作検証を完了することで、導入期間を数分の一に短縮しました。
安全性・効率性・コストを多面的に検証できるため、リスクを抑えつつスピーディーな導入が可能です。こうした仮想での実証→現場実装の仕組みは、モノづくりの新しい標準になりつつあります。
プラント設備の3Dモデル化で遠隔監視と異常検知を実現
プラント運営を行う企業では、設備全体を3Dモデル化し、現場を仮想空間上で可視化しています。実施しているのは、温度や圧力、振動などのデータをAIが解析し、異常の兆候を自動検知することです。
保守対応をリモートで支援することで、現場の安全性を高めつつ、人材不足にも対応しています。熟練技術者のノウハウをデジタルに置き換え、継承する仕組みとしても期待されています。
拠点をつなぎ、AIによる最適生産モデルを構築
世界各地に工場を持つ企業では、各拠点をデジタル空間で連携させ、稼働データや在庫情報を一元管理しています。AIが全体のデータを分析し、最も効率的な生産スケジュールを自動で提示しています。
その結果、設備稼働率の向上だけでなく、エネルギー使用量やCO₂排出の削減にも成功しました。デジタルツインが、グローバルサプライチェーン全体の最適化を支える中核技術になりつつあります。
事例から見える共通点
ここまで説明してきた成功事例に共通するのは、明確な課題意識と段階的な導入ステップです。
まずPoCを通じて効果を可視化し、その成果を基に全社展開へと広げていっています。デジタルツインを単なるシミュレーション技術として終わらせず、経営判断の材料として活用している点が特長的です。
成果を分けるのは、技術力そのものではなく、目的設定と継続運用の仕組みづくりにあります。
国土交通省が主導する都市デジタルツインプロジェクト

日本政府は、都市・インフラ分野でデジタルツイン技術を社会に根づかせるため、国土交通省が主導でさまざまな施策を展開しています。ここでは、主要なプロジェクトとその意義、実際の活用例、今後の課題を整理します。
国土交通省が描く政策枠組みとプロジェクト
国土交通省が中心となって推進しているプロジェクトがPLATEAU(プラトー)です。PLATEAUは、全国の都市を対象に3D都市モデルを整備し、オープンデータ化することで、都市デジタルツインを社会実装する基盤づくりを目指すものです。
PLATEAUでは、都市の地形・建物形状・道路などの空間情報を3Dモデルで構築し、それを官民で共有・活用できるようにしています。PLATEAUは、自治体のまちづくりや防災、環境シミュレーションなど、幅広い用途に応用される可能性があります。
また、国土交通省は国土交通データプラットフォームの整備を進めており、さまざまな行政・民間が持つ地理空間データやインフラ情報を集約・可視化する仕組みです。将来的なデジタルツイン実現の土台となるものになっています。
こうした基盤構築を経て、PLATEAUは当初の実証・PoCフェーズから、より実用的なユースケースの実装へとステージを移行しています。
実際の活用例:防災・都市管理・イベント空間
PLATEAUプロジェクトの実際の活用例をご紹介します。
防災シミュレーションと災害対応
PLATEAUを使った都市デジタルツインは、すでに浸水シミュレーションや被災現場支援ツールの開発に用いられています。防災科研(NIED)と連携し、被災前の建物情報を基に現場での意思決定を支援する技術開発も進んでいます。
また、河川流域の洪水・治水対策に対しては、流域全体を仮想空間で再現可能です。被害想定・対策効果を可視化するデジタルテストベッドの構築が進められています。
都市計画・まちづくり
都市の人流シミュレーションや街区設計、環境・緑化計画など、まちづくりの現場でもPLATEAUの3Dモデルが活用されています。例えば、豊洲や松山市などで、建物の利用や回遊経路の検討に3Dモデル基盤が使われた事例も報告されています。
また、地方自治体との連携により、PLATEAUに整備された3D都市モデルを基に、不動産分野の新サービス創出を狙う事業が複数採択されているのも注目ポイントです。
熱中症対策やイベント運営
最近では、国土交通省と内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)が協力し、大阪・関西万博会場を対象に熱中症対策デジタルツインを構築する実証が行われました。高解像度の気温モデルやWBGTシミュレーションを用いて、来場者の安全性を確保する取り組みとして注目されました。
課題と展望:本格社会実装に向けて
PLATEAUは、これまでの実証段階を越えて、国・地方・民間が連携して自律展開するエコシステムの構築を目指しています。数年前には国土交通省から多様な主体からの技術・サービス提案を受け付ける情報提供依頼(RFI#1)が発表されました。
一方で、次のような課題も顕在化しています。
- データ整備のばらつき:自治体間で3Dモデルやセンサー網の精度に差がある
- コスト負担と収益モデル不在:整備・維持コストをどう分担し、収益化するかの道筋が不透明
- ユースケース不足:具体的に使える応用がまだ限定的
- 技術標準化と相互運用性:複数関係者・システムを統合する際の共通規格の整備
こうした課題を克服していくことが、国が掲げるまちづくりDXやスマートシティ実現の鍵です。
デジタルツインがもたらす経営メリット

デジタルツインの価値は、単にデータを可視化することにとどまりません。企業経営の観点から見ると、収益性・安全性・生産性のすべてを底上げする中核技術です。ここでは、製造業を中心に、経営にどのような変化をもたらすのかを整理します。
予知保全で設備トラブルを未然に防ぐ
生産ラインや設備は、一度止まると大きな損失を生みます。デジタルツインを活用すれば、IoTセンサーで収集した稼働データを分析し、異常の兆候を早期に検知できます。
例えば、モーターの振動や温度データをリアルタイムで監視することで、次にどの部品が壊れるかを予測可能です。結果として、突発的な設備停止を防ぎ、計画的にメンテナンスできます。
デジタルツインは単なる保守効率化にとどまらず、止まらない生産を経営の標準に変える重要な仕組みです。
仮想空間で検証しムダとリスクを減らす
新製品の開発や生産ラインの変更は、実際に設備を動かすと多大なコストと時間がかかります。デジタルツインでは、その試行錯誤を仮想空間で完結できます。あるメーカーでは、新ライン設計をデジタル空間でシミュレーションし、現場導入時の手戻りを最小化しました。結果、設備改修にかかるコストを数十%削減しています。
また、危険作業や災害リスクの高い環境では、実際に人を動かす前に仮想環境で安全確認を行えます。これにより人的リスクの低減と作業効率の両立が可能です。
品質が向上して顧客満足を最大化できる
デジタルツインは品質改善にも大きな影響をもたらします。生産工程のばらつきをリアルタイムで分析し、最適な条件を自動でフィードバックすることで、製品品質の均一化と歩留まり向上を実現します。
さらに、製品が市場でどのように使われているかをデジタル空間で再現できるため、使用状況データを基に設計段階から改良を進める顧客起点のモノづくりも可能です。
デジタルツイン導入の進め方

デジタルツインの導入は、単なるシステムの刷新ではなく、組織の業務・文化を変える取り組みです。成功の鍵は導入目的の明確化、小規模なPoCによる実証、継続的な運用定着にあります。
共創型パートナーと連携しながら、技術と業界知識を融合させ、運用・教育・文化浸透まで含めた全体設計を行うことが重要です。
まずは目的を明確化する
デジタルツイン導入の第一歩は、なぜ導入するのかを明確にするところから始まります。多くの失敗例は、目的があいまいなまま技術導入だけが先行している点にあります。稼働率を10%改善する、不良率を半減させる、エネルギー消費を5%削減するといった、定量的なKPIを設定することが成功の前提です。
目的が不明確なままでは、運用が形骸化し、成果も見えにくくなります。導入前に課題と期待成果を明文化し、経営層と現場の両方がどの指標で成功を判断するのかを共有しておくことが、プロジェクト成功の目印となります。
小規模なPoCからスタートし、成果を検証する
導入初期から全社展開を狙うのではなく、まずは限定的な範囲でPoC(概念実証)を実施するのが現実的です。限定した工場ラインやプロセスでデータを収集・分析し、効果を数値で可視化します。その検証を経てモデルを最適化し、実運用に耐えうる形へと磨き上げていきます。
この段階では、技術的成功だけでなく、現場の理解と協力体制を築くのも重要です。小さく始め、成功体験を積み重ねることで、社内の納得感と推進力を高めていくことができます。
フェーズごとに本格展開し、運用を定着させる
PoCで成果を確認した後は、段階的に対象範囲を広げて全社展開へと進めます。しかし、拡張フェーズでは、導入しただけで終わらせない運用設計が不可欠です。
教育プログラムの整備、データ更新のワークフロー構築、セキュリティ対策の実装など、日常業務に根付く仕組みを整える必要があります。また、経営層がROIを定期的に確認し、現場が改善提案を行うような双方向の文化づくりが、継続的な運用を支えます。
デジタルツインは導入して終わりのツールではありません。運用と改善を繰り返すサイクルを設計できるかどうかが、真の成功を分けるポイントです。
デジタルツイン導入のパートナー選びのポイント

デジタルツインは、単独で完結するプロジェクトではありません。IoT・AI・クラウド・セキュリティ・業務プロセス設計といった多様な要素が関わるため、信頼できるパートナー選びが成果を大きく左右します。
選定の基準は業界理解、共創姿勢、一貫した支援体制の3つです。
深い業界知識と実績があるか
自社特有の業務構造や課題を理解しているパートナーほど、導入の現実的な回答を示せます。それぞれの分野で成功事例を持つ企業は、プロジェクトのリスクや落とし穴を熟知しています。
業界構造や専門プロセスへの理解が深ければ、実現可能な提案を行うことができ、プロジェクトの成功確率は格段に高まるため、重要なポイントです。
共に課題解決する「共創」の姿勢があるか
優れたパートナーは、単なるシステムベンダーではなく、課題解決の共同創作者として関わってくれます。
導入初期から課題発見・目標設定に並走し、データ整備・運用フェーズまで責任をもって支援する姿勢が求められます。納品して終わりではなく、成果が出るまで伴走する柔軟な体制を持つ企業ほど、長期的な信頼関係を築きやすいです。
設計から運用まで任せられる体制があるか
デジタルツインは、構想・設計・構築・運用の各フェーズが密接に連動するプロジェクトです。そのため、これらを一貫してサポートできるワンストップ体制のパートナーが理想的です。体制が分断されると、責任範囲があいまいになり、意思決定の遅延やトラブル対応の遅れにつながりやすくなります。
構想段階から運用フェーズまでを通して支援できる企業であれば、導入負担を軽減しながら、迅速で柔軟な対応が可能です。デジタルツインのような長期的プロジェクトでは、だれと進めるかが、何を導入するかと同じくらい重要です。
デジタルツインの展望

デジタルツインは、もはや単一企業の効率化にとどまりません。都市・産業・医療・環境といった社会全体をつなぐ基盤技術へと進化しています。IoTやAI、クラウド技術の発展によって、現実と仮想がリアルタイムに連動する未来がすぐそこまで来ています。
サステナブル社会を支えるインフラへ
デジタルツインは、環境・交通・エネルギーといった社会課題の解決にも大きく影響します。都市の気温上昇や豪雨被害をシミュレーションし、都市設計や防災計画を最適化することで、持続可能な社会の構築につながります。
カーボンニュートラル都市の実現を見据えた3Dモデル分析も始まっており、環境と経済を両立させる都市経営が次のテーマです。
デジタルツインが導く現実と仮想の融合社会
デジタルツインは、もはや現実を模倣する技術ではありません。現実と仮想が相互に学び合い、新しい価値を生み出す循環型の社会基盤へと進化しつつあります。
製造現場では、生産の最適化だけでなく、環境負荷の低減やサプライチェーンの再構築に活用されています。都市では、交通・防災・エネルギーを統合的に設計するスマートシティの中核技術として、日常の安心と効率を支えている重要な技術です。
企業にとって重要なのは、技術を導入することではなく、デジタルと現実を循環させる仕組みを構想する力です。未来の競争軸は、どのような製品を作るかではなく、どのような現実を創り直せるかに移りつつあるといえるでしょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
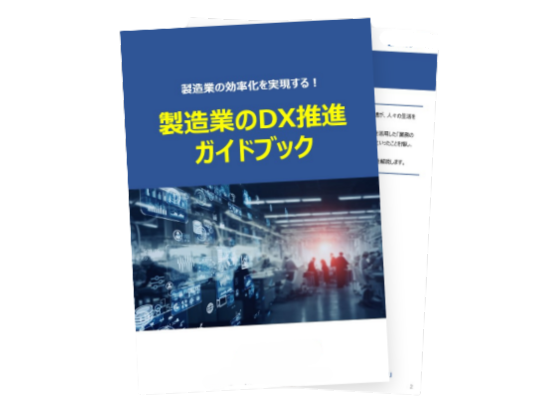
製造業の効率化を実現する!
製造業のDX推進ガイドブック