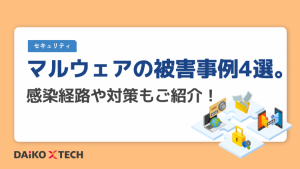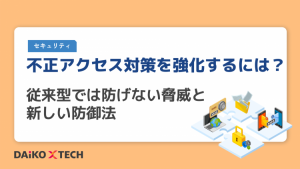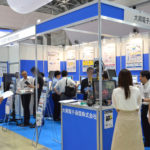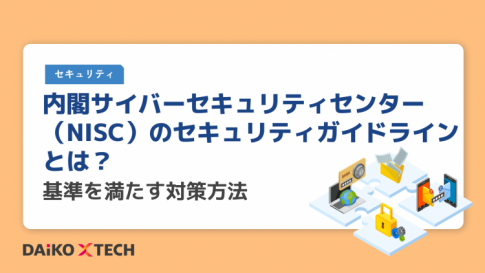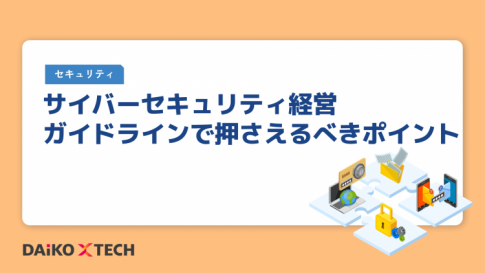サイバー攻撃の巧妙化が進む中で、「現状のセキュリティ対策で本当に十分なのだろうか?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
日々変化するマルウェアの手口に対し、従来型のセキュリティだけで対処し続けることに不安を抱くのは当然のことです。
本記事では、EDRセキュリティの基本的な仕組みや他のセキュリティソリューションとの違い、現場で注目される理由をわかりやすく解説したうえで、近年セキュリティ先進企業が導入を進めている「OSプロテクト型」という新たな対策にも焦点を当ててご紹介します。
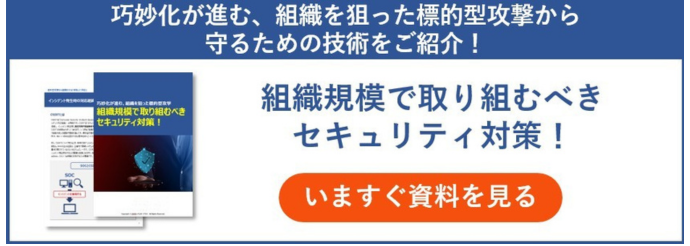
目次
EDRとは

EDRは、パソコンやサーバといったエンドポイント(ユーザーが直接操作する端末機器)に対するサイバー攻撃を検知・調査・対応するための重要なセキュリティ技術です。
従来のウイルス対策ソフトとは異なり、攻撃の兆候をリアルタイムで捉えて対応を図る点が大きな特徴です。
以下では、EDRの基本的な仕組みや他のセキュリティ対策との違い、そして注目されている背景についてわかりやすく解説していきます。
EDRの概要
EDRとは「Endpoint Detection and Response」の略で、日本語では「エンドポイント検知と対応」と訳されます。
具体的には、PCやサーバなどのエンドポイントを常に監視し、異常な動作や不審な挙動を検知した際に即座にアラートを出したり、記録を残したりして攻撃の拡大を防ぐ役割を担います。
一般的なウイルス対策ソフト(アンチウイルス)は、既知のウイルス定義に基づいてマルウェアを検出しますが、EDRはそれに加えて、未知の脅威や標的型攻撃にも対応できるよう、行動ベースの検知を行う点が特徴です。
例えば、システムファイルの改ざんや不正な通信など、攻撃の兆候を見逃さずに捉えられます。
また、検知後の対応もEDRの強みで、不審なプロセスの強制終了や感染が疑われる端末のネットワークからの隔離といった対策も可能です。
これにより、攻撃を初期段階で抑え込み、被害を最小限に食い止められます。
EPP・NGAV・MDRとの違い
EDRと混同されがちなセキュリティ製品に、EPP(Endpoint Protection Platform)、NGAV(Next-Generation Antivirus)、MDR(Managed Detection and Response)がありますが、それぞれ役割が異なります。
以下で詳しく見ていきましょう。
|
名称 |
主な役割 |
特徴 |
|
EDR |
攻撃の検知・対応・追跡 |
・リアルタイム監視で異常行動を検知 ・感染後の迅速な対応が可能 |
|
EPP |
ウイルスやマルウェアの侵入を予防 |
・従来型アンチウイルスやファイアウォールを含む ・定義ファイルに基づく検出 |
|
NGAV |
AI・機械学習による高度な検知 |
・定義ファイルに頼らない ・未知のマルウェアに対応 |
|
MDR |
セキュリティの監視・運用代行 |
・EDRを活用した専門家の監視 ・人手が足りない企業に最適 |
EPPは、主にウイルスやマルウェアの侵入を防ぐ「予防型」のセキュリティ製品で、従来型のアンチウイルスやファイアウォールなども含まれます。
一方でEDRは、「検知と対応」を目的としており感染後の追跡や対処が中心です。
つまり、EPPが「入口対策」であるのに対し、EDRは「侵入後の対応」に主眼が置かれています。
NGAVは、AIや機械学習を活用し、従来のウイルス定義に頼らずにマルウェアを検知できる次世代のアンチウイルスです。
NGAVとEDRが一体となって提供されることもあり、組み合わせることで強力なセキュリティ体制が構築されます。
MDRは、EDRなどを活用しながら、専門のセキュリティチームが監視・分析・対応を代行してくれるサービスです。
自社で運用リソースを確保できない企業にとっては、MDRを活用することでEDRの機能を最大限に活かすことが可能です。
EDRが注目されている背景
近年EDRが多くの企業で注目されている背景には、サイバー攻撃の高度化と巧妙化があります。
特に「ゼロデイ攻撃」や「ファイルレス攻撃」など、従来のアンチウイルスでは検知が難しい手法が増加しており、防御一辺倒のセキュリティでは対応しきれない現実が浮き彫りになっています。
また、テレワークやクラウド活用の拡大により、従来の境界型防御では守りきれない場面も増えました。
オフィスの外でも安全に業務を行うためには、端末単位でのセキュリティ管理が必要不可欠であり、そのニーズに応えるのがEDRです。
さらに、情報漏えいやランサムウェア被害が社会的に大きな問題となっており、迅速な対応と原因調査が求められるケースが増えています。
EDRは、攻撃の痕跡を記録し後からの解析や対応策の策定にも役立つため、企業のセキュリティ体制強化に欠かせないツールとして支持を集めています。
EDRのセキュリティ機能

EDRには、サイバー攻撃を早期に発見し、影響を最小限にとどめるためのさまざまなセキュリティ機能が備わっています。
主に「監視」「分析・検知」「インシデント対応」「フォレンジック調査」の4つがあり、これらが連携して動くことで、攻撃に対して柔軟かつ迅速に対応することが可能になります。
以下で、それぞれの機能について詳しく見ていきましょう。
|
機能 |
主な役割 |
ポイント |
|
監視 |
端末(エンドポイント)の動作や通信を常に見張る |
・不審な動きにすぐ気づける ・ログを記録して後で分析に活用できる |
|
分析・検知 |
集めたデータをもとに危険な動きを自動で見つける |
・AIやルールで怪しい動作を判断 ・未知の攻撃にも気づける |
|
インシデント対応 |
危険な端末やプログラムに対して自動または手動で対応する |
・感染したPCをネットワークから切り離す ・不審な動作を止めて被害拡大を防ぐ |
|
フォレンジック調査 |
攻撃の痕跡をもとに何が起きたかを調べて再発防止につなげる |
・いつ何が起きたかを時系列で確認可能 ・法的対応や報告にも役立つ |
監視
EDRの最も基本的な役割のひとつが、エンドポイントの常時監視です。
ここで言うエンドポイントとは、パソコンやスマートフォン、サーバーなど社員やユーザーが直接操作する端末を指します。
EDRはこれらの端末の動作やファイルの変化、アプリの起動状況、通信ログなどをリアルタイムで監視しています。
この監視機能によって、突然知らないプログラムが動き出したり、勝手に外部のサイトと通信を始めたりといった不審な動きがあれば、即座に検知可能です。
企業にとっては、攻撃の「兆候」を早期に察知できるという点が大きなメリットです。
また、監視によって蓄積されたログ情報は、後述の分析や調査にも活用できます。
監視だけでは攻撃を防ぎきれないこともありますが、まず異変に「気づく」ことがセキュリティ対策の第一歩となります。
分析・検知
EDRはただ監視するだけではありません。
収集した動作ログをもとに「これは危険な動きではないか?」という分析を自動的に行い、異常や攻撃の兆候を検知します。
これが、EDRが持つ「分析・検知」機能です。
例えば、正規の社員が通常は使わないようなコマンド操作や、夜間に自動的に行われたファイルの暗号化処理など、攻撃者の典型的な行動パターンに一致する場合には、「この動きは怪しい」と判断されアラートが出されます。
この機能はAIやルールベースの仕組みで実現されており、過去の攻撃パターンや学習データに基づいて、未知の脅威にも対応できるよう工夫されています。
従来型のアンチウイルスでは見逃してしまうような行動も、EDRなら見つけられる可能性が高い点が特徴です。
インシデント対応
EDRはただ異常を検知して知らせるだけでなく、実際に「対応する」機能も持っています。
具体的には、マルウェアに感染したと疑われる端末があればその端末をネットワークから隔離したり、不審なプログラムの動作を自動的に停止したりすることが可能です。
このような対応をインシデント対応と呼び、万が一の被害が広がらないように、EDRは即座に手を打つことができます。
人間が操作する前に自動的に対処できるため、被害の拡大を防ぐスピード感も大きな強みです。
また、セキュリティ担当者が遠隔から指示を出すこともでき、感染端末の再起動や復旧作業などもスムーズに行えます。
EDRは単なる見張り番ではなく、いざというときには消火活動まで担えるツールです。
フォレンジック調査
攻撃のあった後に「何が起こったのか」「どこから侵入されたのか」「どのような被害が出たのか」を調べるための機能が、フォレンジック調査です。
EDRは日々記録している膨大なログデータをもとに、時系列で細かく分析できるようになっています。
この機能により、「いつどのファイルが改ざんされたのか」「誰がどの操作を行ったのか」「その後どのような通信があったのか」といったことを後から正確に確認可能です。
こうした情報は、再発防止策の立案や法的対応の資料としても活用されます。
また、攻撃者の手口を分析することで、次回以降に備えたルールの見直しやEDR設定の強化にもつながります。
フォレンジック調査は、セキュリティ被害からの早期回復や再発防止を実現するうえで欠かせない機能です。
EDRが脅威に対応する仕組み

EDRは、個別のセキュリティ機能が単独で働くのではなく、「監視」「分析・検知」「対応」「調査」の各機能が一体となって、サイバー攻撃の流れ全体に対応する仕組みとして機能します。
EDRの特徴は、サイバー攻撃のライフサイクルに合わせて、各ステップに適したアクションを自動または半自動で連携的に実行できる点です。
例えば、未知の攻撃が侵入した場合、まず端末のふるまいを常時監視するセンサーが異常に気づきます。
次に、AIによるふるまい分析により、通常とは異なる挙動が「攻撃」と判定されれば、即座に隔離や遮断の処理が実行されます。
さらに、その一連のログや通信履歴はすべて記録され、後からの分析や社内外への説明責任にも対応できる状態に整理することも可能です。
このようにEDRは1つの出来事をきっかけに、「検知→即応→記録→調査→再発防止」という一連のサイクルを自動的にまわす仕組みを備えており、従来の単機能型セキュリティとは大きく異なります。
つまりEDRとは、個別機能の集合体ではなく、一貫した流れで脅威と向き合う防御体制そのものです。
EDRやEPPだけではセキュリティ対策は不十分

セキュリティ対策を行う上で、これまで正攻法と考えられていた手法の代表例が「EPP」「EDR」です。
エンドポイント保護プラットフォームを意味するEPPは、ファイアウォールやIPSを利用して、企業外部のインターネットと企業内ネットワーク(LAN)の境界でマルウェアの侵入を防ぐ、という方法。
そして、万が一、マルウェアの侵入・感染を許した場合に、その後の対応を迅速に行うための打ち手がEDRです。
それぞれの位置付けや役割が異なるため、企業はEPP・EDRの双方を導入し、運用することが求められます。
しかし、マルウェアの進化に伴い、これらの対策では不充分なケースが増えてきています。
マルウェアのついて詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
EPP・EDRが抱える、セキュリティの「弱点」

結論から述べると、EPP・EDRには決定的な弱点があります。
例えば、EPPの基本的な方針は「マルウェアによる攻撃を水際で防ぐ」というものですが、ここでは定義ファイルに従ってPCを守ります。
しかし、マルウェアに対応した定義ファイルがなければ検知ができないため、「未知の脅威や新種のウイルスには対応できない」という弱点があります。
また、EDRは近年良く聞かれるジャンルの製品ではありますが、そもそもの目的は「マルウェアの検知・観察や記録を行い、その攻撃を遮断すること」にあります。
これらはすでにマルウェアがネットワーク内に侵入していることを前提としているため、感染自体を防ぐことはできません。
つまり、マルウェアに感染した後の「2次被害」を最小限にするための仕組みと言えます。
このように、従来型のセキュリティ製品は適用範囲が異なっており、それぞれが弱点を持っています。
では、マルウェアが社内ネットワークに侵入した際、被害を防ぐためにはどのような対応策が必要なのでしょうか?
マルウェアが侵入しても破壊させない。「OSプロテクト型」セキュリティとは?

新たなマルウェアが日々作られている中、侵入を完全に防ぐことは不可能といえます。
そこで、新しい概念として「マルウェアに侵入されても悪さをさせない」という対応策があります。この特徴には2つの観点があります。
1つ目は、「システムの正しい動作と機能を守る」ということ。
OSを壊させない、マルウェアに感染させない、という点に重きを置いています。
この点からは、従来型のセキュリティソフトとはそもそも考え方が異なることがわかります。
2つ目は、「マルウェアの検知・駆除はしない」ということ。
検知や駆除を行うためには、パターンマッチングを始めとする「一定の基準に基づく判定」が必要になります。
これを行う限り、亜種や新種が出てきた際には都度対応が必要になり、守る側の対応は常に後手になってしまうのです。
このようなコンセプトの元、先進企業各社が導入している仕組みが「OSプロテクト型のセキュリティ(以下、OSプロテクト型)」です。
OSプロテクト型セキュリティ導入のメリット
OSプロテクト型の代表的なメリットは3つです。
1. すり抜けが発生しにくい
セキュリティ対策を考える上では、穴の空いたスイスチーズに見立てた「スイスチーズモデル」という多層防御の考え方が重要視されています。
これは、形の違う複数の対策を多層的に構築し、安全性を高めていくという考え方です。
しかし、多層防御を構築したとしても、すべての穴を通過する脅威(=マルウェア)は存在します。
だからこそ、OSプロテクト型では守るべきPC自体を防御し、例えすり抜けが発生しても、「最終防衛ライン」としてOSの動作・機能を守ることに特化しています。
2. 未知のマルウェアにも対応可能
OSプロテクト型では、基本的にOSが「信頼する」という設定した以外のアプリの起動を阻止する他、アプリ起動後の不正な動作の制御を行っています。
その他にも、プロセスの監視隔離機能も備えているため、想定外の動作も制御することが可能です。
3. 更新・アップデートが不要
マルウェアに対応した定義ファイルを持たないため、EPPでは必要とされたような更新作業が不要になります。
このように、OSプロテクト型には複数のメリットがあり、EPP・EDRのデメリットをカバーする仕組みが整っているのです。
「侵入されても壊させない」最新セキュリティ対策をはじめよう。

マルウェアと企業の”いたちごっこ”に終止符をうつ「OSプロテクト型のセキュリティ」。
最終的には、運用体制やコンプライアンス、費用対効果などを踏まえた上での対応を検討する必要があります。
だからこそ、いずれか単体での対策ではなく、「EPP・EDRの検知型」と「OSプロテクト型セキュリティ」を掛け合わせた多層防御の対策が望ましいでしょう。
従来型のセキュリティを超えた新概念の詳細については、次の資料をご一読ください。
マルウェアが動いても「感染させない」。
不正な動作をすべてシャットアウトする新型セキュリティ「AppGuard」については、下記よりご覧いただけます。
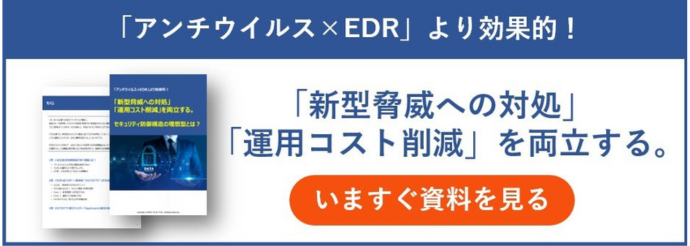
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
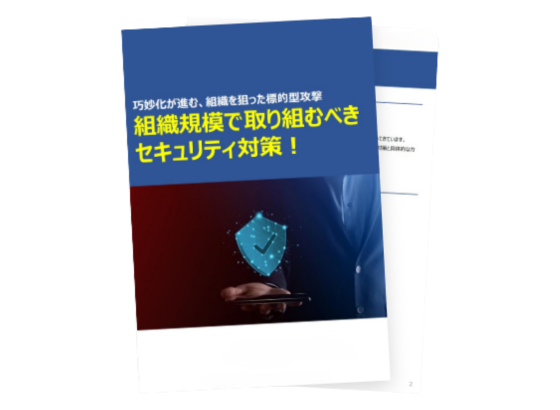
巧妙化が進む、組織を狙った標的型攻撃から守るための技術をご紹介
組織規模で取り組むべきセキュリティ対策!

- この記事を監修した人
- 16年間、SIerやソフト開発会社でITソリューション営業として従事。
セキュリティおいては、主にエンドポイント、無害化、認証製品の経験を積み
DAIKO XTECHに入社後は、さらに専門性を高め、セキュリティにおける幅広いニーズに答えていくための提案活動や企画プロモーションを展開。
お客さまと一緒に悩み、一緒に課題解決が出来る活動を心掛けている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
ICTソリューション推進部
セキュリティビジネス課 - 中須 寛人