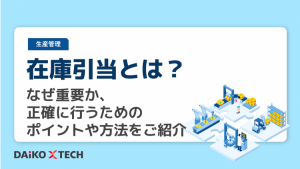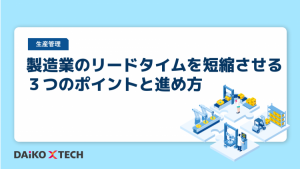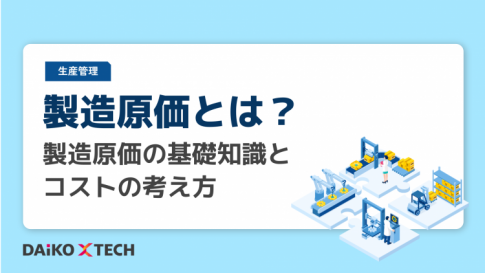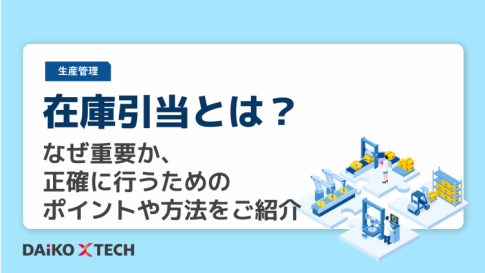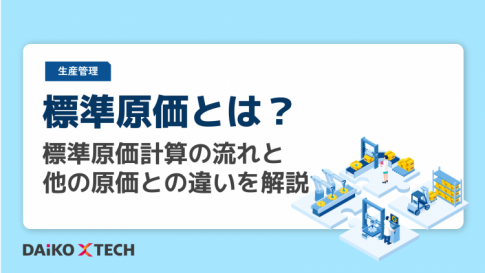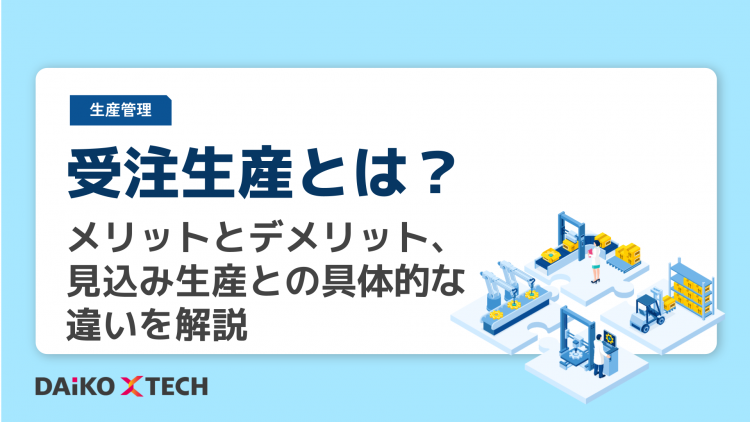
受注生産とは、顧客の要望・受注希望に合わせて、製品を製造する生産形態を指します。受注から生産までのフローを大まかに分類すると、「見込み生産」と「受注生産」の2つに分けられるため、2つの違いをよく把握することで、生産管理を効率的に行えるようになります。
今回は、見込み生産と受注生産の違いやそれぞれのメリット、デメリットについてご紹介します。
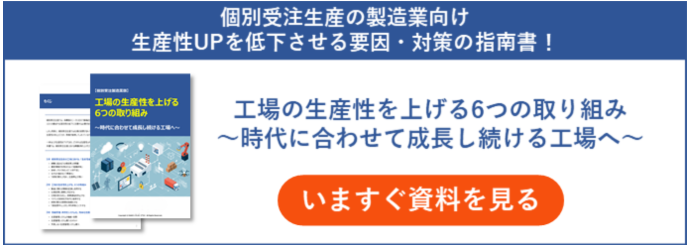
目次
受注生産とは
受注生産とは、顧客の要望・受注希望に合わせて、製品を生産する生産形態を指します。必要な分だけ、必要な際に生産を行うため、在庫のリスクを軽減しつつ、顧客の満足度向上に寄与できます。
本章では、見込み生産との違いや、受注生産に向いている製品などをご紹介します。
受注生産と見込み生産の違い
製造業において、製品をどのタイミングで生産するかの計画は重要です。どのタイミングでどれだけの製品を生産するかによって、在庫の量や売り上げが大きく左右されます。生産のタイミングは大きく分けて「見込み生産」と「受注生産」の2つがあり、受注の前に生産するのが見込み生産、受注してから生産するのが受注生産です。
見込み生産と受注生産の大きな違いは「生産が先か」「受注が先か」という点であり、それぞれにメリット、デメリットが存在するため、特性を理解した上で生産方式を選択する必要があります。
受注してからの生産だと在庫を抱える必要がなく、キャッシュフローの滞りなく売り上げにつなげることが可能な一方、受注生産では十分な納品が難しいことも多いため、製品によっては見込み生産を行います。
受注生産に向いている製品
受注生産に向いている製品には以下のような特性があります。
- 生産数が少なく、大量生産の必要がない製品
- 原価が高く、在庫を多く保有できない製品
- カスタマイズ性が求められる製品
- 試作を行っている段階の製品
例えば、工作機械や金型といった特殊な機械を使う製品、船舶といった生産性が少なく原価が高い製品、オーダーメイドの家具や注文住宅などカスタマイズができる製品などは、受注生産に向いています。
一方で、大量生産で安く生産・販売ができる製品は見込み生産に向いています。また、受注生産とは反対に、売れる見通しが立てやすく、汎用的な製品も見込み生産には適しています。
受注生産の生産方式
受注生産では主に「個別受注生産」と「繰返受注生産」の2種類の生産方式があります。
■個別受注生産(個別受注設計生産)
個別受注生産とは、顧客の受注に応じ、初めから設計・開発を行う生産形態です。大量の生産に対応することは難しいですが、設計・開発から行うため、多種多様な要望に応じることができます。そのため、多品種少量生産に向いています。
■繰返受注生産
繰返受注生産とは、図面や設計といった仕様があらかじめ決定している製品を、受注毎に繰り返し生産する形態を指します。仕様変更が少ないものは、繰返受注生産で対応することができます。
最初から設計・開発を行う必要がないため、生産効率を向上することが可能です。
受注生産における生産効率を高める効果的な方法については、以下の資料で解説しています。
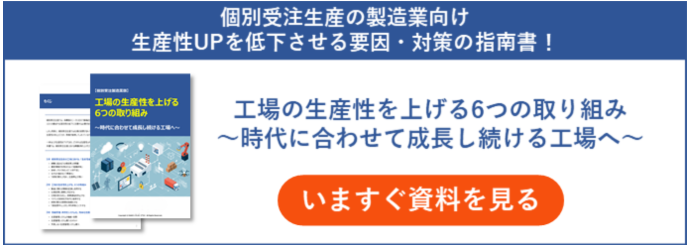
ここまで、受注生産の特徴について見込み生産と比較しながら解説してきました。
次章からは、見込み生産と受注生産それぞれのメリット、デメリットをご紹介します。
見込み生産のメリット

汎用性の高い製品や大量生産を行う商製品に向いているのが、見込み生産です。ここでは、見込み生産のメリットとデメリットをご紹介します。
メリット1:リードタイムが短くなる
見込み生産を行うと、受注から納品するまでの「リードタイム」を短くすることが可能です。複数の顧客に納品する製品を一度に生産する、複数の製品に使う材料や部品をあらかじめストックしておいていつでも生産を開始できるようにする、在庫を計画的に抱えておくなどの工夫でリードタイムを短くできます。
また、顧客にとってのリードタイムである「注文してから納品されるまで」の時間も、見込み生産の方が短くなります。場合によってはすでに生産してある在庫を出荷するだけなので、素早い納品により顧客満足度を高めることが可能です。
メリット2:汎用的な製品に向いている
複数の顧客に納品するような製品、競合他社も似たような製品を出しているような製品は、無理に受注生産しようとするとコストがかさみ採算が取れなくなることがあります。このような場合には、見込み生産を採用することで競合と戦える製品戦略を立てることが可能です。
見込み生産のデメリット
デメリット1:余剰在庫のリスクがある
見込み生産は「これくらいの受注があるだろう」という予測から生産計画を立てるため、受注数が予測を下回れば余剰在庫を多く抱えることになります。多すぎる在庫は保管するためのスペースや管理コストを増やす原因になるだけでなく、企業のキャッシュを長く滞らせることになるため、資金繰りが難しくなっていきます。
また、今後製品のバージョンアップを行い、新製品を販売する際に、在庫分が旧式となってしまう点にも注意が必要です。
デメリット2:競合他社が多く、売れ残るリスクがある
汎用性のある製品に向いている見込み生産は、他社も近い条件で生産・販売が可能なため、競合が多くなります。そのため、売れ残るリスクが高まります。売れ残るリスクを低減するために製品を値下げすることも可能ですが、結果的に売り上げ減少や現場の負担増加につながりかねません。
受注生産のメリット

見込み生産とは反対に、多品種少量生産やカスタマイズ可能な製品に向いているのが受注生産です。ここでは、受注生産のメリットとデメリットをご紹介します。
メリット1:顧客の要望に応えることができ、顧客満足度向上につながる
受注生産では顧客から注文があってから生産を開始するため、顧客からヒアリングをして希望に合わせたカスタマイズを施すことができます。そのため、競合他社と差別化した製品を設計する上では受注生産が向いています。顧客の要望を反映できるため、顧客満足度の高い製品の製造が期待できます。
見込み生産でも、安定的に品質を担保することはできるため一定の顧客満足度を得られます。しかし、近年進んでいる顧客ニーズの多様化を考えると、独自性を押し出す製品の製造が行える受注生産は、満足度の向上により寄与すると言えます。
メリット2:適切な在庫を維持しやすい
受注生産では注文があった分だけを生産すれば良いので、ロット数などの関係である程度の余りが出るケースを考えても、在庫を最小限に留めることができます。これにより、廃棄リスクや、在庫の保管コストの削減ができます。
受注してから生産という構造上在庫が過剰になることは考えにくく、キャッシュを滞らせずに売り上げにつなげる経営戦略を立てることが可能です。
適切な在庫管理を実現するポイントについては以下記事でご紹介しています。ぜひご覧ください。
受注生産のデメリット
デメリット1:リードタイムが長くなる
受注生産では、受注してから納品するまでのリードタイムが長くなる傾向にあります。ここで注意しなければならないのは、顧客から見たリードタイムです。
実際に生産を行う工場では1週間単位、2週間単位、あるいは1ヶ月単位で生産計画が立てられているため、受注してすぐに生産を開始できるわけではありません。受注があってから製品の生産リソースが確保され、それから生産が始まるため、製品自体の製造リードタイムが1週間だったとしても顧客から見たリードタイムは通常それ以上となります。
リードタイムの短縮方法については以下の記事で対策について解説しています。ぜひご覧ください。
デメリット2:仕様変更が多く発生する
顧客の要望に合わせながら設計・開発を行うため、生産開始直前や生産開始後に仕様変更の要望が発生しやすいです。これにより、手戻りが発生し、資材や稼働分のコストのムダが発生するリスクがあります。
また、受注生産では多種多様な部品を使用しているため、情報管理が煩雑化しやすく、仕様変更に早急に対応するのが困難な点もデメリットとして挙げられます。
そのため、仕様変更があったとしても、各部門と素早く連携するための体制を整える必要があります。
ここまでご紹介したように、受注生産は見込み生産にはないメリットを持っており、今後顧客に求められる生産形態であると言えます。しかし、同時にデメリットも多く存在します。
では、こういった受注生産の課題を解決するための対策としてどのようなことができるのでしょうか?
受注生産の課題解決には、一元管理ができるシステムの導入がおすすめ
受注生産は、適切な在庫を維持しやすく競合との差別化も図りやすい一方、受注のたびに仕様や生産数が変動する可能性があるため管理が煩雑になりがちです。
そのため、受注生産でもシンプルで誰にでも分かりやすい管理をするには、受注から発注までを一括管理できる生産管理システムを導入するのがおすすめです。
DAIKO XTECHでも、多品種少量生産に特化した「rBOM」を提供しています。「rBOM」は部品表をベースにした生産管理システムであることから、細かい仕様変更もスムーズに行うことができ、管理の難しい多品種少量生産でも対応可能です。
また、仕様変更はリアルタイムで各部門に共有されるため、情報共有がスムーズになるだけでなく、重要事項の伝達漏れ・遅れを防ぎます。統合化されたシステムは自部門の効率化だけでなく、全体最適な視点での管理を可能にするため、生産に関わる社員が利用することで「常に納期を意識した生産」の実現に役立てます。
受注生産における課題を解決したい方、「rBOM」に興味のある方はぜひ詳細をご覧ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
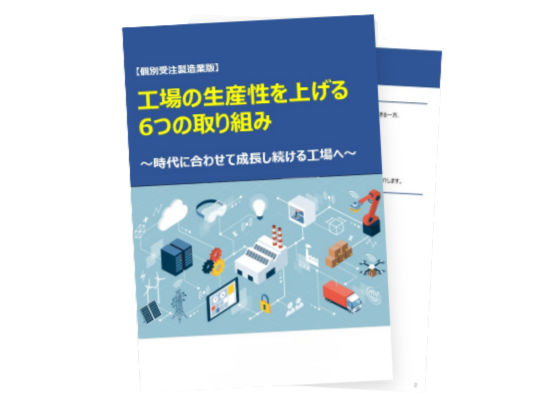
個別受注生産の製造業向け 生産性UPを低下させる要因・対策の指南書です!
工場の生産性を上げる 6つの取り組み
~時代に合わせて成長し続ける工場へ~

- この記事を監修した人
- 入社後15年間、長野支店にてシステムエンジニアとして活動。
運送業、倉庫業のお客さまを中心に担当し、業務システム構築からインフラ環境構築等の経験を積む。
その後、製造業のお客さまも担当し、rBOM導入のプロジェクトにも関わるように。
16年目に現部門に異動し、rBOM全国支援の担当者となる。
現在はrBOMだけではなく、製造業全般のソリューション提案を手掛けている。
料理が趣味、これからお菓子作りにも挑戦しようか迷っている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部 - 田幸 義則