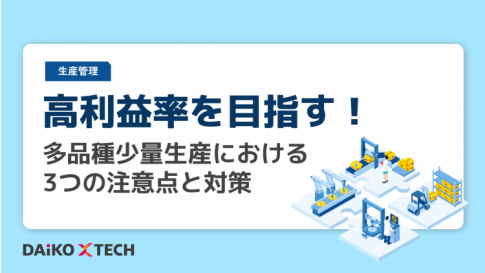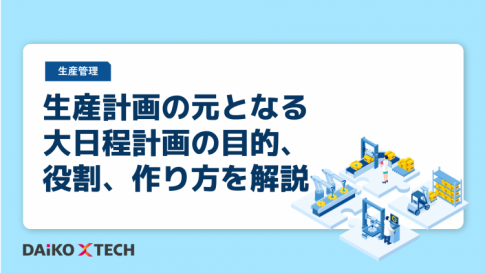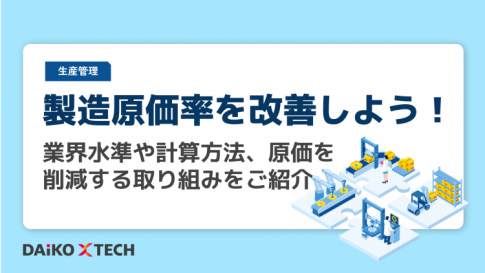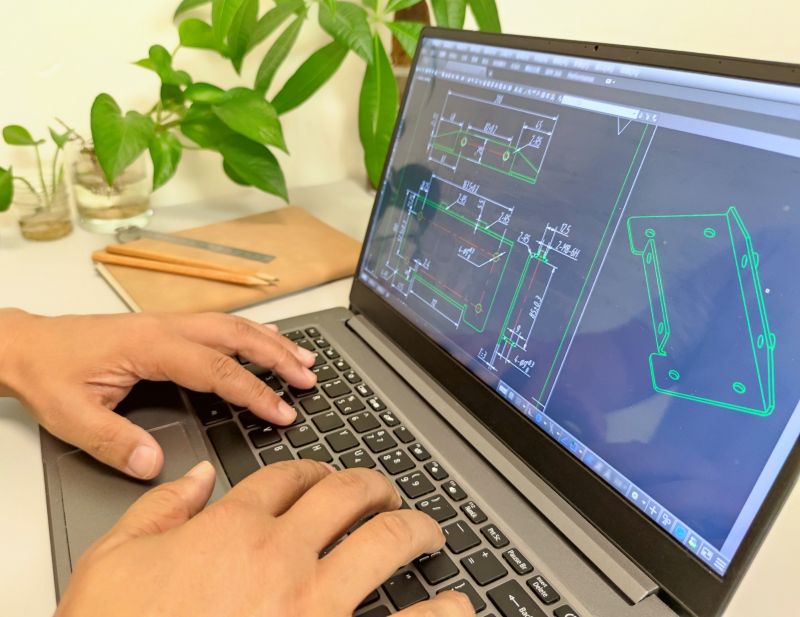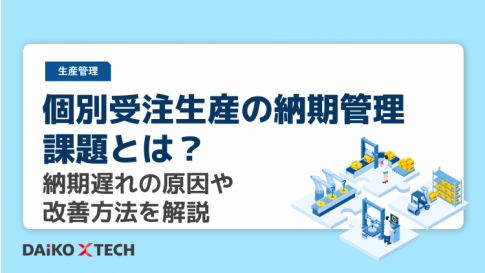製造業において、製造管理の最適化は生命線ともいえる重要課題です。では、似たような言葉である生産管理とは何が違うのでしょうか。今回の記事では、生産管理と製造管理の違いに加え、製造管理に求められること、製造管理を徹底することで得られるメリットなどをご紹介します。
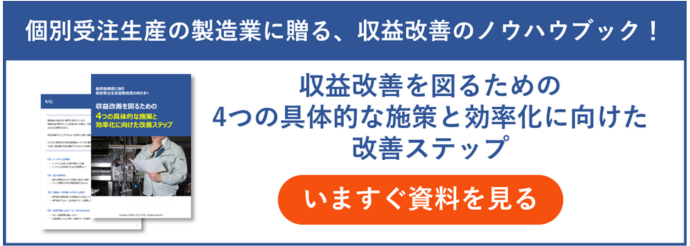
目次
生産管理と製造管理の違いとは
生産管理と製造管理とは、混同されがちな言葉ですが、それぞれの業務領域が異なります。初めに、生産管理と製造管理の違いを押さえておきましょう。
生産管理とは
生産管理とは、設計・調達・作業などの生産活動全体を品質・原価・数量・納期の観点から総合的に管理することです。受注から製造、出荷までの一連の工程を効率的に運営・管理する役割を担っています。
主な業務内容は、生産計画の立案と実行管理、原材料・部品の在庫管理、製造工程のスケジュール管理、品質管理体制の構築と運用、生産コストの分析ならびに改善などです。
生産管理の目的は、生産効率の最大化やコストの最適化、品質の維持・向上、納期遵守率の向上を通じて、顧客満足度の向上を目指す点にあります。
そのために、工程管理や品質管理などの専門知識に加え、生産管理システムの操作能力、データ分析力が求められます。
プロジェクトマネジメント能力やコミュニケーション能力、現場を理解する実務経験も重要です。生産管理は製造業における中核的な管理業務として、企業の生産性と収益性に直接的な影響を与える重要な役目を果たします。
製造管理とは
製造管理とは、製造現場における部品の製造作業、組み立て作業、金属加工、製造ラインなどの実務的な管理のことです。
製造管理システム(MES)を活用して、製造ラインの稼働時間、製造数、検品データなどを収集・分析し、製造精度の向上や工程の改善を実施する役割を担っています。
主な業務内容は、製造ライン全体の運営管理、製造装置の稼働状況の監視、品質検査データの収集と分析、工具や設備のメンテナンスの計画立案などです。
また、製造現場での人員配置や作業進捗の管理、不良品発生時の原因究明と対策の立案なども担います。
製品の品質維持と向上、製造コストの削減、生産効率の最大化、製造現場の安全確保を目的としています。
製造管理に求められるスキルは、製造工程や設備に関する専門知識、製造管理システムの活用能力、品質管理手法の理解です。
現場作業員とのコミュニケーション能力、問題解決力、データに基づく分析力も求められます。
近年では、製造データの自動収集・分析の重要性が高まっており、ITやデジタル技術への理解も必須です。
生産管理と製造管理の違い
生産管理が設計から納品までの生産活動全体を包括的に管理するのに対し、製造管理は生産管理の一部として位置づけられ、より製造現場に特化した管理を指します。生産管理が全体的な視点で工程を管理するのに対して、製造管理は製造現場での具体的な作業や工程の管理に焦点を当てている点が大きな違いです。
生産管理は受発注や在庫管理、原価管理など幅広い業務を含むのに対し、製造管理は製造ラインの稼働管理や品質データの収集・分析といった現場レベルの業務が中心です。
データ管理の面からみると、生産管理は全社的な生産計画や在庫情報を扱います。一方、製造管理は製造装置から得られる稼働データや品質検査データなど、より詳細な製造現場のデータを扱う特徴があります。
製造管理に求められること
製造管理において最も大切なことは、現場視点に立ち、製造ラインや制御システムを最適なバランスで稼働させることです。限られた生産リソースでより高い生産性を発揮する上では、製造ラインの稼働時間・製品の製造数・不良品の数など、あらゆるデータを蓄積し、常に最適解を導き出すことが求められます。
しかし、市場のニーズが多様化し、製造工程の複雑化が進む今、生産性と品質の双方を最大化することには困難を伴います。だからこそ、製造管理にはこれまで以上に多くの機能と高い性能が必要とされているのです。そこで活用の幅が広がりつつあるのが、製造管理工程のシステム化です。
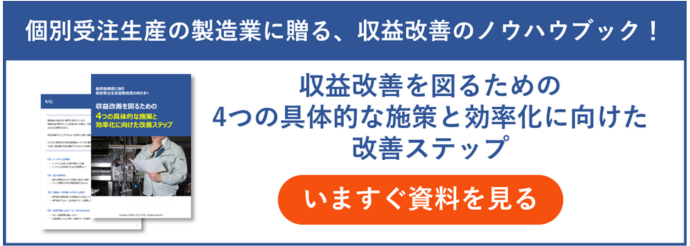
製造管理工程でシステムを導入するメリット
製造管理工程をシステム化することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。主なポイントとしては、次の3つが挙げられます。
メリット① 人手不足が解消できる
1つ目は、労働力不足の解消です。作業実績の収集を自動化し、分析を行うことで、高いスキルを持たない従業員でも対応可能な業務を広げることができます。その他にも、熟練技術者の技術をデータ化すれば、従業員の技能向上にも繋げることができるでしょう。
この他、業務を効率化するためのポイントを押さえ、業務時間の短縮にも繋げることも可能です。
メリット② データ処理が膨大でも対応できる
2つ目は、現場から得られる膨大なデータへの対応です。センサ技術や産業機械の進化に伴い、製造現場から得られるデータ量は膨大な量へと変化しています。そして、そのデータを活用してリアルタイムに製造プロセスを自動化するためには、データ処理の高速化と膨大化への対応が欠かせません。
システムを活用することで、エッジコンピューターとクラウドコンピューティングと相互に連携し、動作遅延を最小にしながら自動化を行うことが可能になります。
メリット③ 多品量少量生産管理の実現
3つ目は、生産スタイルの変化への対応です。市場ニーズの多様化に伴い、少品種大量生産の時代は終わりを告げ、多品種少量生産が主流の時代になりました。そうした中で製造現場のきめ細やかなオペレーションを実現する上でも、システムが重要な役割を果たします。システムを自動的に制御することでマス・カスタマイゼーションを実現し、大量生産の生産性を保ちながら多様な仕様に対応することができるのです。
では、システムを選ぶ際に求められる視点とは、どのようなものでしょうか。
製造管理のシステムの選び方
製造業のデジタル化が進む中、製造管理システムの導入は多くの企業にとって重要な経営課題です。
しかし、システム導入には多額の投資と人的リソースが必要となるため、慎重な選定が求められます。ここでは、製造管理システムを選ぶ際の重要なポイントについて解説します。
自社の目的と課題を明確化する
製造管理システムを選定する最初のステップは、自社が抱える課題や達成したい目的を明確にする点です。
システムによって実装されている機能や実現できることは大きく異なるため、導入目的に合致したシステムを選ぶことが重要です。
高額な費用を投じて導入しても、目的達成や課題解決ができないことを避けるため、事前の目的設定は慎重に行う必要があります。
製造形態との適合性を確認する
自社の製造形態に適したシステムかどうかの確認は不可欠です。大量生産型か少量多品種生産か、または個別受注生産方式かによって、必要とされる機能は大きく異なります。
特に個別受注生産の場合、製品仕様が細かく異なる場合も多いため、そうした柔軟性にシステムが対応できるか確認が必要です。導入を検討する際は、工場規模や生産方式に対応したシステムを選定しましょう。
導入形態とコストを検討する
システムの導入形態は、オンプレミスとクラウドの2種類から選択します。オンプレミスは自社内にサーバーを設置する方式で、カスタマイズ性に優れる反面、初期コストが高額です。
一方、クラウド型は初期コストを抑えられますが、カスタマイズ性が限られます。自社の予算と必要なカスタマイズ度合いを考慮して選択する必要があります。
サポート体制を確認する
システム導入後の安定運用のため、ベンダーのサポート体制は重要な選定ポイントです。導入時のサポートはもちろん、運用開始後のトラブル対応や問い合わせ対応の充実度を確認します。
24時間体制での対応の有無、マニュアルの整備状況、メールや電話でのサポート体制など、具体的なサポート内容を事前に把握しておくことが推奨されます。
生産管理だけでなく、製造管理ができるシステムを選ぼう
前述のように製造管理とは生産管理の一部であり、製品の品質と生産性を決める上での最重要領域ともいえます。だからこそ、これらをバラバラに捉えるのではなく統合的に考え、システム選びを進めていくことが求められます。
生産管理システムを導入する際には、製造管理の分野をどれだけカバーできているか、確認することが欠かせないでしょう。そこで最適な仕組みが製造管理も網羅した、生産管理システム「rBOM」です。
製造管理も網羅した、生産管理システム「rBOM」
「rBOM」は、製造現場と生産活動全体を繋ぐことができる生産管理システムです。特に、個別受注生産・多品種少量生産を行う企業に最適な機能を多数搭載しています。 例えば、製造時に使用した情報をまとめてデータベースに記録し、他部門とリアルタイムに連携することが可能。生産管理システムやスケジューラを活用すれば進捗状況が可視化できるため、飛び込み作業が多い現場においても納期遅延を未然に防ぐこともできます。
また、万が一遅延が発生している場合には、その作業工程を迅速に確認でき、遅延している理由や影響範囲も確認することができます。製造ラインや制御システムを最適なバランスを考える上でも欠かせない仕組みといえるでしょう。
「製造管理」への注力をお考えの企業様は、製造管理も網羅した生産管理システム「rBOM」の活用をご検討ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
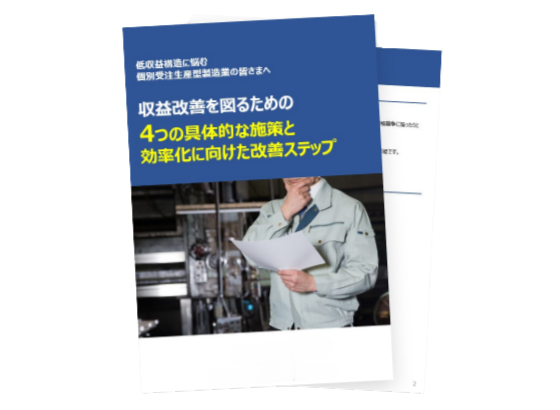
リードタイムの短縮、設計の標準化、情報共有の改善、生産管理の改善.... 個別受注生産の製造業に贈る、収益改善のノウハウブック!
収益改善を図るための4つの具体的な施策と
効率化に向けた改善ステップ

- この記事を監修した人
- 入社後15年間、長野支店にてシステムエンジニアとして活動。
運送業、倉庫業のお客さまを中心に担当し、業務システム構築からインフラ環境構築等の経験を積む。
その後、製造業のお客さまも担当し、rBOM導入のプロジェクトにも関わるように。
16年目に現部門に異動し、rBOM全国支援の担当者となる。
現在はrBOMだけではなく、製造業全般のソリューション提案を手掛けている。
料理が趣味、これからお菓子作りにも挑戦しようか迷っている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部 - 田幸 義則