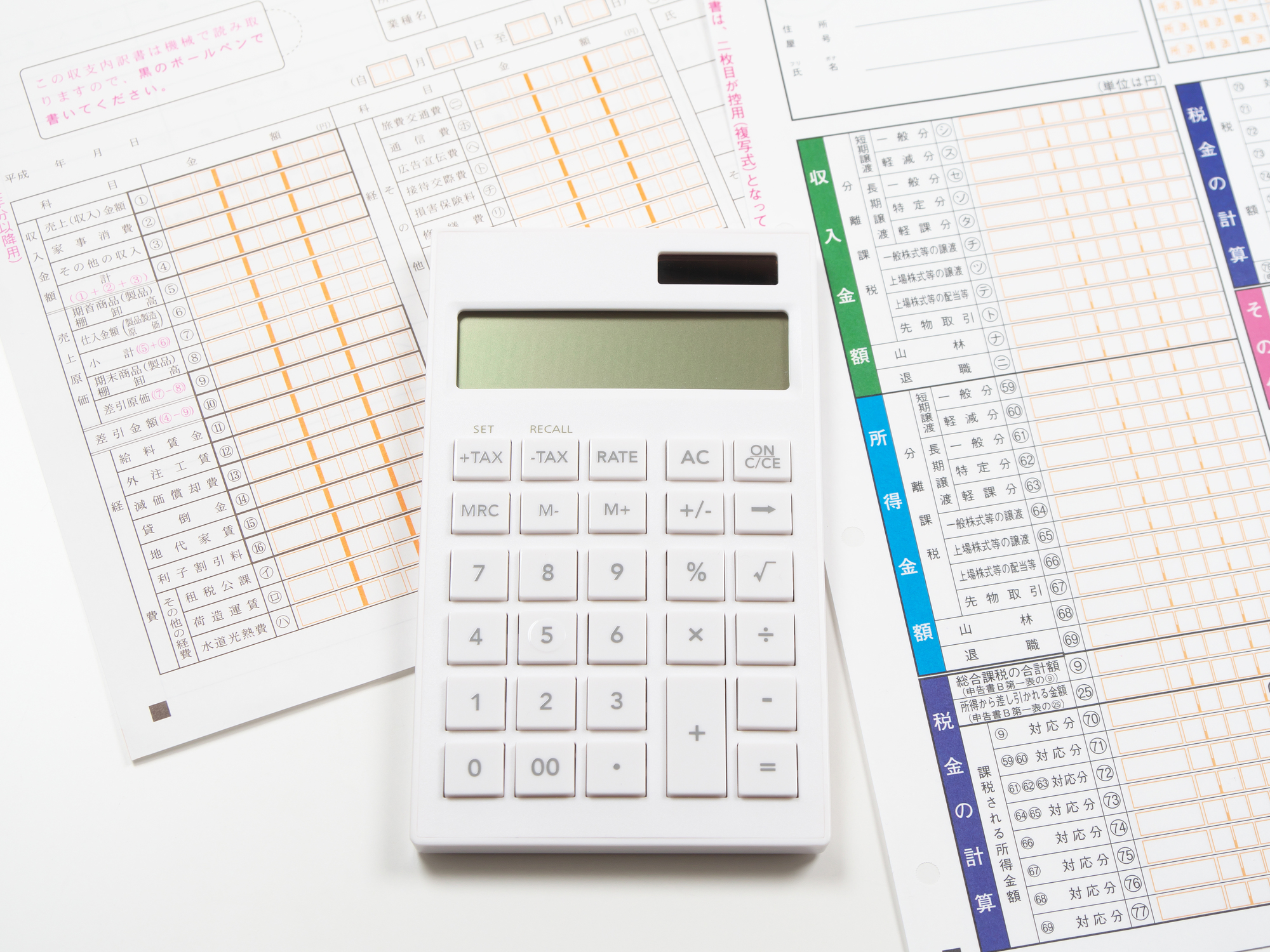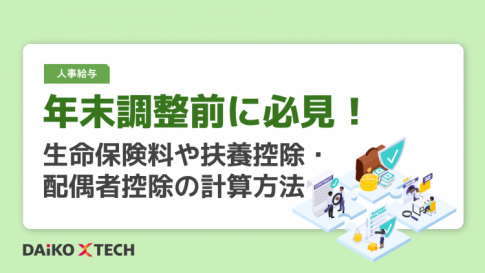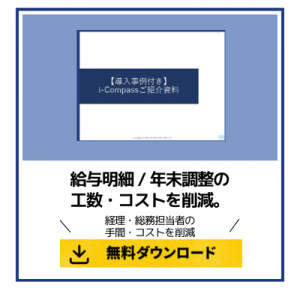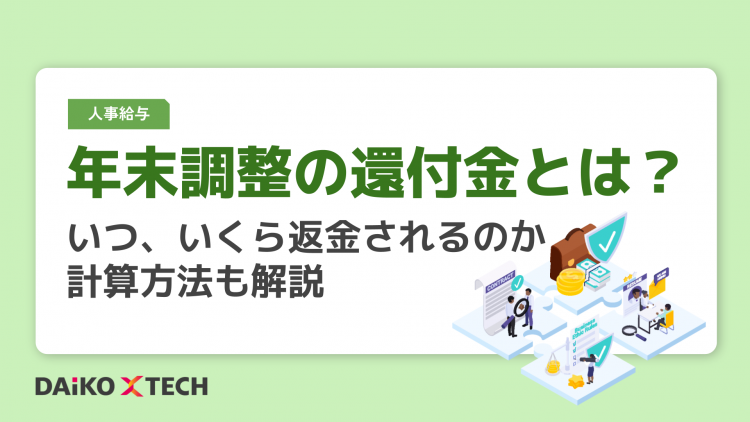
毎年行われる年末調整や確定申告により所得税の過払いなど、支払いすぎた税金が還付金として返金されるため、適切な手続きを踏む必要があります。
年末調整や確定申告で還付金を受け取るために、過払い金を返金してもらう方法を確認しておきましょう。
本記事では、年末調整や確定申告で過払いした所得税を受け取る方法を詳しく解説します。年末調整で還付金を受け取れるケースや受け取れないケースもあわせて解説するため、ぜひ最後までご覧ください。
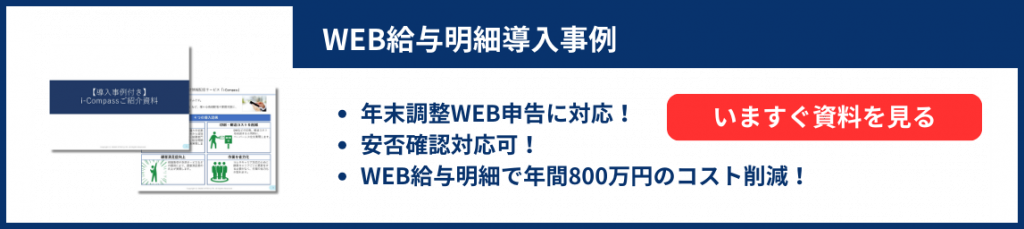
目次
年末調整の還付金とは?所得税が返金される仕組み

年末調整の還付金とは、1月1日~12月31日の期間に給料から徴収された源泉徴収税額が、納めるべき所得税額を超過した場合に返還されます。
そもそも年末調整は、給与所得者が毎月給料から差し引かれている源泉徴収税を、1年間の合計で適正に計算し直し、過不足分を年末に清算する制度です。
毎月給料から差し引かれる源泉徴収税額は、給与所得によって決まりますが、各種控除によって差額が生じてしまいます。
年末調整によって、所得税を払いすぎていると判断された場合、超過分が還付金として返還される仕組みです。
年末調整で還付金を受け取れるケース

年末調整で還付金が返還されるケースは、主に次のとおりです。
■ 家族構成の変化によって控除が増えるケース
- 結婚して配偶者控除・配偶者特別控除が適用される
- 扶養家族が増えた(子ども・親など)ことで扶養控除が増える
- 離婚・死別により寡婦控除が適用される
- ひとり親に該当し、ひとり親控除が適用される
- 本人または家族に障がいがあり、障がい者控除が適用される
■ 各種保険料や掛金を支払っているケース
- 生命保険に加入していて生命保険料控除を申告する
- 地震保険料を払っていて地震保険料控除がある
- 国民年金など、個人で社会保険料を払った(社会保険料控除)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)を払っている場合(小規模企業共済等掛金控除)
■ 大きな控除があるケース
- 住宅ローンを利用しており、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用される
年末調整では、1年間で納めた所得税が「正しい金額より多かった場合」に還付金が発生します。
そのため、控除が増えた、生活の変化によって新しく適用されるようになった場合に、年末調整の還付金を受け取れます。
年末調整に関する記事はこちらからご覧ください。
確定申告をすれば還付金をもらえるケース
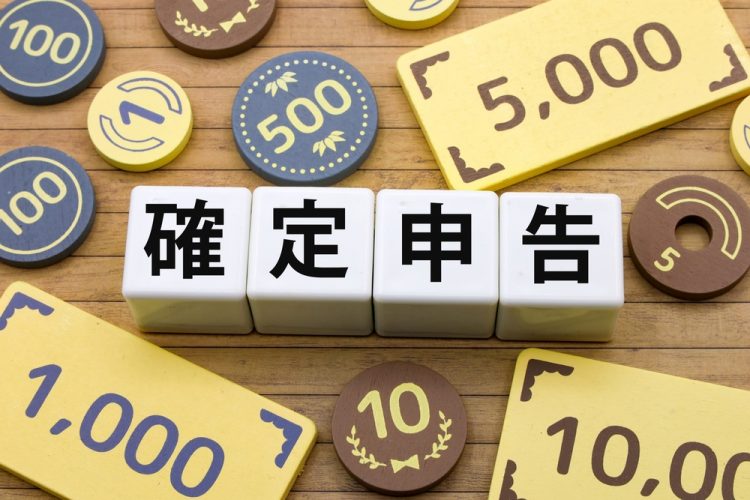
従業員が何らかの事情で会社の年末調整に間に合わなかった場合や、年末調整では申告できない特定の支出がある場合は、後日、従業員自身が確定申告を行うことで還付金を受け取れることがあります。
確定申告によって還付金を受け取れる主なケースは次のとおりです。
- 雑損控除の申請によって還付金が発生する場合
- 寄附金控除(ふるさと納税など)により税金が戻る場合
- 医療費控除の対象となり、払いすぎた税金が返ってくる場合
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の初年度申告を行う場合
- 年末調整を受けずに退職したため、納めすぎた税金が発生している場合
会社員の場合は、年末調整によって1年間の所得税を計算し直しますが、下記のような場合は自分で確定申告をする必要があります。
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
- 特定の所得控除や税額控除を適用する場合
- 給与・報酬以外で源泉徴収されている場合
- 予定納税額が多すぎた場合
- 過去の申告で控除を漏らしていた場合
確定申告で新たな控除を申請した場合、所得を計算し直すため、支払いすぎた源泉徴収税が返還される仕組みです。
年末調整の還付金はいつ受け取れる?

年末調整は、1月1日~12月31日までの所得を基に、納めるべき所得税額を決めます。
そのため、多くの企業では12月給与で年末調整を実施しますが、返金は1月にずれ込む企業もあります。
年末調整を提出してから還付金が還元されるまで一定の時間がかかるため、場合によっては1月の給与で返還分の差額を受け取れます。
なお、給与や賞与に上乗せして還付金を受け取る方法の他に、還付金を現金として受け取る方法もあります。
還付金の返還方法は企業によって異なるので、気になる方は勤務先の担当者に確認しておきましょう。
年末調整の還付金の計算方法

年末調整の還付金がいくらか計算する際は、下記を用意しておくと、スムーズに計算できます。
- 1月~12月までの給与明細
- 所得控除の対象となる書類(社会保険料控除証明書・生命保険料控除証明書など)
- 住宅ローンの年末残高を証明する書類(住宅ローン年末残高証明書)
上記の書類を用意しておくと、1年間の所得・源泉徴収税額を計算しやすいため、還付金額を求められます。
具体的な計算方法は、下記のとおりです。
- 給与総収入額から給与所得額を計算する
- 所得控除額の合計額を計算する
- 給与所得額から合計控除額を差し引き、課税所得税額を計算する
- 課税所得額から所得税を求める
- 所得税額と源泉徴収税額の差分から還付金額を計算する
それぞれの手順を確認して、年末調整の還付金額を計算しましょう。
給与総収入額から給与所得額を計算する
年末調整の計算は、まず「年間の給与総収入額」を正しく把握することから始まります。
給与総収入額とは、1月〜12月までに受け取った給与・賞与の合計額のことです。給与総収入額から、そのまま所得税を計算するわけではなく、国が定めた「給与所得控除」を差し引いて税額を算出します。
給与所得控除とは、給与を得るために必要な諸経費を差し引く仕組みで、収入に応じて自動的に計算されるものです。
|
給与総収入額 |
給与所得控除額 |
|
190万円以下 |
65万円 |
|
190万円超〜360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
|
360万円超〜660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
|
660万円超〜850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
|
850万円超 |
195万円(上限) |
給与総収入額から給与所得控除を引くと「給与所得額」が算出され、実際に所得税を計算する際の基礎を作り出せます。
所得控除額の合計額を計算する
給与所得額を計算した後は、「所得控除」を合計します。
所得控除とは、納税者の生活状況や負担に応じて税金を軽減する仕組みで、下記のようなものが代表的です。
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
これらの控除は、証明書や申告書の内容を基に1年間の合計額を算出します。
控除が多いほど課税対象となる所得が減り、結果として所得税が少なくなるため、還付金が増える可能性があります。
年末調整で提出する書類の多くは、この所得控除の金額を正確に反映するために必要なので、証明書類を漏れなく確認することが大切です。
給与所得額から合計控除額を差し引き、課税所得税額を計算する
給与所得額と所得控除の総額を計算した後は、「課税所得額」を求めます。
課税所得額の計算方法は、給与所得額から所得控除の合計を差し引くだけです。
合計所得控除を差し引いた後の金額が、「実際に税金がかかる所得」です。
課税所得額から所得税を求める
課税所得額が確定したら、次に「所得税額」を計算します。
所得税は「超過累進税率」が採用されており、課税所得額に応じて税率が段階的に上がる方式です。
|
課税対象の所得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000円〜1,949,000円 |
5% |
0円 |
|
1,950,000円〜3,299,000円 |
10% |
97,500円 |
|
3,300,000円〜6,949,000円 |
20% |
427,500円 |
|
6,950,000円〜8,999,000円 |
23% |
636,000円 |
|
9,000,000円〜17,999,000円 |
33% |
1,536,000円 |
|
18,000,000円〜39,999,000円 |
40% |
2,796,000円 |
|
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
例えば、課税所得が195万円未満なら5%、330万円未満なら10%など、税率表に当てはめて計算します。
|
課税所得額×税率-控除額=所得税額 |
さらに、一定額の控除(税額控除とは別)が設定されているため、単純に税率を掛けるだけではなく、表を基に細かく計算する必要があります。
年末調整では、会社側が自動計算してくれますが、還付金の仕組みを理解するために自分でも計算式を理解しておきましょう。
所得税額と源泉徴収税額の差分から還付金額を計算する
最後に、年間の源泉徴収税額と、本来支払うべき所得税額を比較します。
源泉徴収税額の方が多ければ、その差分が「還付金」として戻ってきます。
反対に、本来の所得税額の方が多かった場合は、不足分が追加徴収される仕組みです。
還付金が発生する主な理由は、控除の増加や年間の所得の変動などで、納めすぎていた税金が調整されるためです。
年末調整で還付金が受け取れない場合もある?

年末調整は「必ずお金が戻ってくるもの」ではなく、場合によっては還付金が発生しないケースも珍しくありません。
年末調整とは、1年間に支払った源泉徴収税額と、本来支払うべき所得税額の差を精算する仕組みであり、「納めすぎていた場合のみ返金される」ものです。
そのため、源泉徴収税額がもともと適正、もしくは不足していた場合には還付金を受け取れません。
具体的には、以下のような場合は、年間の源泉徴収額と実際の所得税額との差が小さく、還付金は生じません。
- 扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除などの所得控除がほとんどないケース
- ボーナスや給与の変動が少なく源泉徴収税額のズレが出にくいケース
- 住宅ローン控除の初年度や医療費控除・寄附金控除など年末調整で扱えない控除があるケース
つまり、年末調整で還付金が出るかどうかは「源泉徴収税額との誤差があるかどうか」によって決まります。
年末調整で扱えない控除がある場合は、確定申告で源泉徴収税額と所得税額の差分を申告すれば、差額が還付されるケースもあります。
年末調整をきちんと行い還付金を受け取ろう
年末調整に必要な書類を提出し忘れてしまうと、企業が年末調整の手続きを進められません。その場合、還付金も戻ってこないため、年末調整で必要な書類の記入・提出は早めに行いましょう。特に各種控除がある場合は書類の手配などに時間がかかることもあるため、注意が必要です。
また、確定申告の対象となる方は、その準備も早めに行いましょう。
年末調整は、従業員にとっても企業側にとっても手間がかかり、提出漏れや記入ミスが起こりやすい手続きです。
こうした負担やリスクを軽減したい場合は、i-Compass給与明細 年末調整オプションの活用をご検討ください。
i-Compassなら、従業員の方がスマートフォンから必要情報を迷わず入力でき、抜け漏れを防ぎながらスムーズに申告できます。企業側では、提出状況や内容をクラウド上で一元管理できるため、総務・人事部門の作業負担も大幅に軽減可能です。
年末調整をもっと簡単・確実に進めたい方は、下記よりi-Compassをご確認ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓

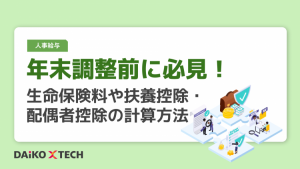
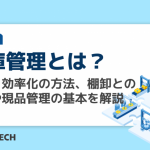


-768x512-1.jpg)