D’s TALK Vol.56|2024年7月発行
掲載コンテンツ 【D’s INTERVIEW File.12】 自分の可能性を追求するために、自分自身に挑み、走り続ける。 現役プロ陸上競技短距離選手 末續 慎吾 氏 【特集】 ウエルビーイング経営 「働きやすさ」から「...
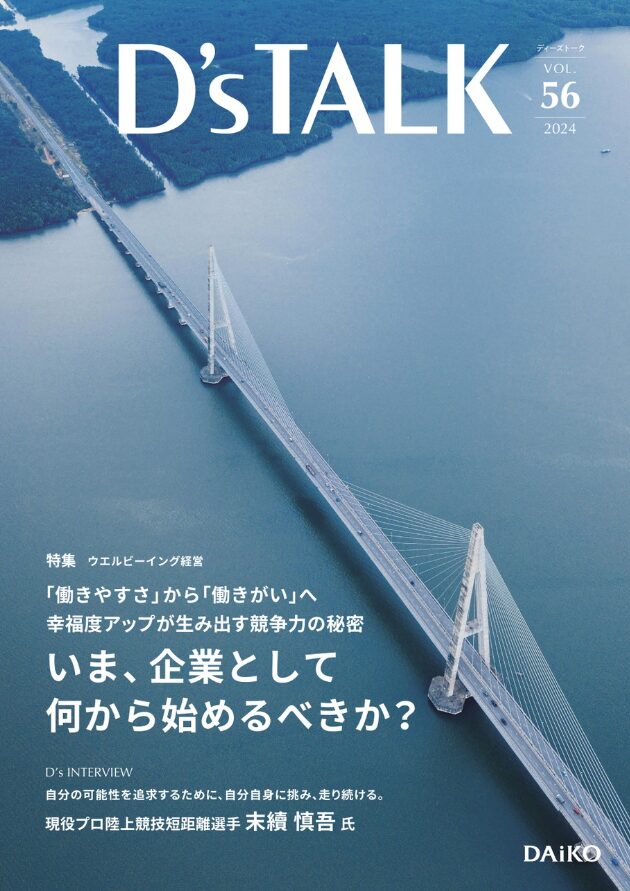 その他
その他掲載コンテンツ 【D’s INTERVIEW File.12】 自分の可能性を追求するために、自分自身に挑み、走り続ける。 現役プロ陸上競技短距離選手 末續 慎吾 氏 【特集】 ウエルビーイング経営 「働きやすさ」から「...
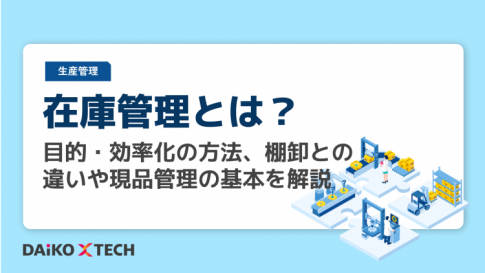 生産管理
生産管理在庫の数量や品質、所在などを管理する在庫管理は企業にとって非常に重要ですが、在庫管理の効率化について課題を抱えている企業も少なくありません。在庫管理を効率化し、適正在庫を維持するためには、在庫管理の基本を理解しておくこと...
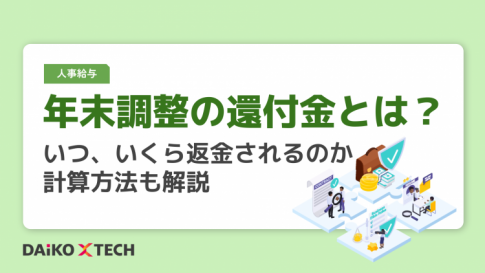 人事・給与
人事・給与毎年行われる年末調整や確定申告により所得税の過払いなど、支払いすぎた税金が還付金として返金されるため、適切な手続きを踏む必要があります。 年末調整や確定申告で還付金を受け取るために、過払い金を返金してもらう方法を確認して...
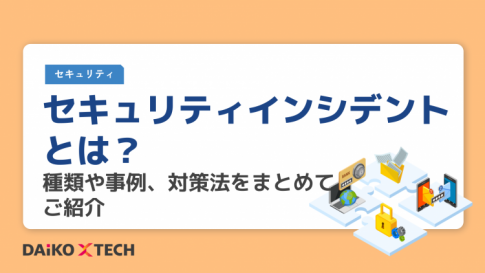 セキュリティ
セキュリティセキュリティインシデントとは、企業や組織が悪意ある第三者からの攻撃を受けたり情報漏えいしたりするなど、セキュリティの脅威となる事象のことを指します。昨今、セキュリティ脅威がますます複雑になってきており、セキュリティインシ...
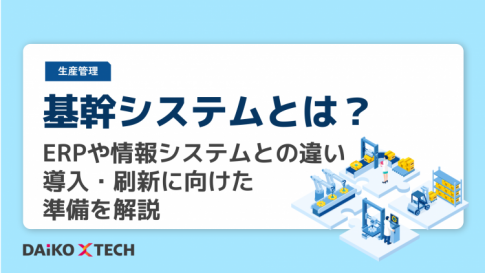 生産管理
生産管理企業の基幹となる業務をシステム化し、効率化やミスの削減などを目指したものが「基幹システム」です。基幹システムは大企業を中心に導入されていますが、中小企業においても多大な効果が期待できます。今回は、基幹システムの基本的な特...
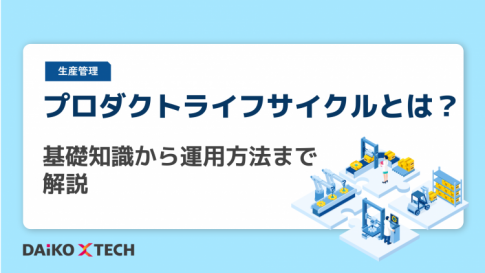 生産管理
生産管理近年、多くの製造業で取り入れられている「プロダクトライフサイクル」。プロダクトライフサイクルの概念を取り入れて適切な戦略を取ることで市場競争力を高め、かつ無駄のないコスト投入ができるようになります。 今回は、そんなプロダ...
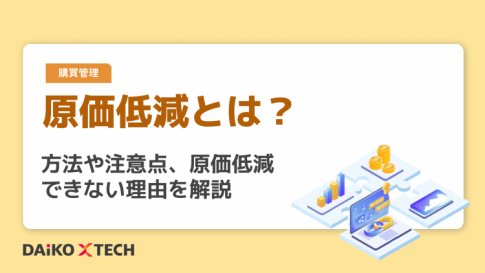 購買管理
購買管理原価低減とは、製品製造に関わるすべてのコストを削減する活動のことです。企業の利益向上の手段の1つですが、原価低減が上手くいかないケースもよく見られます。 今回は、原価低減の基本から実施時の注意点、よくある課題とその解決方...
 購買管理
購買管理副資材は工具や工作機械のメンテナンス・修理・操業に必要な備品や消耗品を指します。製品に必要な原材料とは違い、生産に直接関係するわけではありませんが、欠けているとスムーズに作業ができなくなる物も副資材に含まれます。設備停止...
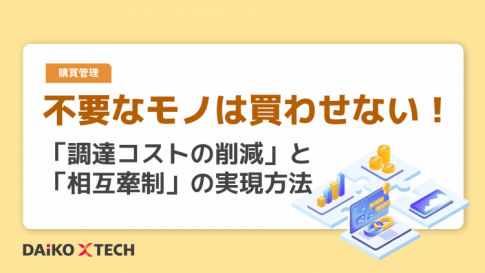 購買管理
購買管理消費者ニーズの多様化、グローバル化の進展により、企業へのコスト削減要請は厳しさを増しています。その一方、購買プロセスの不透明さを解消できず、調達コストの増加や不正購買に悩む企業が存在することも事実です。 コスト削減とコン...
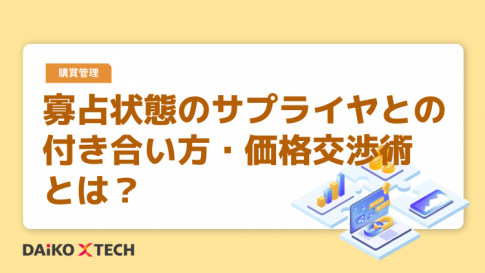 購買管理
購買管理自社と取引を行うサプライヤが、その分野・業界で寡占状態であり、取引のやりにくさを感じているご担当者さまは多いのではないでしょうか。 この記事では、そのような寡占状態のサプライヤとどのようにして付き合っていけばいいのかを解...