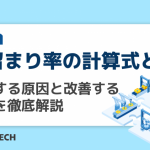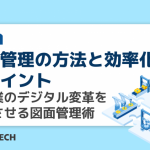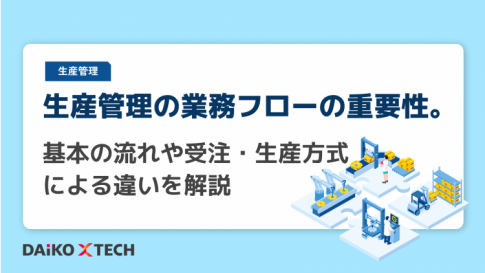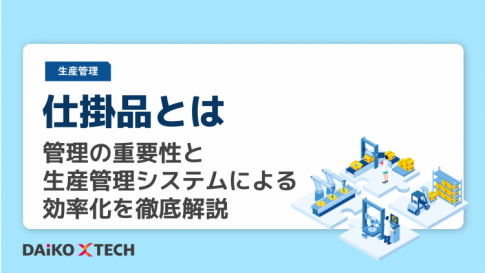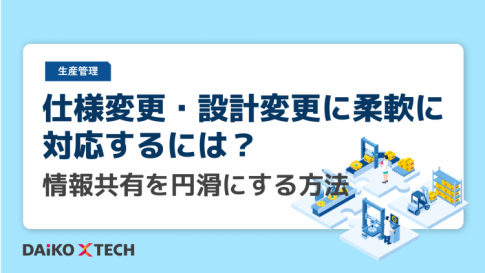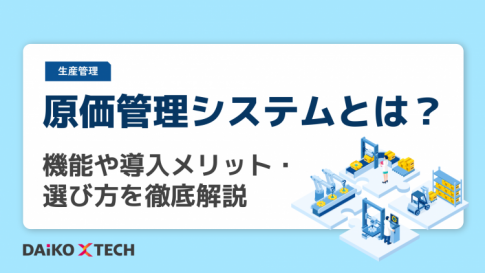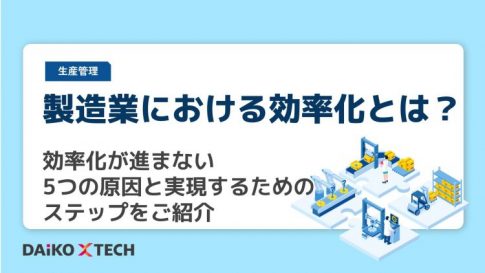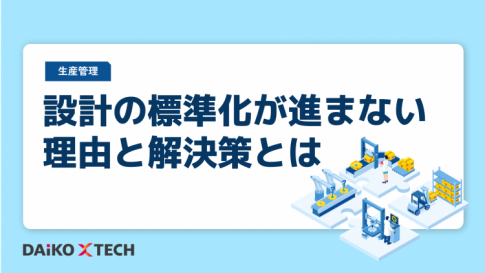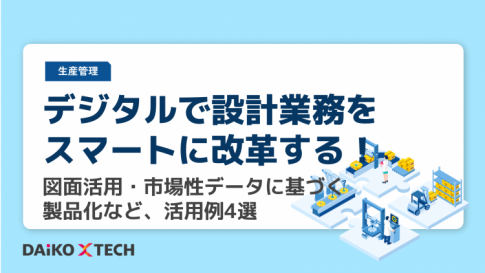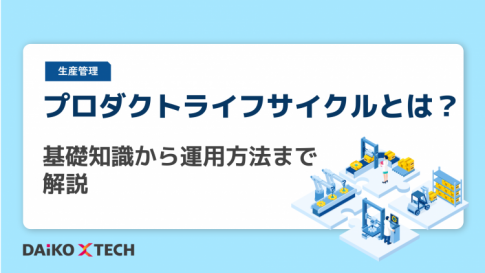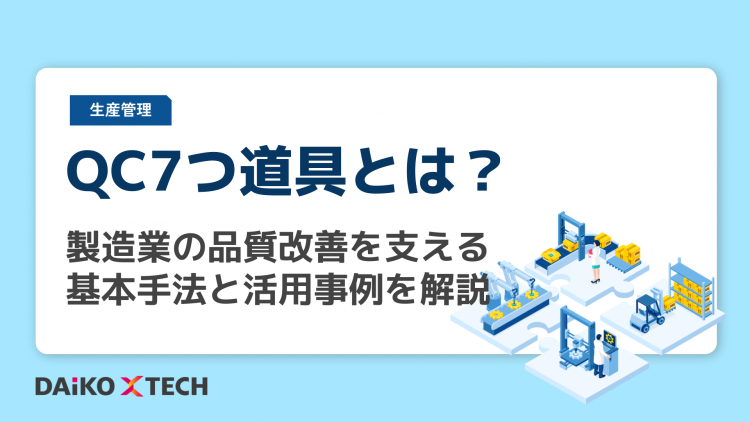
QC7つ道具とは、品質特性などのデータを解析し、問題解決を図るために用いられる7つの統計的手法の総称です。
製造業において品質管理は、製品の品質向上と生産性改善に不可欠な取り組みです。
中でもQC7つ道具は、製造現場での問題解決に効果的な統計的手法として広く活用されています。
そこで本記事では、QC7つ道具の基本概念から実践的な活用方法まで、わかりやすく解説します。
品質向上とコスト削減を両立させる、戦略的な品質管理を行うためにお役立てください。
目次
QC7つ道具とは

QC7つ道具は、品質管理(Quality Control)において用いられる、品質特性などのデータを解析し問題解決を行うための7つの方法を組み合わせた分析手法です。
1960年代に日本科学技術連盟を中心に、米国から導入された統計学的手法から使いやすいものをまとめたもので、日本の品質管理の第一人者である石川馨の貢献により体系化されました。
以降、製造現場での品質改善活動において、問題の発見から解決までのプロセスを効率的に進めるうえで役立っています。
QC7つ道具の種類
QC7つ道具は、製造現場の品質管理を支えるために開発された、データ分析と問題解決のための基本的な7つの手法です。
現場で発生する課題を「見える化」し、根本原因の特定や改善策の立案に役立ちます。
各手法は、用途や目的に応じて使い分けることで、効率的な品質改善が実現します。
QC7つ道具の種類は、以下の通りです。
|
手法名 |
主な目的・特長 |
|
パレート図 |
問題の優先順位を明確にする |
|
特性要因図 |
問題の根本原因を体系的に分析する |
|
グラフ(層別) |
データの傾向や変化を視覚的に示す |
|
ヒストグラム |
データのばらつきや分布を把握する |
|
散布図 |
2つの要因の相関関係を分析する |
|
チェックシート |
データを正確・簡単に収集する |
|
管理図 |
工程の安定性や異常を監視する |
これらの手法を適切に活用することで、現場の品質課題を迅速かつ客観的に解決へ導くことが可能です。
また、品質管理における問題解決のための手法「新QC7つの道具」やQC7つの道具との違い、手法の覚え方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:新QC7つ道具とは?従来との違いや活用術をわかりやすく解説
QC7つ道具を使用する目的

QC7つ道具は、製造現場における品質管理や業務改善のためにさまざまな目的で活用されています。その主な目的について詳しく見ていきましょう。
問題点を見える化するため
製造現場では、さまざまな問題が複雑に絡み合っていることが多く、その全体像を把握することは容易ではありません。
QC7つ道具は、こうした複雑な問題を視覚的に表現し、「見える化」する機能を持っています。
例えば、管理図を使用することで工程の安定性を視覚的に把握したり、特性要因図を用いて問題の原因を体系的に整理したり、これまで気づかなかった問題点の発見が可能です。
見える化された問題は、経営層から現場作業者まで共通の認識として共有できるため、組織全体での改善活動の推進に役立ちます。
不良や不具合の整理・分析のため
製造現場で発生する不良や不具合は、その種類や発生頻度、影響度などさまざまです。
QC7つ道具を活用することで、これらの不良や不具合を効率的に整理・分析し、優先的に取り組むべき課題を特定できます。
特に、パレート図はデータを大きさ順に並べて累積比率を示すことで、問題の重要度を視覚的に把握できる手法です。
この手法はパレートの法則(「80:20の法則」とも呼ばれ、全体の80%の結果が20%の要因から生じるといった考え方)が多くの場面で当てはまることから広く活用されています。
限られたリソースを効果的に配分するための意思決定に効果的です。
例えば、複数の不良モードがある場合、パレート図を作成することで全体の不良率に大きく影響している上位の不良モードに集中的に取り組めます。
また、改善前後のパレート図を比較し、改善効果を視覚的に確認することも可能です。
データを視覚化し、客観的な分析に役立てるため
数値データをそのまま見ても、その意味や傾向を理解することは困難です。
QC7つ道具を活用すると、データを視覚的に表現し、誰もが理解しやすい形に変換できます。
例えば、ヒストグラムを使ってデータの分布状況を視覚化したり、散布図で2つの要因の関係性を図示したりすると、データの持つ意味を直感的に理解することが可能です。
QC7つ道具を活用すれば、客観的な事実に基づいた分析と意思決定の促進が期待できます。
改善策の効果検証をするため
改善策の効果検証は、品質管理の現場において重要なプロセスです。
QC7つ道具を活用することで、導入した対策が実際にどれだけ効果を発揮しているかを、客観的なデータで確認できます。
例えば、グラフやヒストグラム、管理図、散布図などを用いて、対策前後のデータを比較・分析することで、改善の成果を明確に把握できます。
また、チェックシートで現場の変化を継続的に記録することで、改善活動の定着度や再発防止策の有効性も評価可能です。
感覚や経験則に頼らず、経営層や現場責任者が納得できる形で次の施策へつなげる判断がしやすくなります。
チームにおける意思決定をサポートするため
製造現場での改善活動は、多くの場合チームで取り組みます。
QC7つ道具を活用することで、チームメンバー間での情報共有や合意形成を促進し、効果的な意思決定をサポートできます。
例えば、特性要因図を用いたブレインストーミングを行うことで、チームの知識や経験を集約し、多角的な視点から問題の原因を探ることが可能です。
また、パレート図を活用して優先的に取り組むべき課題を明確にすることで、チームの方向性を統一できます。
QC7つ道具の各手法の特長と活用方法

QC7つ道具の各手法には、それぞれ特長と効果的な活用方法があります。
ここでは、各手法の特長と具体的な活用法について詳しく解説します。
散布図の活用法
散布図は、2つの変数間の関係性を点で表現し、相関関係を分析するための手法です。
特長:
- 2つの要因(変数)の関係性を視覚的に表現できる
- 正の相関、負の相関、無相関などの関係を直感的に把握できる
- 因果関係の推測に役立つ
活用法:
- 品質特性と製造条件の関係分析(例:温度と製品硬度の関係)
- 工程パラメータの最適化(例:圧力と製品強度の関係から最適圧力を決定)
- 設備の劣化診断(例:使用時間と精度の関係から劣化傾向を把握)
散布図を作成する際は、横軸に原因と考えられる要因、縦軸に結果と考えられる要因をとると、因果関係が把握しやすくなります。
チェックシートの活用法
チェックシートは、データを効率的に収集・整理するための表形式の手法です。
特長:
- データ収集の効率化と標準化が図れる
- 収集したデータを一目で把握できる
- さまざまな形式に応用可能
活用法:
- 不良品の種類と発生数のカウント
- 工程の各ステップでの検査結果の記録
- 設備の稼働状況や故障履歴の管理
- クレームや顧客からのフィードバックの整理
チェックシートは、データ収集の基礎となる手法であり、他のQC手法の前提となるデータの提供に活用されます。
そのため、収集する項目や記録方法を事前に十分検討することが重要です。
管理図の活用法
管理図は、工程の安定性を時系列で監視し、異常を早期に発見するための手法です。
特長:
- 工程の変動を「管理限界」と呼ばれる基準線と比較して評価
- 通常の変動(偶然原因)と異常な変動(特定原因)を区別できる
- 工程の安定性を継続的にモニタリングできる
活用法:
- 製造工程の安定性監視(例:部品寸法のばらつき監視)
- 品質特性の変化傾向の把握(例:強度の経時変化)
- 改善活動の効果確認(例:改善前後での不良率の変化)
- 予防保全のタイミング決定(例:設備精度の低下傾向から保全時期を予測)
管理図には、計量値用(X-R管理図など)と計数値用(p管理図、c管理図など)があり、データの種類に応じて適切な管理図を選択することが重要です。
特性要因図の活用法
特性要因図(魚の骨図、石川図とも呼ばれる)は、問題の原因を「人」「機械」「材料」「方法」などの観点から体系的に整理し、真因を追究するための図解手法です。
特長:
- 問題の原因を体系的に整理できる
- チームでのブレインストーミングに適している
- 複雑な問題の構造を視覚化できる
活用法:
- 不良発生原因の体系的整理
- 品質問題の根本原因分析
- 生産性低下要因の特定
- 新製品開発時の潜在的問題点の洗い出し
特性要因図を作成する際は、まず「結果」を明確にし、次に大骨(主要因)を設定した上で、中骨、小骨と細分化していくことが効果的です。
また、「なぜ?なぜ?」と繰り返し問いかけることで、より根本的な原因に迫れます。
ヒストグラムの活用法
ヒストグラムは、データのばらつきや分布状況を棒グラフで表し、工程能力を評価するための手法です。
特長:
- データの分布形状を視覚的に表現できる
- 平均値、ばらつきの大きさ、異常値の有無などを把握できる
- 規格値との関係から工程能力を評価できる
活用法:
- 製品寸法のばらつき評価
- 工程能力指数(Cp、Cpk)の算出
- 異常値や特殊な分布パターンの検出
- 改善前後でのばらつき比較
ヒストグラムを作成する際は、適切な階級数(通常10〜20程度)を設定し、十分なデータ数(統計的に有効な分布を得るためには、一般に50件以上のデータが推奨されます)を確保することが重要です。
パレート図の活用法
パレート図は、問題の発生頻度や影響度を棒グラフと折れ線グラフで表現し、重要な問題を優先的に取り組むべき対象を明確にする手法です。
特長:
- 「重要な少数」と「些細な多数」を区別できる(パレートの法則)
- 問題の優先順位付けに役立つ
- 改善効果の確認に適している
活用法:
- 不良モードの優先順位付け
- クレーム内容の分析
- 設備故障原因の分析
- 改善活動の効果確認
パレート図を作成する際は、横軸に項目(不良の種類など)を発生頻度の高い順に並べ、縦軸に発生頻度と累積比率を表示します。
一般的に、累積比率が80%に達するまでの項目に優先的に取り組むことが効果的です(80:20の法則)。
グラフ(層別)の活用法
グラフは、データの変化や傾向を視覚的に表現し、時系列での変化を把握するための手法です。
また、層別はデータを特定の基準(作業者、機械、材料、時間帯など)で分類し、より詳細な分析を行うための手法です。
特長:
- データの時系列変化を視覚的に表現できる
- さまざまなグラフ形式(折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフなど)を目的に応じて選択できる
- 層別と組み合わせることで、より詳細な分析が可能
活用法:
- 生産量や不良率の推移分析
- 作業者別、機械別、材料ロット別などの比較分析
- 時間帯別、曜日別、季節別などの傾向分析
- 改善活動の前後比較
グラフを作成する際は、目的に応じて適切なグラフ形式を選択し、誤解を招かないよう軸の目盛りや凡例を明確に表示することが重要です。
また、層別を行う際は、意味のある分類基準を選定し、各層のデータ数が十分確保できるよう注意する必要があります。
QC7つ道具の活用例

QC7つ道具は、単独で使用するだけでなく、問題解決のプロセスに沿って組み合わせることでより効果的に活用できます。
ここでは、問題解決の各フェーズにおける活用例をご紹介します。
問題発見フェーズでの活用
問題発見フェーズでは、現状を正確に把握し、取り組むべき課題を明確にすることが目的です。
このフェーズでは、以下のQC手法が効果的です。
チェックシート:データの収集と整理
製造ラインでの不良品発生状況を記録するチェックシートを作成し、不良モード別、工程別、時間帯別などの観点でデータを収集します。
例えば、プレス工程での不良発生状況を記録するチェックシートを用意し、1週間のデータを収集し、不良の発生パターンを把握します。
パレート図:問題の優先順位付け
チェックシートで収集したデータを基に、不良モード別のパレート図を作成します。
例えば、プレス工程での不良を「キズ」「寸法不良」「バリ」などの不良モード別に集計し、発生頻度の高い順に並べることで、優先的に取り組むべき不良モードを特定できます。
ヒストグラム:データの分布状況の把握
重要な品質特性の測定データを収集し、ヒストグラムを作成して分布状況を確認します。
例えば、製品の重要寸法の測定値を100個分収集し、ヒストグラムを作成することで、ばらつきの程度や規格値との関係を視覚的に把握できます。
管理図:工程の異常検出
重要な品質特性や不良率の推移を管理図で監視します。
例えば、日別の不良率をp管理図にプロットし、管理限界を超える異常点や特異なパターンがないかを確認することで、工程の安定性を評価できます。
これらの手法を組み合わせることで、「どの問題に取り組むべきか」を客観的に判断することが可能です。
例えば、パレート図で特定した主要な不良モードについて、ヒストグラムや管理図を用いて詳細に分析することで、問題の本質をより深く理解できます。
要因分析フェーズでの活用
要因分析フェーズでは、問題の原因を特定することが目的です。
このフェーズでは、以下のQC手法が効果的です。
特性要因図:問題の原因を体系的に整理
問題発見フェーズで特定した主要な不良モードについて、特性要因図を作成します。
例えば、「キズ不良」を頭に置き、「人」「機械」「材料」「方法」「測定」「環境」の観点から考えられる原因を洗い出します。
チームでのブレインストーミングを通じて、さまざまな視点からの意見を集約することが重要です。
散布図:要因と結果の関係分析
特性要因図で抽出した要因の中から、特に影響が大きいと思われる要因について、散布図を用いて定量的な関係を確認します。
例えば、「プレス圧力」と「キズ発生率」の関係を散布図で分析し、相関関係の有無や強さを確認します。
層別:条件別の傾向分析
データを特定の条件で層別し、問題の発生パターンを詳細に分析します。
例えば、キズ不良の発生率を「機械別」「作業者別」「材料ロット別」などの観点で層別し、特定の条件下で不良率が高くなる傾向がないかを確認します。
これらの手法を組み合わせることで、問題の真の原因を特定できます。
例えば、特性要因図で抽出した複数の要因について、散布図や層別分析を行い、統計的に有意な影響を持つ要因を絞り込むことが可能です。
対策立案・実施フェーズでの活用
対策立案・実施フェーズでは、特定した原因に対する効果的な対策を立案し、実行することが目的です。
このフェーズでは、以下のQC手法が効果的です。
特性要因図:対策案の体系的整理
特定した原因に対する対策案を特性要因図の形式で整理します。
例えば、「キズ不良の削減」を頭に置き、各原因に対応する具体的な対策を体系的に整理します。
パレート図:対策の優先順位付け
複数の対策案について、期待される効果やコスト、実現可能性などを考慮して優先順位を付けます。
例えば、各対策案の期待効果(不良削減数)を推定し、パレート図で視覚化することで、効果の大きい対策から順に実施できます。
チェックシート:対策実施状況の管理
立案した対策の実施状況を管理するためのチェックシートを作成します。
例えば、各対策の担当者、期限、進捗状況などを記録するチェックシートを用意し、定期的に更新することで、対策の確実な実施が促進できます。
これらの手法を組み合わせることで、効果的な対策の立案と確実な実施が可能です。
特性要因図で整理した対策案をパレート図で優先順位付けし、チェックシートで実施状況を管理するといった流れで改善を進めるなど手法を組み合わせると効果的です。
効果確認フェーズでの活用
効果確認フェーズでは、実施した対策の効果を検証し、必要に応じて追加対策を検討することが目的です。
このフェーズでは、以下のQC手法が効果的です。
ヒストグラム:改善前後のデータ分布比較
対策前後の品質特性データを収集し、ヒストグラムで分布状況の変化を確認します。例えば、重要寸法の測定値について、対策前後のヒストグラムを比較し、ばらつきの減少や中心値の改善を確認します。
管理図:工程安定性の改善確認
対策後の品質特性や不良率の推移を管理図で監視し、工程の安定性向上を確認します。例えば、日別の不良率をp管理図にプロットし、対策前後で管理限界や平均値がどのように変化したかを確認します。
パレート図:不良モード構成の変化確認
対策後の不良モード別発生状況をパレート図で表示し、対策前と比較します。例えば、対策前に最も多かった「キズ不良」が減少し、不良モードの構成比がどのように変化したかを確認します。
これらの手法を組み合わせることで、対策の効果を多角的に検証できます。
効果が不十分な場合は、要因分析フェーズに戻り、追加の原因分析と対策立案を行うことも重要です。
QC7つ道具導入時の注意点

QC7つ道具を効果的に活用するためには、いくつかの重要な注意点があります。
ここでは、導入時に特に留意すべきポイントについて解説します。
問題の性質に応じて最適な手法を選択すること
QC7つ道具は、それぞれ異なる特長と適用範囲を持っています。
問題の性質や解決の目的に応じて、最適な手法を選択することが重要です。
例えば、不良モードが多岐にわたり、優先順位付けが必要な場合はパレート図が適しています。
一方、2つの変数間の関係を調査する場合は散布図が効果的です。
また、プロセスの安定性を継続的に監視する場合は。管理図が最適です。
適切な手法の選択には、以下のポイントを考慮しましょう。
- 問題の性質:定量的か定性的か、単一要因か複合要因か
- 分析の目的:現状把握、原因特定、効果確認など
- 利用可能なデータ:データの種類、量、精度
- 分析の対象者:現場作業者、管理者、経営層など
最適な手法を選択することで、効率的な分析と的確な問題解決が可能です。
また、複数の手法を組み合わせることで、より包括的な分析が実現できることも覚えておきましょう。
データ収集時には、信頼性確保と一貫性に注意すること
QC7つ道具による分析の質は、収集するデータの質に大きく依存します。
信頼性の高いデータを一貫した方法で収集することが、正確な分析と適切な意思決定の基盤です。
データ収集時には、以下の点に注意しましょう。
- 測定方法の標準化:測定器具、測定方法、測定条件を統一する
- サンプリング方法の適正化:偏りのないサンプル抽出を心がける
- データ量の確保:統計的に意味のある分析に必要な十分なデータ量を確保する
- 記録の正確性:データの転記ミスや記録漏れを防止する
- 測定者の教育:測定技術や記録方法について適切な教育を行う
特に製造現場では、作業の忙しさや環境条件の変化などにより、データ収集の質が低下するリスクがあります。
このリスクを最小化するために、チェックシートなどの標準化されたフォーマットを活用し、データ収集の手順を明確に定義することが重要です。
また、自動測定システムやIoT技術を活用すると、人為的なミスを減らし、より信頼性の高いデータ収集が実現可能です。
改善活動は現場作業者から管理職まで幅広く参加すること
QC7つ道具を最大限に活用し、現場の品質改善を持続的に進めるためには、現場作業者から管理職まで幅広い層が改善活動に参加することが不可欠です。
現場の第一線で働く作業者は、日々の業務を通じて小さな異変や課題を最も早く察知できます。
一方で、管理職や経営層は、全体最適やリソース配分、戦略的な視点から改善活動を後押しする役割を担います。
全員が自分ごととして品質改善に関わることが重要です。
現場の知恵と経営判断が融合し、実効性の高い改善策を生み出せます。
全員参加型の改善活動を徹底し、継続的な成長と競争力強化につなげましょう。
QC7つ道具で製造現場を変革しよう

製造業を取り巻く環境は、グローバル競争の激化やお客さまニーズの多様化により、一層厳しさを増しています。
この厳しい状況下で競争力を維持・強化するためには、品質向上とコスト削減を両立させる効率的な製造マネジメントが不可欠です。
QC7つ道具の活用は、データに基づく意思決定の文化ではなく、感覚や経験だけに頼らない科学的なアプローチが可能です。
さらに、QC7つ道具による現場改善に加え、個別受注生産の現場で生産性向上に悩まれている方には、「工場の生産性を上げる6つの取り組み〜時代に合わせて成長し続ける工場へ〜」のホワイトペーパーをご覧ください。
生産性低下の要因や有効な対策を具体的に解説していますので、ぜひご活用ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
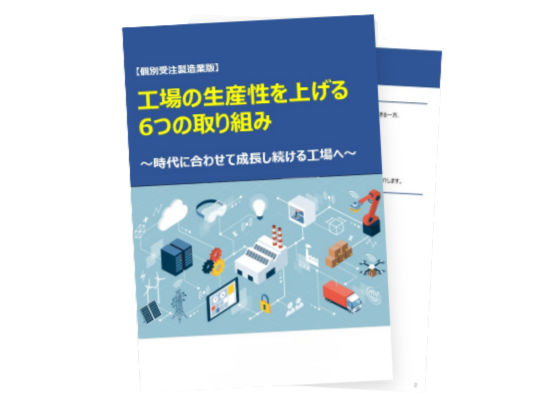
個別受注生産の製造業向け 生産性UPを低下させる要因・対策の指南書です!
工場の生産性を上げる 6つの取り組み
~時代に合わせて成長し続ける工場へ~