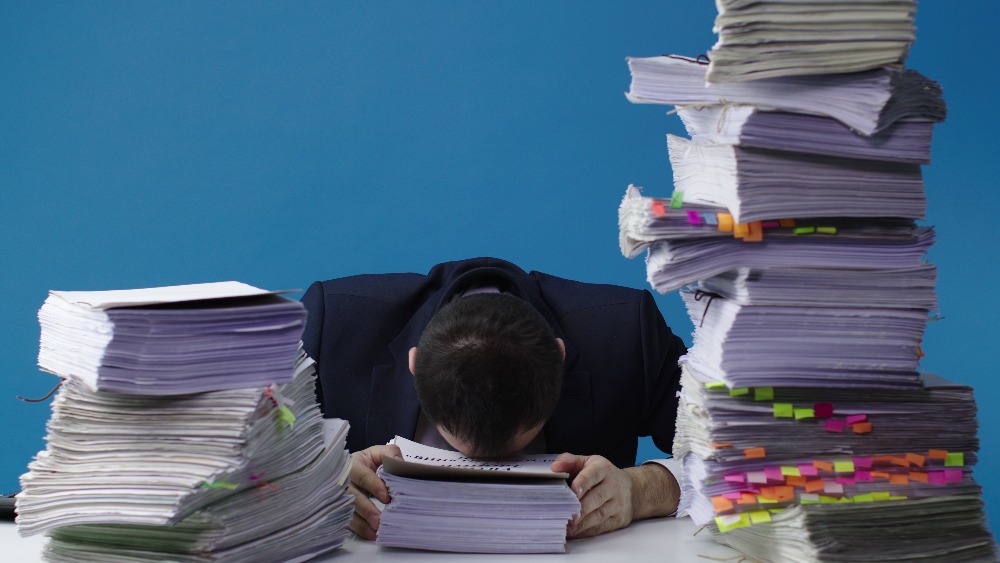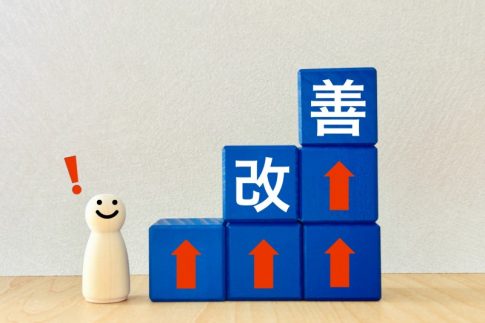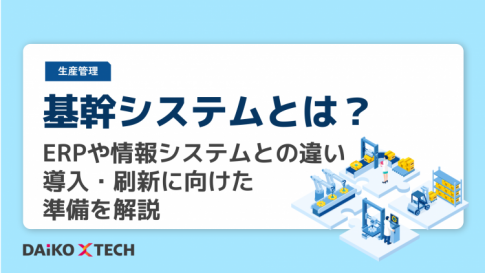製造業において、製品の原価を正確に把握し管理することは、企業の収益性と競争力を維持・向上させるために不可欠です。その中でも実際原価計算は、実際の製造過程で発生する費用を適切に把握し、財務会計と原価管理の両面で重要な役割を果たしています。
本記事では、実際原価計算の基本的な仕組みから具体的な計算方法、メリットとデメリットまでを分かりやすく解説しています。製造業や建設業における活用事例も交えながら、実務での応用方法についても詳しく説明していきますので、実際原価計算の導入・改善を検討している企業の方々は必見です。ぜひ最後までご覧ください。
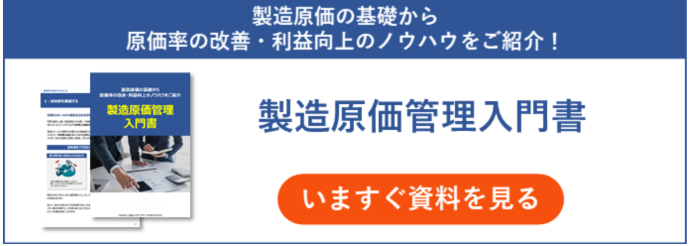
目次
実際原価計算とは

製造業において、製品の原価を正確に把握し管理することは、企業の収益性と競争力を向上するために重要です。特に、実際原価計算は製造過程で発生するさまざまな費用を適切に把握し、財務会計と原価管理の両面で大切な役割を果たしています。
ここでは、実際原価計算の定義と目的、その特徴、標準原価との違いについて詳しく解説していきます。
実際原価計算の定義と目的
実際原価計算とは、製品の製造過程で実際に発生したすべての費用を集計し、製品の原価を算定する方法です。実際に使用した原材料や部品などの数量と取得単価、実際に費やされた作業時間、実際に発生した諸経費などを正確に積算して計算を行います。
主な構成要素としては、直接費(直接材料費、直接労務費、直接経費)と間接費(間接材料費、間接労務費、間接経費)があり、これらを合算して製造原価を算出します。直接費は製造番号や作業番号に直接紐付けられる費用であり、間接費は工場全体の管理費用など、製品に直接紐付けられない費用です。
実際原価計算の目的は以下の2つに大別されます。
1つ目が財務会計目的です。製品の実際原価を正確に把握することで、財務会計における棚卸資産評価や売上原価計算に貢献します。これにより、ステークホルダーへの正確な財務情報の開示が可能です。
2つ目が原価管理目的です。実際の製造過程で発生した原価を詳細に把握することで、標準原価との差異を分析できます。この分析によって生産効率の評価や改善点の特定、コスト削減の機会の発見などが可能となり、より効率的な生産活動の実現につながります。
実際原価計算の特徴
実際原価計算は、製品製造において実際に発生した費用をもとに計算を行う方法です。一見すると正確な原価を表しているように見えますが、材料相場の変動、作業能率の変化、操業度の変動などの外部要因や偶発的な要因に左右される性質があるため、必ずしも製品の真の原価を表しているとは言えません。
このため、実際原価計算においても製造間接費については「正常配賦」という手法を採用します。これは予定配賦率に実際作業時間を乗じて原価を算出する方法です。ゴールデンウィークなどの長期休暇による操業日数の変動が原価に与える影響を平準化できます。
また、予定配賦率と実際配賦率との差異は「原価差異」として把握し、その後の分析により原因を究明します。特に製造間接費については固定費と変動費を区別し、変動予算を用いて管理することで、より正確な原価差異の分析が可能です。
実務面では材料費会計における継続記録法の採用による適切な損益管理、労務費における主費と副費の区分、原価差異の適切な処理が重要です。原価差異の処理については、材料受入価格差異は材料の払出高と期末在高に配賦し、その他の原価差異は原則として当年度の売上原価に賦課します。
これらの特徴を踏まえ、効果的な原価管理を実現するためには、標準原価計算との併用や適切な製造間接費の配賦方法の選択が不可欠です。
標準原価との違い
実際原価は、製品の製造過程で実際に発生した費用を集計して算出する原価です。材料費や労務費、経費など、実際の製造活動で発生したすべての費用を正確に積算して計算します。
実際原価は精度の高さが特徴ですが、材料相場の変動、作業能率の変化、操業度の変動などの外部要因や偶発的な要因に左右されるため、必ずしも製品の真の原価を表しているとは限りません。また、計算に時間を要するため、タイムリーな原価管理の難しさが特徴です。
一方、標準原価は科学的・統計的な分析に基づいて設定された理想的な原価です。製品の製造において、効率的な生産活動が行われた場合を想定して算出されます。無駄のない材料調達、効率的な製造工程の稼働、適正な歩留まり率などの条件下で計算される原価です。標準原価は、原価管理の目標値として機能し、実際原価との差異分析を通じて、生産活動における問題点の把握や改善点の特定に活用されます。
これらの違いから、多くの企業では実際原価計算と標準原価計算を併用するのが一般的です。標準原価を目標値として設定し、実際原価との差異を分析することで、より効果的な原価管理と生産性の向上を図れます。また、標準原価は予算編成や価格設定の基準としても活用され、経営管理において重要な役割を果たしています。
実際原価計算の計算方法

製造業において、製品の原価を適切に把握することは経営管理の要です。原価計算には実際原価計算と標準原価計算がありますが、ここでは実際原価計算に焦点を当てます。集計方法、予定配賦率の算出方法、実際原価の配賦方法について詳しく解説していきます。
実際原価の集計
実際原価の集計は、製品の原価を算定するための基本的な計算過程です。
まず、製造原価の構成要素である直接費と間接費を区分して集計します。直接費は製品に直接紐付けられる費用で、直接材料費、直接労務費、直接経費から構成されます。一方、間接費は製品に直接紐付けられない費用で、間接材料費、間接労務費、間接経費から構成されるものです。
直接製造原価の計算では、直接材料費、直接労務費、直接経費を合算します。材料費の把握には継続記録法または棚卸計算法を用います。特に継続記録法では一品目ごとの受払及び残高を記録することで、より正確な材料の会計管理が可能です。労務費については、賃金給料等の労務主費に加え、社会保険料等の法定福利費や退職給付引当金繰入額などの労務副費も含めて計算します。
間接製造原価の計算で使用するのは、製造間接費に対して「正常配賦」です。予定配賦率に実際作業時間を乗じて算出します。予定配賦率により、ゴールデンウィークなどの休暇による操業度の変動が原価に与える影響を平準化できます。
製造原価の総額を求める方法は、直接製造原価と間接製造原価の合算です。一般管理費および販売管理費の加算によって総原価が算出されます。予定配賦率と実際配賦率との差異は「原価差異」として把握し、後の分析により原因を究明することが重要です。
予定配賦率の算出
予定配賦率は、製造間接費の配賦額を算定するために事前に決定する比率です。製造間接費予算額を基準操業度で割って算出されます(予定配賦率 = 製造間接費予定額 ÷ 基準操業度)。
製造間接費予算の設定には、固定予算と変動予算の2つの方法があります。固定予算は操業度に関わらず一定の予算額を設定する方法です。すべての製造間接費を固定費として扱います。一方、変動予算は製造間接費を変動費と固定費に分けて設定する方法です。「製造間接費予算額 = 変動費率 × 操業度 + 固定費」で算出します。
基準操業度は以下の4種類です。
- 最大操業度
- 実際的操業度
- 正常操業度
- 予定操業度
企業は自社の状況に応じて適切な基準操業度を選択します。例えば、絶えず変化にさらされる業界では、長期的な平均である正常操業度よりも、短期的な予測に基づく予定操業度の方が適切な場合も少なくありません。
算出された予定配賦率は、実際の製造間接費配賦額(予定配賦額)を計算する際に使用されます。予定配賦額は、予定配賦率に実際操業度を掛けることで求められます(予定配賦額 = 予定配賦率 × 実際操業度)。この方法により、迅速な原価計算が可能となり、操業度の変動による原価変動を抑制可能です。
実際原価の配賦
実際原価の配賦は、製品の製造において実際に発生した費用を製品に割り当てる過程です。実際配賦率(製造間接費実際発生額 ÷ 配賦基準数値の合計)に基づいて、各製品への製造間接費の配賦を行います。配賦基準としては、直接工の直接作業時間、直接労務費、直接材料費、機械運転時間などが用いられます。
しかし、実際原価の配賦の課題は原価計算の遅延です。実際配賦では、一定期間の製造間接費の実際発生額が確定するまで配賦計算を行えないため、各製品の原価計算に時間がかかってしまいます。
また、製品原価の不安定性も課題です。特に製造間接費に含まれる固定費は、操業度に関係なく一定額が発生します。そのため、操業度の変動によって製品の単位原価が大きく変動してしまう可能性があります。
このような実際原価配賦の課題を解決するため、多くの企業で採用しているのが、予定配賦率を用いた配賦方法です。製造間接費については予定配賦率に基づく「正常配賦」を行い、予定配賦率と実際配賦率との差異は「原価差異」として把握し、後に分析して原因を究明する方法が一般的です。これにより、より安定的かつタイムリーな原価計算が可能です。
実際原価計算と原価差異

実際原価計算は、製造工程で実際に発生した材料費、人件費、間接費、輸送費などの原価を用いて製造原価を算出する方法です。各製品のコストを実際の数量や生産量に基づいて単位コスト化することで、正確な製品コストを把握できます。
一方で、標準原価との差異である原価差異が発生し、この分析・管理が原価管理において重要な役割を果たします。
原価差異の種類
原価差異にはまず、材料に関する差異として材料受入価格差異があり、材料の標準価格と実際の受入価格との差額を表します。次に直接材料費差異があり、価格差異と数量差異に分解されます。
労務費に関しては直接労務費差異があり、分類されるのは賃率差異と作業時間差異です。また製造間接費差異があり、予算差異、能率差異、操業度差異などに分解して分析されます。
原価差異分析の重要性
原価差異の分析は、企業の原価管理において重要です。標準原価と実際原価の差を分析すると、製品の実際コストが標準原価からどの程度逸脱しているかを把握でき、原価管理の正確性向上や無駄な費用の削減につながります。
また、製品の価格設定において実際のコストを反映させることができ、より競争力のある価格設定が可能です。
原価差異の分析方法
原価差異の分析には、具体的な計算式が用いられます。例えば価格差異は「(実際の価格 – 標準価格) × 実際の数量」で計算され、数量差異は「(実際の数量 – 標準数量) × 標準原価」で計算されます。
賃率差異の算出方法は「(実際の賃金率 – 標準賃金率) × 実際の労働時間」、時間差異は「(実際の労働時間 – 標準労働時間) × 標準賃金率」です。これらの分析を通じて、原価の変動要因を特定し、適切な対策が立てられます。
原価差異の会計処理
原価差異の会計処理は、その性質によって異なります。異常な状態に基づく数量差異、作業時間差異、能率差異などは非原価項目として処理されます。
一方、通常の原価差異は材料受入差異を除き、当年度の売上原価に賦課されるのが原則です。材料受入価格差異については、当年度の材料の払出高と期末在高に配賦され、期末在高については適当な種類群別に配賦されます。
また、予定価格等が不適当で比較的多額の原価差異が生じる場合は以下の通りに対応します。
- 個別原価計算では指図書別または科目別に処理
- 総合原価計算では科目別に処理
当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に配賦します。
実際原価計算のメリット

実際原価計算には以下のような重要なメリットがあります。
- 正確な原価が把握できる
- 収益性が向上する
- 問題点の早期発見ができる
それぞれ詳しく解説します。
正確な原価が把握できる
実際原価計算の大きなメリットは、製品やサービスの正確な原価を把握できる点です。各製品のコストを実際の数量や生産量に基づいて単位コスト化するため、1つの製品コストが正確に計算されます。製品の価格設定において実際のコストを反映でき、より実質的な価格設定が可能です。
また、製造工程で発生する直接材料費、直接労務費、製造間接費などのすべての原価要素を実際の発生額に基づいて集計するため、より現実に即した原価情報を得られます。この正確な原価情報は、財務諸表の作成や在庫評価など、会計上の重要な判断に欠かせません。
収益性が向上する
正確な原価情報に基づいて価格設定を行うと、製品ごとの適切な利益率を確保できます。標準原価では把握できない原価の変動や市場の実態を反映させられるため、より競争力のある価格設定が可能で、収益性の向上につながります。
実際の原価データを基に製品別の損益を「見える化」すれば、より効果的な利益管理を行うことが可能です。例えば、製品ごとの実際の利益率を把握すると、高収益製品への経営資源の集中や、低収益製品の改善・撤退の判断材料として活用できます。取引先との価格交渉においても、実際の原価データに基づく説得力のある提案ができます。
問題点の早期発見ができる
実際原価計算を通じて、製造工程における非効率な部分や予想以上にコストがかかっている工程を特定できます。これにより、原価の無駄を早期に発見し、適切な対策を立てられます。例えば、特定の工程で材料のロスが多い、作業時間が想定より長いといった問題点を具体的に把握し、改善活動につなげることが可能です。
また、部門別に原価を把握すると、各部門の管理責任を明確にし、より効果的な原価管理を実現できます。各部門の実際のコスト発生状況を詳細に分析すれば、部門ごとの業績評価や予算管理にも活用可能です。製造部門だけでなく、間接部門も含めた全社的な原価低減活動の推進に役立ちます。
継続的な実際原価の把握により、季節変動や市場環境の変化による原価への影響も明確です。これにより、将来の原価変動を予測し、事前に対策を立てられます。ただし、製品の原価を事後的にしか把握できない点や、データ収集と集計に時間と労力がかかる点には注意が必要です。
実際原価計算のデメリット

実際原価計算は正確な原価を把握できる一方で、以下のデメリットがあります。
- 計算の手間がかかる
- コストが増加する
- 予定配賦率の設定が難しい
ひとつずつ見ていきましょう。
計算の手間がかかる
実際原価計算は、製造工程で実際に発生した材料費、人件費、間接費など、すべての原価データを収集し集計する必要があります。特に複雑な製品の生産プロセスでは、データ収集と集計作業が煩雑かつ長時間に及ぶ場合があります。
例えば、多品種少量生産の製造現場では、製品ごとの作業時間の記録、使用材料の数量管理、製造間接費の配賦計算など、膨大なデータ処理が必要です。これらの作業に多くの時間を要するため、月次決算などのタイムリーな経営判断に必要な情報を提供することが難しくなります。
また、製品完成後でないと正確な原価が確定しないため、進行中の案件の収益性を把握するのも困難です。
コストが増加する
実際原価計算では、詳細なデータ収集と分析のために多くの人的リソースが必要です。また、正確なデータを収集・管理するためのシステムの導入や維持にもコストがかかります。特に、製造間接費の配賦計算や製品別原価の集計など、複雑な計算プロセスを管理するための人件費や設備投資が欠かせません。
実際原価を正確に把握するためには、生産現場での詳細な作業記録、材料の受払管理、間接費の配賦基準の設定など、さまざまな管理体制の整備が必要です。これらの体制を維持するためには、専門知識を持った人材の確保や教育訓練、システムの更新なども含めて、継続的なコスト負担が発生します。
予定配賦率の設定が難しい
製造間接費の配賦において、実際の操業度に基づいて配賦率を設定する必要がありますが、操業度の変動により製品単位あたりの原価が大きく変動してしまう問題があります。特に固定費の割合が高い製造環境において顕著な問題です。
例えば、生産量が少ない月は固定費の影響で単位原価が高くなり、生産量が多い月は単位原価が低くなるため、安定した原価管理が困難です。また、他製品の操業度の影響を受けて原価が変動するため、製品別の正確な収益性分析が難しくなります。
季節的な変動や特殊な要因による操業度の変化(設備のメンテナンス期間や大型連休など)に対して、適切な配賦率をどのように設定するかという課題もあります。これらの変動要因を考慮しながら、合理的な配賦率を設定するのは非常に複雑な作業になります。
実際原価計算の活用事例

実際原価計算は、さまざまな業種で活用されており、特に製造業や建設業において重要な役割を果たしています。
製造業における事例
製造業では、実際原価計算を通じて製品ごとの正確なコスト把握が可能です。例えば、自動車部品メーカーでは、直接材料費、直接労務費、製造間接費を製品別に集計します。この方法により、各部品の正確な製造原価を把握し、適切な価格設定や収益性を分析できます。
また、材料の受払を継続記録法で管理すれば、在庫管理の精度向上や横流しの防止にも役立ちます。
建設業における事例
建設業では、プロジェクトごとに異なる仕様や条件があるため、実際原価計算が特に重要です。建設会社は工事ごとに発生する直接材料費、直接労務費、直接経費を詳細に集計します。間接費も適切に配賦することで、工事案件ごとの正確な利益率を把握し、将来の見積精度の向上や価格交渉に活用できます。
実際原価計算を理解して業務に活かそう

実際原価計算は、製品の製造過程で実際に発生したコストを正確に把握し、企業の財務会計と原価管理に重要な役割を果たします。正確な原価情報に基づいて価格設定を行うと適切な利益率を確保でき、製品別の損益の「見える化」により効果的な経営判断が可能です。
また、実際原価計算と標準原価計算を併用すれば、より効果的な原価管理が実現できます。原価差異の分析を通じて、製造工程における非効率な部分や予想以上にコストがかかっている工程を特定し、適切な改善策を立てられます。
一方で、実際原価計算にはデータ収集と集計の手間、システム導入・維持のコスト、予定配賦率設定の難しさが課題です。課題を理解した上で、自社の状況に適した原価計算システムを構築し、経営判断や業務改善に活用することが重要です。
適切な原価管理は、企業の収益性向上と競争力強化につなげるために重要です。本記事の内容をよく理解して、業務に活かしてください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
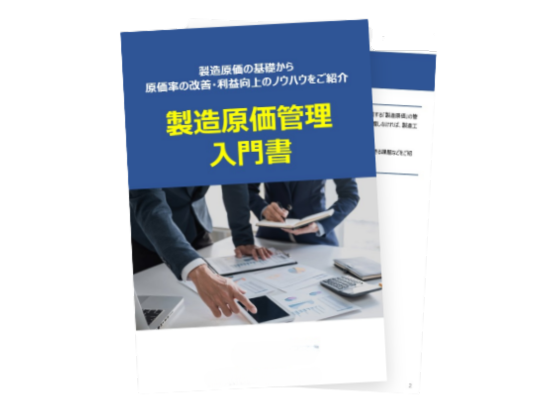
製造原価の基礎から 原価率の改善・利益向上のノウハウをご紹介
製造原価管理入門書