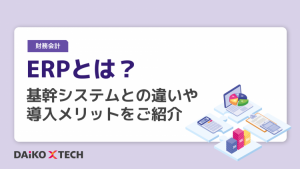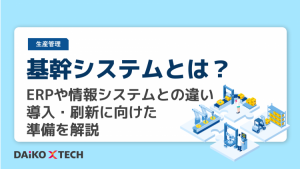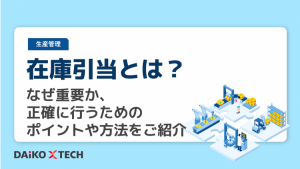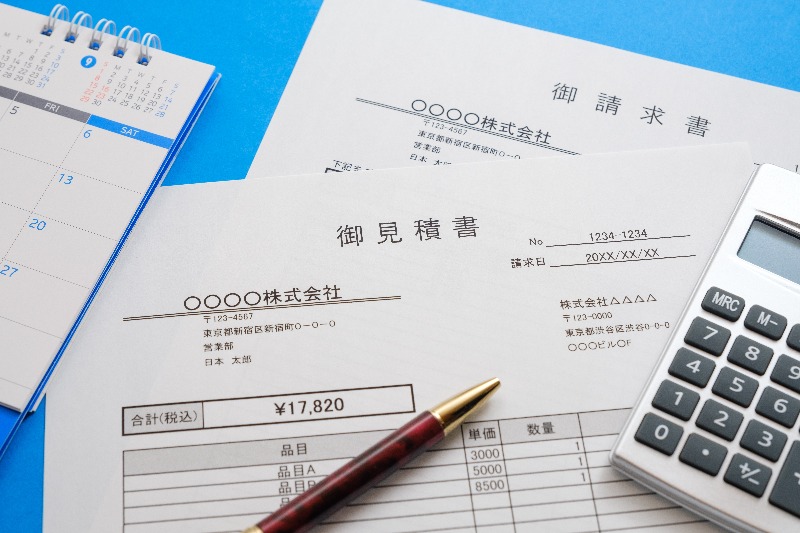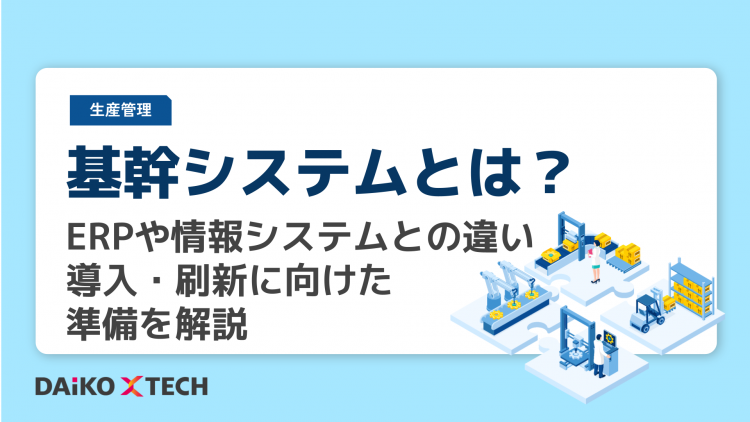
企業の基幹となる業務をシステム化し、効率化やミスの削減などを目指したものが「基幹システム」です。基幹システムは大企業を中心に導入されていますが、中小企業においても多大な効果が期待できます。今回は、基幹システムの基本的な特徴やERPとの違い、導入のメリットなどについてご紹介します。
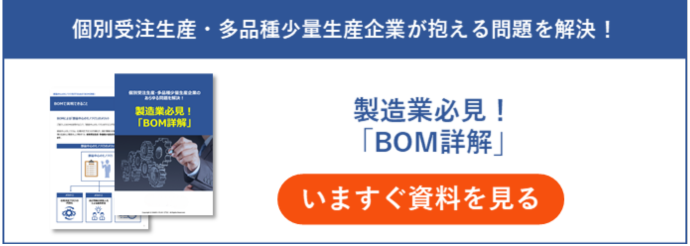
目次
基幹システムとは

基幹システムは、企業の基幹となる業務をコンピュータで管理しようとするシステムの総称です。基幹システムという決まった枠組みやパッケージがあるわけではなく、基幹システムというカテゴリの中に販売管理システムや購買管理システム、在庫管理システム、会計システム、人事給与システムなどが含まれています。
業種によって基幹とする業務は異なるため、基幹システムと一口に言っても、どの業種で使われているかによって変わります。例えば、会計システムや人事給与システムは多くの業種にとって基幹システムとなりますが、在庫を持たない業種にとって在庫管理システムは基幹システムではありません。また、製造業においては他の業種と違い、生産管理システムが基幹システムとなります。
どの基幹システムも業務の効率化を目指したもので、人力で行っていた業務をシステム化することで工数の短縮や人為的ミスの削減が可能です。
基盤システムとの違い
基盤システムとは、企業が業務を運用する際に使用するシステム全体の制御や最適化を図るためのシステムで、土台となるITインフラストラクチャ全体をサポートします。
基幹システムやその他のアプリケーションがスムーズに動作し、セキュリティが維持されるよう設計されており、「サーバー、ネットワークインフラ、OS、データベース、バックアップシステム」などが基盤システムに含まれます。あらゆるシステムやアプリケーションを制御し、安定したインフラ環境を整える役割を担うのが基盤システムです。
ERPとの違い
基幹システムと混同されやすいものとして、ERP(Enterprise Resource Planning)があります。「企業資源計画」と訳されるERPは、企業が保有する基幹システムといった複数の資源を1つに統合し、情報を一元管理することで経営分析に活かせます。これにより、どの部署からも共通の情報が参照できるようになります。
一方の基幹システムは、販売管理システムや生産管理システムとしてそれぞれが独立して稼働します。データを連携することでERPのように稼働させることは可能ですが、基本的には個々のシステムを指す言葉です。ERPは企業の業務全体をカバーする大規模なシステムとなるため、導入障壁を考えると基幹システムのほうが導入しやすいと言えます。
ERPの詳細は以下記事にまとめていますので、あわせてご覧ください。
情報系システムとの違い
基幹システムに対して、情報系システムという言葉が使われることがあります。言葉だけでは分かりにくいですが、基幹システムは基幹であるため「これがなければ困る」というものである一方、情報系システムは「なくても良いがあれば便利」というものです。言い換えれば、基幹システムはトラブルで停止すると非常に困りますが、情報系システムは停止しても基幹システムと比べると影響は少ないです。
情報系システムには、例えばスケジュール管理システムやグループウェア、メールシステムが含まれます。導入することで業務効率化が図れる点は同じですが、基幹システムと比べると業務への影響度が低いため、導入障壁は基幹システムよりも下がります。
| 項目 | 基幹システム | 情報系システム |
| 定義 | 組織の主要な業務プロセスをサポートし、管理するために設計されたシステム | 情報に関連する一般的な業務プロセスをサポートするシステム |
| 主な焦点 | 主要な業務プロセスとその効率的な実行 | 情報の処理、保存、伝達、アクセス、分析など情報のライフサイクル全般 |
| 重要度 | 高い トラブルで停止すると被害は甚大に |
低い トラブルで停止しても、基幹システムと比べて影響は少ない |
| 例 | 販売管理システムや購買管理システム、在庫管理システム、会計システム、人事給与システムなど | スケジュール管理システムやグループウェア、メールシステムなど |
業務システムとの違い
基幹システムと業務システムの大きな違いは、企業活動への影響度です。
基幹システムは企業の経営を支える根幹的な業務(販売管理、在庫管理、生産管理、財務会計など)を担うため、システムが停止すると企業活動全体が停止してしまいます。一方、業務システムは特定の業務や部門をサポートするためのシステムで、停止しても代替手段で業務を継続することが可能です。
また、適用範囲にも違いがあります。基幹システムは企業経営に直結する特定の重要業務に特化しているのに対し、業務システムはより広範な業務をカバーし、特定の部門や業務を包括的にサポートするものです。
例えば、基幹システムには会計システムや在庫管理システム、製造プロセス管理システムなどがあります。一方、業務システムには人事給与システム、コミュニケーションツール、マーケティングツールなどが含まれます。
つまり、基幹システムが担っているのは、企業の存続に関わる重要度の高い業務です。基幹システムは代替が効かない性質を持つのに対し、業務システムは企業活動を円滑にするための補助的な役割を果たし、代替手段が存在するのが特徴です。
基幹システムの主な種類

ここでは基幹システムの機能について、種類別にご紹介します。
| 種類 | 中分類 | 詳細 |
| 生産管理システム | ー | 生産計画、製造プロセス管理、品質管理、資材調達など、製品生産に関連する業務プロセスを効率化し、追跡 |
| 販売管理システム | 見積管理 | 見積の作成 |
| 受注管理 | 注文の受け入れと処理 | |
| 売上管理 | 売上記録と請求書発行 | |
| 購買管理システム | 発注管理 | 発注の処理と納品スケジュールの管理 |
| 出荷管理 | 出荷・納品の管理 | |
| 在庫管理システム | 在庫検索 | 製品や管理場所の在庫数を管理し、検索可能に |
| 棚卸 | データと現物の数量の管理 | |
| 在庫調整 | 抱える在庫を出荷量に合わせて調整、最適化 | |
| 会計システム | ー | 取引情報の管理および経営最適化のための財務情報の管理 |
| 人事給与システム | ー | 採用管理や人事評価、給与計算など、従業員の一連の人事情報を管理、人的資源の活用、最適化 |
| 労務管理システム | ー | 勤務スケジュールの作成、労働時間記録、有給休暇管理など、労働者の勤務と給与に関連する業務を効率的に管理 |
生産管理システム
生産計画、製造プロセス管理、品質管理、資材調達など、製品生産に関連する業務プロセスを効率化し、追跡するためのシステムです。
販売管理システム
見積管理、受注管理、売上管理など、販売に関連する業務を処理・管理するためのシステムです。
購買管理システム
発注管理や出荷管理など、組織の発注から支払いまでの購買に関する一連の業務を管理・効率化するためのシステムです。
在庫管理システム
在庫の過不足をなくすために、正確な在庫品目と数量を追跡し、在庫の受け入れ、出荷、品質管理、棚卸などを把握・管理するためのシステムです。
会計システム
取引情報や財務情報など、企業のお金のやりとりを管理するシステムです。財務諸表を作成して企業の財務状況を明確化し、経営判断に必要な情報を管理するなどの機能があります。会計システムだけでなく、販売や人事給与のシステムと連携できるものもあり、業務効率化につなげることができます。 <!–業務連携を可能にする会計システムは下記URLからご覧いただけます。
人事給与システム
人事給与システムとは、採用管理や人事評価、給与計算など、従業員の採用から異動、退職までの一連の人事情報を管理するためのシステムです。近年、この管理システムを導入し、人的資源を活用した経営戦略を進める企業が増えており、電子化することで業務効率化やコスト削減を実現しています。システムの詳細は下記からご覧ください。
労務管理システム
勤務スケジュールの作成、労働時間記録、有給休暇管理など、労働者の勤務と給与に関連する業務を効率的に管理するためのシステムです。
基幹システム導入の3つのメリット

基幹システムを導入することで得られるメリットは、大きく以下の3つにまとめられます。
業務の効率化
基幹システム導入における大きなメリットの1つが、業務の効率化です。例えば在庫管理システムであれば数値をコンピュータに入力するだけで入出庫の管理ができるようになり、手間が大幅に削減されます。購買管理システムと連携できれば、仕入れがあったときに自動的に在庫管理システムの数値も更新されます。
業務の標準化
業務効率化により、業務内容がシンプルになると、だれが作業しても同じ品質の成果物を生み出せます。また、新人が覚えるべき内容も少なくなり、新人とベテランの質の差を小さくすることが可能です。これにより、人員の異動や退職があっても業務の質を維持しやすくなります。
経営状況の可視化
基幹システムを導入すれば、購買や在庫、生産、販売といった情報がデータで閲覧できるようになるため、経営状況の可視化につながります。基幹システムではリアルタイムに情報を更新・共有することが可能なため、状況に変化があったときにも素早い経営判断につながります。
基幹システム導入の2つのデメリット

基幹システムは多くのメリットがある一方で、導入にあたっては課題やリスクがあります。システム導入を成功させるためには、以下の2つのデメリットを十分に理解し、適切な対策を実行しなければなりません。
満足な費用対効果が得られない場合がある
基幹システムの導入には、多額の導入費用や運用管理コストが発生します。業務効率化によるコスト削減や人件費削減といったメリットが、基幹システムの導入費用に見合わない可能性があります。
また、企業の業務内容に適合しないシステムを選択してしまうと使いづらさから十分に活用されず、導入だけで終わってしまうケースも少なくありません。
このリスクを回避するためには、導入の目的や必要性を明確にし、自社に最適なシステムを慎重に選定することが重要です。システム導入後の社員教育や研修体制の整備、マニュアルの作成など、社員がスムーズにシステムを使いこなせるような支援体制を整えるのも必要不可欠です。
システムトラブルが業務に影響する場合がある
基幹システムは企業の生産管理や受発注管理など、重要な業務を担うシステムであるため、トラブルが発生した際の影響が極めて大きくなります。従来であれば各部門の管理者が人的作業で対応できていたトラブルも、システムへの依存度が高まることで迅速な対応が難しくなる可能性があります。
そのため、導入時にはセキュリティ管理体制の構築や、トラブル発生時の対応手順の整備など、万全の危機管理体制を整えておくことが欠かせません。システムの安定稼働を維持するための定期的なメンテナンスや、バックアップ体制の確立も重要な検討事項です。
基幹システムのタイプと費用相場

基幹システムは便利なシステムですが、現在の業務フローをデジタルに置き換える作業が必要なため、気軽に導入できるものではありません。また、いくつかのシステムがパッケージになっているタイプや業種に特化したタイプ、ERPなど、システム導入にもさまざまな選択肢があるため自社の環境と改善したい課題に適したシステムをよく吟味することが大切です。
自社に合った基幹システムが選定できるよう、次章では、基幹システムの製品タイプと特徴、費用をご紹介します。
オンプレミス型
自社でサーバーを購入し、サーバーに基幹システムをインストールして使用するタイプの製品です。
- 良い点:カスタマイズ性があり、機能が充実している
-
- 組織の特定の要件に合わせて高度にカスタマイズ可能
- 悪い点:初期費用が高く、管理やメンテナンスが必要
-
-
- サーバーの購入、設置、メンテナンス、セキュリティ管理に責任が伴う
- 導入時の初期コストが高く、サーバー、ライセンス、専門家の雇用、設備の保守に多くの資金とリソースが必要
-
費用:
-
- 初期費用:1,000万円~
- 月額費用:数万円~
クラウド型
クラウドプロバイダーを提供する基幹システムを、インターネットを介して使用するタイプの製品です。
- 良い点:柔軟性およびコスト効率が高い
-
- 導入時の初期コストが比較的低く、サーバーの購入やメンテナンスが不要
- 必要に応じてスケーリングができ、リソースを柔軟に調整できる
-
- 悪い点:カスタマイズ性が低く、定着に時間がかかる
- クラウド型のため、機能カスタマイズできない製品がほとんど
- システムに業務を合わせる必要があるため、現場のシステム定着までに時間がかかる
- 悪い点:カスタマイズ性が低く、定着に時間がかかる
費用:
-
- 初期費用:0円~
- 月額費用:1万円~
オンプレミス型、クラウド型双方のメリット・デメリットを比較し、自社に合っているタイプを導入しましょう。高度なカスタマイズが必要なのであればオンプレミス型、早く安く導入したいのであればクラウド型がおすすめです。
また、両方のアプローチを組み合わせてハイブリッドな基幹システム環境を採用することも可能です。
基幹システムの導入に必要な期間

基幹システムの導入期間は、プロジェクトの複雑性やスケール、選択したシステムのタイプなどによって異なります。一般的に、基幹システムの導入には数ヶ月から数年かかることがあります。
以下は一般的な導入期間の目安です。
カスタマイズ可能な製品:
-
- ノンカスタマイズで最低3ヶ月、カスタマイズで通常6ヶ月以上の導入期間が掛かります。
小規模な組織:
-
- 小規模の組織やプロジェクトでは、1年未満の導入期間が一般的です。
大規模な組織:
-
- 大規模な組織やプロジェクトでは、1年以上の導入期間が一般的です。複雑なプロセスの統合、大量のデータ移行、セキュリティ要件への適合などが必要なため、長い時間がかかります。
クラウド型システム:
- クラウド型基幹システムは通常、オンプレミス型よりも迅速な導入が可能で、数カ月から1年以内で運用を開始できます。
基幹システム導入の流れと構築方法

基幹システムの導入は、以下のステップで行われます。
①要件定義(導入目的の整理)
成果を最大化するために、まずは組織が何を達成したいのかを明確にすることが重要です。導入目的やゴールを明確にし、業務システムに必要な機能・仕様を決定します。導入目的やゴールを正確に把握し、これまで手作業だった業務をどのようにシステム化するのか、細かく的確にイメージしましょう。
システムの全体像が把握できたら、導入目的や業務フローにおいて取りこぼしが無いかを確認します。すべてがシステムとして動くように、機能の一つひとつを細分化して要件をまとめます。
場合によっては、業務プロセス自体を見直し、より効率的な業務プロセスに修正することも必要です。また、要求内容の全てをシステム化できるとは限らないため、できないことは要件定義の時点で切り分けをしておきます。
この作業は、システム化の成敗を分ける非常に重要な部分ですので、社内で時間をかけて行いましょう。売上が10億を超える企業であれば、ITコンサルタントに入ってもらい要件を整理してもらうとよいでしょう。
②提案依頼書の作成と依頼
要件定義に基づき、システムプロバイダーにRFPという提案依頼書を作成し、提案を求めます。提案依頼書には要件、予算、スケジュール、提供されるサービス、契約条件などが含まれます。複数のベンダーに提案依頼書を送付し、提案を受け取りましょう。
③システムの選定
提案依頼書の作成には専門知識を必要とするため、IT経験者でないと作成が困難です。IT経験者がいない場合は、最低限パワーポイントやExcelで課題や要件を整理してから提案依頼するとより精度の高い提案をもらえるようになります。曖昧な要件だと見積金額も高くなるので注意してください。
各ベンダーの提案を受け取ったら、自社の要件にマッチしているか評価をし、最適なシステムプロバイダーを選定します。選定の際には提案の適合性、コスト、信頼性、サポート、実績などを考慮します。
評価する主なポイントとしては以下になります。
- 機能 スケジュール 費用 契約内容、支払条件 システム的な誓約 会社情報(実績や会社規模) プロジェクトマネージャー(経験豊富か)
④実装・テスト
システムの実装プロセスでは、システムを設定し、データを移行、不具合がないかテストを行います。業務プロセスの処理やデータ連携に問題がないか確認し、問題が発見された場合、修正と再テストを繰り返します。
⑤運用・保守
システムが導入されると、運用と保守の段階に進みます。社員が新しいシステムに慣れるために、教育やトレーニングをしていきます。また運用開始後に、不具合や新機能の必要性に気づく場合があります。その場合は、定期的に保守・修正を行っていきましょう。
製造業の基幹システム選びのポイントは?

プロジェクトの成功基盤を築く重要なステップです。組織の要件と目標に最も合致する基幹システムを選択しましょう。先ほどご紹介した自社に合ったシステムを選ぶこと以外の選定ポイントを解説します。
使いやすいか
基幹システムはユーザーにとって使いやすい必要があります。社員のトレーニング期間を最小限に抑え、生産性を向上させるためにも、ユーザビリティが高いシステムを選択しましょう。インターフェースである作業画面や操作性は、デモやユーザーテストで確認することができます。
使いづらいシステムを選んでしまった場合、社員の定着までに時間がかかり、社内からもストレスや不満の声が上がることも少なくありません。
安定稼働するためのサポート体制が十分か
基幹システムは長期間にわたって安定的に運用される必要があります。テクニカルサポート、保守、アップデート、トラブルシューティングなど、安定稼働するためのサポート体制や、プロバイダーの対応能力を確認しましょう。他社の評判なども参考にするとよいでしょう。
強固なセキュリティか
基幹システムの多くは、自社の社員や顧客の個人情報、自社の機密情報など、重要な情報を取り扱っています。情報漏えいによる企業ダメージは甚大ですから、強固なセキュリティを実現しているシステムを選ぶ必要があります。プロバイダーのセキュリティポリシー、データ暗号化、アクセス制御、セキュリティ監査などを評価し、コンプライアンスに適合しているか確認しましょう。
自社の業務内容に適しているか
基幹システムを選定する際は、自社の業務内容や特性に適したシステムであるかどうかを慎重に検討する必要があります。例えば、生産管理システムを導入する場合、システムがカバーできる業務範囲と生産方式の2つの観点から評価することが重要です。
システムの業務範囲については、自社が求める業務内容をどの程度カバーできるのかを確認します。現状抱えている業務課題を解決できるだけの機能が備わっているかどうかを詳細に検討しなければなりません。
生産方式の観点では、システムが得意とする生産方式と自社の生産方式が合致しているかを見極めます。個別受注生産や多品種少量生産を行っている企業なのか、あるいは繰返生産や少品種大量生産を行っている企業なのかによって、最適なシステムは異なってきます。複数の生産方式を採用している場合は、それらに柔軟に対応できるシステムを選ばなければなりません。
このように、自社の業務特性や運用方法を十分に理解したうえで、それらに適合するシステムの選定が導入後の効果的な活用につながります。
既存システムと連携できるか
基幹システムを新規導入する際は、社内の既存システムとの連携可能性を検討することが重要です。例えば、生産管理システムを導入する場合、すでに運用している会計システムとの連携が可能かどうかを確認する必要があります。
両システムを連携させて統合基幹業務システムとして活用できれば、生産管理システムで蓄積された情報を会計業務にも活用できるようになり、業務効率が大きく向上します。新規システムと既存システムを効果的に連携させると、より広範囲な業務改善効果を生み出すことが可能です。
システム選定時には単体での機能だけで判断しないでください。既存システムとの連携性や連携によって得られる具体的なメリットについても十分に検討することが、投資効果を最大化するポイントです。
基幹システムの導入時に気を付けるべきポイント

基幹システムは企業の重要な業務を担う基盤となるため、導入には慎重な計画と準備が必要です。システムの安定稼働を確保し、円滑な運用を実現するために、以下の2つのポイントに注意してください。
リスク管理を徹底する
基幹システムの導入にはさまざまなリスクが伴うため、事前の対策が不可欠です。特に重要なのは、データ移行時のデータ損失リスクとシステムの互換性に関するリスクです。データ移行の際にはバックアップを取り、システムの互換性については導入前に十分な動作確認を行わなければなりません。
これらのリスクに対しては、事前に潜在的な問題を洗い出し、それぞれに対する具体的な対策計画を立てておく必要があります。また、予期せぬ問題が発生した際にも迅速に対応できるよう、計画には柔軟性を持たせることが求められます。
運用の体制を整えておく
導入後の円滑な運用のためには、適切なトレーニングとサポート体制の構築が重要です。まず、従業員に対して新システムの操作方法や導入によるメリットを詳しく説明し、研修を実施する必要があります。
また、導入後も継続的なサポート体制を整え、現場からのフィードバックを常に得られる環境を整備することが大切です。新しいシステムは導入して終わりではなく、運用しながら最適化を図っていかなければなりません。このような体制を整えておけば、より効果的な生産性の向上を実現できます。
基幹システムは刷新が必要?

基幹システムを導入して業務効率化を実現した企業であっても、その後の対応を怠ると新たな課題に直面することになります。
経済産業省の調査により、既存の基幹システムを更改しないままだと、2025年以降の経済損失は年間最大12兆円にのぼる可能性があります。基幹システムを長年使用し続けることで、レガシー化が進んで企業活動にさまざまなリスクをもたらすため、適切なタイミングでの刷新が必要不可欠です。
基幹システムの刷新が必要な理由
基幹システムを刷新すると、企業は複数のメリットを得られます。
企業のデータを一元管理できるようになり、必要な情報への素早いアクセスと迅速な意思決定が可能になります。最新の技術やシステムに対応できるようになり、IoTやAIなどの新技術を活用した経営も実現可能です。
また、システムの一元化により運用・保守コストや社員教育にかかるコストを大幅に削減できます。
基幹システムを刷新しないリスク
老朽化した基幹システムを刷新せずに使用し続けると、重大な問題が発生する可能性があります。
一つはシステムのパフォーマンス低下により業務が非効率化し、生産性が低下する点です。次に、度重なるカスタマイズによりシステムが複雑化し、ブラックボックス化するリスクも高まります。
さらに、ベンダーのサポート終了によりセキュリティ対策が困難になり、情報漏洩のリスクも増加します。
基幹システム刷新におすすめのタイミング
基幹システムの刷新を検討すべき主なタイミングは3つあります。
1つ目は事業拡大に伴ってシステム対応が必要になった時です。古いシステムでは事業拡大に対応できず、パフォーマンスの低下やセキュリティの脆弱性が問題になります。
2つ目はシステムのブラックボックス化が進行した時です。システムの全容を把握できる人材が限られ、不具合や障害への対応が困難になります。
3つ目は保守契約やサポートの終了時期が近づいた時です。一般的に導入から5年程度で保守契約が終了するため、その前に刷新を検討しなければなりません。
基幹システムの刷新方法

基幹システムを刷新する際には、企業の状況や目的に応じて3つの方法から選択できます。それぞれの特徴を理解し、自社に最適な方法を選ぶことが重要です。
リビルド(再構築)
リビルドは、業務を大幅に見直したい場合に適した方法です。システムを一から作り直すため、レガシーシステムからの完全な脱却が可能です。
ただし、システム構築に必要な有識者の確保が成功の鍵になり、刷新方法の中では最も難易度が高いとされています。新しい業務プロセスに合わせて基幹システムを完全に作り直せる一方で、専門知識を持った人材の確保が必要です。
マイグレーション(移行・リライト)
マイグレーションは、既存のシステムを活かしながら新環境への移行を行う方法です。現状のシステム課題に対して、リスクやコストを抑えた解決を図れます。
また、ベースとなるシステムを活用するため、不具合の発生リスクや刷新にかかる時間、現場業務への負担を軽減できます。さらに、新システムを運用する際のオペレーションミスを防ぎやすく、安全性に優れているのが特徴です。有識者が少なくても実行できる点も大きなメリットです。
リホスト
リホストは、予算が限られている場合や、保守性・生産性の向上を主な目的としない場合に選択される方法です。改修やバージョンアップのみの基盤変更、保守、運用を行うため、業務への影響は最小限に抑えられます。
ただし、大幅な改善を先延ばしにすることになるため、将来的な課題を残す可能性がある点に注意が必要です。
製造業でも基幹システムの導入・刷新は必要

基幹システムは長らく大企業を中心に使用されてきましたが、安価に導入できるクラウド型の基幹システムが増加してきていることもあり、中小企業でも導入しやすくなっています。上手く導入できれば業種の効率化、標準化、経営状況の可視化などさまざまなメリットがあるため、ぜひ最適なシステムを探してみてください。
大興電子通信ではさまざまな業種・部門に合わせた基幹システムをご用意しております。ソリューションマップからも、「部門・業務」「業種」「課題・目的」別でも検索できますので、下記ページより自社の課題に合った基幹システムを探してみてください。
ビジネスの課題をITの力で解決する
DAIKO XTECHが提供するソリューション一覧
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
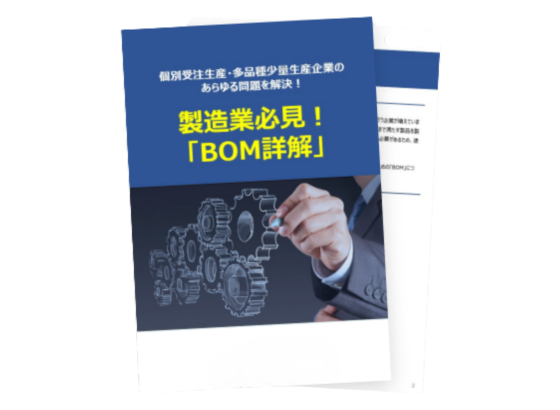
個別受注生産・多品種少量生産企業の あらゆる問題を解決!
製造業必見!「BOM詳解」

- この記事を監修した人
- 入社後15年間、長野支店にてシステムエンジニアとして活動。
運送業、倉庫業のお客さまを中心に担当し、業務システム構築からインフラ環境構築等の経験を積む。
その後、製造業のお客さまも担当し、rBOM導入のプロジェクトにも関わるように。
16年目に現部門に異動し、rBOM全国支援の担当者となる。
現在はrBOMだけではなく、製造業全般のソリューション提案を手掛けている。
料理が趣味、これからお菓子作りにも挑戦しようか迷っている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部 - 田幸 義則