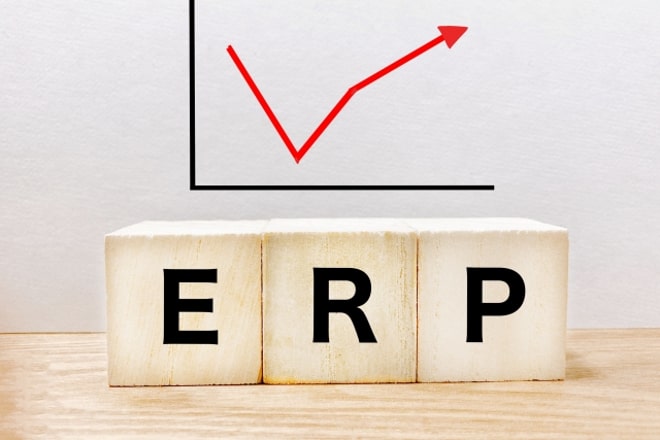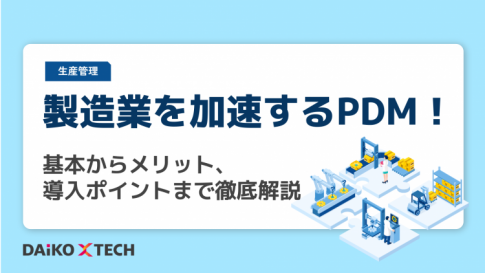製造業におけるコストダウンにはどのような戦術があるでしょうか?製造業において重要な要素であるQCDの一つであるコスト。
コストの考え方や、コストダウンのためにできることを項目別に解説していきます。
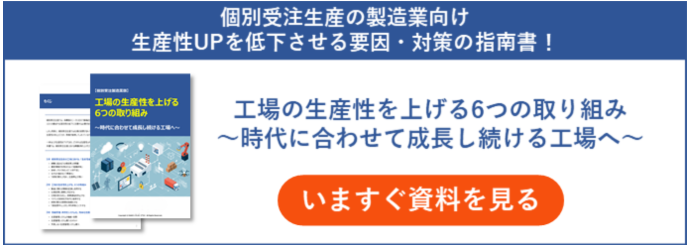
目次
製造業におけるコストの種類
 製造業ではさまざまなコストがかかります。
製造業ではさまざまなコストがかかります。
コスト削減を効率よく効果的に進めていくためには、まずどのようなコストがあるのか、削減しやすいコスト・削減しづらいコストについて理解してから進めていきましょう。
固定費と変動費
コストを大きく二つに分けると、固定費と変動費に分かれます。
固定費とは、売上や生産量の増減とはかかわらず毎月一定かかるコストのことです。
変動費とは、売上や生産量に比例して増減するコストのことです。
まず、自社でかかるコストを固定費・変動費のどちらなのか区分けしてみましょう。
以下に一般的な製造業のコストをご紹介します。
固定費の主な例は以下の通りです。
- 人件費
- 研究費
- 減価償却費
- 地代家賃
- 水道光熱費
- 通信費
変動費の主な例は以下の通りです。
- 原材料費
- 燃料費
- 外注費
さらに、製造に必要なコストは主に材料費・労務費・経費の3つに分けられます。
製造業では業種にもよりますが、構成比としては材料費>労務費≧経費の順番です。
削減しやすいコスト、削減しづらいコスト
次に、削減しやすいコストと削減しづらいコストについてご紹介します。
製造業においては、まずは生産に直接影響を及ぼさないコストから削減を進めるのが良いです。
削減しやすいコストは、経費のような製造に直接かかわらないコストです。
- 水道光熱費
- 通信費
- 消耗品等の経費
削減しづらいコストは、材料費・労務費のような製造に直接かかわるコストです。
- 人件費
- 研究費
- 原材料費
特に人件費・研究費・原材料費のコストについては、安易に削減してしまうと品質や生産体制に影響が出てしまう可能性があるので、慎重に対応していく必要があります。
また、人件費や原材料費については設計や生産計画段階で7〜8割程度は決定してしまうため、最初の分析が大変重要です。
製造業におけるコストの考え方
 次に、製造業におけるコストの考え方についてご説明します。
次に、製造業におけるコストの考え方についてご説明します。
コストは製造業においてどのように位置付けられ、どういう視点で削減していくべきかを見ていきましょう。
QCDのバランスを考える
まず、製造業にはQCDという欠かせない3要素があります。
Q:Quality(品質)
C:Cost(コスト)
D:Delivery(納期)
QCDの中で製造業の企業が重視しなければならないのは、品質です。
どんなに安くて早く納品される製品であったとしても、品質の悪い製品を生産すると顧客からの信用を得ることはできません。
次に、コストと納期は、顧客や自社の現在の状況に応じて優先度を判断していく必要があります。
また、QCDはどの項目も無視できない重要な要素ですが、バランスを考えることが大変重要です。
コストばかりを優先すると、品質の良い製品を作ることはできません。
納期ばかりを気にすると、生産に人員をかけ過ぎてコストが膨らみすぎる可能性があります。
また、品質を重視し過ぎて納期に間に合わなくなったり、コストがかかり過ぎて利益が上がらなくなったりすることもあります。
QCDは相関関係にあることをしっかりと理解しておきましょう。
QCDとは?管理手法や製造業における重要性、バランスの取り方を解説
7つのムダから考える
次に、コストを削減するための考え方として、7つのムダの視点をご紹介します。
トヨタ生産方式で使われる言葉ですが、製造現場でのムダな行為を以下のように説明しています。
- 加工のムダ
- 在庫のムダ
- 造りすぎのムダ
- 手待ちのムダ
- 動作のムダ
- 運搬のムダ
- 不良、手直しのムダ
7つのムダの観点で現場内のコスト削減を進めることも大切です。
ひとつずつ確認していきましょう。
加工のムダ
加工のムダとは、必要のない加工や検査が行われていることです。
作業標準を都度見直す、作業手順書を改訂するといった作業を行うことで無駄な作業を削減できます。
在庫のムダ
在庫のムダとは、必要以上の材料や商品在庫を保管してしまうことです。
「不測の事態が起きたときのために」などと、製造現場の担当者が肌感覚で保管してしまうこともあります。
結果的に長く使われず廃棄処分となってしまうとコストとなってしまいます。
特に、在庫管理に関しては作業を行う担当者の感覚に任せるのではなく、生産管理として在庫をデータ管理するのもコスト削減の施策のひとつです。
造りすぎのムダ
造りすぎのムダは製品や仕掛品を多く作りすぎてしまうことです。
生産管理や生産計画がしっかり機能しておらず、材料があるだけ造ってしまうような状態はすぐに解消しましょう。
在庫管理や生産計画が製造部門までしっかり行き渡っておらず、部署別の管理となっていることが原因の可能性があります。
生産計画から製造・出荷に至るまで一貫して管理できるようにシステム化を進めていくことが造りすぎのムダを解消する近道です。
手待ちのムダ
手待ちのムダとは、製造部門の作業者が行う作業がなくなったり、機械のチョコ停・ドカ停などにより、待ちの状態になっていることを言います。
製造部門の人員はできる限り組みつけや加工などの価値作業を行わなければなりません。
行う作業がなくなったなど単なる手待ちが多い場合には、作業時間や人員配置の見直しが必要です。
しかし機械のチョコ停が頻繁に起きて作業が止まっていることが多いような場合には、機械の点検作業やメンテナンス自体を管理していくことも重要です。
動作のムダ
動作のムダとは、しゃがむ作業や拾う作業、必要な道具を探す作業など価値作業を行うためではあるものの、動作のムダが多い状態を言います。
作業を行うにあたり、使う道具は手を伸ばして取れる範囲に配置するなどの工夫が必要です。
具体的には、
- すべての道具が80cm以内の手が届きやすい場所にある
- 作業は脇の下〜腰までの範囲で行う
の状態がベストです。
コスト削減の観点でいうと、動作のムダの改善を通じて不要な器具を整理したり、発注する数量を削減してコスト削減につながります。
運搬のムダ
運搬のムダとは、後工程へ製品を運んだり、材料を運ぶ際に必要以上に手間や時間がかかってしまっている状態を言います。
現場内のレイアウトを変えることは簡単に取り組めることではありません。
しかし、生産計画や各工程の作業をしっかり工程間・部署間で共有すれば少しでも運搬距離を短くして、工程間の運搬のための梱包のムダも改善が期待できます。
梱包のムダを見直すこともコスト削減につながります。
不良・手直しのムダ
不良・手直しのムダは大きくコストを圧迫します。
納品後の顧客クレームによる不良・手直しはもちろん、工程間や最終検査で不良が見つかることも無くしていかなければなりません。
不良品で破棄処分となれば人件費だけでなく材料費・水道光熱費などの損失だけでなく、売上も上がりません。
作業標準の見直しや品質検査の精度向上とともに、工程間の情報共有も進めていきましょう。
4M視点で考える
4Mとは、品質管理を行う上で大切な視点です。コストについても4M視点で考えていくことができます。
4Mとは、Man(人)・Material(材料)・Machine(機械)・Method(方法)のことです。
それぞれについて、まず着目したい課題を決めて、要因を突き止めていきます。
|
Man(人) |
作業者の経験不足や伝達不足の問題 |
|
Material(材料) |
部品や材料の問題 |
|
Machine(機械) |
機械の故障や経年劣化の問題 |
|
Method(方法) |
手順や方法の問題 |
4Mが変わったときが大きな変化点とも言われています。
ミスが起こりやすいだけでなく、課題が見えてくるポイントでもあるため、4Mの視点でコストを考えてみるのも重要です。
製造業のコストダウン戦術
 次に、コストダウン戦術をご紹介します。
次に、コストダウン戦術をご紹介します。
コストダウンのためだからと言って初めから製造にかかわる部分を削減するのではなく、削減しやすいコストから削減を進めていきます。
さらに、直接費・間接費の観点で進めていくことも重要です。
直接費:製造に直接的に影響する費用
間接費:製造にかかわらず企業活動をしていればかかる費用
まずは間接費からコストダウンの取り組みを行っていきます。
経費のコストダウン戦術
まずは、生産体制に大きく影響しない経費の部分からコストダウンを進めていきます。
経費にかかわるコストダウンは手軽に取り組めるものも多く、即効性のあるコストダウン戦術が多いのが特長です。
水道光熱費
経費の中でも、削減に取りかかりやすいコストです。
電球をLEDに変えたり、使用電気量に応じてプランの見直しを行います。
水道やガス代に関しても契約プランの見直しができる場合は積極的に行います。
消耗品費
消耗品費についても同じようにコストを削減しやすい項目です。
文房具や印刷用の紙代、インクカートリッジ代など事務用品だけでなく、現場での梱包資材についても、よりコストのかからない資材に変更を検討します。
紙ベースの資料が多い場合には、ペーパーレス化を進めていくのも良い手段です。
ただし、製造に必要な消耗品まで削りすぎないように気をつけなければなりません。
通信費
光熱費同様、使用量に応じた料金プランに変更するだけでなく、スマートフォンやタブレットの契約台数・ブランドの見直しなども必要に応じて行っていきます。
設備・システム費
設備やシステム費も見直すべき項目です。
古くなった設備はメンテナンスの回数が増えたり、チョコ停が頻発するなど生産性を下げている可能性があります。
また、システム費についても、長年使用しているシステムだと技術のアップデートが進んでいないこともあり得ます。
材料費のコストダウン戦術
次に、材料費にまつわるコストダウン戦術をご説明します。
材料費は製造業にまつわるコストの中で構成比が高い項目です。
真っ先に取り組むべき課題ですが、生産活動に影響が出てしまうと顧客への納品の遅れや重大な品質問題へつながる恐れがあります。
材料費に関しては設計時の試算も重要ですが、製造段階まできている製品に関する材料であれば生産計画に影響のないように慎重に行いましょう。
購買部門でのデータ分析
購買部門で材料費に関するデータ分析を進めていきます。
もし購買データがExcelでの履歴保管やPDF、紙ベースの見積でしか保管されていない場合には、適切なデータ解析をするためにもシステム導入によるデータ化も検討します。
分析手法には次のような種類があります。
|
市場分析 |
市場では材料や部品が大体どれくらいの価格で流通しているのかの分析を行う。 併せて物価変動の動向も把握する。 |
|
ABC分析 |
主に在庫管理で使われる手法。 部品や材料ごとに使用頻度・数量などのデータを基に A(重要)B(中程度の重要性)C(重要度が低い)と評価をつけていく。 |
|
回帰分析 |
結果に対してどのような要因があり導き出されたのかを分析する手法。 すでに価格が決まっているものでも、どのような要因で決められたことなのかを分析する。 |
|
クラスター分析 |
個々のデータを類似点別に分けて分析する手法。 仕入先の地域や納期・品質・価格といった観点で分析する。 |
分析後の戦術
分析の結果、ある材料のコストをもっと削減できると分析ができれば、購買部門が主導でコストダウンの検討を行います。
ただ、やみくもな価格交渉は仕入先を苦しめてしまうことにもつながります。
まずは以下のような取り組みを行います。
- 必要な材料を適正数量発注するように修正する
- 過剰なサービス要求によるコスト増があれば調整する
- 適正在庫数と使用のタイミングを把握し、ロット発注でコストを下げる
- 仕入先を絞り、発注数を多くしてボリュームディスカウント交渉をする
まずは自社で行える改善や修正を行った上で価格交渉を行います。
もし購買部門が経験や勘によって価格交渉を行っているような場合は、購買データをシステム化してデータの分析をするだけでも適正価格・適正在庫の把握によるコストダウンが期待できます。
労務費のコストダウン
労務費のコストダウンは手を出しづらい分野です。
安易に人件費をカットするために解雇や早期退職募集を行うと、増産体制になった際に弊害が出る可能性があります。
慌てて人を雇ったとしても技術力が追いつかず、品質や納期にまで影響を及ぼしてしまうリスクもあるでしょう。
しかし、少子高齢化の影響による労働人口の減少を考慮しても、職人の勘と経験に頼った技術をデータ化し、工場全体をIT化していく必要があります。
以下のような取り組みを行えば、すぐに効果が出ることは難しくても長期的に見て労務費を削減していくことができます。
eラーニングやVRでの技術トレーニングの導入
OJTでの技術習得が主である製造業の現場は多く存在します。
しかし、OJTでは教える立場の人間・教わる立場の人間の少なくとも2人分の労務費を価値作業から外すことでムダにしてしまっている側面もあります。
必要な知識を動画として残してeラーニング化したり、技術習得をVRで学習できれば、指導者の労務費削減だけでなく、企業の財産として技術を残すことができます。
併せて、業務マニュアルの整備を行うことも重要です。
また、動画として技術者の動きを保管しておくと、動作のムダを検証したり、作業標準の見直しにも役立つことが期待できます。
多能工化を進める
多能工化は、常に同じ製品を一定数作るような企業ではなく、繁忙期と閑散期の差が大きいような企業に有効な手段です。
常にA工程に入る人員ではなく、時期によってA工程に入ることができたり、B工程に入ることができたり、と複数の工程の作業を担うことができる多能工を育てます。
各工程に常に一定以上の人員を配置しておく必要がなくなるため、結果的に労務費の削減につながります。
また、業務の負荷に応じて人員を動かすことができれば、不測の事態にも対応しやすくなります。
AI-OCRとRPA技術の導入
紙面の数値や金額を人間の手入力で行っていると、思わぬミスや不良の原因になることがあります。
AI-OCRではAIを使って紙面上の数値を判断し、データ化ができます。
RPAでは読み込んだデータをシステムに入力する作業を自動化できます。
ヒューマンエラーが起こりやすく、重大な品質問題へつながることもあるデータ入力などはAI-OCRとRPAを導入すると労務費削減や品質の維持につながります。
外部委託を活用する
外部委託の活用も労務費の削減につながります。
品質に直結しないような業務や、単純作業などを外部委託すれば労務費の削減につながる可能性があります。
生産管理システムの導入
生産管理システムを導入すれば、製品に関するあらゆる情報を一元化できます。
必要なデータや資料についても、簡単に部署間で共有が可能となり、不要な会議や同行を減らすことで残業代の削減等労務費の削減にもつながります。
製造業のコストダウン戦術にはPDCAを回すことも重要
 製造業のコスト削減は、QCDのバランスが重要です。
製造業のコスト削減は、QCDのバランスが重要です。
やみくもに前年比や構成比を基にコスト削減を行おうとすると、品質が下がり顧客の信頼を失うことにもなり得ます。
また、分析もせず仕入先へ値下げ要求を行うことは仕入先との関係性を壊してしまう可能性が高いです。
コスト分析をしっかりと行いながら各関係者がコスト意識を持って業務にあたることも重要な観点のひとつです。
また、コストダウン戦術の実施後は、効果測定を行いましょう。
PDCAをしっかり回しながら、常にコスト削減を意識し、利益を出し続ける仕組みを作り続けていきましょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
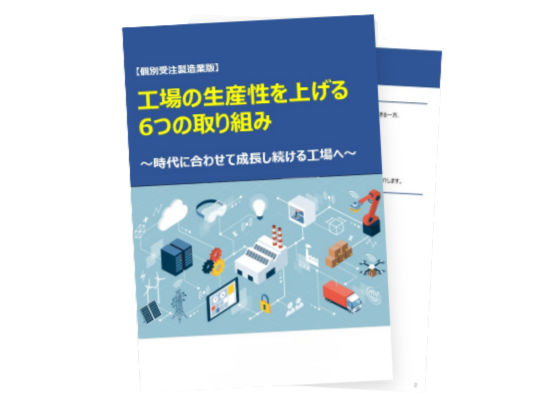
個別受注生産の製造業向け 生産性UPを低下させる要因・対策の指南書です!
工場の生産性を上げる 6つの取り組み
~時代に合わせて成長し続ける工場へ~