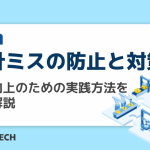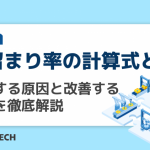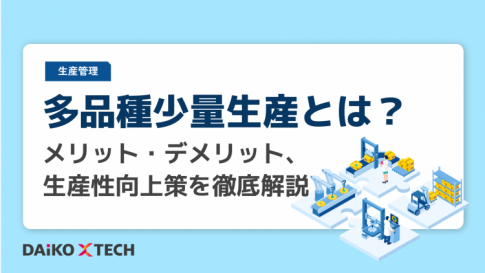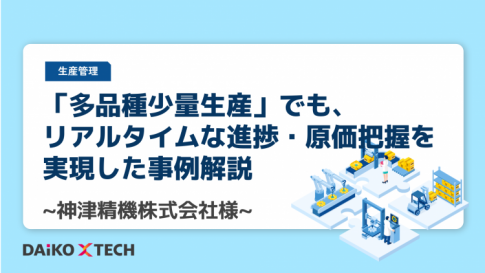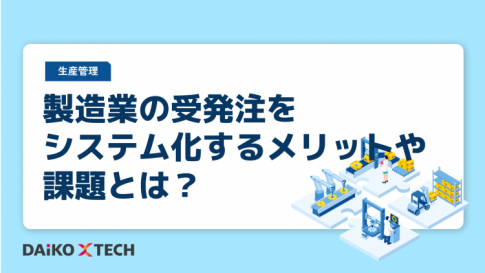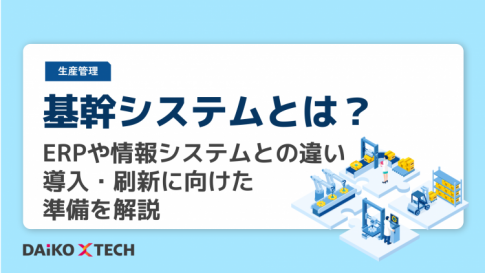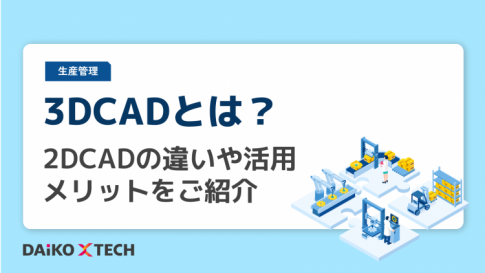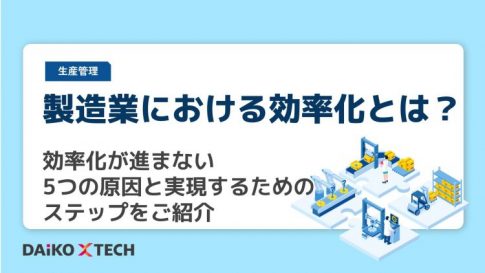事業を円滑に進めて、利益を最大化させるためにはコストリダクションが効果的です。
コストリダクションは、人件費や光熱費・原料費などさまざまなコストを削減することを指します。
ただし、コストリダクションを実施する手順や成功させるコツを押さえておかなければ、思い通りの成果を得られません。
そこで本記事では、コストリダクションを実施する手順や成功させるコツを詳しく解説します。
コストリダクションのメリットとデメリット、コストダウンとの違いもあわせて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
コストリダクションとは

コストリダクションとは、「cost(費用)」と「reduction(削減)」を組み合わせた用語で、コスト削減の意味を持ちます。
製造業では、人件費や光熱費など製造プロセスで発生するコストの他に、原料費や設計費などさまざまなコストが発生します。
コストリダクションを実現するために、無駄な経費を削減したり、効率的な資源配分を行ったりと、全体のコスト構造を改善し利益を最大化しましょう。
具体的には、下記のような方法があります。
- 原材料の調達方法を見直す
- 業務プロセスを効率化する
- テクノロジーの活用によって手作業を減らす
- 委託先を変更する
- 仕入価格の交渉を進める
- エネルギーコストを削減する
コストリダクションの目的は、上記の方法で収益性を向上させたり、競争力を強化したりすることです。
コストダウンとの違い
コストリダクションと混同されやすい用語に、コストダウンがあります。それぞれの違いは、次のとおりです。
|
用語 |
意味 |
ポイント |
|
コストリダクション |
長期的な視点で、全体的なコスト構造を改善するための取り組み |
|
|
コストダウン |
短期的、直接的なコスト削減 |
|
コストダウンとは、コストを削減することを指し、人件費や光熱費・原料費などを抑える取り組みです。
対して、コストリダクションは中長期的にコスト構造を改善する取り組みであり、現在発生しているコストを削減するだけでなく、継続的に利益を向上させる仕組みづくりを指します。
コストリダクションは、無駄を排除し削減を目指す取り組みです。そのため、コストダウンはコストリダクションの一部であり、双方には目指すべき方向性と目的・取り組み期間に違いがあります。
コストコントロールとの違い
コストコントロールもコストリダクションと混同されやすい用語です。それぞれの違いは、
以下のとおりです。
|
用語 |
意味 |
ポイント |
|
コストリダクション |
費用そのものを削減するための戦略的な取り組み |
|
|
コストコントロール |
既存の予算や計画の範囲内で費用を管理する活動 |
|
コストコントロールは、製造段階で取り組む原価管理を指し、品質を維持しながら業務効率化や要因管理により、コストダウンを目指します。
対して、コストリダクションは、企画設計の段階で製品の使用や原材料・製造プロセスを見直して、コストダウンを目指す点が違います。
コストリダクションとコストコントロールでは、実施するプロセスや目的が異なるので、それぞれの違いに注意しましょう。
コストリダクションが推奨される原価企画とは

コストリダクションは、原価企画の段階から推進するべきです。
コストリダクションを推進するために、下記のポイントを押さえておきましょう。
- 原価企画とは
- 原価企画が注目される理由
原価企画とは
原価企画とは、企画段階で目標となる原価を設定することです。
製造業では、企画段階でコンセプトやターゲット、材料や設計・製造方法などを事前に決めておく必要があります。
原価企画とは、製品・サービスの売上目標から目標利益を差し引き、最低額の許容原価を決めるプロセスです。
製品の利益を設定する際は、確保するべき売上額を求め、製品価格や製造プロセスにおけるコストを洗い出しましょう。
原価企画の段階で、コストリダクションを実施することで、最終的な利益を増加させて収益性を確保できます。
コストを抑えつつ高品質な製品をスムーズに製造するため、原価企画でのコストリダクションが推進されているのです。
原価企画が注目される理由
原価企画が注目される理由は、消費者行動の変化が要因です。
戦後の物資不足後に迎えた高度成長期に、日本は大量生産・大量消費の時代を迎えました。
しかし、バブル崩壊後に消費者の経済力が変化し、インターネットの普及、ニーズが多様化したことにより、大量生産・大量消費の時代は終わりました。
現在では、インターネットを通じて消費者が製品を比較してから購入するようになり、品質や性能に加えてコストパフォーマンスや他にはない独自性が求められています。
製品を総合的に評価して、コストパフォーマンスが高いものを購入する傾向にあり、品質と性能、コストのバランスが重要視されています。
そのため、製品をつくる前から「いくらなら売れるのか」を慎重に設定する必要があり、原価企画が注目されているのです。
原価企画の段階からコストリダクションに取り組めば、製造プロセスでの無駄なコストを削減し、コストパフォーマンスの高い製品を市場に流通させられます。
コストリダクションを実施する手順

コストリダクションを実施する手順は、下記のとおりです。
- 現状のコストを把握する
- 削減するコストを決定する
- 目標を設定する
- 具体的な方法を検討する
- 実行し評価・改善する
それぞれの手順を確認して、原価企画の段階からコストリダクションを実施しましょう。
ステップ1.現状のコストを把握する
コストリダクションを成功させるには、まず自社のコスト構造を詳細に理解することが大切です。
各部門やプロセスごとにかかるコストを洗い出し、どこでどの程度の費用が発生しているのかを明確化しましょう。
現状のコストを把握するために、過去数年間の財務データや各項目の支出明細を分析する作業が発生します。
なお、現状のコストを分析する際は、5W1Hを意識して細かく洗い出しましょう。
- When(いつ)
- Where(どこで)
- Who(だれが)
- What(なにを)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
5W1Hを意識することで、コストを発生させる担当者や部署、原因を追及できます。
どの項目で無駄が生じているのか、どの分野が効率化可能かを的確に判断するために、詳細なデータを洗い出すことが大切です。
現状の把握が不十分だと、削減の方向性を誤り、逆にコスト増加や業務の非効率化を招くリスクもあります。
ステップ2.削減するコストを決定する
現状のコスト構造を把握した後は、削減対象を明確にしましょう。
すべての費用を一律に削減するのではなく、優先順位をつけてコストリダクションを実施することが大切です。
例えば、直接原価や変動費よりも、固定費や間接費を見直すほうが効果的な場合があります。
また、品質や生産性に影響を及ぼさずに削減できるコストを選べば、生産工程を遅延させずにコストリダクションを実施できます。
削減対象を決定する際には、コスト削減による影響を事前にシミュレーションし、リスクを最小限に抑えましょう。
コスト削減後の収益や運営に、どの程度の影響が出るかを慎重に検討した上で、削減対象を決定してください。
ステップ3.目標を設定する
削減するコストを決定した後は、コストリダクションを実施する具体的な目標を設定します。
目標は達成可能でありながらも、挑戦する価値のあるレベルに設定することが大切です。
下記のように数値や期間を明確に設けて、目標を設定すれば達成に向けて施策を実施しやすいです。
- 次の四半期までに固定費を10%削減する
- 半年以内に変動費を5%削減する
- 製品1台に対する製造コストを3%削減する
具体的な数値目標を立てれば、進捗を定量的に把握できます。
また、目標は各部門やプロセスごとに分けて設定し、関係者がその重要性と目指すべき成果を理解できるように工夫しましょう。
現実的かつ明確な目標を設定することが、コストリダクションを成功へと導くコツです。
ステップ4.具体的な方法を検討する
目標が定まったら、達成するための具体的な方法を検討しましょう。
具体的な方法を決める段階で、現行プロセスを改善したり製造効率を向上させるテクノロジーを導入したりなど、多方面からのアプローチを検討してください。
具体的には、下記のような施策がコストリダクションの主な手法です。
- 購買プロセスを見直して原材料の仕入単価を引き下げる
- サプライチェーンの再構築により物流コストを削減する
- ITソリューションを活用して、事務作業の効率を上げる
- AIやloT技術を導入して生産性を向上させる
施策ごとの効果を予測し、メリットとデメリットを比較検討した上で、実現可能性の高い手段を選定しましょう。
なお、施策を決める際は得られる効果や導入コストだけでなく、現場の意見を収集することが大切です。
コストリダクションの観点だけでなく、施策を実行することで現場に与える影響や負担を考慮しなければ、従業員に混乱や反発を生じさせます。
コストリダクションの具体的な施策を検討する段階で、現場の従業員と相談して、受け入れ可能で実現可能な方法を取り入れましょう。
ステップ5.実行し評価・改善する
計画した方法を実際に実行した後は、成果を評価してください。
ただ施策を実行するだけでなく、削減目標がどの程度達成されたのかを数値的に測定し、期待通りの成果が出ているかを確認します。
目標に届いていない場合は、原因を分析し必要な修正を加えて、再度施策を実行しましょう。
PDCAサイクルを回して改善を繰り返すことで、より効果的な方法を模索し、コスト削減につなげられます。
また、削減策が業務に与える影響も評価し、業務効率や品質が低下していないか確認することも大切です。
コストリダクションを成功させるために、施策が組織全体に与える影響を広く検討した上で、長期的な改善を目指しましょう。
コストリダクションのメリット

コストリダクションのメリットは、次のとおりです。
- コストカットにより財務状況を改善できる
- 資源を有効活用できる
- 品質を維持しながらコストカットできる
- 業務の効率化と生産性の向上
それぞれのメリットを確認して、コストリダクションに注力するべきか検討しましょう。
メリット1.コストカットにより財務状況を改善できる
コストリダクションに取り組めば、収益構造が最適化し、企業の財務状況を改善できます。
固定費や間接費などのランニングコストを削減すれば、収益が安定しやすく、事業拡大や新たな投資に回せる余剰資金を生み出せます。
また、コストリダクションを実施すれば資金運用を効率化して、長期的に財務状況を健全化できるのです。
そのため、経営の安定感を高めて企業の信用力を向上させ、外部調達や取引先との関係強化にもつながります。
コストリダクションは、コストカットにより財務状況を改善し、組織にさまざまなメリットを与えるため推奨されています。
メリット2.資源を有効活用できる
コストリダクションを実施するメリットは、従来であれば無駄に使われていた資源や資材を見直し、有効活用できることです。
余剰在庫の削減やエネルギー消費の効率化など、無駄を排除すれば資源の利用効率が向上します。
同じ資源でより多くの価値を生み出せれば、コスト削減だけでなく、環境負荷の軽減や持続可能性の向上などのメリットも得られます。
メリット3.品質を維持しながらコストカットできる
従来のコストダウンでは、品質を低下させてコスト削減する方法が主流でしたが、適切なコストリダクションを実施すれば品質を維持しながらコストカットできます。
工程やプロセスの無駄を排除すれば、品質を保ちながらコスト削減を実現することが可能です。
製造プロセスの効率化や作業手順の簡略化など、製品の品質を落とさずに生産コストを抑える施策が効果的です。
コストリダクションは品質に影響を与えずにコスト構造を改善できるため、お客さま満足度を損なうことなく競争力を高められます。
メリット4.業務の効率化と生産性の向上
コストリダクションを実施する過程で、無駄な手順や非効率的な業務プロセスが明確化されます。
無駄なタスクを把握した上で、業務プロセスと作業手順を改善すれば、業務全体が効率化され、生産性を向上させることが可能です。
例えば、従来の紙ベースの管理をデジタル化すれば事務作業の手間を削減し、業務フローを簡略化して従業員の負担を軽減することで、時間や労力を有効に活用できます。
業務効率化の効果は、単なるコスト削減以上に従業員のモチベーション向上や組織全体のパフォーマンス向上につながります。
コストリダクションのデメリット

コストリダクションのデメリットは、次の2つです。
- 品質低下につながるリスクがある
- 作業工程に悪影響を与えるリスクがある
コストリダクションはメリットだけでなくデメリットも存在するので、双方を確認した上で取り組むべきか検討しましょう。
デメリット1.品質低下につながるリスクがある
コストリダクションを推進し過ぎると、製品やサービスの品質維持が難しくなるため注意しましょう。
安価な材料を使ったり品質管理工程を簡略化したりなど、短期的なコスト削減効果を目指すと品質が低下し、長期的にはお客さまからの信頼を損ねるリスクがあります。
お客さまの満足度低下やクレームの増加によりブランド価値が損なわれると、結果として売上の減少や市場シェアの縮小につながりかねません。
デメリット2.作業工程に悪影響を与えるリスクがある
過度なコストリダクションは、作業現場に過剰な負担をもたらし、工程自体の効率を下げるリスクがあります。
十分なリソースが確保できず、従業員が限界を超えた長時間労働を強いられると、ミスや事故が増えるため危険です。
また、設備の保守が不十分な場合は、機械トラブルが発生し生産ラインが停止するリスクもあります。
さまざまなリスクが顕在化することで、コストリダクションを実施しても追加コストが発生し、当初の削減効果が相殺されてしまうのです。
従業員のモチベーションが下がったり、労働環境が悪化したりすると、従業員の離職率が増加し生産性が低下するので危険です。
コストリダクションを適切に実施できず、離職率の増加や生産性が低下すると、業績悪化につながるリスクがあります。
製造業におけるコストの種類

コストリダクションを実施する際は、削減対象を決めるために、どのようなコストが存在するのか把握しておく必要があります。
製造業におけるコストは、主に製造原価と販売費の2種類に分類されます。
製造原価とは、主に下記の製品を製造するために必要なコストのことです。
- 材料費(製品製造に必要な原材料や部品のコスト)
- 労務費(製品製造に関わる従業員の賃金や採用費)
- 経費(工場の賃貸料、減価償却費、水道光熱費、外注加工費など製造に関する必要経費)
対して、販売費は上記の製造原価以外に発生する、製造工程に関わりがないコストです。
主に下記のようなコストが、販売費に分類されます。
- 役員報酬
- 従業員の賃金
- 福利厚生費
- 広告宣伝費
- 旅費交通費
- 通信費
- 研究開発費
- 賃貸料
- 水道光熱費
- 減価償却費
- 事務用品費
- 消耗品費
- 租税公課
製造業で発生するコストの中で、削減しやすいコストとしにくいコストを押さえて、削減対象を決めてください。
削減しやすいコスト
削減しやすいコストは、利益に直接的な影響を及ぼさないものが多いです。
具体的には、下記のようなコストは削減しやすい傾向にあります。
- 水道光熱費
- 減価償却費
- 事務用品費
- 消耗品費
- 広告宣伝費
- 旅費交通費
- 通信費
- システム投資
- 設備への投資
製造原価より販売費のほうが、削減しやすいので、まずは不要なコストを洗い出して削減しましょう。
ただ福利厚生費や給料など、削減することで従業員のモチベーションを低下させるコストもあるので、むやみに削減しないよう注意してください。
削減しにくいコスト
削減しにくいコストは、製品の品質に影響しやすいものです。
製造原価にあたるものが多く、主に下記のようなコストが削減しにくい傾向にあります。
- 仕入代
- 管理費
- 材料費
- 人件費
- 研究開発費
- 税金
上記のコストを削減すれば、大幅なコストダウンにつながりますが、製品の品質が低下するリスクがあります。
そのため、削減した後にどのような方法で品質を維持するか、削減しても他の代用方法で品質低下を防げるかを検討した上で、コストリダクションを実施することが大切です。
コストリダクションを実施して企業の競争力を高めよう

コストリダクションを実施すれば、製品の品質を維持した上でコストカットを実現できます。
中長期的な収益性の確保と企業の競争力向上につながるため、コストリダクションが注目されています。
コストリダクションを実施する段階は、原価企画のタイミングが推奨されており、製品製造の前から原価を調整することが大切です。
実施する手順とメリット・デメリットを理解した上で、現状のコストから削減するべき対象を洗い出してください。
生産管理と購買管理を徹底し、コストリダクションを実施することで、コスト構造を改善して収益性を向上させられます。
企業の成長に向けてコストリダクションを実施するために、削減しやすいコストから改善していきましょう。