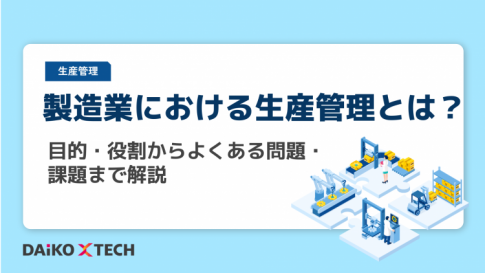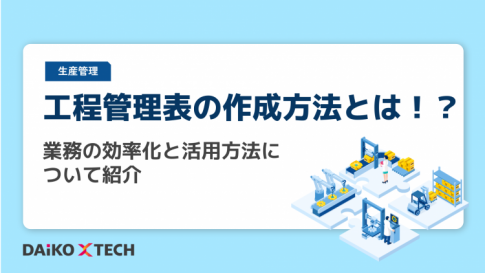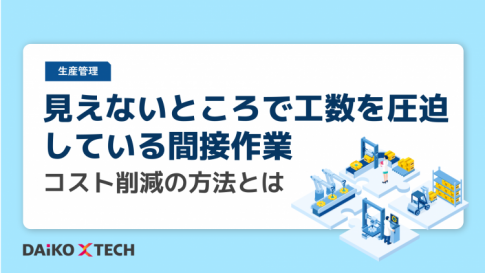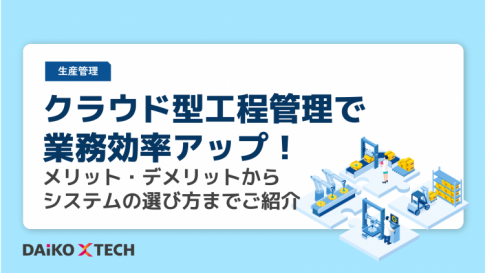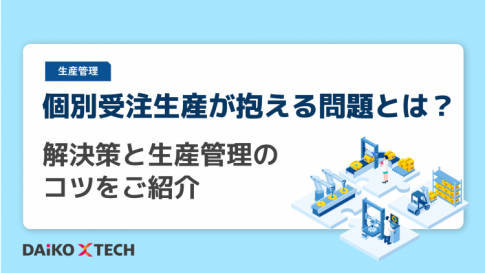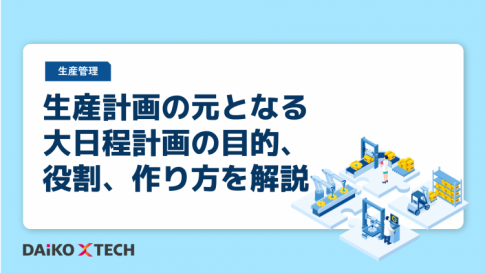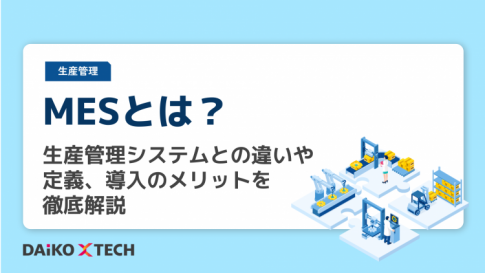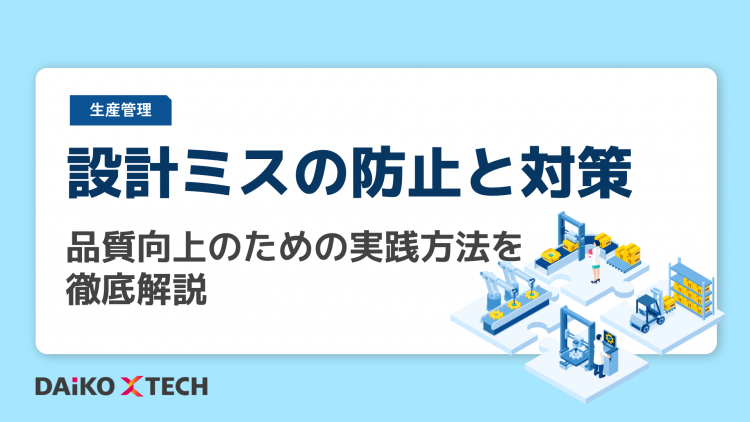
製品開発や建設プロジェクトにおいて設計ミスは品質低下、コスト増加、納期遅延を引き起こすだけでなく、最悪の場合は重大事故や企業の信頼喪失につながる深刻な問題です。
本記事では設計ミスの定義から影響、主な原因を解説し、組織と個人それぞれのレベルで実践できる具体的な防止策と事例から学ぶ教訓をご紹介します。明確な品質管理体制の構築から日常的なチェック方法まで、あらゆる業界の設計者と管理者に役立つ実践的な知識を網羅しています。
PLMの資料ダウンロードはこちらから
目次
設計ミスとは?

設計ミスとは、機械や部品の設計時に、要求される性能や強度を満たすための計算や検証に誤りが生じることを指します。広い意味では、製品の仕様、材料の選定、組み立て方法、機能性など、設計プロセス全体にわたって発生する可能性のあるあらゆる過ちが含まれます。
例えば、必要な機能が設計段階で考慮されていなかったり、製造可能性を無視して設計が進められた結果として製造段階で問題が発生したりすることも設計ミスの一種です。機械や製品の設計は設計者の能力に大きく依存する分野であり、完全にミスを防ぐのは困難です。
しかし設計段階でのミスは後工程に多大な影響を及ぼし、手戻りやコスト増加、製品の安全性に関わる重大な問題を引き起こす可能性があります。したがって、設計ミスを未然に防ぐための対策を立てることは、効率的な製品開発と高品質な製品提供のために非常に重要です。
設計ミスが引き起こす影響

設計ミスは製品開発プロセスにおいて看過できない重大な問題です。設計ミスは単なる技術的な問題ではなく、製造現場での混乱から市場での企業信頼失墜まで、広範囲に影響を及ぼします。
以下では設計ミスが製造段階と出荷後に及ぼす具体的な影響と、企業イメージへの長期的な損害について詳しく解説します。
製造段階における問題
設計ミスが製造段階で発覚した場合、部品が正しく組み付けられないといった問題が発生します。これにより、製造ラインの停止や出荷の遅延、生産計画の根本的な見直しが必要になる場合もあります。
例えば、3D CAD上で設計された部品が、実際の製造現場で工作機械のスペース不足や組み立て作業が困難なケースです。住宅設計においても、打ち合わせの内容が施工時に反映されていなかったり、図面と実際の施工が異なったりする事例があります。これらの問題は無駄な手戻りを発生させ、開発期間の長期化やコスト増大を招きます。
出荷後の問題と重大なリスク
設計ミスが製品の出荷後に発覚した場合、その影響はさらに深刻になります。製造物責任法(PL法)に基づく損害賠償責任が発生する可能性や、利用者の負傷などの重大事故につながるリスクも考えられます。建設業界では以前から、CADの設計ミスが原因でガス管に衝突して爆発が起きたり、建物が倒壊したりする重大事故の可能性も指摘されていました。
近年ではSNSなどの普及により、製品の不具合に関する情報が瞬時に拡散されるため、迅速かつ適切な対応が求められています。設計ミスのある製品が市場に出回ることは、企業の信頼を大きく損なうだけでなく、訴訟や企業イメージの低下にもつながります。
住宅設計においても、設計ミスは住環境の快適性や安全性に直接的な影響を与えるため、深刻な問題です。
企業イメージと信頼への影響
出荷後の設計ミスは重大な事故に至らなくても、顧客の不満を引き起こし、企業イメージを損なう可能性があります。不良品を購入した顧客は不快感を抱き、その経験をSNSなどで発信するケースもあるためです。
近年、個人の情報発信力は増大しており、一つの設計ミスが瞬く間に広範囲に拡散して企業の評判を傷つける場合があります。したがって、設計ミスは単なる技術的問題だけでなく、企業の信頼を揺るがす重大なリスクとして捉え、真摯な対応が求められます。
設計ミスの主な原因:人為的要因と組織的要因

設計ミスは個人の能力と組織システム両方に起因しています。
人為的要因
設計ミスは、設計者の経験や知識の不足によって引き起こされる場合があります。新しいシステムや複雑な要件に対して十分な理解や調査が不足している場合、設計に不備が生じやすい傾向です。
また、設計者間のコミュニケーション不足も重要な原因の一つです。設計者、製造担当者、品質管理スタッフ、さらには顧客との間で、要求事項や仕様に関する情報共有が不十分な場合、誤った設計や認識のずれが生じます。
設計やレビューの際の確認不足も人為的な設計ミスを引き起こします。設計者は自身の作成した設計に対して「思い込み」が働きやすく、間違いを見落としがちです。長時間作業による集中力低下や疲労、単調な作業による油断なども、見落としや入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発します。
経験豊富な設計者でも、慣れによる油断から基本的なチェックを怠る場合があります。
組織的要因
設計ミスは、個々の設計者の能力や注意不足だけでなく、組織全体の管理体制や文化に深く根ざしている場合があります。品質管理システムなど組織的な管理体制が不十分だと、設計ミスを防ぐ障壁となるでしょう。明確な設計プロセスや手順が確立されていない場合、設計の品質は個々の担当者に依存しやすくなり、ミスが発生しても発見されにくくなります。
組織内のコミュニケーション不足や、ミスを報告しにくい企業文化も、設計ミスを助長します。ミスが発覚した場合に責任追及や処罰を恐れるような雰囲気がある組織では、ミスが隠蔽されたり、報告が遅れたりする傾向です。
このような組織文化はミスから学ぶ機会を失わせ、結果的に同様のミスが再発する可能性を高めます。一方、ミスを成長の機会と捉えてオープンに議論し、改善策を立てることを奨励する組織文化は、設計ミスの低減に大きく貢献します。
設計変更の管理プロセスの不備も、組織的な設計ミスの原因です。設計変更が適切に記録、伝達、承認されない場合、設計の整合性が失われて誤った情報に基づいて製造が進められる可能性があります。
設計基準や部品の標準化が不足している場合、設計の複雑性が増し、ミスのリスクが高まります。設計ツールや技術の適切な活用がなされていない場合も、設計効率の低下やミスの増加につながる場合があるため、注意しなければなりません。
設計ミスを防ぐための組織的な対策

設計ミスを未然に防ぐには、個人の注意力に頼るだけでなく組織全体として取り組まなければなりません。以下では、具体的な対策について詳しく解説します。
品質マネジメントシステムの導入と活用
ISO9000のような品質マネジメントシステム(QMS)を導入し、設計や検査に関する規約を設けることは、設計ミスを組織的に防ぐための有効な手段です。
QMSは設計プロセス全体を標準化し、文書化すると、品質の維持と向上を図るための枠組みとなります。これにより、設計の各段階における責任と権限が明確になり、一貫性のある品質管理が可能です。
明確な設計・検査ルールの策定
設計ミスを未然に防ぐためには、具体的な設計・検査に関するルールを明確に定める必要があります。
- 図面作成の基準
- 材料選定のガイドライン
- 許容公差の範囲
- 設計レビューの手順 など
これらのルールを文書化し、全設計者がアクセスできるようにすれば、設計の品質を一定水準に保つことができます。
デザインレビュー(DR)の実施
設計変更部分や相互確認が必要な部分など、特にミスが発生しやすい箇所に対しては、デザインレビュー(DR)を実施することが重要です。
DRは複数の専門家が設計内容をレビューし、潜在的な問題点や改善点を見つけ出すための有効な手法です。異なる視点からのチェックを加えて、設計者自身では気づきにくいミスや考慮漏れを発見できます。
チェックリストの活用
ミスが起こりやすい箇所については、チェックリストを活用すると確認漏れを防げます。
チェックリストには設計に必要な項目や確認事項を具体的に記載し、設計者は設計完了後に各項目をチェックすることで、抜けや漏れがないかを確認します。定期的にチェックリストを見直し、改善するのも重要です。
早期発見と報告の奨励
設計ミスに気づいたら、放置せずに速やかに上司などに報告し、周囲と情報共有を行うことが重要です。設計ミスは早期に対応するほど影響を小さく抑えられます。ミスの隠蔽や報告の遅延は問題を深刻化させるため、避けてください。
コミュニケーションの促進と企業文化の醸成
組織として日頃からコミュニケーションを取りやすい雰囲気を作り、ミスや困りごとが共有しやすいようにするのも大切です。
オープンなコミュニケーションは設計者間の連携を強化し、知識や経験の共有を促進します。ミスを報告した際に非難するのではなく、改善策を共に考えるような企業文化を醸成するのも、設計ミスを減らすために重要です。
設計変更管理プロセスの確立
設計変更はミスが発生しやすいタイミングの一つです。したがって、設計変更を行う際には変更の理由、内容、影響範囲などを明確に記録し、関係者間で共有する過程を確立する必要があります。変更の承認フローを設け、複数人で確認すれば、変更に伴うミスを減らせます。
PDM(製品情報管理)システムの導入
PDM(製品情報管理)システムは、CADデータや部品表(BOM)など、製品設計に関するデータを一元管理するシステムです。PDMを導入すれば、設計データのバージョン管理、アクセス権限の設定、ワークフローの管理などが効率的に行えるようになり、設計ミスや情報共有の遅れを防げます。
設計者は常に最新のデータにアクセスでき、設計変更の履歴も管理できるため、問題発生時の追跡も容易です。
個人で実践できる設計ミス対策

組織的な対策と並行して、設計者個人が日常業務の中で実践できる具体的なミス防止策も非常に重要です。個人レベルの対策は、特別な予算や組織改革を必要とせず、すぐに取り入れられる実践的手法として効果的です。以下では、設計品質を高めるために個人が実践できる7つの具体的な方法を紹介します。
設計前後に改めて見直す
設計作業が終わった直後にチェックするのではなく、一旦設計から離れて別の作業を行うなどして頭をリセットすると「自分の思い込み」による見逃しを防止できます。時間を置くことで新たな視点で設計を見直しでき、ミスに気づきやすくなります。
紙媒体でのチェック
CADで設計した図面をディスプレイ上でチェックするだけでなく、紙に印刷してチェックするのも有効です。紙媒体でチェックすることで、ディスプレイとは異なる視覚的な認識が働き、間違いを発見しやすくなります。
系統的なチェック方法
図面をチェックする際には、左上から順番に目を追い、チェックした箇所を赤ペンなどで塗りつぶしていくことで見落としを防止できます。チェック漏れの寸法がないかを確認するのも重要です。
経験者への相談
経験の浅い設計者は、判断に迷う場合や自信がない場合は、積極的に上司や先輩に相談することが重要です。経験豊富な設計者の知識や視点を借りれば、潜在的な問題点や改善点を見つけられます。
ミスが起こりやすい箇所の意識
ミスが起こりやすいのは以下の箇所です。
- 設計変更箇所
- 複数の担当者とのインターフェース部分
- ソフトウェアに関連する部分 など
過去の経験からミスが発生しやすいと認識されている箇所については、特に注意深く設計とチェックを行う必要があります。
設計テンプレートとチェックリストの活用(個人利用)
組織で用意されている設計テンプレートやチェックリストだけでなく、自分自身で作成したチェックリストを活用するのも有効です。過去のミスや反省点を踏まえ、独自のチェック項目を作成し、設計の品質向上に役立てます。
重要情報の二重確認
寸法、公差、部品番号など、設計図面における重要な情報は、二重に確認する習慣を身につけることが大切です。
設計ミスが発生した時の対処法

設計ミスが発生した場合、まず速やかに関係者へ報告することが重要です。隠蔽や先送りは問題を悪化させるだけです。報告後はミスの影響範囲を特定し、必要な修正対応を計画的に進めます。設計変更の内容は文書化し、関係者全員に確実に伝達する必要があります。
また、発生したミスを分析し、根本原因を特定するのも重要です。同様のミスを繰り返さないために、設計プロセスや確認体制の見直し、チェックリストの改訂などの再発防止策を立ててください。設計ミスは単なる失敗として片付けるのではなく、組織全体の学びとして活用する姿勢が大切です。
事例から学ぶ:設計ミスの教訓

理論だけでなく実際の事例から学ぶことは、設計ミスの防止において非常に効果的です。過去に起きたさまざまな業界での設計ミスとその影響を分析することで、同様の失敗を繰り返さないための具体的な教訓が得られます。
以下では、実際に起きた代表的な設計ミスの事例とそこから導き出される重要な教訓を紹介します。これらの事例を理解することで、自社の設計プロセスにおける潜在的なリスクを特定し、効果的な予防策を立ててください。
生産プロセスにおける手戻り
近年ニーズが高まる製品の小型化の追求により、筐体内部に基板やハーネスを高密度で配置するケースが増加しています。その際、生産プロセスに渡ってから部品や工具の干渉で作業性が上げられないなどの問題から手戻りが発生する場合があります。この事例からわかるのは、設計段階で製造プロセスを十分に考慮することの重要性です。
上流工程での連携不足による設計ミス
デザイナーやエンジニア、設計者同士など、上流工程でのコミュニケーション不足や認識違いは設計上の大きなミスにつながります。設計上のミスが見逃され、後工程で発覚すると大きな手戻りが発生し、開発の遅れやコスト増につながりかねません。この事例は、製品開発の初期段階からの関係者間の密な連携と情報共有の重要性を示しています。
CADの設計ミスによる事故
CADの設計ミスは、最悪の場合重大事故の発生に発展する可能性があります。設計図面通りに工事を行ったら、ガス管に衝突して爆発が起きたり、倒壊事故が発生したりする事例があります。安全に関わる設計においては寸分の狂いも許されないこと、徹底的なチェック体制が不可欠です。
ソフトウェア開発における設計ミス
ソフトウェア開発においては、要件定義書の内容が実際の要件と異なっていたり、曖昧なために設計者が誤った解釈をしてしまったりするケースがあります。これにより、必要な機能が設計から漏れたり、誤った内容で設計が行われたりする可能性があります。
機械設計においても、顧客や関係者からの要求事項を正確に理解し、設計に反映させなければなりません。
設計ミスを減らし、高品質な製品開発へ

設計ミスは、製品開発における品質、コスト、納期に大きな影響を与えるだけでなく、企業の信頼をも揺るがす可能性があります。その原因は、設計者の個人的な要因から、組織全体の管理体制や文化までさまざまです。
設計ミスを効果的に防止するためには、組織的な品質管理体制の構築、明確なルールと基準の設定、多重なチェック体制の導入などの多角的なアプローチが不可欠です。個々の設計者も対策を日々の業務の中で実践することが重要になります。
過去の設計ミス事例から得られた教訓を活かし、同様のミスを繰り返さないための対策を立てるのも大切です。設計ミスが発生した場合には速やかに報告し、影響範囲を把握した上で適切な対応を行い、根本原因の分析と再発防止策の実施を徹底しなければなりません。
設計ミスを減らすことは、高品質な製品開発に直結します。組織全体で設計ミス防止に取り組み、顧客に安全で信頼性の高い製品を提供することで、企業の持続的な成長と発展につながります。
設計ミスを早期に発見して品質問題を未然に防げるPLMシステムについての資料は、こちらからダウンロードできます。