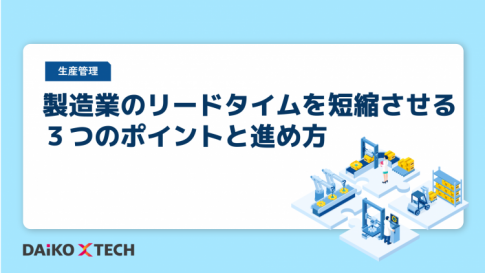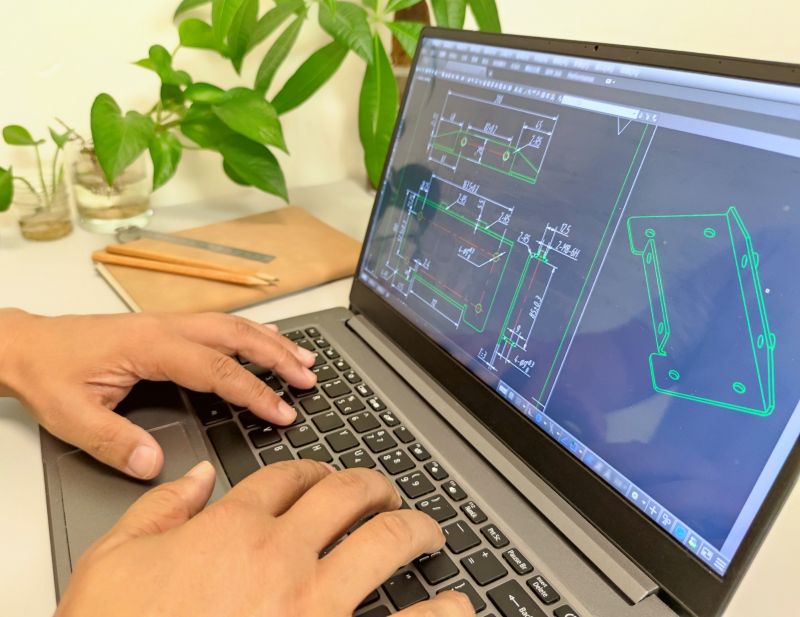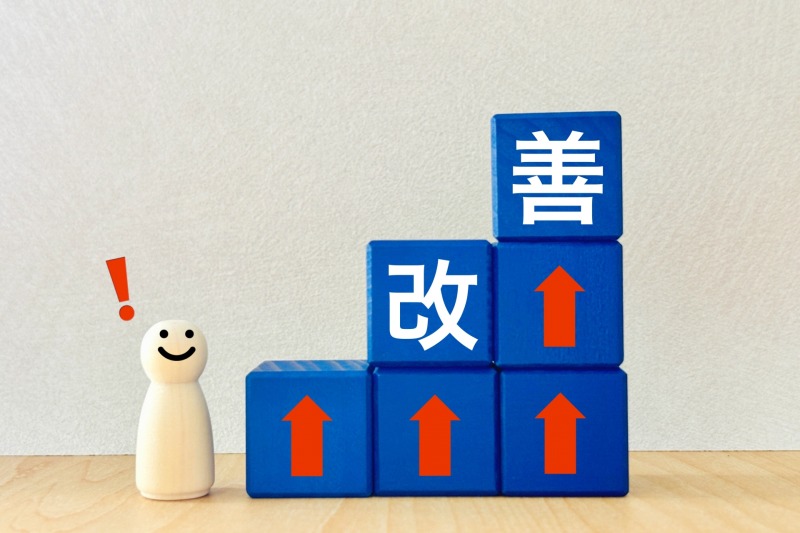
設計業務改善とは、設計部門におけるムダや非効率を取り除き、業務の質とスピードを高める取り組みです。しかし、現場ではさまざまな課題が改善を阻み、思うように生産性が上がらないケースも少なくありません。
設計フローの複雑化、情報共有の滞り、属人化した業務プロセスなどがその一例です。本記事では、設計業務改善を阻害する主な課題を整理し、それらを解消するための具体的な施策を紹介します。さらに、改善提案を進める手順も解説し、効果的に生産性を向上させる方法をお伝えします。
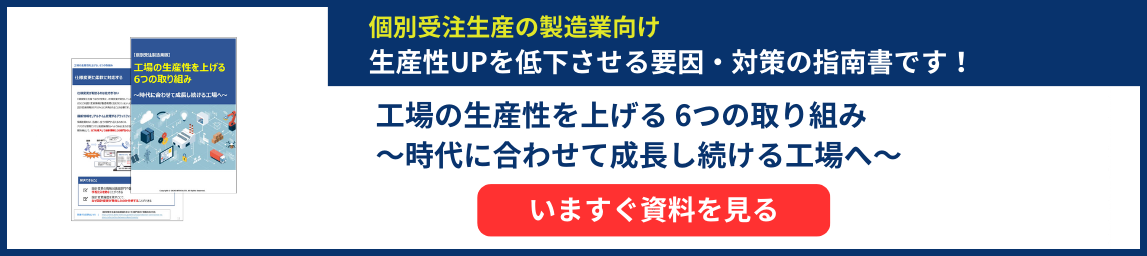
目次
設計業務改善とは

設計業務改善とは、図面作成にかかる業務手順を見直し、生産性向上を図ることです。
作業スピードを向上させるだけでなく、設計業務全体における課題を洗い出し、トヨタ生産方式における『ムリ・ムダ・ムラ(3M)』を減らしながら効率化を実現します。
また、顧客の要望を汲み取るためにコミュニケーション能力を強化し、より詳細なヒアリングを実施することで、経験・知識に基づいた分析・考察を実現できます。
業務改善と業務効率化の違い
「業務改善」と「業務効率化」は混同されやすい用語ですが、下記のような違いがあります。
- 業務効率化
作業時間の短縮や手間の削減など、効率を上げることに重点を置く取り組み - 業務改善
効率化を含む、業務の質・成果・安全性・顧客満足度などを総合的に向上させる取り組み
設計業務改善は、効率化にとどまらず、設計品質の向上やエラー削減など、設計業務における課題解決を含めた幅広い活動です。
設計変更と設計改善の違い
設計変更と設計改善も混同されやすい用語ですが、下記のような点が異なります。
- 設計変更
製品仕様や図面内容を後から修正・追加すること - 設計改善
設計プロセスや成果物の品質を向上させるための計画的な取り組み
設計変更は、顧客要望や市場ニーズの変化、設計ミスの修正など、必要に迫られて行われることがほとんどです。
対して設計改善は、過去の不具合データを分析して設計基準を見直したり、作図ルールやテンプレートを最適化したりと自発的に行う活動が該当します。
設計業務改善が求められる理由
近年、製品の多様化や短納期化が進み、設計部門は限られた時間と人員で高品質な成果物を提供する必要性を迫られています。
しかし現場では、以下のような課題が多く見られ、時間や人員などのリソースが不足しています。
- 設計変更時の情報共有不足による手戻り
- 特定の個人に依存する業務手順やノウハウの属人化
- データや図面の管理ルールが統一されていない
- 他部署や外注先との連携不足
上記のような設計業務の課題を放置すると、納期遅延やコスト増加、品質低下につながるため要注意です。
設計業務改善を阻む課題

設計業務改善を進めるには、現場で抱える課題を正確に把握し、優先度をつけて対策する必要があります。
現場では次のような要因が課題となり、改善提案や施策の実行がスムーズに進められないケースも少なくありません。
- 度重なる設計変更によるタスク増
- データ管理が煩雑
- 人材不足
- 予算不足
- 他部署との連携不足
- 技術の属人化
設計業務を改善するために、現場で施策を阻む課題を把握しておきましょう。
度重なる設計変更によるタスク増
製品開発では、顧客要望や市場環境の変化に伴い、設計変更が何度も発生するものです。
顧客の要望や市場環境の変化に応じるために、設計変更は避けられないケースもありますが、度重なる図面や仕様書・関連資料の修正を行っていては、タスクが雪だるま式に増えてしまいます。
さらに、変更内容の共有や承認フローが不十分だと、手戻りや作業ミスが頻発し、納期遅延やコスト増加を招きます。
結果として、改善活動に割ける時間やリソースが削られ、設計業務改善の効果が発揮されません。
データ管理が煩雑
膨大な設計データを適切に管理できていない場合は、再利用したい場合でもすぐに見つからず、業務効率が低下してしまいます。
設計業務に関するデータの管理ルールが統一されていない場合、下記のような課題が生じてしまいます。
- 最新版のファイルがどれかわからない
- 過去データの検索に時間がかかる
- 担当者によってデータ管理方法が異なり保管場所にバラつきがある
複数案件が並行する現場では、データの重複や誤使用のリスクが高いため、十分に注意しなければなりません。
適切な管理システムやフォルダ構造が整っていない環境では、業務時間の多くがデータ探しや整理に費やされ、設計業務改善の取り組みが後回しになってしまうのです。
人材不足
深刻な少子高齢化に伴う労働人口減少により、製造業も人材不足に悩まされており、専門スキルを有する設計部門の人材を獲得しにくい状態が続いています。
経済産業省が公表した「2025年版ものづくり白書」によると、全産業に占める製造業の就業者の割合は、2023年が15.6%・2024年が15.4%と減少傾向にあります。
特に34歳以下の若年層が減少しており、少子高齢化が改善されない限りは、今後も製造業従事者が減少する見込みです。
人員が限られている状態では、日常業務をこなしながら設計業務改善にも取り組むのは、従業員に大きな負担がかかります。
また、若手育成の時間も不足し、改善活動を担える人材が育ちにくい悪循環が生まれます。
人材不足は作業の属人化や納期遅延、品質低下を引き起こしやすく、改善効果が限定的になるため早急に対処すべき課題です。
予算不足
設計業務改善には、新しい設計支援ツールやデータ管理システムの導入、教育研修を実施する投資が必要です。
しかし予算が十分に確保できないと、根本的な課題解決ではなく部分的な対処しかできず、改善効果が下がってしまいます。
また、コスト削減を優先しすぎると、必要な機能やサポートが不足し、導入したシステムが定着しないリスクもあります。
限られた予算の中で効果を最大化させるためには、費用対効果を明確にし、段階的に施策を進める戦略が必要です。
他部署との連携不足
設計業務は、製造部門・品質管理部門・営業部門など多くの部署と密接に関わります。
部署間の連携が不十分な状態で改善施策を進めると、要件の誤解や情報の伝達漏れが起こり、手戻りや納期遅延につながります。
設計変更時に関係部署への周知が不十分な場合、現場や顧客対応に混乱が生じやすくなるので要注意です。
部門間で情報共有の仕組みやルールが確立していない場合、設計業務改善の効果が下がってしまうため、システム連携や定例ミーティングなどにより部署間のコミュニケーションを強化しましょう。
技術の属人化
ベテラン設計者の知識やノウハウが文書化されず、特定の個人に依存している技術の属人化が生じている場合、担当者の異動や退職により業務が停滞したり品質が低下したりするリスクが高まります。
設計業務改善を継続的に進めるためには、業務の標準化やマニュアル化、ナレッジ共有の仕組みづくりが欠かせません。
設計業務改善に効果的な施策

設計業務改善に効果的な施策は、下記の6つです。
- 業務の標準化
- 3DCAD導入
- データ連携・一元化
- 業務のDX化
- 部署間のコミュニケーション活性化
- 設計プロセスの最適化
業務の標準化
設計業務における手順やルールを統一すれば、ムダな作業や品質のバラつきを減らせます。
具体的には、下記のように業務を標準化させて、担当者ごとのバラつきを防ぎましょう。
- 図面や部品表(BOM)のフォーマットを統一
- 命名規則の明確化
- 承認フローの標準化
また、標準化された手順は新人教育にも活用でき、人材育成の効率化にもつながります。
業務の属人化を防ぎ、設計改善につながる組織づくりを目指すうえで、業務の標準化は欠かせません。
3DCAD導入
設計業務改善を妨げる要因である人員不足や部署間のコミュニケーション不足を解消するために、従来の2DCADから3DCADに移行しましょう。
3DCADでは立体的なモデルを作成できるため、製品の干渉チェックや組立シミュレーションを事前に行え、試作回数や手戻りを削減できます。
また、設計変更時の修正範囲が自動反映され、レンダリング機能で完成イメージを共有できるため、業務効率化や他部署・顧客とのコミュニケーション促進につながります。
作業スピードが向上し意思疎通もスムーズになるため、設計業務改善に費やす時間を確保できるのです。
データ連携・一元化
設計部門と、製造・購買・品質管理など他部門のデータを連携・一元化すれば、情報の齟齬や更新漏れを防ぐことができます。。
PLM(製品ライフサイクル管理)やPDM(製品データ管理)システムを活用して、最新の図面や部品情報を共有し、設計変更時の混乱を回避しましょう。
データが分散している状態では、検索や確認作業に時間を取られますが、データを一元管理しておけば管理にかかる手間を削減し、設計業務改善の効果を発揮できます。
業務のDX化
設計業務のDX化は、クラウドツールや自動化ソフトを活用してプロセス全体をデジタル化する取り組みです。
クラウド型CADやオンラインレビューシステムを導入すれば、場所を問わず共同作業できるため、設計業務改善につながります。
また、設計変更や進捗管理を自動で記録・共有する仕組みを整えれば、情報伝達ミスの削減にもつながり品質・生産性向上も期待できます。
設計DXとは?効果が出やすい進め方や実際の設計DX事例をご紹介
部署間のコミュニケーション活性化
設計業務改善を進めるには、設計部門だけでなく製造・品質・営業など関連部署とのスムーズな連携が必要です。
定例ミーティングや社内掲示板での情報共有、オンラインチャットツールの活用など、コミュニケーションを活性化する仕組みを整えて、要件の齟齬や情報伝達の遅れを防ぎましょう。
早期の段階で関係部署の意見を取り入れておけば、後工程での手戻り削減や設計改善の質向上にもつながります。
設計プロセスの最適化
設計業務改善を実施するためには、設計プロセスを可視化し、不要な工程や重複作業を省く作業が必要です。
設計プロセスのフローチャート化やプロジェクト管理ツールを活用して、現状の流れを分析しましょう。
分析結果を基に、工程の順序変更や並行化・チェックポイントの明確化など業務改善を行い、納期短縮や品質安定につなげてください。
改善提案で設計業務改善するプロセス

改善提案で設計業務を改善する際は、下記のプロセスを踏みましょう。
- 課題の洗い出し
- 業務改善案の策定
- コスト・リソースの算出
- 改善策の実施
- PDCAサイクルを回す
1.課題の洗い出し
最初のステップは、現場の設計業務で発生している課題を具体的に洗い出すことです。
設計業務改善を阻害している要因を明確化するために、下記の施策を実施しましょう。
- 現場の従業員へのヒアリング
- 業務フローの可視化
- 過去のトラブル事例の分析
課題が生じている背景と発生頻度・影響範囲を把握しておけば、後の改善案をスムーズに策定できます。
2.業務改善案の策定
課題が特定できた後は、解決するための具体的な業務改善案を策定しましょう。
改善提案には、業務の標準化やツール導入、設計プロセスの見直しなどが含まれます。
複数の改善提案を検討し、効果・実現可能性・導入コストを比較してください。
現場の設計者や関連部署の意見を取り入れて、実用性の高い設計改善案を策定することが大切です。
3.コスト・リソースの算出
改善案を実行するには、必要なコストとリソースを明確にする必要があります。
具体的には、下記のようなコスト・リソースを洗い出し、必要な人員や予算を決めましょう。
- システム導入費やライセンス料
- 人件費
- 教育研修費
- 改善施策に費やす時間
- 改善策を実行する人員
自社だけで対応できない場合は、外部委託も検討してください。
4.改善策の実施
コストやリソースの計画が整ったら、改善策を実行する段階です。
新しいツールの導入や業務フローの変更・設計手順書の改訂など、施策内容に応じて導入スケジュールを設定します。
小規模なパイロット運用から始め、現場の反応や問題点を確認しながら組織全体へ展開していく流れが効果的です。
現場担当者がスムーズに対応できるよう、導入前後の説明や研修を徹底しましょう。
5.PDCAサイクルを回す
改善策を実施したら終わりではなく、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを継続的に回しましょう。
実施後の効果測定を行い、計画通りの成果が出ているか、想定外の課題が発生していないかを確認します。
測定結果をもとに再度改善提案を行い、設計業務改善を継続的に発展させることが大切です。
設計業務改善で生産性を向上させよう!

設計業務改善の効果を発揮するには、現状の課題を分析し、改善策を阻害する障壁を取り除く必要があります。
まずは課題を洗い出し、改善提案の立案、コスト・リソースの算出を行い、改善策を実施しましょう。
自社だけでリソースやノウハウが不足する場合は、外部委託するのも一つの手です。
人材不足や生産性の低下に悩んでいる企業は、改善提案を行って設計業務を効率化しましょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
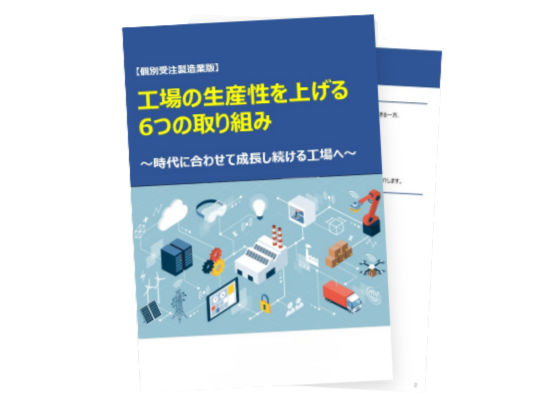
個別受注生産の製造業向け 生産性UPを低下させる要因・対策の指南書です!
工場の生産性を上げる 6つの取り組み
~時代に合わせて成長し続ける工場へ~