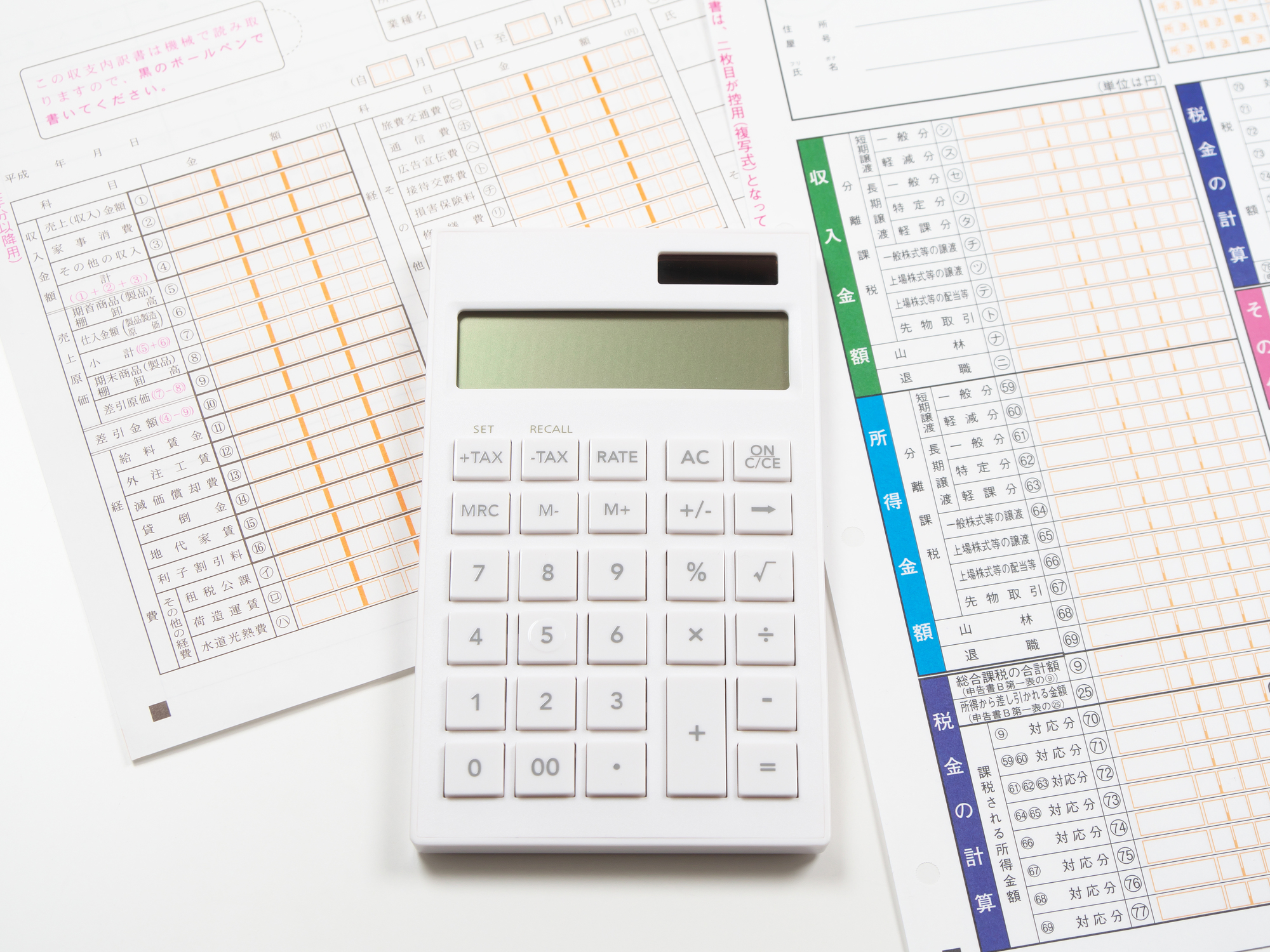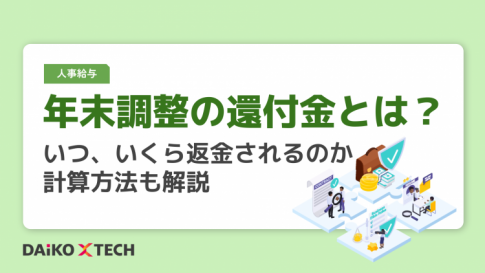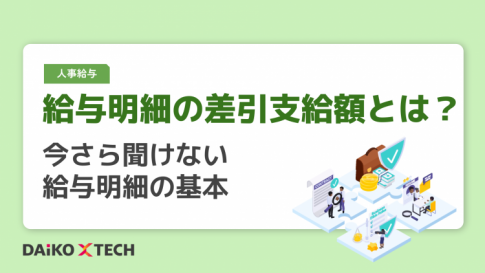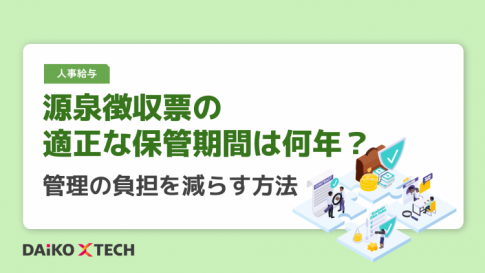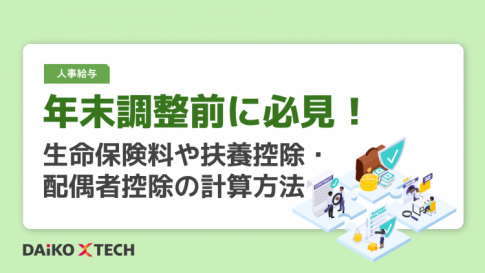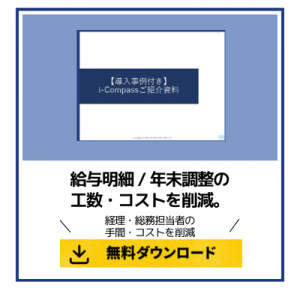2024年(令和6年)6月から定額減税が実施されています。
定額減税には、毎月の給与から天引きする「月次減税」と、年末調整で調整する「年調減税」の2つがあります。
企業経営者・労務担当者は、業務負担が増えるため、早めに対策しておくのが賢明です。
そこで本記事では、定額減税の目的や対象者について解説したうえで、年末調整で定額減税を適用させる手順や具体例を紹介します。
また、年調減税の注意点や申請のポイント、よくある質問についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
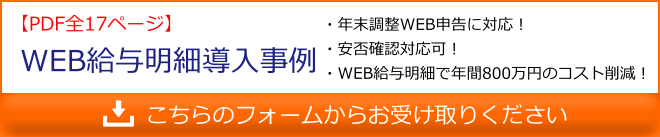
目次
定額減税とは

定額減税とは、特定の条件を満たす納税者に対して、本来納めるべき所得税・住民税を減額する制度です。
物価高や実質賃金の水準低迷を受けて、2024年(令和6年)6月から実施されています。
年末調整のときにも適用されるため、企業経営者・労務担当者は、定額減税の仕組みと手続きを把握しておくことが重要です。
ここからは、定額減税の目的、対象者、減税額について解説します。
定額減税の目的
令和6年度税制改正によると、定額減税の目的は、「デフレからの完全脱却」です。
30年間落ち込んだ日本の消費を増やすための施策として実施されています。
そのため、正社員やパート・アルバイト、自営業者、年金受給者を含めた幅広い国民が対象です。
インフレの影響により、経済的に困難な状況にある人々の税負担を軽くし、生活の安定を図ります。
定額減税の対象者
定額減税の対象となるのは、一定の基準を満たす所得税・住民税の納税者です。
ただし、一定の所得以上の方は対象外となります。詳細は以下の通りです。
- 日本に住所を有する方、もしくはこれまで1年以上日本で生活している方
- 2024年(令和6年)分の所得税・住民税を納税する者
- 2024年(令和6年)の合計所得金額が1,805万円以下の方*1
*1:収入が給与のみの場合は所得が2,000万円以下の方、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は2,015万円以下の方
参照:定額減税について|国税庁
定額減税の減税額
定額減税の減税額は、以下の通りです。
|
対象者 |
所得税 |
住民税 |
|
本人 |
30,000円 |
10,000円 |
|
同一生計の配偶者・扶養親族 |
30,000円 |
10,000円 |
納税者に配偶者や扶養親族がいる場合は、一人当たり所得税30,000円、住民税10,000円が控除されます。
例えば、配偶者と3人の扶養親族がいる場合、減税額は以下の計算で求められます。
|
所得税:5人×30,000円=150,000円 |
|
住民税:5人×10,000円=50,000円 |
定額減税は、世帯当たりの適応ではなく、一人当たりの減税制度であることに注意が必要です。
参照:定額減税について|国税庁
年末調整で定額減税を適用させる手順

年末調整で定額減税を適用させる手順は、以下の通りです。
- 従業員に同一生計配偶者・扶養親族と人数を確認する
- 定額減税額を計算する
- 所得税額から定額減税を控除する
- 定額減税を源泉徴収票に記載する
- 法定調書を作成して税務署に提出する
特に従業員の給与計算担当者は、プロセスに沿った対応が求められます。
ここからは、具体的な業務内容について解説します。
従業員に対象者と人数を確認する
企業経営者・労務担当者は、従業員に同一生計配偶者・扶養親族と人数を確認しましょう。
年末調整の対象者は、基本的にほぼすべての方が定額減税の対象者となります。
従業員から提出してもらう書類は以下の通りです。
- 基礎控除申告書
- 保険料控除申告書
基礎控除申告書は、2024年(令和6年)分から定額減税に係る項目が追加されています。
従来の書式で提出を求めないように注意しましょう。
また、上記2通の申告書を月次減税のためにすでに従業員から提出を受けている場合も、年調減税のために新たに提出してもらう必要があります。
この点は、従来の年末調整のプロセスと同様です。
同一生計配偶者と扶養親族の確認方法については、上記を参考にしてください。
|
同一生計配偶者 |
いずれかに該当する方 ・「配偶者控除等申告書」に記載されている控除対象配偶者 ・合計所得⾦額が48万円以下の配偶者のうち、「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載されている配偶者 |
|
扶養親族 |
・「扶養控除等申告書」および「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載されている扶養親族 ・「扶養控除等申告書」の住民税に関する項目に記載されている16歳未満の扶養親族 |
また、合計所得金額1,000万円を超える従業員は、配偶者特別控除を受けられませんが、配偶者分が定額減税の対象になる点に注意が必要です。
参照:扶養親族|国税庁
定額減税額を計算する
従業員に提出してもらった申告書から、定額減税額を計算しましょう。
定額減税の減税額を計算するときに注目すべきポイントは以下の2つです。
- 同一生計の配偶者の有無
- 扶養親族の有無(扶養親族がいる場合はその人数)
年末調整は所得税についての申告です。一人当たり30,000円の減税額が適用されます。
例えば、本人と親一人を扶養している場合、合計減税額は60,000円です。
所得税額から定額減税を控除する
従来の方法で従業員の合計所得税額を計算してから、年調減税額を控除します。
所得税額と年調減税額は、給与システムに情報を取り込んで計算することが一般的です。
手計算の場合は、国税庁が提供する以下のツールを活用しましょう。
- 年末調整計算シート
- 令和6年源泉徴収簿
定額減税後の所得税額を求める計算式はこちらです。
|
(合計所得税額-年調減税額)×102.1%=所得税額 |
復興特別所得税を合わせて計算するため、2.1%が加えられています。
また、年調減税額が合計所得税額を超える場合、年末調整計算シートや源泉徴収簿に差額を記載する必要があります。
定額減税を源泉徴収票に記載する
最終的な所得税額や過不足額の計算ができたら、その結果を源泉徴収票に記載します。
従業員が今回の確定申告で適用された減税額と、引ききれなかった残りの控除額を知るためです。
源泉徴収票への具体的な記載方法はこちらです。
- 源泉徴収時所得税減税控除済額○○円
- 控除外額○○円
上記の文言を、従業員の源泉徴収票の摘要欄に記載する必要があります。
法定調書を作成して税務署に提出する
最後に、法定調書を作成して税務署に提出します。
年末調整の結果やそれぞれの従業員が納めた所得税を、税務署に把握してもらうためです。
法定調書の作成は、税理士に依頼することが一般的ですが、国税庁のひな形から自力で作成することも不可能ではありません。
個人事業者や小規模の法人経営者で、法定調書を自力で提出したい方は、提出期限を過ぎないように注意してください。
参照:令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁
年末調整で定額減税を適用した場合の減税額の具体例
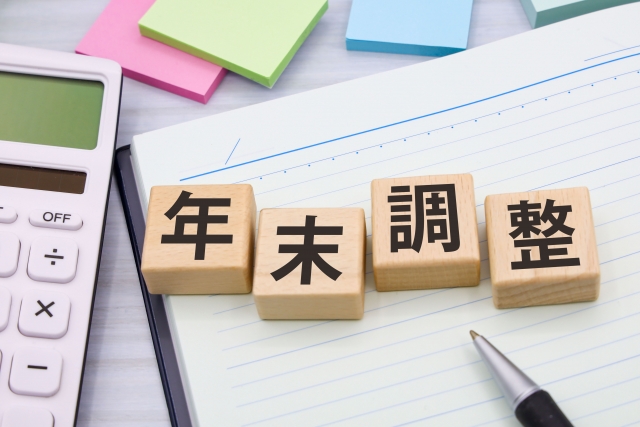
年末調整で定額減税を適用した場合、どの程度の減税が見込まれるのでしょうか。
ここからは、具体的な事例をもとに3つのシミュレーションを紹介します。
単身者1人暮らし世帯
標準的な単身者1人暮らし世帯についてシミュレーションしていきます。前提条件は以下の通りです。
- 年間総所得は400万円
- 同一生計配偶者や扶養親族はなし
年末調整で定額減税を適用すると、納税額の概算は以下の通りです。
|
支給額 |
4,000,000円 |
|
年調所得税額 |
80,000円 |
|
減税額 |
30,000円 |
|
所得税額 |
50,000円 |
このケースでは控除外額がないため、今回の年末調整で全額減税の恩恵があります。
夫婦2人暮らし世帯
共働きの夫婦2人暮らし世帯についてシミュレーションしていきます。前提条件は以下の通りです。
- 夫の年間総所得は600万円
- 妻の年間総所得は400万円
- 扶養親族はなし
年末調整で定額減税を適用すると、納税額の概算は以下の通りです。
|
夫 |
妻 |
|
|
支給額 |
6,000,000円 |
4,000,000円 |
|
年調所得税額 |
180,000円 |
80,000円 |
|
減税額 |
30,000円 |
30,000円 |
|
所得税額 |
150,000円 |
50,000円 |
夫婦のどちらも同一生計配偶者に該当しないため、既婚者であっても単身者と同様の手続きで年末調整を実施します。
夫婦2人と子1人の世帯
夫婦2人と子1人の世帯についてシミュレーションしていきます。前提条件は以下の通りです。
- 夫の年間総所得は800万円
- 妻は同一生計配偶者
- 子供は扶養親族
年末調整で定額減税を適用すると、納税額の概算は以下の通りです。
|
支給額 |
8,000,000円 |
|
年調所得税額 |
270,000円 |
|
減税額 |
90,000円 |
|
所得税額 |
180,000円 |
企業経営者・労務担当者は、基礎控除申告書や保険料控除申告書から、定額減税の該当人数を正しく把握して、適切に処理する必要があります。
年末調整で定額減税を適用するときの注意点
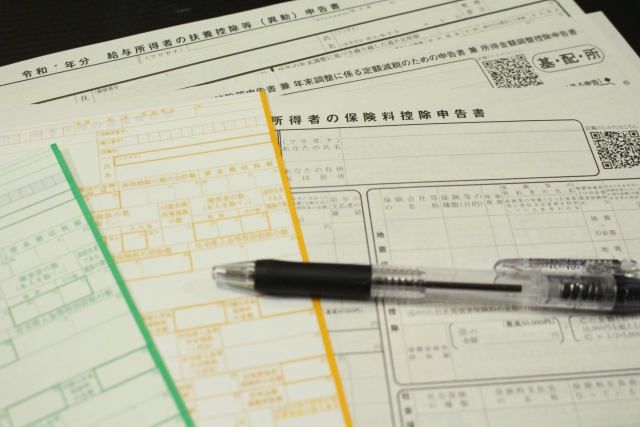
年末調整で定額減税を適用するとき、注意点が3つあります。
- 所得金額が合計1,805万円以上の場合は適用外
- 5月31日より前に退職した従業員は適用外
- 入社日によって適用範囲が異なる
企業経営者・労務担当者は、間違えやすいポイントを避けて、給与計算業務を正確に実施しなければいけません。
ここからは、それぞれの注意点について解説します。
所得金額が合計1,805万円以上の場合は適用外
所得金額が合計1,805万円以上の場合は、定額減税の適用外であるため注意が必要です。
合計所得金額には、企業からの給与所得の他に、事業所得や不動産所得なども含まれます。
本業以外の収入源がある従業員には、合計所得金額が1,805万円以上か否かを確認しておきましょう。
また、所得金額が合計1,805万円以上の方でも月次減税は適用できます。その場合は、年末調整で差し引き計算する業務が必要です。
5月31日より前に退職した従業員は適用外
5月31日より前に退職した従業員については、年末調整の定額減税を考慮する必要はありません。
定額減税が適用されるのは、6月1日以降に発生する収入であるためです。
例えば、5月末日に退職している従業員で、給与や賞与、退職金の支払いが完了している場合です。
この従業員には、これまでの退職者と同様に源泉徴収票を送付するのみで問題ありません。
入社日によって適用範囲が異なる
定額減税は、入社日によって適用されるか異なる場合があります。
基準日である2024年(令和6年)6月1日に在籍していることが条件であるためです。
例えば、6月1日に入社した従業員は、月次減税を受けられます。
一方で、6月2日に入社した従業員は、月次減税を受けられないため、年末調整で減税額を確定させて差し引きすることが必要です。
企業経営者・労務担当者は、従業員の入社日によって「月次減税」と「年調減税」の扱いが異なることを把握しておきましょう。
年末調整で定額減税を漏れなく処理するポイント

年末調整で定額減税を漏れなく申請するポイントは2つです。
- 扶養家族の増減はその都度把握する
- 年末調整を電子化する
ここからは、それぞれのポイントについて解説します。
扶養家族の増減はその都度把握する
定額減税の申請漏れが発生する原因の一つに、扶養家族の増減があります。
出産や結婚により従業員の配偶者や扶養家族の状況が変化した場合、企業側もその都度把握することが重要です。
例えば、労務担当者が従業員の家族構成や扶養状況をシステムで管理することが効果的です。
年末調整の前に従業員から提出される基礎控除申告書・保険料控除申告書の内容とシステムの内容を確認できれば、定額減税の申請漏れは発生しにくくなります。
年末調整を電子化する
年末調整で定額減税を漏れなく申請するためには、労務管理の電子化が効果的です。
エクセルや紙で手計算した源泉徴収票は、入力ミスや定額減税の申請漏れが発生しやすいためです。
例えば、2024年(令和6年)版の給与計算システムを導入すれば、年末調整の複雑な計算を自動で処理してくれます。
また、税務署への提出も電子上で完結するため、作業効率が大幅に向上することが期待できます。
企業全体の業務効率を上げたい方は、定額減税の年末調整をきっかけに、システムの導入を検討してみてください。
年末調整での定額減税についてよくある質問

年末調整の通常業務に、初めて実施される定額減税が加わると、業務の中で疑問に思うことは多いでしょう。
ここからは、年末調整での定額減税についてよくある質問に回答します。
扶養控除等申告書を提出していない従業員も申請できますか?
扶養控除等申告書を提出していない従業員は、年末調整の定額減税は申請できません。
扶養控除等申告書とは、従業員の扶養親族から各種控除を把握するために重要な書類です。
また、扶養控除等申告書の未提出により年末調整ができない場合は、従業員が自分で確定申告する必要があります。
企業経営者・労務担当者は、未提出の従業員に対して、定額減税の対象から外れてしまうことを伝えることが望ましいです。
扶養親族に所得がある場合は適用されますか?
扶養親族に所得がある場合でも、年間所得金額が48万円以下(アルバイトなどの給与所得の場合は103万円以下)であれば、扶養者に定額減税が適用されます。
また、扶養親族の年間所得金額が48万円以上(給与所得の場合は103万円以上)で税法上の扶養から外れます。
この場合は、被扶養者自身に定額減税が適用されます。
2024年(令和6年)の年末調整に向けて、アルバイト先に扶養控除等申告書を提出することが必要です。
住宅ローン控除額は減りますか?
年末調整で定額減税を適用することで、住宅ローン控除額が減ることはありません。
住宅ローン控除は、年調所得税額から定額減税額を差し引く前に計算するためです。
また、住宅ローン控除によって年調所得税額が定額減税額より小さくなる場合、引ききれなかった分が給付金として還付されます。
このように、住宅ローン控除があるために、定額減税の恩恵が小さくなることはありません。
ふるさと納税の控除上限額は減りますか?
年末調整で定額減税を適用することで、ふるさと納税の控除上限額が減ることはありません。
ふるさと納税の控除上限額は、定額減税額を差し引く前の所得額から計算されるためです。計算式はこちらです。
|
所得税の控除上限額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率 |
そもそもふるさと納税は、地方自治体への寄付によって、その年の所得税と住民税の納付額が割り引かれる制度です。
定額減税とは競合しないため、従業員から質問がある場合は、その旨を説明することが望ましいです。
年末調整では確実に定額減税を申請しよう

年末調整での定額減税は、従業員の所得税負担を軽減する重要な制度です。
一方で、2024年(令和6年)の年末調整は、定額減税の影響で労務担当者への業務負担が増えます。
企業は最新の給与計算システムを導入して、年末調整を電子化したり、従業員に扶養家族の人数を定期的に確認したりなどの対策が有効です。
万が一、申請ミスがあると定額減税が適用されないことがあります。年末調整に向けて社内体制を整えることが重要です。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓