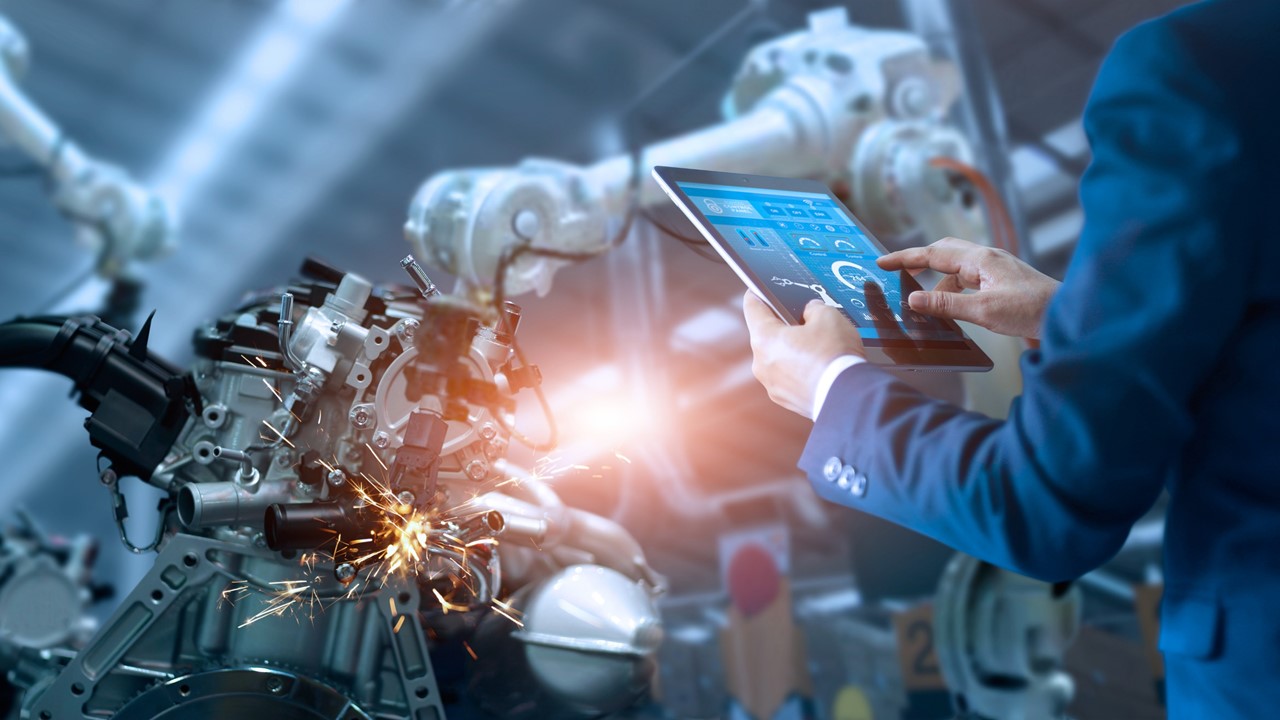モノづくりでは、生産性向上のために工場の稼働率を上げる必要があります。
工場全体の稼働率を上げるには、設備稼働率のみに注目せずに、人員配置や作業のムダ取り、生産方式の見直しなどあらゆる視点で改善点を見つけなければなりません。
本記事では、工場の稼働率の考え方や、稼働率が上がらない具体的な原因、稼働率を上げるためのポイントについて解説します。
また、実際に稼働率の改善に成功した事例もご紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
目次
工場の稼働率とは?

工場の稼働率とは、設備や人員が実際に稼働している割合を示す指標です。
工場全体の生産性を把握するために重要です。
モノづくりを行う上で、稼働率はコスト削減や納期遵守、利益率の向上に直結するため、多くの企業で重視されています。
本章では、稼働率の定義や計算方法、設備稼働率との違いについて解説します。
稼働率の定義
稼働率は、工場全体の生産能力に対して実際にどれくらい生産できたかを表す指標です。
生産能力の対象には設備だけでなく、人員配置や原材料の入荷状況、生産計画の進捗なども含まれ、生産全体の稼働状況を指します。
稼働率は、100%に近づけるように向上を目指す必要がありますが、100%を超えて高ければ高いほど良いわけではありません。
例えば、本来8時間労働の工場で、1日あたり10時間稼働している場合を想定します。この場合、工場の稼働率は120%です。
ロボットやAIを活用して無人での製造ができている場合は別として、従業員を毎日残業させて稼働率を上げるような工場では、従業員への負荷が続きます。
従業員が健康を害してしまったり、集中力不足でのヒューマンエラーにより不良率が上がってしまったりといったリスクもあります。
よって、稼働率は100%に近い数値が理想的ですが、100%を超える場合には過重労働などへの配慮や工夫が重要です。
稼働率の計算方法
稼働率の計算方法には2種類あります。
- 生産性に注目した稼働率
- 稼働時間に注目した稼働率
以下で詳しく解説します。
生産性に注目した稼働率
まずは、生産量に注目した稼働率の計算方法をご紹介します。
|
稼働率(%) = 実際の生産数 / 理論上最大の生産量 × 100 |
例を挙げると、理論上は1日で製品を100個生産できるラインにおいて、何らかの原因で70個しか製造できなかったとすると、稼働率は以下のとおり計算できます。
|
稼働率 = (70個 / 100個) × 100 = 70% |
以上のように、生産量に注目した稼働率は、実際の生産量を理論上最大の生産量で割ることで求められます。
稼働時間に注目した稼働率
次に、稼働時間に注目した稼働率の計算方法は以下です。
|
稼働率(%) = 実際の稼働時間 / 本来稼働するべき時間 × 100 |
例を挙げると、生産計画上は1日7時間稼働するべきラインが、何らかの原因で実際に動いていた時間が5時間だとすると、稼働率は以下のとおり計算できます。
|
稼働率 = (5時間 / 7時間) × 100 ≒ 71.4% |
以上のように、稼働時間に注目した稼働率は、実際の稼働時間を理論上稼働できる時間で割ることで求められます。
設備稼働率との違い
次に、稼働率と設備稼働率との違いを解説します。
設備稼働率とは、稼働可能な設備がどの程度生産に使用されたかを表す指標で、以下のように計算できます。
|
設備稼働率(%) = 生産実績 / 生産能力 × 100 |
稼働率と設備稼働率の違いは、稼働率は設備だけでなく、人員配置や原材料の入荷状況、生産計画の進捗なども含まれるのに対して、設備稼働率はあくまで設備に関してのみの稼働率である点です。
設備稼働率については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。
可動率との違い
次に、稼働率と可動率の違いを解説します。
可動率は、「べきどうりつ」と読み、設備の信頼性・安定性を評価するための指標です。
設備を利用する予定だった時間のうち実際に利用できた時間で評価し、設備が計画通りに稼働できているかを数値で把握できます。
可動率は、以下で計算します。
|
可動率(%) = 総可動時間(設備が停止せずに使用できた時間)/ 総稼働可能時間(設備が本来稼働できる時間) × 100 |
例えば、1日8時間の運転が可能な生産ラインで2時間設備トラブルで停止、6時間稼働した場合には、可動率は以下の通りです。
|
可動率 = (6時間 / 8時間)× 100 = 75% |
つまり、稼働率との違いは以下のとおりです。
稼働率は設備だけでなく、人員配置や原材料の入荷状況、生産計画の進捗なども含むため、100%を超えることもあります。
一方可動率については、設備が本来稼働できる時間を超えて稼働はしないため、100%を超えることはありません。
以上の点で稼働率と可動率には違いがあります。
稼働率が上がらない具体的な原因

次に、本章では稼働率が上がらない具体的な原因について解説します。
稼働率が向上しない原因は、主に以下が挙げられます。
- ムダ作業が多い
- 不良率が高い
- チョコ停の頻発
- 手作業や手間のかかる作業が多い
- 需要予測の精度が低い
以下で詳しく解説します。
ムダ作業が多い
稼働率が上がらない原因には、ムダ作業の多さが挙げられます。
工程内でのムダ作業が多いと、生産効率が下がり生産予定数に達しない可能性があるためです。
トヨタ生産方式には7つのムダの考え方があります。
- 加工のムダ
- 在庫のムダ
- 作りすぎのムダ
- 手待ちのムダ
- 動作のムダ
- 運搬のムダ
- 不良・手直しのムダ
製造業の作業は、付加価値を生む作業と付加価値を生まない作業に分かれます。
ムダ作業はまさに付加価値を生まない作業であり、できる限り削減しなければなりません。
例えば運搬のムダに注目すると、当初の工程設計では効率的に運搬できていたものの、設備の入れ替えや作業順序の変更により工程間の運搬にムダが発生してしまうケースも想定されます。
稼働率を上げるためには、ムダ作業を減らし、作業者をできる限り付加価値を生む作業に集中させる必要があります。
不良率が高い
不良率が高いことも稼働率低下の原因の一つです。
特に、前章で述べたうち生産性に注目した稼働率について考えるとわかりやすいです。
工程間で不良が発生し手戻りや手直しが多くなると、必然的に生産量が減り稼働率は低下します。
不良率が高いと顧客満足度にも大きく影響するため、不良率は目標数値を決めて常にモニタリングしなければなりません。
例を挙げると、不良率の目標数値として、3σ(シグマ)の指標があります。
3σとは、1,000個製造したうちの不良品数を3個以下に収めることを目標とする指標です。
不良率で表すと0.3%となり、一般的に品質基準として多く用いられています。
不良率に関しては以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。
製造業の品質不良の原因とは?不良目安や削減の方法を解説! | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
チョコ停の頻発
チョコ停の頻発も稼働率を下げる原因の一つです。
チョコ停とは、部品の詰まりなどの軽微な設備トラブルから、数秒から数分間生産ラインがストップすることを言います。
チョコ停の他にもドカ停があり、以下のように定義されています。
|
種類 |
定義 |
概要 |
|
チョコ停 |
短時間(数十秒〜数分程度)で復旧するトラブルにより生産ラインが停止する |
現場作業者で解決できるレベル |
|
ドカ停 |
長時間(1時間以上)にわたって生産ラインが停止する重大な故障 |
現場作業員だけでは対応できず、保全担当者や機械メーカーが対応し解決するレベル |
チョコ停は短時間で解決されるため稼働率に影響しないように思えますが、頻発すると生産性を下げてしまいます。
また、チョコ停が積み重なって大きな故障となり、結果的にドカ停につながることも少なくありません。
したがって、チョコ停の頻発も稼働率を下げる要因の一つと言えます。
手作業や手間のかかる作業が多い
稼働率が上がらない原因には、手作業や手間のかかる作業が多いことも挙げられます。
手作業が多く手間のかかる作業が多い工程では、加工待ちなど生産ライン内で滞留が起こりやすくなってしまうためです。
いわゆるボトルネック工程(製造工程のうち処理がもっとも遅く、生産性の低い工程)を特定し、できる限り自動化を行うなどの対応を行う必要があります。
ボトルネック工程の見つけ方には以下があります。
- 加工時間と比べて段取り替え時間が長い工程を探す
- 他の工程と比較して稼働率が極端に高い工程を探す
- 製造時間が長くなっている工程を探す
稼働率が高いことは評価されるべきですが、特定の工程だけで極端に稼働率が高い工程がある場合には、工場全体でみると稼働率を下げてしまっている可能性があります。
他の工程と同じ生産量であるにもかかわらず、特定の工程だけが稼働率の高い状況となっており、生産効率が悪くボトルネックとなっている可能性があるためです。
需要予測の精度が低い
需要予測の精度が低いことも稼働率が上がらない原因の一つです。
需要予測の精度が低いと、生産量の調整が難しくなるためです。
例えば、需要予測では3カ月で1,000個売れるとして生産計画を立てた場合に、実際に生産を始めた場合に1カ月で100個程しか売上がなかった場合には、余剰在庫による資金繰り悪化を防ぐために生産量を抑えなければいけません。
したがって、需要予測の精度が低いと、生産量を抑えるために結果的に稼働率が下がってしまうケースがあります。
稼働率を上げるためのポイント

稼働率が上がらない原因を理解したところで、本章では稼働率を上げるためのポイントをご紹介します。
4Mとは、製造業において品質向上や生産性向上のためにMan(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)の4つの要素に分けて分析・問題解決をおこないます。
本章では、稼働率を上げるためのポイントを4Mに分けて以下の通り解説します。
- Man(人)の観点での改善ポイント
- Machine(機械)の観点での改善ポイント
- Material(材料)の観点での改善ポイント
- Method(方法)の観点での改善ポイント
4Mについては、以下の記事で管理方法など詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。
4M変更とは|製造業の品質と生産性を向上させる鍵 | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
Man(人)の観点での改善ポイント
まず、Man(人)に焦点を当てて、稼働率の改善ポイントをご紹介します。
具体的には、以下のような施策が挙げられます。
- 多能工化を促進する
- 作業標準書の策定
- AIやロボットの活用
以下で詳しく解説します。
多能工化を促進する
まずは、多能工化を促進し、稼働率を上げる方法があります。
特に手作業や手間のかかる工程では、属人化により生産効率が低下しやすくなります。
属人化してしまうと技術継承の問題もありますが、工程自体がブラックボックス化し、稼働率を上げられるのかどうかさえ分かりづらくなってしまいます。
よって、できる限り属人化を解消するために、多能工育成を進める必要があります。
具体的には、スキルマップを取り入れることで促進が図れます。
スキルマップに工程や部門ごとの作業を細かく記載し、作業者ごとに作業可否や評価を行います。
工程の作業がすべて行えるようになった作業者には、さらに別の工程の作業を覚えてもらうように運用すると効率的に多能工化を進められます。
作業標準書の策定
作業標準書の策定も稼働率向上につながります。
特に不良率が高い工程には効果的です。
不良率の高さの原因には設備や機械のメンテナンス不足も想定されるものの、作業者が目と耳で覚えただけの作業を行い、ミスやヒューマンエラーを繰り返しているケースもあります。
作業標準書は一度策定するだけでなく、変更があれば都度修正し最新の状態にしておく必要があります。
特に、機械の変更や手順の変更が起こった際に、口頭の説明だけで作業標準書の修正忘れが起きやすい傾向があります。
以上のように稼働率向上のためには、作業標準書を策定して不良率を下げることもポイントの一つです。
AIやロボットの活用
AIやロボットの活用も稼働率向上に貢献します。
特に、手作業が多く手間がかかるボトルネック工程で活用すれば、稼働率の向上につながります。
手作業によるミスやヒューマンエラーは改善活動による低減は可能ですが、ゼロにはできません。
例えば、不良や停滞が起こりやすい工程内で、ネジ締めなどの単純で手間のかかる作業をロボットに切り替えるだけでも工程間の流れがスムーズになり、結果的に工程全体の稼働率が向上します。
Machine(機械)の観点での改善ポイント
次に、Machine(機械)に焦点を当てて、稼働率の改善ポイントをご紹介します。
特に設備稼働率の向上を目標とします。
具体的には、以下のような施策が挙げられます。
- IoTやセンサーによる予防保全、異常予知
- 稼働データの振り返りと目標設定
以下で詳しく解説します。
IoTやセンサーによる予防保全、異常予知
IoTやセンサーによる予防保全や異常予知も稼働率向上につながります。
モノづくりの現場において点検は、今でも人間の目による目視チェック、簡単なシートへの記入で行われることも少なくありません。
点検が疎かになると、チョコ停の頻発につながり、さらにはドカ停による長時間への生産ライン停止にも直結します。
また、点検のために作業者の手が止まり、稼働率を下げてしまいます。
IoTやセンサーで点検を行うことで、人手に頼らないリアルタイムでの点検が可能です。
さらに、AIを搭載できれば、設備や機械の状態をリアルタイムで監視し、故障を予測できます。
例えば刃具破損の予測を行うことで、生産ラインの停止だけでなく従業員の事故も防止できます。
よって、IoTやセンサーによる予防保全や異常予知は稼働率の向上につながります。
稼働データの振り返りと目標設定
稼働データの振り返りと目標設定も、稼働率向上のためのポイントの一つです。
具体的には、ボトルネック工程の発見、分析、改善を行います。
稼働率で見て、ある工程がボトルネックであることがわかれば、原因分析を行い、改善を繰り返すことで稼働率が向上できます。
原因分析の際にはMan(人)だけでなく、Machine(機械)の稼働率にも注目して、稼働データの振り返りを行いましょう。
そして目標とする稼働率を設定し、改善を行います。
設備や機械の能力の問題で稼働率が下がっている場合には、設備の入れ替えや追加の設備導入を行う必要があります。
Material(材料)の観点での改善ポイント
次に、Material(材料)に焦点を当てて、稼働率の改善ポイントをご紹介します。
原材料を適量、適時調達できないと稼働率も下がってしまいます。
具体的には、以下のような施策が挙げられます。
- 適正在庫の維持
- 購買管理システムの導入
以下で詳しく解説します。
適正在庫の維持
まずは、稼働率を上げるために適正在庫の維持が効果的です。
稼働率を上げようとしても、原材料がないと生産が行えません。
しかし、いつでも生産が行えるようにと過剰在庫の状態を作ってしまうと、キャッシュフローの悪化へとつながります。
よって、稼働率を上げるためには、生産時に過不足がない程度に適正在庫を保持する必要があります。
適正在庫については、以下の記事で詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。
購買管理システムの導入
稼働率を上げるために、購買管理システムを導入するのも施策の一つです。
原材料不足による稼働停止を防ぐためには人の勘に頼った発注タイミングではなく、システム化して根拠に基づくリードタイム管理をしなければなりません。
購買管理システムを導入すれば、以下のようなメリットがあります。
- 在庫状況や納期をリアルタイムで把握し、欠品を事前に回避できる
- 発注リードタイムを可視化できる
- 発注忘れや二重発注などのヒューマンエラーを削減できる
購買管理システムのメリットや選び方については、下記の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。
購買管理システムを導入する4つのメリットと3つの選び方 | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
Method(方法)の観点での改善ポイント
次に、Method(方法)に焦点を当てて、稼働率の改善ポイントをご紹介します。
具体的には、以下のような施策が挙げられます。
- 段取り替えの短縮
- ラインバランスの調整
- 需要予測精度の向上
- 適切な生産方式の選択
リーン生産方式とは?基礎知識からメリット・デメリットまで徹底解説 | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
段取り替えの短縮
段取り替えの短縮も稼働率向上のためのポイントです。
段取り替えとは、生産ラインで製品や部品の種類を切り替えるために行う準備作業のことで、回数が多かったり時間が長かったりすると稼働率の悪化につながります。
段取り替え短縮のためには具体的には以下の方法があります。
- 内段取り(機械を止めて行う作業)を外段取り(機械を止めずに行う作業)化する
- 互換性のある機械や治具を活用して、工程の切り替えを容易にする
- 色や形状、サイズが近い製品をまとめて作ることで生産順序を最適化する
ラインバランスの調整
稼働率向上のためには、ラインバランスを分析し調整するのも有効です。
ラインバランス分析とは、工程ごとの能力差を均等化して、生産効率を上げることです。
IE(インダストリアルエンジニアリング)の方法研究と作業測定を組み合わせた、応用的な手法です。
具体的には以下の手法を用いて分析します。
- ピッチダイアグラム:グラフの縦軸に工程ごとの作業時間を並べ、横軸に工程や作業者を並べて工程ごとのラインバランスを可視化する
- 連合作業分析:「単独作業」「連合作業」「不稼働」の3分類でチャートを作成し作業者の配置などを見直す
IEを活用して工程ごとの能力を比較しラインバランスを均等化できれば、稼働率も向上できます。
IEについては以下の記事でもご紹介しておりますので、ぜひご一読ください。
IEとは?生産管理における導入のメリットから注意点・事例までご紹介! | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
需要予測精度の向上
稼働率を上げるためには、需要予測精度の向上も効果的です。
需要予測精度を上げるためには、以下のポイントがあります。
- 過去データを用いて誤差を少なくする
- 予測値と実績値を定期的に分析・評価する
- 元データの量と質を向上させる
以下で詳しく需要予測の重要性や課題、向上のためのポイントについて解説しておりますのでぜひご一読ください。
需要予測の重要性を徹底解説|5つの手法と精度向上のためのポイント | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
適切な生産方式の選択
稼働率を上げるためには、適切な生産方式を選択するのも重要です。
設備や人員配置、生産の流れ、在庫管理方法などが生産方式によって大きく異なります。
もし現場に合わない方式を採用すると、ムダな待ち時間や工程間の滞留が発生し、稼働率が低下する原因になってしまいます。
例を挙げると、以下のような生産方式があります。
- セル生産方式:多品種少量生産に向いている生産方式
- ライン生産方式:大量生産に向いている生産方式
以下の記事では、生産方式の違いについても詳しく解説しておりますのでぜひご一読ください。
セル生産方式とは?ライン生産方式との違いやITを活用した新たなセル生産方式もご紹介 | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
稼働率向上に成功した取り組み事例
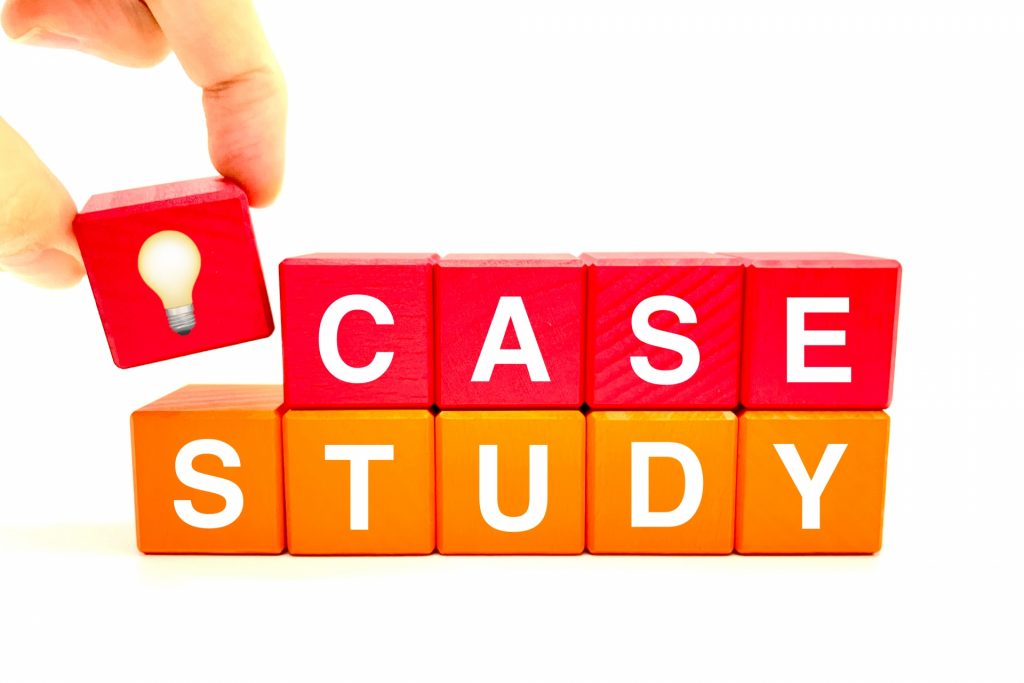
本章では、稼働率向上に成功した取り組み事例をご紹介します。
稼働状況をリアルタイムに収集した事例
自動車部品メーカの企業さまでは、各設備から稼働データを収集できるようにシステムを開発しました。
結果として、生産性が低いラインがわかり、原因を分析して対策することにより、稼働率を 50%から 90%まで改善しました。
稼働状況の見える化は適正な受注判断にもつながり、12年間で売上も35 億円から 83 億円に増加(約 2.4 倍)しました。
同業者工場と連携して稼働率を上げた事例
小売店と国内の技術力のある縫製工場を適材適所でつなぐクラウドソーシングサービスを活用した事例もあります。
運営会社が小売業者と縫製工場の間で企画から製品納入までコントロールし、縫製工場の稼働状況も把握してリアルタイムで対応しました。
結果として、縫製工場の閑散格差を是正して稼働率向上を実現しました。
受発注・生産コストの削減や小ロットでも低価格を実現し、納期の短縮にも成功しています。
工場の稼働率を上げるためには、4M視点での解決が重要

工場の稼働率は、生産能力に対して実際に稼働した割合を示す重要指標で、生産性向上やコスト削減に直結します。
工場全体の稼働率を上げるためには、設備稼働率のみに注目せずに、人員配置や作業のムダ取り、生産方式の見直しなどあらゆる視点で改善点を見つけなければなりません。
稼働率を低下させる要因にはムダ作業や、不良率の悪化、チョコ停の頻発、手作業の過多、需要予測精度の低さなどがあり、稼働率改善には4M(人・機械・材料・方法)視点での対策が有効です。
以下のホワイトペーパーでは、モノづくり企業が収益改善を行うための具体的な施策について解説しておりますので、ぜひご一読ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
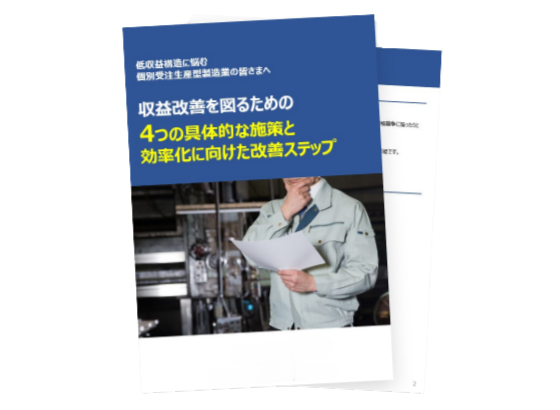
リードタイムの短縮、設計の標準化、情報共有の改善、生産管理の改善.... 個別受注生産の製造業に贈る、収益改善のノウハウブック!
収益改善を図るための4つの具体的な施策と
効率化に向けた改善ステップ