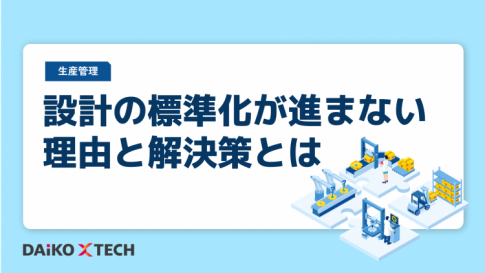安全在庫とは、欠品防止のための最低限の在庫量です。製造業において過剰在庫は保管・維持・処分のコスト増加につながります。
一方で、欠品は販売機会の損失だけではなく、顧客満足度の低下やブランドイメージの悪化に関係します。そのため、安全在庫を意識した適切な在庫管理が、製造業で成功するためのポイントと言えるでしょう。
そこで本記事では、安全在庫の概要と4つの求め方、計算方法について解説します。また、安全在庫を維持するメリットや注意点についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次
安全在庫とは欠品防止のための最低限の在庫量

安全在庫とは、欠品防止のための最低限の在庫量のことです。また、安全在庫は季節や流行による需要の波だけでなく、補充期間も考慮されている考え方と言えます。
例えば、調達リードタイムの長さ、在庫消費量の変動の大きさなども加味することが重要です。安全在庫が確保できていないと、需要の増加に対応できずに欠品が続き、販売機会の損失につながります。
他方で、安全在庫と類似する言葉に「適正在庫」と「発注点」が挙げられます。どちらも在庫管理を最適化するときに出てくる重要な言葉です。それぞれの意味の違いや安全在庫との関係性について解説します。
安全在庫と適正在庫の違い
適正在庫とは、企業の利益が最大化する在庫量のことです。欠品や過剰在庫を発生させないために、「安全在庫+α」で設定されることが一般的と言えます。適正在庫の計算方法は以下の通りです。
|
適正在庫=安全在庫+一定期間に必要な在庫量 |
例えば、安全在庫が200個の商品があるとします。一方で、受発注状況により在庫数は常に一定とは限りません。そこで、在庫数の下限である200個に、過去の月間販売数100~300個を足した300~500個を適正在庫として確保します。
つまり、安全在庫は欠品リスクを考慮した最低限の在庫量なのに対して、適正在庫はさまざまな受発注状況に対応し、企業の利益を高める在庫量である点に違いがあります。
安全在庫と発注点の違い
発注点とは、在庫量が一定数を下回った時点で発注をかける在庫水準のことです。在庫を発注してから到着するまでには一定のリードタイムが必要です。そこで、発注点は安全在庫に発注リードタイムを考慮して求めます。
|
発注点=安全在庫+1日の平均出荷量×発注リードタイム |
例えば、安全在庫が200個、1日の平均出荷量が10個、発注リードタイムが3日の場合、発注点は230個(200+10×3)となります。
発注点は、仕入先の状況や市場の需要に応じて適正値を変動させることが有効です。安全在庫や適正在庫を維持する上で必要な在庫管理法の一つと言えます。
安全在庫の4つの求め方と計算例

安全在庫を求めるには、下記の4つの要素が必要です。
- 安全係数(安全在庫係数)
- 使用量の標準偏差
- 発注リードタイム(調達期間)
- 発注間隔
また、安全在庫は下記の計算式で求められます。
|
安全在庫 = 安全係数 × 使用量の標準偏差 × √(発注リードタイム+発注間隔) |
ここからは、それぞれの要素と具体的な計算例を紹介します。
①安全係数(安全在庫係数)
安全係数(安全在庫係数)とは、「欠品は統計学的にあるものだ」と仮定した場合の許容率(欠品許容率)のことです。例えば、100個の注文に対して5個の欠品が許容できる場合、欠品許容率は5%となります。
安全在庫を求める計算式で必要なのは、この欠品許容率に応じた安全係数です。こちらの早見表を活用しましょう。
|
欠品許容率 |
安全係数(安全在庫係数) |
|
0.1% |
3.10 |
|
1% |
2.33 |
|
2% |
2.06 |
|
5% |
1.65 |
|
10% |
1.29 |
|
20% |
0.85 |
|
30% |
0.53 |
また、エクセル(Excel)からはNORMSINV関数を使って求められます。
|
安全係数(安全在庫係数)=NORMSINV(1-欠品許容率) |
製造業における欠品許容率は5%、安全係数1.65を採用することが一般的です。
②使用量の標準偏差
使用量の標準偏差とは、需要の変動を判断するための数値で、過去の在庫使用量から求めます。在庫使用量のバラツキが大きいほど、標準偏差の数値は大きくなります。
使用量の標準偏差は、人の手で計算することもできますが、エクセル(Excel)のSTDEV関数を使えば簡単です。
|
=STDEV(数値を入力した最初のセル:数値を入力した最後のセル) |
これからの需要の変動をより実態に近づけるためには、可能な限りたくさんのデータを活用することが重要です。
③発注リードタイム(調達期間)
発注リードタイム(調達期間)とは、仕入先に商品を発注してから実際に手元に届くまでの期間のことです。
例えば、7月1日に発注して7月4日に納品した場合、発注リードタイムは3となります。仕入先の事情で発注リードタイムにバラツキがあるケースでは、標準偏差を活用することも効果的です。
④発注間隔
発注間隔は、商品を定期的に仕入れる場合に用いる数値です。具体的には、一度発注してから次に発注するまでの期間(間隔)のことを指します。
例えば、一週間に1回のペースで発注しているなら、発注間隔は7となります。なお、発注ペースが定まっていないときは、発注間隔は0で計算することが一般的です。
製造業における安全在庫の計算例
こちらの条件で製造業における安全在庫を実際に計算してみましょう。
|
安全係数(安全在庫係数) |
1.65(欠品許容率5%) |
|
使用量の標準偏差 |
8 |
|
発注リードタイム(調達期間) |
6 |
|
発注間隔 |
10 |
計算例はこちらです。
|
安全在庫=1.65×8×√(6+10)=52.8 |
今回の計算では52.8と算出されました。小数点以下は切り上げるため、安全在庫は53個となります。
安全在庫を維持する3つのメリット

安全在庫を維持するメリットは、以下の3つです。
- 販売機会の損失防止
- 余剰在庫の減少
- キャッシュフローの改善
それぞれの詳細について解説します。
販売機会の損失防止
安全在庫を維持することで、欠品による販売機会の損失を防止できます。欠品は既存顧客への信頼を裏切るだけではなく、他社への乗り換えを招く大きなリスクであるためです。
例えば、リピート顧客が多いBtoBの製造業は、一度の欠品が長期的な損失につながる可能性が高まります。
適切な安全在庫の維持は、このようなリスクを抑えるだけではなく、顧客満足度の向上に有効な基本戦略です。特に人気商品や季節商品などは、過去の販売データから需要を分析し予測を立て、販売機会の損失を最小限に抑えましょう。
余剰在庫の減少
安全在庫を維持すると、余剰在庫を抱えるリスクが減少します。余剰在庫が陳腐化すると、廃棄処分や値下げ販売を強いられる可能性が高まります。
例えば、消費期限がある商品を製造している場合、余剰在庫はそのまま廃棄損として扱うことが一般的です。また、一定期間でモデルが変わる商品を値下げ販売をするにも、保管・管理にコストが必要です。
安全在庫を徹底することで、過剰な在庫が削減され、スペースの最適化や物流コストの削減に効果が期待できます。
キャッシュフローの改善
安全在庫を維持することで、企業のキャッシュフローが改善する場合があります。余剰在庫は、企業全体の在庫回転率を低下させるためです。
例えば、倉庫に100万円分の余剰在庫が眠っている場合、他の事業に投資できたはずの100万円が放置されていたことになります。また、投資機会があるにも関わらず、在庫で資金がロックされていて、迅速に対応できないなどの状況になりかねません。
したがって、安全在庫を意識した在庫管理は、在庫回転率を高め、経営の安定性向上につながります。
安全在庫を取り入れるときの4つの注意点

安全在庫を取り入れるときは、こちらの4つの点に注意しましょう。
- 安全在庫でも欠品リスクはゼロではない
- 季節ごとの商品は安全在庫の計算ができない
- 安全在庫の計算に時間がかかる場合がある
- リードタイムが変動すると再計算が必要になる
それぞれの注意点について解説します。
安全在庫でも欠品リスクはゼロではない
安全在庫は過去の需要から算出した最低限の在庫量です。必ずしも欠品リスクはゼロではない点に注意が必要です。
例えば、新商品の発売やキャンペーン期間中は、データでは予測できない突発的な需要が生まれる可能性があります。また、予期せぬ供給トラブルや災害によるリスクを完全に払しょくすることはできません。
対策としては、安全在庫を決定するためのデータを増やし、需要予測の精度を高めることが有効です。さらに、仕入先や配送業者を複数確保するなど、サプライチェーンの整備を進めましょう。
季節ごとの商品は安全在庫の計算ができない
安全在庫は、過去の需要データやリードタイムが算出できる商品に対して有効な手法です。需要が一定ではない商品は、安全在庫を正確に計算することが難しい場合があります。
具体的には、こたつやエアコンなどの家電製品、新生活時期のキッチン用品やインテリア雑貨などが該当します。
季節ごとの商品は、需要が急激に増加する一方で、下落幅も短期的です。過去の需要データに加えて、競合他社の動きや市場のトレンドなどを総合的に判断した在庫管理が求められます。
安全在庫の計算に時間がかかる場合がある
安全在庫の計算は、過去の需要データの収集、分析、予測、準備など、複数のステップが必要です。特に取り扱う商品数が多様な場合、データの収集や分析に時間と労力がかかる場合があります。
在庫管理システムや需要予測ツールを導入して、効率化を図ることが有効です。また、ABC分析(重点分析)などで商品を分類して、安全在庫を計算する商品に優先順位をつけることも効果的です。
リードタイムが変動すると再計算が必要になる
安全在庫を計算する上で必要なリードタイムは、必ず一定とは限りません。発注リードタイムが変動する場合は、安全在庫の再計算が必要です。
例えば、発注リードタイムを延長させる主な要因として、仕入先の生産遅延や天候不順、物流トラブルなどが挙げられます。また、海外から原材料を輸入する場合は、輸出規制や地政学的リスクによる遅延も考えられます。
定期的にリードタイムの変動を確認して、必要な場合は安全在庫を適切に調整しましょう。
安全在庫を意識して機会損失を無くそう!

安全在庫とは、欠品防止のための最低限の在庫量のことを指します。特に製造業は仕入先の動向や需要のバランスの変化によって、安全在庫の数値が変動しやすい業界です。
安全在庫を下回ることで、欠品による機会損失が発生しやすくなります。また、顧客満足度が低下し、最悪の場合は企業のキャッシュフローが悪化することもあります。
一方で、安全在庫を維持していれば、大きな機会損失は避けられます。本記事で紹介した4つの注意点を意識しながら、安全在庫を意識した健康経営に努めましょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
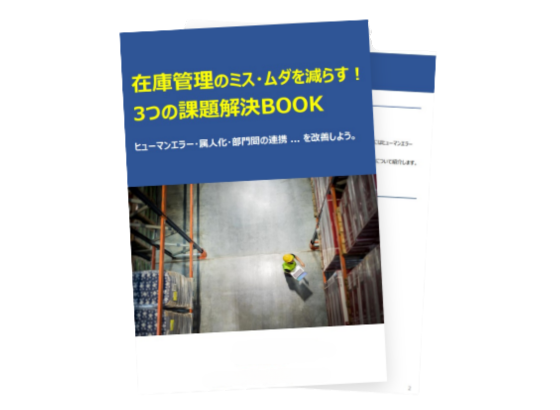
ヒューマンエラー・属人化・部門間の連携 ... を改善しよう。
在庫管理のミス・ムダを減らす!
3つの課題解決BOOK