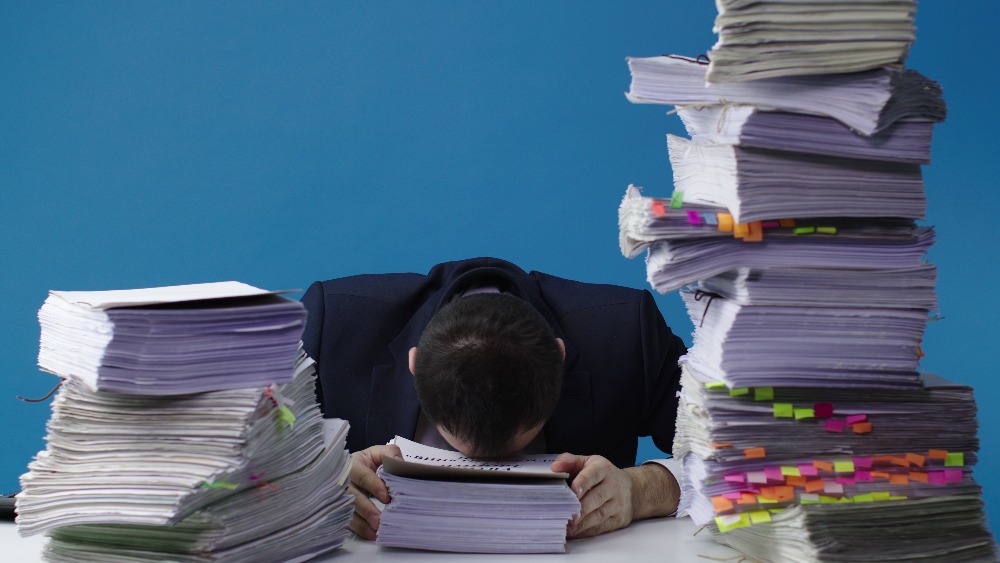日本経済を根幹から支え続けてきた製造業。そんなものづくりの現場で、気候変動や感染症の蔓延、国際紛争といったリスク要因の増加により、製造コストの上昇や利益圧縮、生産拠点の国内回帰、人手不足など、さまざまな課題が表面化しています。
本記事では、製造業の今後の課題と求められる対応策について解説します。
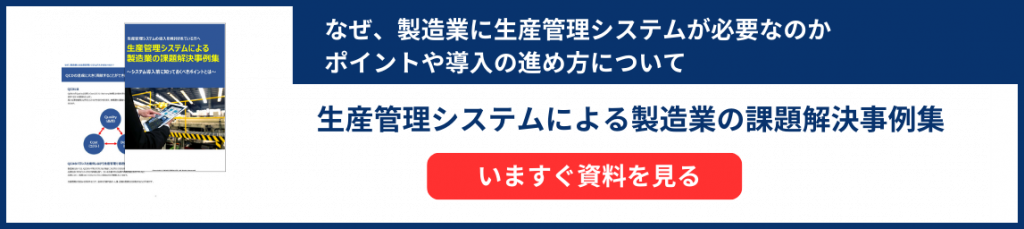
目次
製造業の現状

日銀の2024年4月「全国企業短期経済観測調査」によると、2023年6月〜同年12月までの調査では改善傾向にあった大企業製造業の業況が2024年3月の調査で悪化しました。中小製造業でも同じく2024年3月調査でマイナス水準に転じています。
背景として、コロナ禍を機に生じたサプライチェーンの分断や国際紛争、長引く円安に起因する資源価格の高騰、部品素材の不足などが挙げられます。これらの要因で製品価格を上げざるを得ず、加えて個人消費もコロナ禍前の水準に戻るか、上回りつつあるものの、実質賃金が伸び悩んでいるために需要は未だ不安定な状況です。
大企業の多くで製造コストの上昇を価格転嫁する動きがあるものの、全製造業の99%以上を占める中小企業ではそれが叶わず、厳しい利益圧縮の洗礼を浴びているケースが散見されます。
加えて、資源高や外国における人件費の高騰、長引く円安により円高時に海外拠点にシフトしたメリットが享受できにくい現象が起きています。そこで国内回帰するかどうかの判断を迫られている企業が少なくありません。
人手不足も製造業の行き先に暗い影を落としています。厚生労働省の2024年版「ものづくり白書」によると2023年の製造業の就業者数は、2002年比で147万人も減少しています。とりわけ34歳以下の若年就業者は、125万人減と深刻です。
給与を増額して人手を補充できればよいですが、特に中小企業ではその余裕がありません。経営そのものが成り立たなくなったり、後継者不足で事業継承が困難になったりするケースもみられます。
製造業が解決すべき課題

製造業が今後、解決すべき課題を具体的に解説します。
原材料価格の高騰
近年、さまざまな原材料価格が高騰しているため、製造業はそのコストを価格転嫁せざるを得ない状況です。
帝国データバンクの調査によると、2024年10月に値上げされる食品は2,911品目にのぼります。これにより、2022年の1年間で2万5,768品目、2023年には3万2,396品目の値上げがあった上に、2024年は1万2,401品目に達する見込みです。
同じ企業が同じ商品を複数回値上げする例もあり、その要因として原材料の価格の高騰が挙げられます。農産物、水産物、畜産物などあらゆる原材料が、燃料費の高騰などを理由に価格を上昇させています。企業努力だけでは限界を迎えた製造各社は、生き残りをかけてやむを得ず値上げに踏み切っている状況です。
資源エネルギー庁の2022年の速報値では、我が国の石油における中東への依存度は94.1%です。今後、中東紛争が長期化すれば、エネルギー価格の高騰も進んで多くの製造業で製造コストが底上げされ、さらに値上げを強いられる可能性があります。
デジタル化DXの遅れ
ものづくりとはいえ、すべての製造プロセスを人の手に委ねる時代ではなくなりました。しかし、製造業の多くで未だに属人化から脱出できない例があります。
世の中のデジタル化に合わせて、製造業も生産、在庫、輸送、納品、販売からなる一連のプロセスをデジタル化しなければ、生き残れない時代になりつつあります。特に若者の就業者が減り、社員の高齢化が進む中小企業では、製造技術をベテラン社員に依存する傾向が強いです。しかし今後これでは通用しにくくなるため、デジタル化によるノウハウの共有は、喫緊の課題といえます。
物流クライシスとサプライチェーンの分断
トラックドライバーの時間外労働の上限規制により、輸送力が不足したり、輸送費が高騰したりする2024年問題が表面化しています。
製品の輸送手段が確保できなければ、売上悪化に加えてリードタイム延長により社会的信用を失うリスクが高まります。紛争や自然災害に起因するサプライチェーンの分断も企業経営を揺るがす重大な脅威になりかねません。
人手不足
前記の「ものづくり白書」によると、中小製造業における従業員の過不足DI(従業員が「過剰」と回答した企業の割合から「不足」と回答した企業の割合を差し引いたもの)は、2009年の「18.2%」をピークに下降傾向が続き、2023年には「-20.4%」をマークしています。
特に労働集約型の製造業では、従来の生産規模を維持することも困難になりつつあります。
仕事を受注しても人がいなければ製造できません。すると可能な範囲にまでロットを減らさざるを得なくなり、それ以上の成長は望めなくなります。
製造業にこれから求められる対策

上記の課題を踏まえ、これから製造業が取るべき対策について解説します。
サプライチェーンの見直しと再構築
製造業のビジネスは、自社だけでは成り立ちません。仕入先、自社、物流業者、卸売業者、小売業者からなるサプライチェーンが適切にマネジメントされてこそ企業価値が高まります。
しかし決まったルートのみの場合、多様化するリスクへの対応は困難です。常により効率的なネットワークを構築しつつ、アクシデントには柔軟に対応できるサプライチェーンを複数パターン用意しておく必要があります。そのためにも、商品がどこでどのような状況にあるかが見える化できるITシステムの導入が欠かせません。
適切な在庫管理
製造業では、在庫の過不足を起こさない適切な管理が必須です。無駄に原材料の発注回数が増えるとコストが増加します。効率的な輸送のためにも、適切な在庫管理が欠かせません。
適正在庫を実現し、確実に維持していくためには、生産管理をシステム化して予算や原価、債務などにも配慮した発注管理ができる体制の構築が重要です。
優秀な人材の確保と育成
製造業では、今後も人手不足の慢性化が続くと予想されます。雇用年齢を延長したり、女性や外国人の割合を増やしたりといった戦略が有効でしょう。
イメージアップ戦略により若者の働き手を確保することも大切です。
先々は中枢として活躍してもらうためにも、魅力ある組織づくりや精度の高い人材育成システムの構築が求められます。
DXの推進で業務効率化
製造業では、業務効率化を促進しなければ過重労働や人手不足からの脱却は困難です。
そのために製造プロセスのオートメーション化やIT技術を活用したDXが欠かせません。
具体的には、生産管理システムの導入により、受発注管理に加え適切なサプライチェーンの構築や、適正在庫の維持、リードタイムの短縮にも高い効果が見込めます。データの入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防止したり、正確な原価の把握がリアルタイムで行えることによって、業務効率化が目に見えて促進されます。
生産管理システムとは?主な機能や導入メリット、選び方をご紹介
まとめ

製造業が直面する課題を克服するのは、決して容易ではありません。適切な生産管理システムの導入によるDXをはかり、業務効率化を促進することが重要になります。
当社が提供するホワイトペーパー『生産管理システムにおける製造業の課題解決事例集』では、製造業に生産管理システムが必要な理由と、実際に各社が抱えていた課題と、生産管理システムによって得られたリアルな改善効果を4つの事例とともにご紹介しています。
さらに、生産管理システムを導入する前に確認しておきたいポイントや導入の進め方についても解説していますので、ぜひご覧ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
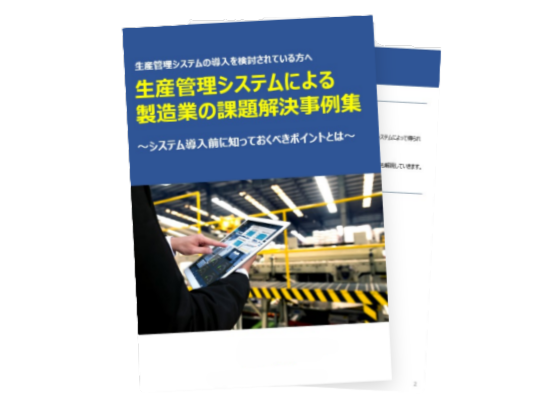
なぜ、製造業に生産管理システムが必要なのか ポイントや導入の進め方についてまとめました
生産管理システムによる製造業の課題解決事例集