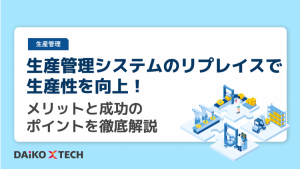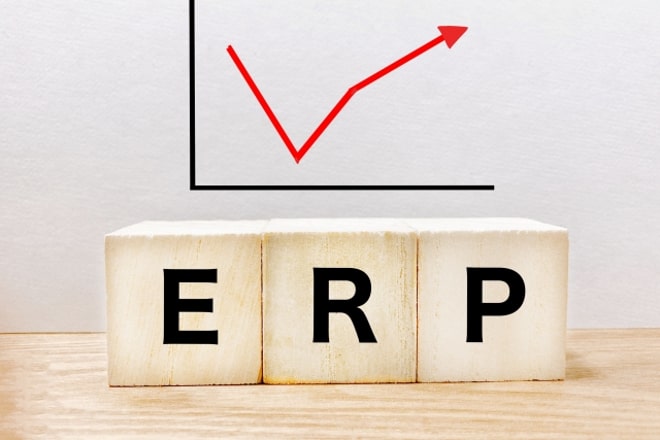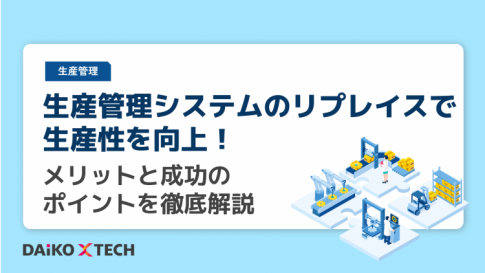生産管理システムは製造業の現場業務を統合的に管理でき、導入のメリットが多いことからさまざまな企業で取り入れられています。そこで本記事では、生産管理システムの概要から導入メリット、選定時のポイントまでまとめてご紹介します。生産管理システムの基礎知識を身につけたい方や、Excel・紙を使った生産管理に課題を感じている方は、ぜひご参考ください。
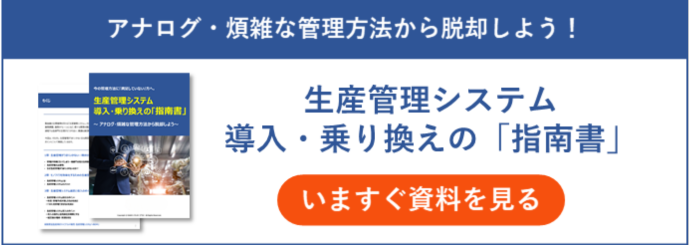
目次
生産管理システムとは?
 生産管理システムは、製造現場の納期・在庫・工程・コストといった、モノづくりの情報を管理するシステムです。一部の内容はExcelなどでも管理できますが、効率的に業務を進めたい場合は生産管理システムの導入をおすすめします。特定の業種に合わせた生産管理システムも登場しているため、導入によって効率化や改善点を見つけ出す効果が期待できます。
生産管理システムは、製造現場の納期・在庫・工程・コストといった、モノづくりの情報を管理するシステムです。一部の内容はExcelなどでも管理できますが、効率的に業務を進めたい場合は生産管理システムの導入をおすすめします。特定の業種に合わせた生産管理システムも登場しているため、導入によって効率化や改善点を見つけ出す効果が期待できます。
生産管理とは
生産管理は、製造業における根幹となる業務プロセスであり、受注から納品まで一連の製造活動を統合的にコントロールする業務です。
製品を効率的に生産するため、品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)の3要素を最適化し、企業の競争力向上と利益最大化を実現します。
現代の製造業では、顧客ニーズの多様化や市場環境の変化により、従来の単純な大量生産モデルでは対応が困難です。このような状況下で、生産管理は多岐にわたる業務領域を横断的に管理する役割を担っています。
ERP・MESとの違いは「管理範囲の違い」
生産管理システムと混同されやすいものに、ERP(Enterprise Resources Planning:基幹システム)とMES(Manufacturing Execution System:製造実行システム)があります。
生産管理システム・ERP・MESはいずれも業務の「効率化」を促す点で共通していますが、対象とする業務範囲が異なります。具体的には、ERP>生産管理システム>MESの順で管理する業務が限定されます。
・ERP:企業における基幹業務全体を管理 製造や購買、人事、会計、財務、流通部門など
・生産管理システム:生産活動に関わる業務を管理 生産計画や品質管理、在庫管理など
・MES:製造工程の業務を管理 進捗管理や稼働状況の管理、生産実績の収集など
生産管理システムの対象となる業界・業種
生産管理システムは、数多くの製造業企業で導入されています。企業規模は問わず、大企業から中堅・中小企業などで幅広く活用されており、導入されている業種もさまざまです。業種の一例としては、自動車部品や化学、金属加工、鉄鋼、印刷などが挙げられ、こうした特定の業種に対して最適化されたパッケージ製品もあれば、カスタマイズ性が高く汎用性が高いテンプレート形式のシステムもあります。
生産管理システムが必要な理由

現代の製造業において、顧客ニーズの多様化やサプライチェーンの複雑化は、経営における大きな課題です。
このような環境下で企業が持続的に成長し、利益を確保するためには、生産活動の根幹をなす「納期」「在庫」「工程」「原価」の4つの要素を的確に管理することが求められます。生産管理システムは、これら4つの重要指標を一元的に管理・最適化し、製造業特有の課題を解決するために導入されるシステムです。
以下では、この4つの観点から生産管理システムが必要とされる理由を具体的に解説します。
課題1:厳格化する納期要求への対応
近年、市場のグローバル化や顧客ニーズの多様化に伴い、製品の納期は短縮化・厳格化する傾向にあります。
このような状況下で、Excelや手作業による情報管理に頼っていると、部門間の情報伝達にタイムラグが生じ、急な仕様変更や予期せぬトラブルへの対応が遅れがちです。
例えば、営業部門が受けた短納期案件の情報が製造現場に正確に伝わらなかったり、資材調達の遅れが発覚するのに時間がかかったりすることで、結果的に納期遅延という致命的な問題を引き起こしかねません。
そこで生産管理システムを導入することで、受注から資材調達、各製造工程の進捗状況、出荷までの一連の情報をリアルタイムに一元管理できます。
問題が発生した際も迅速に影響範囲を特定し、代替案を講じることが可能です。
課題2:過剰在庫と欠品による機会損失の防止
適切な在庫レベルを維持し、企業のキャッシュフローを健全化するために、生産管理システムの導入が効果的です。
在庫過多は保管コストや管理工数が増大し、製品の陳腐化や品質劣化のリスクも高まります。
一方で、在庫不足は急な需要に対応できず販売機会を失う機会損失や、顧客の信頼低下を招きます。
こうした「過剰在庫」と「欠品」は、いずれも企業の収益性を著しく悪化させる要因です。
生産管理システムを活用すれば、過去の販売実績や現在の受注状況から高精度な需要予測を行い、それに基づいて最適な生産計画を立案できます。
また、原材料や仕掛品、製品在庫の状況をリアルタイムで可視化できるため、常に適正な在庫量を維持することが可能となり、企業のキャッシュフローの健全化も期待できます。
課題3:生産工程のブラックボックス化の解消
多くの製造現場では、個々の工程の進捗状況や設備の稼働データが担当者の経験と勘に依存し、組織全体で共有されていない「ブラックボックス」状態に陥りがちです。このような状態では、以下のような問題が発生します。
- 生産性の停滞:工程全体のボトルネックが特定できず、改善活動が進まない
- 品質の不安定化:作業が標準化されず、担当者によって品質にばらつきが出る
- 技術継承の困難:熟練工の持つノウハウが形式知化されず、若手への継承が滞る
生産管理システムを導入し、各工程の実績データ(作業時間、出来高、設備稼働率など)を収集・分析することで、これまで見えなかった現場の状況が客観的な数値として可視化されます。
ボトルネックとなっている工程の特定や非効率な作業の改善が容易になります。
課題4:不明確な原価構造の改善
「この製品は本当に儲かっているのか」「どの工程にコストがかかりすぎているのか」といった問いに即答できない場合、その企業の原価管理はどんぶり勘定に陥っている可能性があります。
材料費や労務費といった変動要素を正確に反映しない原価計算では、適切な販売価格の設定は困難です。
気づかないうちに利益率の低い製品ばかりを生産・販売してしまい、収益を圧迫しているケースも少なくありません。
生産管理システムでは、製品ごと、あるいは製造ロットごとに、仕入れた部品の価格や実際にかかった作業時間といった実績データを基にして、正確な製造原価をリアルタイムに算出することが可能です。
標準原価と実際原価を比較分析することで、想定外のコストが発生している工程を特定し、具体的なコスト削減策を講じることができます。
生産管理システムの主な機能
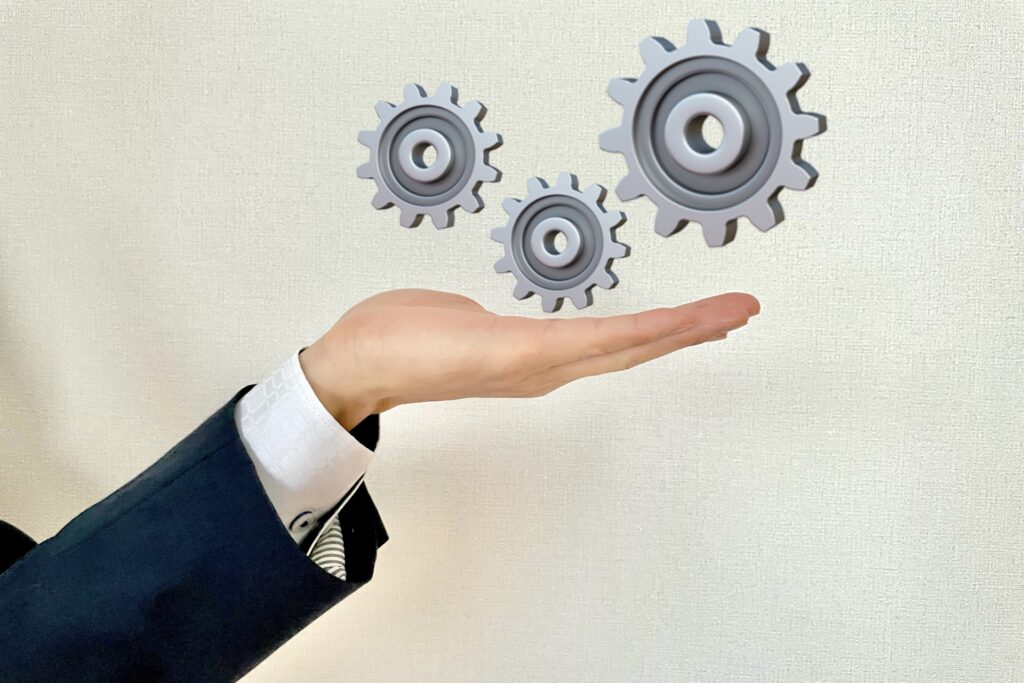 生産管理システムの主な機能としては、次のようなものがあります。
生産管理システムの主な機能としては、次のようなものがあります。

生産計画
生産計画は、製造業において、どの製品をいつ、どれだけ、どのような費用をかけて生産するのかを計画するものです。生産計画は、受注した製品を納期に間に合わせるために、また安定して利益を出すために作られ、多くの場合、大日程計画・中日程計画・小日程計画に分かれます。
長期的に大まかな計画を立てる大日程計画から、直近の従業員の動きを1日や1時間単位で決める小日程計画までを継続的に作ることで、納期に間に合わせつつ最小限の費用で利益を上げられるようになります。生産管理システムでは、生産計画を各種管理に結びつけることで各部門の連携を強化することが可能です。
販売管理
販売管理は、受注から出荷、請求、売上の管理までを行うマネジメントです。注文の受注から請求までを1つのシステムで管理することで、受注漏れといった事務的なミスを最小限にすることを目指します。
また、販売管理では商品の在庫数も管理し、その受注は納期までに納品可能なのかの判断も行います。生産計画との関わりも深いため、生産管理システムで一元管理することでよりスムーズな管理ができるようになります。
所要量展開
所要量展開では、作成されたオーダーを基に部品表を参照・子品目に展開し、各品目の所要量を算出します。原材料や部品の必要数量を正しく計算することで資材の発注を行えます。個別受注生産の場合には、人が適切な調達手段を判断し、必要な部品を手配することが大切です。
購買管理
販売管理が完成した製品の取り扱いを管理するものだとすれば、購買管理は製品を作るための素材や部品の取り扱いを管理するものです。購買管理では、製品の製造に必要な素材・部品の購入や支払いの管理、入庫や出庫などを記録することによる仕入れ・在庫の管理などを行います。
必要な数の素材・部品を仕入れていなければ計画的な生産は実現できません。そのため、生産計画との関わりが深く、生産管理システムで一元管理することで効率化を図ることができます。
工程管理
工程管理は生産管理と同じ意味の言葉と捉えられますが、狭義には生産管理の一部、特に実際に製造を行う部分の管理を指します。工程管理では製造の全体の流れを管理し、一部に遅れがあれば調整を行うなどの対処を行います。また、均一的な品質を維持することも工程管理に含まれます。
出荷管理
工場は受注に対して正確に出荷するまでの責任を負っているため、出荷管理を適切に行うことが必要です。出荷管理では遅延や出荷ミスを防ぐことが重要であり、そのためのポイントとして納期管理と誤出荷防止が挙げられます。
在庫管理
在庫管理では、完成品の他、製造の途中である仕掛品や素材・部品の在庫なども管理します。適切な在庫管理を行うことでスムーズな生産を実現し、納期遅れを防止しつつキャッシュフローも正常に保つことができます。
この他にも、製番管理・手配進捗・原価進捗の情報共有や一元化によって生産管理業務をサポートします。基本となるパッケージだけでなく、オプションで機能を拡張できるサービスを提供している企業もあり、自社にとって適切な生産管理システムを選ぶことが大切です。
原価管理
原価管理では、製品ごと、あるいはロットごとの製造原価計算や、標準原価と実際原価の比較分析、間接材のコスト管理など、生産活動に関わる原価の管理を行います。部品の仕入価格や在庫などの情報から、リアルタイムに最新の原価を反映できることが一般的です。そのため、原価低減・収益拡大に向けた活動を最適化することができます。
ここまで、生産管理システムの基本的な特徴や機能について説明しましたが、以下からは、具体的に生産管理システムにどのような種類があるかを解説します。
予算管理
予算管理では、生産活動に関わる予算の策定から実績管理まで、製造現場の財務計画を包括的にコントロールします。
具体的には、原材料費、労務費、設備投資費、間接費などの予算設定と、計画に対する実績の進捗監視を行います。
従来のExcelベースの手作業管理と比較して、各部門の予算情報を統合的に把握できることが特徴です。
生産管理システムの予算管理機能では、他の機能との連携により自動計算が実現されます。在庫管理や工程管理から得られるデータを基に、リアルタイムで予算消化状況を更新し、予算超過リスクの早期発見が可能です。
生産管理システムの主な種類

生産管理システムは多様であり、自社に最適なものを選ぶためには、複数の観点から分類して理解することが有効です。
生産管理システムの主な種類として「生産方式」「企業規模」「提供形態」の3つが挙げられます。
以下で、それぞれの特徴について具体的に解説します。
【生産方式】受注生産・計画生産
生産管理システムは、企業の主力となる「生産方式」に合わせて選定することが重要です。生産方式は、大きく「受注生産」と「計画生産」に大別され、それぞれ管理すべき項目や業務フローが異なるためです。
受注生産
顧客からの注文を受けてから製品の製造を開始する方式です。一品一様の特注品や多品種少量生産がこれに該当します。
計画生産
事前に立てた需要予測に基づき製品を生産し、在庫として保管。顧客からの注文には在庫から引き当てて対応する方式です。主に少品種大量生産の製品で採用されます。
この2つの生産方式では、管理の重点が以下のように異なります。
|
項目 |
受注生産 |
計画生産 |
|
管理の起点 |
個別の受注案件 |
需要予測・販売計画 |
|
管理の中心 |
案件ごとの進捗管理・原価管理(製番管理) |
適正在庫の維持・欠品防止(MRP※による所要量計算) |
|
主な課題 |
・複雑な工程管理 ・正確な見積り ・案件ごとの原価把握 ・納期遵守 |
・需要予測の精度 ・過剰在庫の発生 ・欠品による機会損失 ・在庫管理コスト |
|
向いている製品 |
産業機械、試作品、特注家具など |
食品、日用品、自動車部品(量産品)など |
※MRP(Material Requirements Planning):資材所要量計画のこと
自社の生産方式がどちらのタイプか、あるいは両方が混在するハイブリッド型かを明確にし、その方式を得意とするシステムの導入を検討することが、導入成功への第一歩です。
受注生産向けのシステムは個別原価計算や詳細な工程管理機能に強く、計画生産向けのシステムは需要予測や高精度な在庫管理機能に強みを持つ傾向があります。
【企業規模】大企業・中堅企業・中小企業
生産管理システムに求められる機能や役割は、企業の規模によっても大きく異なります。そのため、自社の事業規模に適したシステムを選定することが、費用対効果の観点からも重要です。
企業の成長段階や事業の複雑性に応じて、必要となる管理レベルや機能の範囲、カスタマイズ性が変わります。企業規模による主な特徴は以下の通りです。
|
企業規模 |
主な特徴とシステムに求める要件 |
|
中小企業 |
・導入コストと使いやすさを重視 限られた予算内で導入・運用できることが前提。特定の業種や業務に特化した、比較的シンプルな機能構成のクラウド型システムが選ばれることが多いです。 ・基本的な機能で十分な場合が多い まずはExcelや手作業からの移行を目指し、在庫管理や工程の見える化など、中核となる機能からスモールスタートするケースが中心となります。 |
|
中堅企業 |
・機能の網羅性と拡張性のバランス 事業の成長に合わせて機能を追加できる拡張性や、ある程度のカスタマイズ性が求められます。複数の生産方式に対応できるハイブリッド型のシステムや、他システムとの連携機能も重要な選定ポイントです。 ・全部門を横断した情報活用 生産部門だけでなく、販売・購買・会計といった複数部門でのデータ活用を視野に入れたシステム選定が必要です。 |
|
大企業 |
・グループ全体での統合管理と高度な経営分析 複数の工場や海外拠点を含めたサプライチェーン全体の情報を一元管理できる、大規模なシステム(ERP)が求められます。グループ会社間の取引や多言語・多通貨への対応も必須です。 ・高度なカスタマイズ性と連携 独自の業務プロセスや既存の基幹システムに合わせて、大幅なカスタマイズを前提とした導入が一般的です。BIツールと連携し、経営戦略の意思決定にデータを活用します。 |
このように、企業の規模によって解決したい課題やシステムに期待する役割はさまざまです。自社の現状と将来の事業展開を見据え、最適な拡張性と機能を持つシステムを選ぶ必要があります。
【提供形態】オンプレミス型・クラウド型
生産管理システムは、その提供形態によって「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類に分けられます。
それぞれにメリット・デメリットがあり、自社のIT方針やセキュリティポリシー、予算に合わせて選択することが重要です。
オンプレミス型
自社内にサーバーを設置し、ソフトウェアをインストールして利用する形態です。
クラウド型
ベンダーが提供するサーバー上のソフトウェアに、インターネット経由でアクセスして利用する形態です。
両者の主な違いは以下の通りです。
|
比較項目 |
オンプレミス型 |
クラウド型 |
|
初期費用 |
高額(サーバー購入費、ソフトウェアライセンス費など) |
初期費用は低額または不要(利用料に含まれる) |
|
ランニングコスト |
保守や運用の人件費、電気代などが継続的に発生 |
月額・年額のサービス利用料が発生 |
|
カスタマイズ性 |
高い。自社の業務に合わせて自由に構築できる |
制限あり。標準機能の範囲での利用が基本 |
|
導入スピード |
時間がかかる(サーバー構築、インストール、設定など) |
短期間で導入可能 |
|
保守・運用 |
自社で対応(専門知識を持つ人員が必要) |
ベンダーが対応(法改正や機能アップデートも自動) |
|
セキュリティ |
クローズドな環境で運用できるため、自社のポリシーに合わせた強固な対策が可能 |
ベンダーのセキュリティレベルに依存する |
|
場所の制約 |
原則として社内ネットワークからのみアクセス可能(VPNなどを利用すれば外部アクセスも可能) |
インターネット環境があればどこからでもアクセス可能 |
かつてはオンプレミス型が主流でしたが、近年は初期費用を抑えられ、メンテナンスの負担も少ないクラウド型を導入する企業が増えています。
しかし、独自の業務フローが複雑で大規模なカスタマイズが必要な場合や、セキュリティ要件が非常に厳しい場合には、オンプレミス型が適していることもあります。
両者の特性を理解し、自社にとって最適な提供形態を選択することが重要です。
生産管理システム導入のメリット
 次に、生産管理システムの導入によって得られるメリットをご紹介します。
次に、生産管理システムの導入によって得られるメリットをご紹介します。
業務の効率化ができる
生産管理システムの導入は、製造業における業務プロセス全体を効率化します。
これまで部門ごとに手作業で行われていたデータ入力や帳票作成、情報共有などがシステムによって自動化されるためです。
例えば、受注情報がリアルタイムで生産計画に連携され、各部門は常に最新の状況を基に業務を遂行できます。
これにより、情報の確認や待ち時間といった無駄が削減され、従業員はより付加価値の高い業務に集中することが可能です。
余剰在庫・コスト削減ができる
生産管理システムによって、必要数の在庫を確保しながら余剰在庫を防ぎ、管理にかかるコストを最小限に抑えられます。
生産管理システムでは販売・生産・在庫といった情報を1つのシステムで統合管理できるため、製品の在庫状況をすぐに確認できます。 倉庫内の在庫は、抱えているだけで検品や保管など在庫品管理をするコストがかかるため、余剰在庫は悩みの種となります。生産管理システムを導入することにより、「需要」「供給」「生産能力のバランス」が可視化され、どの程度在庫を確保すべきかの判断ができます。
2024年版『ものづくり白書』によると、デジタル技術の活用により、従業員数が301人以上の企業では74.6%、300人以下の企業では54.2%が「在庫管理の効率化」に効果が出たと回答しています。このように、システムを導入することで在庫を適切に管理することが可能になります。
また、余剰在庫だけでなく、売り切れ防止に役立てることも可能です。買い手がいる場合に製品を提供できなければ、売上を伸ばすことはできないため、その機会損失を防ぐことにも役立ちます。
情報が一元管理できる
生産管理システムでは各業務を一元管理するため、製造に関わる全ての情報を把握することができます。 販売や工程管理など、業務ごとに独自の管理システムを導入していてはそれぞれの部門情報しか把握できませんが、生産管理システムでは部門を超えて「工数」「実績」「販売」「製造」状況をリアルタイムに伝えられます。そのため、組織の土台強化につながります。
実際に、データの一元管理により各部門の状況をリアルタイムで把握できるようになり、業務効率を実現した例をご紹介しております。より詳しい内容にご興味がある方は以下からご覧ください。
また、デジタル技術の導入によるデータの一元化が進むことで、過去の実績も参照できるようになるため、品質の安定や作業の再現性が向上します。『2024年版ものづくり白書』によれば、デジタル技術を活用して「過去と同じような作業がやりやすくなる」と報告している企業は、従業員数301人以上の企業では47.9%、300人以下の企業では44.5%に達しています。
リードタイムの短縮ができる
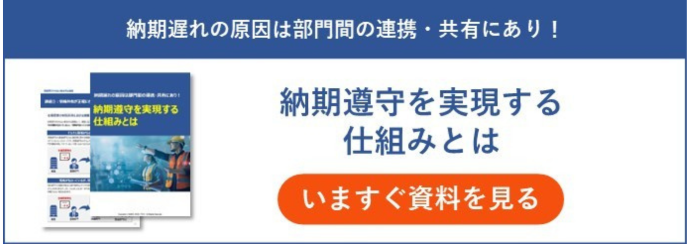
生産管理システムを導入することで、発注から納品までのリードタイムを短縮でき、生産力の向上だけでなく顧客満足度の向上にもつながります。
システム導入によって情報が一元管理されると業務量の調査が容易になり、無駄の特定や改善を実施しやすくなります。また、滞留在庫、生産性、業務効率を分析できるため、不良品率の原因の解明や改善が容易になります。これらによって作業工数の無駄が削減され、現在よりも更にリードタイムを短縮することが可能です。
実際に、『2024年版ものづくり白書』によると、デジタル技術の活用効果として「開発・製造等のリードタイムの削減」を挙げた企業は、従業員数が301人以上の企業では76.1%、300人以下の企業では58.1%にのぼります。
見える化を促進できる
生産管理システムを導入すると、工程進捗や在庫・備品の見える化が実現できます。 見える化が進んでいない現場では、状況把握をリアルタイムに行えないため、他の作業員への確認作業が発生したり、人員配置やスケジュール感が適正化されなかったりと、業務コストに無駄が生じやすくなります。
しかし、システムを導入することで、進捗がリアルタイムで見えるため、必要な指示を早い段階で伝えられます。その結果として、作業工数や業務コストの削減につながります。</p
生産管理システム導入のメリットについてはこちらの記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
次章では、実際に生産管理システムを導入する際の注意点について解説します。
属人性を解消できる
製造現場では、熟練作業者の経験や勘に依存した業務運用が属人性の原因となりがちです。
生産管理システムの導入により、これらの暗黙知を明文化し、標準的な業務プロセスとして定着させることが可能です。
システム内に作業手順、品質基準、判断基準を蓄積することで、誰もが同一水準の業務を実行できる環境を構築できます。
また、過去の製造データや不具合対応履歴をデータベース化することで、ベテラン社員の退職時にも貴重なノウハウが失われるリスクを回避できます。
さらに、新入社員の教育期間短縮や、急な人員変更への柔軟な対応も実現可能です。
生産管理システム選定時のポイント

生産管理システムは、設計・開発・営業といった製造業の全ての工程に関わる非常に重要なシステムであるため、自社に最適なものを選ぶことが大切です。 システムの選び方のポイントとして、以下の3つが挙げられます。
カバーできる業務範囲の観点から選定する
システム選定の1つ目のポイントは、システムで対応できる業務範囲です。導入を検討しているシステムが、求める業務範囲をカバーしているかを確認しましょう。生産管理システムで管理したい業務が、導入したシステムで対応できなかった場合、別システムを導入し直すコストや手間が発生してしまいます。
ただし、機能の種類が多くなるほど、初期費用や運用費用が高額になることがあります。そのため、必要な機能を事前に明確化し、最適なシステムを選ぶことが鍵になります。
得意とする生産方式の観点から選定する
2つ目のポイントは、そのシステムが得意とする生産方式と自社の生産方式が合致しているかです。具体的な生産方式としては、個別受注生産・多品種少量生産に適した生産管理システム、繰返生産・少品種大量生産に適したシステム、そして複数の生産方式に対応できるシステムの3種類があります。
例えば、特注品の製造を行っており、受注ごとに部品の仕様が変わるような企業では、個別受注・多品種少量生産に対応したシステムを選ぶと良いでしょう。
自社の生産管理システム導入の目的と優先順位を決める
上記2つの観点からシステムを選ぶためには、前提としてシステムの導入目的や必要とする機能の優先順位を決めておく必要があります。
例えば、導入後に実際にシステムを使用する部門に、現在の業務の課題をヒアリングするなどして、解決するべき事象とその優先順位を検討しておくことで、どの生産管理システムが自社に最も適したものなのかを判断しやすくなります。
また、既に生産管理関連のシステムを導入している場合は、まずは現システムで対応している業務が検討中のシステムでも対応可能かを必ず確認しましょう。そのうえで、新システムで新たに実現したい要件を織り込んで、導入後の業務対応に支障が出ない、最適なシステムを選定することが重要です。
以下では、生産管理システムを導入する際の手順をより詳細に解説していますので、あわせてご覧ください。
生産管理システムの導入手順
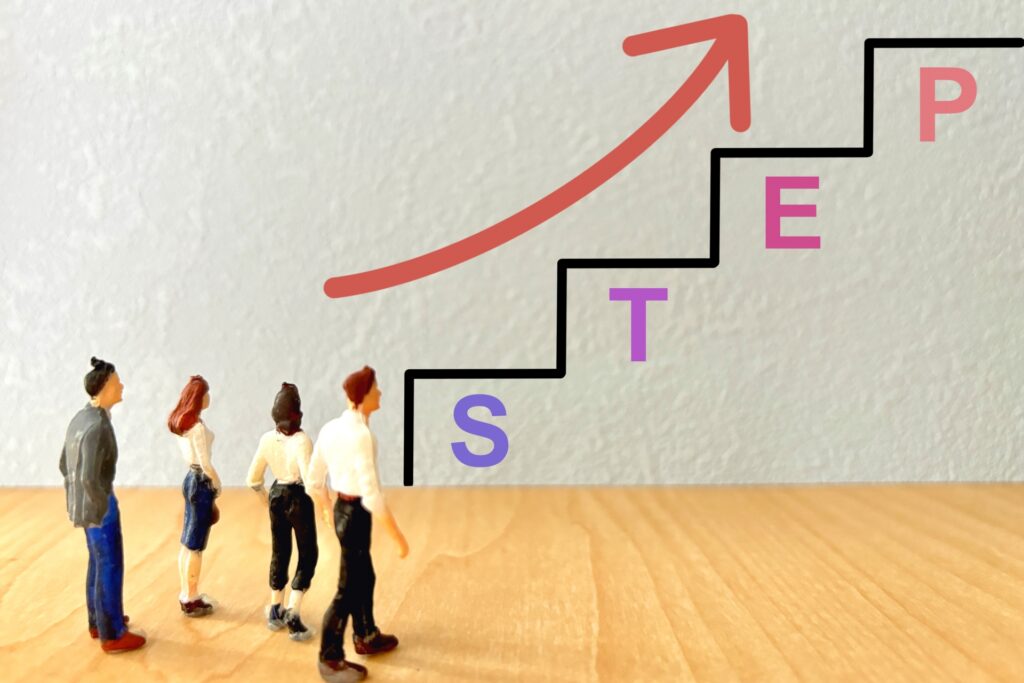 次に、生産管理システムの具体的な導入手順を解説します。
次に、生産管理システムの具体的な導入手順を解説します。
【ステップ1】自社の問題を把握する
導入の第一歩として、現状と課題を正確に把握することが必要です。製造業の場合、納期遅れ、在庫過多、生産コストの増加などが頻繁に起こっていないかなどを評価します。また、従業員の意見やお客さまからの苦情も重要な情報源となります。
これらの情報を基に問題点を把握し、解決すべき具体的な課題をリストアップすることが、最適なシステムを選定するための基盤となります。
【ステップ2】システムの候補を出す
次に明確化した問題を解決できる生産管理システムの候補を挙げます。市場にはさまざまな生産管理システムがあり、大きく分けて中小企業向け、中堅企業向け、大企業向けのシステムがあります。
各システムの機能、コスト、導入後のサポート体制などを比較し、要求を満たす候補を絞り込みます。可能であれば、検討候補としているシステムについて、デモンストレーションなどで確認することで、より具体的なイメージを持つことができます。
【ステップ3】自社の状況からシステムを絞る
候補を絞った後は、自社の具体的な状況を考慮して最終的な選定を行います。選定にあたっては、導入コストだけでなく、ランニングコストも含めた総額、カスタマイズ性、他の既存システムとの互換性、将来的な拡張性などを考慮します。
また、生産管理システムを使用する従業員の意見や、ユーザーインターフェースも重要な選定基準です。
【ステップ4】生産管理システムが浸透するための取り組みを実施する
システム導入が決定したら、社内での浸透を図るための施策を実施します。従業員教育では、システムの基本的な使い方だけでなく、なぜそのシステムを導入したのか、どのように業務が改善されるのかを理解してもらうことが重要です。また、使用した際の意見や感想を収集し、問題が発生した際には迅速に対応を行うことで、システムの効果を発揮できるようにします。
生産管理システムの導入は単に技術的な導入に留まらず、組織全体での変革と捉えるべきです。上記の手順を実行することで、システムの持つポテンシャルを引き出し、企業運営の効率化を実現できます。
生産管理システムを導入する際の注意点
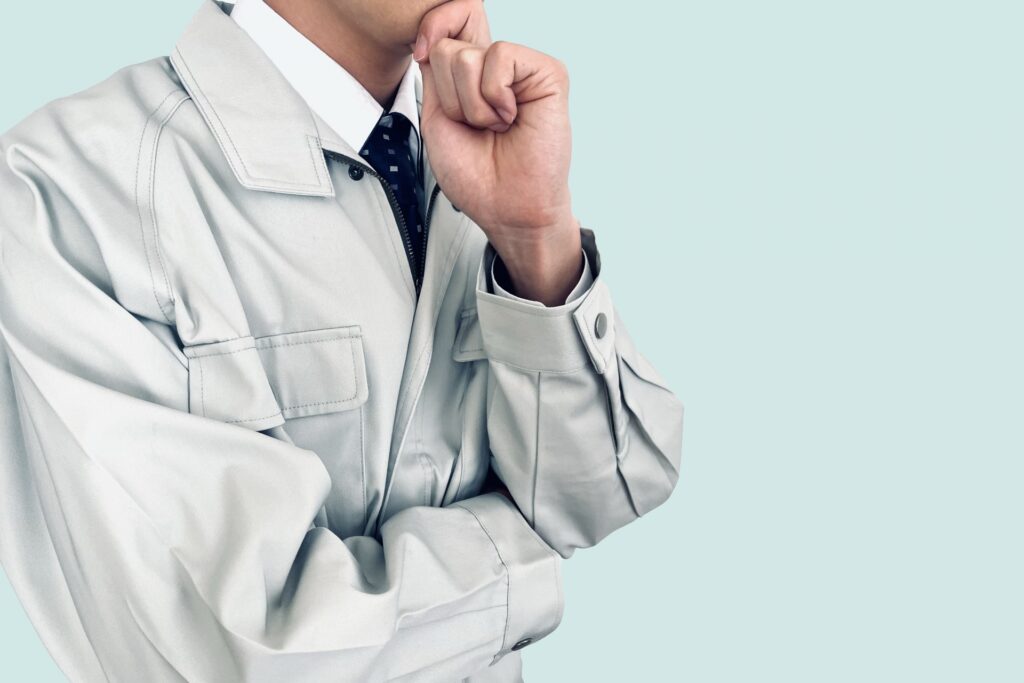 生産管理システムの導入は、企業にとって大きなメリットをもたらす一方で、慎重に進めなければならないポイントが幾つか存在します。
生産管理システムの導入は、企業にとって大きなメリットをもたらす一方で、慎重に進めなければならないポイントが幾つか存在します。
注意点1:費用対効果の見極め
生産管理システムの導入は、高額な初期投資を伴うことが一般的です。導入費用にはハードウェアやソフトウェアのライセンス料、SEによる設定費用やカスタマイズ費用が含まれます。
また、運用開始後もシステムのメンテナンスやアップデートなどのランニングコストがかかるため、これらのコストを事前に把握し、長期的な予算計画を立てることが重要です。
『2024年版ものづくり白書』によると、特に従業員数300人以下の企業において、デジタル技術の活用が、営業利益率の向上に寄与しているケースが多いとの報告があります。
一方で、営業利益率が横ばいまたは減少している企業も存在しています。さまざまな外的または内的要因も考慮する必要があるため一概には言えませんが、デジタル技術の導入が必ずしも即座にコスト削減へ結びつくわけではないことを理解しておくことが重要です。
注意点2:他システムとの連携も検討する必要がある
生産管理システムを導入する際、既存のITインフラや他の業務用ソフトウェアとの連携を考慮する必要があります。考慮する点として、データの互換性やインターフェースの統合などがあります。システムがスムーズに連携できない場合、情報の断片化や入力ミスなど、新たな問題が発生する可能性があります。
具体的な例として、ERPシステムやCRMシステムとのデータ連携が挙げられます。これらのシステムと生産管理システムが一体となることで、企業全体の業務効率が向上しますが、連携に不備があると逆効果になる場合があります。
注意点3:社内に浸透させるための工夫が必須
生産管理システムを導入しても、従業員が新システムを適切に使用できなければ、その効果は半減します。したがって、導入にあたっては従業員教育が不可欠です。また、従業員からの意見を取り入れ、システムの使い勝手を改善することも重要です。
これらの課題に対して適切な対策を講じることで、システムの導入効果を高める必要があります。
業務改善には生産管理システムの導入を
 製造業では現場の業務効率を改善し、可能な限りロスをなくすことで利益を上げることが重要です。しかし、効率化について課題を抱えているケースもあります。 生産管理システムは、製造業における煩雑な作業をシステム上で管理し、効率の良い生産活動を実現するツールです。そのため、なかなか業務効率化が進まない場合は、自社の規模や業種、製造フローに合った生産管理システムの検討をおすすめします。
製造業では現場の業務効率を改善し、可能な限りロスをなくすことで利益を上げることが重要です。しかし、効率化について課題を抱えているケースもあります。 生産管理システムは、製造業における煩雑な作業をシステム上で管理し、効率の良い生産活動を実現するツールです。そのため、なかなか業務効率化が進まない場合は、自社の規模や業種、製造フローに合った生産管理システムの検討をおすすめします。
DAIKO XTECHでは生産管理システム「rBOM」をご提供しています。 導入までのサポートや導入後の伴走体制も充実していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
BOMの統合により情報共有をシームレス化。
リアルタイムな進捗・原価把握を実現する生産管理システム「rBOM」については、
下記よりご覧いただけます。
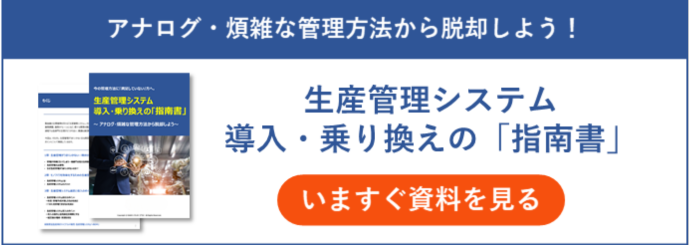
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
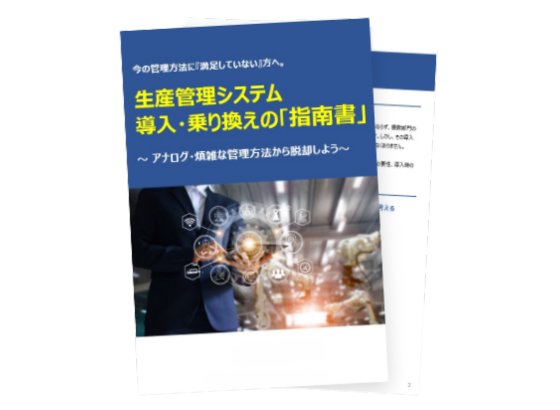
今の生産管理方法に不満がある、という方へ。
生産管理システム 導入・乗り換えの「指南書」