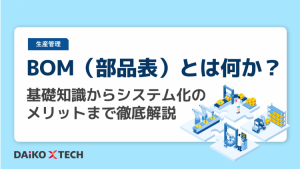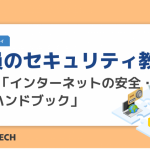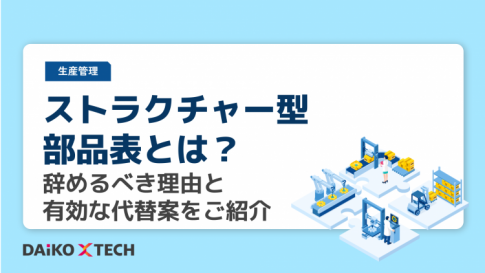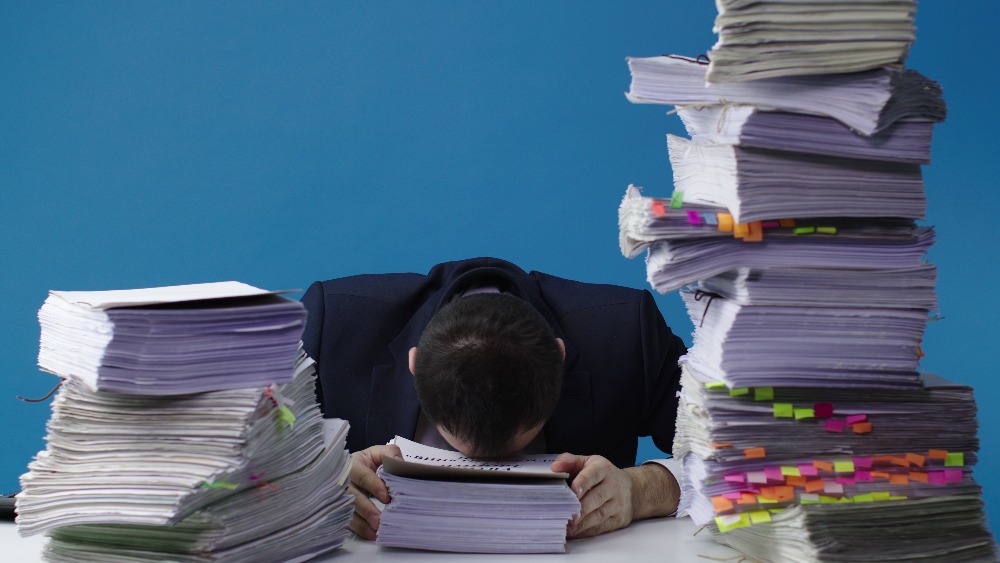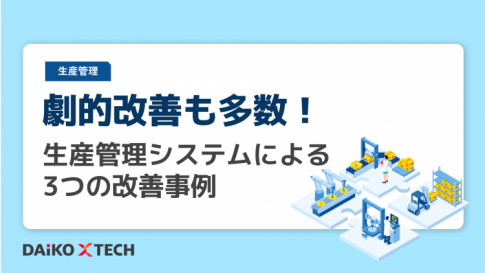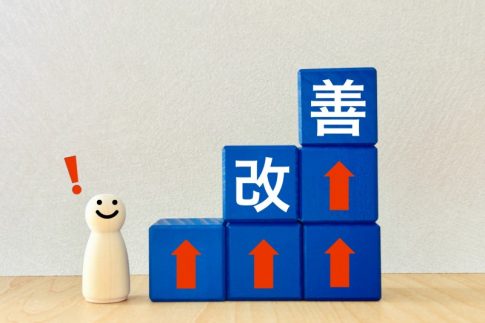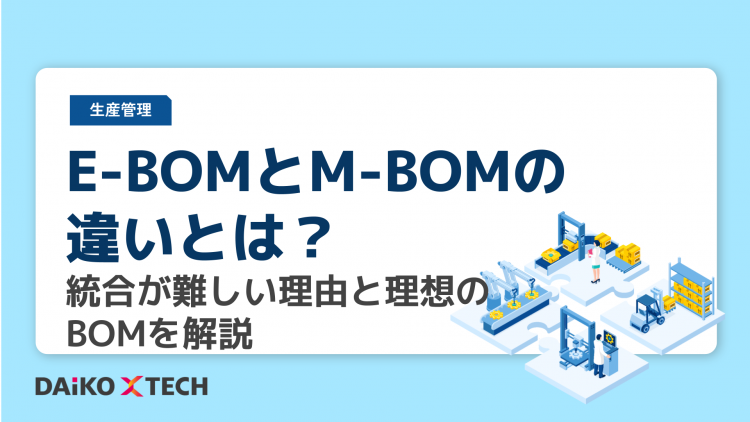
設計と製造の現場にそれぞれ存在する「BOM(部品表)」。情報が断片化すると、設計と現物に食い違いが生じたり、部品在庫の不足を招いたりと思わぬトラブルを招きます。特に、仕様変更の多い「個別受注生産」ではその影響も深刻です。
E-BOMとM-BOMの連携は、個別受注生産企業が共通で抱える課題であるにも関わらず、変わらず解決されないままでした。一体なぜでしょうか。
本記事では個別受注生産の現場において、E-BOMとM-BOMの双方の連携が困難である理由を説明した上で、トラブルのない理想のBOMはどのように構築できるのか、解説します。トラブルなく市場や顧客のニーズに素早く対応できる製造環境を整えたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
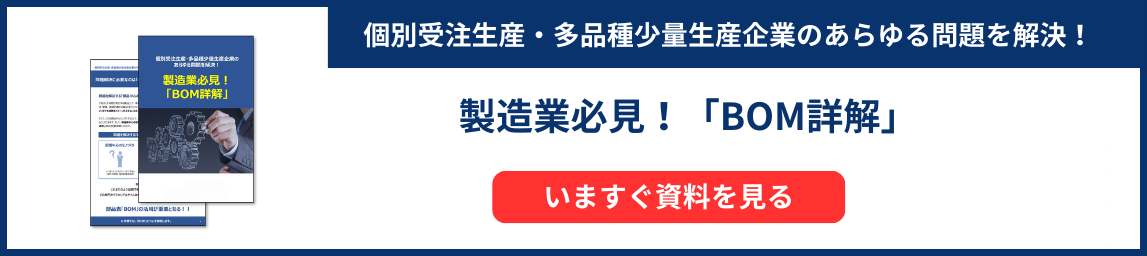
目次
E-BOMとは?
E-BOMとはEngineering-BOMの略称で、設計部門が作成する部品表のことです。E-BOMには、製品の部品やユニット構成を一覧表にまとめたもので、全部品の種類や数がリストアップされており、製品の設計情報や重要な諸元などが含まれています。
部品表(BOM)の主な役割や種類別の特徴、などについては、下記の記事をご覧ください。
E-BOMとM-BOMの違い
似ている言葉にM-BOM がありますが、使用する部門や用途が異なります。
M-BOMとはManufacturing-BOMの略称で、製造部門が使用するための部品表を指し、生産工程に準じて設計部品表を再編したものです。
製造に必要な部品・資材に加え、部品の組立ての順番や加工方法などの工程情報が記載されており、生産スケジューリングや生産指示、部品手配に活用されています。通常は設計を基に製造が行われるので、M-BOMは設計部門からの情報を元に、製造部門が必要な情報を生産工程に準じて追記します。
<E-BOMとM-BOMの違い>
● E-BOM:設計部門が使用。製品を製造する部品やユニット構成をまとめる
● M-BOM:製造部門が使用。製品を製造するために必要な部品や資源をまとめる
BOMを活用する部門が異なるため、それぞれの部門の用途に適したシステムが採用されています。
E-BOMとM-BOMを連携するメリット
各部門で使用されているBOMですが、双方を連携させることで複数のメリットが見込めます。
- 生産拠点間や部門間における情報乖離の解消
- 設計の仕様変更における対応の迅速化、納期の短縮
- 個別原価管理、手配進捗管理の精度向上…など
BOMの情報は設計部門や製造部門だけではなく、購買・調達部門や物流部門、販売部門でも使用されます。顧客の要望に応じて設計・購買・製造する個別受注生産において、部門単位のバラバラで煩雑な情報管理をしていては、情報伝達に遅れや漏れが生じ、納期や品質にまで影響が出てしまいます。
E-BOMとM-BOMの双方を連携させることで、どの部門からでもリアルタイムな情報を得ることができ、複雑化する製品の詳細さえも素早く把握できるようになるため、製品のスピーディな供給が実現できます。
しかし、BOMを連携させるのは容易ではなく、いくつかの課題をクリアしなければなりません。
E-BOMとM-BOMを統合したくても、できないのはなぜか?
そもそもE-BOM(設計部品表)とM-BOM(製造部品表)はなぜ統合できないのでしょうか。その背景には、次のような要因があることが挙げられます。
品目コードがバラバラ
設計部門から見ると一つの品目であっても、製造部門では複数の品目(中間部品)で管理している場合があります。こうしたケースでは、E-BOMとM-BOMで品目コードが統一されていないことが多く、BOMの統合は困難を極めます。これらの情報が共有できていないと、製造部門では都度「部品表の翻訳作業」が発生することになるのです。
拠点が離れている/システムが別々になっている
各拠点で異なったシステムを導入しており、各BOMがバラバラに管理されているケースが見受けられます。こうした状況では、データの乖離に加えて管理プロセスも異なることも多いため、これらの事情が統合を一層困難にしているともいえます。
通常のサプライヤ以外から部品を購入する場合がある
急な仕様変更が入った場合、工場では一時的に普段とは別のサプライヤから部品を調達するなど代替部品を使用するケースがあります。そうした場合、急遽、素材や品番の変更によりM-BOMの情報も修正する必要があります。このような変更によって生じる差異は、E-BOMとM-BOMの統合を困難にする一つの要因にもなりえます。
M-BOMは仕様変更をすぐに反映できない
本来、設計部門でE-BOMの情報を更新した場合(例:改版、品質改善など)には、M-BOMもそれに連動させる必要があるでしょう。しかし、工場には部品在庫がある都合上、M-BOMをすぐに切り替えられないことがあります。こうした積み重ねが、やがてE-BOMとM-BOMの統合を困難にしていっているといっても過言ではありません。
では、こうした背景を踏まえ、BOMをどのように扱うことが必要なのでしょうか。
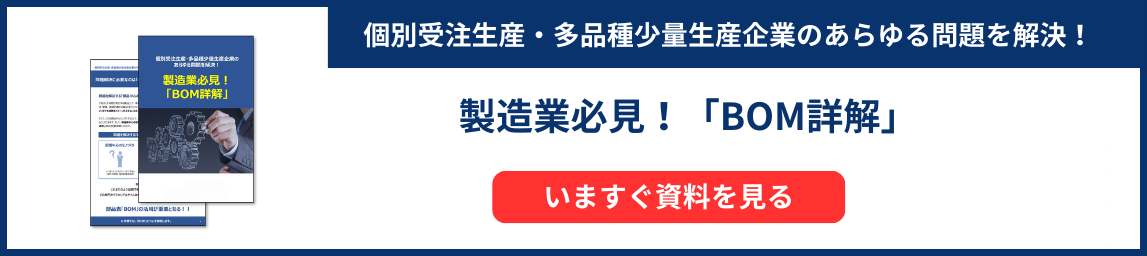
E-BOMとM-BOMの統合に必要なこと
E-BOMとM-BOMの統合を図る上で鍵となるのが、「製番別サマリー型部品表」の採用です。製番別サマリー型部品表とは、「製番」という管理番号を振った上で任意の階層を作成し、設計変更履歴の管理を可能とした部品表のこと。この方法によって、ストラクチャー型部品表で見られた課題を解消しつつ、効率的な管理を実現することができます。
ストラクチャー型から製番別サマリー型へ
従来の「ストラクチャー型部品表」では、初めに品目情報を登録し、親子関係を定義した上で工程情報を付加する必要がありました。そのため、一つの部品が異なるだけで別機種として扱う必要があり、BOMの管理が煩雑化しやすかったのです。そこで、「製番別サマリー型部品表」を採用し、設計変更履歴の管理を可能とすることで、仕様変更が多い個別受注生産に柔軟に対応が可能になります。
標準BOMと製番BOMで分けて考える
この手法でポイントとなるのが、あるべきBOMのマスタ(標準BOM)と、現実のBOM履歴データ(製番BOM)を区別することです。製造の現場では、予定よりも多くの部品が必要になったり、急な理由で代替品が必要になったりすることがあります。だからこそ、それらの履歴も含めて管理できるような方法を予め考慮することが欠かせません。
E-BOMとM-BOMを統合進化させるBOMシステム
乖離が起きるE-BOMとM-BOMを統合するためには、単に物理的な統合を目指すのではなく、現場の業務に則した発展的な統合が理想です。
そこで必要なのがE-BOMとM-BOMを統合進化させた「BOMシステム」の導入です。
そもそもBOMシステムとは、部品表を効率的に管理するための仕組みなのですが、パターン化ができなかった図面中心のモノづくりから、業務効率化を図り、部門や工程毎の効率化に取り組んだ結果、E-BOMとM-BOMといった、部門毎のBOMが生み出されたという経緯があります。
しかし、これからは部門毎の業務改革ではなく、あらゆる部門を巻き込んだ全社改革が必要であり、図面中心から部品中心のモノづくりに移行する必要があります。それを可能にするのがBOMシステムです。それでは、改めて、BOMシステムについて振り返ってみましょう。
BOMシステムの機能
BOMシステムとは、部品表を効率的に管理する仕組みのことです。製品に必要な部品情報を統合的に管理でき、各部門へのスムーズな情報提供を実現します。
BOMシステムの基本的な機能としては、以下の通りです。
| BOMシステムの機能 | 内容 |
| BOM(部品表)管理機能 |
|
| BOM(部品表)更新機能 |
|
| 在庫管理機能 |
|
| 製品管理機能 |
|
一般的なBOMの種類
BOMの種類は、E-BOMやM-BOM以外にも存在し、「登録方法」と「用途」に分けて見ることも可能です。
| 登録方法による種類 | 特徴 |
| サマリー型 | 製品を構成する部品や原材料の所要量を一覧にまとめる |
| ストラクチャー型 | 製品の構成をツリー形式の階層構造で管理する |
| 用途による種類 | 特徴 |
| E-BOM(設計部品表) | 製品に必要な部品や技術情報をまとめた一覧表 |
| M-BOM(製品部品表) | 製品を構成するために必要な部品や工程、生産資源などをまとめた一覧表 |
| 購買BOM | 部品の購買に関する情報をまとめた一覧表 |
| サービスBOM | 製品サービスや保守メンテナンスの情報をまとめた一覧表 |
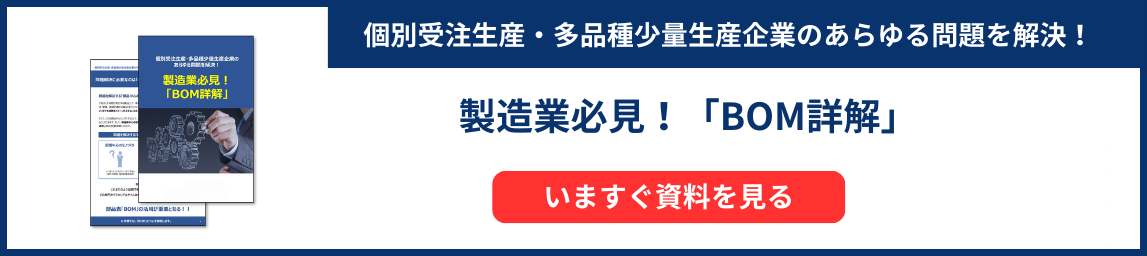
おすすめのBOMシステムは「rBOM」
これまでBOMシステムの基本機能や、一般的なBOMの種類について見てきましたが、おすすめはDAIKO XTECHが提供する「rBOM」です。
「rBOM」は、今回ご紹介した「製番別サマリー型部品表」を採用した国内統合BOM導入数ナンバーワン(導入社数200社)のシステムです。rBOM導入により、「標準BOM」と「製番BOM」の統合管理が実現でき、流用設計による効率化が可能になります。
また、rBOMでは販売管理と生産管理を一つのデータベースで管理しているため、設計・製造のみならず、営業、購買との連携を強化することも可能です。そのため、仕様変更の多い「個別受注生産」の現場に最適な仕組みといえます。
E-BOMとM-BOMの管理におけるトラブルを防止するための、理想のBOM管理を実現し、設計・製造の双方に最適な仕組みをお探しの企業さまは、個別受注向けハイブリッド販売・生産管理システム「rBOM」の活用をご検討ください。「rBOM」で「部品表中心のモノづくり」を実現しましょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
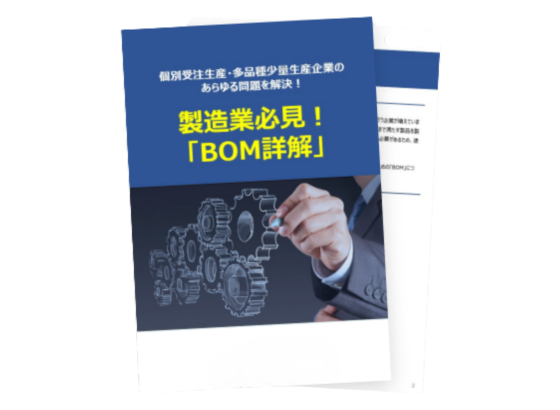
個別受注生産・多品種少量生産企業の あらゆる問題を解決!
製造業必見!「BOM詳解」

- この記事を監修した人
- 入社後15年間、長野支店にてシステムエンジニアとして活動。
運送業、倉庫業のお客さまを中心に担当し、業務システム構築からインフラ環境構築等の経験を積む。
その後、製造業のお客さまも担当し、rBOM導入のプロジェクトにも関わるように。
16年目に現部門に異動し、rBOM全国支援の担当者となる。
現在はrBOMだけではなく、製造業全般のソリューション提案を手掛けている。
料理が趣味、これからお菓子作りにも挑戦しようか迷っている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部 - 田幸 義則