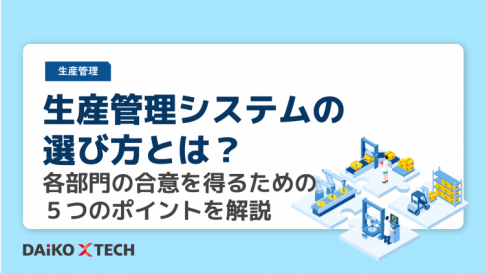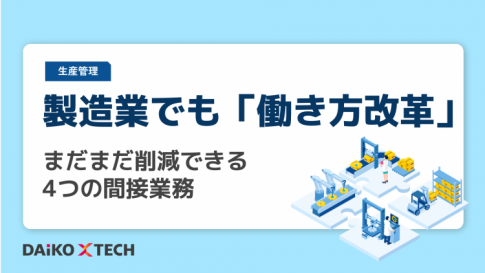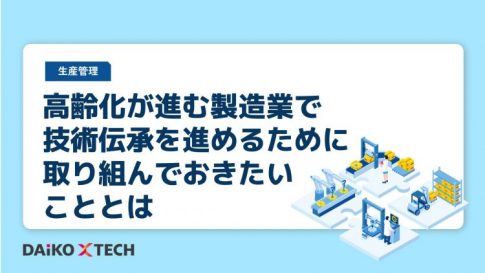PSI管理とは、在庫過多や欠品といった課題を未然に防ぐための管理手法です。
製造や在庫、販売の業務に携わる中で、「PSI管理って具体的にどう進めればいいの?」「在庫を適正化したいけど何から始めればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
PSI管理は、手順や導入方法を理解しないまま取り組むと、かえって現場が混乱してしまうことがあります。
本記事では、PSI管理の基本的な考え方から、導入ステップ、成果につながる実践ポイント、さらには支援ツールまでを徹底的に解説します。
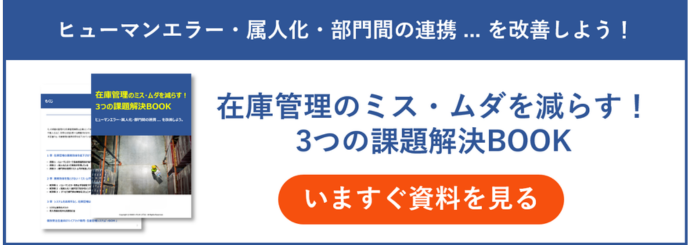
目次
PSI管理とは

PSI管理とは、「生産(Production)」「販売(Sales)」「在庫(Inventory)」の3つの要素を連動させて、無駄のない在庫管理や生産・販売の最適化を図る手法です。各工程を分けて考えるのではなくトータルで捉えることで、モノの流れをスムーズにし、利益を最大化できます。
PSIの構成(生産・販売・在庫)
PSI管理は3つの計画を組み合わせることで、在庫の過不足を防ぎ、効率的な生産と販売を実現する仕組みです。
生産計画(P)は、製品を「いつ・どれだけ作るか」を事前に決める工程であり、安定した供給体制を築くための出発点です。
販売計画(S)は、その生産計画に基づき「いつ・どれだけ売れるか」を見定め、需要の動きを予測して具体的な販売目標を設定します。
そして在庫計画(I)では、販売や生産のタイミングに合わせて「どれだけ在庫を持つか」を調整します。
これらの計画が連携していないと、販売量に対して生産が追いつかなかったり、逆に在庫が余ってしまったりといった問題が起こりかねません。
また、在庫が過剰になると保管コストがかさみ、反対に欠品が起きれば販売機会を失うリスクも高まります。
そのため、3つの計画をつなぎ、情報を一元化して管理することが安定した業務運営に求められます。
PSI管理が注目される背景

近年、製造業や小売業を取り巻く環境は大きく変化しており、PSI管理の重要性がますます高まっています。
ここでは、なぜ今PSI管理が必要とされているのか、その背景となる3つの変化について解説します。
需要変動の激化とサプライチェーンの複雑化
市場の需要は、以前に比べて急激に変動する傾向が強まっています。
季節変動に加えてトレンドの変化や災害、感染症などの外的要因によって、消費者の購買行動が予測しづらくなってきました。
加えて、グローバル化の進展によりサプライチェーンも複雑になり、製造・供給までのリードタイムや取引先の状況にも注意を払う必要があります。
こうした環境の変化に柔軟に対応するには、販売・生産・在庫の各部門が常に情報を連携させながら、変化に即応できる体制を整えておくことが欠かせません。
在庫の適正化ニーズの高まり
企業にとって在庫は「資産」である一方、「コスト」でもあります。
過剰な在庫は保管費用や廃棄リスクを増やす一方、在庫不足は販売機会の損失につながります。
こうした背景から、いかに適正な量だけを在庫として持つかが企業経営の鍵となっているのです。
とくに製造業や小売業では、需要の読み違いや仕入れのタイミングミスが大きな損失を生むことも珍しくありません。
そのため、販売計画と生産計画、在庫量を一体で考えるPSI管理のニーズが高まっています。
在庫を抱えることのリスク
過剰な在庫は、保管コストの増加や保管スペースの圧迫につながるだけでなく、商品の品質劣化や陳腐化といったリスクも生み出します。
とくに賞味期限や型落ちの影響を受けやすい商品では、在庫回転率の低下が大きな損失につながる可能性があります。
また、在庫が滞留することでキャッシュフローが悪化し、経営資源を有効に活用できない事態も招きかねません。
こうした在庫リスクを軽減し、効率的な経営を実現するためにも、部門間での情報共有をベースとしたPSI管理の導入が求められています。
PSI管理のメリット

PSI管理を導入することで、在庫ロスや無駄なコストを防ぎながら、企業全体の運用効率を大きく向上させることができます。
ここでは、PSI管理によって得られる4つのメリットを解説します。
欠品と過剰在庫を防止できる
PSI管理により計画を一元化することで、欠品や過剰在庫などの在庫トラブルを防げます。
販売実績や需要予測に基づいて生産・仕入れを調整できるため、必要なタイミングで必要な量の商品を確保できます。
たとえば、季節によって需要に大きな波がある商品でも、PSI管理を活用することで売れ残りを最小限に抑え、欠品による販売機会の損失も防ぐことが可能です。
さらに、商品回転率が向上すれば、保管コストや廃棄ロスの削減にもつながります。
これらの管理が適切に行われることで、企業の利益構造が改善されるのはもちろん、経営判断もスムーズになる点が大きな強みです。
サプライチェーン全体の効率化につながる
PSI管理では、各部門の情報をリアルタイムで共有・連携することが基本となるため、サプライチェーン全体の可視化と効率化が実現します。
販売部門が出した予測に基づいて、生産部門や在庫部門が連動して動くことで、各工程間の調整ミスや手戻りを削減できます。
製造現場が販売動向を事前に把握できれば、材料の調達も計画的に行えるため、リードタイムの短縮が可能です。
また、情報が一元管理されていれば、外注先や取引先とのやり取りもスムーズになり、納期遅れや在庫過多といったリスクも回避しやすくなります。
こうした一連の流れがスピーディに進むことで、全体としての業務負荷が軽減され、コスト削減と顧客満足度の向上の両立が可能になります。
生産効率向上とコスト削減が期待できる
販売計画と連動して生産計画を立てると、生産のムダを減らせます。
PSI管理では、販売見込みに応じて生産量を調整できるため、生産現場の負担軽減にもつながります。
これにより、従業員の働き方の安定化や、生産スケジュールの平準化が実現可能です。
さらに、余剰な生産を避けることで、原材料のロスや仕入れの無駄も抑制できます。
製造業では、日々の受注動向に応じて細かく生産計画を調整することが求められますが、PSIを活用すればその対応力が大きく向上します。
顧客満足度の向上につながる
顧客が欲しい商品を、必要なときに確実に届けられれば、その企業への信頼度は自然と高まります。
PSI管理を通じて需要予測の精度が上がり、在庫調整や生産計画が適切に行われるようになると、納期の遅延や欠品が大幅に減少します。
結果として、顧客は「いつでも安心して注文できる企業」として認識し、リピート購入や紹介につながる可能性が高まるでしょう。
とくに、BtoB取引などでは納期遵守が信頼関係の鍵となるため、PSIによる安定供給の仕組みは重要です。
また、柔軟な対応力があることで急な注文や需要の変化にも即座に対応でき、顧客の期待を超えるサービス提供が可能となります。
PSI管理の導入手順

PSI管理を導入する際は、単に在庫を管理するのではなく、販売や生産といったプロセス全体を計画的に連動させることが重要です。
以下では、導入時に押さえるべき6つのステップを順に解説します。
①需要予測
PSI管理の最初のステップは、将来の販売数量を予測することです。
需要予測は、販売・生産・在庫すべての計画の土台となるため、精度が重要です。
主に過去の販売データや季節要因、販促スケジュール、市場動向などをもとに分析を行い、どの製品がいつどれだけ売れるのかを見積もります。
予測が不正確であると、生産・在庫計画も連鎖的に狂ってしまうため、現場とマーケティング部門との情報共有が不可欠です。
高精度な需要予測が、安定したPSI管理の第一歩となります。
②販売計画の策定
需要予測の結果をもとに、具体的な販売計画を立てます。
ここでは、「どの商品を、どの時期に、どのくらい売るか」という販売目標を明確にし、それを達成するための販促施策や販売チャネルの調整なども含めて計画します。
販売計画は生産と在庫の管理に直結するため、曖昧なままでは全体のバランスが崩れかねません。
月単位・週単位で数値目標を設定し、必要に応じて現場とすり合わせながら精度を高めることが求められます。
③生産計画の立案
販売計画が決まったら、それをもとに生産計画を立てます。
この段階では、生産ラインの能力やリードタイム、原材料の在庫状況などを踏まえながら無理のないスケジュールを組みます。
また、生産ロットの最適化や設備の稼働率なども考慮し、コストと効率のバランスを取ることが重要です。
過不足のない計画にするためには、販売側との情報共有と生産現場の実態を反映させた設計がポイントになります。
④在庫計画と最適化
生産計画が整ったら、それに基づいて在庫量を調整します。
ここでの目標は、欠品を避けながらも過剰在庫を抱えないようにすることです。
具体的には、安全在庫の設定や在庫回転率の見直し、仕入れタイミングの最適化などが含まれます。
販売や生産の動きに応じて柔軟に対応する必要があるため、在庫データのリアルタイム把握や分析が鍵となります。
適切な在庫計画により、保管コストや廃棄リスクを抑えることが可能です。
⑤PSI計画表への反映と実績管理
ここまでの各計画を、PSI計画表にまとめて可視化します。
PSI計画表は販売・生産・在庫の全体像を一つのシートで確認できるようにしたもので、部門間の連携と進捗管理に役立ちます。
定期的に実績と計画の差異をチェックし、必要に応じて調整を加えることが大切です。
PDCAサイクルをまわすことで、より精度の高い計画運用が実現できます。
⑥分析・検証による改善
最後に全体の振り返りと改善活動を行いましょう。
計画と実績のズレがなぜ起きたのかを分析し、次回の計画に生かすことで継続的な精度向上が期待できます。
特に、需要予測や在庫設定の精度、部門間の情報共有体制に注目し、ボトルネックとなる部分を特定・解消していくことが重要です。
PSI管理を成功させるポイント

PSI管理は、計画を立てただけでは十分な効果を発揮しません。
現場に定着させ、継続的に成果を出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
下記で詳しく解説します。
拠点間の情報共有と一元管理を徹底する
PSI管理の精度を高めるためには、本社・工場・倉庫・営業所といった各拠点の情報をリアルタイムで共有し、一元的に管理することが不可欠です。
情報が部門ごとに分断されていると、販売数や在庫数に食い違いが生じやすく、全体最適が実現しにくくなります。
クラウドツールなどを活用して、すべての関係者が同じ数値を見ながら意思決定できる環境を整えることがスムーズな運用の鍵です。
正確なデータをもとに需要を予測する
需要予測はPSI管理の出発点であり、精度がそのまま計画の信頼性に直結します。
過去の販売実績だけでなく、季節性や販促イベント、外部の市場動向なども加味して予測を立てることが大切です。
PSI管理は人の勘に頼るのではなく、POSデータや顧客データ、AIによる予測モデルなど、客観的な数値に基づいた判断が求められます。
データを正しく扱うことで、需給バランスのブレを防ぎやすくなります。
柔軟に生産・在庫調整をする
需要は常に一定とは限らないため、販売や生産の計画も柔軟に見直せる体制が必要です。
急に需要が落ち込んだ場合には生産を一時的に止めたり、逆に想定以上に売れ行きが伸びた場合には、追加生産や在庫の再配分で対応する必要があります。
こうした判断を速やかに行うには、日々の数値の変化に目を配りながら、関係部署間で機動的に連携を取ることが重要です。
分析と検証を通じて精度を向上させる
計画と実績のズレは、必ずどこかに原因があります。
それを放置せず、しっかりと分析・検証することで、次の計画精度が向上していきます。
たとえば、販売計画より大幅に少ない売上だった場合は、予測手法に問題がなかったかを見直す必要があります。
PDCAを回し続けることで、組織としての予測力と対応力が磨かれ、安定したPSI運用が実現できるようになります。
PSI管理で在庫の最適化と経営の安定化を目指そう

PSI管理は、販売・生産・在庫を一体で管理することで、在庫の最適化と経営の安定化を実現できる強力な手法です。
需要予測から計画、実行、検証までを一貫して行うことで、欠品や在庫過多といったリスクを防ぎ、顧客満足度の向上やコスト削減にもつながります。
PSI管理は精度の高いデータ活用と部門横断の連携、そして継続的な改善が大切なポイントです。
本記事を参考にPSI管理を導入・運用し、持続的な事業成長を目指しましょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
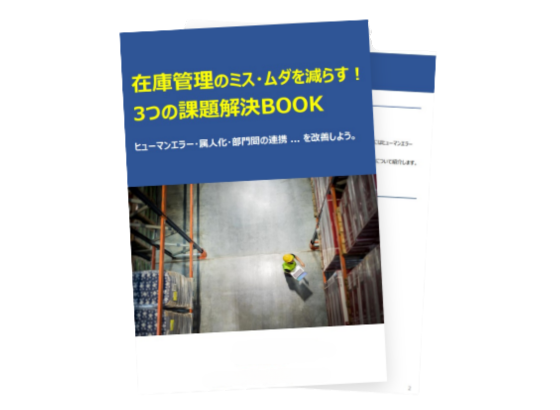
ヒューマンエラー・属人化・部門間の連携 ... を改善しよう。
在庫管理のミス・ムダを減らす!
3つの課題解決BOOK