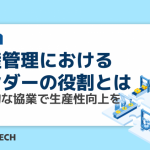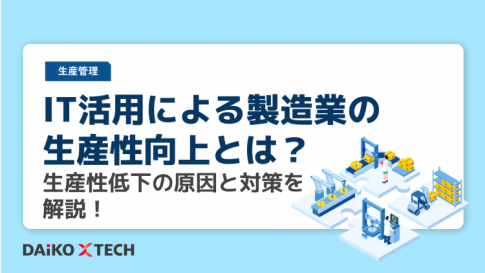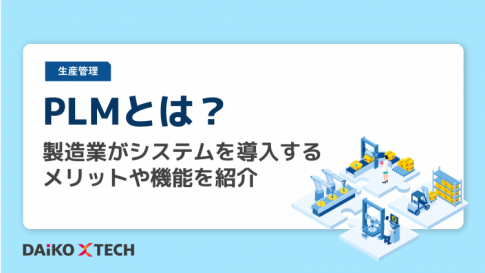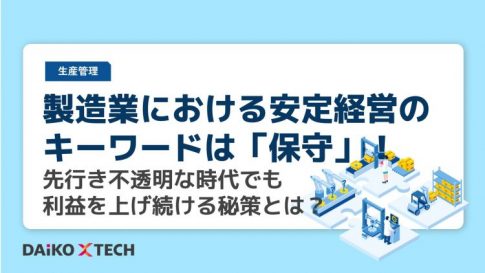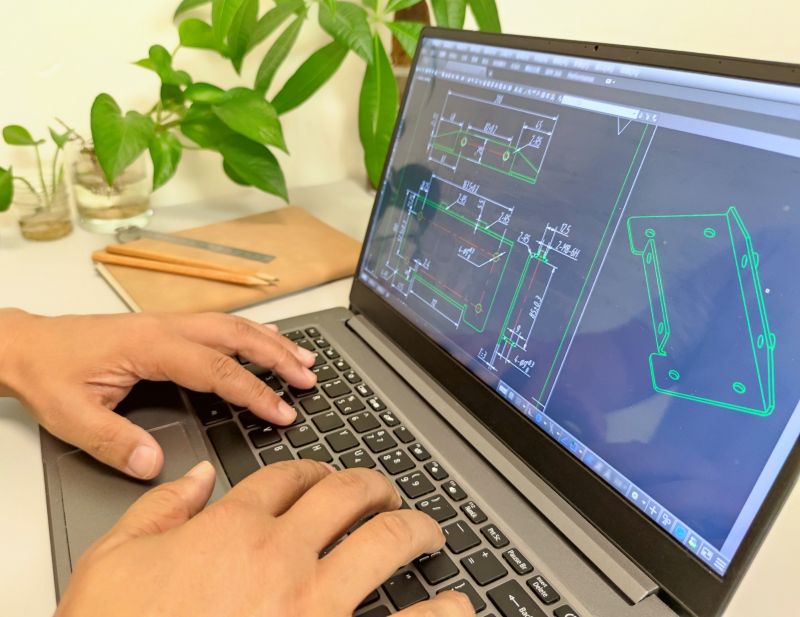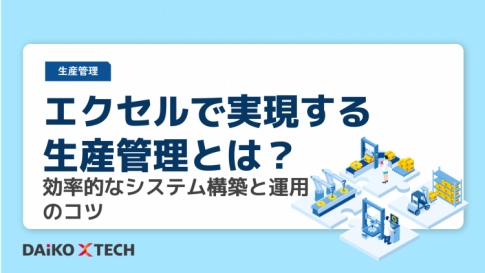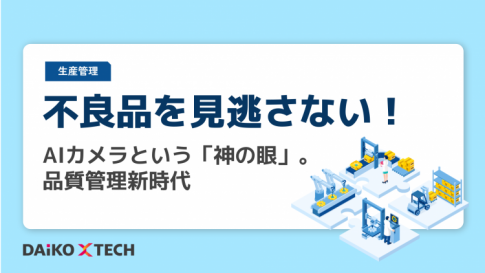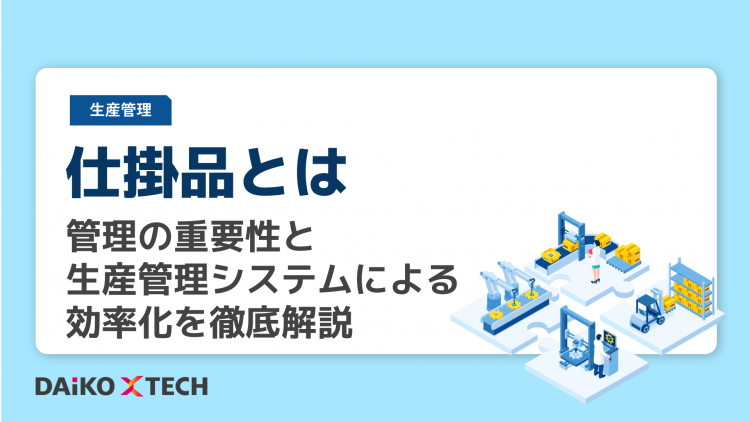
仕掛品とは、製造途中段階の製品を指します。 原材料費や労務費などのコストが発生していますが、まだ完成しておらず、販売できない状態です。
仕掛品の管理は製造業の会計や在庫管理において非常に重要です。
本記事では、仕掛品の定義から始まり、半製品との違い、棚卸資産としての計上方法、管理における課題を詳しく説明しています。また、生産管理システムによる効率化まで、仕掛品に関するあらゆる情報も網羅的に解説します。
仕掛品管理を最適化し、企業の収益力向上を目指してください。
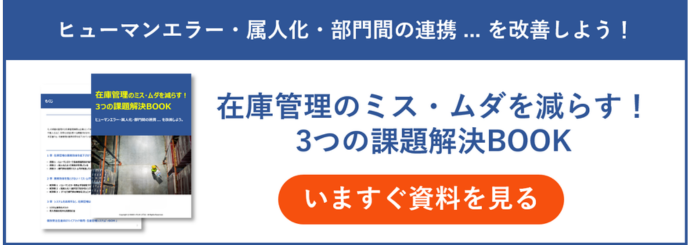
目次
仕掛品とは|半製品との違い

製造業において、仕掛品と半製品はどちらも製造過程における重要な要素です。しかし、定義や特性は違います。製品の製造原価を正確に把握し、効率的な在庫管理を行うためには、双方の違いについての理解が不可欠です。
以下では、仕掛品と半製品それぞれの定義、特徴について詳しく解説するとともに、企業における適切な在庫管理の重要性について説明します。
仕掛品とは
仕掛品とは、企業会計において、販売を目的とした製品の製造過程で、まだ完成していない状態のものを指します。言い換えれば、製造が始まっており、原材料費や労務費などのコストがすでに投入されているものの、最終的な製品として完成し、販売できる状態にはなっていないものです。
例えば、スマートフォンであれば、部品は揃っているものの、まだ画面が取り付けられていない状態です。衣類であれば、裁断や縫製は終わっているものの、ファスナーが取り付けられていない状態などが仕掛品に該当します。
仕掛品は、企業の会計上、棚卸資産として扱われます。仕掛品にも製造原価が含まれており、将来の収益獲得に貢献する可能性があるためです。
しかし、仕掛品は完成品ではないため、そのままでは販売できません。そのため、企業は仕掛品の在庫管理を適切に行い、過剰な在庫を抱えないことが必要です。過剰な在庫は、保管コストの増加や、陳腐化による損失のリスクを高める可能性があります。
また、仕掛品は、製造原価を計算する上でも重要です。製造原価は、期首の仕掛品在庫と、期中に発生した製造費用から、期末の仕掛品在庫を差し引いて計算されます。
つまり、仕掛品は製造原価を正確に算出するために欠かせない要素です。 原材料費や労務費などの製造費用は、完成品だけではありません。仕掛品にも含まれているため、期首と期末の仕掛品在庫を把握すると、その期間に実際にかかった製造原価を計算できます。
正確な原価計算は、企業の利益を正しく把握し、適切な経営判断を行う上で非常に重要です。 また、仕掛品の数量把握は、在庫管理の効率化にもつながります。 過剰な仕掛品は在庫コストの増加や資金繰りの悪化を招く一方、不足は生産の遅延を引き起こす可能性があります。
仕掛品は企業の会計や在庫管理において重要な要素であり、適切な管理を行うことが企業の収益力向上につながります。
半製品とは
半製品とは、企業会計において、製造過程の中間段階にある製品で、それ自体で販売可能な状態にあるものを指します。言い換えれば、完成品として最終的な形にはなっていないものの、ある程度の加工が施され、そのままでも市場に流通させ、販売できる製品のことです。
例えば以下が半製品に該当します。
- 瓶詰めされたジャムにラベルが貼られていない状態
- 木工品製作企業が製造した板材そのもの
- 刺繍などの装飾が施されていない無地のバッグ
以上はさらなる加工を加えることで完成品しますが、現状のままでも販売できます。
半製品は仕掛品と混同されがちです。しかし、仕掛品はそれ自体では販売できない点で明確に区別されます。仕掛品はあくまで製造途中のものであり、さらなる加工を経て完成品となる必要があります。
会計上、半製品は仕掛品と同様に棚卸資産です。半製品にも製造原価が含まれており、企業の資産として計上する必要があるためです。
企業は、半製品の在庫管理を適切に行うことで、過剰な在庫や在庫不足を防ぎ、円滑な生産活動ができます。また、半製品の状態でも販売できるのは、顧客のニーズに合わせて柔軟に製品を提供できる点で、企業にとって大きなメリットです。
仕掛品の棚卸計上方法

仕掛品は、棚卸資産として期末に評価し、貸借対照表に計上する必要があります。正確な棚卸計上を行うためには、仕掛品を適切に把握し、その価値の評価が重要です。
具体的には、以下の3つの要素を明確にしてください。
工程
仕掛品は、完成品に至るまでの製造過程のどの段階にあるのかの把握が非常に重要です。製造工程をより細かく区分し、それぞれの工程における仕掛品の状態を明確に定義しておかなければなりません。
例えば、ある製品の製造工程が材料加工、組立、塗装、検査の4つの工程で構成されているとします。この場合、各工程の終了時点で、仕掛品を材料加工完了、組立完了、塗装完了のように、具体的な状態を示す名称で区分します。
工程を明確にすると、各工程に投入された費用(材料費、労務費、経費など)をより正確に把握でき、仕掛品の原価を適切に計算可能です。
品番
仕掛品を識別するために、品番を付与します。品番は、製品の種類や工程、仕様などを識別できるような体系的なものにしなければなりません。
例えば「製品A-材料加工完了」「製品A-組立完了」のように、製品の種類と工程を組み合わせた品番を付与すると、仕掛品を一意に識別し、管理できます。
原価
仕掛品の原価は、各工程に投入された材料費、労務費、経費などを集計して計算したものです。
材料費は各工程で使用された原材料の費用を集計、労務費は各工程に携わった作業員の賃金や給与を集計したものです。経費は各工程で発生した製造間接費(工場の賃借料、光熱費など)を適切な方法で配賦し、集計します。
原価計算の方法としては、個別法、先入先出法、総平均法など、さまざまな方法があります。企業は、自社の事業内容や規模、管理の複雑さなどを考慮して、適切な方法の選択が必要です。
仕掛品管理の課題
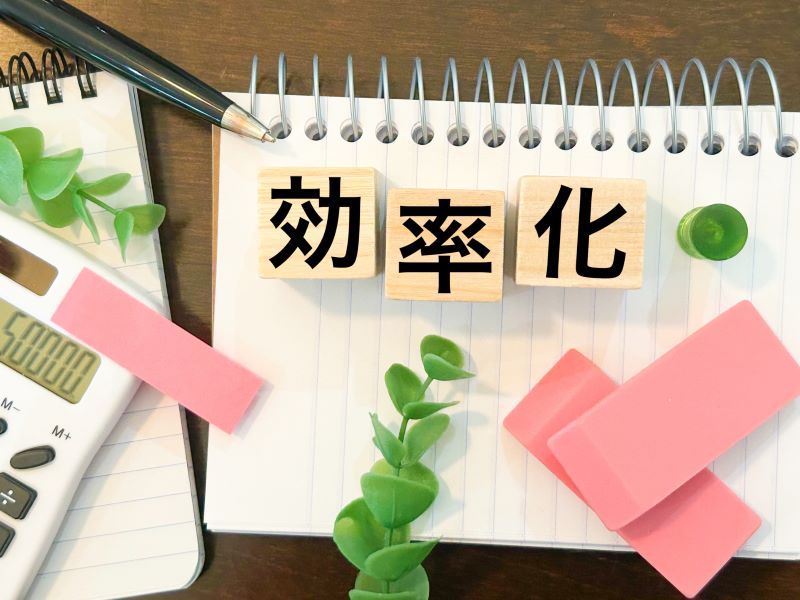
仕掛品は、製造業における在庫管理において、特有の難しさを抱えています。完成品や原材料とは異なる性質を持つ仕掛品は、管理を複雑化させ、さまざまな課題を生み出す要因です。
具体的には、以下の3つの課題が挙げられます。
正確な数量把握が困難
仕掛品は、完成品とは異なり、製造工程の途中に存在し、形状や状態が刻一刻と変化していくため、正確な数量の把握が非常に困難です。
目視によるカウントは、どうしても人為的なミスが発生しやすく、正確性に欠けるだけでなく、作業者の負担も大きくなってしまいます。製造現場の作業員は、本来の業務に加えて、仕掛品の数量カウントなどの煩雑な作業に時間を割かなければならず、生産性の低下にもつながりかねません。
仕掛品は、製造ライン上を常に移動していたり、複数の工程にまたがって保管されていたりするため、所在の特定自体が容易ではありません。仕掛品の形状や材質によっては、バーコードやタグを貼るのが難しい場合もあり、ツールを用いた数量管理ができないケースもあります。
例えば、液体状の化学薬品や、高温の金属部品など、特殊な条件下で取り扱われる仕掛品には、一般的なバーコードやタグは適用できない場合が少なくありません。仕掛品特有の性質が、数量把握をより一層困難にしています。
原価計算の複雑さ
仕掛品の原価計算は、完成品に比べてはるかに複雑です。なぜなら、仕掛品には、材料費、労務費、経費など、さまざまな費用が工程ごとに投入されており、費用を正確に把握し、各工程に適切に配賦しなければならないからです。
特に、製造間接費の配賦は、適切な基準を設定するのが難しく、原価計算の精度に大きな影響を与える可能性があります。製造間接費には、工場の賃借料や光熱費、製造設備の減価償却費など、さまざまな費用が対象です。しかし、費用をどのように仕掛品に配賦するかは、企業によって判断が異なります。
例えば、作業時間や機械の使用時間、生産数量などを基準として配賦する方法がありますが、どの基準を採用するかによって、原価計算の結果は大きく変わってきます。
仕掛品の数量把握が困難な場合は、原価計算の精度低下も避けられません。例えば、ある工程で実際には100個の仕掛品が生産されていたにもかかわらず、数量把握のミスで80個と記録されていた場合です。その工程に投入された費用は、80個の仕掛品に配賦されてしまい、原価計算に誤差が生じてしまいます。
過剰在庫のリスク
仕掛品の過剰な在庫は、保管スペースの圧迫、在庫の陳腐化、資金繰りの悪化など、企業にとってさまざまな問題を引き起こします。仕掛品は、完成品に比べて保管スペースを必要とする場合が多く、過剰な在庫は倉庫のスペースを圧迫し、他の製品の保管や物流に支障をきたすためです。
仕掛品は、長期間保管しておくと、品質が劣化したり、陳腐化したりするリスクがあります。特に、技術革新の激しい業界では、仕掛品がすぐに陳腐化してしまう可能性が高く、多額の損失につながる可能性も懸念されます。
仕掛品は将来の需要を見越して生産される場合が多く、需要予測の不確実性により過剰在庫が発生しやすくなります。また、数量把握が困難な場合も、必要以上の仕掛品を保有してしまう可能性があります。
正確な数量を把握できないまま生産を続けると、過剰在庫に気づかず、無駄な在庫を抱えてしまうリスクが高まります。特に仕掛品は完成品に比べて需要変動の影響を受けやすいため、過剰在庫のリスクはさらに高くなるのが懸念点です。
適切な管理を行わなければ、企業の収益力に悪影響を及ぼす可能性があります。
生産管理システムによる仕掛品管理の効率化

現代の製造業において、仕掛品管理はますます複雑化し、重要性が増しています。 手作業による管理では、正確な状況把握や迅速な対応が難しく、さまざまな問題を引き起こす可能性も懸念されます。
近年注目されているのが生産管理システムです。 生産管理システムを活用すれば、仕掛品管理を飛躍的に効率化し、企業の競争力強化につなげることが可能です。
具体的には、以下の5つのポイントで仕掛品管理の効率化を実現します。
リアルタイムの在庫把握
生産管理システムを導入すると、仕掛品に関するさまざまな情報、例えば数量、所在、状態などをリアルタイムに把握できます。作業員が自身の作業を終える度にシステムに情報を記録すると、仕掛品の状況が常に更新されます。そのため現場の状況を正確に反映した在庫状況のリアルタイムでの把握が可能です。
従来のように、紙やスプレッドシートなどを用いて手作業で在庫を管理する必要がなくなり、人為的なミスや情報の遅れを効果的に防止できます。
例えば、手書きの伝票を用いた在庫管理では、転記ミスや記入漏れが発生しやすく、正確な在庫状況の把握が困難でした。情報共有に入力するのも時間がかかり、タイムラグが生じてしまうことも少なくありませんでした。生産管理システム導入により、これらの問題を解決し、常に最新の情報に基づいた在庫管理が可能です。
データの可視化と共有
生産管理システムは、仕掛品の在庫状況をグラフや表などで可視化し、関係部署間で容易に共有を可能にします。在庫状況をわかりやすく可視化すると、現場の作業員だけでなく、管理者や経営層も、現在の在庫状況を直感的に理解できるためです。
これにより、問題点や改善点を迅速に把握し、適切な対策が可能です。例えば、特定の工程で仕掛品が滞留している場合は、グラフで可視化すると、状況をすぐに把握し、原因究明や対策を迅速に行えます。
また、情報を共有すると、部門間の連携が強化され、全体最適な在庫管理の実現が可能です。例えば、営業部門が受注した製品情報が、生産管理システムを通じて生産部門に共有される場合です。生産部門はそれに基づいて生産計画を調整し、必要な仕掛品を適切なタイミングで準備できます。
原価計算の自動化
生産管理システムは、仕掛品に投入された材料費、労務費、経費などを自動で集計し、原価計算を自動化します。原価計算にかかる時間を大幅に短縮できるだけでなく、人為的なミスを削減し、より正確な原価情報を把握できます。
正確な原価情報の把握は、企業の収益管理において非常に重要です。適切な費用設定や利益管理を行うための基礎となるデータであり、原価計算の自動化によって、より精度の高い経営判断が可能です。
過剰在庫の防止
生産管理システムは、需要予測に基づいた生産計画の立案を支援し、過剰な仕掛品の発生を抑制します。過去の販売実績や市場トレンドなどのデータに基づいて、将来の需要を予測し、それに合わせて生産計画を立て、必要以上の仕掛品生産を防ぎます。
また、在庫状況のリアルタイムでの把握は、必要以上の生産を防ぎ、適正在庫の維持が可能です。常に最新の在庫状況を把握しておくと、現在の在庫量を正確に把握し、必要に応じて生産量を調整できます。保管スペースの無駄や在庫の陳腐化を防ぎ、キャッシュフローの悪化を抑制可能です。
経営判断の迅速化
生産管理システムは、仕掛品に関するさまざまなデータの収集と分析により、経営判断を支援します。例えば、在庫回転率や生産効率などの指標を分析すれば、問題点を発見し、改善策を検討できます。
在庫回転率が低い場合は、在庫が滞留している可能性があり、保管コストの増加や陳腐化のリスクが高まっていると判断可能です。生産効率が低い場合は、製造工程に無駄が多い可能性があり、工程の見直しや設備投資による改善が必要です。
正確な在庫情報の把握は、将来の需要予測や生産計画の精度向上に役立てられます。過去の在庫状況や需要変動などのデータに基づいて、より精度の高い需要予測を行い、それに基づいた生産計画を立てられるためです。過剰在庫や在庫不足のリスクを軽減し、安定的な生産活動を実現できます。
仕掛品管理の効率を向上させよう

企業の収益力向上には、正確な原価計算、在庫管理が不可欠であり、そのなかで仕掛品の管理は重要な役割を果たします。
しかし、仕掛品の管理には、数量把握の困難さ、原価計算の複雑さ、過剰在庫のリスクなど、いくつかの課題に注意する必要があります。課題を克服するためには、生産管理システムの導入が有効です。
生産管理システムは、リアルタイムの在庫把握、データの可視化と共有、原価計算の自動化、過剰在庫の防止、経営判断の迅速化などに役立ちます。さまざまな機能の提供により、仕掛品管理を効率化し、企業の競争力強化を支援します。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
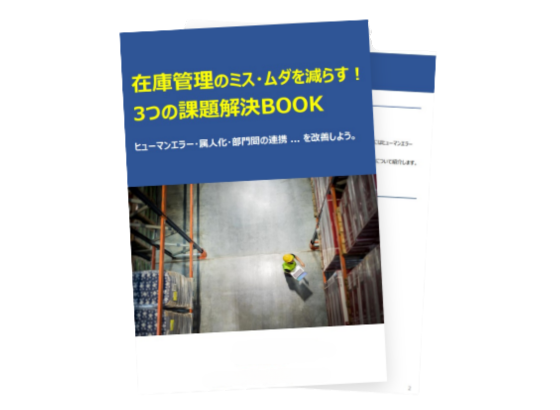
ヒューマンエラー・属人化・部門間の連携 ... を改善しよう。
在庫管理のミス・ムダを減らす!
3つの課題解決BOOK