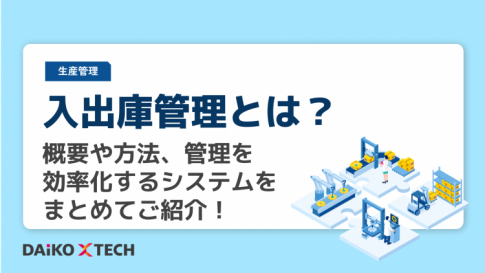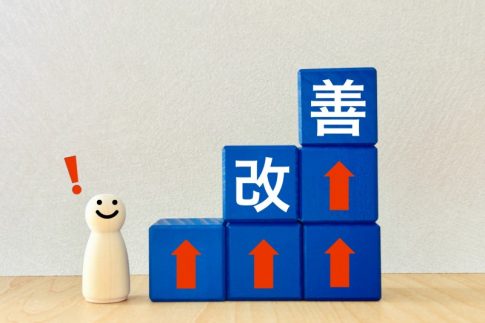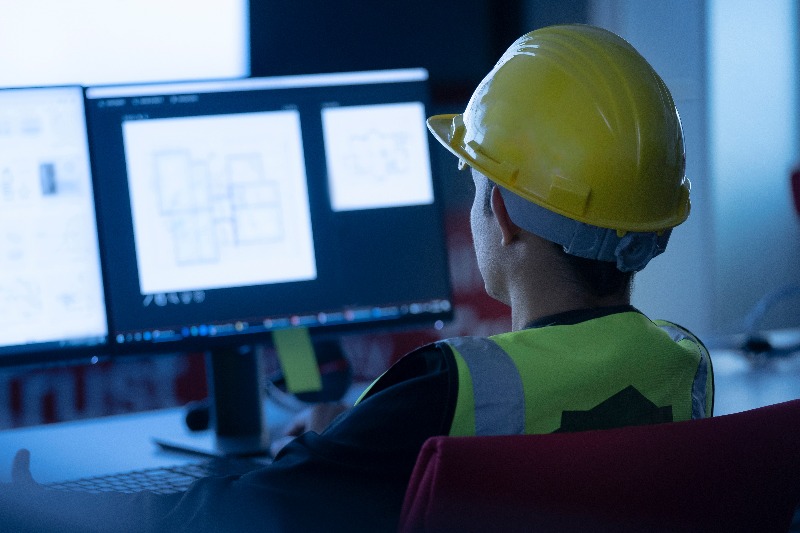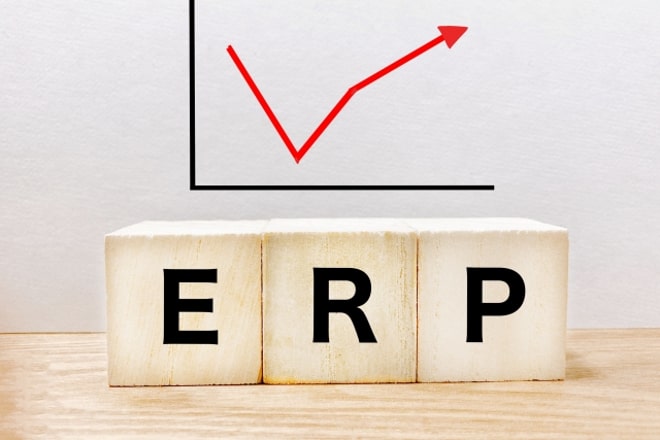)
生産管理と混合されやすい言葉として、ERPが挙げられます。どちらも高品質な製品を生み出すための管理手法ですが、目的や機能が異なります。
ERPのメリット・デメリットを確認して、生産管理にERPを導入するべきか検討しましょう。この記事では生産管理とERPの違いについて、導入するメリット・デメリットを交えて解説します。導入する際の注意点やERPの選び方もあわせて解説するため、生産性を向上させたい企業はぜひ最後までご覧ください。
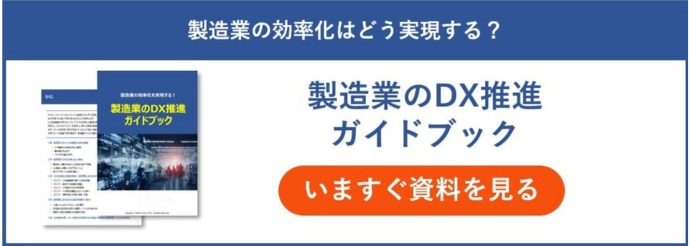
目次
生産管理とERPの違いとは?

製品の品質やコスト・納期を守る上で、生産管理・ERPシステムの導入が重要です。しかし生産管理とERPはそれぞれ目的や備わっている主な機能が異なるため、システム導入を検討するために違いを理解しておく必要があります。
ここでご紹介する生産管理とERPの違いを参考にして、どちらのシステムを導入するべきか検討しましょう。
生産管理とは
生産管理とは、品質・コスト・納期(QCD)を最適化するための管理手法です。お客さまへ提供できる品質を確保しながら、コストを抑えて納期までに製品を仕上げるために、生産管理を行います。
生産管理を理解するためにも、生産管理における目的とシステムに必要な主な機能を確認しましょう。
生産管理の目的
生産管理の目的は、主に「品質(Quality)」「原価(Cost)」「納期(Delivery)」のQCDを最適化することです。
高品質な製品を低コストでスピーディーに納品するためには、効率化された生産計画を立てる必要があります。また余分な在庫を抱えないよう、需要に適した生産計画が必要であり、納期を遵守するためには進捗状況を都度確認しておくことが大切です。
「規定どおりの品質を担保しているか」「納期に間に合うスケジュールで製造できているか」など生産工程を管理しQCDの向上を目指すことが生産管理の目的です。
生産管理の主な機能
生産管理システムには、主に次のような機能が搭載されています。
|
生産管理システムの主な機能 |
機能の内容 |
|
受注管理 |
受注状況や納期を確認し、リアルタイムによる把握が可能 |
|
工程管理 |
予定どおりのスケジュールが進行されているかチェックできる |
|
品質管理 |
製品が品質基準を満たしているか管理できる |
|
出荷管理 |
受注や販売の状況に応じて、最適な出荷環境が整っているかチェックできる |
|
必要材料試算 |
生産計画に基づいた必要となる材料や設備を試算できる |
|
生産計画 |
受注状況や見込み需要に基づいた、生産計画の立案が可能 |
生産管理システムには、生産管理における一連の流れを管理する機能が備わっています。そのため生産管理システムを導入すれば、人的リソースを軽減し管理コストを抑えながら高品質な製品を納品することが可能です。
ERPとは
ERPとは「Enterprise Resource Planning」の略称であり、企業資源計画の意味合いを持ちます。具体的には、企業が持つ在庫や財務会計などの情報資源を最適化する管理手法です。
生産管理だけでなく会計・人事・物流など、企業における業務全体を総合し、一元管理することで管理コストを軽減します。ERPについての理解を深めるために、目的やERPシステムに搭載されている主な機能を確認しておきましょう。
ERPの目的
ERPの目的は、企業の業務全体を効率化することです。
主な業務である製造・流通・販売・在庫管理・財務会計・人事管理までを総合して管理し、自社のリソースをリアルタイムで管理します。各業務が工程ごとにわかれていると、各工程間での連携が必要であり、それぞれの管理システムでリアルタイムの情報を把握することが難しいです。
ERPシステムでは、さまざまな業務を一元管理できるため、生産管理システムや会計システム・人事管理システムなどの複数のシステムを統合して管理できます。
そのため複数のシステムを運用するコストを抑えて、ERPシステムだけで企業の業務全体を管理することが可能です。
ERPの主な機能
ERPシステムに搭載されている主な機能は、次のとおりです。
|
ERPシステムの主な機能 |
内容 |
|
財務会計 |
財務諸表作成や仕訳の登録、請求書発行、入金管理など |
|
生産管理 |
製造計画立案や工程管理、品質管理、出荷管理など |
|
人事管理 |
従業員情報の登録や異動管理、マイナンバー・社会保険管理、給与計算など |
|
経費精算 |
従業員の立替精算など経費処理を行う |
|
在庫管理 |
現在保有している在庫状況や見込み需要を把握する |
|
販売管理 |
見積書作成から受注管理、在庫確認や出荷情報の登録、請求書の発行など |
|
債権・債務管理 |
売掛金の管理や入金による債権消込の実施、請求書に基づいた振込など |
生産工程だけでなく在庫管理・販売・人事・経費精算・債務整理など、さまざまな業務を一元管理できます。ERPシステムを導入すれば、生産管理を含むさまざまな業務の管理コストを軽減できます。
生産管理やERPを導入するメリット
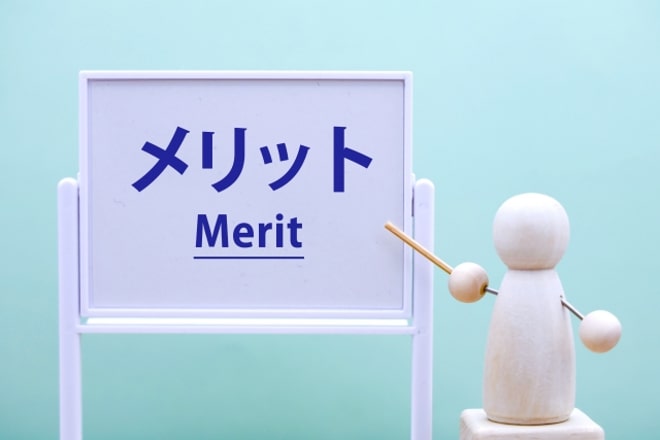
生産管理やERPを導入するべきか悩んでいる企業は、システムを導入することで得られるメリットを確認しておきましょう。
生産管理やERPを導入するメリットは、次のとおりです。
- コストカットへつながる
- 各工程を可視化できる
- スムーズにノウハウを共有できる
- 生産性を向上できる
それぞれのメリットを確認して、生産管理やERPシステムを導入するべきか検討しましょう。
コストカットへつながる
生産管理やERPを導入するメリットは、コストカットへつながることです。単純作業をシステムで自動化し管理業務の工数を削減できるため、人件費の削減につながります。
具体的には在庫管理や会計管理などの入力作業や集計業務の際に、ERPシステムを活用すれば作業効率化による工数削減が可能です。管理コストの軽減を目指す企業にとって、ERPの導入は課題解消につながります。
各工程を可視化できる
生産管理やERPを導入すれば、各工程を可視化できます。
生産管理やERPシステムによって、各工程の進捗状況や不具合をリアルタイムで把握できるため、必要な指示を速やかに伝達可能です。
工程ごとの進捗状況を可視化できるため、スケジュールどおりに作業が進んでいるか、納期に合わせた調整を行いやすいです。各工程が可視化されれば、QCDを改善し管理者の負担を軽減できます。
スムーズにノウハウを共有できる
生産管理やERPシステムを導入するメリットは、スムーズにノウハウを共有できることです。
生産管理・ERPシステムの導入によって、従業員の経験やスキルに依存していた業務を、システムで自動化して属人化を防止できます。人材に頼らない生産ができるため、現場の従業員全体に業務のノウハウを共有して、組織全体の生産性向上へとつながります。
また生産管理・ERPシステムには、ノウハウをスムーズに共有する情報共有機能が備わっており、細かなアドバイスやポイントまで周知させることが可能です。
生産性を向上できる
生産管理やERPを導入すれば、生産性を向上できます。
企業のさまざまな業務を一元管理するため、部署間をまたいだ情報共有や業務連携を実現しやすいです。各部署・各工程が業務を効率化できるため、組織全体の生産性向上につながります。
生産管理やERPを導入するデメリット

生産管理やERPを導入する際には、メリットだけでなくデメリットも確認しておく必要があります。メリットだけ確認して生産管理やERPシステムを導入した場合、運用してから後悔する可能性があるため要注意です。
生産管理やERPを導入するデメリットは、次のとおりです。
- 導入・運用コストがかかる
- システム選定が難しい
- 現場の対応力に依存する
それぞれのデメリットを確認して、生産管理やERPシステムを導入するべきか検討する判断材料にしましょう。
導入・運用コストがかかる
生産管理・ERPシステムを導入するデメリットは、導入・運用コストがかかることです。導入する際の初期費用として数百万円単位のコストが必要で、現場の仕様にあわせてカスタマイズする場合はさらに追加コストが発生します。
適切に運用していくためには、定期メンテナンスを実施する必要があり、運用コストもかかるため費用対効果を測定しなければなりません。生産管理・ERPシステムの導入によって得られる効果に対して支払うコストがいくら必要か、事前に見積を依頼して費用対効果を測定しましょう。
システム選定が難しい
生産管理・ERPの導入の導入に際して、システム選定が難しいこともデメリットの一つつです。生産管理システムやERPシステムは、さまざまなベンダーが開発・販売しており、市場から自社に適したシステムを選定しなければなりません。
費用面や機能面だけでなく、実際に導入してからの操作性やアフターサービスの充実度などを確認しておかなければ、システム選定で後悔するリスクがあります。生産管理・ERPシステムを選ぶ際には、口コミや評判・操作性・アフターサービスの充実度など、さまざまな観点から自社に適したシステムを導入しましょう。
現場の対応力に依存する
生産管理・ERPシステムを導入しても、すぐに業務を効率化できるかは現場によって異なります。生産管理・ERPシステムの効果を発揮するには、現場の対応力に依存するため適切に運用できるよう対処しなければなりません。
組織風土や生産体制・現場のノウハウによって、生産管理・ERPシステムの機能・操作性に慣れず、導入当初は生産性が低下する可能性もあります。
すでに生産管理システムを導入している現場で、新たなシステムを切り替える場合には、操作方法を一から覚え直す手間が発生してしまい従業員の負担が増えます。生産管理・ERPシステムの必要性を現場に周知させて、操作に慣れるまで社内で協力してノウハウを蓄積していくことが重要です。
生産管理におけるERPの選び方

生産管理にERPを活用したい場合、数多くのベンダーが提供しているERPシステムの中から自社に適したシステムを見極めなければなりません。生産管理におけるERPの選び方として、次のポイントを押さえておきましょう。
- 対応業務の範囲を確認しておく
- 対応ジャンルを確認しておく
- 他業務分野の対応範囲を確認しておく
- 自社に適した運用形態を見極める
- クラウド型かオンプレミスどちらを選ぶべきか、それぞれの特長を解説
- セキュリティ性の高さを確認しておく
- サポート体制の充実度を確認しておく
それぞれのポイントを確認して、ERPシステムを選ぶ際の参考にしてください。
対応業務の範囲を確認しておく
ERPシステムを選ぶ際には、対応業務の範囲を確認しておきましょう。ERPシステムによって搭載されている機能や対応できる業務の範囲が異なるため、自社の要件と照らし合わせて求める業務範囲に対応しているか確認しておかなければなりません。
ERPシステムが自社に適合(Fit)している部分と乖離(Gap)している部分があるかをチェックする「Fit&Gap分析」を利用すれば、導入するシステムが求める業務範囲に対応しているかを確認できます。
対応ジャンルを確認しておく
ERPシステムを選ぶときのポイントとして、対応ジャンルを確認しておくことが大切です。自動車業界向け・金属加工業向け・機械製造業向け・情報サービス業向け・精密機器業界向けなど、ERPシステムによって対応ジャンルが異なります。
自社の業界やジャンルに適したERPシステムを導入することで、生産管理を効率化できるため、システム選びの際には対応ジャンルを確認しておきましょう。
関係部門の対応範囲を確認しておく
ERPを選ぶ際には、関係部門の対応範囲を確認しておきましょう。生産管理だけでなく、在庫管理や財務会計・人事管理など複数の部門にも対応しているERPシステムを導入すれば、部署間の連携を実現して業務効率を向上できます。
生産側だけでなく販売側や流通側・経理側・営業側など、さまざまな側面の意見を参考に、QCD向上につなげられます。
自社に適した運用形態を見極める
ERPシステムを選ぶ際には、クラウド型かオンプレミス型どちらを選ぶべきか、自社に適した運用形態を見極めることが大切です。
ERPシステムには、クラウド型かオンプレミス型の2種類があり、それぞれの特長が異なります。クラウド型はベンダーが構築したシステムを使用する運用形態で、自社内でシステム構築・開発する手間がかかりません。システム開発にかかるコストを抑えられるため、初期費用を抑えてERPシステムを導入したい企業はクラウド型のシステムがおすすめです。
ベンダー側でシステムのバックアップやメンテナンスなどを行ってくれるため、システム運用のタスクやコストを軽減できます。
対してオンプレミス型は、自社のサーバー内にシステムを構築する運用形態で、クラウド型より高いカスタマイズ性があります。しかしシステムを一から構築する手間やコストがかかり、メンテナンスやバックアップも自社で行わなければなりません。
自社が求めるニーズや課題に適した運用形態のERPを探して、導入するシステムを検討しましょう。
セキュリティ性の高さを確認しておく
生産管理におけるERPを選ぶ際には、セキュリティ性の高さを確認しておきましょう。
サプライチェーンを狙ったサイバー攻撃などを防止する必要があり、セキュリティ性を強化しておかなければ、機会損失が起きるリスクが生じます。
ERPは企業内の業務全体を一元管理するため、サイバー攻撃に合った際には甚大な被害を受けます。そのためERPシステムを選ぶ際には、通信の暗号化や二段階認証に対応しているか、セキュリティ性の高さをチェックしておきましょう。
サポート体制の充実度を確認しておく
ERPシステムを導入する際には、サポート体制の充実度を確認しておくことが大切です。
ERPは現場の対応力に依存することが多く、ITリテラシーやシステム操作に慣れた人材がいなければ、適切に運用することが難しいです。
操作方法に関する疑問点や不具合が生じた際の対応など、ベンダーが対応してくれるサポート体制の有無を確認しておく必要があります。必要なサポート体制が整ったシステムを導入すれば、生産管理をスムーズに行えます。
生産管理システム・ERPを導入する際の注意点

生産管理システム・ERPを導入して適切に運用するためには、いくつか注意点を押さえておく必要があります。
生産管理システム・ERPを導入する際の注意点は、次のとおりです。
- 導入目的を明確化しておく
- 組織内でシステム導入の目的を共有しておく
- 運用体制を整備しておく
- 費用対効果を測定しておく
それぞれの注意点を確認して、生産管理システムやERPの導入に備えて対処しましょう。
導入目的を明確化しておく
生産管理システム・ERPを導入する際には、導入目的を明確化しておく必要があります。「なぜ生産管理システムやERPを導入するのか」目的が明確化されていないと、どのような機能・仕様のシステムを選ぶべきか検討できません。
注意するべきは、生産管理システムやERPを導入することを目的とするのではなく、導入してから運用する目的を明確化しておくことが大切です。生産管理システムやERPを導入する際には、導入目的を明確化して目的に合ったシステムを選びましょう。
組織内でシステム導入の目的を共有しておく
生産管理システム・ERPを導入する際の注意点として、導入目的を明確化するだけでなく、組織内でシステム導入の目的を共有しておきましょう。「なぜ生産管理システム・ERPを導入するのか」を組織内で共有しておくことで、システム導入をスムーズに行えます。
組織内でシステムの操作方法やマニュアル・運用ルールを共有して、適切に運用できるよう事前準備しておきましょう。
また導入目的と導入によって得られる効果を説明しておくことで、従業員のモチベーションを向上させられます。従業員のモチベーションと生産性を向上させるためにも、システム導入の目的を周知させることが大切です。
運用体制を整備しておく
生産管理システム・ERPを導入する際の注意点として、運用体制を整備しておきましょう。いきなり生産管理システム・ERPを導入しても、運用体制を整備しておかなければ、効果的にシステムを活用できません。
操作方法を指導し運用方法を共有するプロジェクトチームを構築し、導入後の安定した運用に備えましょう。
費用対効果を測定しておく
ERPを導入する際の注意点として、費用対効果を測定して導入するシステムを選んでください。搭載されている機能の多さや企業規模の大きさで、導入するシステムを選ぶと、費用対効果が低くシステム選びで後悔する可能性があります。
導入することで得られる効果を測定し、必要な費用と比較して、費用対効果の高いシステムを導入しましょう。
生産管理にERPを導入して生産性を向上しよう!

生産管理にERPを導入すれば、生産性の向上につながります。
ERPシステムによって、企業全体の業務を向上させれば、管理コストや人的リソースを軽減することが可能です。さらに部署間の垣根を超えて、スムーズにノウハウを共有できるため、業務の属人化を防止できます。
市場には数多くの生産管理システム・ERPシステムが出回っているため、自社が求める対応範囲やジャンル・運用体制に適したシステムを探すことが大切です。生産管理を効率化して企業全体の生産性を向上させたい企業は、自社に合ったERPシステムを導入しましょう。
DAIKO XTECHでは、工程管理だけでなく、生産管理・購買管理・在庫管理などさまざまなシステムを包含または連携できる「rBOM」を提供しています。各部門の連携性を強化し、受注から出荷までの情報を可視化できるため、リードタイムを短縮してQCDを向上できます。
個別受注生産システムである「rBOM」を導入すれば、業務の身の丈に合ったシステムを構築でき、各工程の可視化や生産性の向上などの実現が可能です。ERPシステムの導入を検討している企業は、ぜひ以下資料から「rBOM」の詳細をご覧ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
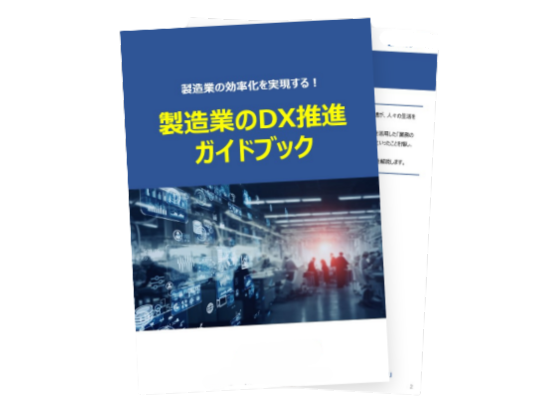
製造業の効率化を実現する!
製造業のDX推進ガイドブック