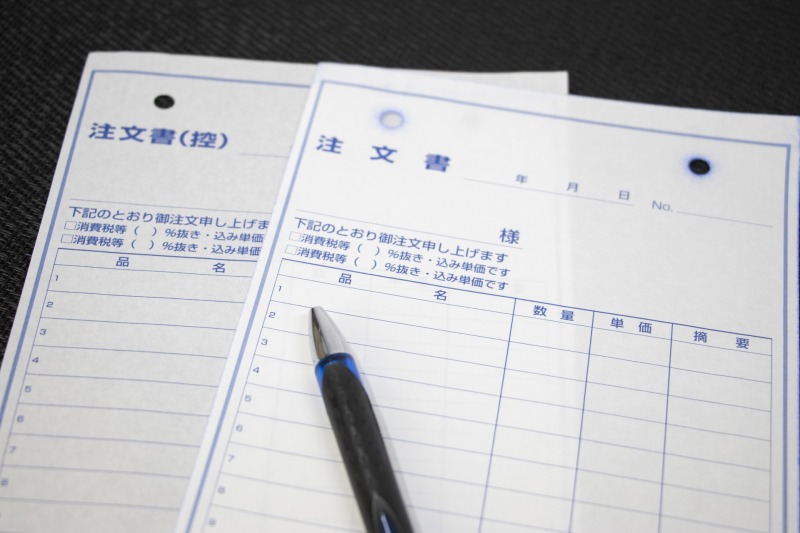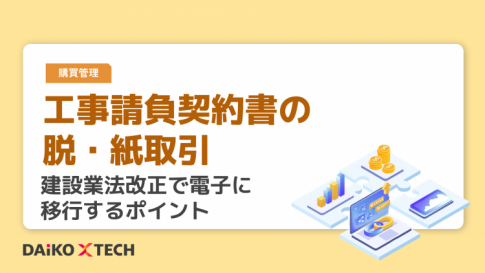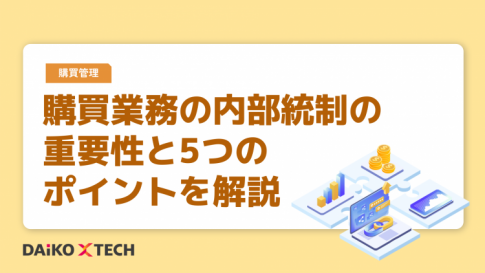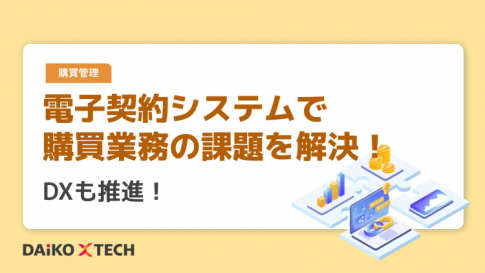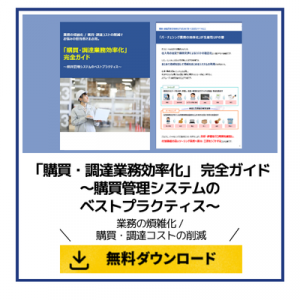製造業の現場では、日々大量の注文書が発生し、その管理方法に頭を悩ませている経営者や責任者の方も多いのではないでしょうか。
従来の紙ベースでの保管では、保管場所の確保、検索時間の増加、書類の紛失といった課題が山積みです。
2024年1月から電子帳簿保存法の電子取引データ保存が完全義務化されたことで、注文書の電子化対応は法的要件となりました。
しかし、この変化を単なる負担と捉えるのではなく、業務効率化とコスト削減の機会として活用することが重要です。
適切な電子化戦略により、製造業特有の複雑な取引形態にも対応しながら、生産性向上と法令遵守を同時に実現できます。
この記事では、注文書保管の電子化について法的要件から実務上のポイントまで詳しく解説します。
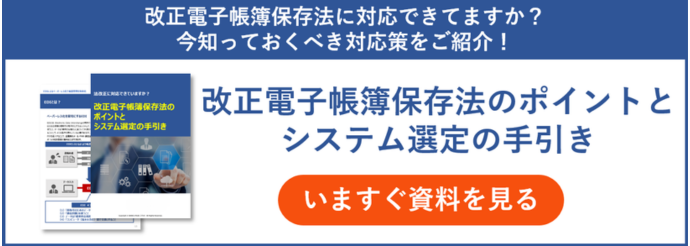
目次
主な注文書の保管方法
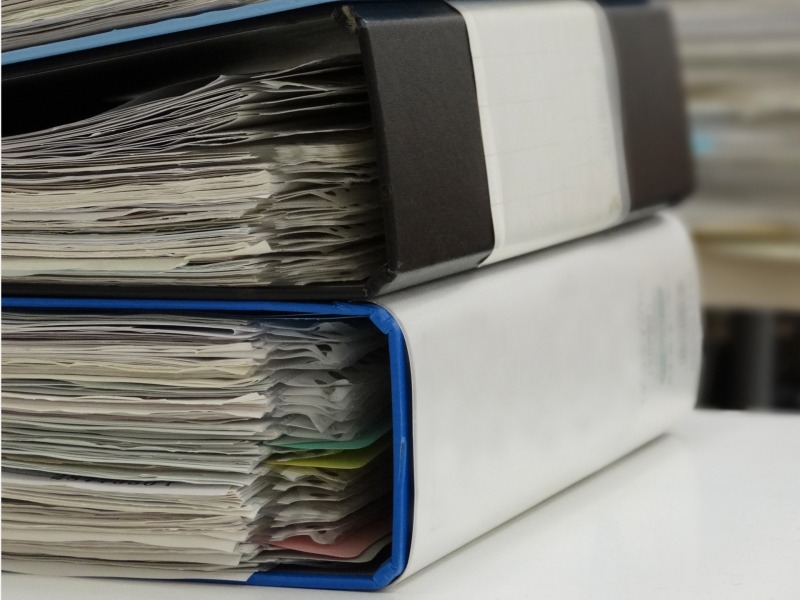
製造業における注文書の保管方法は、事業の状況や取引形態に応じて選択できますが、主に「紙」「スキャナ保存」「電子データ」の3つの方法に大別されます。
従来一般的であった紙での保管に加え、電子帳簿保存法の改正に伴い、スキャナ保存や電子データでの保存が急速に普及しています。
以下では、これら3つの保管方法の具体的な内容について解説します。
紙で保管
紙での保管は、印刷された注文書をファイリングして管理する、従来から続く最も基本的な方法です。
しかし、事業が成長し取引量が増加するにつれて、以下のような経営課題が顕在化する傾向があります。
|
課題 |
内容 |
|
物理的コスト |
保管キャビネットや倉庫などの物理的なスペース確保と、その賃料や管理費用が発生します。 |
|
人的コスト |
必要な書類を探し出すためのファイリングや検索に時間がかかり、人件費の増大につながります。 |
|
セキュリティリスク |
盗難、紛失、火災や水害といった災害による物理的な破損・劣化のリスクが常に伴います。 |
|
業務継続性 |
災害時やオフィス外での業務継続が困難になり、事業継続計画(BCP)の観点から脆弱性を抱えます。 |
手軽に始められる一方で、事業規模の拡大に比例して管理コストやリスクが増大するため、多くの企業でペーパーレス化への移行が検討されています。
スキャナ保存
スキャナ保存は、紙で受け取った注文書をスキャナーで読み取り、電子データに変換して保存する方法です。
この方法は、紙媒体でのやり取りが依然として多いものの、保管コストの削減や情報の活用を推進したい企業にとって、現実的な第一歩となります。
紙の原本を電子化することで、物理的な保管スペースを大幅に削減できる点が大きなメリットです。
スキャナ保存を導入するメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 省スペース化とコスト削減:紙の原本を破棄できるようになるため、書庫やキャビネットが不要になり、オフィススペースの有効活用や賃料削減に貢献
- 検索性の向上:ファイル名や日付、取引先名などで検索可能になり、必要な情報を迅速に見つけ出せる
- 情報共有の円滑化:データ化されているため、拠点間での情報共有が容易になり、業務の属人化を防ぐ
デメリット
- スキャン作業の発生:紙の書類をスキャンし、定められたルールでファイリングする手間と時間が必要
- 法令要件の遵守:電子帳簿保存法のスキャナ保存要件(解像度、タイムスタンプの付与など)を正確に満たす必要がある
紙文化から電子化への過渡期にある企業にとって、スキャナ保存は既存の業務フローを大きく変えることなくペーパーレス化の利点を享受できる有効な手段です。
電子データで保管
電子データでの保管は、電子メールやEDI(電子データ交換)、Web受発注システムなどを通じて受け取った注文書データを、そのまま電子データの状態で保存・管理する方法です。
これは、業務プロセス全体のデジタル変革を目指す上で最も効果的な保管方法です。
紙を一切介さないため、印刷、郵送、ファイリングといった物理的な作業が不要になり、業務効率を飛躍的に向上させます。
電子データ保管がもたらす主なメリットとデメリットは、以下の通りです。
メリット
- 抜本的な業務効率化:データ受領から保管、承認、後続業務への連携までをシステム上で一気通貫で行える
- コストパフォーマンス:用紙代、印刷代、郵送費、保管スペースといった物理的なコストを根本から削減
- 多様な働き方への対応:いつでもどこでもデータにアクセスできるため、テレワークや複数拠点での業務に柔軟に対応可能
- データ活用の促進:蓄積された購買データを分析し、原価管理の精度向上や発注先の最適化といった経営戦略に活かせる
デメリット
- システム導入のコスト:電子データ保管に対応したシステムの構築には、初期費用や維持管理費がかかるなど導入にはコストが発生する
- システム障害によるデータ消失のリスク:ハードウェアやソフトウェアの故障、ウイルス、自然災害などによるシステム障害でデータが失われる可能性があり、復旧にもコストがかかる場合がある
- データ漏洩のリスク:電子データは紙に比べて拡散が容易であり、不正アクセスや誤送信、デバイスの紛失などにより情報が漏洩する危険性がある
導入にはシステムの構築や取引先との調整が必要ですが、これらの初期投資を上回る業務改善効果と競争力強化が期待できるため、多くの先進的な企業がこの方法への移行を進めています。
電子帳簿保存法の義務化とは
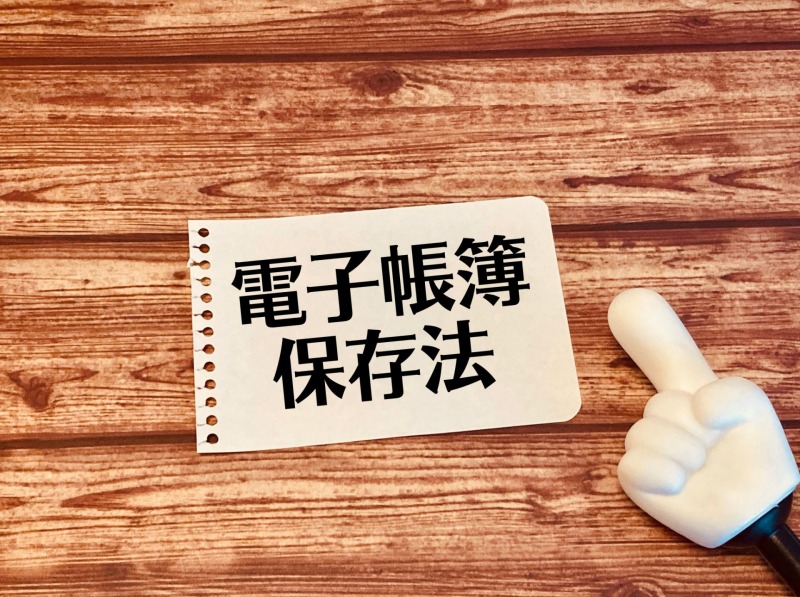
2024年1月から、電子帳簿保存法における「電子取引データの電子保存」が義務化されました。
この義務化は、具体的に誰が対象で、何を、どのように保存する必要があるのかを正確に理解することが、適切な対応への第一歩です。
以下で、対象者、対象データ、そして満たすべき保存要件について押さえておくべきポイントを解説します。
対象者
電子帳簿保存法の対象は、事業規模の大小や法人・個人事業主の別を問わず、所得税および法人税の保存義務があるすべての事業者です。
つまり、国内で事業を行い、税務申告をしている企業や個人は、例外なくこの法律の適用を受けます。
大企業だけでなく、サプライチェーンを支える中小の製造業者や、個人で部品加工などを請け負う事業主もすべて対象に含まれます。
電子取引データとは
電子取引データとは、取引情報の授受を電子的な方法で行う取引に関するデータを指します。
紙を介さずにやり取りされる情報がすべて該当すると考えるとわかりやすいでしょう。
製造業の現場においては、日常的に発生する以下のようなデータが電子取引データに該当します。
- EDI(電子データ交換)システムを通じて授受した注文データ
- 電子メールに添付されたPDF形式の注文書や請求書
- 取引先のウェブサイトからダウンロードした発注情報や納品書
- クラウドサービスを利用した受発注システムの取引記録
- FAX機能を持つ複合機で送受信した注文書データ(ペーパーレスFAX)
これらのデータを紙に出力して保存することは、2024年1月1日以降、原則として認められなくなりました。
そのため、データ形式のまま、法的な要件を満たして保存する体制の構築が急務です。
保存要件
電子取引データを保存する際には、単にコンピュータのフォルダに保存するだけでは不十分です。
法律では、データの信頼性を担保するために「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの大きな要件を満たすことが求められています。
真実性の確保
真実性の確保とは、保存された電子データが、作成されてから一貫して改ざんされていない「本物」であることを証明するための要件です。
これを満たすためには、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
- タイムスタンプの付与:データが特定の時刻に存在し、それ以降改変されていないことを証明するタイムスタンプを、取引情報に付与する必要がある
- 訂正・削除履歴の確保:データの訂正や削除を行った場合に、その事実と内容が記録として残るシステム、またはそもそも訂正・削除ができないシステムを導入して利用すること
- 事務処理規程の整備:電子データの訂正や削除に関して、目的や手順などを定めた社内規程(事務処理規程)を作成し、それに沿った運用を行うこと
多くの企業では、運用の手間や確実性を考慮し、これらの要件に対応した文書管理システムや販売管理システムを導入する方法が選択されています。
可視性の確保
可視性の確保とは、保存した電子データを、税務調査などで必要になった際に、いつでも誰でも明瞭な状態で確認・出力できるようにしておくための要件です。
具体的には、以下の3つの措置が求められます。
|
措置 |
具体的な内容 |
|
保存場所への必要設備の設置 |
電子データを保存する場所に、そのデータを表示・印刷するためのディスプレイ、PC、プリンタ、およびそれらの操作マニュアルを備え付ける |
|
検索機能の確保 |
「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の3つの項目でデータを検索できる機能を確保する |
|
範囲指定・複数条件検索 |
日付や金額の範囲を指定した検索や、2つ以上の項目を組み合わせて検索できる機能を確保すること(※税務調査官のダウンロードの求めに応じられる場合は不要) |
これらの要件は、単にデータを保存するだけでなく、必要な情報を迅速に探し出せる「使えるデータ」として管理することの重要性を示しています。
電子帳簿保存法に基づく書類の電子保存方法の種類

電子帳簿保存法を正しく理解し、自社の注文書管理に適用するためには、法律で定められた3つの保存区分を把握することが不可欠です。
書類を「どのように作成・受領したか」によって、適用される区分と対応方法が異なります。
この3つの区分は、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」に分類されます。
特に重要なのは、対応が任意である「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」と、対応が義務である「電子取引データ保存」を明確に区別することです。
以下の表で、それぞれの区分の概要と対象書類、対応の要否を整理します。
|
保存区分 |
対象となる書類の例 |
対応の要否 |
|
電子帳簿等保存 |
会計ソフトで作成した総勘定元帳 自社でPCで作成した注文書(控) |
任意 |
|
スキャナ保存 |
取引先から紙で受け取った注文書 紙で発行した領収書の控え |
任意 |
|
電子取引データ保存 |
メールで受領したPDFの注文書 EDIシステムで授受した取引データ |
義務 |
次の項目から、それぞれの区分について詳しく解説します。
電子帳簿等保存
電子帳簿等保存は、自社が会計ソフトや販売管理システムなどを利用して、一貫してコンピュータで作成した帳簿や書類を、電子データのまま保存することを認める制度です。
例えば、自社の販売管理システムで作成した注文書の控えや、会計ソフトで作成した総勘定元帳などがこれに該当します。
この区分の適用は任意であり、従来通り紙に印刷して保存することも認められています。
電子データのまま保存する場合は、税務署への事前申請は不要ですが、前述した「可視性の確保」など一定の要件を満たす必要があります。
スキャナ保存
スキャナ保存は、紙で受け取った、あるいは自社で作成した国税関係書類を、スキャナやスマートフォンで読み取り、画像データとして保存することを認める制度です。
製造現場では、依然として取引先から紙の注文書をFAXや郵送で受け取るケースも少なくありません。
これらの書類をスキャナ保存することで、物理的な保管スペースの削減や、検索性の向上といったメリットが得られます。
この区分の適用も任意であり、紙のまま保存し続けることも可能です。
スキャナ保存を行うためには、一定の解像度でのスキャンやタイムスタンプの付与、訂正・削除履歴が残るシステムの利用など、電子帳簿保存法が定める厳格な要件を満たす必要があります。
電子取引データ保存
電子取引データ保存は、EDI取引や電子メールなど、電子的に授受した取引情報を、電子データのまま保存することを定めた制度です。
前述の2つと決定的に違うのは、この区分の適用が義務である点です。
2024年1月1日以降、電子データで受け取った注文書や請求書などを紙に印刷して保存することは、原則として認められません。
保存にあたっては、「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。すべての事業者が対応必須のこの要件をクリアするため、多くの企業が電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を進めています。
これは、法令遵守だけでなく、業務効率化を推進する機会でもあります。
注文書の保管期間

注文書は、税務上重要な書類として、一定期間の保存が法律で義務付けられています。
保管期間は事業形態や所得状況によって異なるため、経営者や総務責任者は、自社の状況に応じたルールを正確に把握し、適切な管理体制を構築することが重要です。
以下に、具体的な保管期間を事業形態ごとに解説します。
法人の場合
法人企業の場合、注文書を含む取引関係書類の保存期間は、原則として7年間と定められています。
これは、会社法や法人税法に基づく規定によるもので、事業年度終了後から7年間、書類を適切に保管しなければなりません。
欠損金が発生している場合など、最長10年間の保存が必要となるケースもあります。
税務アドバイザーとの連携を通じて、自社に適用される期間を明確にすることが重要です。
個人事業主の場合
個人事業主における注文書などの取引書類の保存期間は、原則として5年間です。
ただし、青色申告を行っている場合には、帳簿や決算関係書類とともに7年間の保存が求められる点に注意が必要です。
事業規模が小さい場合でも、税務調査に備えるため、保存期間を厳守し、データ管理のルールを整備することが大切です。
副業収入が一定以上ある場合
副業による収入が一定額を超える場合、個人事業主と同様に、注文書や関連書類の保存が義務付けられます。
具体的には、事業所得や雑所得として申告が必要な場合、5年間の保存が基本となります。青色申告を選択している場合には7年間となるため、副業の規模や申告方法に応じて、適切な期間を把握し、対応することが重要です。
注文書電子化で得られる5つのメリット

注文書の電子化は、単なる法令対応にとどまらず、製造業の業務プロセス全体に革新をもたらす可能性を秘めています。
経営戦略や現場の生産性向上に直結する利点が多く、デジタル化の推進は競争力強化の鍵となるでしょう。
以下に、注文書の電子化がもたらすメリットを5つ紹介します。
業務効率の向上
注文書を電子化することで、受発注プロセスにおける手作業が大幅に削減可能です。
紙の書類を扱う際の印刷、ファイリング、配送、確認といった一連の作業が不要となり、現場スタッフや事務担当者の負担が軽減されます。
業務のリードタイムが短縮され、生産計画や納期管理の精度が向上する効果が期待できます。
コスト削減
電子化は、物理的な書類管理に伴うさまざまな経費を抑える効果があります。
例えば、紙代、印刷代、郵送費、保管スペースの賃料などが不要となり、コストパフォーマンスの向上が実現します。
こうした節約分を、設備投資や人材育成など、事業成長のための戦略的な領域に再配分できる点も見逃せないメリットです。
情報活用の促進
デジタルデータとして保存された注文書は、検索機能や分類機能を活用することで、必要な情報を瞬時に取り出せるメリットがあります。
例えば、取引先名や日付、金額などの条件で絞り込みが可能となり、過去の取引履歴を基にした分析や、発注傾向の把握が容易になります。
データに基づく意思決定の質とスピードが向上する点は大きなメリットです。
紛失・劣化リスクの低減とBCP対策強化
紙の書類は、紛失や盗難、火災や水害による破損のリスクを常に抱えていますが、電子化することでこれらの危険性を大幅に低減できます。
クラウドサービスやバックアップ体制を活用すれば、災害時でもデータを保護し、事業継続計画(BCP)の強化につながります。
製造業において、取引データの保全は事業の信頼性に直結するため、この点は特に重視すべきです。
テレワークなど多様な働き方への対応
電子化された注文書は、インターネット環境があればどこからでもアクセスが可能です。
事務所にいなくても承認や確認作業が行えるため、テレワークや出張先での業務継続が容易になります。
働き方の柔軟性が高まることで、従業員の満足度向上や優秀な人材の確保にもつながるメリットです。
注文書電子化の注意点

注文書の電子化を進める際には、法令遵守と運用面での課題に十分配慮する必要があります。
製造業の現場では、取引先との調整や社内ルールの整備が欠かせず、経営層や総務責任者が主導して対応を進めることが大切です。
以下に、注文書の電子化を進める上で特に注意すべき点を紹介します。
保存方法の区分を正しく把握する
電子帳簿保存法では、保存方法が「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つに区分されており、それぞれ要件が異なります。
自社の注文書がどの区分に該当するかを正確に判断し、適切な対応を行うことが求められます。
区分を誤ると法令違反となるリスクがあるため、専門家の意見を取り入れながら進めるのが賢明です。
電子帳簿保存法の保存要件を満たす
電子化されたデータの保存には、真実性と可視性の確保が必須条件として定められています。
タイムスタンプの付与や検索機能の整備、訂正・削除履歴の管理など、細かな要件を満たすための運用ルールやシステム選定が必要です。
法令を遵守することで、税務調査時のリスクを最小限に抑えましょう。
スキャナ保存時の追加要件に注意する
スキャナ保存を選択する場合、紙の書類を電子化する際の追加要件に留意しなければなりません。
具体的には、解像度(200dpi以上)、カラー画像での保存、タイムスタンプの付与、入力期限(最長2カ月以内)などが求められます。
これらの条件を満たすための社内体制や機器の準備を整えることが重要です。
注文書の電子化で電子帳簿保存法の義務化に対応しよう

製造業における注文書の電子化は、法令対応と業務効率化の鍵ですが、どのシステムを選べばよいか迷うことも少なくありません。
システム選定で重要な指標となるのが、サービスが法的要件を満たしていることを証明する「JIIMA認証」です。
国税庁公認のJIIMA認証を取得した「EdiGate DX-Pless」は、タイムスタンプ付与や検索機能など電子帳簿保存法の要件に完全対応しています。
基幹システムと連携し、注文書を含むあらゆる帳票を自動で電子保管できるため、法令遵守とバックオフィス業務の大幅な効率化を両立します。
まずは無料トライアルで、その利便性をお試しください。
「EdiGate DX-Pless」の詳細は、こちら