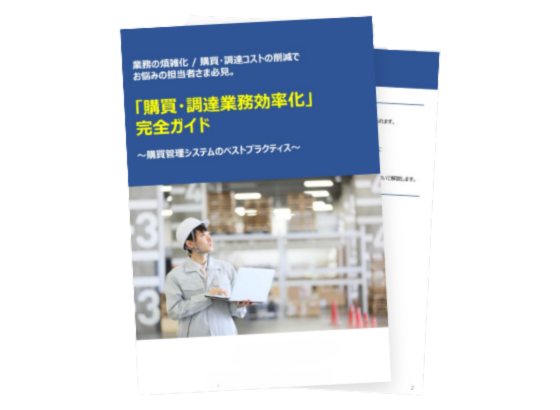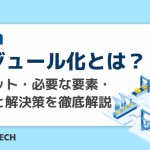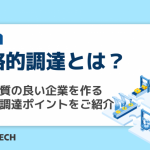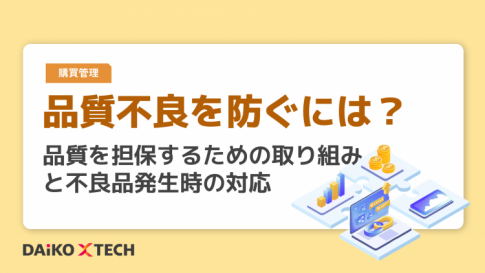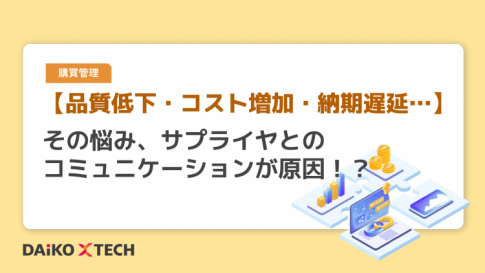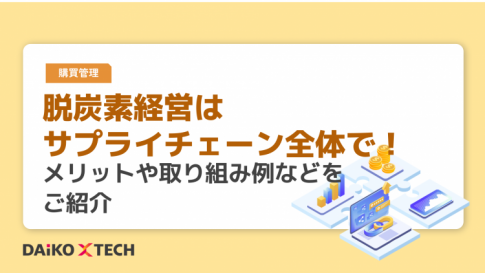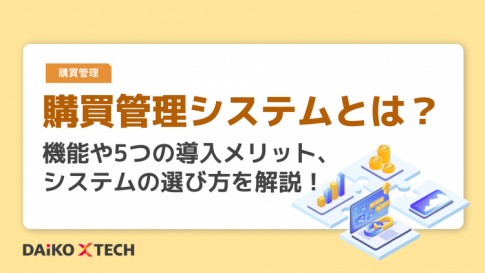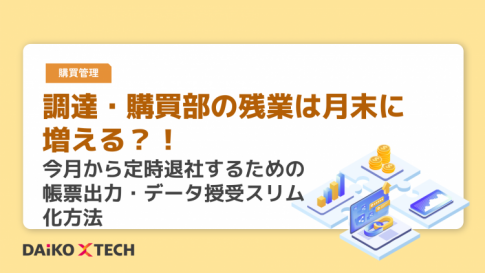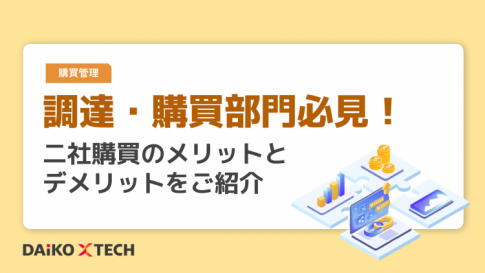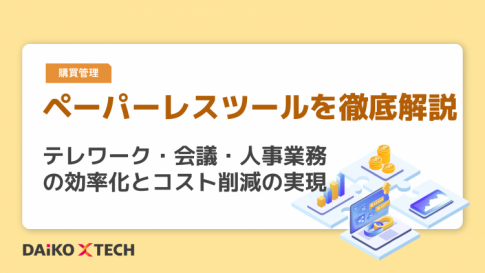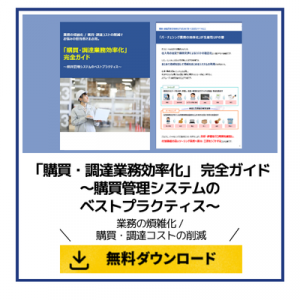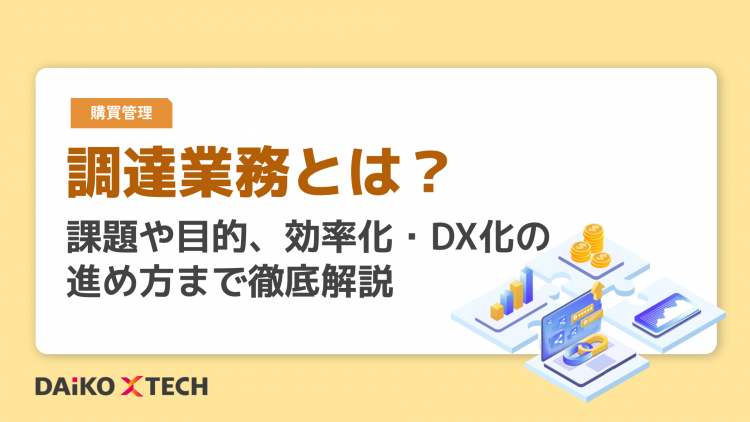
調達業務とは、自社の生産活動に必要な原材料や部品などを、最適な品質・価格・納期(QCD)で安定的に確保する一連の活動です。製造業において調達管理は、製品の品質やコスト、納期に直結する重要な役割を担っており、企業の競争力を左右する要素といえます。
しかし、調達担当者は、サプライヤの選定や価格交渉、煩雑な事務作業、他部門との調整など、多くの課題に直面しているのではないでしょうか。
本記事では、調達管理の基本的な業務内容やフロー、購買管理との違いを解説します。さらに製造業で調達業務が重視される理由や調達担当者に求められる能力、現場で直面しやすい課題についても詳しくご紹介します。

目次
調達管理業務とは

調達管理業務とは、生産計画に基づいて、原材料や部品・設備・消耗品など生産に必要な「モノ」、「人」や「金」の調達を管理する業務です。
ただ資材を調達するだけでなく、「どこから仕入れるのか」「どのタイミングで供給するのか」など、仕入先やタイミングを考慮する必要があります。
価格やロット数・在庫数・市場のニーズなど諸条件を確認して、総合的な視点で最適な調達を行う業務が調達管理です。
調達管理の目的
調達管理の主な目的は、製造に必要な資源を適切なタイミングで確保し、生産活動の標準化とコスト最適化を実現することです。具体的には以下の3つの目的があります。
|
目的 |
内容 |
|
安定的な資材供給の確保 |
製造ラインの停止を防ぎ、計画通りの生産を維持するため、必要な資材を安定的に調達する |
|
コスト削減と利益率の向上 |
仕入価格の交渉や複数社からの相見積により、調達コストを抑えて企業の利益率を高める |
|
品質基準の維持と向上 |
信頼できる仕入先から高品質な資材を調達し、最終製品の品質を保証する |
これらの目的を達成するため、調達担当者は市場動向の把握や仕入先との関係構築、社内各部門との連携を日常的に行います。調達管理を適切に実施すれば、製造現場の生産性向上と企業全体の競争力強化につながるでしょう。
製造業で購買・調達が重視される理由
製造業において、購買・調達業務が特に重要視されるのには明確な理由があります。それは、調達業務が以下のように企業の「利益」「生産活動」「品質」という、経営の根幹をなす3つの要素に直接的な影響を与えるためです。
|
重視される側面 |
具体的な理由 |
|
利益への直接的な影響 |
製造原価における原材料費や部品費が占める割合は大きく、調達コストをわずか数パーセント削減するだけでも、営業利益を大幅に改善する効果が期待できます。これは、売上を同額向上させるよりも容易に利益貢献できるケースが多く、収益性向上の重要なレバーとなります。 |
|
生産活動の標準化 |
生産ラインは、一つの部品が欠けるだけで停止する可能性があります。購買・調達は、必要な資材を計画通りに供給し続けることで、生産の遅延や機会損失を防ぐ「サプライチェーンの要」です。安定供給体制の構築は、事業継続計画(BCP)の観点からも不可欠です。 |
|
製品品質の担保 |
最終製品の品質は、調達する部品や原材料の品質に大きく依存します。信頼できるサプライヤを選定し、仕様通りの品質を確保することは、製品の信頼性を守り、ブランドイメージを維持するうえで欠かせないプロセスです。品質不良による手戻りやリコールは、多大な損失につながります。 |
このように、購買・調達はコスト管理、安定生産、品質保証という製造業の生命線を一手に担う活動です。そのため、その業務プロセスをいかに最適化し、戦略的に遂行するかが、企業の競争力を決定づける鍵となります。
購買管理と調達管理の違い
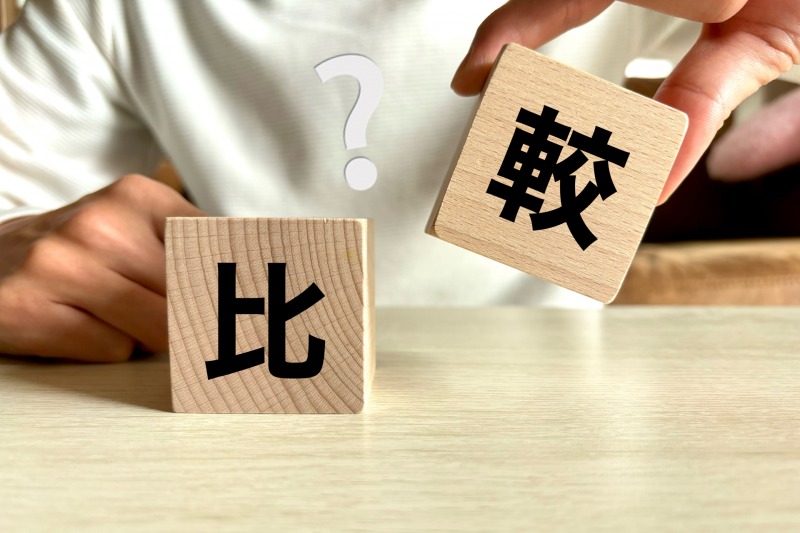
調達管理が生産に必要なモノや人材・資金を調達するのに対して、購買管理は原材料や物品の購入を検討し発注するまでのプロセスを指します。
どちらも原材料や物品の購入を管理するため、混同されやすいですが、主に次のような違いがあります。
|
購買管理 |
調達管理 |
|
|
管理目的 |
モノを購入する |
モノを購入し納品まで管理する |
|
入手手段 |
購入 |
購入や借入など |
|
対象 |
資材や物品 |
モノ、人材、資金など |
購買管理がモノを購入するまで管理するのに対して、調達管理はモノを発注して納品するまで管理することです。
購買管理は、資材を購入して仕入れますが、調達管理では購入だけでなく借入などさまざまな手段で、生産に必要なモノや人・金を共有します。
調達管理の業務内容とは?

調達管理の業務内容は、次のとおりです。
- 仕入先の選択
- 仕入価格の交渉
- 企画・開発・製造など他部門との調整
- 見積・発注と納期管理
- 検査・検収
それぞれの業務に必要な資質や能力を解説するため、調達管理を行う際の参考にしてください。
1.仕入先の選択
資材を適切に調達するために、どの業者から仕入れるのか選択します。既存の仕入業者から選択するだけではなく、新規業者を開拓することも重要です。
不測の事態で資材が調達できなくなることも想定して、複数の安定した仕入先を確保しなければなりません。こうした適切な選択・開拓を行うためには、戦略的な視野と経験が求められます。
2.仕入価格の交渉
見積価格が適切か判断し、価格交渉を行うことも調達管理の重要な業務です。品質を確保しながら、より安い価格で仕入れるためには、原価や市場動向に関する正確な知識が求められます。
業者に適切な価格を提示するためには、仕入価格、品質、納期の早さなど、必要な基準を正確に理解して交渉する能力が必要です。
3.企画・開発・製造など他部門との調整
企画・開発・製造など資材を必要とする部門に、適切に届けられるよう調整することが調達管理の重要な業務です。必要な資材の種類、数量、納期、価格を明確にし、業者への発注から部門への引き渡しまでの計画を立てます。
調達業務は多くの関係者とやり取りが必要なため、コミュニケーション能力も重要です。
4.見積・発注と納期管理
計画・調整したスケジュールを元に、仕入業者へ見積を行い発注をかけます。また、発注した資材が期日通り届くかどうか確認を行うことも、調達において欠かせない業務です。
ときにはスケジュールの変更を余儀なくされることもあるため、仕入先や社内の関係者との調整も必要とされます。
見積・発注と納期管理の業務では、以下のような資料が発生します。
|
資料 |
内容 |
目的 |
|
見積依頼書(RFQ) |
複数の仕入先に対して、資材の見積価格や納期条件を依頼する文書 |
最適な調達条件を比較検討するため |
|
発注書(PO) |
正式に資材の購入を依頼する文書で、品目・数量・単価・納期・納品場所などを明記 |
契約内容を明確化し、双方の認識を統一するため |
|
納期管理表 |
各発注案件の納期予定日・進捗状況・遅延リスクなどを一覧化した管理資料 |
納期遅延を未然に防ぎ、生産計画への影響を最小化するため |
|
納期調整依頼書 |
生産計画の変更や緊急対応が必要な際に、仕入先へ納期変更を依頼する文書 |
スケジュール変更に柔軟に対応し、生産活動を維持するため |
これらの資料を適切に作成・管理することで、調達プロセスの透明性が高まり、関係者間の情報共有がスムーズに進みます。
5.検査・検収
届いた資材の数や品質に問題がないか、検査・検収を行います。正確な検査・検収を行うためには、品質管理に関する知識や、より専門的な知識を持つ品質管理部門や製造部門などとの連携が重要です。
検査・検収の業務では、以下のような資料が発生します。
|
資料 |
内容 |
目的 |
|
受入検査記録 |
納品された資材の外観検査・寸法測定・数量確認などの結果を記録した文書 |
品質基準を満たしているか証明し、トレーサビリティを確保するため |
|
検収報告書 |
発注内容と納品内容の照合結果をまとめ、検収合格または不合格を判定した文書 |
支払処理を進める根拠とし、契約履行を確認するため |
|
不良品報告書 |
品質不良や数量不足が発見された際に、具体的な不良内容と対応を記録した文書 |
仕入先へ返品・交換を依頼し、再発防止策を協議するため |
|
在庫受入伝票 |
検収が完了した資材を在庫システムに登録するための伝票 |
正確な在庫数量を把握し、製造部門への払い出しを可能にするため |
これらの資料を確実に作成することで、調達した資材の品質保証と適切な在庫管理が実現し、製造工程への円滑な資材供給が可能となります。
調達管理の対象となる資材や資源

調達管理の対象となる資材や資源は、主に次のとおりです。
|
対象となる資材や資源 |
具体例 |
|
原材料 |
鉄材・樹脂材など加工して使用するもの |
|
部品 |
ネジやナットなどすぐに使用できるもの |
|
仕掛品 |
製造途中にある在庫品 |
|
保守部品 |
劣化や摩耗が生じた際に交換する部品 |
|
ソフトウェア |
製品に搭載するソフトウェア |
|
設備 |
製造設備や機械など |
|
副資材(MRO品) |
梱包材や工具、手袋、メンテナンスパーツなど生産業務に使うもの |
|
エネルギー |
電気やガス、水など |
原材料や部品、仕掛品などの「直接材」は売上や利益に直結します。対して、副資材やエネルギーなどの「間接材」は、業務を進める上で必要な資材・資源です。
調達管理の対象となる資材や資源は、大きく分けて「直接材」と「間接材」に分類されます。
調達管理業務のフロー

調達管理業務の基本プロセスは、次のとおりです。
- 調達管理計画の策定
- 調達の実施
- 調達の管理
- 検収
それぞれの基本プロセスを確認して、調達管理を適切に行いましょう。
1.調達管理計画の策定
調達品目情報や調達方法を決めるために、調達管理計画を策定します。
調達品目を整理するためには、プロジェクトマネジメント計画書や要求事項文書から内製と外注のどちらが適しているか検討する必要があります。
外注の場合は、調達の進め方をまとめた「調達マネジメント計画書」と、要件に関して取り決めた「調達作業範囲記述書」を作成しましょう。
外注を依頼する際の文書として、下記の4種類を活用してください。
|
文書の種類 |
特徴 |
|
RFI(情報提供依頼書) |
業務委託や入札、調達情報、製品やサービスの情報を収集するための文書 |
|
RFP(提案依頼書) |
自社が求める製品やサービスを提案してもらうための条件をまとめた文書 |
|
IFB(入札招請書) |
調達や業務委託する場合に、納入業者に調達に入札するよう求める文書 |
|
RFQ(見積依頼書) |
購入したい商品やサービスの見積価格を提示してもらう文書 |
上記の文書を活用すれば、外注先とスムーズに取引を進められます。
また、調達管理計画の策定段階では、以下の資料を作成することで、調達業務の方向性と基準を明確化することが可能です。
|
内容 |
活用目的 |
|
|
調達マネジメント計画書 |
調達の進め方、管理方法、スケジュール、承認プロセスなどを定義した文書 |
調達活動全体の指針とし、関係者間で調達方針を共有するため |
|
調達作業範囲記述書 |
外注する業務や資材の要件、仕様、品質基準、納期などを詳細に記載した文書 |
サプライヤとの責任範囲を明確にし、認識のズレを防ぐため |
|
発注選定基準表 |
サプライヤを選定する際の評価項目(品質・価格・納期・信頼性など)と配点を定めた基準表 |
客観的かつ公平にサプライヤを評価し、最適な発注先を選定するため |
|
調達予算計画書 |
各調達品目の予算配分と支出スケジュールを記載した計画書 |
コスト管理を適切に行い、予算超過を防止するため |
2.調達の実施
調達管理計画を策定した後は、計画書に基づいて発注先を選定しましょう。自社が求める条件に合った発注先と交渉を進め、契約を締結させてください。
発注先を選定する際は、調達する対象によって選定基準が異なります。
例えば、製造に必要な部品を調達する際は、複数のサプライヤーに見積依頼して、QCD(品質・コスト・納期)の観点から最適な発注先を見極めましょう。
ソフトウェアを調達する際は、複数のサプライヤーから提案を受けられるよう、コンペ方式で発注先を選定してください。
発注先と交渉を行った上で、合意書を交わしてから調達を実施しましょう。
現場で使う資料例
- 見積比較表(スコアリング):単価、LT、最小ロット、欠品履歴、総合点
- 交渉論点シート:価格方式、価格改定条項、VMI可否、補給部品対応
- 契約ひな形:基本契約、品質協定、秘密保持、個別注文の優先順位
- 発注書(PO):品目コード、仕様/版数、数量、単価、希望納期、分納、検収基準、承認
3.調達の管理
発注先と契約を締結した後は、契約通りに調達が実施されているか管理する必要があります。
サプライヤーに進行をまかせていると、納期遅れなどのトラブルが発生する可能性があるため、進捗管理や品質管理を行います。
スケジュール通りに調達が進んでいるか、注文数や納品数が合っているかを確認し、計画通りに納品されるようサプライヤーの進捗を管理してください。
調達の管理段階では、以下の資料を作成することで、調達プロセスの進捗を可視化し、問題の早期発見と対応が可能です。
|
内容 |
活用目的 |
|
|
進捗管理表 |
各発注案件の進捗状況、予定納期、実績納期、遅延リスクなどを一覧化した管理表 |
納期遅延の兆候を早期に発見し、必要な対策を講じるため |
|
サプライヤ定期連絡記録 |
サプライヤとの定期的な連絡内容、確認事項、課題と対応策を記録した文書 |
コミュニケーション履歴を残し、認識のズレを防止するため |
|
品質監視レポート |
納品前の品質確認結果や、サプライヤの製造工程での品質データをまとめたレポート |
品質問題を未然に防ぎ、納品後の不良を最小化するため |
|
変更管理記録 |
数量変更、納期変更、仕様変更などの変更内容と承認プロセスを記録した文書 |
変更履歴を明確に管理し、契約内容との整合性を保つため |
4.検収
資材や資源が納品された後は、作業と成果物を確認して検収しましょう。調達した資材がモノの場合は、品質・納期・数量などをチェックします。
ソフトウェアやエネルギー資源を調達した場合は、希望どおりの仕様と合っているか確認する必要があります。
検収で成果物が不合格の場合は、納入者に連絡して資材の納品や修正を依頼します。
検収段階では、以下の資料を作成することで、納品物の品質を保証し、支払処理と在庫管理を適切に進められます。
|
内容 |
活用目的 |
|
|
受入検査チェックリスト |
納品された資材の外観、寸法、数量、仕様などを項目ごとにチェックする検査表 |
検査漏れを防ぎ、品質基準を満たしているか客観的に判定するため |
|
検収完了報告書 |
発注内容と納品内容を照合し、検収結果(合格・不合格)を記載した正式な報告書 |
支払承認の根拠とし、契約履行の証跡を残すため |
|
不良品対応記録 |
品質不良や数量不足が発見された際の具体的内容、サプライヤへの連絡内容、対応結果を記録した文書 |
不良原因を追跡し、再発防止策をサプライヤと協議するため |
|
在庫受入伝票 |
検収が完了した資材を在庫管理システムに登録するための正式な受入伝票 |
正確な在庫数量を把握し、製造部門への払い出しを可能にするため |
|
サプライヤ評価データ |
納期遵守率、品質合格率、対応品質などを数値化したサプライヤ評価データ |
次回以降のサプライヤ選定や継続取引判断の根拠資料とするため |
調達業務に求められる能力

調達業務に求められる能力は、次のとおりです。
- 市場動向のリサーチ力
- コミュニケーション力・交渉力
- スケジュール管理能力
- 課題解決力
それぞれの能力を確認して、調達業務を効率化しましょう。
市場動向のリサーチ力
調達業務において、市場動向のリサーチ力は欠かせません。
原材料やサービスの価格変動、供給の安定性、業界のトレンドを正確に把握するリサーチ力は、調達業務を進める上で必要なスキルです。
市場動向をリサーチして、自社に合った調達先を選定し、適切なタイミングで調達を依頼できるため、QCD維持・向上につながります。
コミュニケーション力・交渉力
調達業務を円滑に進める上で、コミュニケーション力や交渉力が重要です。
調達担当者には、サプライヤーや社内の関係者と良好な関係を築き、円滑に業務を進めるためコミュニケーションを頻繁に取ります。
また、価格交渉や納期調整の場面では、相手を説得し合意を得る交渉力が求められます。
高いコミュニケーション力と交渉力があれば、調達条件を最適化することが可能です。
スケジュール管理能力
調達業務では、納期を守るための進捗管理・スケジュール管理能力が重要です。
必要な資材やサービスを適切なタイミングで確保するためには、サプライヤーの進捗状況を管理し納品スケジュールを調整する必要があります。
スケジュール管理能力には、納期遅延を防ぐためのリスク管理や柔軟な対応力も含まれます。
課題解決力
調達プロセスには、予期せぬ問題が発生するケースがあるため、課題解決力が必要です。
サプライヤーのトラブルや市場の変動に対応するために、原因を分析し代替案を提案できる課題解決力が求められます。
これらの能力を身につければ、調達業務の効率化と品質向上を実現することができます。
調達業務の課題
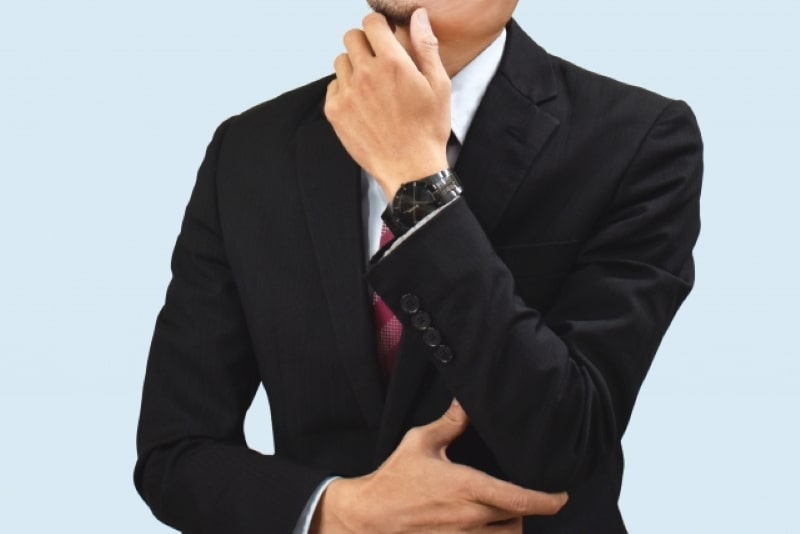
調達業務をスムーズに進めるためには、下記の調達業務の課題を解決する必要があります。
- ノウハウが属人化しやすい
- 購買価格にばらつきが生じやすい
- 事務作業が煩雑化しやすい
- サプライチェーンマネジメントが難しい
調達業務を効率的に進めるため、上記の課題を確認して対策しましょう。

ノウハウが属人化しやすい
調達業務では、サプライヤとの交渉経験や市場価格の知識、品質判断の基準などが担当者個人に蓄積されやすく、ノウハウの属人化が深刻な課題です。
特定の担当者しか仕入先との関係性を把握していない状況では、急な欠勤や退職が発生した際に業務が停滞するリスクがあります。
見積書や発注書の様式、管理方法が担当者ごとに異なるケースも多く、組織全体で情報共有ができていない企業は少なくありません。
対策としては、調達管理システムの導入により取引履歴や交渉内容をデータベース化し、組織全体で情報を共有できる仕組みを構築することが有効です。
業務マニュアルの整備や定期的な社内研修も、ノウハウの標準化に役立ちます。
購買価格にばらつきが生じやすい
調達業務において、購買価格にばらつきが生じやすいことも重要な課題です。
担当者によって価格交渉力に差があったり、過去の仕入データを参照せずに発注したりすることで、同じ資材でも購入時期や担当者により価格が異なる状況が発生します。
市場価格は時間や状況によって変動するため、常に適切な価格で調達するには過去の仕入価格データの管理・分析が不可欠です。
しかし、データが一元管理されていない企業では、妥当な価格かどうかの判断基準が曖昧になりがちです。
対策として、仕入価格の履歴をデータベース化し、複数社からの相見積を取得して価格比較を徹底することが重要です。
購買管理システムを活用すれば、リアルタイムで市場価格と自社の購入価格を比較でき、コスト削減の機会を逃しません。
事務作業が煩雑化しやすい
調達業務では、見積書や発注書の作成・送付、納期確認、在庫照合などのルーチンワークが多く、事務作業の煩雑化が課題となっています。
特に消耗品などの間接材は品種が多く、各部門から頻繁に調達依頼が発生するため、見積や発注の処理に多大な時間を要します。
手作業での書類作成やメール・FAXでのやり取りが中心の企業では、入力ミスや情報伝達の遅延が発生しやすく、確認作業にも手間がかかるのが現状です。
こうした反復業務に時間を取られると、本来注力すべき価格交渉や新規サプライヤの開拓といった戦略的な調達活動に時間を割けません。
事務作業の煩雑化を解決するには、調達プロセスの標準化とシステム化が効果的です。
購買管理システムを導入すれば、発注書の自動生成や承認フローの電子化により、業務効率が大幅に向上します。
サプライチェーンマネジメントが難しい
調達業務における大きな課題の一つが、サプライチェーン全体を把握し管理することの難しさです。
製造業では、資材調達から製造、出荷まで複数の部門やサプライヤが関与するため、全体の流れを可視化できていない企業が多く存在します。
担当者が各関係者に個別に確認を取る体制では、情報伝達に時間がかかり、伝達ミスも発生しやすくなります。その結果、納期遅れや過剰在庫、在庫切れといったトラブルが起こり、生産計画全体に影響を及ぼしかねません。
対策としては、調達管理部門だけでなく、社内の業務フロー全般を見直し、部門間の情報共有を促進することが重要です。
統合的な管理システムを導入することで、サプライチェーン全体の可視化が実現し、適切な在庫管理と納期管理が可能となります。
調達業務を効率化する方法

属人化やコストのばらつきといった課題を抱える調達業務を、より戦略的で生産性の高い活動へと変革させるためには、具体的なアプローチが必要です。
ここでは、そのための効果的な2つの方法を解説します。
調達マネジメントを適正化する
調達業務の効率化を目指すうえで、まず取り組むべきは調達マネジメントの適正化です。
調達マネジメントとは、単に物品を購入するだけでなく、「何(What)を、いつ(When)、どこから(Where)、どれだけ(How much)、いくらで(How much price)購入するか」という調達活動の全プロセスを、戦略的な視点から管理・最適化することです。
このマネジメントが機能していないと、場当たり的な対応に終始し、根本的な課題解決には至りません。
調達マネジメントの適正化は、以下の3つの柱で進めることが有効です。
|
取り組みの柱 |
具体的な内容と目的 |
|
1. 業務プロセスの標準化 |
各部門や担当者で異なっていた発注ルール、見積の取得方法、承認フローなどを全社的に統一します。これにより、業務の属人化を防ぎ、誰が担当しても一定の品質を担保できる体制を構築します。また、プロセスの可視化は、内部統制の強化にも直結します。 |
|
2. 戦略的ソーシングの実践 |
目先の価格だけでなく、品質、供給の安定性、技術力、そして将来的な協力関係といった多角的な視点でサプライヤを評価・選定します。取引先を戦略的に集約することで、より強固なパートナーシップを築き、価格交渉力を高め、安定したサプライチェーンを確保することが目的です。 |
|
3. データに基づく継続的な改善 |
過去の購買実績、サプライヤの評価、コストの推移といったデータを収集・分析し、客観的な根拠に基づいて調達戦略を見直します。勘や経験だけに頼るのではなく、データドリブンなアプローチを取り入れることで、継続的なコスト削減や品質改善の機会を発見できます。 |
これらの取り組みを通じて調達マネジメントを適正化することで、調達部門は単なる購買部署から、企業の利益創出に貢献する戦略的パートナーへと進化することが可能です。
購買管理システムを導入する
調達マネジメントを適正化し、その効果を最大化するための具体的な手段が「購買管理システム」の導入です。
手作業やExcelによる管理では限界があった業務の標準化やデータ活用を、システムによって飛躍的に向上させることができます。
購買管理システムは、調達業務にまつわるさまざまな課題を解決し、担当者を煩雑な作業から解放する力を持っています。
システム導入によって得られる主なメリットは以下の通りです。
|
導入メリット |
システムが実現すること |
|
1. 圧倒的な業務効率化 |
見積依頼から発注、検収、支払い依頼までの一連のプロセスをシステム上で一元管理。手作業による伝票作成や転記作業が不要になり、承認フローも電子化されるため、業務時間を大幅に短縮できます。 |
|
2. 全社的なコスト削減 |
全社の購買データが可視化されることで、「どの部署が・何を・いくらで」購入しているかが一目瞭然になります。これにより、部門を超えた集中購買によるボリュームディスカウントや、不適切な高コストでの購買の抑制が可能となります。 |
|
3. 内部統制とコンプライアンスの強化 |
システム上で設定された承認ルートと権限に基づき、購買プロセスが実行されるため、不正な発注やコンプライアンス違反のリスクを低減します。また、すべての取引記録がログとして残るため、監査対応も容易です。 |
|
4. 戦略的な意思決定の支援 |
蓄積された購買データを分析することで、サプライヤごとの実績評価、品目ごとのコスト分析などが可能になります。これにより、客観的なデータに基づいたサプライヤ選定や価格交渉といった、より戦略的な活動に注力できます。 |
購買管理システムの導入は、単なる業務効率化ツールにとどまりません。それは、調達部門が本来果たすべき戦略的機能を遂行するための経営基盤であり、企業の競争力を高めるための重要な投資と言えるでしょう。
調達業務をDX化するメリット

 調達業務のDX化は、業務効率の向上だけでなく、経営戦略上の競争力強化にもつながります。ここでは、DX化により得られる5つの具体的なメリットを解説します。
調達業務のDX化は、業務効率の向上だけでなく、経営戦略上の競争力強化にもつながります。ここでは、DX化により得られる5つの具体的なメリットを解説します。
発注業務を効率化できる
DX化により発注業務の効率が飛躍的に向上します。
従来は見積依頼書や発注書を手作業で作成し、メールやFAXで送信していた作業が、システム上でワンクリックで完結することが可能です。
承認フローも電子化されるため、承認待ちの時間が短縮され、発注リードタイムが大幅に削減されます。
さらに発注履歴がデータベースに自動保存されるため、過去の取引内容を瞬時に検索でき、類似案件の発注時の参考に役立ちます。
購買価格の標準化ができる
DXを通じて全社の購買データを一元的に可視化・分析することで、部門ごとにバラバラだった購買価格の適正化を図れます。
システムが過去の取引価格や市場価格を提示してくれるため、担当者の経験や勘に頼ることなく、データに基づいた価格交渉が可能です。
これにより、不必要な高値での購入を防ぎ、購買価格の標準化とコスト削減を実現します。
属人性を解消し透明性を向上できる
DX化により調達業務の属人性が解消され、組織全体で情報を共有できます。
サプライヤとの交渉履歴や取引条件、品質評価データがシステムに記録されるため、特定の担当者しか知らない情報がなくなるためです。
業務プロセスが可視化され、誰がどの段階で承認したのかも明確になるため、不正取引の防止にもつながります。
さらに後任者への引き継ぎがスムーズに行え、担当者の急な欠勤や退職時でも業務が停滞しません。
コア業務に集中できる
発注や納期管理といった定型的な事務作業をシステムに任せることで、調達担当者は本来注力すべきコア業務に多くの時間を割けるようになります。
例えば、新規サプライヤの開拓、既存サプライヤとの関係強化、市場動向の分析に基づいたコスト削減戦略の立案など、より付加価値の高い戦略的な活動に集中することが可能です。
人事評価制度の構築に役立つ
DX化により調達業務の成果が数値化され、公平な人事評価制度の構築が可能です。
コスト削減率、納期遵守率、サプライヤ評価スコアなどのKPIがシステムで自動集計されるため、各担当者の業績を客観的に評価できます。
従来は評価しにくかった調達業務の貢献度が可視化され、適切なフィードバックと報酬設定が実現します。
調達担当者のモチベーション向上と人材育成が促進され、組織全体の調達力の強化が可能です。
調達業務をDXするときの注意点

調達業務のDXは、単にデジタルツールを導入すれば成功するわけではありません。
その効果を最大化するためには、陥りがちな落とし穴を避け、戦略的にプロジェクトを推進する必要があります。
ここでは、DX化を成功に導くために特に重要となる2つの注意点について解説します。
ソーシングもシステム化する
調達業務のDXを検討する際、多くの企業が見積取得や発注といった日々の「パーチェシング(購買)」業務の効率化に注目しがちです。
しかし、真の変革を遂げるには、サプライヤの選定や価格交渉といった、より上流にある「ソーシング」の領域もシステム化の対象に含めることが重要です。
ソーシングは、調達コストや品質を決定づける根幹のプロセスであり、この領域が属人的なままだとDXの効果は限定的になります。
|
業務内容 |
DX化を怠った場合の問題点 |
|
|
ソーシング |
サプライヤの探索・評価・選定、価格交渉、契約 |
担当者の経験と勘に依存し、最適なサプライヤ選定や価格交渉ができているか客観的に判断できない。取引経緯がブラックボックス化する。 |
|
パーチェシング |
見積依頼、発注、検収、支払い |
事務作業の効率は上がるが、そもそも「高く買っている」という根本的なコスト課題は解決されない。 |
ソーシングをシステム化することで、サプライヤ情報や過去の取引実績、交渉履歴が一元管理され、データに基づいた最適なサプライヤ選定が可能になります。
調達DXの恩恵を最大限に引き出すためには、パーチェシングだけでなく、ソーシング領域のデジタル化も同時に推進する視点が不可欠です。
データに基づく効果検証を行う
購買管理システムの導入はゴールではなく、DXのスタートラインです。
導入後にその効果を客観的に評価し、継続的な改善活動につなげるプロセスがなければ、投資対効果を最大化することはできません。
そのために不可欠なのが、データに基づく定量的な効果検証です。
DX推進にあたっては、事前に「何を」「どの程度」改善するのかという具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、導入前後でその数値を比較・検証する仕組みを構築する必要があります。
|
効果検証の指標(KPI例) |
測定方法 |
|
調達コスト削減率 |
システム導入前後で、同一品目や類似品目の平均購入単価がどの程度変化したかを比較する。 |
|
業務リードタイム短縮率 |
見積依頼から発注完了まで、あるいは発注から検収完了までの平均所要時間を測定し、短縮率を算出する。 |
|
納期遵守率 |
システム上で管理される納期情報と、実際の納品日の差異を分析し、サプライヤごとの遵守率を可視化する。 |
|
ペーパーレス化率 |
発注書や請求書など、従来は紙で扱っていた帳票のうち、電子化された割合を測定する。 |
これらの客観的なデータに基づいてPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回し、新たな課題の発見やプロセスの最適化を継続的に行うことこそが、調達DXを真の成功に導く鍵となります。
自社にあった調達業務システムの選び方

調達業務システムを導入する際は、自社の業務特性や課題に適したシステムを選定することが成功の鍵です。
システム選定時に確認すべきポイントを理解し、最適なシステムを見極めましょう。
調達業務システムを選ぶ際は、以下の6つの観点から総合的に評価することが重要です。
|
選定基準 |
確認ポイント |
重要性 |
|
機能の適合性 |
見積管理、発注管理、検収管理、サプライヤ管理など、自社が必要とする機能が網羅されているか確認する。特に製造業では、直接材と間接材の両方に対応できるかがポイント |
業務効率化の成否を左右する最重要項目 |
|
既存システムとの連携性 |
生産管理システムや在庫管理システム、会計システムなど既存の基幹システムとデータ連携が可能か確認する。API連携やデータ形式の互換性を事前に検証すること |
システム導入効果を最大化するための必須要件 |
|
カスタマイズの柔軟性 |
自社独自の業務フローや承認ルートに対応できるカスタマイズ性があるか確認する。標準機能だけでは対応できない要件がある場合、追加開発の可否とコストを把握する |
業務フィットを高め、現場の定着率を向上させる |
|
操作性とユーザビリティ |
直感的に操作できるインターフェースか、マニュアルなしでも使いこなせるか確認する。トライアル期間を活用し、実際の担当者に操作してもらい評価することが有効 |
現場の受け入れと活用促進に直結する |
|
サポート体制 |
自社への導入研修や運用サポート体制はもちろん、取引先であるサプライヤへのシステム展開支援が充実しているかを確認しましょう。システムトラブル時の対応速度やベンダーの実績も重要な判断材料です。 |
安定運用と継続的な改善活動を支える基盤 |
|
コストと投資対効果 |
初期導入費用だけでなく、月額利用料、カスタマイズ費用、保守費用などトータルコストを算出する。削減できる工数やコストを試算し、投資回収期間を明確化する |
経営判断と予算承認を得るための根拠 |
システム選定時は、複数のベンダーから提案を受け、デモンストレーションや無料トライアルを活用して比較検討しましょう。
調達業務をDXによって業務効率を改善した企業事例

調達業務のDXは、理論上多くのメリットをもたらしますが、実際に取り組んだ企業はどのような成果を上げているのでしょうか。
ここでは、具体的な課題をDXによって解決し、業務効率やコスト競争力の向上を実現した3つの企業の事例をご紹介します。
事例1:サプライヤ管理の効率化で納期遵守率95%を達成した自動車部品メーカー
ある自動車部品メーカーでは、200社以上のサプライヤと取引があり、納期管理が煩雑化していました。担当者が個別にメールや電話で納期確認を行っており、情報が属人化し、納期遅延が頻発していたのです。
この企業は、サプライヤポータル機能を持つ調達管理システムを導入し、サプライヤがシステム上で納期回答や出荷連絡を行える仕組みを構築しました。進捗状況がリアルタイムで可視化され、遅延リスクの早期発見が可能になったのです。
導入後、納期遵守率は70%から95%に向上し、生産計画の標準化が実現しました。また、納期確認に費やしていた時間が月間80時間削減され、サプライヤとの関係強化や新規開拓活動に時間を割けるようになっています。
事例2:ホクト株式会社様 – 段階的なシステム導入で購買業務を標準化し、年間250万円のコスト削減を実現
ホクト株式会社様では、全国の複数拠点で購買業務が独自に運用されており、紙ベースでの見積書や発注書のやり取りが多く、業務の標準化とペーパーレス化が課題となっていました。
コンサルティング会社からの提案をきっかけに、調達支援システム「PROCURESUITE」の導入を決定し、長野県内の拠点からスタートして段階的に全国へ展開する慎重なアプローチを採用しました。
システム導入により、見積依頼から発注、検収までの一連のプロセスを電子化し、承認フローもシステム上で完結できるようになりました。
導入後は、相見積の作成が容易になり、安価な業者を選定できるようになったことで仕入コストの削減を実現しています。
さらに導入から3年が経過した時点で、継続的にシステムの活用範囲を広げた結果、全体工数が導入前の1/2にまで短縮されました。
特に注目すべき成果は、相見積取得の徹底により、間接材の購入価格を年間250万円削減できた点です。
購買データの蓄積と分析により、価格交渉の根拠となるデータが明確になり、サプライヤとの価格交渉を優位に進められるようになりました。
この事例は、DXが単なる業務効率化にとどまらず、継続的な改善活動を通じて企業の収益性向上に直結することを示しています。
詳細な導入事例は、以下のページで確認できます。
関連:導入から3年で活用を深化。PROCURESUITEで間接材購入価格を250万円/年 削減
調達管理業務をシステム化で効率化しよう

調達管理は、他の業務を円滑に行うために欠かせない業務です。さらに購入費用などのコストに直結する業務でもあるため、戦略的な視野が求められる業務でもあり、多くの課題を解決しなければなりません。
調達管理をシステム化すれば、業務効率を向上させて従業員の負担を軽減できます。、調達管理に不慣れな担当者でも簡単に情報管理・スケジュール管理ができるシステムを導入すれば、業務の属人化を防止できます。
管理システムを導入する際は、他部門とも連携できるシステムを選び、より効率的な業務を実現しましょう。
調達支援システム「PROCURE SUITE」を活用すれば、調達プロセスを可視化し業務コスト・工数を削減できます。
詳しくは下記のボタンより、資料をダウンロードできるため、お気軽にご請求ください。
煩雑化している購買業務を効率化。調達プロセスの可視化ができる調達支援システム
おすすめのお役立ち資料はこちら↓