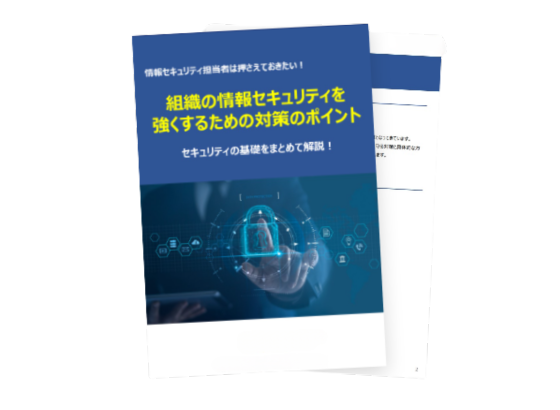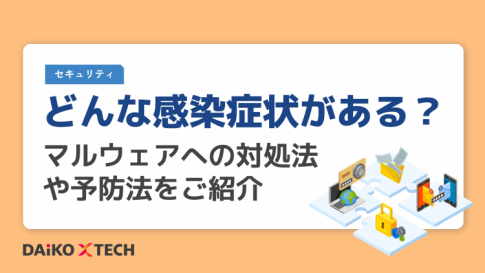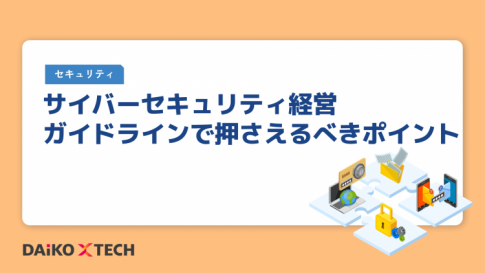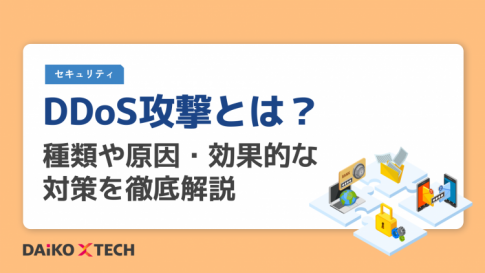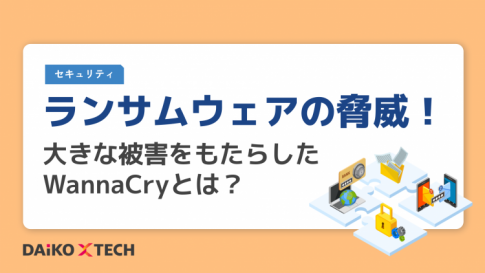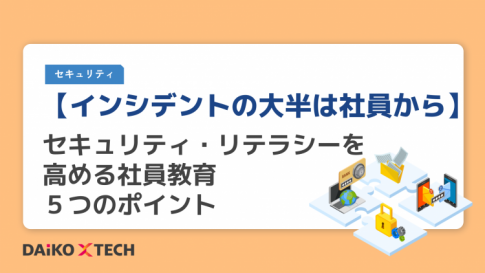情報資産管理台帳とは、企業や組織が保有する情報資産を一元的に把握・管理するための一覧表やデータベースのことです。
情報管理台帳の目的を正しく理解し、適切に作成・運用することは、企業のセキュリティレベルを本質的に向上させ、経営リスクを低減する強力なツールとなります。
この記事では、情報資産管理台帳の根本的な目的から、監査にも通用する具体的な作成手順、そして形骸化させないための運用ポイントまでを分かりやすく解説します。
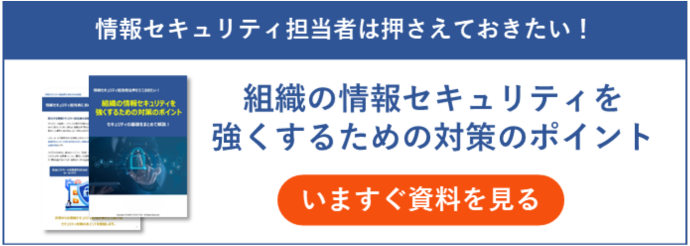
目次
そもそも情報資産管理台帳とは?
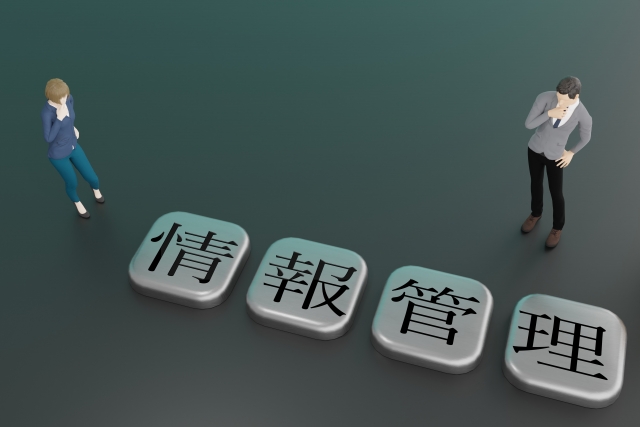
情報資産管理台帳について理解を深めるためには、まず「情報資産」という言葉の意味を正しく把握することが重要です。
ここでは、基本的な概念から分かりやすく解説します。
情報資産とは
情報資産とは、企業や組織にとって価値を持つ情報のすべてを指します。
これは、単にデジタルデータだけを意味するものではありません。
ハードウェアやソフトウェア、さらには従業員の持つ知識やノウハウまで、幅広いものが含まれます。
|
分類 |
具体例 |
|
データ |
顧客情報、財務情報、人事情報、技術情報、営業秘密 |
|
ハードウェア |
サーバー、パソコン、スマートフォン、ネットワーク機器、USBメモリ |
|
ソフトウェア |
OS、業務アプリケーション、ウイルス対策ソフト、自社開発システム |
|
知的財産 |
特許、商標、著作権、設計図、ノウハウ |
|
従業員・組織 |
従業員の知識やスキル、組織の運用ノウハウ、サプライヤーとの関係性 |
情報資産管理台帳とは情報資産の「カルテ」
情報資産管理台帳とは、これらの多岐にわたる情報資産を一覧化し、管理するための台帳です。
言わば、一つひとつの情報資産に関する「カルテ」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
この台帳は、単に資産の名称をリストアップするだけではありません。
情報資産管理台帳のどこに保管され、誰が管理し、どの程度の重要性を持つのかといった情報を記録します。
さらに、その資産に潜むリスクを評価し、どのような対策を講じているかを記載することで、情報資産を保護するための重要な基盤となります。
情報資産管理台帳を作成する5つの重要な目的

情報資産管理台帳の作成は、企業のセキュリティとガバナンスを強化し、経営を安定させるための重要な活動です。
ここでは、台帳を作成する5つの具体的な目的を解説します。
|
目的 |
主なメリット |
|
1. 情報資産の可視化 |
組織が保有する全資産を網羅的に把握し、管理の漏れを防ぐ |
|
2. リスク管理の強化 |
潜在的なリスクを評価し、優先順位をつけて効果的な対策を実施できる |
|
3. コンプライアンス遵守 |
ISMS/Pマークや各種法令の要求事項を満たし、対外的な信頼を得る |
|
4. 業務効率化 |
資産の所在や管理者を明確にし、情報探索の時間を短縮する |
|
5. 知的財産の保護 |
企業の競争力の源泉である知的財産を特定し、適切に保護する |
目的1:情報資産の「見える化」による現状把握
最初の目的は、組織内にどのような情報資産が、どこに、どのように存在しているのかを正確に把握することです。
これが「情報資産の見える化(可視化)」です。
多くの企業では、各部署が個別に情報を管理しているため、全社的な視点で資産を把握できていないケースが少なくありません。
台帳を作成することで、これまで管理対象から漏れていたサーバーや、退職者が利用していたアカウントなどを発見できます。
このように全体像を可視化することが、適切な管理の第一歩となります。
目的2:セキュリティリスクの適切な評価と対策
2つ目の目的は、情報漏洩や不正アクセス、データ損失といったセキュリティリスクを管理することです。
台帳を通じて各資産の重要度を評価し、それぞれにどのような脅威や脆弱性が存在するのかを分析します。
例えば、顧客データを扱うサーバーには「ランサムウェア攻撃」という脅威があり、「パッチが未適用」という脆弱性が存在するかもしれません。
台帳上でこれらのリスクを評価し、スコア化することで、限られた予算とリソースをどこに優先的に投下すべきか、合理的な判断が可能になります。
目的3:ISMS認証や法令遵守(コンプライアンス)への対応
情報資産管理台帳の作成は、ISMS(ISO/IEC 27001)やプライバシーマークといった情報セキュリティ関連の認証を取得・維持するために必須の要件です。
また、個人情報保護法やEUのGDPRなど、国内外の法令も企業に対して厳格な情報管理を求めています。
監査や審査の際には、この台帳が自社は適切に情報資産を管理し、リスク対策を講じていることを示す客観的な証拠となります。
つまり、台帳は企業の社会的信頼性を担保するための重要な文書と言えます。
目的4:業務効率の向上と無駄なコストの削減
4つ目の目的は、日々の業務を効率化することです。
台帳によって情報資産の保管場所や管理者が一元管理されていれば、必要な情報へ迅速にアクセスできます。
さらに、使用されていないソフトウェアライセンスや過剰なスペックのサーバーなどを特定し、ITコストを削減する効果も期待できます。
目的5:知的財産の保護と企業競争力の維持
最後の目的は、企業の競争力の源泉となる知的財産を守ることです。
製品の設計図や独自の製造ノウハウ、極秘のマーケティング戦略などは、企業の最も重要な情報資産と言えるでしょう。
台帳作成の過程でこれらの知的財産を明確に特定し、その重要度に応じた最高レベルのセキュリティ対策を講じることが可能になります。
これは、模倣や情報流出から自社の強みを守り、持続的な成長を支える「攻めのセキュリティ」と言えます。
【項目一覧】情報資産管理台帳に記載すべき内容

ISMS認証などの要件を満たし、かつ実用的な台帳を作成するために推奨される項目を一覧にまとめました。
これらを基本とし、自社の状況に合わせて項目を追加・修正してください。
|
基本項目 |
説明 |
記入例 |
|
資産ID |
情報資産を社内で一意に識別するための番号 |
HW-001, SW-015, DOC-101 |
|
資産名 |
情報資産の具体的な名称 |
経理部ファイルサーバー, 顧客管理システム, 営業秘密保持契約書 |
|
資産の分類 |
ハードウェア、ソフトウェア、データなどの分類 |
ハードウェア |
|
管理部署・責任者 |
その資産を主管する部署と管理責任者 |
経理部・〇〇部長 |
|
保管場所・媒体 |
物理的な場所やサーバー名、書類、USBメモリなどの媒体種別 |
本社サーバルームA-3ラック, クラウド(AWS), 紙媒体 |
|
利用者・アクセス範囲 |
その資産を利用できる従業員の範囲 |
経理部員のみ |
|
個人情報の有無 |
個人情報が含まれるかどうか |
有 |
|
保存期間 |
法令や社内規程で定められた保存期間 |
7年間 |
|
機密性・完全性・可用性 |
情報セキュリティの3要素(CIA)に基づく評価値(後述) |
機密性:3, 完全性:3, 可用性:2 |
|
重要度(総合評価) |
CIA評価を基にした総合的な重要度(高・中・低など) |
高 |
|
リスク評価 |
想定される脅威、脆弱性、発生時の影響度 |
脅威:ランサムウェア感染, 脆弱性:OSパッチ未適用 |
|
セキュリティ対策 |
実施している、または計画している具体的な保護措置 |
ウイルス対策ソフト導入, アクセス制御, 定期バックアップ |
|
登録日・更新日 |
台帳に情報を登録した日と最終更新日 |
2024/10/01 |
|
備考 |
その他特記事項 |
リース物件(契約期間:〜2026/09/30) |
製造業の信頼を守る|情報セキュリティ監査とは?必要性から基準、資格まで徹底解説
情報資産管理台帳の具体的な作り方

目的と記載項目がわかったところで、いよいよ作成手順です。
以下の4つのステップに沿って進めれば、誰でも効率的に、かつ網羅性の高い情報資産管理台帳を作成できます。
ステップ1:情報資産の洗い出しと特定
最初のステップは、自社が保有する情報資産を漏れなくリストアップすることです。
この「棚卸し」作業が台帳の品質を左右する最も重要な工程と言えます。
- 各部門へのヒアリング: 経理、人事、営業、開発など、各部門の担当者に業務で使用している情報、書類、機器などをヒアリングします。
- 既存台帳の活用: 固定資産管理台帳やソフトウェアライセンス管理簿など、すでにあるリストを確認し、転記します。
- IT資産管理ツールの利用: ネットワークに接続されているPCやサーバー、インストールされているソフトウェアを自動で検出できるツールを使えば、手作業による漏れやミスを大幅に削減できます。
この段階では、重要度の判断はせず、とにかくあらゆる資産を洗い出すことに集中するのがポイントです。
ステップ2:台帳フォーマットの作成(IPAのテンプレート活用)
次に、洗い出した情報を記入するための台帳フォーマットを用意します。
ゼロからExcelで作成することも可能ですが、効率性と網羅性を考えると、公的機関が提供するテンプレートを活用するのが賢明です。
特におすすめなのが、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開しているサンプルです。
ISMS認証を意識した項目が揃っており、無料でダウンロードしてすぐに利用できます。
まずはこのテンプレートをベースに、自社に不要な項目を削ったり、必要な項目を追加したりしてカスタマイズしましょう。
ステップ3:リスク評価とセキュリティ対策の検討
フォーマットが完成したら、洗い出した資産を一つずつ台帳に記入していきます。
その際、各資産に対してリスク評価を行います。
これは主に「機密性」「完全性」「可用性」の3つの観点(CIA)で行います。
|
評価観点 |
意味 |
評価の問いかけ |
|
機密性 (Confidentiality) |
認可された者だけがアクセスできること |
この情報が漏えいしたら、どれくらいの損害が出るか? |
|
完全性 (Integrity) |
情報が正確かつ最新の状態に保たれていること |
この情報が改ざんされたら、どれくらいの損害が出るか? |
|
可用性 (Availability) |
必要な時にいつでも情報にアクセスできること |
この情報が利用できなくなったら、どれくらいの損害が出るか? |
これらの観点で「高(3)・中(2)・低(1)」のように点数付けし、その資産の重要度を判断します。
そして、評価したリスクに応じて、「アクセス権限を最小化する」「データを暗号化する」といった具体的なセキュリティ対策を決定し、台帳に記載します。
ステップ4:台帳の運用と定期的な見直し
情報資産管理台帳は、一度作成したら終わりではありません。
事業内容の変化、新しいシステムの導入、従業員の入退社などにより、組織の情報資産は日々変化します。
そのため、台帳を常に最新の状態に保つための運用ルールを定めることが不可欠です。
- 更新担当者を決める: 資産の追加や変更があった際に、誰が台帳を更新するのかを明確にします。
- 定期的な棚卸しを実施する: 少なくとも年に1回は、全社的に情報資産の棚卸しを行い、台帳の内容と実態に乖離がないかを確認します。
- 監査やインシデントからのフィードバック: 内部や外部監査での指摘事項や、実際に発生したセキュリティインシデント(事故)の結果を台帳の評価や対策に反映させ、継続的な改善を行います。
情報資産管理台帳の運用ポイント

台帳を作成しても、それが活用されなければ意味がありません。
ここでは、台帳を形骸化させず、生きたツールとして運用していくための2つの重要なポイントを紹介します。
情報資産に潜むリスクを再評価する
ビジネス環境や技術は常に変化しており、それに伴い情報資産に潜むリスクも変わります。
例えば、新しい種類のサイバー攻撃が登場したり、法規制が改正されたりすることがあります。
したがって、台帳の定期的な見直しの際には、単に資産の増減を確認するだけでなく、リスク評価そのものを見直すことが重要です。
「以前は『中』リスクと評価していたが、最近の攻撃傾向を考えると『高』リスクに変更すべきではないか」といった議論を定期的に行うことで、常に現状に即したセキュリティ対策を維持できます。
情報資産管理ツールを導入する
従業員数が多く、保有するIT資産が数百、数千を超える規模の組織では、Excelによる手作業での台帳管理には限界があります。
更新漏れや記載ミスが発生しやすく、管理者の負担も非常に大きくなります。
そこで導入を検討したいのが、IT資産管理ツールです。
「使いやすさ」を追求した設計で、ログ管理・セキュリティ対策・デバイス管理など、情報漏えい対策に欠かせない多彩な機能を搭載。
クライアントPCだけでなく、オフィス内のネットワークに接続されたIT機器も含めて、一元的に管理することが可能です。
組織の規模や運用方針に合ったツールを選定することで、より精度の高い情報資産管理の実現につながります。
情報資産管理台帳を情報資産の安全な運用管理に活用しよう

情報資産管理台帳は、企業の重要な資産を守り、事業を継続させるための土台となる不可欠なツールです。
その目的は、単にリストを作ることではなく、資産を見える化し、リスクを評価して、適切な対策を講じることにあります。
除法資産管理台帳の作成は、担当者一人でも推進可能ですが、組織の規模によってはIT資産管理ツールの導入を検討した方が良い場合もあります。
正確で実用的な台帳を整備し、組織全体のセキュリティレベルを向上させましょう。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓