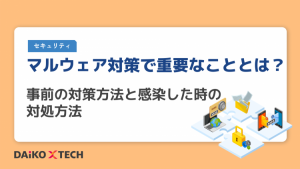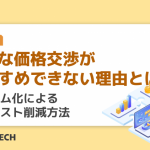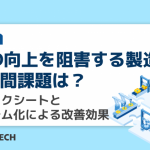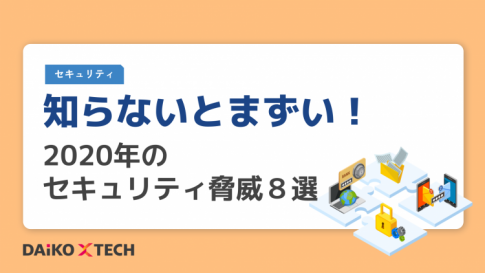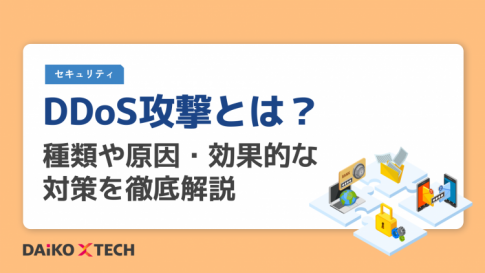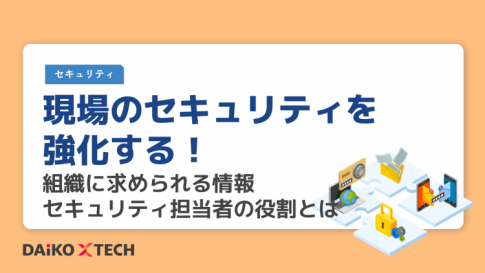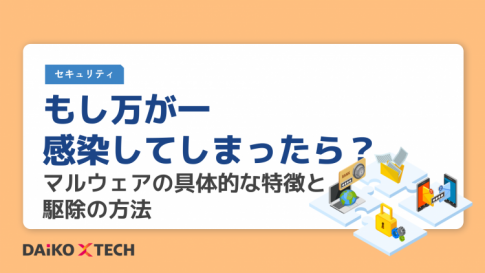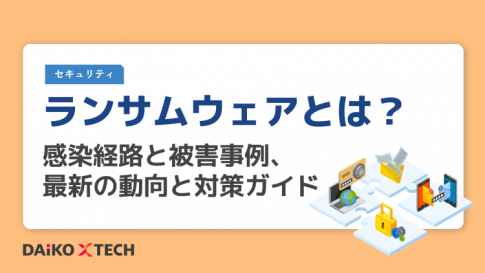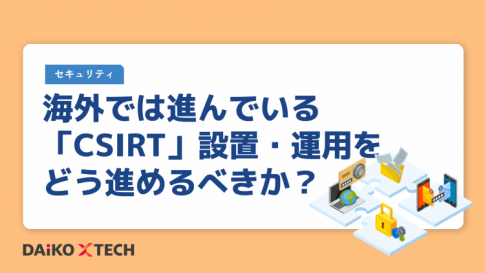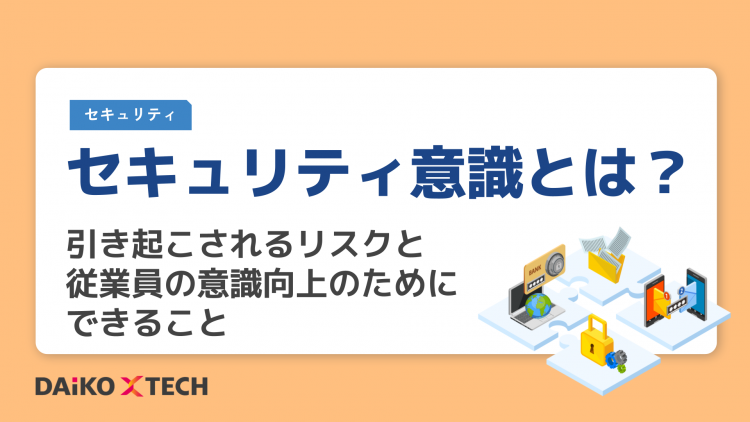
セキュリティ意識とは、企業の機密情報や個人情報といった重要な情報資産をサイバー攻撃や内部の過失など、さまざまな脅威から守るために、従業員一人一人が持つべき知識や行動、責任感のことです。
セキュリティ意識が低い状態は、企業にとって重大なリスクとなります。実際、2023年に国内で発生した個人情報漏えい事案の約86%が、誤送信や紛失などのヒューマンエラーであったことが報告されています。
どれほど強固なセキュリティシステムを導入していても、従業員一人の「うっかりミス」が、企業の競争力を根底から覆し、サプライチェーン全体に多大な迷惑をかける事態に発展しかねません。
そこで本記事では、現場で働く従業員一人一人に求められるセキュリティ意識の重要性を再確認し、組織全体のセキュリティレベルを底上げするための具体的な方法について解説していきます。
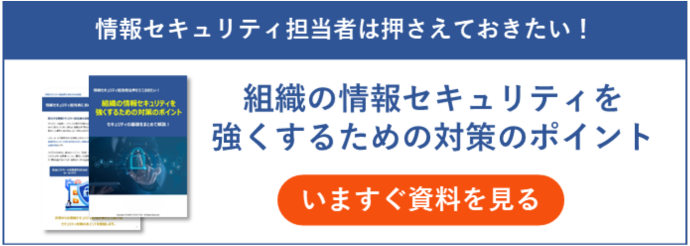
目次
セキュリティ意識とは

セキュリティ意識とは、自分や会社の情報が盗まれたり悪用されたりしないよう、日常的に注意を払う心構えのことです。
これは、単に社内ルールを守ることだけを指すのではありません。
企業の機密情報や生産システムといった重要な情報資産を、さまざまな脅威から守るために、従業員一人ひとりが持つべき知識や判断力、責任感のことを指します。
特に製造業では、工場のスマート化(DX)に伴い、これまで外部と接続されていなかった生産制御システム(OT)が社内ネットワークやインターネットに接続される機会が増えています。
この変化は、生産性向上に貢献する一方で、サイバー攻撃の標的となるリスクを飛躍的に高める要因になりました。
そのため、近年では、従業員一人ひとりが「自分ごと」としてセキュリティリスクを捉え、日々の業務に潜む危険を予見し、適切に行動する「セキュリティ意識」が求められています。
従業員のセキュリティ意識が低いことによって引き起こされるリスク

従業員のセキュリティ意識の低さは、企業の存続に関わる深刻な問題に発展します。
最新のセキュリティシステムを導入していても、人的な脆弱性がサイバー攻撃の突破口となるケースは少なくありません。
特に製造業においては、生産ラインの停止や事業継続を脅かす事態に発展する可能性があります。
以下では、従業員のセキュリティ意識が低いことによって生じるリスクについて詳しく解説します。
機密情報の漏えい
従業員のセキュリティ意識の欠如は、企業の競争力の源泉である機密情報の漏えいに直結します。
特に製造業においては、独自の技術情報、製品の設計図、原価情報、顧客リストといった情報がサイバー攻撃の格好の標的です。
2023年に個人情報漏えい事故を公表した上場企業のうち、最も多かった業種は製造業でした。
漏えいの原因の多くは、悪意のあるメールの添付ファイルを不用意に開くことや、社内で許可されていないクラウドサービスを利用するなど、日常業務の中での些細な行動にあります。
退職者による情報の持ち出しといった内部不正のリスクも無視できません。
これらの情報が競合他社や国外に流出した場合、企業の優位性を根底から覆す深刻な事態を招きます。
マルウェア感染
特に近年猛威を振るうマルウェアへの感染は、従業員のセキュリティ意識の低さが引き起こす典型的なリスクです。
マルウェア感染とは、コンピューターやスマートフォンなどのデバイスが、悪意のあるソフトウェアやプログラムに侵入されることです。
業務を装ったメールのリンクをクリックする、提供元不明のソフトウェアをインストールするなど、従業員の不用意な行動がマルウェアの侵入経路となります。
製造業においてマルウェア感染が深刻なのは、生産ラインを制御するOT(Operational Technology)システムにまで影響が及ぶ可能性がある点です。
万が一、OTシステムが停止すれば、工場の稼働が全面的にストップし、生産計画に甚大な遅延が生じます。
復旧には多大な時間とコストを要するだけでなく、サプライチェーン全体に迷惑をかける事態に発展しかねません。
社会的信頼の低下
情報漏えいや生産停止といった事実は、プレスリリースや報道を通じて瞬く間に社会へ知れ渡り、企業のブランドイメージを著しく損ないます。
顧客からの信認を失うだけでなく、株価の下落や取引先からの契約見直しといった事態にもなりかねません。
自社がサイバー攻撃の起点となり、取引先にまで被害を広げてしまった場合、サプライチェーン全体を揺るがす問題へと発展します。
一度失った信頼を取り戻すことは極めて困難であり、企業存続の危機に直結するリスクです。
金銭的被害の発生
セキュリティインシデントの発生は、直接的および間接的に、甚大な金銭的被害を企業にもたらします。
その被害は単なるシステムの復旧費用にとどまらず、企業の経営基盤を揺るがすリスクとなります。
具体的に想定される金銭的被害は、以下の通りです。
|
被害の種類 |
具体的な内容 |
|
直接的損害 |
・原因調査やシステム復旧にかかる費用 ・顧客や取引先への損害賠償金・見舞金 ・弁護士費用などの法的対応コスト ・コールセンター設置などの顧客対応費用 |
|
間接的損害 |
・生産ライン停止や事業中断に伴う逸失利益 ・社会的信頼の低下による顧客離れ・受注機会の損失 ・ブランドイメージの毀損と株価の下落 ・再発防止策を講じるための新たな設備投資 |
これらの被害総額は、インシデントの規模によっては数億円を超えることもあり、決して珍しいことではありません。
セキュリティ対策は単なるコストではなく、未来の損失を防ぐための重要な経営投資と捉えることが重要です。
従業員のセキュリティ意識を向上するには

従業員のセキュリティ意識を高めるためには、単なる知識の習得だけでなく、実践的な教育や組織全体での取り組みが不可欠です。
次に、効果的な意識向上のための具体策について解説します。
従業員にセキュリティ教育を行う
セキュリティ意識の向上には、定期的かつ実践的な教育の実施が欠かせません。
一度きりの研修では知識が定着しにくいため、eラーニングや集合研修などを組み合わせ、継続的に学ぶ機会を提供することが重要です。
特に効果的なのが、疑似的な体験を通じて脅威への対応力を養う訓練です。
例えば、実際の攻撃メールを模した「標的型メール訓練」サービスなどを利用すれば、従業員は安全な環境で不審なメールを見抜く力や誤って開封してしまった際の報告手順を実践的に学べます。
教育内容も、一般的なIT知識だけでなく、「工場の生産システムが停止するリスク」や「サプライヤーを装った攻撃メール」といった製造業特有のシナリオを取り入れましょう。
従業員がリスクを「自分ごと」として捉えやすくなり、教育効果が飛躍的に高まります。
情報セキュリティポリシーを策定する
従業員が遵守すべき行動の拠り所として、明確な情報セキュリティポリシー(統一ルール)の策定が求められます。
ポリシーは、組織の情報資産を守るための羅針盤であり、従業員一人ひとりがセキュリティに関する判断に迷った際の指針となります。
ポリシーには、以下のような具体的なルールを明記することが重要です。
|
対象項目 |
ルールの具体例 |
|
パスワード管理 |
・推測されにくい複雑な文字列の設定 ・定期的な変更の義務付け ・複数サービスでの使い回しの禁止 |
|
情報機器の利用 |
・私物PCやスマートフォンの業務利用に関する規定 ・USBメモリなど外部記憶媒体の取り扱い手順 |
|
ネットワーク接続 |
・無許可のフリーWi-Fiへの接続禁止 ・OT環境とIT環境のネットワーク分離に関するルール |
策定したポリシーは、ただ配布するだけでなく、研修などを通じてその背景や目的を丁寧に説明し、全従業員に内容を深く理解してもらうことが重要です。
セキュリティ文化を構築する
ルールや教育だけでは、セキュリティ対策は形骸化してしまいます。
真に強固な組織を築くためには、従業員が自発的に行動する「セキュリティ文化」を醸成することが重要です。
この文化を根付かせる第一歩は、経営層がセキュリティの重要性を明確に発信し続けることです。
経営トップが「セキュリティは事業継続に不可欠な経営課題である」という姿勢を示すことで、従業員の意識は大きく変わります。
このような地道な活動を通じて、セキュリティが「やらされる仕事」ではなく、「全員で取り組むべき大切なこと」という共通認識が組織に浸透していきます。
社内の情報管理の徹底をする
日々の業務における基本的な情報管理の徹底は、セキュリティインシデントを防ぐための土台となります。
特に重要なのが、「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」体制の確立です。
「不審なメールを受信した」「PCの動作がおかしい」といった些細な異変であっても、従業員が躊躇なく速やかに担当部署へ報告できる環境が、被害の拡大を防ぐ鍵となります。
そのためには、相談窓口を明確にし、「報告することが評価される」というポジティブな雰囲気作りが欠かせません。
従業員が躊躇なく相談できる環境を整備することで、早期発見と迅速な対応が可能になります。
セキュリティ対策ツールを活用する
従業員の意識向上やルール徹底だけでは、巧妙化・高度化する全てのサイバー攻撃を防ぎきることは困難です。
そこで、人的な対策を補完し、防御力をさらに高めるために、セキュリティ対策ツールの活用が不可欠となります。
導入すべきツールは、従来のウイルス対策ソフトやファイアウォールに限りません。現代の脅威に対応するためには、以下のような、より高度な仕組みが必要です。
|
ツールの種類 |
主な機能と効果 |
|
EDR (Endpoint Detection and Response) |
PCやサーバーなどの端末(エンドポイント)の操作を常時監視し、不審な挙動を検知・分析。マルウェア感染後の迅速な対応を可能にする。 |
|
資産管理ツール |
社内で使用されているPC、ソフトウェア、ライセンスなどを一元管理。許可されていないソフトの利用や、パッチが未適用の脆弱な端末を可視化する。 |
|
OTセキュリティソリューション |
製造業特有の生産制御システム(OT)のネットワークを監視し、工場をサイバー攻撃から保護する専門ツール。 |
これらのツールは、24時間365日システムを監視し、人間の目では見逃してしまうような脅威の兆候を捉えることができます。
教育という「人」の対策と、ツールという「技術」の対策を両輪で進めることで、多層的な防御体制を構築し、企業のリスクを最小限に抑えることが可能です。
セキュリティ意識を向上するメリット

セキュリティ意識の向上は、単なるコストや負担として捉えるべきではありません。
むしろ、企業の競争力と持続的成長を支えるための戦略的な投資です。
従業員がセキュリティに対する当事者意識を持つことで、組織全体の防御力は飛躍的に高まります。
以降では、セキュリティ意識を向上するメリットについて詳しく解説します。
セキュリティリスクが軽減する
従業員一人一人のセキュリティ意識の向上は、サイバー攻撃による被害や内部不正といったインシデントの発生確率を直接的に引き下げる効果があります。
これは、組織における最も基本的な、そして効果的な防御策の一つです。
従業員が脅威を正しく認識することで、以下のような危険な行動を自律的に回避できるようになります。
- 取引先や公的機関を装った巧妙な標的型メールの添付ファイルを安易に開かない
- 業務に関係のないWebサイトを閲覧したり、提供元不明のソフトウェアをインストールしたりしない
- 工場の制御用PCなど、重要な端末に許可なくUSBメモリを接続しない
このような個々の行動変容の積み重ねが、ランサムウェア感染による生産停止や企業の生命線である設計図・顧客情報の漏えいといった、事業継続を揺るがす致命的なリスクを未然に防ぐことに直結します。
社内のセキュリティ体制が強固になる
従業員のセキュリティ意識の向上は、個人のリスク回避能力を高めるだけでなく、組織全体のセキュリティ体制そのものをより強固なものへと進化させます。
セキュリティが一部の専門部署だけの課題ではなく、全従業員が当事者として関わる「組織文化」として根付くためです。
これにより、技術的な対策だけではカバーしきれない領域を補い、多層的な防御網を構築できます。具体的には、以下のような好循環が生まれます。
|
体制強化のポイント |
具体的な効果 |
|
脅威の早期発見 |
従業員がPCの不審な動作や怪しいメールといった脅威の兆候に気づきやすくなり、速やかに担当部署へ報告する文化が醸成される。 |
|
迅速な初動対応 |
この「早期報告」が、インシデント発生時の被害拡大を防ぐための初動対応を迅速化し、事業への影響を最小限に抑えることに繋がる。 |
|
対策の実効性向上 |
現場レベルで重要性が理解されることで、資産管理や脆弱性対策といった全社的な取り組みへの協力が得られやすくなり、対策が形骸化しなくなる。 |
このように、従業員の意識という土台が盤石になることで、技術的なセキュリティ対策がより効果的に機能します。
なぜセキュリティ対策を強化してもウイルスに感染してしまうのか

前述のような対策を実施しても、ウイルス感染のリスクを完全になくすことはできません。その理由の一つが、ヒューマンエラーを原因としたインシデントを完全に防ぐのが難しいためです。
例え、従業員側に悪意がなくても、不注意でセキュリティリスクに直面することがあります。
また、「セキュリティ対策ソフトを入れているから大丈夫」と油断し、悪意のあるプログラムを知らずにダウンロードしてしまうことも考えられます。
サイバー攻撃やマルウェアは年々多様化しており、未知のウイルスに遭遇した場合、従来型のセキュリティソフトではすり抜けが発生しかねません。
そうした場合、完全に感染を防ぐことは極めて困難でしょう。
そこで検討したいのが、万が一、マルウェアが従業員のPCなどに侵入した場合の対応策です。
すり抜けられてしまったら?OSプロテクト型セキュリティ「AppGuard」

従来型のアンチウイルスソフトは、過去の情報に基づいたファイルや動作パターンのマッチングによって脅威を検知しています。
しかし、この方法では、新種のマルウェアなど未知の脅威を防ぐことができません。
そこで注目されているのが、「マルウェアを探し出して駆除」するのではなく、「OSの正常な動作を守ることによって感染を防ぐ」という、新しい概念のマルウェア対策製品です。DAIKO XTECHが提供するOSプロテクト型セキュリティ製品「AppGuard®」は、従来型のアンチウイルスソフトとは異なる新しい発想に基づいた仕組みです。
このソフトウェアでは、OSに対する不正なプロセスを監視・遮断して、正常なプロセスのみを許可することでOSの中枢部(OSレジストリ、システムスペース、メモリなど)を悪意ある行為から守ることを目的としています。
昨今は、次世代型アンチウイルス製品(NGAV)やEDR製品も普及していますが、それぞれにはカバーできない範囲も存在しており、マルウェアの「初期進入」の後の対策が不足していました。
そこで、防御壁をすり抜けてきた未知のマルウェアへの対策として、「マルウェア感染」 を防御するAppGuard®が確かな力を発揮するわけです。
内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)ガイドラインに準拠し、20年間突破されていない信頼性を誇る「AppGuard®」。テレワークが広まりを見せる環境下でも組織の情報セキュリティを維持・向上させたいとお考えの企業様は、お気軽にお問い合せください。
従業員のセキュリティ意識を向上して企業の情報資産を守ろう

従業員全員が高いセキュリティ意識を持つことは、企業の情報資産を守るための最も重要な基盤です。
近年、人的ミスや油断が大きな損失や信頼低下につながります。日常業務の中で「自分ごと」としてリスクを捉え、適切な行動を積み重ねることが不可欠です。
定期的な教育や明確なルールの策定、組織全体での情報共有と相談体制の構築、そして最新のセキュリティ対策ツールの活用を通じて、多層的な防御体制を築きましょう。
組織の防御力を高め、事業の安定と成長を実現するためにも、今こそ自社のセキュリティ対策を見直してみませんか。
「組織の情報セキュリティを強くするための対策のポイント」こちらのホワイトペーパーでは、担当者が押さえておきたいセキュリティ対策の基礎から最新の対策までをわかりやすく解説しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。

- この記事を監修した人
- 16年間、SIerやソフト開発会社でITソリューション営業として従事。
セキュリティおいては、主にエンドポイント、無害化、認証製品の経験を積み
DAIKO XTECHに入社後は、さらに専門性を高め、セキュリティにおける幅広いニーズに答えていくための提案活動や企画プロモーションを展開。
お客さまと一緒に悩み、一緒に課題解決が出来る活動を心掛けている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
ICTソリューション推進部
セキュリティビジネス課 - 中須 寛人