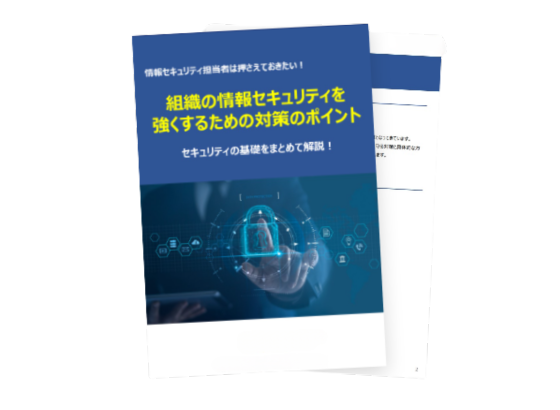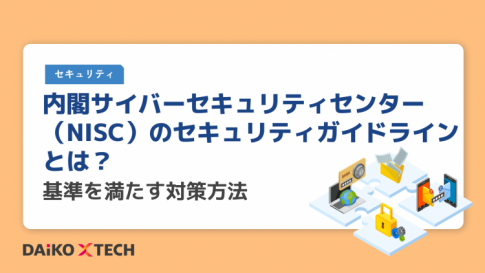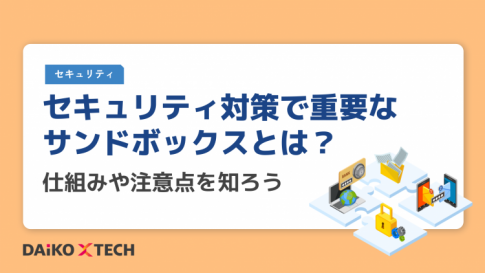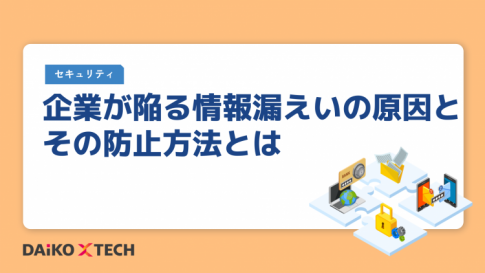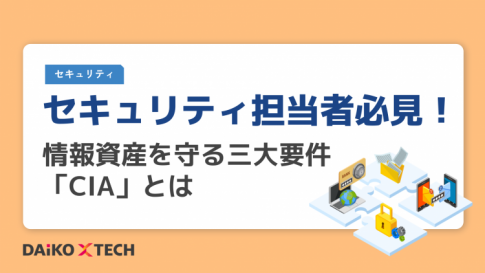特権ID管理とは、システム管理者や機密データへアクセスできる「特権ID」を厳格に管理し、不正利用や情報漏えいリスクを抑えるための重要な取り組みです。
昨今、DX(デジタルトランスフォーメーション)やスマートファクトリー化が進む製造業では、ITネットワークとOT(生産制御システム)との連携が進むとともにサイバー攻撃のリスクも深刻化しています。
特権IDの管理不備は、生産停止・情報漏えい・信用失墜など大きな被害につながるため、早急な対策が必須です。
本記事では、特権ID管理の基本から、管理不備がもたらす具体的なリスク、そして遵守すべきガイドラインまでをわかりやすく解説します。
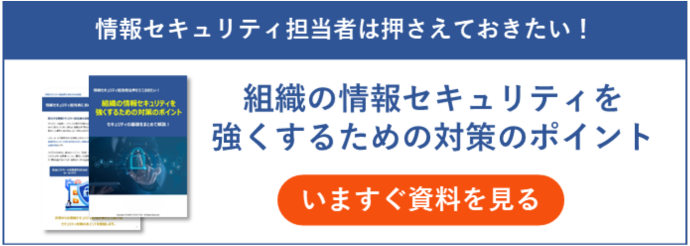
目次
特権ID管理とは?

特権ID管理とは、企業の情報システムにおいて強力な権限を持つ「特権ID」を、厳格なルールと仕組みに基づいて統制・監視する重要な取り組みです。
この特権IDが不正に使用された場合、基幹システムの停止、機密情報の漏えい、データの改ざんといった、事業の根幹を揺るがす深刻なインシデントに直結するからです。
例えば、製造業における生産管理システムや品質管理システム、あるいは設計図などの知的財産を保管するサーバーへのアクセス権は、まさに特権IDに該当します。
これらのIDの管理がずさんな状態では、悪意のある攻撃者にとって格好の侵入経路となり、企業の競争力を根底から覆されるリスクを常に抱えることになります。
したがって、企業の重要な情報資産を保護し、事業継続性を確保する上で、特権ID管理は単なる情報システム部門の課題ではなく、経営レベルで取り組むべき極めて重要なセキュリティ対策です。
特権IDと一般ID(管理者ID)の違い
特権IDと一般IDの最も大きな違いは、その「権限の範囲」と「システム全体に与える影響の大きさ」にあります。
業務を遂行するために必要な最小限の権限が与えられる一般IDに対し、特権IDはシステムの設定変更や全データの閲覧・削除など、ほぼすべての操作が可能です。
以下の表で、それぞれのIDの特性を比較してみましょう。
|
項目 |
一般ID(利用者ID) |
管理者ID |
特権ID(スーパーユーザー) |
|
主な利用者 |
一般従業員 |
各部署のシステム担当者、情報システム部門員 |
システム開発者、保守委託先、ごく一部のシステム管理者 |
|
主な利用目的 |
日常業務の遂行(データ入力、閲覧など) |
特定システムのユーザー管理、アプリケーションの運用 |
システムの根幹に関わる設定変更、メンテナンス、障害対応 |
|
権限の範囲 |
担当業務に必要な範囲に限定される |
担当する特定のシステムやアプリケーションの管理権限 |
OS、データベース、ネットワーク機器など、ほぼすべての操作が可能 |
|
リスクの大きさ |
小〜中。影響範囲は限定的。 |
中〜大。担当システム内での影響が大きい。 |
極めて大きい。システム全体の停止や情報漏えいに直結する。 |
|
管理のポイント |
定期的な棚卸し、不要IDの削除 |
職務分掌に基づき、必要最小限の権限を付与 |
利用の厳格な申請・承認、パスワードの秘匿化、全操作の記録 |
この区別が不明確な企業では、必要以上の権限を持つアカウントが乱立し、セキュリティリスクの温床となる危険性があります。
特権ID管理システムとは
特権IDの厳格な管理を実現する上で中核となるのが、「特権ID管理システム」です。
特権IDの利用申請から承認、貸し出し、利用後の返却、そして操作内容の記録といった一連の管理プロセスを自動化するシステムです。
従来、Excel台帳や紙の申請書を用いて手作業で行われていた管理では、承認プロセスの形骸化、パスワードの使い回し、退職者IDの放置、そして「誰が、いつ、何をしたか」という操作証跡の追跡が困難である、といった課題がありました。
特権ID管理システムは、こうした属人的な管理手法から脱却し、組織として統制の取れたセキュリティポリシーを一貫して適用するための強力な基盤となります。
特権ID管理システムの機能
専門的なソリューションである特権ID管理システムは、多岐にわたる機能を組み合わせることで、堅牢な管理体制を構築します。
これらの機能は、不正利用を未然に防ぐ「予防的統制」と、インシデント発生時に迅速な対応を可能にする「発見的統制」の両面からアプローチします。
システムが提供する代表的な機能には、以下のようなものがあります。
|
機能カテゴリ |
主要機能 |
製造業での効果 |
|
認証・認可 |
多要素認証、ワンタイムパスワード |
工場システムへの不正侵入防止 |
|
セッション管理 |
セッション録画、リアルタイム監視 |
作業内容の完全な証跡確保 |
|
パスワード管理 |
自動生成、定期ローテーション |
管理負荷軽減と強固なセキュリティ |
|
ワークフロー |
申請承認、利用時間制限 |
適切な権限統制と内部統制強化 |
|
レポート機能 |
利用状況分析、コンプライアンス報告 |
監査対応の効率化 |
なぜ今、製造業で特権ID管理の重要性が増しているのか?

現代の製造業界では、特権ID管理の重要性が従来とは比較にならないレベルまで高まっています。
この背景には、製造現場を取り巻く以下のような環境の劇的な変化があります。
サイバー攻撃の急増と巨大化
近年、製造業を標的とするサイバー攻撃、特に身代金を要求するランサムウェアが急増・巧妙化しています。
工場では、ITネットワークとOT(生産制御システム)との連携により攻撃の脅威に直接晒されるようになりました。
攻撃者は脆弱性を突き、システム全体を掌握できる特権IDの窃取を狙います。万が一、この特権IDを奪われると生産ラインが停止し、甚大な被害は避けられません。
このような脅威には「侵入されること」を前提とした「ゼロトラスト」の考え方が不可欠です。その中核として、万が一の侵入時にも被害を最小限に抑えるための特権ID管理の徹底が、今まさに求められています。
AI、IoT、クラウドなどの新技術導入の拡大
製造業では、生産性向上のためAIやIoT、クラウドの導入が加速しています。
しかし、このDXの進展は、システム連携の複雑化や外部接続点の増加を招き、サイバー攻撃の対象領域を格段に拡大させるという新たなセキュリティリスクを生んでいます。
特に、IoTセンサーやクラウドアプリケーションなど、管理すべき特権IDは爆発的に増加しており、手作業での管理はもはや不可能です。管理漏れが一つでもあれば、そこが侵入経路となりシステム全体を危険に晒します。
この課題を解決するには、さまざまな環境に散在する全ての特権IDを一元的に可視化し、統一されたポリシーで管理する仕組みが不可欠です。
スマートファクトリーの恩恵を安全に享受するため、この基盤となるセキュリティ体制の見直しが重要視されています。
内部統制・法令対応、業界ガイドラインの要請
特権ID管理の強化は、サイバー攻撃対策という側面だけでなく、企業の社会的責任を果たす上でも重要です。
なぜなら、上場企業に義務付けられているJ-SOX法(内部統制報告制度)への対応や、経済産業省などが公表するセキュリティガイドラインの遵守において、特権IDの厳格な管理が明確に求められているからです。
具体的には、以下の点が挙げられます。
|
概要と特権ID管理との関連 |
|
|
J-SOX法(内部統制報告制度) |
財務報告の信頼性を確保するための体制構築を求める法律です。監査では、財務諸表を作成するITシステムへのアクセス管理が厳しくチェックされます。特に、システム改ざんなどが可能な特権IDの管理不備は、「IT全般統制(ITGC)の不備」として指摘される最たるものです。監査法人に対して、特権IDの利用申請・承認記録や操作ログを明確に提示できなければなりません。 |
|
セキュリティガイドライン |
経済産業省とIPAが発行する「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」では、経営者が認識すべき重要項目の一つとして、アクセス管理の強化が挙げられています。これは、サプライヤー選定の基準としても参照されることが増えており、対策の有無がビジネスチャンスにも影響します。 |
|
サプライチェーンからの要請 |
大手の自動車メーカーや電機メーカーなどは、取引先であるサプライヤーに対しても、自社と同等のセキュリティレベルを求める傾向が強まっています。ISMS(ISO27001)などの認証取得を条件とするケースもあり、その中で特権ID管理は重要な審査項目となります。 |
このように、特権ID管理は、もはや自主的な取り組みではなく、法令や社会からの要請に応えるための必須事項です。
管理体制の不備は、監査での指摘や取引機会の損失に直結する経営リスクであると認識する必要があります。
特権IDの管理不備が招く、製造業特有の4大リスク

製造業において特権IDの管理が不適切な状態で放置されると、他業界では発生しない深刻なリスクが顕在化します。
工場長や経営陣が認識すべき、製造業特有のリスクを詳しく解説します。
リスク1:生産ラインの停止 – ランサムウェア攻撃による事業中断
製造業にとって、生産ラインの停止は事業継続を脅かす大きなリスクです。ランサムウェア攻撃は、この最悪のシナリオを現実のものとします。
攻撃者は、窃取した特権IDを使い、工場の生産を管理するMES(製造実行システム)や、生産設備を制御するシステムに侵入し、データを次々と暗号化していきます。
この攻撃を受けると、生産計画の実行、工程の進捗管理、品質データの収集といった、生産に不可欠な機能がすべて停止します。
その結果、物理的な生産ラインも稼働不能に陥り、操業再開の目途が立たないまま、甚大な被害が発生します。
特権IDの厳格な管理は、この壊滅的なリスクから事業を守るための重要な取り組みです。
リスク2:技術・機密情報の漏えい – サプライチェーン全体への影響
製造業の競争力の源泉は、長年培ってきた独自の技術情報や設計データ、製造ノウハウにあります。
これらの知的財産が保管されているサーバーへのアクセス権を持つ特権IDは、まさに「宝の蔵」の鍵です。この鍵が外部の攻撃者や内部の不正者の手に渡れば、企業の生命線ともいえる機密情報が根こそぎ盗み出される危険性があります。
特に、サプライチェーンの一員として他社から機密情報を預かっている場合、情報漏えいは自社だけの問題ではなくなります。
取引先からの信用を完全に失い、サプライチェーン全体から排除されるなどになりかねません。
特権IDの不正利用を防止・監視する体制の構築は、自社の技術を守り、ビジネスパートナーとの信頼関係を維持するための必須条件です。
リスク3:内部不正 – 退職者や委託先担当者による不正操作
セキュリティ上の脅威は、必ずしも外部からだけもたらされるわけではありません。
企業の内部情報に精通し、正当なアクセス権を持つ従業員や、業務委託先の担当者による「内部不正」は、発見が困難であり、深刻な被害を引き起こす可能性があります。
特に、システムに対してあらゆる操作が可能な特権IDの不正利用は、致命的な結果を招きます。
こうした内部不正のリスクを防ぐには、「誰が、いつ、どのIDを使って、何をしたのか」を正確に追跡できる仕組みが不可欠です。
特権ID管理システムを導入し、IDの貸し出しを個人に紐づけ、すべての操作を記録することで、不正行為に対する強力な抑止力となります。
リスク4:監査指摘と信用の失墜 – J-SOX法などへの抵触
特権ID管理の不備は、サイバー攻撃のような直接的な被害だけでなく、企業の社会的信用を大きく損なう「監査リスク」にも直結します。
特に、株式を上場している企業は、J-SOX法に基づく内部統制監査において、特権IDの管理状況を厳しく評価されます。
監査では、「誰が重要なシステムへの特権アクセス権を持つか」「その承認プロセスは適切か」「特権IDによる操作が記録・レビューされているか」について、客観的な証拠の提示が求められます。
Excel台帳のような手作業での管理では、これらの要求に十分応えることは困難です。
管理体制の不備が「開示すべき重要な不備」として指摘されると、投資家や取引先からの信用を失い、株価の下落やブランドイメージの低下に繋がりかねません。
そのため、特権ID管理の徹底は、監査に耐えうる強固なガバナンス体制を築き、ステークホルダーからの信頼を維持するため重要です。
【特権ID管理ガイドライン】管理職として押さえるべきポイント

製造業の管理職が特権ID管理を効果的に推進するためには、各種ガイドラインが示す要件を正確に理解し、自社の事業特性に適合した実装戦略を策定する必要があります。
ここでは、特権IDガイドラインに記載されているポイントについて解説します。
IPAや経産省が示すセキュリティガイドラインの要点
企業のセキュリティ対策を進める上で羅針盤となるのが、IPAや経済産業省が公開している各種ガイドラインです。
これらは、現代のサイバー脅威を想定した上で、経営者がリーダーシップを発揮して取り組むべき対策を体系的に示しています。
特権ID管理に関連する要点は、特に厳格な対応が求められる項目です。
代表的なガイドラインにおける、特権ID管理に関する要求事項のポイントは以下の通りです。
|
ガイドライン名 |
特権ID管理に関連する主な要点 |
|
(経済産業省・IPA) |
重要業務の継続に影響するリスクの認識と対策: ・生産ラインの制御システムなど、事業継続に不可欠なシステムを守るためのアクセス管理強化を指示。 ・特権IDの不正利用が事業停止に直結するリスクとして明記。 |
|
(経済産業省) |
アクセス制御方針の確立: ・「誰に」「どの情報資産への」「どのような権限を」与えるかを明確に定義。 ・特権IDについては、職務分掌の原則に基づき、必要最小限の権限とすることを要求。 |
|
(IPA) |
重要な処理における管理機能の堅牢化: ・管理者ページのアクセス制限強化(IPアドレス制限、二要素認証など)。 ・強力な権限を持つIDのパスワード管理徹底(複雑性、定期変更)。 |
これらのガイドラインが共通して示唆しているのは、「特権IDは特別なリスク源である」という認識に基づき、一般ユーザーとは明確に区別した管理体制を構築する必要性です。
ガイドラインへの準拠は、企業のセキュリティ態勢の成熟度を示す客観的な指標となります。
J-SOX法(内部統制報告制度)で求められる特権ID管理とは?
上場企業にとって、J-SOX法への対応は法的な義務です。
この制度において、特権IDの管理は、財務報告の信頼性を保証する「IT全般統制(ITGC)」の根幹をなす要素として、極めて厳しく評価されます。
特権IDがあれば財務データを改ざんできてしまうため、その管理不備は内部統制の致命的な欠陥と見なされるからです。
監査では、口頭での説明やExcelの管理台帳だけでは不十分で、「誰が、いつ、なぜ特権IDを必要とし、誰が承認し、何を行ったか」という一連のプロセスを、客観的な証跡(ログ)をもって証明することが求められます。
具体的に、監査対応で必要となる特権ID管理のポイントは以下の通りです。
- IDと利用者の紐付け:共有IDではなく、利用者を特定できる仕組みを構築する。
- 申請・承認プロセスの記録:特権IDの利用申請書や、承認者の記録が、追跡可能な形で保管されていること。
- パスワードの厳格な管理:パスワードの定期的な強制変更や、利用者にパスワードを知らせない仕組みが導入されていること。
- アクセスと操作の完全な記録:特権IDによるログイン記録だけでなく、実行されたコマンドや操作内容がすべて記録されていること。
- 定期的なモニタリングとレビュー:記録された操作ログが、第三者(例:監査部)によって定期的にレビューされ、不正がないかチェックされていること。
これらの要件を満たすためには、手作業による管理には限界があり、特権ID管理システムのような仕組みによる統制が、事実上欠かせません。
参考:金融庁『内部統制報告制度に関する事例集』
特権ID管理システム導入のメリット

特権ID管理システムの導入は、単なるセキュリティ対策に留まらず、組織の管理体制そのものを高度化させる戦略的な一手です。
属人的で不透明になりがちな運用をシステムによって自動化・可視化することで、業務プロセス全体の質が向上します。
ここでは、特権ID管理システム導入がもたらす4つの具体的なメリットを解説します。
セキュリティリスクの大幅な軽減
特権ID管理システム導入の最大のメリットは、深刻なセキュリティリスクを仕組みによって大幅に軽減できる点です。
このシステムは、不正アクセスや内部不正に対する多層的な防御壁として機能します。具体的には、以下の効果が期待できます。
- 不正アクセスリスクの低減:利用申請・承認ワークフローとパスワードの自動管理により、不正利用や情報漏えいのリスクを根本から断ちます。
- 内部不正リスクの低減:「誰が何をしたか」が全て記録・可視化されるため、不正行為への強力な抑止力となります。
- 操作ミスによる障害リスクの低減:実行できるコマンドを制限することで、ヒューマンエラーによる重大なインシデントを未然に防ぎます。
このように、人の注意力に依存する性善説の管理から、システムによる厳格な統制(性悪説に基づく管理)へ移行することで、企業の重要資産を堅牢に保護できます。
異常監視や事後監査・調査が容易
特権ID管理システムの導入は、インシデント発生時の迅速な対応と、監査における証明責任の円滑な遂行を可能にします。
システムが特権IDによる「誰が、いつ、何をしたか」という操作内容をすべて客観的な証跡として自動記録するため、問題発生後の原因究明や影響範囲の特定が、迅速かつ正確に行えるからです。
従来の手作業による管理では、障害発生時に原因の特定が遅れ、被害が拡大するケースがありました。
また、監査の際には、紙の申請書やExcelの台帳をかき集め、証跡を準備するために多大な工数を要していました。
特権ID管理システムは、こうした課題を抜本的に解決します。
法令・コンプライアンス対応の実現
特権ID管理システムの導入は、J-SOX法や各種セキュリティガイドラインといった、企業に課せられた法令・コンプライアンス要件へ対応するための、現実的かつ効果的な手段です。これらの規制が共通して求める「厳格なアクセス管理と操作の記録」という要求を、システム機能によって満たすことができます。
例えば、特権IDの利用申請・承認のワークフロー記録や、IDごとのアクセスログ、パスワードの変更履歴といった証跡を、いつでも正確に提示できます。
手作業でこれらの証跡を漏れなく管理し、その正当性を証明することは、非常に困難であり、管理不備として指摘されるリスクが常に伴います。
特権ID管理システムは、コンプライアンス遵守に必要な統制レベルを仕組みとして担保し、監査指摘のリスクを低減させ、企業の社会的信用を維持するため重要な役割を担います。
管理効率の向上
特権IDの管理を手作業で行うことは、情報システム部門にとって大きな負担です。
紙の申請書でのやり取り、Excel台帳への手入力、サーバーごとの手動でのパスワード変更といった煩雑な業務は、多くの時間と労力を費やすだけでなく、人的ミスを誘発する温床にもなっています。
その結果、本来注力すべき戦略的なIT業務が後回しになってしまうという課題を抱える企業は少なくありません。
この根深い問題を解決するのが、特権ID管理システムによるプロセスの自動化です。
特権ID管理システムの選定ポイントと導入時の注意点

特権ID管理システムの導入メリットは明確ですが、その効果を最大限に引き出すためには、自社の環境や目的に合致した製品を選定し、適切に導入・運用することが不可欠です。
ここでは、システム選定で失敗しないための重要なポイントと、導入と並行して進めるべき組織的な対策について解説します。
ポイント1:管理対象システムとの相性と機能要件の確認
特権ID管理システムの選定における最初のステップは、自社のIT環境を正確に把握し、「何を」「どこまで」管理したいのかという要件を明確にすることです。
製品によって対応できるOSやデータベース、クラウドサービス、ネットワーク機器が異なるためです。
特に製造業の工場では、独自の制御システムや古いOSが稼働している場合もあり、これらに対応できるかは重要な確認事項となります。また、必要な機能が備わっているかの確認も欠かせません。
自社のセキュリティポリシーや運用ルールに照らし合わせ、必須機能と推奨機能を整理し、評価のチェックリストを作成することをお勧めします。
ポイント2:導入形態と運用負荷の見極め
次に検討すべきは、システムの「導入形態」と、導入後に発生する「運用負荷」です。特権ID管理システムは、以下のように大きく分けて2つの導入形態があります。
|
導入形態 |
特徴 |
メリット |
デメリット |
|
ゲートウェイ型 |
利用者と管理対象サーバーの間に中継サーバー(ゲートウェイ)を設置。 |
管理対象サーバーにエージェント(専用ソフト)を導入する必要がなく、既存環境への影響が少ない。導入が比較的容易。 |
エージェント型に比べて、取得できるログの詳細度や制御の粒度が制限される場合がある。 |
|
エージェント型 |
管理対象の全てのサーバーにエージェントを導入。 |
OSレベルで詳細な操作ログの取得や、きめ細かなコマンド制御が可能。 |
全ての対象サーバーへのエージェント導入・管理に手間がかかる。OSアップデート時などの互換性確認が必要。 |
どちらの形態が最適かは、管理対象のシステムの重要度や求める統制レベル、そして情報システム部門の人的リソースによって異なります。
例えば、導入の迅速性を優先するならゲートウェイ型、基幹システムに対して最も厳格な統制を適用したいならエージェント型、という判断が考えられます。
ポイント3:システム導入と並行して進めるべき組織的対策
特権ID管理システムを導入するだけでは万全なセキュリティは実現できません。
その効果を最大限に引き出すには、システムという「仕組み」を支える組織的な「ルール」と「文化」の醸成が不可欠です。
具体的には、システム導入と並行して以下の組織的対策に取り組むことが重要です。
- 特権ID管理規定の策定・周知:利用方針や緊急時の手順、罰則などを明確に文書化し、全社で徹底する。
- 役割と責任の明確化:申請者、承認者、利用者、監査者などの役割と責任範囲を定義し、属人性を排除する。
- 従業員へのセキュリティ教育:特権ID管理の重要性やリスクについて定期的に教育し、従業員一人ひとりの意識を向上させる。
これらの組織的対策を講じることで初めて、導入したシステムが形骸化することなく、実効性のあるセキュリティ基盤として機能します。
特権ID管理運用のポイント
特権ID管理システムを導入した後は、その効果を継続的に維持し、高めていくための運用が重要です。
ここでは、特権ID管理を形骸化させず、実効性のあるものにし続けるための3つの重要な運用ポイントについて解説します。
管理手順・運用ルールの整備
特権ID管理システムを効果的に運用するための土台となるのが、具体的で実践的な「管理手順」と「運用ルール」です。
これらが明確に文書化され、関係者全員に共有されていなければ社内活用が進まず、人によって対応が異なるなど、統制の綻びが生じる原因となります。
定める運用ルールの具体的な項目には、以下のようなものがあります。
|
ルールのカテゴリ |
具体的な規定項目の例 |
|
IDのライフサイクル管理 |
・新規IDの発行、変更、削除に関する申請・承認フロー ・人事異動や退職に伴うIDの権限変更・削除プロセスの定義 |
|
利用時のルール |
・利用目的と利用期間の明確化 ・1回の申請で許可する作業範囲の定義 ・緊急時(システム障害など)における特例的な申請・承認フロー |
|
パスワードポリシー |
・パスワードの最低文字数や複雑性の要件 ・パスワードの有効期間と定期的な変更の義務付け |
|
ログ管理・監査 |
・アクセスログおよび操作ログの保管期間 ・定期的なログ監査の実施責任者と実施周期 |
これらのルールを整備し、遵守することを徹底することで、特権IDの利用に一貫した規律がもたらされ、セキュリティレベルを安定的に維持することが可能です。
適切なアクセス権限設計と定期的な見直し
特権ID管理における最も基本的な原則は、「必要最小限の権限」を付与することです。
これは、担当者が業務を遂行する上で、本当に必要な権限のみを与え、それ以上の権限は与えないという考え方です。
万が一そのIDが不正使用された場合でも、被害を最小限に食い止めることができるからです。
例えば、データベースのバックアップ担当者にはデータの参照権限のみを与え、データの書き込みや削除の権限は与えない、といった設計がこれにあたります。
しかし、一度設定した権限が永遠に最適であり続けるわけではありません。組織変更、人事異動、担当プロジェクトの終了など、ビジネスの状況は常に変化します。
そのため、アクセス権限が実態に合っているかを定期的に検証し、不要になった権限を速やかに剥奪する「見直し」のプロセスが不可欠です。年に一度、あるいは半期に一度といった周期で、全ての特権IDの棚卸しを行い、その権限の妥当性を評価する仕組みを構築することが、セキュリティホールを生み出さないために重要です。
監査体制・事後検証の仕組みの構築
特権ID管理システムのログ記録機能は、記録するだけでは不正の抑止にはなりません。そのログを「誰が、いつ、どのように」レビューするのか、という監査体制を構築して初めて価値が発揮され、不正行為に対する最後の砦となります。監査体制を構築する上でのポイントは以下の通りです。
- 独立性の確保:監査は、システム管理者とは別の独立した部署(内部監査室など)が行い、客観性を保つ。
- 監査内容の明確化:業務時間外のアクセスや禁止コマンドの実行など、重点的にチェックする監査項目を事前に定義する。
- 定期的な実施と報告:監査を月次などで定期的に行い、その結果を経営層へ報告するフローを確立する。
このようにログを「見ている」という姿勢を明確にすることが、内部不正への強力な心理的抑止力となり、組織全体のガバナンス強化に直結します。
特権ID管理で工場と事業を守ろう

ここまで見てきたように、特権ID管理は、製造業の事業継続性を左右する重要な経営課題です。
サイバー攻撃の脅威が工場内部にまで及ぶ現代において、生産ラインの停止や技術情報漏えいといった致命的なリスクから事業を守るためには、特権IDを厳格に管理していくことが重要です。
特権ID管理の強化は、組織全体のセキュリティレベルを向上させるための重要な第一歩です。
しかし、対策は多岐にわたります。情報セキュリティ担当者として押さえるべき、PCやネットワーク、社員教育に至るまでの網羅的な対策ポイントをまとめた資料「組織の情報セキュリティを強くするための対策のポイント」をご用意しました。
自社のセキュリティ体制をさらに強固なものにするため、ぜひご活用ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓