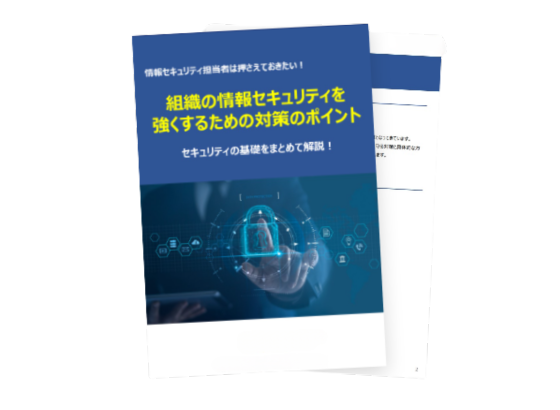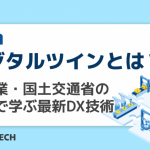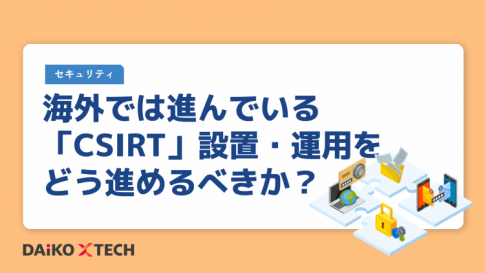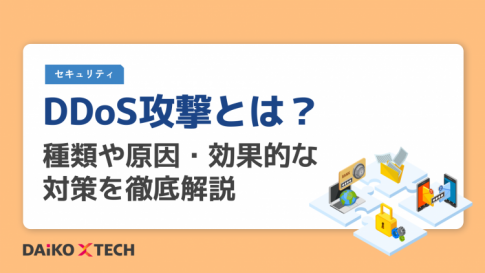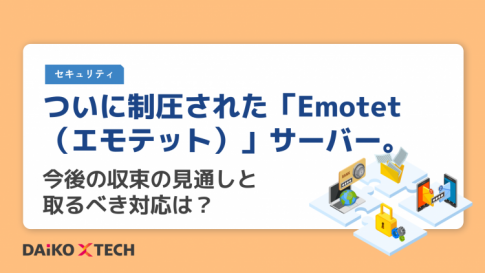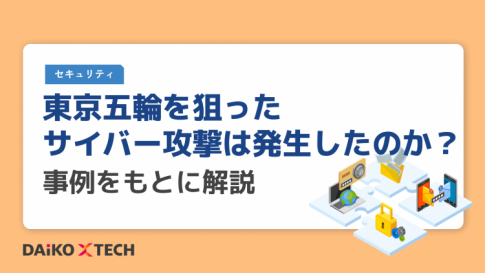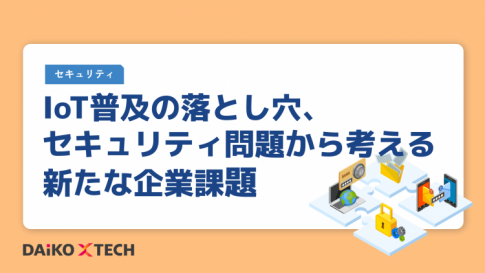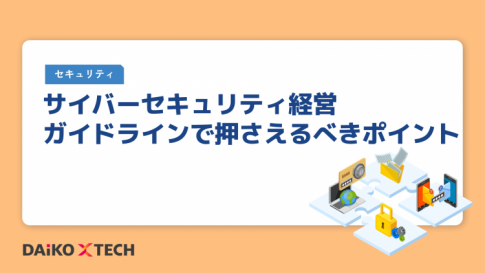昨今、シャドーITの対策に取り組む企業が増えています。
自社の機密情報を守り、セキュリティを強化するうえでシャドーITの確認や監視は欠かせません。
実際、シャドーITを見落としていたために、情報漏えいや不正アクセスによる多大な損失を被った事例もあります。
しかし、シャドーITの対策をどのように実施すれば良いかわからないと感じる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、シャドーITと呼ばれる問題について、定義・発生原因・具体的なリスクに加え、有効な対策までを網羅的に解説します。
自社のITセキュリティを強化する際の参考にしてください。
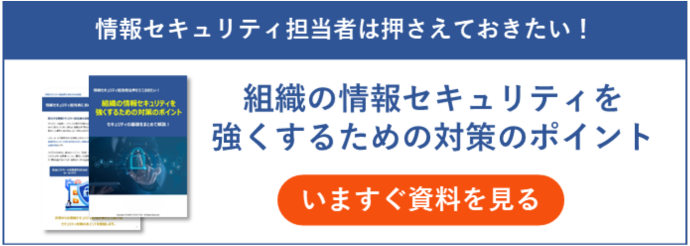
目次
シャドーITとは

まず、「シャドーIT」の基本的な意味を確認しましょう。
シャドーITの具体的な定義だけでなく、混同されがちな関連用語との違いを明確に理解することが、対策を考えるうえでの第一歩です。
シャドーITの定義
シャドーITとは、企業のIT部門が管理や承認をしていないデバイス・ソフトウェア・クラウドサービスなどを従業員が業務に利用する状態を指します。
文字通り、「影のIT」とも呼ばれており、IT部門の監視が行き届かない領域でIT利用が拡大している状況を意味します。
従業員は日々の業務効率化や課題解決のために、個人の判断でITツールを導入するケースは珍しくありません。
もちろん、その動機は必ずしも悪意によるものではありません。
例えば、使い慣れた個人のスマートフォンで業務メールをチェックしたり、プロジェクト管理のために無料のクラウドストレージを利用したりするケースが挙げられます。
しかし、シャドーITは利便性だけでなく、さまざまなリスクが生じることにも目を向けなければなりません。
シャドーITを放置することは、企業のセキュリティガバナンスを著しく損なう行為です。
利便性を追求するあまり、セキュリティリスクやコンプライアンスリスクを無視すると、企業全体の信頼を失墜させることにもつながります。
そのため、シャドーITの実態を把握し、適切な管理体制を構築することが、現代の企業にとって重要な課題です。
シャドーITに該当するものはどれか
具体的にどのようなものがシャドーITに該当するのか、代表的な例を見てみましょう。
自社の状況と照らし合わせながら確認してください。
|
カテゴリ |
具体例 |
|
個人所有デバイス |
私物のスマートフォンやノートパソコン・タブレット・USBメモリ |
|
クラウドストレージ |
Googleドライブ・Dropbox・OneDriveなどの個人アカウント |
|
コミュニケーションツール |
LINE・Chatwork・Slackなどの個人アカウント・フリーメール(GmailやYahoo!メールなど) |
|
SaaS/Webサービス |
Trello(タスク管理)・Canva(デザイン)・DeepL(翻訳)などの無断契約・利用 |
|
生成AIツール |
ChatGPT・Gemini・Claudeなどの個人アカウントでの業務利用 |
|
ネットワーク |
カフェやコワーキングスペースのフリーWi-Fi・私物のWi-Fiルーター |
上記の表でわかるように、シャドーITに該当するものはデバイスだけでなく、ソフトウェアも含まれます。
特に無料で利用できるソフトウェアは手軽に導入できるうえに、企業の管理をすり抜けやすい点に注意が必要です。
シャドーAIとの違い
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIツールの急速な普及に伴い、「シャドーAI」のような新たな問題が浮上しています。
シャドーAIとは、従業員が企業の許可なく生成AIツールを業務で利用することです。
シャドーAIはシャドーITの一種として扱われますが、より深刻なリスクを伴う可能性があります。
例えば、従業員が業務で利用する際に、お客さま情報や企業の機密情報などを生成AIツールに入力した場合、それらの情報がAIの学習データとして利用されるリスクが発生します。
その結果、情報漏えいのリスクが高まり、企業の信頼を損なうだけでなく、法的な責任を問われる事態になりかねません。
また、生成AIツールが生成した成果物の著作権にも注意が必要です。
従業員が業務で生成AIツールを利用して作成した資料が、著作権侵害にあたる場合、企業が訴訟を起こされるリスクがあります。
さらに、生成された情報が不正確であったり、偏った情報に基づいていた場合、企業の意思決定に悪影響を及ぼす可能性もあります。
そのため、企業は従業員への教育・利用ルールの策定・適切なAIツールの導入などを通じて、シャドーAI対策を講じなければなりません。
BYODとの違い
シャドーITとよく混同される言葉に「BYOD(Bring Your Own Device)」があります。
BYODは、従業員が個人所有のデバイスを業務で利用することを、企業が公式に許可し、管理する制度のことです。
両者の決定的な違いは、「企業の承認と管理の有無」にあります。
以下の表で違いをチェックしましょう。
|
項目 |
シャドーIT(Shadow IT) |
BYOD(Bring Your Own Device) |
|
定義 |
企業が把握・承認していないITツールやサービスの業務利用 |
企業が公式に許可し、管理された私物デバイスの業務利用 |
|
承認の有無 |
承認なし |
承認あり |
|
管理体制 |
管理なし(野放し状態) |
MDMなどによる管理あり |
|
セキュリティ対策 |
不十分、脆弱性が放置されやすい |
MDM・データ分離・VPNなど対策が講じられる |
|
企業にとってのリスク |
未知数で非常に高い |
想定・管理可能 |
このように、シャドーITは企業の管理外にあるためリスクが非常に高いのに対し、BYODは企業がリスクを管理下に置いたうえで利便性を追求する、まったく性質の異なるものです。
一見すると従業員が自由に私物デバイスを利用しているように見えますが、実際は企業の管理体制が整っているからこそ実践できる取り組みです。
サンクションITとの違い
サンクションITとは、シャドーITと対比される概念であり、企業が正式に許可し、セキュリティポリシーに沿って管理・運用されるITツールやサービスを指します。
具体的には、社内で利用が許可されている業務用のソフトウェア・コミュニケーションツール・会社が契約しているクラウドサービスなどが該当します。
サンクションITは企業が管理しているため、安全な運用が可能です。
企業にとって理想的な状態は、従業員が業務で使用するすべてのIT環境がサンクションITとして管理されていることです。
これにより、企業はセキュリティリスクを最小限に抑え、情報漏えいや不正アクセスといった脅威を防止できます。
また、コンプライアンスを遵守し、法規制や業界標準に適合した運用を実現するうえでもサンクションITの実現は不可欠です。
さらに、IT資産の一元管理は、コスト削減や効率的なリソース配分にもつながり、企業の競争力強化に貢献します。
シャドーITが発生しやすいツール

本章では、シャドーITが発生しやすいツールを以下に分けて解説します。
- ノートパソコン・スマートフォン
- フリーメール
- チャットアプリ
- フリーWi-Fi
- クラウドサービス
いずれのツールも、個人利用では非常に便利ですが、ビジネスで利用するにはセキュリティ上の懸念がある点に注意しなければなりません。
それぞれのツールが持つリスクを把握し、適切な対策を講じましょう。
ノートパソコン・スマートフォン
私物のノートパソコンやスマートフォンを業務に利用するシャドーITは、情報セキュリティ上の深刻なリスクをもたらします。
私物は会社のセキュリティポリシーが適用されないため、ウイルス対策ソフトウェアの不備やOSのアップデート遅延により、マルウェア感染のリスクが高まります。
また、私物デバイスは紛失・盗難のリスクもあります。
機密情報が保存された状態で紛失し、お客さま情報や財務情報などの漏えいが発生すると、企業の信用失墜や法的責任を招きかねません。
シャドーITはセキュリティ対策が不十分な私物デバイスを経由して、企業全体のセキュリティを脅かす可能性があります。
フリーメール
GmailやYahoo!メールなどのフリーメールは、手軽に利用できるため個人利用では非常に便利です。
しかし、業務利用においては注意が必要です。
なぜなら、フリーメールアドレスで業務を行うと、メールの送受信履歴が会社の管理下に置かれず、情報セキュリティ上のリスクが高まるからです。
具体的には、従業員がお客さま情報や契約情報などの機密情報をフリーメールでやり取りした場合、情報漏えいのリスクが生じます。
また、退職者が会社の重要な情報を自分のフリーメールアカウントに転送し、持ち出すことも容易になる点にも注意が必要です。
従業員の利用しているアカウントが流出する事態になれば、不正アクセスの温床にもなります。
フリーメールのような、企業が管理できないメールシステムはセキュリティホールになりやすいものです。
業務でメールを利用する際は、企業が管理できるメールシステムを導入しましょう。
チャットアプリ
業務連絡にLINE・Slack・Chatworkなどの個人アカウントを使用するケースは珍しくありませんが、セキュリティ上のリスクを考慮する必要があります。
これらのツールは手軽に利用できる反面、情報漏えいのリスクが伴います。
例えば、誤送信によって機密情報が意図しない相手に伝わってしまう可能性があります。
また、個人アカウントはセキュリティ対策が企業レベルに比べて脆弱な場合が多く、アカウント乗っ取りのリスクも無視できません。
さらに、個人向けのチャットアプリは業務利用を想定して設計されていないため、ログの管理機能が不足しているケースが想定されます。
万が一、情報漏えいが発生した場合、原因究明や影響範囲の特定が困難になる可能性があります。
コンプライアンスの観点からも、業務利用においてはセキュリティ対策が施された専用のコミュニケーションツールを導入しましょう。
フリーWi-Fi
フリーWi-Fiは便利な一方で、セキュリティ上のリスクが高い点に注意しましょう。
特に外出先やカフェなどで提供されているWi-Fiは、暗号化されていない場合が多く、通信内容が第三者に傍受される可能性があります。
もし不正アクセスを受ければ、クレジットカード情報やログインID・パスワードなど、個人情報が盗まれる危険性が高まります。
特に、企業の機密情報やお客さま情報など、重要なデータを扱う業務においては、フリーWi-Fiの利用は厳禁です。
情報漏えいが発生した場合、企業は信用を失い、損害賠償責任を負う事態になる可能性があります。
VPN(Virtual Private Network)による通信の暗号化やモバイルWi-Fiルーターの利用など、安全な通信手段を確保することが重要です。
また、公共の場での作業は、画面にフィルターをかけるなど、覗き見対策も徹底しましょう。
クラウドサービス
個人利用できるクラウドストレージも、無視できないシャドーITです。
DropboxやGoogleドライブといったサービスは利便性が高い一方、個人アカウントでの利用は企業の管理下から外れるため、情報漏えいのリスクが高まります。
特に、業務データを個人用クラウドストレージに保存・共有する場合、アクセス権の設定が不十分だと、機密情報が意図せず外部に公開される危険性があります。
例えば、共有リンクの設定ミスや、退職者のアカウント管理の不備などが原因で、情報漏えいが発生する点にも注意が必要です。
さらに、個人用クラウドストレージは、企業のセキュリティポリシーや監査体制の対象外となることが多いため、万が一の事故が発生した場合の追跡や対応が困難です。
クラウドストレージの利用状況を監視する仕組みを導入し、不審なアクセスやデータの持ち出しを早期に発見しましょう。
シャドーITが発生する原因

シャドーITが発生する原因は、以下のとおりです。
- 利便性と効率性の追求
- クラウドサービスの普及
- テレワークの普及と働き方の多様化
- セキュリティ意識の低下
- IT監視体制の不備
単に従業員のルール違反と切り捨てるのではなく、その背景にある根本的な原因を理解することが、効果的な対策を講じる鍵となります。
利便性と効率性の追求
従業員がシャドーITを利用する最大の動機は、「仕事をより早く、より効率的に進めたい」といった切実なニーズに起因します。
会社が提供する公式ツールが、現代の業務スピードや複雑な要求に応えきれていない場合、従業員は代替手段を模索せざるを得ません。
例えば、公式ツールのインターフェースが操作に時間がかかったり、必要な機能が不足していたりするような状況だと、業務が非効率化します。
あるいは利用申請の手続きが煩雑で承認までに時間がかかるといった状況も、従業員にストレスを与える要素です。
このような不満があると、従業員は日々の業務をスムーズに進めるために、より手軽で高機能な個人向けツールに頼るようになります。
個人向けツールは、使い慣れているうえに必要な機能をすぐに利用できるため、業務効率の大幅な向上が期待できるものです。
しかし、従業員個人によるツールの導入が常態化すると、シャドーITが蔓延し、セキュリティリスクを管理できなくなります。
企業としては公式ツールの改善や利用プロセスの見直しを行い、従業員のニーズに応えるとともに、安全なIT環境を構築していく必要があります。
クラウドサービスの普及
現代では、ITの専門知識がなくても、個人が手軽に契約・利用できるクラウドサービスが数多く存在します。
SaaSモデルの普及によって、高度な機能を持つツールが無料でも使えるようになりました。
特にDropboxのようなクラウドストレージや、Canvaのようなグラフィックデザインツールは高機能なうえに無料で利用できるため、従業員個人でも簡単に導入できます。
しかし、個人の判断で業務で扱う資料や機密情報を保存できるようになったことは、企業にとって重大なリスクです。
個人が利用するクラウドサービスは管理が行き届かないため、知らない間に情報が流出する恐れがあります。
テレワークの普及と働き方の多様化
テレワークの普及は、従業員が働く環境に大きな変化をもたらしました。従業員は自宅やカフェなど、IT部門の監視が行き届きにくい場所で働く機会が増加しています。
一方、テレワークは従業員が自身の判断で、非公式なツールやサービスを業務に利用しやすい環境を生み出しています。
セキュリティ対策が不十分なストレージサービスに機密情報を保存したり、承認されていないコミュニケーションツールでお客さま情報を含むやり取りをしたりするケースが典型例です。
したがって、企業はテレワーク環境における情報セキュリティ対策を強化する必要があります。
また、従業員の利用状況を把握するためのツールを導入し、不審なアクティビティを早期に検知できる体制を構築しましょう。
テレワークの利便性を最大限に活かしつつ、セキュリティリスクを最小限に抑えるためのバランスの取れた対策が求められています。
セキュリティ意識の低下
シャドーITのリスクや、従業員のセキュリティ意識の低下も無視できない要因です。
「自分だけなら大丈夫」「少し使うだけだから問題ない」といった安易な考えは、セキュリティホールを生み出し、組織全体を危険にさらす可能性があります。
無料で利用できるツールが増えている昨今、従業員の個人の判断で導入を決定するような状況は、セキュリティリスクを高めるだけです。
リスクを軽減するためには、組織全体でのシャドーITに対する意識改革が不可欠です。
個々の従業員がシャドーITの潜在的な危険性を理解し、組織のセキュリティポリシーを遵守するよう努める必要があります。
さらに定期的な研修や啓発活動を通じて、セキュリティ意識を高めるとともに、組織が許可した安全なIT環境を提供することが重要です。
安易な行動が組織全体に及ぼす影響を認識し、適切なIT利用を心がけることが、情報セキュリティを守ることにつながります。
IT監視体制の不備
従業員のIT利用状況を正確に把握できていない状況は、企業にとって深刻なリスクを孕んでいます。
まず、どのようなツールが利用されているのかを把握できていない場合、セキュリティ上の脆弱性を見過ごしてしまう可能性があります。
また、「誰がどのツールをどのように使っているか」「どのように業務を進めているか」を可視化できていないと、業務効率の低下にもつながります。
例えば、同じような機能を持つツールが複数部署で重複して利用されていたり、非効率な使い方が蔓延していたりする状況が想定されるためです。
これらの問題を解決するためには、IT資産管理ツールの導入や、従業員への定期的なアンケート調査などが有効です。
また、IT部門だけでなく、各部署の責任者も協力して、IT利用状況の可視化に取り組む必要があります。
可視化された情報を元に、セキュリティポリシーの見直しや、従業員への適切なIT研修を実施することで、シャドーITのリスクを軽減し、業務効率の向上を図れます。
シャドーITがもたらすリスク

シャドーITがもたらすリスクは、以下のとおりです。
- 情報漏えい
- マルウェア感染とサイバー攻撃
- コンプライアンス違反と法的制裁
- IT統制の崩壊と非効率な運用
- 退職者によるデータの持ち出し・残留
シャドーITは、単なるルール違反では済みません。
情報漏えいやサイバー攻撃の温床となり、企業の信頼や事業継続そのものを脅かす、深刻な経営リスクをもたらします。
情報漏えい
シャドーITが引き起こすもっとも重大なリスクは、やはり情報漏えいです。
シャドーITがあると、管理者の目が届かない場所で機密情報が扱われるため、企業のセキュリティ対策が行き届きません。
また、簡単に利用できるクラウドストレージやアプリケーションは、セキュリティ設定が不十分な場合が多く、悪意のある第三者が侵入する恐れがあります。
このように、管理外のツールに機密情報や個人情報が保存されることは、企業の信頼を根底から揺るがす大規模な情報漏えいにつながりかねない行為です。
情報漏えいは、企業のブランドイメージを毀損するだけでなく、損害賠償請求や事業停止命令など、経営に深刻な影響を与える可能性があります。
マルウェア感染とサイバー攻撃
セキュリティ対策が不十分な個人デバイスや未承認のソフトウェアは、ウイルスやランサムウェアといったマルウェアの格好の侵入経路です。
脆弱性を放置すると、攻撃者は容易にシステムへ侵入し、悪意のあるコードを実行しやすくなります。
また、一つのデバイスが感染すると、そこを起点に社内ネットワーク全体へと被害が拡大するリスクが高まります。
マルウェアはネットワークを通じて拡散し、他のデバイスやサーバに感染を広げ、最終的にはシステムの停止や事業の中断といった甚大な被害を引き起こしかねないものです。
機密情報の漏えいや改ざんも起こりうるため、企業の信頼を大きく損なうことにもつながりかねません。
したがって、個人デバイスのセキュリティ対策を徹底し、承認されたソフトウェアのみを使用することが、組織全体のセキュリティを守るうえで極めて重要です。
コンプライアンス違反と法的制裁
個人情報保護法や業界規制に未準拠のツール利用は、重大なコンプライアンス違反を招きます。
違反行為を放置すれば、企業は高額な罰金・行政指導・訴訟などの法的制裁を受け、社会的信用を失墜させる可能性があります。
コンプライアンス遵守は、企業存続の基盤であり、適切なツール選定と運用体制の構築が欠かせません。
定期的な監査と従業員教育を通じて、リスクを最小限に抑えることが重要です。
違反事例の研究や専門家への相談も有効な対策となります。
IT統制の崩壊と非効率な運用
シャドーITの横行は、IT部門が定めるセキュリティポリシーを無効化し、組織全体のITガバナンス(統制)を崩壊させる深刻なリスクをもたらします。
IT部門が把握していないシステムは、セキュリティ上の脆弱性を見過ごす原因となり、サイバー攻撃の格好の標的となりかねません。
また、シャドーITは運用面でも大きな非効率を生み出します。
IT部門は、本来注力すべき戦略的な業務から離れ、未把握のツールに関する問い合わせ対応やトラブルシューティングに時間を費やさざるを得ません。
結果として、業務効率が低下する要因となります。
シャドーITの蔓延は、セキュリティリスクの増大と運用コストの増加を招き、組織の持続的な成長を妨げる事態を招く要因です。
退職者によるデータの持ち出し・残留
従業員退職時における、クラウドストレージの業務データ残存は深刻なリスクです。
個人アカウントの利用は、会社側がアカウントの存在を把握できず、退職後にデータ削除が困難となる状況を生み出します。
これにより、情報漏えいのリスクが長期にわたり継続し、お客さま情報や機密情報が外部に漏えいする危険性があります。
さらに、企業の重要な知的財産である技術情報・設計図・ノウハウなどが流出し、競争力の低下や損害賠償請求につながる可能性も無視できません。
退職者の私物デバイスにデータが残存している場合も同様のリスクが存在します。
企業は、クラウドストレージの利用状況を把握し、退職時のデータ返却・削除に関する明確なルールを定めましょう。
シャドーITによる情報漏えいの事例

シャドーITによる情報漏えいの事例には、以下のものがあります。
- 病院のケース
- ファイル転送サービスのケース
- 自治体のケース
シャドーITの脅威を、過去に実際に発生した事例から学びましょう。
病院のケース
ある地方の病院では、2021年にフィッシング詐欺によって患者情報が漏えいする事件が発生しました。
勤務していた医師が、個人で利用していたクラウドサービスのIDとパスワードが窃取されたことが原因です。
患者情報を外部のクラウドサービスに保存することは、規程で禁止されていましたが、当該医師は遵守していませんでした。その結果、269人の患者情報を攻撃者が閲覧できる状況を招いています。
当該病院は再発を防ぐため、あらためてセキュリティ対策を徹底し、職員の意識向上に取り組むことを表明しています。
ファイル転送サービスのケース
2019年、フリーで利用できるファイル転送サービスがサイバー攻撃を受け、約480万件の個人情報が流出する事件が発生しました。
当該サービスは多くのビジネスパーソンに利用されていましたが、企業の承認を得ずにシャドーITとして利用していたケースが多く、情報漏えいの発覚が遅れる一因になったと指摘されています。
元々当該サービスは保存データが暗号化されていないことから、セキュリティリスクが高いサービスとして認識されていました。
しかし、多くの企業がサービスの利用を把握しておらず、従業員が個人で利用した結果、この事件に巻き込まれています。
事件以降、当該サービスを含め、利用の停止やガイドラインの策定などに取り組む企業が増加しました。
この事例は、安易にクラウドサービスを利用するリスクを如実に示していると考えられます。
自治体のケース
2018年、ある地方自治体の職員が業務で利用していたフリーメールのアカウントが不正アクセスを受け、1,800人分の個人情報が流出したケースです。
元々、その自治体はフリーメールの利用を規程で禁止していましたが、管理体制が形骸化していました。
そのため、複数の職員がスキャナーなどで取り込んだデータを直接フリーメールで扱うような状況が常態化していました。
このケースは、管理体制の不備や、職員の意識の低さがトラブルを招く典型例です。
シャドーITをなくすには、管理体制の形骸化を防ぐ取り組みが求められます。
シャドーITに有効な対策

シャドーITを防止するには、以下の対策が有効です。
- 利用実態を正確に検知する
- ポリシーとガイドラインを定める
- 従業員へのセキュリティ教育を強化する
- 利便性の高い代替ツールを導入する
- シャドーITを制御できるシステムを導入する
- ゼロトラストの考え方を導入する
単にツールを禁止するだけでは、根本的な解決にはなりません。
セキュリティと利便性のバランスを取りながら、IT利用を健全化していくための多角的なアプローチが必要です。
利用実態を正確に検知する
シャドーITの対策の第一歩は、利用実態の正確な検知です。
まずは従業員にアンケートやヒアリングを実施し、利用されているITツールを明らかにしましょう。
利用実態の把握は、企業のセキュリティ対策だけでなく、IT運用全体の課題を抽出するうえでも有効な取り組みです。
もし、シャドーITが発見された際はガイドラインを策定するなど、運用に関する企業の方針を明示しましょう。
なお、利用実態を調査する過程で、従業員が利用しているツールが有用だと判明した際は、正式な導入を検討することもおすすめです。
ポリシーとガイドラインを定める
ITツールの利用に関する明確なルールを策定し、全従業員に周知徹底することも不可欠です。
特に以下の内容は、必ず明記しましょう。
- 利用を許可するサービス、禁止するサービスは何か
- データの保存場所や共有方法はどうするか
- 私物デバイスを利用する場合の条件は何か(BYODポリシー)
策定したガイドラインは、従業員がいつでも参照できるようにしておくことが重要です。
また、ルールに基づいた運用がされているか、定期的にチェックしましょう。
従業員へのセキュリティ教育を強化する
ツールやルールを整備しても、従業員のセキュリティ意識が低ければ意味がありません。
定期的な研修を実施し、シャドーITがもたらすリスクや過去のインシデント事例を共有することで、従業員の意識向上を図りましょう。
研修では、具体的な事例を基に、なぜシャドーITが危険なのかを理解させ、安全な代替手段を提示することが重要です。
加えて、セキュリティに関する最新情報を常に提供し、従業員が常に警戒心を持つように促しましょう。
利便性の高い代替ツールを導入する
従業員がシャドーITに手を出す背景には、企業が採用しているツールへの不満の表れでもあります。
IT部門は、従業員のニーズをヒアリングし、セキュリティが確保されたうえで利便性の高い代替ツールを公式に導入・提供することを検討すべきです。
安全かつ便利なビジネスチャットアプリやオンラインストレージを提供することで、シャドーITの利用動機を根本から減らせます。
また、最適な代替ツールを導入できれば、業務の効率化や生産性の向上が見込めます。
シャドーITを制御できるシステムを導入する
検知や従業員教育も重要ですが、技術的なシャドーITの制御も欠かせません。
CASB(Cloud Access Security Broker)のようなツールは、企業が許可していないクラウドサービスへのアクセスをブロックしたり、機密情報の含まれるファイルのアップロードを禁止したりする機能を提供します。
これらの機能は、従業員が意図せず企業のセキュリティポリシーに違反する行為を未然に防ぐ効果があります。
CASBを使えば、個人用のクラウドストレージに社内データをアップロードしようとする行為や、承認されていないツールを使用して機密情報を共有しようとする行為のブロックが可能です。
また、ポリシー違反が発生した場合の迅速な対応を可能にするアラート機能なども備わっているため、セキュリティ体制の継続的な改善を実現できます。
IT統制を進める上で押さえておきたいセキュリティ対策のポイント | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
ゼロトラストの考え方を導入する
従来の境界型防御は、社内を安全地帯・社外を危険地帯と区別していましたが、クラウド利用やテレワークの普及により、この考え方は時代遅れとなりました。
そのため、昨今重視されているのがゼロトラストの概念です。
ゼロトラストとは、「何も信頼せず、常に検証する」の原則に基づき、ネットワークの内外を問わず、すべてのアクセス要求を厳格に検証するセキュリティモデルを指します。
ユーザー認証・デバイス認証・アプリケーション認証を多層的に行うことで、たとえ社内ネットワークからのアクセスであっても、不正なアクセスを未然に防止できます。
ゼロトラストの考え方への移行は、シャドーIT対策として非常に有効であり、企業全体のセキュリティレベル向上に不可欠な取り組みです。
ゼロトラストセキュリティとは?実現のステップと要件、対策方法を紹介
シャドーIT対策ならDAIKO XTECHへご相談を

シャドーIT対策は、ツールの導入からポリシー策定、従業員教育まで多岐にわたり、IT部門のご担当者様だけでは対応が難しい場合も少なくありません。
そのような場合は、ぜひ専門家の力を活用してください。
DAIKO XTECHは、多くの企業のICTシステムを支えてきた実績とノウハウで、お客さまのシャドーIT対策を強力にサポートします。
DAIKO XTECHの強みは、お客さまの課題解決を幅広いソリューションでサポートできる点です。お客さまの現在のIT環境やご予算、解決したい課題に応じて、数あるセキュリティ製品の中から最適な組み合わせをご提案します。
どのようなソリューションを導入すべきか不明な際は、ぜひお気軽に弊社セキュリティアドバイザーまでご相談ください。
シャドーITにはリスクを踏まえた適切な対策を実施しよう

シャドーITは、従業員の利便性追求から生まれる一方で、情報漏えいやサイバー攻撃など、企業に深刻なダメージを与える重大なリスクをはらんでいます。
この問題を単なる「従業員のルール違反」として片付けるのではなく、従業員のニーズを理解することが重要です。
シャドーITの対策をセキュリティと生産性を両立させるための「経営課題」として捉えましょう。
利用実態の可視化・従業員教育・ゼロトラストに基づいた技術的制御など、多角的なアプローチを組み合わせることで、シャドーITのリスクを管理し、安全で生産性の高いデジタル環境を構築できます。
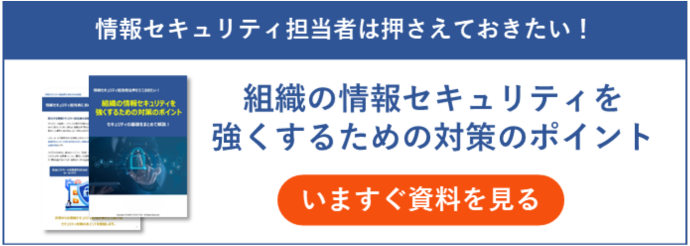
おすすめのお役立ち資料はこちら↓