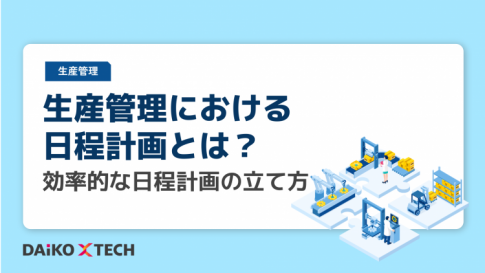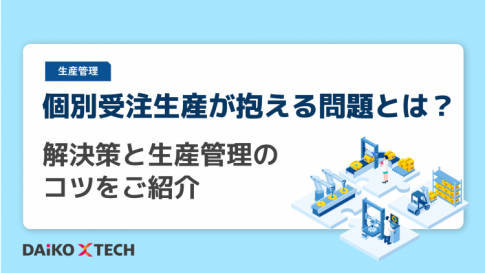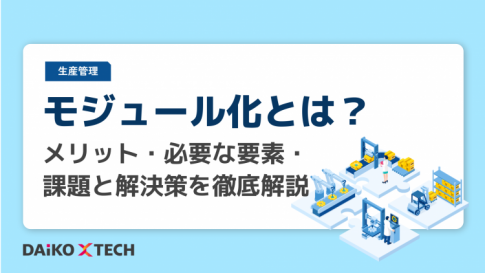原価管理システムは、複雑な原価計算を効率化できるシステムのことです。原価管理計算を自動化して正確性の高い原価管理が行えます。
この記事では、原価管理システムの意義や原価管理の課題を押さえながら、原価管理システムの機能、導入のメリット、システムの選び方などをわかりやすく解説します。
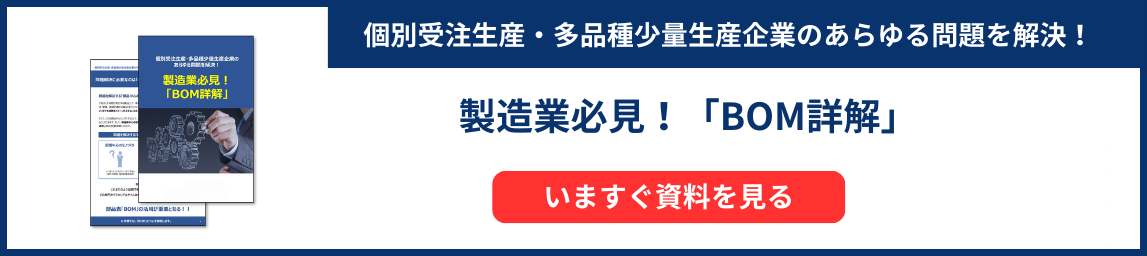
目次
製造業における原価管理とは

製造業では、製品を製造するためにかかったコスト(=原価)を計算し、最適化するために原価管理を行います。
原価管理は、製造業にとって不可欠ですが、その理由と目的について解説します。
原価管理が経営に欠かせない理由
製造業が共通して目指すのは、利益の最大化です。販売価格から、製造にかかったすべてのコスト(=原価)を差し引くと利益が算出できます。
仮に複数の競合が同じ価格で同等品を同数販売した場合、原価がもっとも安い企業が最大の利益を確保できます。
利益が多ければ、それを原資に新商品開発や設備投資、優秀な人材の確保などが可能となるため、業績向上につながるでしょう。
逆に原価が高ければ、利益圧縮によって企業体力は目減りします。競争力を高めるには、コスト削減が必要ですが、そのためにも原価管理が不可欠となるのです。
原価管理の目的
原価管理のためには、原価を正確に算出する原価計算が欠かせません。
さらに、原価計算は、「財務会計」と「管理会計」の2つの目的に分けられます。
財務会計とは、株主や取引先、債権者といった利害関係者に向けて財務状況を開示するための会計です。
具体的には、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフローなどで、年度末の決算に際して作成され、納税額の計算にも活用されます。
一方の管理会計は、経営改善や危機管理を目的とした企業内会計のことです。
財務会計のように決算期に関係なく、四半期や月間、週単位あるいは営業日ごとといった具合に独自のルールで指標を算出のうえ分析し、意思決定の材料にします。
いずれの観点からも、原価低減は重要とされています。原価が低く抑えられれば、利益が増えるので経営は安定し、株主や取引先などのステークホルダーより高い評価が受けられます。
しかし、原価が高い場合は、収益が下がるため放置していては競争力や市場価値の低下を招くでしょう。
ただし原価は、市況や製造量などによって増減する変動費が多くを占めるため、その動きを予測して原価管理を行うのは、決して容易ではありません。
また、原価を低く抑えたから良いとは必ずしも言い切れません。原料低減に伴い原材料の質を下げると、結果的に製品の品質の低下につながり、たとえ販売価格を安くしても製品そのものが売れなくなる可能性があるからです。
例えば製造業の中でも食品業界では、多くの場合、一社が販売する商品の中で利益創出の柱となるのは、全体の一部であって、その他はほとんど利益を生まないという厳しい現実があります。この場合、主力商品の原価を低くしすぎると商品本来の魅力が薄れ、企業全体の売上が下がる恐れがあります。
そこで主力商品の原価は現状のままにし、安価なコストで製造できる新商品を開発したり、売上の低い商品は思い切って製造を打ち切ったりという判断をするケースもあります。
このように製造業にとって原価管理は経営のあらゆる意思決定を左右し、その根幹を支える大変重要なプロセスといえます。そのため、原価計算を迅速かつ正確に行うことが、非常に重要です。
原価管理の手順
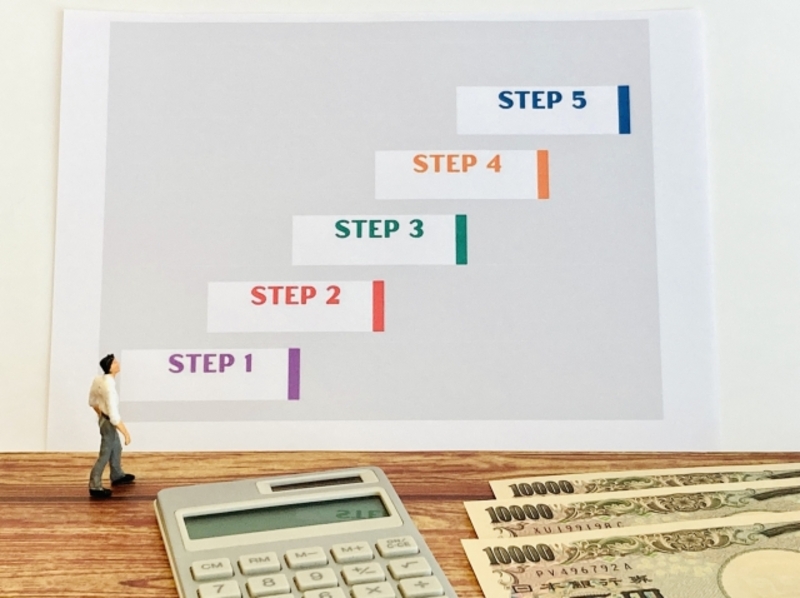
原価管理は、以下の4つの手順で進めます。
- 予定原価の設定
- 実際原価の計算
- 実際原価との差異を計算・分析
- 適切な原価と価格の設定
原価管理の要諦は、原価を割り出すことではありません。企業によって最適な原価を探り、その時勢ごとの最適価格を設定して、利益最大化を図ることにあります。
原価管理は、利益最大化という目的を達成するために行われるという点を念頭に置くと、以下の手順についての理解が進みやすいでしょう。
予定原価の設定
原価管理では、まず予定原価の設定を行います。
予定原価とは、製品を製造する上でコストがいくら必要かをあらかじめ計算することです。
原価には、材料費や物流コスト、人件費など、製造に必要なすべてのコストが含まれます。これらを過去の実績や経験から、予定原価としてできるだけ正確に割り出します。
予定原価が現実に即していれば、それを元に調達した資金の妥当性が高まります。
しかし現実に比べて低く設定されている場合は、追加で資金を確保する必要が生じるでしょう。この場合は、予算やキャッシュフローにマイナスの影響を及ぼす恐れがあります。
実際原価の計算
製品を製造するにあたって実際にかかった原価が、実際原価です。
原価は、労務費・材料費・経費のいずれかに分類されます。またこれら3つの費用は、製造量や売上、急な物価変動などによって増減する変動費と、製造量などに関係なく必要になる固定費のいずれかに分類可能です。
材料費はすべてが変動費ですし、労務費と経費にも少なからず変動費が含まれます。そのため、実際に製造した後でないと正確な原価が算出できないことから、予定原価と実際原価の値には、差異が発生しやすくなります。
実際原価との差異を計算・分析
実際原価を算出後、予定原価との差異を計算します。
この結果、予定原価が実際原価より高ければ(有利差異という)、予測値が高すぎたことになります。実際原価が予定原価を上回れば(不利差異という)、実値が高かったことを意味します。
前者の場合は、必要以上に余分な資金を準備しなければならないため、繰り返しを防ぐためにも差異の原因究明が必要です。
後者の場合は、想定より多くのコストがかかっているため、適正な支出であったのか十分に精査し、課題改善に取り組む必要があるでしょう。
適切な原価と価格の設定
実値との差異を分析したら、次に向けて適切な原価と販売価格の設定に移ります。
資材や物流費、人件費の高騰などでコストが抑えにくい場合は、販売価格を上げて対応する必要があります。
競合が多いとか、消費が低迷しているなどの理由で販売価格を下げざるを得ない場合は、原価を下げる工夫と企業努力が欠かせません。
具体的には、製造工程を見直したり、原料や仕入れ先を変えたり、あるいは仕入れ先に仕入れ価格の割引を要請するといった取り組みが必要になります。
原価管理の課題

製造業の原価管理には、以下の4つの課題が散見されます。
- 原価計算が複雑で負担が大きい
- 製造拠点が複数あるため一元管理が困難
- 原価計算の精度が低い
- Excelでの管理に限界がある
原価計算が複雑で負担が大きい
原価計算を正確に行うには、かなり複雑な工程を踏む必要があります。
特に製造業の場合は、コスト構造が複雑です。また、単にコストがいくらかだけでなく、それらを部門ごとや製造工程ごとに配賦しなければなりません。
そのためには、製造現場における様々な動きや事象をつぶさに管理したり、情報を吸い上げたりする必要があります。
これらの作業は人手で行う必要があり、担当者の負担が大きくなります。
H3 製造拠点が複数あるため一元管理が困難
製造拠点が複数に分かれている企業では、原価管理の方法が異なる例が珍しくありません。そのため、一元管理が難しく、企業全体の原価管理が複雑になるだけでなく、正確な原価を把握することが困難になります。
それに加え、海外にも製造拠点が存在する場合、適切な原価管理はさらに複雑になると考えられます。
原価計算の精度が低い
膨大な労力と時間を費やす割に、その複雑さゆえに原価計算の精度が予想外に低い例が珍しくありません。
これには、大きく2つの原因があると考えられます。
一つは、原価計算を適正に行う環境やシステム、十分なスキルをもった人材が不足していることです。
ただ原価計算に問題があるとは理解していても、実際は営業や製造、広告など目先の業務に追われて、原価計算の改善にまで手が回らないというケースがあります。
システムを変更するにはコストと手間がかかるため、従来の方法で何とかやり過ごしたいのが本音という経営者もいます。
もう一つは、近年、国内外を問わず不確実性が急激に高まっている点が挙げられます。
広範囲にわたる感染症の蔓延、地域や国家間の紛争、気候変動などによってサプライチェーンが寸断されたり、未曾有の物価高騰が生じたりといった現象が、原価予測を難しくしています。
そのため、従来の方法では予測と実値に差異が生じ、原価計算の精度の低下につながります。
Excelでの原価計算が限界
原価計算にExcelを利用している企業が多いです。しかし、「計算工程が複雑で属人化している」「データの一元化が困難」「行や列を新たに追加すると崩れて修正できない」などの理由から限界を感じているケースが少なくありません。
原価管理システムとは

原価管理にありがちな課題を解決するツールとして有効なのが、「原価管理システム」です。
原価管理システムを使うと、必要なデータを入力するだけで、予定原価や原価差異の割り出し、損益計算書の作成などが自動化できるようになります。
適正原価や価格を設定するためのシミュレーション、生産管理や販売管理、在庫管理といった基幹システムとの連携も可能なため、原価管理のデジタル化や業務効率化が促進できます。
原価管理システムの機能

原価管理システムの主な6つの機能について紹介します。
- 原価計算機能
- 原価差異分析機能
- 損益計算機能
- 配賦計算機能
- 原価シミュレーション機能
- システム連携機能
原価計算機能
予定原価や標準原価、実際原価といったさまざまなパターンの原価計算が自動化できます。
原価計算は、多くのデータを活用し、複雑な計算を繰り返さなければなりません。追加・削除・修正もつきものですが、原価管理システムなら単純な操作で実行可能です。
原価を正確に算出することにより、重要度の高い意思決定を強力にサポートします。
原価差異分析機能
原価管理システムは、実値との差異を分析できます。有利差異や不利差異について具体的な費目における差異金額の詳細が把握可能です。
損益計算機能
製品や部門ごと、あるいは四半期など期間を区切って損益が計算できる機能です。損益計算書を作成することもできます。
収益性の良し悪しが明確になるため、予算の振り分けやプロダクトの品質改善・新商品開発といった意思決定をサポートします。
配賦計算機能
原価計算における配賦は、企業によって基準が異なります。部門別配布や製品別配賦のパターンを定義できるのが配賦計算機能です。
配賦計算が自動化できると、原価計算の精度が高まり、特定の部門だけでなく、会社全体の利益が俯瞰できるようになります。
原価シミュレーション機能
変動要因を予測して、原価や収益に与える影響を分析できるのが、原価シミュレーション機能です。
売上目標を設定した上での原価算出や、新製品の販売数量の決定、材料費高騰時の販売価格の変更など、さまざまなシミュレーションにより、中長期的な意思決定をサポートします。
システム連携機能
原価管理システムは、既存システムとの連携によりパフォーマンスが向上します。
具体的には、生産管理、販売管理、在庫管理、会計管理などと連携することで、より精度の高い原価管理が実現します。
原価管理システムの種類

原価管理システムには以下の3つのタイプがあります。
- 特定の業界に最適化された業界特化型
- プロジェクト単位でコスト管理が行えるプロジェクト管理型
- 汎用性の高い多用途型
導入する際は、それぞれの特徴を理解した上で最適なものを選ぶことが大切です。
特定の業界に最適化された業界特化型
業界特化型の原価管理システムは、特定の業界に最適化されたサービスです。
特に製造業に特化した原価管理システムは多数販売されているので、活用することをおすすめします。
製造業の場合は、生産管理、販売管理、在庫管理などとの連携が欠かせません。材料やパーツ、そして製品ごとに生産や管理拠点が異なることも少なくないでしょう。サプライチェーン内で発生する原価についてもつぶさに把握する必要があります。
こうした課題にスムーズに対応するには、業界特化型の原価管理システムがうってつけです。
プロジェクト単位でコスト管理を行えるプロジェクト管理型
プロジェクト管理型の原価管理システムは、案件や契約などのプロジェクトごとに原価管理を行う企業向けのサービスです。
広告・コンテンツ制作、コンサルティング、ITサービスといった業界はプロジェクトごとに原価計算を行うケースが多いです。
プロジェクト管理型の原価管理システムなら、各プロジェクトで発生する労務費・仕入・外注費などの各原価項目を紐付けて一元管理できます。
プロジェクトを同時に進めている場合は、間接費の配賦が複雑です。費やした作業時間などに応じて基準を設け、各プロジェクトごとに振り分けなければなりません。このプロセスも、プロジェクト管理型の原価管理システムを利用するとスムーズに行えます。
汎用性の高い多用途型
多用途型は、業界や業種に関係なく幅広い原価管理に対応できるのが特徴です。業界特有の処理が必要というより、複雑な業務プロセスや配賦基準の設定が不要なケースで汎用的に活用されます。
製造業における原価管理システム導入のメリット

製造業が原価管理システムを導入する主なメリットは、以下の4点です。
- 人件費が削減できる
- 経営判断をサポートできる
- 原価変動リスクに対応できる
- 他システムとの連携がきる
人件費が削減できる
原価管理システムは、最低限のデータを入力するだけで、原価管理のプロセスを自動化できます。
こうした理由から原価管理プロセスが大幅に効率化されるため、人件費の削減が可能です。
経営判断をサポートできる
原価管理システムがあれば、損益分岐点の算出が容易になります。損益分岐点とは、売上とコストが同額で、利益が0になる売上のことです。例えば、100円で販売している商品の原価が70円の場合、損益分岐点比率は70%となります。一般的に、損益分岐点比率が低いほど経営状態が安定していると言われています。
損益分岐点率を下げて収益を増やすには、販売価格を上げるかコストを抑えるしかありません。
原価管理システムは、こうした経営判断をサポートします。
原価変動リスクに対応できる
物価上昇や為替変動により、原価が変動するケースが珍しくありません。企業経営においてこうした原価変動を後追いしていたのでは、対応が遅れて、利益喪失や負債増加といったリスクを回避することが困難になります。
そこで原価管理システムを使うと、原価が変動した場合の適切な販売価格や販売量などをシミュレーションできます。さまざまなケースを想定して何度でも試算できるため、原価変動に対応しやすくなります。
他システムとの連携が可能
原価計算には、原価に関するさまざまなデータが必要になります。原価管理システムは、生産管理・在庫管理・販売管理、会計といった基幹システムとの連携により、迅速かつ効率的なデータ統合を実現します。
これによって業務効率化が推進可能です。
製造業における原価管理システム導入のデメリット
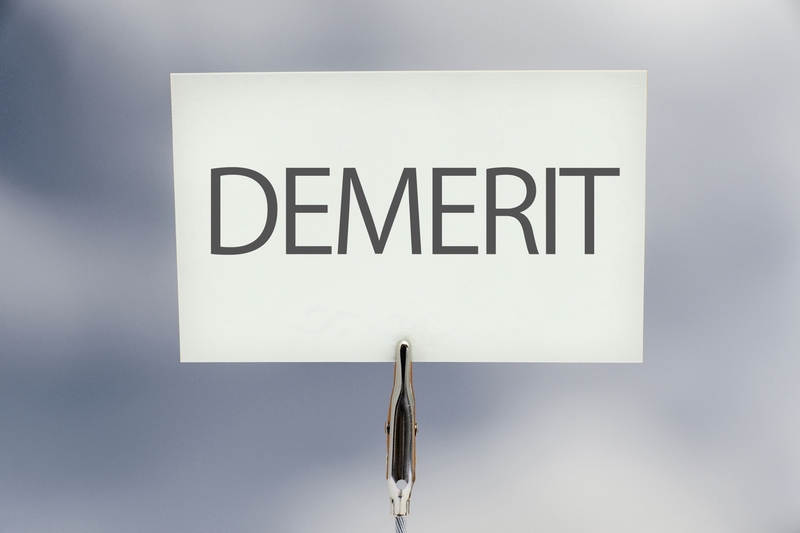
原価管理システムの導入は、実施することにより多くのメリットが受けられます。
ただし、導入にはコストがかかりますし、サービスによって業界特化型、プロジェクト管理型、多用途型と特性が異なるため、自社に合ったシステムを導入しなければ原価管理がかえって複雑化する恐れがあります。
したがって、導入にあたっては機能や料金プランをよく吟味する必要があるでしょう。
原価管理システムの選び方

原価管理システムには、さまざまなタイプがあります。
そこで、最適なサービスを選択するための基準や考え方について解説します。
自社のニーズに適合しているか
原価管理システムを選ぶ上でもっとも重要なのは、自社のニーズに適合しているかという点です。
この点で適切な解を得るには、自社における原価管理の課題を具体的に書き出してみるとよいでしょう。
担当者にも細かくヒアリングし、真の意味で課題解決と業務効率化を推進できる道筋を立てる必要があります。
こうすることで、必要な機能が具体化するため、適切な原価管理システムが選択しやすくなります。
ニーズに適合しているか判断しにくい場合は、積極的に資料請求するなどして過去の実績や導入例をチェックするのもおすすめです。
また、原価管理システムは有料のため、予算の面でも自社に見合った無理のないものを選択する必要があります。
近年、クラウド型のシステムが多く提供されていますが、カスタマイズ性に優れたオンプレミス型は導入コストが高くなる傾向があるため、慎重に検討する必要があります。
オンプレミス型は、すでに社内に専用サーバーが設置されている場合はまだしも、一から構築するとなると相当額の予算が必要になるため、注意が必要です。
自動配賦機能を備えているか
原価管理を複雑にする要因の一つに「配賦」があります。配賦は、独自のルールを設定し、原価と実値との差異をなくすことが求められます。
とくに同時に複数の製品を製造し、原材料を共有していたり、多拠点で製造していたり、一人の社員が複数の作業に携わっていたりする場合は、配賦が複雑化します。配布が複雑だと、当然ミスも起きやすくなるでしょう。
こうした場合は、自動配布機能を備えた原価管理システムが、必須です。
その他、原価管理システムの選び方については下記記事を参考にしてください
https://www.daikodenshi.jp/daiko-plus/production-control/basis-of-cost-management/
原価管理システムを導入して原価管理を効率化しよう

製造業にとって原価管理は、決算業務や利益計画の策定、販売価格の決定など企業経営の基盤となる非常に重要なプロセスです。しかし、原価計算は大変複雑なため、正確に行うのは決して容易ではありません。
そこで原価管理システムを導入すれば、複雑な原価管理が自動化できるため、業務効率がアップし、コスト削減も実現できます。
なお当社では、原価管理を強力にサポートできるハイブリッド販売・生産管理システム「rBOM」をご提供しています。営業、設計、購買、製造といった異なる部門の曖昧になりがちな原価をリアルタイムで正確に把握できるため、コストを最適化して収益増に繋げることが可能です。
複雑な原価計算からの解放と精度の高い原価管理の実現にご関心のある方は、下記リンクから「rBOM」の資料をぜひご確認ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
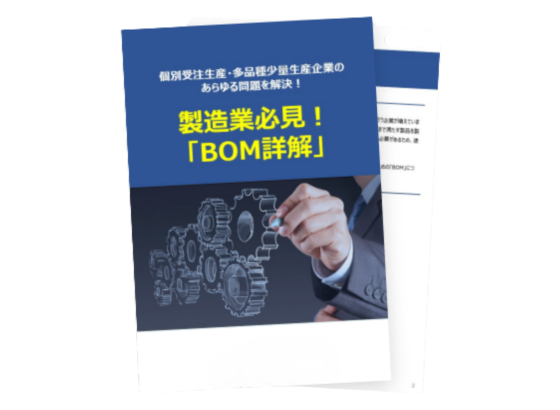
個別受注生産・多品種少量生産企業の あらゆる問題を解決!
製造業必見!「BOM詳解」