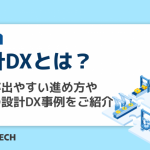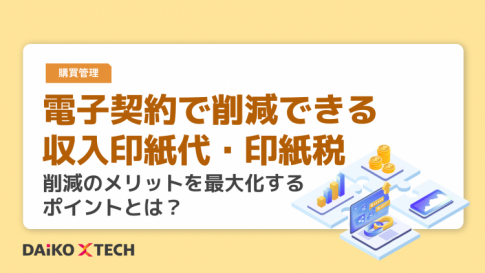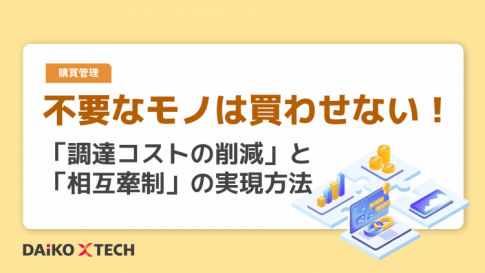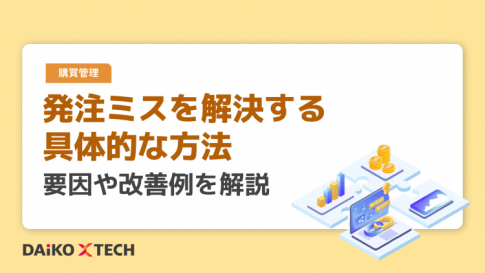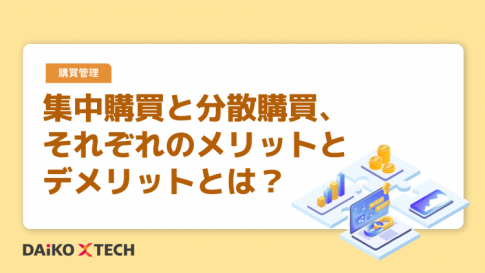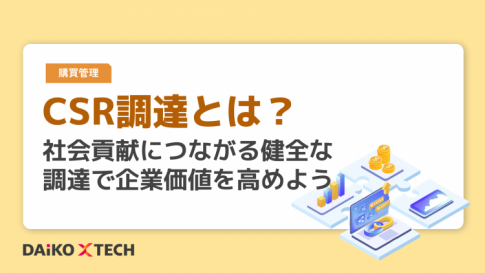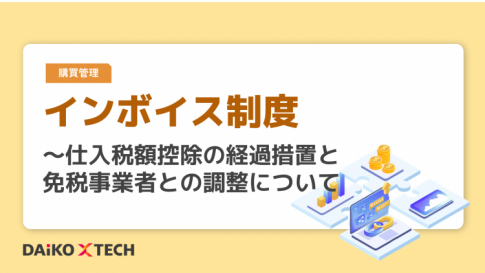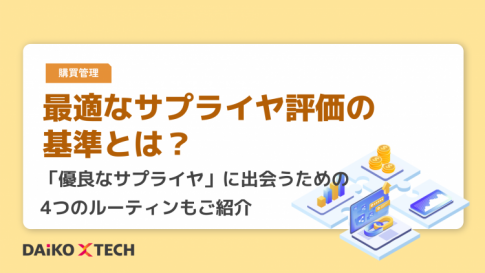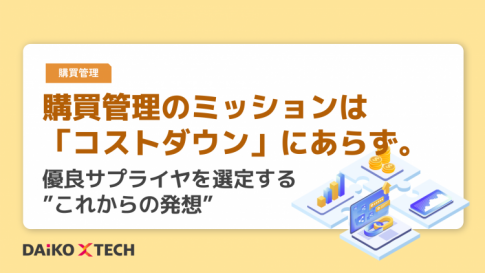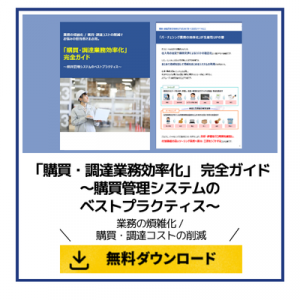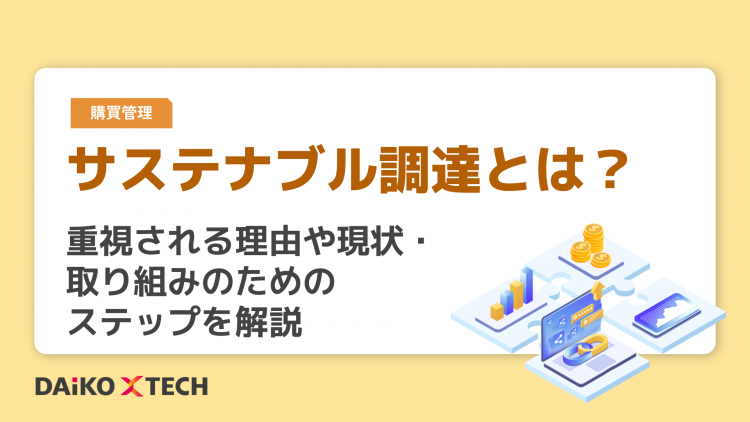
サステナブル調達とは、地球や未来を大切に考え、環境を守りながら豊かな社会を次世代へ引き継ぐために、調達活動で「持続可能性」を重視する取り組みのことです。
大企業での取り組みが進むとともに、サプライチェーンや仕入先となる中小企業へも行動規範が定められています。
本記事ではサステナブル調達の意義や重視される理由、事例などを通して現状や取り組みについてのステップも解説します。
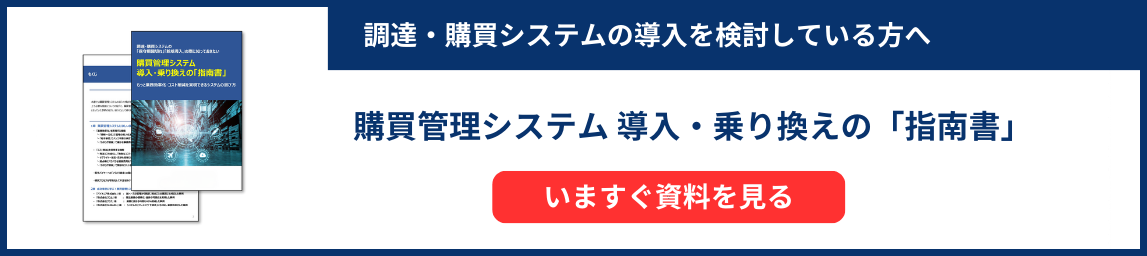
目次
サステナブル調達とは

モノづくり企業において、調達とは自社の製品・サービスに関する原材料や部品、付属品などを外部より購入し、入手する業務のことです。
本章では、地球環境や人権保護の観点から近年注目を集めるサステナブル調達について、用語の意味や成り立ちについて解説します。
さらに、他の調達の考え方であるものの類似点があり混同されやすい「グリーン調達」や「CSR調達」との違いについてもご紹介します。
サステナブル調達の概要
サステナブル調達とは、調達活動において環境や社会に配慮しながら地球環境を維持し、豊かな社会環境を持続させる取り組みのことです。
「サステナブル」の言葉のイメージから、エコ活動の一貫と誤解されることもありますが、サステナブル調達では地球環境だけでなく、人権の尊重も重視されます。
近年では、環境問題や労働問題が世界的に大きく取り上げられる傾向にあります。
具体的には、以下のような例が挙げられます。
- 環境破壊につながる製品を開発していた
- 製品自体には問題がなくても、原材料の乱獲により野生動物の減少につながっていた
- 著しい低賃金や児童労働によって成り立っている製品であった
これからのモノづくり企業には、自社製品が環境・人権を侵害していないかに注意しながらモノづくりを行うだけでなく、原材料が影響する環境問題やサプライチェーンの労働環境にも配慮する社会的責任があります。
グリーン調達との違い
グリーン調達とは、企業が調達活動をする上で、できる限り環境負荷の小さいものを優先的に選択する取り組みのことです。
環境に配慮した製品開発を行うことで、環境問題の改善へつながります。
サステナブル調達とグリーン調達の大きな違いは、対象です。
グリーン調達の対象は環境であるのに対し、サステナブル調達は環境問題への配慮だけでなく、労働環境・人権の保護による持続可能な社会環境を達成する点で違いがあります。
下記記事では、グリーン調達の仕組みや目的、実践するメリットについて解説していますので、ぜひご一読ください。
グリーン調達とは?環境に配慮した調達方法の基本から導入メリットまで解説
CSR調達との違い
次に、サステナブル調達の混同しやすいものとしてCSR調達との違いについて解説します。
CSR調達とは、人権問題や労働環境、環境への配慮の観点から調達先の選定を行うことです。
サステナブル調達とCSR調達の大きな違いは、目的です。
CSR調達の目的は、企業がCSR調達に取り組むことで社会貢献をして、消費者や株主・従業員からの信頼を得ることにあります。
一方で、サステナブル調達の目的はサプライチェーン全体での環境負荷を低減し、人権や労働問題を解決し持続可能なビジネス運営を確立する点で違いがあります。
下記記事では、CSR調達の概要や取り組みのメリットについて解説しています。
ぜひご一読ください。
CSR調達とは? 社会貢献につながる健全な調達で企業価値を高めよう
サステナブル調達が重視される理由

サステナブル調達は、大企業が自社のイメージのために取り組んでいる広告の代わりと誤った認識をされることがあります。
これは決して大企業に限ったことではなく、サプライチェーンの中で関わる企業すべてが意識的に取り組むべき課題です。
本章では、モノづくり企業がなぜサステナブル調達に取り組むべきなのか、サステナブル調達が重視される理由について解説します。
企業が社会的責任を果たす必要があるため
サステナブル調達が重視される理由の一つとして、企業は事業を行う際に社会的責任を果たす必要がある点が挙げられます。
事業活動を行うことで、地球環境が汚染されてしまったり、人権が無視されてしまったりするような労働環境となってしまうことのないように常に自社製品や製造過程、調達活動についても管理しなければなりません。
企業には主に以下の2つの果たすべき社会的責任があります。
- 環境問題に関する社会的責任
- 人権問題に関する社会的責任
以下で詳しく解説します。
環境問題に関する社会的責任
モノづくり企業において、環境問題に関する社会的責任には以下が挙げられます。
- 有害物質を使用して製造を行わない責任
- モノづくりを行う中で環境汚染の原因となる物質を排出しない責任
- 過剰な森林伐採や資源採掘により生態系に悪影響を与えない責任
製造過程において環境問題を考慮しながら、さらに消費者の使用過程でも環境問題につながらないようなモノづくりに留意する必要があります。
環境問題への取り組みとして一例を挙げると、Scope3排出量の開示が挙げられます。
Scope3とは温室効果ガスのうち、サプライチェーンで発生した間接的な温室効果ガスが該当します。
|
Scope1:事業者が燃料消費などにより直接排出された温室効果ガス Scope2:他社から供給された電気や熱・蒸気の使用により間接的に排出された温室効果ガス Scope3:Scope1、Scope2以外のサプライチェーンに属する他社により間接的に排出された温室効果ガス |
参考:サプライチェーン排出量全般 | グリーン・バリューチェーンプラットフォーム | 環境省
Scope3排出量については、サプライチェーンすべての調査が難しいこと、同意が得られないことなどから必ずしも開示するように定められたものではありません。
しかし、パリ協定で温室効果ガスの排出削減への努力が義務付けられ、企業版であるSBTでは、企業自身だけではなく、サプライチェーンを3つのScopeに分類し、各Scopeで削減目標の達成が求められています。
日本では、2025年1月時点で、SBT認定取得済みの企業が1,400社以上(うち中小企業は1,100社以上)となっています。
参考:排出量削減目標の設定 | グリーン・バリューチェーンプラットフォーム | 環境省
上記で挙げたSBTのように、環境問題に関する社会的責任は決して大企業に限ったものではなく、サプライチェーンとしてモノづくりに関わる中小企業も重視し、環境問題に取り組まなければならない重要な責任があります。
人権問題に関する社会的責任
人権問題に関する社会的責任には、具体的には以下のような例が挙げられます。
- 途上国での強制労働や児童労働を伴わない企業活動を行う責任
- 差別やハラスメントを防止する責任
- 劣悪な労働環境や労働条件で従業員を従事させない責任
国連人権理事会が2011年に制定した「ビジネスと人権に関する指導原則」によると、自社内部だけでなく、バリューチェーン全体で発生する人権リスクにも対応する責任が言及されています。
バリューチェーンとは、企業の事業活動を価値創造のための一連の流れとして考えることで、対象範囲はサプライチェーンと同様です。
人権問題に関しても、自社だけで取り組む課題ではなく、サプライチェーン全体で取り組む責任があることが示されています。
企業がサプライチェーン全体で、事業における人権リスクの防止や軽減策を講じ、取り組みの実効性や対処方法について情報開示する一連の行動を人権デューディリジェンスと言います。
ヨーロッパで特に進んでおり、日本でも、2020年には「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」が策定されました。
また、2020年には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が策定され、国としても人権を尊重する取り組みを促進しています。
さらに、時代の変化に伴って、守るべき人権は広がっています。
具体的には以下のような例が挙げられます。
- ジェンダーに関する人権
- プライバシーに関する人権
- 消費者の安全に関する人権
上記から、モノづくり企業においても、自社だけでなくサプライチェーン全体で慎重に人権問題に取り組む社会的責任があります。
参考:
ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために(A/HRC/17/31)
法務省:「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)について
「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」を公表しました
経営上のリスクを避けるため
サステナブル調達が重視される背景には、経営上のリスクを避けるためといった理由も挙げられます。
モノづくり企業に限らず、ミスや大きな問題が発覚した際には世間から厳しい評価や追求を受けるだけでなく、以降の取引や株価にも悪影響を及ぼします。
サステナブル調達を行わずに環境問題や人権侵害が発覚した場合には、以下のようなリスクが想定されます。
- 不買運動につながるリスク
- 投資先からの低評価につながるリスク
以降で解説します。
不買運動につながるリスク
サステナブル調達を行わずに環境問題や人権侵害が発覚した場合には、消費者からの不買運動につながるリスクがあります。
海外では、不買運動が起きなかった場合の売上予測をしたところ、日本円で約1兆円を超える売上の喪失であったケースも存在します。
投資先からの低評価につながるリスク
サステナブル調達を行わずに環境問題や人権侵害が発覚した場合には、投資先から評価されずに十分な資金を獲得できないリスクもあります。
投資家の投資基準の一つに、ESG投資の考え方があります。
ESGとは、環境・社会・ガバナンスの頭文字から取ったものです。
投資の際に財務面だけでなく環境・社会・ガバナンスといったサステナビリティの観点で企業を分析・評価を行い、高評価の企業へ投資を行います。
また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に関する情報開示も投資基準として注目されています。
TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の頭文字を取っており、金融安定理事会(FSB)により設置されました。
2017年に、企業が年次の財務報告において財務に影響のある気候関連情報の開示を推奨する報告書を出しています。
TCFD提言への賛同は、投資家からの評価基準としても重視されているため、大企業の取り組みが増加しました。
なお、TCFDは2023年10月に解散し、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)へ統合され役割が引き継がれています。
企業においても、投資家から評価されるために収益を上げることは当然として、投資家から評価を得るためにも、健全で持続可能な発展を目指す経営を進めていく必要があります。
企業が価値を向上させつつ持続的に成長するため
また、サステナブル調達が重視される理由には、企業の価値向上と持続的な成長をするためといった理由もあります。
モノづくり企業は、原材料や部品を加工して製品を作り出すプロセスであり、原材料となる資源は有限です。
地球環境や生態系を脅かすことで、結果的に原材料の調達ができなくなり、事業継続が困難になってしまうことも想定されます。
人権問題を無視して従業員を過重労働させ、従業員からの信頼を失い退職者が続出してしまうリスクもあります。
また、過重労働や途上国での強制労働のような人権侵害は、発注側が自社の利益ばかりを考え、低価格での調達を暗に強要していることも一因です。
原材料の価格には適切な理由があるか、違法な労働や人権侵害から得られたものでないか、調達時にしっかりと調査しなければなりません。
持続可能なモノづくりを促進しサステナブル調達を行えば、健全な企業として価値を高め、持続的な成長へとつながります。
サステナブル調達への取り組みのためのステップとは
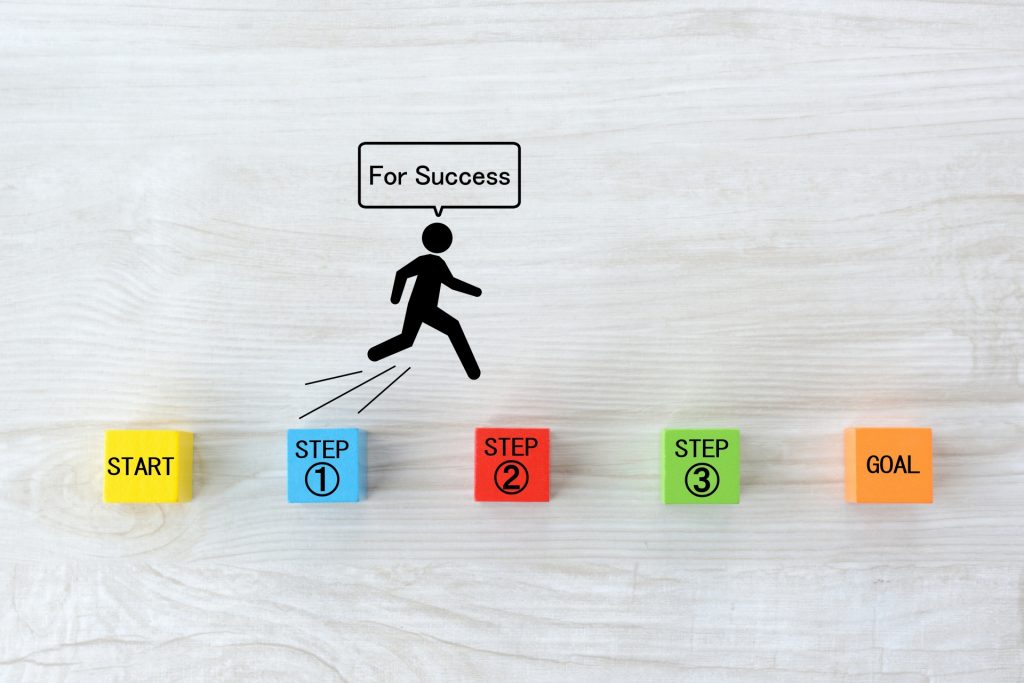
サステナブル調達は、自社だけの問題で済む取り組みではなく、仕入先や取引相手への調査や協力依頼をしなければ成り立ちません。
しかし、始めようと思っても現在の生産体制や仕入先との関係性から、どう始めていくべきか悩ましい問題でもあります。
本章では、どうすれば効果的に進められるのか、サステナブル調達への取り組みのためのステップをご紹介します。
調達方針を策定する
まずは、企業のトップである経営者と調達部門が中心となり、調達方針を策定する必要があります。
コストや納期などの要件だけではなく、人権の尊重・環境への配慮などのサステナブル調達につながる項目を含んだ方針を作成します。
具体的には、以下のような項目に対して調達方針を明らかにしておくと良いです。
- 人権の尊重
- 労働環境の整備
- 環境への配慮
- 品質や安全の確保
- 公正・適正な取引
- 情報管理と適切な開示
自社の製品やサービスに応じてどのような方針で調達を行うのか、取り組み内容などを検討して策定します。
また、調達方針は一般消費者や株主に対してもすぐに確認できるように公表しておくことが望ましいです。
近年では策定したサステナブル調達方針を企業のwebページ上で公表している企業が多く見られるため、同業他社の公表している内容を参考にして策定するのもおすすめです。
人権に関する評価を行う
次に、現在ではビジネスと人権の問題は発覚すると大きな影響があるため、事業活動を行う中であらゆる人権侵害の可能性を分析して評価しなければなりません。
2022年9月には、日本政府のガイドラインとして「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が、決定されています。
同ガイドラインによると、企業による人権尊重の取り組みの全体像が以下のように示されています。
- 人権尊重方針
- 人権尊重責任に関するコミットメント(約束) の表明
- 人権DD(デューディリジェンス)
- 負の影響の特定・評価
- 負の影響の防止・軽減
- 取り組みの実効性の評価
- 説明・情報開示
- 救済
- 負の影響への対応
上記の「負の影響」については、3つの類型があります。
|
cause |
企業自ら引き起こす |
|
contribute |
直接・間接に助長する |
|
directly linked |
自社の事業・製品・サービスと直接関連する |
自ら引き起こす影響はもちろん、間接的に助長するものや、自社製品やサービスに直接関連するものと、影響範囲が幅広く設定されていることに注意が必要です。
参考:責任あるサプライチェーン等における 人権尊重のためのガイドライン
また、人権の内容については、国連人権憲章や「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」に挙げられた基本的な権利に関する原則の内容を遵守する他に、具体的に以下の内容も示されています。
- 強制労働や児童労働に服さない自由
- 結社の自由
- 団体交渉権
- 雇用及び職業における差別からの自由
- 居住移転の自由
- 人種、障害の有無、宗教、社会的出身、性別・ジェンダーによる差別からの自由
また、人権の保護が弱い国や地域において、人権への負の影響の深刻度が高い強制労働や児童労働等には特に留意が必要であることが明記されています。
自社の事業活動が人権に負の影響を与えないか、上記を参考にしながら分析・評価し、人権侵害とならないような予防策を講じましょう。
社員教育や研修を行う
サステナブル調達は、調達部門だけが取り組むべき問題ではありません。
開発部門や品質保証に関わる部署など、あらゆる部門の社員が取り組まなければならない課題です。
サステナブル調達に関する知識を持っていないと、社内での反発や疑念が出てしまったり、調達方針を理解していない部門が判断を誤ってしまったりする危険性もあります。
よって、関わる部門の従業員に対しては、サステナブル調達の基本的な考え方や必要性に関する理解を促さなければなりません。
具体的には、社員のサステナビリティ意識向上の方法として、研修の実施が有効です。
サステナビリティ全体の教育に関しては、外部の研修やeラーニング教材を活用すると良いでしょう。
自社のサステナブル調達方針に関しては、調達部門などが主導し自社での研修や教育を行います。
モノづくり企業では、製造部門が常に稼働していることもありなかなか集合教育を行う時間が取りづらいことが考えられます。自社教材として動画化し、個人が自身の業務の隙間時間に学習できるようにするのもおすすめです。
社内の環境・制度の整備を行う
サステナブル調達を実施するために、社内の環境・制度の整備を行うことも重要です。
特に人権の面では、自社の制度が整備されていないことが原因で発生する場合も多くあります。
長時間労働や劣悪な労働環境を助長するような制度が放置されていることで、従業員に人権意識が醸成されずに、調達時にもサステナビリティを軽視した判断をしてしまう可能性もあるでしょう。
例を挙げると、納期が間に合いそうになければ深夜や休日に工場を稼働させるのが当たり前になっている企業担当者が、仕入先に対して現実的には無理な納期を強要したり、仕入先の利益にならないような低価格での販売を要求したりするケースです。
サステナブル調達を策定するに当たっては、自社の制度も見直し、時代やサステナビリティに則していない制度は改良していくことが重要です。
仕入先・取引先へも調査・対応を行う
前述したように、サステナブル調達はサプライチェーン全体を対象範囲としているため、自社だけが取り組みをして解決するものではありません。
仕入先や関連する取引先にも、自社が策定した方針や対策を共有し、調査・対応を行います。
しかし、Excelで回答フォーマットを作成し、大量の調査と回答をさせることで仕入先や取引先の業務負荷を上げてしまい、改善までたどりつかないケースも散見されます。
仕入先だけに負担をかけないように、仕入先へ説明会の開催や、評価機能のある購買システムへの乗り換えも検討しましょう。
モニタリングを実施する
調達方針は現状の調査や評価、公表も重要ですが、方針に則った調達がなされているか継続的にモニタリングを実施しましょう。
定期的なモニタリングを実施し、基準に達していない仕入先や取引先があった場合には、早急に状況の改善や是正の依頼を行います。
仕入先や取引先と連携しながらサステナブル調達に継続的に取り組めば、効果も高まり、株主や顧客からの評価の向上が期待できます。
サステナブル調達成功のポイント

次に、サステナブル調達を成功させるためのポイントをご紹介します。
サステナブル調達を策定しただけで、社内外のチェックシートへの回答を行うだけの単純作業になり、形骸化しているケースも見受けられます。
本章では、形骸化しないためのポイントとして、システムの見直し・社内での意識向上・認証取得の3点について解説します。
購買システムの導入・見直し
サステナブル調達を成功させるポイントの一つとして、購買システムの導入や見直しが挙げられます。
調達部門で購入履歴や仕入先情報をExcelで管理している場合には、調査だけでも多くの手間と時間を要してしまいます。
購買システムを導入すれば、現在の仕入先情報の調査がスムーズです。
新規調達の際にも、システム上で情報管理を行うことで購入プロセスを一元管理して、選定状況を見える化できます。
また、定期的にサステナブル調達方針を満たしているかモニタリングを行う際にも、購買システムを活用し、情報をシステム上に蓄積し活用していくことが重要です。
社内全体でサスティナビリティの意識を向上させる
次に、社内全体でサスティナビリティの意識向上を図ることもポイントです。
前述の通り、サスティナビリティに関する問題が発覚すると、サプライチェーン全体の責任を問われるケースが見受けられます。
調達部門だけでなく、事業に関わるすべての部署の従業員がサステナビリティのリスクをしっかりと理解しておかなければなりません。
SDGsの17個の目標を伝えるだけではなく、本質的な教育を行い社内全体の意識向上に努めることが大切です。
ISO 20400の認証取得
ISO 20400の認証を取得するのもサステナブル調達成功のポイントの一つです。
ISOの認証取得には手間と時間が掛かるイメージがありますが、ISO 20400は「ガイダンス規格」の位置付けです。
以下で詳しく解説します。
ISO 20400の概要と認証取得の効果
ISO 20400は、「持続可能な調達の手引」として企業の調達プロセスにはQCDだけではなく、環境、社会、経済的問題に対応するためにSDGsへの貢献も重要な要素であるとの考えの元、2017年に発行されました。
日本科学技術連盟によると持続可能な開発とは、以下のように示されています。
「持続可能な調達」とは、調達方針及び慣行に持続可能性を統合し、組織のライフサイクル全体にわたる、「生産性の改善」「価値及びパフォーマンスの評価」「購入者・サプライヤー及び全てのステークホルダー間のより良好なコミュニケーション」を可能にすることで、環境、社会、経済的課題への取り組みと会社業績の両面で成果を生みだす調達の考え方です。
引用:ISO 20400 | 日本科学技術連盟(JUSE-ISO Center)
ISO 20400は「ガイダンス規格」に位置する規格ですが、2022年4月より日本科学技術連盟のプライベート認証として認証を開始しています。
認証取得には、以下のような効果が期待できます。
- 既存のマネジメントシステム(ISO 9001やISO 14001、ISO 22000)を活用し持続可能な調達に取り組める
- 株主や取引先等のステークホルダーに対しSDGsやサステナビリティの取り組み姿勢を示せる
- 調達における手順を明確にし、調達のリスク管理を推進できる
ISO 26000との違い
ISO 20400は、2010年に発行されたISO 26000「社会的責任に関する手引」を補完し、企業や団体が、調達を通じて持続可能な発展に貢献するための指針として位置づけられています。
ISO 26000との大きな違いは、原則部分の追加事項です。
ISO20400には、6つの原則が追加されています。
具体的には、以下の赤字の項目が変更及び追加されました。
- 説明責任
- 透明性
- 倫理的な行動
- 完全かつ公平な機会
- ステークホルダーの利害の尊重
- 法の支配及び国際行動規範の尊重
- 人権の尊重
- 革新的な解決策
- ニーズへの焦点
- 統合
- 全費用の分析
- 継続的改善
今までの原則では、「尊重して事業を行う」部分が原則であったのに対して、ISO 20400では事業内容を分析し、問題がある場合には解決に向けて行動を起こし、継続的に改善をするプロセスが組み込まれていることがわかります。
ISO 20400の審査方法
前述の通りISO 20400は「ガイダンス規格」ですが、2022年4月より日本科学技術連盟のプライベート認証として認証を開始しています。
日本科学技術連盟によると、主に以下のような点で審査を行っています。
審査の考え方
- 審査対象範囲は、組織が指定した「品目」、「部門」によって定める
- 審査工数は、審査対象となる「品目数」や「調達に関するリスク」を評価し算出する
- 審査場所は、「本社」または「調達部門を管理しているサイト」で実施する
審査でのチェックポイント
- バリューチェーン、またはサプライチェーンの中で持続可能な調達の中核主題(箇条4.3 項)を考慮してリスクを特定しているか
- 法規制、組織が適用を定めたガイドラインを網羅しているか
引用:ISO 20400 | 日本科学技術連盟(JUSE-ISO Center)
サステナブル調達を行う企業の例
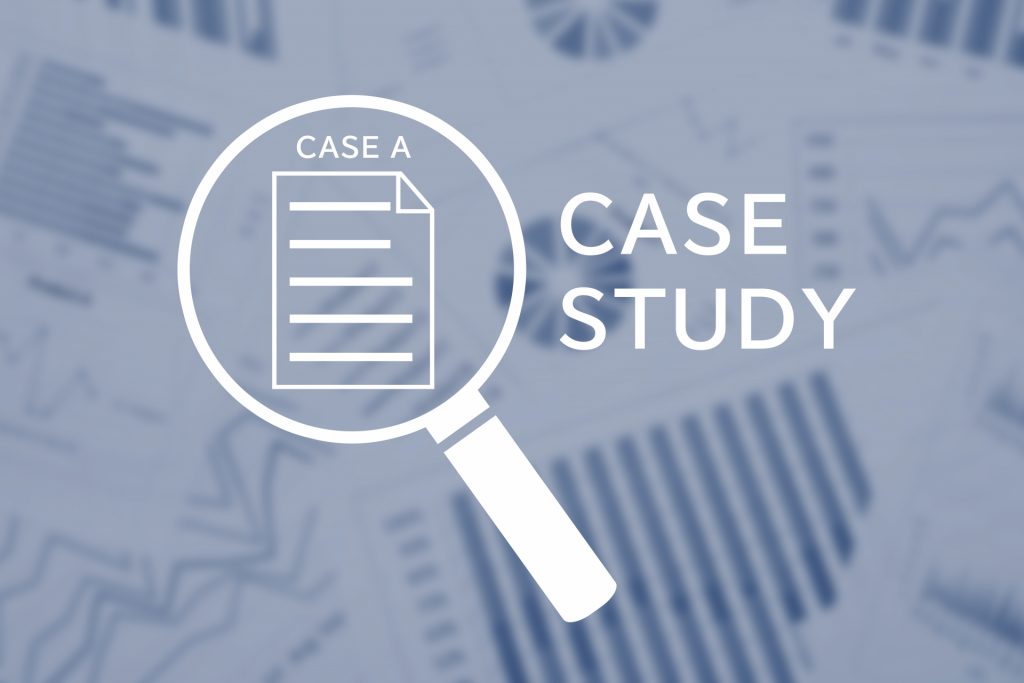
本章では、サステナブル調達を行う企業の事例をご紹介します。
【事例】サプライヤガイドラインを策定し、サステナブル調達を実現している企業の事例
某大手飲料メーカーでは、サステナブル調達を実践するために6つのサステナブル調達基本方針を策定し、関連グループだけでなく、取引先に対しても周知と理解を求める取り組みを行っています。
サステナブル調達方針を推進するために調達開発推進部を設立、サステナビリティ経営推進本部と連携し、サステナブル調達に取り組んでいます。
国内外の仕入先に対して人権・法令遵守・環境等の具体的な遵守事項で構成されたサプライヤガイドラインを制定しました。
サプライチェーン全体で同じ倫理的価値観を共有し、サステナブル調達を実施しています。
【事例】パーム油の調達においてRSPO認証を基準としてサステナブル調達を実現している企業の事例
某大手食品メーカーでは、持続可能なパーム油調達の実現に取り組んでいます。
パーム油は、近年ではパーム農園での森林破壊や人権侵害等の問題との関連性が指摘されています。
持続可能なパーム油を調達するため、具体的に以下の方向性を示しています。
RSPOが定める原則と基準(Principle and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2013)を尊重し、持続可能と認められるパーム油製品を調達し、加えて以下の項目も条件として公表しています。
- 保全価値の高い地域(HCV)を保護している
- 既存のプランテーションの管理を含む、新しい植栽、再植え付け、またはその他の開発の準備に火を用いていない
- 世界人権宣言を支持し、労働者の人権を尊重する
- 植林地の開発の際には先住民族および地域社会の意向を尊重し、公正な苦情処理を行う
- 高炭素ストック(HCS)の森林を保護している
- 新たな泥炭地の開墾を行わない
サステナブル調達に取り組み、持続可能性に配慮しながら企業の価値を高める

本記事では、サステナブル調達について、概要や類似する調達の考え方の違い、取り組みのステップやポイントを解説してきました。
サステナブル調達は、SDGsへの意識が高まっている中、無視したままでは事業の成長は見込めません。
また、決して大企業だけの問題ではなく、サプライチェーン全体で取り組むべき課題であることを意識しましょう。
モノづくり企業においても、サステナブル調達方針を策定し、対策や改善を進めていくことで株主や取引先からの信頼を高めて企業としての継続的な成長につながります。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓