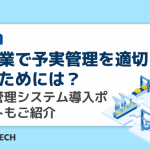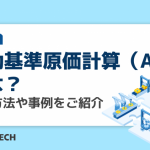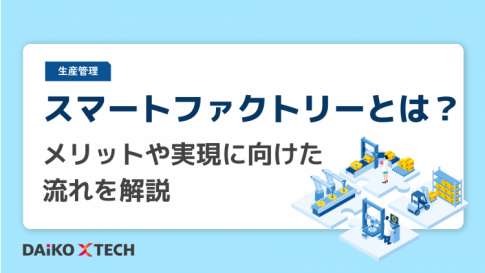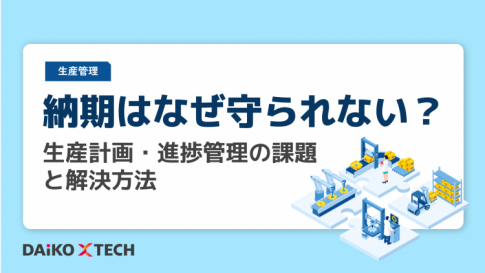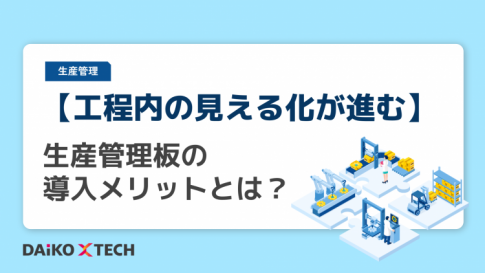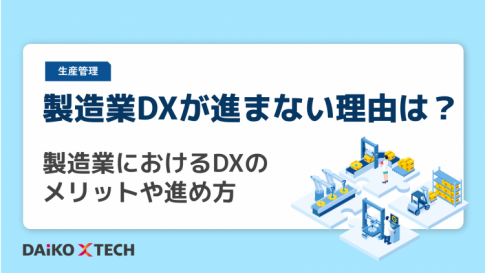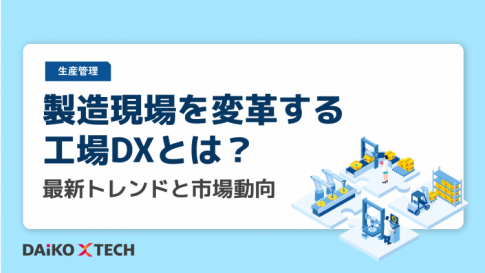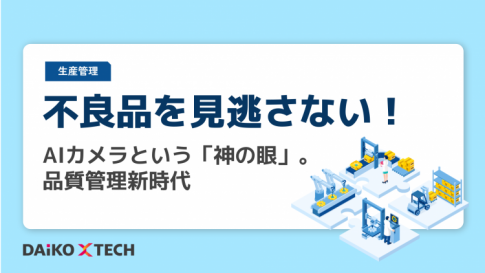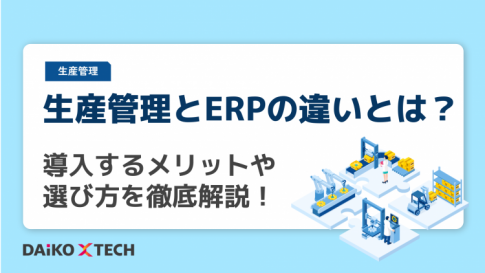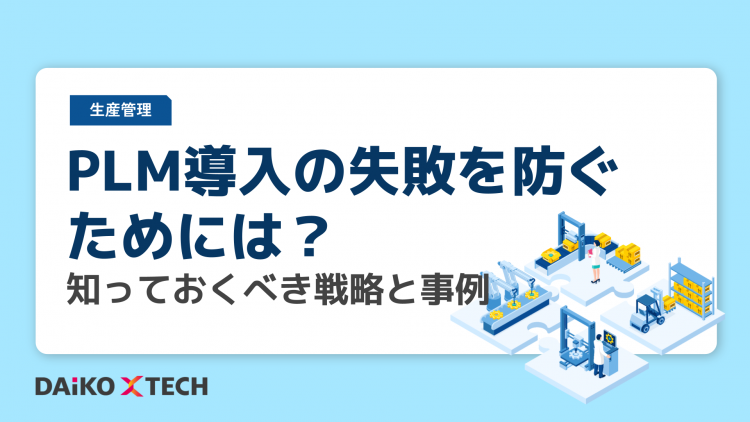
製造業でPLMの導入を検討する企業は少なくありません。しかし現実には、導入が思うように進まず失敗に終わるケースも数多く報告されています。その理由は、システム性能が低いことが原因ではなく、戦略や運用、人材面での準備不足が大きな要因です。
本記事では、よくある失敗の原因と具体的な事例、さらに成功につなげるための戦略や最新動向を紹介します。失敗から学び、前向きに導入を進めるヒントにしていただければ幸いです。
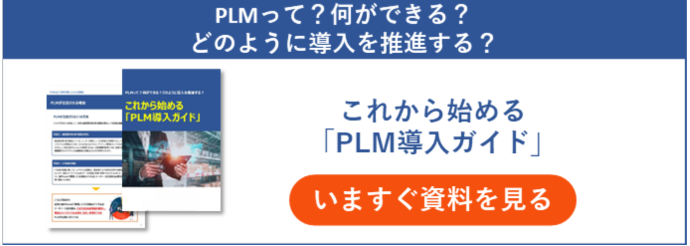
目次
PLMとは

PLMは「Product Lifecycle Management(製品ライフサイクル管理)」の略で、製品が誕生してから廃棄に至るまでの全ライフサイクルを一元的に管理する仕組みです。企画、設計、製造、販売、保守までの各段階をデータでつなぎ、部門を跨いでの経営資源の統合管理に強みを持ち情報共有を可能にします。
ERPが経営資源の管理に強みを持ち、PDMが設計データの管理に特化しているのに対し、PLMはもっと広範囲をカバーします。製品の情報を軸に業務全体をつなげることで、開発スピードの短縮、コスト削減、品質向上の実現が可能です。
つまり、PLMは設計部門が使うシステムではなく、製品戦略全体を支える基盤といえるでしょう。
詳しくは以下の記事も参考にしてください。
PLMシステムとは?導入のメリットと選び方、PDMとの違いについて
PLM導入で失敗が起きやすい理由

PLM導入が思うように成果を出せない背景には、いくつかの共通点があります。特に多いのは、PLMの本質を理解しないままシステムだけを入れてしまうこと、経営戦略と切り離して考えてしまうこと、そして現場との温度差です。
一見小さなすれ違いに見えても、導入後の定着や効果を大きく左右します。以下でそれぞれの失敗要因を掘り下げていきます。
PLMとは何かを正しく理解していない
PLM導入の失敗で最も多いのは、そもそもPLMの本質を正しく理解していないケースです。経営層やIT部門が、新しいシステムを入れれば業務が自動的に効率化すると短絡的に考えれば、現場での混乱は避けられません。
PLMは単なるソフトウェアではなく、業務フローや部門間の連携そのものを見直すものです。従来のやり方を残したまま導入すれば、現場からは使いづらい、手間が増えたと不満が出て、むしろ効率が落ちる場合があります。
背景にあるのは、システム=効率化ツールという思い込みです。ERPやPDMと同じ延長線上でPLMを理解してしまうと、対象範囲の広さや変革の必要性を見落とします。その結果、導入前の期待とのギャップに直面します。PLMを検討する段階で、その役割と効果を正しく理解することが成功の第一歩です。
以下の記事でも詳しく解説しています。
PLMシステムとは?導入のメリットと選び方、PDMとの違いについて
経営戦略とPLMが結びついていない
PLMが失敗に終わるもう一つの典型は、経営戦略と切り離されて導入される点です。経営層が単なるシステム刷新としてしか認識していない場合、プロジェクトはIT部門や現場に丸投げされがちです。そうなると、システムは導入されても経営成果につながらず、形骸化してしまいます。
PLMは単なるコスト削減の道具ではなく、製品競争力を高める経営基盤です。市場投入までのリードタイムを短縮したり、品質を安定させたりすることで、企業全体の競争優位性を強化します。
戦略と切り離して導入すれば、投資したのに成果が見えないという結果に終わります。逆に言えば、経営戦略の中で、PLMで何を実現するのかを定義すれば、プロジェクトは方向性を失わずに進みます。
現場部門との温度差
PLMプロジェクトが失敗する要因には、現場との温度差もあります。IT部門や経営層が効率化できるはずと考えていても、現場からすれば日々の仕事が複雑になるだけと感じる場合があります。
現場との温度差が埋まらないと、システムは導入されても現場で使われず、形だけの存在になりかねません。特にPLMは部門横断で利用するシステムなので、現場の理解と協力なしには定着不可能です。
解決には、導入目的や期待される効果を現場に丁寧に伝え、意見を吸い上げることが必要です。現場が自分たちの課題解決につながると納得すれば、協力的に活用してくれます。
PLM導入の本質はシステム導入ではなく、全社の仕組み改革であり、その中心に現場の意識変化があります。
PLM導入で実際にあったよくある失敗の原因

PLM導入が失敗に終わる背景には、単なる誤操作やシステム不具合だけでなく、組織全体の取り組み方に根本的な問題が潜んでいます。要件定義の不十分さや過度なカスタマイズ、教育不足による現場の不安、部門ごとに異なるデータ管理などは、実際に多くの企業が直面してきた落とし穴です。
ここからは、製造業でよく見られる失敗のパターンを具体例とともに紹介し、そこから導き出せる教訓を整理します。
要件定義の不備からカスタマイズ地獄に陥った例
ある製造業の企業では、導入当初からまずはシステムを入れてから調整すればいいという考え方が根強く、要件定義が曖昧なままプロジェクトが始まりました。
最初は標準機能で十分としていたものの、各部門から次々と「この機能が欲しい」「従来のやり方を残したい」といった要望が上がります。結果として、カスタマイズが雪だるま式に増え、プロジェクトは収拾がつかなくなりました。
初期の段階では、現場の声を聞くこと自体は重要です。しかし要件を明確に整理せず、全部取り込む方向で進めてしまうと、システムは肥大化します。さらにカスタマイズを繰り返すたびに保守コストが増加し、担当者も修正箇所が把握できない状態に陥ります。
最終的に、導入したはずのPLMが業務効率化どころか新たな負担となり、現場に敬遠される事態を招きました。
教育不足でシステムが使われなかった例
別の企業では、PLMを導入したものの、現場社員がシステムを十分に理解できず、結局Excelに戻ってしまいました。導入初期にはベンダーによる操作説明会が一度開かれましたが、その後フォローがなく、日常業務で困ったときに相談できる窓口もありませんでした。
こうした環境では、現場社員にとってPLMはよく分からない新しい仕組みであり、業務効率化につながると実感できません。そのため、慣れているExcelの方が早いという判断に流れてしまいます。特に熟練社員ほど従来のやり方に戻したいという気持ちが強く、若手社員の中にも使いづらいと感じる人が増えていきました。
教育不足が原因で定着しないケースでは、システムそのものの評価が下がり、高い投資をしても意味がなかったという結論になりがちです。つまり、教育は単なるオプションではなく、導入成功のために必要不可欠なフェーズです。
部門間でデータ定義がバラバラだった例
PLMを導入するうえで、部門ごとのデータ定義の違いは大きな障壁です。
ある企業では、設計部門と生産部門で部品番号の付け方が異なっており、同じ部品でも異なるコードで登録されていました。設計が部品Aを使用と指示しても、生産側のデータベースには部品Xとして管理されているため、発注が遅れたり在庫が重複したりする事態が頻発しました。
さらに、この不一致を修正するために、わざわざ人手で突き合わせ作業を行う必要があり、本来の目的である効率化からは程遠い状況になっています。データ定義を統一しないままPLMを導入すれば、システムが混乱を増幅しただけとなりかねません。こうした失敗は、導入前に共通のデータルールを整備していなかったことに起因しています。
PLM導入を成功に導く戦略

失敗の背景を理解したら、次に考えるべきは、ではどうすれば成功できるのかという視点です。PLMはシステム導入で完結するものではなく、経営の方向性や現場の運用と一体になって初めて効果を発揮します。
ここでは、経営戦略との接続、段階的な導入の2つの観点から、PLMを成功に導くための実践的な戦略を解説します。
経営戦略との接続
PLMを成功させるためには、まず経営戦略と直結させることが欠かせません。単にシステムを導入して効率化するといった短期的な視点ではなく、企業全体の競争力を高めるという長期的な目標を設定する必要があります。
例えば、PLMを通じて開発リードタイムの30%短縮を目標に掲げるとします。これにより、新製品を競合よりも早く市場投入できる体制を築くことが可能です。また、不具合率を一定割合削減するという目標を立てれば、顧客満足度の向上にも直結します。
重要なのは、これらの目標をKPI(重要業績評価指標)として明確化し、経営層から現場まで共有する点です。ROI(投資対効果)だけを追い求めるのではなく、製品競争力や顧客価値という観点を取り入れることで、PLMは経営の武器として機能します。
段階的な導入アプローチ
PLMを全社一斉に導入するのはリスクが高く、多額の投資が無駄になる恐れもあります。そのため、段階的導入が成功のカギです。
まずはPoC(Proof of Concept:概念実証)を行い、小規模な範囲でシステムが本当に効果を発揮するのかを確認します。その後、設計部門など影響範囲が限定的な部署に導入し、実績を積み重ねながら次のフェーズへと広げていきます。成功体験の積み上げが、現場の協力を得る最大の武器です。
段階的導入のメリットは、失敗しても影響範囲を限定できる点にもあります。小さな範囲での課題を解決してから拡大することで、全社導入時にはリスクが最小化され、導入スピードも速くなります。
PLM導入の最新動向と成功事例から学ぶ

PLMはかつて、設計情報を一元管理するためのシステムとして導入されるのが一般的でした。しかし近年はクラウド化やAI活用、サステナビリティ対応との結びつきなど、新しい流行が生まれています。
単なるITツールではなく、経営戦略や社会的責任と連動する経営基盤へと進化している点は注目ポイントです。ここでは、最新のトレンドと国内外の成功事例から、これからPLM導入を検討する企業が学ぶべきポイントを整理します。
クラウド化・AI化が進むPLMの最新トレンド
PLMの最新トレンドとして注目されるのが、クラウド化とAI活用です。クラウド型PLMは、従来のオンプレミス型に比べて初期投資が小さく、利用規模に応じた柔軟な料金体系を採用できるため、中堅企業でも導入しやすくなっています。
また、クラウド環境はセキュリティ面でも強化されており、アクセス権限管理やデータ暗号化、バックアップ体制の自動化によって安心して利用できます。リモートワークの普及により、地理的に離れた拠点同士でもリアルタイムに情報を共有できるのも大きなメリットです。
AIの導入も急速に進んでいます。設計段階では過去の設計データを分析し、最適な設計案を提案する設計支援AIの登場が代表的です。生産現場では、需要予測や在庫管理をAIが行うことで、余剰在庫や部品不足を未然に防ぐ仕組みも広がっています。
保守分野では、センサー情報とAIを組み合わせて、故障の兆候を事前に検知し、予防保守を実現する取り組みも進んでいます。
注目すべき国内外の成功事例
実際の成功事例を見ても、共通点があります。
ある大手メーカーでは、設計と生産でバラバラに管理されていた部品情報を統合し、BOM(部品表)の一元管理を実現しました。その結果、設計変更が即座に生産に反映され、納期短縮とコスト削減に結びついています。
また、別の企業ではスモールスタートを徹底し、まず一部門だけでPLMを試験導入しました。小さな成功体験を積み重ねたことで社内の理解が進み、やがて全社的な展開につながっています。
海外の事例では、PLMを通じてサプライチェーン全体のデータを統合し、持続可能性や環境対応の改善まで視野に入れた運用を進めています。
これらの事例に共通するのは、システムありきではなく、経営課題や現場の不満を解消するための手段としてPLMを位置づけている点です。
今後の導入に向けたチェックリスト
これからPLM導入を検討する企業が失敗を避けるためには、事前準備が欠かせません。
- クラウドやAIに対応できる製品を選べるかどうか
- 段階的に導入を進められる仕組みを整えているか
- 現場を巻き込んだ体制を築けているか
- データ統合のルールを確立しているか
以上の点を導入前に点検しておくと、システムが形骸化するリスクを大幅に下げられます。最新動向や成功事例を踏まえたチェックを行えば、自社に合った現実的なロードマップを描けます。
失敗から学び前向きにPLM導入を検討しよう

PLM導入における失敗は、決して珍しいものではありません。要件定義の不備、教育不足、データの不統一など、多くの企業が同じ壁にぶつかっています。
しかし重要なのは、失敗を恐れて立ち止まることではなく、失敗から学び次につなげる姿勢です。PLMは単なるIT投資ではなく経営戦略の実現手段としてとらえ、前向きに取り組んでください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
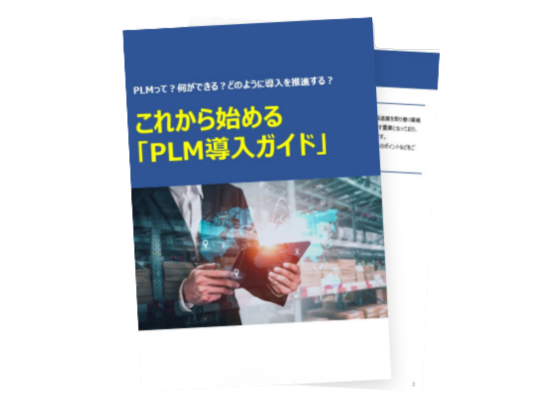
PLMって?何ができる? どのように導入を推進する?
これから始める 「PLM導入ガイド」