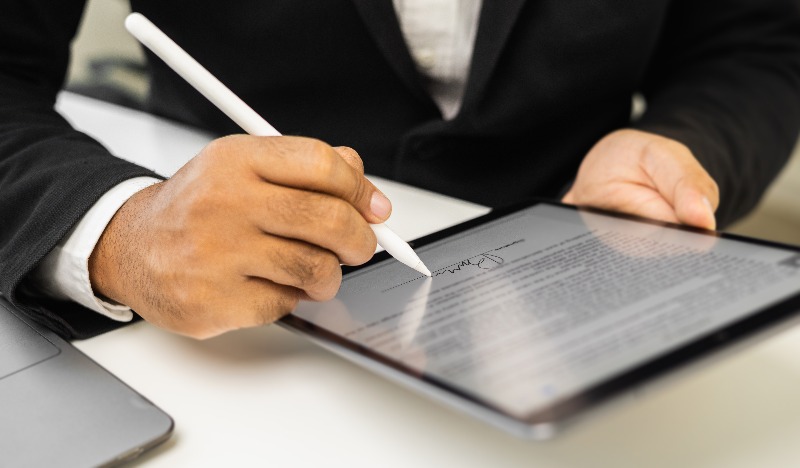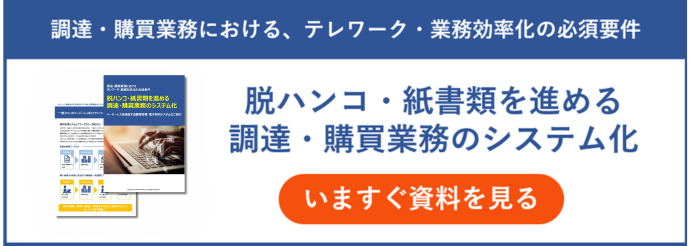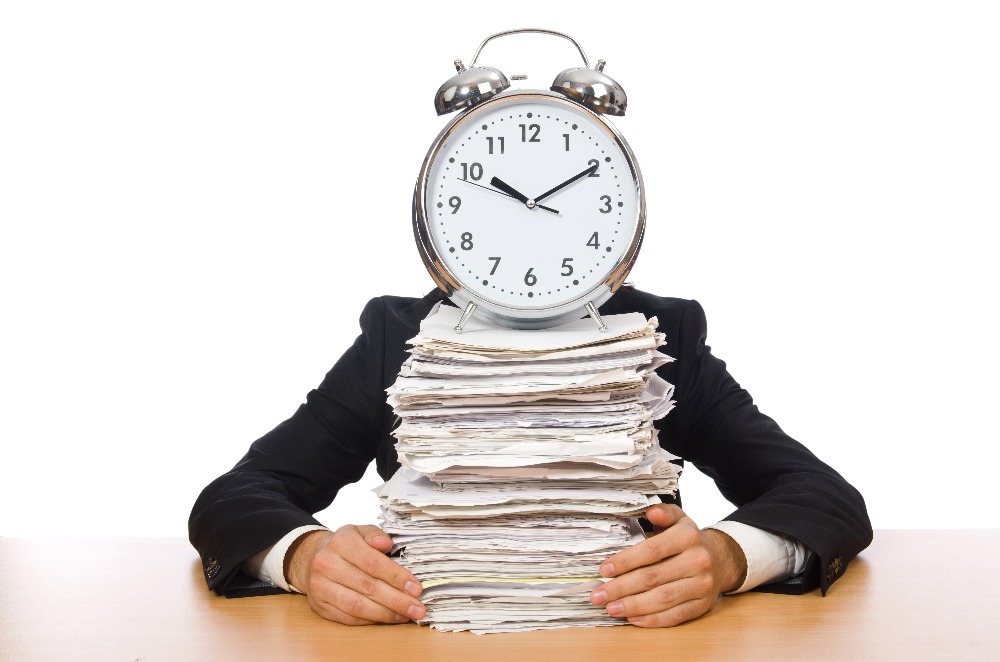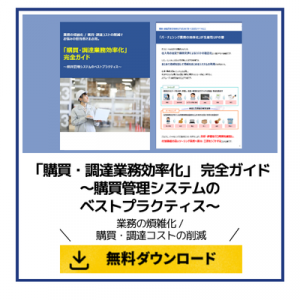建設業法の改正により、建設業界にも電子化の流れが訪れています。電子化を進めることで、業務効率化やコスト削減などさまざまなメリットがありますが、建設業においての電子化にはいくつか注意しておかなければならない点もあります。本記事では、建設業界における電子化のメリットや、電子化サービス導入の注意点についてご紹介します。
目次
昨今の建設業界における電子化の流れ
建設業では長らく書面での工事請負契約が義務化されていましたが、2001年4月に建設業法第19条が改正されたことで、書面化の義務が撤廃されました。
これにより、工事請負契約書の電子化と電子契約が可能となり、建設業でも電子契約を導入する企業が出てきました。しかし、2001年の建設業法改正以降、電子化を後押しするような動きはなく、建設業の電子化は進んでいるとは言えない状況です。
しかし昨今、建設業の電子化に向けた新たな変化が訪れています。本章では、建設業に訪れた新たな動きについてご紹介します。
2020年に働き方改革や生産性の向上への対応に向け建設業法が改正
業務の効率化や作業員への負担の低減が求められる中、2020年に働き方改革や生産性向上へ対応するため、建設業法が改正されました。
2020年の改正は、著しく短い工期での契約締結が禁止されたり、社会保険への加入が義務化されたりするなど、働き方改革を促す内容です。その他にも、現場の生産性向上を目的とした改正があったことから、建設業界で労働環境の改善や作業効率の向上が求められていることがわかります。
このような流れから、労働環境の改善や作業効率の向上に寄与する電子化の必要性も高まるようになりました。
工事請負契約前の見積書などの電子化も2021年9月に解禁
2021年9月にはデジタル改革関連法の施行によって建設業法の第29条が改正されました。
今回の改正によって、工事請負契約書の電子化だけでなく、工事請負契約前の見積書や追加工事に伴う追加・変更契約の電子化も可能となりました。
これらを行うためには、契約相手からの承諾を得るなどの必要がありますが、特定専門工事の元請負人及び下請負人の間の合意書面においては、契約相手の承認を得ることなく、電子化をすることができます。
このように、建設業法の改正により建設業での電子化の流れは加速しています。
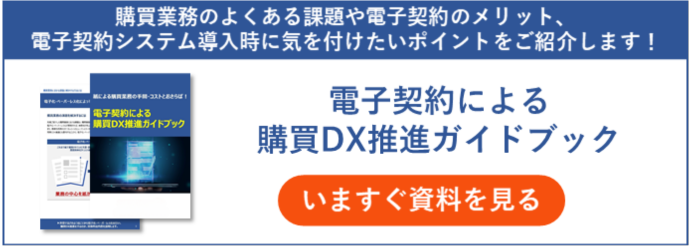
建設業界における電子化の3つのメリット
以下では、建設業界における電子化のメリットを3つご紹介します。
書類関係業務の効率化
電子化する最大のメリットとして、書類関係業務の効率化が挙げられます。
紙ベースで契約書や見積書をやり取りする際には、書類作成や押印・郵送といった手間がかかりましたが、電子化をすることでリードタイムを短縮することが可能です。
また、図面の電子化が実現すれば、最新バージョンや修正後の共有を迅速に手間なく行うことができます。このように紙資料を電子化することで業務の効率化が図れ、テレワーク対応も可能になることから、働き方改革の実現にもつながります。
インク代や印刷費用削減
電子化には紙の書類にかかっていたインク代や印刷費用を削減できるメリットもあります。
これまで、紙の書類にはインクなどの印刷費や紙の費用、また大量の資料を運ぶ輸送コストや、廃棄費用など、多くのコストがかかっていましたが、電子化を実現できれば、これらの費用を削減することが可能です。さらに、ビジネスパートナーの収入印紙代が不要となり、大きな受益効果も期待できます。
コンプライアンスの強化に寄与
電子化をすると、セキュアな環境にデータを保管することが可能になるため、コンプライアンスの強化が期待できます。契約業務の電子化が実現すれば、契約締結までの流れを可視化することができ、データ化された契約書の一元管理が可能です。書類のチェックもスムーズになるため、法律に基づく社内監査も円滑化できることから、コンプライアンスの強化に寄与します。
さらに、電子化された書類であれば、紙による持ち運びや保管中の紛失による情報漏えいのリスクを低減できます。
このように多くのメリットがある電子化ですが、建設業において電子化サービスを導入する際に注意しなければならない点もあります。次章では、建設業界における電子化サービス導入の注意点についてご紹介します。
建設業界における電子化サービス導入の注意点
電子化サービスを導入する際にまず考えなければならないのは、従業員にとって扱いやすいかという点です。電子化サービスを導入しても、従業員にとって使いにくければ、電子化の効果を発揮することは困難です。また、導入以前に使っていたサービスと連携できるか確認しておくことも重要です。
電子化サービス導入の注意点としては以上2つが主になりますが、電子契約においては、これとは別に注意しなければならないポイントがあります。
電子契約時の一定の条件を満たせることができるか
電子契約サービスを導入する前に確認しておきたいのが、原本性・見読性・本人性の3つの要素を満たしているかです。原本性は、電子契約書が改ざんされていないことを確認すること、見読性は契約データを書面に出力できる状態のこと、本人性とは電子契約書のサイン時に本人確認がなされていることです。
これらの要素が1つでも欠けてしまっているサービスであった場合には、作成した電子契約書が法制度や規制などに触れてしまう可能性があります。
3つの要素を満たしているかを確認する際には、以下4つのポイントを確認していくことをおすすめします。
ポイント1:電子化された書類が速やかに整然と表示できるシステムであるか
ポイント2:改ざんを防ぐ公開鍵暗号方式を実装しているか
ポイント3:他人が契約相手になりすましていないか確認するための電子的な証明を行えるか
ポイント4:電磁的記録等で請負契約の内容を整理し、保存を行えるか
また、導入する際には、事前に契約相手から承認を得ておくことも重要です。契約相手の理解をしっかりと得ることで、電子契約での締結をスムーズに懸念なく行えます。
電子契約のグレーゾーン解消制度で認められたサービスであるか
電子契約における懸念をなくすための制度としてグレーゾーン解消制度があります。
この制度は、法解釈の曖昧な点を対象のビジネス分野を所管する省庁に問い合わせることができ、既存の法律と矛盾していないかの懸念を解消することができる制度です。
この制度の基準に対応したサービスであれば、電子契約における懸念を解消できるため、建設業の工事請負契約がスムーズに進めることができます。
このように、電子契約サービス導入前には確認しておきたいポイントが多くあります。
次章では、これらのポイントを満たしたサービスについてご紹介します。
建設業の電子化を実現するために導入すべきサービスとは
昨今の建設業法改正により建設業においても電子化の流れが進みつつあるため、電子契約サービスの導入を検討する企業も増えています。電子契約サービスの導入を成功させるためにも、上述したような電子契約の条件に適応したサービスを選定する必要があります。
DAIKO XTECHの電子契約サービス「DD-CONNECT」では、電子契約サービスの導入~運用支援、アフターサポートまで電子契約の運営に必要なサービスを一括で提供しています。
従来は紙+押印+郵送でやり取りを行っていた「注文書、注文請書」をはじめ、「作業完了報告書」や「請求書」、「検収書」等の電子化を実現し、建設業における「工事請負契約」といった契約書の電子化も可能です。
専任のコンサルタントが業種に沿った法的・事例的な側面からの提案を行ってくれるため、電子帳簿保存法や電子署名法、建設業法や国土交通省のガイドラインへの対応も安心して行うことができます。
また、DD-CONNECTだけでなく、インボイスの保存や電子請求データの配信ができる「EdiGate DX-Pless」や社内システムと連携することで、仕入先との注文書発行業務のコスト削減や納期確認作業を軽減できる「EdiGate/POST」などでも一部電子化に対応することができます。
DD-CONNECTについての詳細は以下URLでも解説していますので、建設業における電子化を検討中の方は是非こちらもご覧ください。
建設業の電子化を実現する「DD-CONNECT」
電子契約システム導入サービスDD-CONNECTについては下記よりご覧いただけます。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓