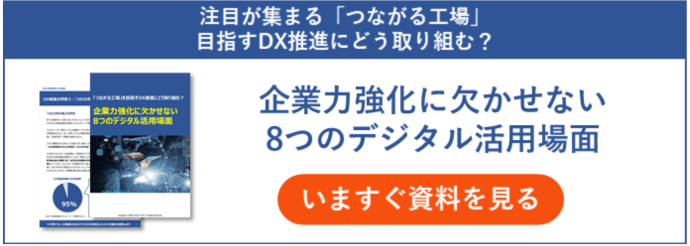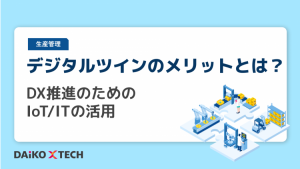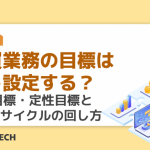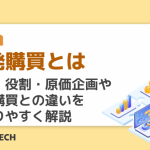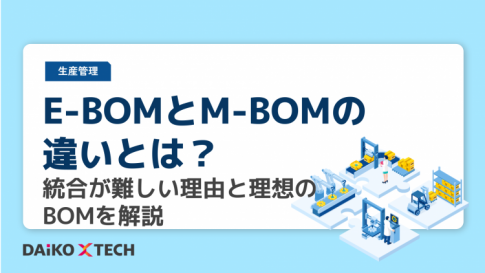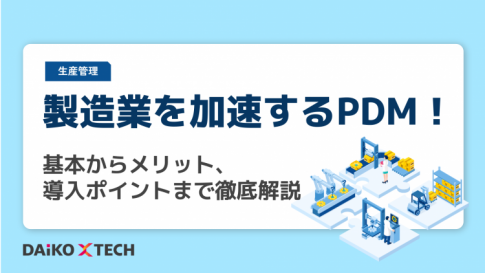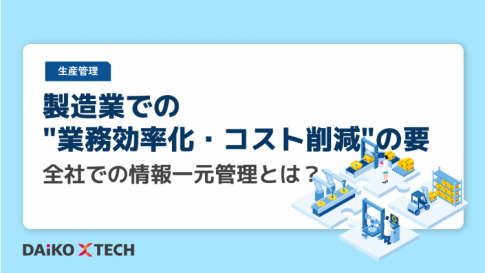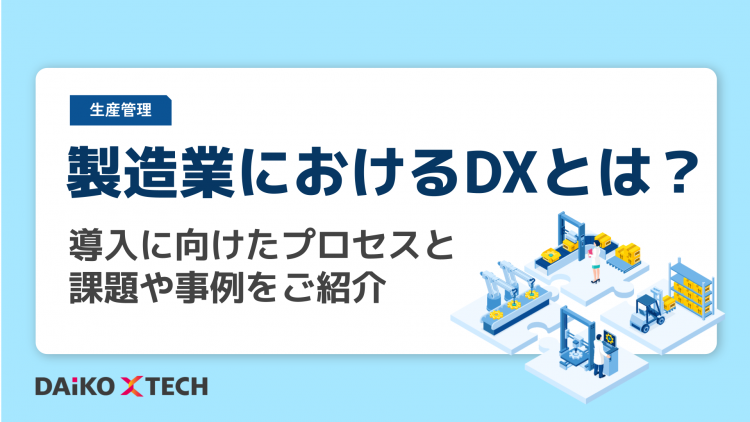
製造業DXとは、デジタル技術を活用して業務のプロセスや提供する製品を変容させることです。製造業DXを進めるうえでの課題として、取り組みの方向性が不明瞭、DX人材の不足などが挙げられます。
そこで本記事では、製造業DXを推進するためのプロセスを解説するとともに、取り組みを始める際に生じやすい課題や成功事例についてご紹介します。
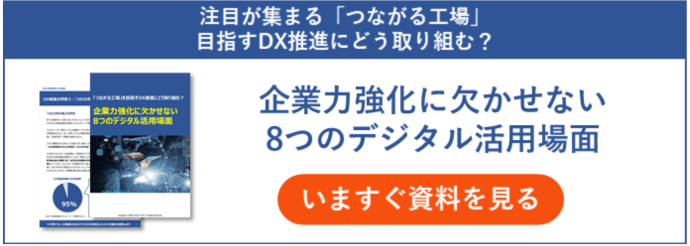
目次
製造業におけるDXとは
DXとはDigital Transformationの略語であり、デジタルによる変容という意味を持ちます。その中でも製造業におけるDXとは、単にデジタル技術を導入するだけでなく、デジタル技術を活用して仕事のプロセスや提供する製品を変容させることを意味します。
DXという単語は産業界を中心に広く使われるようになっていますが、単語自体の意味がすべて同じように使われているとは限りません。DXに関して議論をする際には、お互いの理解を合わせることから取り組みましょう。
本章では、製造業においてDXに期待が集まる理由と製造業におけるDX推進の手段として期待を集めているデジタルツインについてご紹介します。
製造業でDXに期待が集まる理由
日本の製造業は、少子高齢化による労働力不足の加速やユーザーの趣味趣向がグローバル化することで、厳しい状況に置かれています。また、経済産業省による「ものづくり白書 2021」では、多くの外的要因が製造業の事業判断に影響を及ぼす状況であり、事前に外的要因の発生や変化を想定することは難しいと説明されています。
そこで、デジタル技術を活用して仕事の仕組みを変え、効率化や品質の向上を促すDXに取り組むことで、外的要因の発生や変化に対してスムーズな対応が期待されています。製造業におけるDX推進の手段としては、IoTに加え、IoTとの相性が良いデジタルツインの活用が検討されています。
製造業におけるDXとデジタルツイン
デジタルツインとは、物理空間の情報を集め、ほぼリアルタイムで仮想空間に対象物や環境を再現する技術です。製品や製造工程について仮想空間でシミュレーションによる検証を行うことが可能です。
IoTセンサーや通信技術、CPUの処理能力が向上したことで、デジタルツインの活用が実現しました。上手く活用すれば、製造体制の最適化やリードタイムの短縮、コストの削減、問題発生時の原因分析をスムーズに行うことなどが可能になります。
このようにさまざまなメリットが得られるため、DXを推進したい企業では、デジタルツインの活用が積極的に検討されています。デジタルツインの詳細については、以下の記事をご参照ください。
製造業では、課題の解決手段としてDX推進の機運が高まっており、IoTやデジタルツインの活用が検討されています。しかし、実際にこれらの技術の導入を考えた場合、どのように着手すればいいかわからない場合がほとんどです。そこで次章では、DXでできることを紹介します。
製造業のDXでできること

製造業のDXは、さまざまな面で業務改善や競争力強化をもたらします。
主な効果としては以下の通りです。
- 生産性向上
- 業務効率化
- 情報の可視化
- 属人化の解消
- 顧客満足度の向上
各項目の詳細について、以降で詳しく解説していきます。
生産性向上
AIやIoTセンサーを活用した製造設備の自動制御やデータ分析による生産プロセスの最適化によって生産性向上が実現できます。
例えば、製造ラインにIoTセンサーを設置することで、リアルタイムでの稼働状況モニタリングや設備の予防保全が可能となり、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
また、AI技術を活用することで、生産計画の最適化や品質管理の自動化も可能です。
そして、これまで人手で行っていた検査工程や在庫管理などの業務を自動化することで、作業時間の短縮と人的ミスの削減が可能になります。
業務効率化
デジタル技術の導入により、さまざまな業務プロセスを見直し、効率化させることが可能です。
例えば、受発注システムのデジタル化により、注文処理や在庫管理が自動化され、人為的ミスの減少と処理速度の向上が図れます。
また、ERPシステムの導入により、財務、人事、調達などの基幹業務を一元管理し、部門間の情報共有がスムーズになるでしょう。
このようにDXによって単純作業を自動化することで、従業員に付加価値の高い業務に集中させ業務効率化を促進することが可能です。
情報の可視化
製造業におけるDXにより、これまで把握が困難だった製造現場のさまざまなデータをリアルタイムでの可視化が可能です。
具体的には、IoTセンサーや各種モニタリングシステムを活用することで、製造ラインの稼働状況、品質データ、在庫状況などを数値化し、視覚的に把握することが可能です。
例えば、生産設備の稼働状況をダッシュボード化することで、設備の停止時間や不具合の発生頻度などを即座に確認できます。
問題が発生した際の迅速な対応や予防保全の実施タイミングの最適化が図れるでしょう。
また、部門間でのデータ共有が容易になることで、製造現場と管理部門の連携が強化され、経営判断のスピードアップにもつながります。
さらに、過去の製造データを分析することで、品質改善や生産計画の最適化にも貢献します。
属人化の解消
製造におけるDXは、属人化の問題を効果的に解消します。
その理由の一つとしてデジタル技術を活用によって、製造プロセスや技術情報をデータとして蓄積し、誰でもアクセスできる環境が整う環境整備できるためです。
特定の個人の知識や経験に依存していた業務が明確になり、組織全体での共有が可能になります。
また、作業手順や技術がデジタル化され、標準化された作業手順を経由することで、従業員全体の作業レベルが均一化されます。
特定の従業員に過度の負担がかかることを防ぎ、誰でも同じ品質で業務を遂行できる環境が整うでしょう。
さらに、トラブル対応や製造ノウハウをデータベース化することで、過去の経験や解決策を組織全体で共有できます。
新人教育の効率化や突発的な問題への対応力向上が実現し、製造現場の安定的な運営が可能になります。
顧客満足度の向上
製造業におけるDXにより、顧客の求める製品とサービスをより的確に提供することによって顧客満足度の向上が実現できます。
例えば、顧客の購買履歴やフィードバックを蓄積し、AIを用いたデータ分析を行うことで、顧客のニーズや市場のトレンドを正確に把握することで顧客満足向上ができます。
これは、パーソナライズされた提案や迅速なサービス提供が可能となり、顧客の期待に応えることができるためです。
さらに、IoT技術を活用して製品の使用状況をリアルタイムでモニタリングし、予防保全やリモートメンテナンスを実施することで、製品の稼働率と信頼性を向上させることができます。
これにより、故障やトラブルによる顧客の不便を最小限に抑え、長期的な顧客満足度を高めることが可能です。
また、オンラインプラットフォームを通じて、発注状況や納期の確認が簡単にできるようにすることで、顧客の利便性を向上させることも実現できます。
これらの取り組みにより、製造業のDXは顧客体験の質を向上させられます。
製造業がDXを進めるためのプロセス
ステップ1:DX推進指標に基づいた現状把握
DXを推進する前に、経済産業省が策定したDXへの取り組み状況を評価するツールであるDX推進指標に自社を当てはめ、現状把握をします。DX推進指標は日本企業が直面している課題と解決のために押さえるべき事項を中心にまとめられているので、自社が取るべき手段が見えてきます。
また、DX推進指標に対する回答を社内関係者と議論し、認識を共有することで関係者のベクトルを合わせ、次のアクションにつなげやすくなります。
ステップ2:解決すべき課題の明確化
DX推進指標を活用して見えてきた自社の課題の中で、実際に解決すべき課題を明確にする必要があります。さらに、一部の経営層だけで課題を共有するのではなく、DX推進により課題解決に取り組むことをトップが全社的に宣言することが重要です。
DX推進はデジタル技術の活用により変容を促すことなので、中には仕事の仕組みが変わることに抵抗を示す人もいるでしょう。そのような場合でも、トップからの強いメッセージがあれば社員の中に共通認識ができ、DXを推進しやすくなります。
ステップ3:DX推進のための体制整備
DXを推進するためには、IoTやデジタルツインの導入を進めるための体制を整備することが重要です。製造業ではデジタル人材が不足しており、例えば社内の情報システムに関する部署がDX推進業務を兼務する場合が多くあります。
しかし、社内の調整や導入するツールの選定などDX推進の過程ではさまざまな業務が必要となるため、兼務は困難です。DXに専任できる担当者の確保や指揮命令系統の明確化、人材が不足している場合には専門的にDX推進に取り組む外部人材の活用など、体制を整備する必要があります。
ステップ4:DX実現の基盤となるツールの導入
取り組むべき課題の明確化やDX推進の体制整備が完了したら、DX実現の基盤となるツールの導入を進めます。実際の導入にあたっては、ツールを提供する企業の協力を得ながら、自社の環境へのカスタマイズや逆にツールに合わせて自社の環境整備を行う必要があります。
経済産業省によるDXレポートで2025年の崖として指摘されたように、日本の企業では独自のシステムが大きな課題となる可能性があり、仕事のプロセスを含め、システム切り替えのタイミングでは思い切ってビジネスモデルを変容することが効果的です。
ステップ5:運用を通した評価、検証、改善
ツールの導入が完了したら、実際にツールを運用しながらDX推進に対する取り組みの評価や効果的な活動ができたかどうかの検証を行います。また、新たに構築したプロセスなどは、運用を通して見つかった課題を元に改善を続けることが重要です。
このように、振り返りをしっかりと行い、変化を受け入れる体制を作っておくことで、外的要因の影響を受けた場合でも速やかに対応できるようになります。
ここまでは、DXを推進する際のプロセスについて解説してきました。多くの場合、DXを推進する過程で課題が生じてきます。そこで次章では、製造業でDXを進める際に生じる課題、阻害要因についてご紹介します。
製造業DXが進まない理由

製造業のDXは重要性が認識されているにもかかわらず、多くの企業で推進が困難な状況にあります。
DX推進を妨げる主な要因として、以下が挙げられます。
- 社内でDXに対する理解度が低い
- DXのビジョンが不明確
- DX推進に必要な人材の不足
- 予算が不足している
これらの課題は互いに関連しており、一つの課題が他の課題を引き起こす要因となっていることも少なくありません。
以下では、これらの課題について詳しく解説します。
社内でDXに対する理解度が低い
製造業のDX推進において、社内での理解不足は大きな障壁です。
特に製造現場では、長年培ってきた技術や経験を重視する傾向が強く、デジタル化への抵抗感が根強く残っています。
これは、mDX導入後のワークフローの変化や新しいシステム操作に対する不安があるためです。
また、「デジタル化によって熟練工の技術が軽視される」といった誤解や「現状の業務プロセスで十分に機能している」認識により、変革の必要性を実感できていないケースも多く見られます。
さらに、DX導入による具体的な効果や、それによってもたらされる業務改善の可能性が、現場レベルまで十分に伝わっていないことも課題です。
このような理解不足は、DXプロジェクトの計画段階から実行段階まで、さまざまな場面で支障をきたす原因となっています。
DXの阻害要因については、以下の記事で詳細を解説しています。詳しくは以下の記事をご参照ください。
製造業においても推進されているDX。その阻害要因と取り組む際のポイントは?
DXのビジョンが不明確
DXが単なるデジタル化の手段と誤解され、本来の目的や価値がしっかりと認識されていないケースが多々あります。
多くの企業では、デジタル技術を導入すること自体がゴールとなり、実際にどのように活用するかが曖昧なまま進められていることが問題です。
具体的には、「なぜDXが必要なのか」「DXによって何を実現したいのか」「どのような未来を目指すのか」といった本質的な問いに対する答えが不明確なままDXを進めようとしているケースが多く見られます。
このようなビジョンの不明確さは、投資の優先順位付けを困難にし、また社内の推進体制の構築や人材育成の方向性も定まらない原因となっています。
効果的なDX推進には、経営層による明確なビジョンの提示と、それに基づく具体的な戦略の策定が不可欠です。
DX推進に必要な人材の不足
製造業のDX推進において特に必要とされるのは、製造現場の業務知識とデジタル技術の両方を理解し、それらを効果的に組み合わせることができる人材です。
DX推進するためには、データ分析やシステム構築といった技術的なスキルだけでなく、製造プロセスの理解や現場とのコミュニケーション能力も必要です。
しかし、こうした複合的なスキルを持つ人材は極めて少なく、多くの企業が人材確保に苦心しています。
また、外部からの人材採用だけでなく、社内人材の育成も課題です。
既存の従業員に対するデジタルスキル教育には、時間とコストがかかります。
さらに、日々の業務に追われる中で、新しいスキル習得のための十分な時間を確保することも困難な状況です。
このような人材面での課題が、DX推進の大きな障壁となっています。
製造業で求められるデジタル人材についての詳細は、以下の記事を参照してください。
製造業に求められる“デジタル人材”とは?人手不足・DXに対応しよう
予算が不足している
DXの実現には、システム導入の初期投資だけでなく、継続的な運用・保守費用、人材育成費用など、複数の費用項目が必要です。
特に中小製造業にとって、IoTセンサーの導入やクラウドインフラの整備といった大規模な投資は大きな負担となります。
また、投資対効果(ROI)の見通しが不明確な場合も多く、経営層の投資判断を困難にしています。
さらに、システムの保守・運用費用、ライセンス料、セキュリティ対策費用などの継続的なランニングコストも必要です。
こうした費用の積み重ねが、特に規模の小さい製造業にとってDX推進の障壁となっています。
製造業DXを推進するためにできること

以下はDX推進を促進するために考慮すべきポイントです。
- DXに対する組織全体の理解を深める
- デジタル人材の育成を行う
- 業務のオンライン化に取り組む
それぞれの施策を実施することで、製造業におけるDXの実現が一歩進み、競争力の強化につながります。
これらの取り組みを通じて、未来への準備を整え、持続可能な成長を目指しましょう。
DXに対する組織全体の理解を深める
製造業のDX推進を成功させるためには、まず組織全体でDXの本質的な意義と目的を理解することが重要です。
これは単なるデジタル技術の導入ではなく、企業文化や業務プロセスの変革を含む包括的な取り組みであることを、全従業員が認識する必要があります。
具体的な施策としては、定期的な社内セミナーや勉強会の開催、成功事例の共有、外部講師を招いたワークショップなどが効果的です。
特に、現場の従業員に対しては、DX導入による具体的なメリットや日々の業務がどのように改善されるのかを、わかりやすく説明することが重要です。
また、経営層からの明確なメッセージ発信も欠かせません。
DX推進の意義や目標を繰り返し伝えることで、組織全体の意識改革を促し、変革への抵抗感を軽減できます。
全従業員がDXの必要性を理解し、積極的に参画する姿勢を持つことが、成功への第一歩となります。
デジタル人材の育成を行う
製造業におけるDX推進を成功させるには、デジタル人材の育成が欠かせません。
既存の従業員にデジタルスキルを習得させることで、業務に精通した人材が新たな技術を活かせるようになり、DXの効果を最大限に引き出すことができるためです。
製造現場の知識とデジタル技術の両方を持つ人材は、DXの推進において大きなアドバンテージをもたらします。
具体的な育成方法としては、社内研修やeラーニングを活用した体系的な教育プログラムの実施が効果的です。
実務に即したスキルを身につけることができます。
また、外部の専門家を招いての指導や、最新の技術を学ぶ機会を提供することも有益です。デジタル技術を理解し、活用できる人材が増え、DX推進が加速します。
着手しやすい分野から段階的にデジタル化を推進する
最初から大がかりなDXを進めるよりも、小規模・少額ですぐに始められるものから、段階的にデジタル化を推進する方が難易度は低くなります。
例えば、業務効率化のためのデジタルツールの導入は比較的取り組みやすく、かつ効果が見えやすい特徴があります。
まずは紙ベースの業務記録や報告書のデジタル化から始め、徐々に範囲を広げていきましょう。
具体的には、製造工程の可視化するための生産管理システム、在庫状況のリアルタイムで把握するための在庫管理システム、情報共有のためのクラウドツールなど段階的な導入が挙げられます。
また、クラウドのシステムの導入により、同時に情報共有のオンライン化を促進する効果も期待できます。
製造業におけるDXの成功事例
工場IoTによるデジタル化と人材の育成
ある企業では、製造現場やお客様から得たデータを技術開発にタイムリーにフィードバックするために、工場横断のIoTプラットフォームを3年かけて段階的に構築しました。プラットフォームの構築と並行して各社員による小規模なテーマ立案、実行といった取り組みにより、人材の育成も進めています。
また、仕組みの変更に社員が戸惑わないように、社内部署による組織的な教育支援を実施しました。さらに、安心して使用できるようなセキュリティ対策を施したことで、効率化や品質向上に加え、製造現場の情報をタイムリーに開発へフィードバックできる環境を構築しています。
多品種少量生産の効率化と顧客ニーズへの対応能力向上
複数の工場を持つある企業では、各工場がそれぞれの拠点のみに最適化された設計開発を行っており、図面の記載ルールや技術標準が統一されていませんでした。それにより、同じ企業の工場にも関わらず、共通の仕様で生産できない点が大きな課題でした。
DX推進として、共通した技術標準の構築や統合管理体制を構築することで、工場間の連携が可能になり、より顧客に対してメリットのある生産体制を構築できるようになりました。
複数の工場を仮想集約させ連携を可能に
多品種少量生産を行うある企業では、ベテラン担当者の知識や経験に基づいて部品の調達が行われており、他の担当者がタイムリーに対応できない状態でした。この状況を解消するために、現在では部品管理の共有化が可能な生産管理システムを導入しています。
当初の課題であった顧客への対応能力が向上し、さらに、正確な製品原価の把握や棚卸の効率化など、副次的な効果も得られています。
製造業のDX推進により不透明な外的要因への対応能力向上を実現
外的要因の影響で不透明な状況に陥っている製造業では、DXの推進により外的要因への対応能力向上が必要となっています。DX推進指標などを活用して自社の状況を把握し、外部の人材も含めDXを推進できる体制を構築することが重要です。
製造業の根幹をなすのは生産で、まずは生産管理システムの整備から取り組むのがDX推進の効果的な選択肢の一つといえます。
冒頭でご紹介したデジタルツインもDX推進の一環ですが、これを実現するためには3D技術やBOM化が欠かせません。そのベースとなる共通管理のBOM推進のためには、当社が提供する生産管理システム「rBOM」が最適です。
導入までのサポートや導入後の講習なども充実しているため、安心してご活用いただけます。詳細は下記でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
現場からの支持を受けやすい生産管理システムの導入なら | 生産管理システム「rBOM」
リアルタイムな進捗・原価把握を実現する生産管理システム
「rBOM」については、下記よりご覧いただけます。