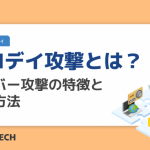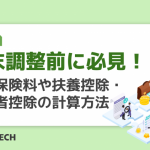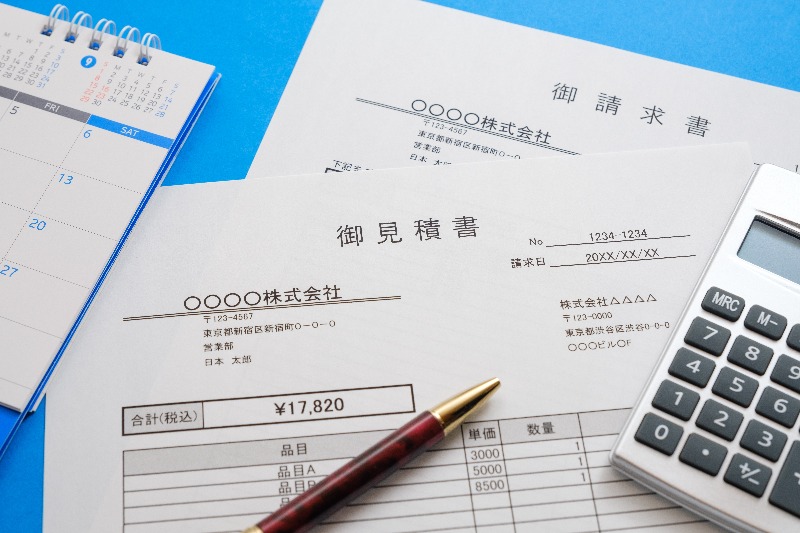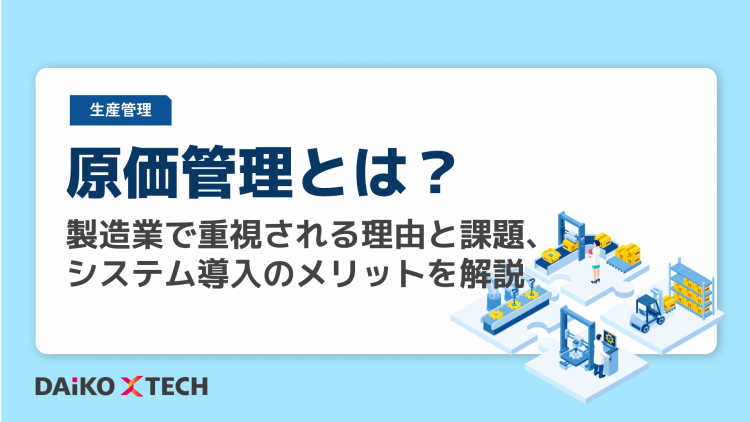
製造業界では、原価管理を行ってコストを最小限に抑え、利益を最大化して会社の成長に繋げる必要があります。ただ、無理のある原価の「削減」ではなく、あくまでも「管理」を念頭におくべきだといわれています。では、「原価を管理する」ためには具体的に何をすればよいのでしょうか。
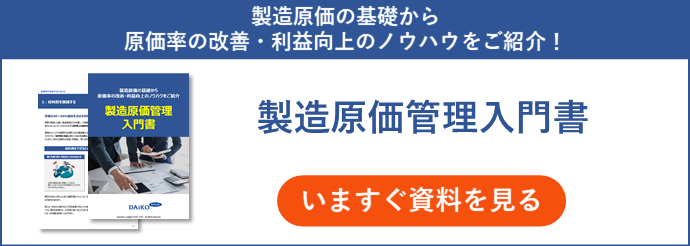
目次
原価管理とは

製品やサービスの原価を管理する手法のことを「原価管理」といい、「コストマネジメント」とも呼ばれます。原価管理では、製品やサービスを生み出すために必要な原価を設定し、実際にかかった原価との差異を分析して適切な原価を計算します。原価管理を広い視点で正しく行うことは、持続的な企業の発展に繋がります。
消費者のニーズが多様化した現在、確実に利益をあげるためには生産における綿密な計画が必要です。このことから、製造業の経営管理で行うことの多かった原価管理は、最近では幅広い業種で活用されています。
製造業で原価管理が必要とされる理由

物を作るときは原材料費や労務費などのコストがかかりますが、それらのコストを原価といい、企画・調整などの管理を行うことを原価管理といいます。しかし、高度経済成長時代や1990年台まではそれほど原価管理は重視されていませんでした。
原価管理が必要になった時代背景
原価管理をめぐる状況が変わったのは、グローバル化が進んだ2000年台からでした。競争力が高まり、安く提供しなければ製品が売れない時代になったのです。安く提供しながらも利益を出すためには、より厳密な原価管理を行う必要があるため、原価管理が必要不可欠となりました。
あらゆる業界で原価管理は重要とされ、製造業だけではなくソフトウェアやコンテンツ制作などのプロジェクト型企業でも同じく重要視されています。
製造業における原価管理の効果
製造業における原価管理は、企業の収益性と競争力を大きく向上させる重要な経営活動です。適切な原価管理を実施することで、以下の効果が得られます。
- 利益率の改善
- 競争力の強化
- 経営判断の質向上
- 継続的な原価管理
製品の製造過程で発生する直接材料費、直接労務費、製造間接費などを詳細に把握・分析することで、無駄なコストを特定して削減、利益率の改善が期待できます。これにより、製品1単位あたりの利益最大化が可能です。
また、原価を正確に把握することで、市場競争力のある適切な価格設定が可能になり、競争力の強化が可能です。原価構造を理解すると、競合他社との差別化ポイントを見出し、戦略的な製品開発や製造プロセスの改善に活かせます。
さらに、標準原価と実際原価の差異分析を通じて、製造プロセスの非効率な部分や改善が必要な領域を特定可能です。これにより、設備投資の判断や製造ラインの改善、外注化の検討など、より戦略的な意思決定で経営判断の質の向上を実現します。
原価管理によって組織全体のコスト意識を向上させると、PDCAサイクルに基づく継続的な原価管理が叶います。従業員一人一人が原価に対する理解を深められ、日常的な業務改善や効率化への取り組みやすくなるでしょう。長期的な企業文化の醸成にもつながります。
このように、製造業における原価管理は、単なるコスト削減を超えて、企業の持続的な成長と競争優位性の確立に貢献する重要な経営ツールとして機能します。
原価管理と関連用語の違い

企業経営において、原価管理、原価計算、予算管理、利益管理などの用語は密接に関連しています。しかし、それぞれ目的と役割は異なります。これらの違いについての理解は、効果的な経営管理を行う上で重要です。
ここでは、原価計算の基本的な概念から始め、関連する管理手法との違いについて詳しく解説していきます。
原価計算
原価を管理する活動すべてを指しますが、管理の内容は3つの段階に分けられます。
- 原価企画
- 原価統制・維持
- 原価低減・改善
①原価企画の段階で開発計画をし、企画設計をしていきます。②原価統制・維持で製造の現場で実際に商品を作りますが、企画段階で算出した原価とのズレを限りなく小さくしていく工夫をします。③原価低減・改善では企画と現場との調整をし、原価の標準自体を改善するのです。実は原価企画の段階で原価は大方決まるといわれていますので、企画設計を現実的に立てなければなりません。
原価企画や原価低減の際には原価の情報が必要なので、原価計算をしていきます。つまり、原価の計算をすることですが、必要となるのは原価管理の現場だけではありません。株主や債権者に提示するための財務会計にも原価計算は必要ですし、会社経営の予算管理のためにも原価計算をしていきます。
予算管理
企業経営においては、原価管理以外にも密接に関連する管理手法があります。例えば、予算管理です。
予算管理は、企業の総収入と総支出などの実績に基づいて一定期間の予算を策定し、その実行を通じて財務のバランスを保つ目的で行われています。また、予算管理は企業の予算編成や各事業への予算配分、予算の執行管理など、原価管理を含めたより広範な管理を指します。
一方、原価管理は製品やサービスの生産過程で発生するコストを詳細に把握し、コストの削減や効率化を図ることに重点を置いた管理手法です。どちらも企業の健全な経営に欠かせないものですが、管理する対象や範囲が異なります。
利益管理
原価管理が製品やサービスに関するコスト削減に特化しているのに対し、利益管理は企業の利益を最大化するのが目的です。売り上げの最大化とコストの削減を通じて達成されます。
利益管理は価格戦略や市場戦略を含むより幅広い戦略的アプローチを取り、全体の財務成績の改善につなげます。つまり、原価管理は利益管理の一部として位置づけられ、コストの管理と削減を通じて利益の増加を目指すことが役割です。
原価管理の手順

原価管理の手順について、4つのステップを詳しく説明します。
原価管理の手順では、標準原価の設定から業務改善まで、一連の流れに沿って体系的に管理を行います。これにより、効率的なコスト管理と継続的な改善が可能です。
1.標準原価の設定
標準原価の設定は、製品1単位あたりの原価目標を概算で決定する過程です。長期的な視点に立った計画上の原価であり、1販売あたりの利益を算出する基準です。
標準原価を適切に設定するためには、市場の相場を考慮した有効なマーケティングが欠かせません。また、利益とのバランスを考慮しながら、過去のデータに基づいて正常な生産状態での原価計算が重要です。
2.原価計算
原価計算の段階では、材料費、労務費、経費などの実際にかかるコストを明確化し、合理的な計算に基づいて集計します。方法は「標準原価計算」「実際原価計算」「直接原価計算」の3つです。
標準原価計算は概算を出す際に用い、実際原価計算は実際の原価情報を集計するために使用します。また、直接原価計算では変動費と固定費を分けて考えると、より詳細な製品ごとの利益分析が可能です。
3.差異の比較分析
差異分析では、設定した標準原価と実際にかかった原価との差異を分析します。この過程は特に重要で、計画と実績の差が生じた原因を詳細に調査します。
実際原価が標準原価を上回る場合、それだけ利益が減少するため、その差異が発生した原因を突き止め、事業における課題点を明確にすることが必要です。これにより、今後の改善方法を見出せます。
4.業務改善
差異分析で明らかになった課題に基づいて具体的な改善を実施します。この段階では、標準原価を引き下げるための工程の見直しや、製造における無駄や非効率の排除、価格設定の見直しなどを行います。
また、改善は単発で終わらせるのではなく、継続的な業務改善や企業経営マネジメントの一環として位置づけることが重要です。
製造業における原価管理の課題

製造業における原価管理は、企業の収益性と競争力を維持するために欠かせませんが、実務においては複数の重要な課題に直面しています。これらの課題は、日々の業務オペレーションから長期的な経営戦略まで、さまざまな側面に影響を及ぼすため深刻です。
以下では、実績原価の正確な把握、従業員のスキル育成、品質とコストの最適なバランスの維持という3つの主要な課題とその対応策について詳しく見ていきます。
正確な実績原価をリアルタイムに把握しにくい
製造業では材料費、労務費、製造間接費など、多岐にわたるコストが発生し、それらを正確にリアルタイムで把握するのは容易ではありません。特に大企業の場合、複数のプロジェクトや部門が存在するため、すべての情報を適切に集約して管理するのは困難です。
収集したデータが不正確だと、コスト計算の誤りにつながり、結果として誤った意思決定を引き起こす可能性があります。
この課題に対しては、生産管理システムの導入が有効な解決策です。システム導入によってデータの一元管理が可能で、各部門間の情報共有がスムーズになり、より正確な原価管理を実現できます。
従業員のスキルが不足している
原価計算やデータ分析を正確に行うためには、専門的な知識と経験が必要です。しかし、スキルを持った人材が不足している場合、正確なデータ収集や分析が困難です。
この課題に対しては経験豊富な従業員による指導やサポート、定期的な講習会やセミナーの実施を通じて、原価計算やデータ分析のスキルを向上させることが重要です。また、組織全体で原価管理の重要性を理解し、その過程に対して積極的に関与する土壌を育てなければなりません。
品質管理とコストのバランスをとるのが難しい
製造業において品質管理は重要で、顧客の要求する品質水準を維持することは競争力を保つ上で欠かせません。しかし高品質を維持するためには、材料の品質管理、製造プロセスの監視、検査、テストなどの追加コストが発生します。品質を犠牲にせずにコストを削減する方法を見出すことは容易ではありません。
この課題に対しては、品質管理に関連する追加コストを適切にトラッキングし、問題を早期に検出することが重要です。また、効率的な生産プロセスの確立と品質管理システムの導入により、両者のバランスが取れます。
効果的に原価管理を行う方法

原価管理を効果的に行うためには、適切なツールの選択が重要です。現在、多くの企業で採用されているのがエクセルを使用する方法と、専用の原価管理システムを導入する方法です。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、企業の状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。
以下では、この2つの方法について詳しく見ていきます。
エクセルで管理する
エクセルのメリットとして、導入費用を抑えられる点や、インターネット上で入手可能なテンプレートをすぐに活用できる点が挙げられます。また社内で原価管理に精通した担当者がいれば、企業独自の管理方法を構築できるほか、基本的な操作さえ覚えれば誰でも使用可能です。
一方で、エクセル管理にはいくつかの課題があります。関数やマクロの知識が必要なため、特定の担当者に業務が集中し管理が属人化しやすい点や、複数のシートやファイルを管理する手間が大きい点です。同時編集が難しく、データ入力ミスのリスクもあります。セキュリティ面での対策が不十分なのも課題です。
原価管理システムを導入する
原価管理システムを導入すると、データを一元管理でき、各部門間の情報共有がスムーズになります。複雑な計算も自動で行えるため、作業効率が大幅に向上し、人為的なエラーも減少させることが可能です。ただし、初期費用や運用コストがかかることや、従業員の教育・トレーニングが必要なのが課題です。
原価管理システムには、企業の効率的な運営を支援するさまざまな便利な機能が備わっています。
- 在庫管理との連動機能によりリアルタイムでの在庫状況の把握や適切な在庫レベルの維持が可能となり、過剰在庫を防止しながら在庫の最適化を実現
- グローバル展開を行う企業向けに、多言語・多通貨に対応した機能を搭載
- 外国為替レートの変動に対応した価格設定が可能
- 販売・生産・在庫のすべての工程情報を一つのシステムで管理でき、生産スケジュールの最適化が可能
- 需要予測や在庫状況の正確な把握により、生産性の向上と顧客満足度の向上を同時に実現
このように、企業の規模や業態に応じて、エクセルでの管理か原価管理システムの導入か、最適な管理方法を選択することが重要です。
原価管理システムの選び方

原価管理システムを導入する際には、企業の規模や業態に応じて適切なシステムを選択することが重要です。効果的なシステム選びのためには、以下の4つの観点から検討を行う必要があります。
在庫管理と連動できるシステムを選ぶ
在庫管理と原価管理は密接な関係にあり、両者を連動させることで大きな効果が得られます。在庫の正確な把握はコスト管理において重要なため、原価管理システムが在庫管理と連動できる場合、在庫の最適化が可能です。
在庫管理に関するデータが原価管理の過程に統合されると、適切な在庫レベルを維持しながら、不要な在庫を抱え込むことなくコストを最小限に抑えられます。
需要予測が適切に行えるか
在庫の過剰保有は保管コストの増加につながり、原価を上昇させる要因です。そのため、原価管理システムを選ぶ際には、需要予測の精度が重要なポイントです。
システムを通じて在庫を最適化できれば、保管コストを抑制できます。具体的には過重在庫や在庫不足を防ぐ機能が備わっているか、需要予測の方法が適切かなどを確認し、結果として保管コストの削減につながるかを検討する必要があります。
操作性がわかりやすいか
システムの使いやすさは、従業員の生産性に大きく影響します。操作が複雑なシステムでは、データ入力ミスや誤った手順の実行といったリスクが高まります。
そのため、従業員がストレスを感じることなく効率的に作業できる、シンプルで直感的なインターフェースを持つシステムを選ばなければなりません。これにより、業務の作業効率を向上させ、コストの削減にもつながります。
サポート体制が充実しているか
システムの選定では、サポート体制の充実度も重要な判断基準です。システムトラブルが発生した際に迅速な対応が得られないと、業務が停止し、企業に大きな損失をもたらす可能性があります。
サポートの範囲、問い合わせ方法、対応時間などを事前に確認し、従業員が使いやすい方法で問い合わせできるかを検討しなければなりません。充実したサポート体制は、システム導入後の安定した運用と、トラブル発生時の迅速な解決を可能にします。
原価管理システムと一緒にERPシステムも導入しよう

ERPシステムのサブシステムに原価管理システムが組み込まれていることもあります。ERPシステムを導入すれば、原価管理システムだけではなくその他の企業経営に欠かせない基幹業務システムをまとめて管理・運用することが可能です。
ERPとは
ERPは「Enterprise Resource Plannning」の略語で、日本語では「統合基幹業務システム」や「業務統合パッケージ」と訳されます。
ERPには、企業活動に必要な以下の機能が一通り揃っています。原価管理には会計や予算の情報が必要になるため、これらデータの連携が重要となります。
- 財務会計管理
- 予算管理
- 在庫管理
- 購買管理
- 販売管理
- 顧客管理
- 営業支援管理
- 人材管理
- プロジェクト管理
- マーケティング管理
- ビジネスインテリジェンス(BI)
- Eコマース
ただし、すべてのERPシステムがこれらすべての機能を揃えているわけではないため、導入前に必ず確認しておくようにしましょう。
ERPシステムのメリット
ERPシステムの活用は、企業のあらゆる情報の一元管理を実現します。さらに各管理システムと連携させることで、情報のやりとりがスムーズになり、業務を効率的に進めることが可能です。
従来、情報系システムや基幹系システムは一元管理されていませんでした。原価管理においては、各基幹システムから逐一情報を選んだうえでフォーマットの統一をし、原価管理システムへの反映を行うというのが主な流れでした。
そこでERPシステムを導入することで各基幹システムの情報をデータベースで一元管理することが可能になるため、効率的な原価管理に繋がります。
リアルタイムな経営の可視化によって迅速な意思決定に繋がる点も、ERPシステムのメリットです。ERPに蓄積されるデータは自動で処理され、経営者が必要なときに必要な情報を確認することが可能です。このことから、経営状況のリアルタイムな把握が行えるようになり、迅速な意思決定にも繋がります。近年では経営におけるスピード感は重要な課題となっているため、ERPシステムの導入には原価管理の効率化を含めたさまざまなメリットがあるといえるでしょう。
競争に勝つためには原価管理が必要不可欠

現代は商品の陳腐化も早いといわれています。そんな時代を生き抜いていくためにも原価管理は欠かせません。システムで自動化していれば単純な労務コストが削減でき、他の取り組みに時間がかけられます。システムを連携・活用して会社の成長に繋げましょう。
製造業向けの原価管理システムで業務を効率化しよう

ここまでご紹介したように、製造原価には、直接製品に関わる製造直接費、間接的に関わる製造間接費があり、人件費や原材料費、設備費用など、さまざまな経費をまたぎます。製造業において売上向上するためには、現状かかっているコストを正確に把握する必要があり、原価の細分化は欠かせません。
特に可視化しづらい製造間接費は、製造現場の稼働状況や経費の流れなどを確認した上で、原価の内訳を把握することが大切です。
間接費を明確にする原価配賦など、精度の高い原価計算を行う場合におすすめなのが、DAIKO XTECHが提供する原価管理システム「SHIN」です。原価の計算だけでなく、利益・原価情報を一枚のコストフロー図で概念的に理解できたり、予算の見込を分析するBI機能を使って決算予測に役立てたりできます。機能性の高さから、お客様からの注目度が高いソリューションでもあります。
「SHIN」に関する詳細情報はこちらからご覧ください。
また、原価管理だけでなく、生産管理・購買管理・在庫管理などさまざまなシステムを包含または連携できるシステムであれば、「rBOM」がおすすめです。直接原価計算を主に扱うことができます。
「rBOM」の詳細にご興味ある方は以下資料からご覧ください。
コスト削減とリードタイムの短縮を実現。 個別受注向けハイブリッド販売・生産管理システム。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
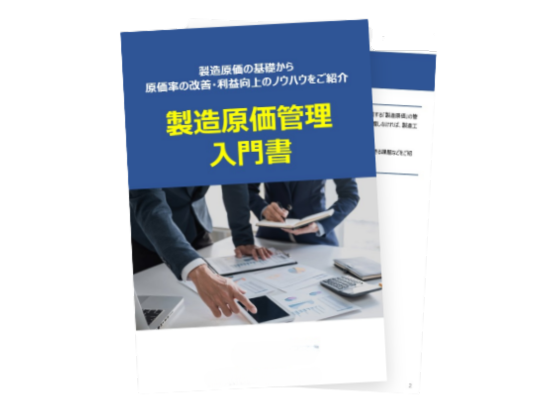
製造原価の基礎から 原価率の改善・利益向上のノウハウをご紹介
製造原価管理入門書

- この記事を監修した人
- 入社後15年間、長野支店にてシステムエンジニアとして活動。
運送業、倉庫業のお客さまを中心に担当し、業務システム構築からインフラ環境構築等の経験を積む。
その後、製造業のお客さまも担当し、rBOM導入のプロジェクトにも関わるように。
16年目に現部門に異動し、rBOM全国支援の担当者となる。
現在はrBOMだけではなく、製造業全般のソリューション提案を手掛けている。
料理が趣味、これからお菓子作りにも挑戦しようか迷っている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部 - 田幸 義則