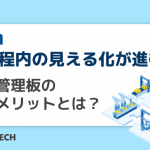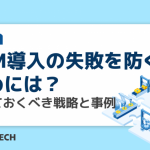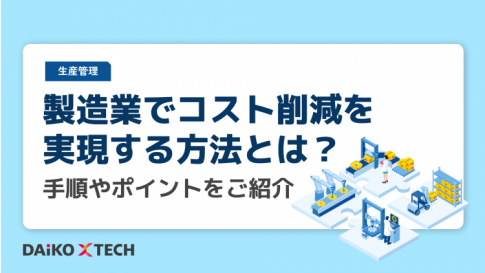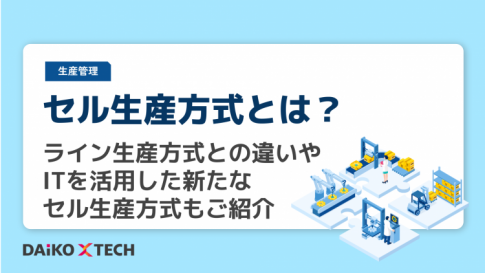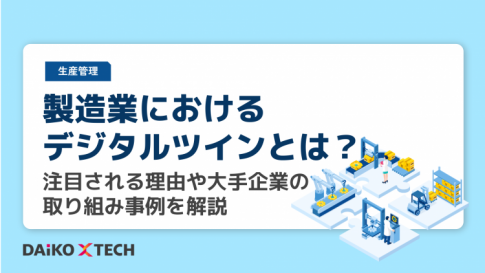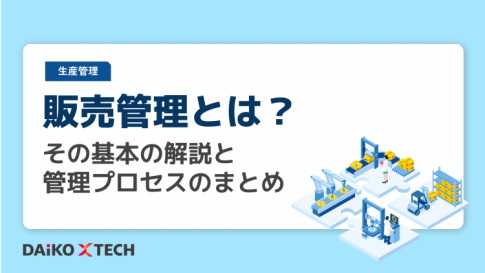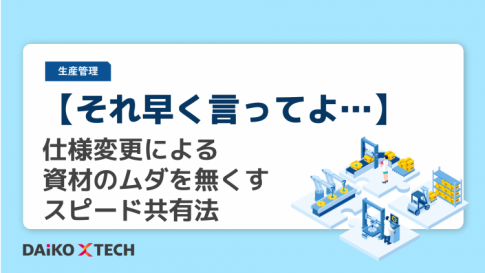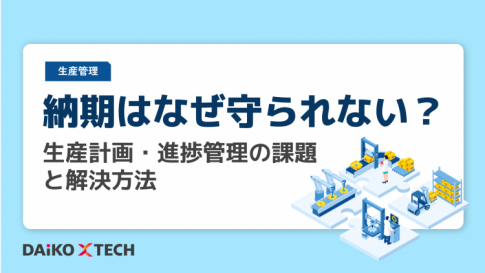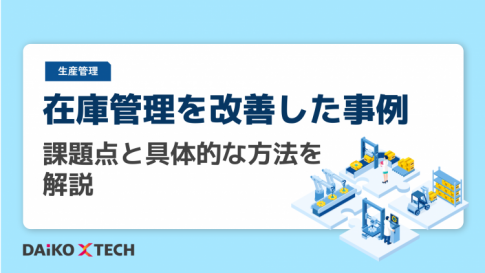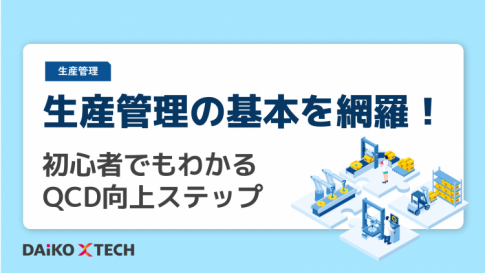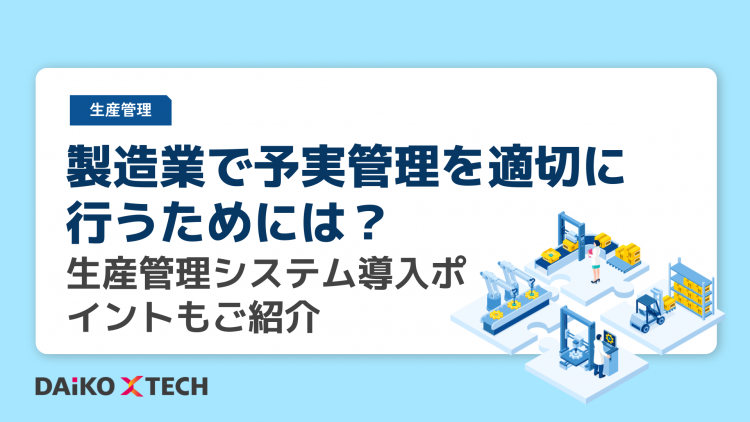
製造業において、予実管理が十分に行われておらず、納期遅延や、生産効率の悪化が見られるケースも少なくありません。
本記事では、製造業における予実管理について、生産管理の業務についても踏まえながらメリットや課題、適切な管理を行うための生産管理システム導入についても解説します。
しかし、自社に合わないシステムを導入してしまったり、導入だけで満足していては適切な予実管理にはつながりません。
記事の後半では生産管理システムの導入ポイントや、他の予実管理に適した方法についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
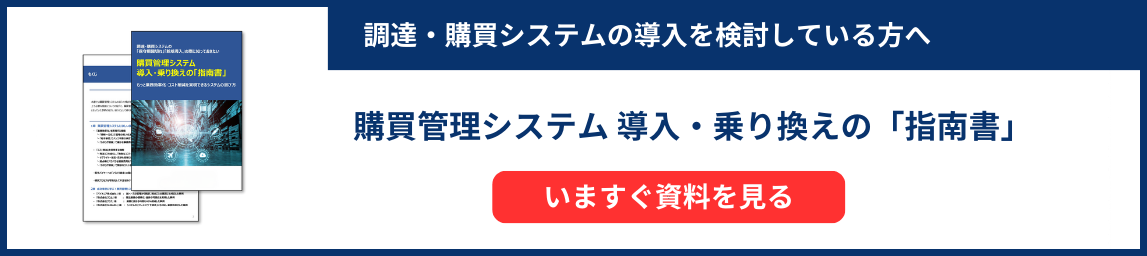
目次
生産管理の基本

生産管理は、モノづくりにおいて基幹業務のひとつであり、顧客ニーズに対応しながら効率的かつ安定的に製品を供給するための仕組みです。
具体的には、生産計画の立案から資材調達、工程管理、品質管理、在庫管理、原価管理までを含む幅広い活動を行います。
安定して工場を稼働し続けるためには、生産管理を適切に機能させなければなりません。
生産管理の定義や基本の考え方
JIS(日本産業規格)によると、生産管理とは「財・サービスの生産に関する管理活動」と定義されています。
市場や顧客からの需要に基づき生産計画を立案し、QCDをバランスよく考慮し、製造から出荷まで管理する一連の業務を指します。
QCDとは、以下の3つの項目で構成されています。
- 品質(Quality):顧客が満足する製品品質を安定的に確保
- コスト(Cost):原材料費、人件費、設備投資を抑えつつ利益を確保
- 納期(Delivery):顧客との約束通りに製品を納品し、信頼関係を維持
品質を最優先とする企業が多いものの、QCDは相互に影響し合うためバランスよく考慮して生産管理を行うことが重要です。
生産管理の目的は、モノづくりでのQCDを維持しながら顧客満足度を高めることと言えます。
QCDのバランスが崩れてしまうと、品質問題や納期遅延により顧客からの信頼を失ってしまうことにもなりかねません。
また、コストを度外視してしまうと利益が出ない経営を続けてしまうことにもつながります。
QCDのバランスが取れた生産管理が行えれば、高品質で低コストなモノづくりを、顧客の納得できる納期で行えるため、競争力の向上にもつながります。
適切な生産管理を行うメリット
適切な生産管理を行えれば、以下のようなメリットが生まれます。
- リードタイムの短縮
- 納期遵守率向上
- 品質向上や不良率の削減
- 適正在庫の維持
- 生産性向上
生産管理は以上のように、モノづくりにおけるあらゆる工程に関わり、全体を指揮する立場であるため、実質的に工場長に近い役割を担うともいわれています。
生産管理の基本業務
次に、生産管理における工場での仕事内容を具体的にご紹介します。
生産管理の仕事内容は主に以下の6種類です。
- 需要予測
- 生産計画
- 調達購買
- 工程管理
- 品質管理
- 原価管理
以下で簡単にご説明します。
需要予測
生産管理では、まず需要予測を行います。
効率的な生産を行い、在庫のムダをなくすためにも、需要予測は重要な業務です。
自社での販売実績や市場でのトレンド、競合となる企業の動向、経済指標といった要因を考慮し、需要予測をしなければなりません。
需要予測は、設備投資の必要性を測り、人員配置計画のためにも重要です。
需要予測の具体的な手法について以下の記事で解説しているため、ぜひご一読ください。
生産計画
次に、需要予測に基づいて生産計画を立案します。
生産計画では、生産量や時期についての計画を立てますが、具体的には主に以下の項目を計画します。
- 製品の種類、製造方法、数量、納期
- 原材料や部品の調達方法や必要数量
- 製造から納期までの具体的なスケジュール
上記を含む生産計画を元に、人員配置や必要コストの計算が行われます。
納期遅れや品質悪化につながらないためにも、計画段階でできる限り無理のない計画を立てる必要があります。
詳しい生産計画の立案方法ついては、以下の記事をご参照ください。
調達購買
生産計画が立案できれば、製品に必要な原材料や部品、資材などについて仕入先を検討し、価格交渉、自社内の調整や検収を行う調達購買業務が必要です。
生産計画を元に仕入先を決定します。
調達購買においても、QCDの最適化を重視してサプライヤーを選定しましょう。
安易に低価格を求め、サプライヤーに無理な見積もりを要求すると、取引を拒否されたり、品質の悪い部品による事故につながる可能性があるため、双方が納得できる価格交渉を行う交渉技術も重要です。
調達購買の詳しい業務については以下の記事をご覧ください。
工程管理
製品の生産が始まると、工程管理で進捗状況を把握し、効率的に製造できるように管理します。
工程管理では、品質の維持と納期遵守ができているかに注目し、製造工程全体を見渡します。
また、工程管理システムを導入できれば、属人化や計算ミスによる事故を防ぐことも可能です。
工程管理については、以下の記事でも詳しく説明しておりますので、ぜひご一読ください。
工程管理とは?製造業における基本手順や効率化する方法をご紹介
品質管理
工程管理を行いながら、生産工程の中で一定の品質を保てるように品質管理も行います。
前述したとおりQCDの中でも品質は最優先事項であるため、品質管理を独立した大きな部門として設けているモノづくり企業も多く存在します。
品質管理は、品質検証と品質改善が主な業務です。
品質検証
品質管理のうち、品質検証では、完成品の品質だけでなく原材料や部品が十分な品質基準を満たしているか検査します。
また、工程が品質を保てる能力を有しているかの検証や、適切な管理がなされているかの検証も行います。
品質改善
品質管理のうちの品質改善では、「再発防止」と「未然防止」の観点で改善を行います。
再発防止とは、すでに発生した事故などに対して、現状を把握し、原因を分析して再発防止策を講じることです。
未然防止とは、現在の生産方法や工程で将来起こりうるリスクを想定して、将来類似のトラブルや事故を未然に防ぐことです。
以下の記事では、品質管理を行う際に基本となるQC7つ道具について解説しておりますので、ぜひご参照ください。
QC7つ道具とは?製造業の品質改善を支える基本手法と活用事例を解説
また、以下の記事では生産管理の全体像について詳しく解説しておりますので、ぜひお読みください。
【生産管理のDX事例】工場での生産管理の仕事内容とは?生産方式別の特徴をわかりやすく解説 | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
製造業における予実管理とは
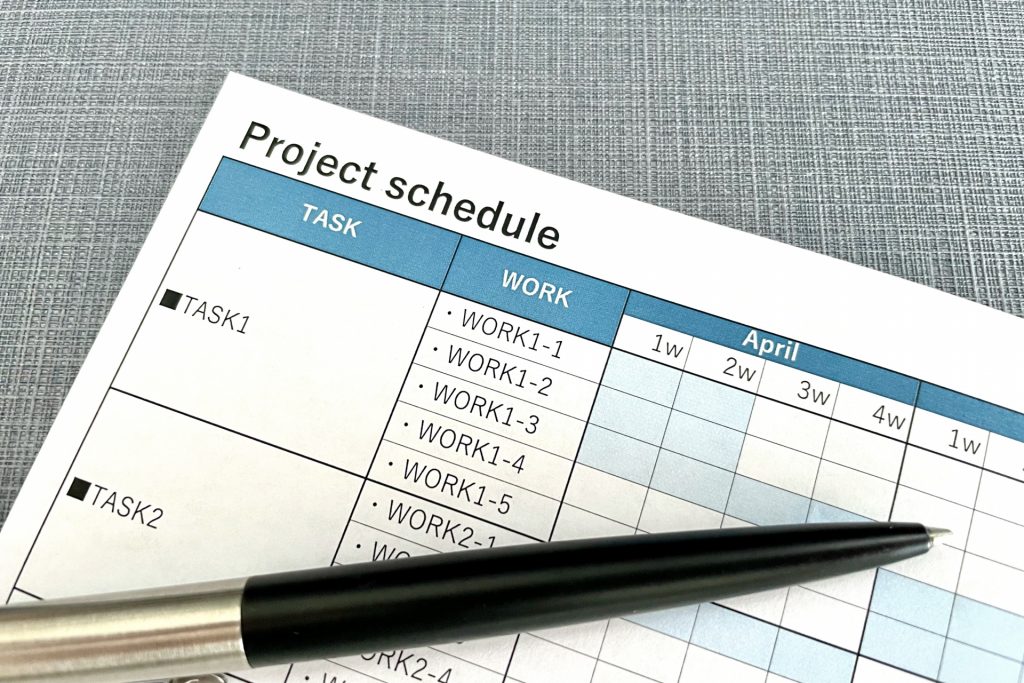
生産管理の基本について理解できたところで、本章では製造業における予実管理について理解を深めましょう。
製造業における予実管理とは、経理上の予算と実績の管理とは異なり、生産計画など事前に立てた予定と実績を比較・分析する手法を指します。
本章では予実管理の基本や目的、適切な予実管理を行うメリットについて解説します。
予実管理の基本
予実管理とは、計画と実績を比較し、差異を分析し、評価するプロセスです。
予実管理によって、経営戦略の見直しや生産工程の見直しを行い、生産効率の向上を目指します。
具体的には、以下のステップで予実管理を行います。
- 予定や目標の設定
- 定期的なモニタリング
- 予定と実績に差異があれば原因の特定
- 改善策の立案と実行
計画と実績のギャップを埋めることで、企業の目標達成に向けた効果的なマネジメントが可能です。
予実管理の目的
モノづくり企業において予実管理を行う目的は、主に以下の4点です。
- 計画の達成度合いの把握をするため
- 問題を早期に発見するため
- 迅速な軌道修正を行うため
- 工場全体の生産効率を向上するため
単に予定と結果としての実績を見比べて差異を分析するだけが予実管理ではありません。
計画の進捗をモニタリングしながら、問題の原因箇所を迅速に特定し、即時に対応し軌道修正を行うことも重要です。
また、生産管理においての予実管理は、工程管理における納期遵守の面でも重要ですが、他の業務においても予実管理を行うことが重要です。
例えば、調達購買においてもサプライヤーを決めて、契約書を交わして完結するわけではありません。
納入された製品や品質規格を満たしているか、事前の計画通りに数量、期日ともに納入が行われているか、行われていない場合には対処を行う必要があります。
生産管理はモノづくりにおいて全体の指揮役でもあるため、どの業務においても予実管理を行い、遅れや問題に対して迅速に対応できるように準備しておきましょう。
適切な予実管理を行うメリット
次に、適切に予実管理を行った場合のメリットについて解説します。
具体的には以下の5点のメリットがあります。
- 生産プロセスが最適化される
- コスト管理を徹底できる
- 納期遵守が強化される
- 品質向上につながる
- 意思決定を迅速にできる
以降で詳しく解説します。
生産プロセスが最適化される
予実管理が適切に行えれば、生産プロセスの最適化につながります。
なぜ予定通りに生産が行えないのか、理由を分析できれば生産工程のボトルネックを特定し、改善策を講じることで生産効率が向上します。
コスト管理を徹底できる
適切な予実管理を行えば、コスト管理が徹底されます。
各部門やプロジェクトにおけるコストの使い方が予算通りにできているかを定量的に把握し、無駄なコストの発生を抑えることで利益率が向上できます。
納期遵守が強化される
納期遵守が強化されることも予実管理のメリットの一つです。
定期的に計画と実績の差異を把握し、適切に対処できれば納期遅延のリスクが低減します。
品質向上につながる
予実管理は、品質に関しても適用可能です。
品質に関する予実管理としては、工程内検査の実施や、自工程完結を徹底して次の工程に不良品を流さないような教育を行うことで、不良品の発生を抑制します。
工程の最後で検査を行うよりも工程単位で予実管理を行えれば、結果として品質向上につながります。
意思決定を迅速にできる
予実管理が適切に行えれば、意思決定を迅速化できることもメリットと言えます。
予実管理ができていないと、モニタリングが適時行われておらず、結果的な予実の差異から原因を推測・分析して対策を行うため、是正対応に時間が掛かってしまいます。
「今期は目標達成できなかったので、来期は達成できるように」などと、実際にはタイムリーに対応できれば達成できた課題を長期に持ち越してしまうこともあり得ます。
したがって、予実管理を行いリアルタイムのデータ分析が行えれば、経営判断をスピーディに行えるメリットがあります。
製造業での予実管理の課題

前章では予実管理の概要やメリットについて解説しましたが、製造業では予実管理がスムーズに行えない課題がいくつか存在します。
製造業は生産プロセスが複雑で、多くの工程や資源が関与するため計画と実績の差異が生じやすい側面があります。
製造業での予実管理には以下の課題が挙げられます。
- 需要変動による計画の見直しが起きる
- 適正在庫が管理されていない
- 多品種少量生産による生産計画の複雑化
- 部門間の連携不足
- ヒューマンエラーによる手配ミス、誤発注
以降で解説します。
需要変動による計画の見直しが起きる
予実管理の課題として、需要変動が起きやすい点があります。
市場の需要が急激に変化すると、生産計画の見直しを行わなければなりません。
あらかじめ決めておいた生産計画を変更するのは単純ではなく、資源や人的リソースを再度組み立て、慎重に検討しなければなりません。
適正在庫が管理されていない
適正在庫の管理が徹底されていないことも予実管理における課題です。
過剰在庫や在庫不足はコスト増大や販売機会の損失につながります。
予実管理において、特に在庫不足が起きてしまうと軌道修正が極めて困難になってしまいます。
多品種少量生産による生産計画の複雑化
多品種少量生産では、予実管理が難しい側面があります。
同じ製品を大量生産すれば、生産工程に掛かる時間や人員配置も読みやすいものの、多品種少量生産の場合には段取り替えの問題や「一部の作業者しか行えない」といった属人化が起こりやすく、生産計画は複雑化します。
部門間の連携不足
部門間の連携不足も、予実管理を行う上での課題です。
納期管理の面での課題ももちろんですが、各部署や工程で個別に目標設定を行っており、全体として統一感のない予実管理となってしまうリスクもあります。
ヒューマンエラーによる手配ミス、誤発注
予実管理を行う上で、ヒューマンエラーが多発すると計画に大きく影響してしまいます。
しかし、手作業で行っている限りヒューマンエラーは低減できてもゼロにはできません。
ヒューマンエラーを予測してある程度の余裕を持たせた計画を立てることも大事ですが、手作業でのエラーの影響が大きい場合にはIoT機器やAI、ロボットなどの導入も検討します。
リアルタイムに状況を把握できていない
リアルタイムに状況を把握できていないのも予実管理では課題の一つです。
Excelやホワイトボードでの手入力でのデータや実績入力では、適切な予実管理が行えません。
例えば、計画に遅れが生じており挽回策を講じる際に、リアルタイムのデータを基に分析を行うのと、半日おきの手入力での作業件数を基に分析を行うのでは、リアルタイムのデータを用いた方がより効果的な挽回策を講じられるのは歴然です。
予実管理のための生産管理システム導入メリット

前章では、予実管理を行うにあたっての製造業ならではの課題をご紹介しました。
課題を解決するためには、生産管理システムの導入が最適な方法です。
本章では、予実管理のために生産管理システムを導入するメリットをご紹介します。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 工程進捗管理が可能
- ヒューマンエラーを削減できる
- 部門を超えて情報を一括管理できる
- リードタイム短縮につながる
- 適正在庫の管理が可能
- 適切な原価管理が行える
- 品質管理を適正化できる
工程進捗管理が可能
生産管理システムを導入すれば、工程進捗管理の負担が軽減されます。
リアルタイムで生産進捗を把握し、納期遅れのリスクに迅速に対応できます。
また、生産スケジュールの最適化機能が搭載されていれば、納期遵守率の向上も期待できます。
ヒューマンエラーを削減できる
ヒューマンエラーを削減できることも生産管理システム導入のメリットの一つです。
手作業での入力を最小限にし、手配ミスや誤発注などのヒューマンエラーを大幅に減少可能です。
さらに、自動発注システムが搭載されていれば、正確性と効率性が向上します。
部門を超えて情報を一括管理できる
生産管理システムでは部門の垣根を超えた、情報の一括管理が可能です。
製造業では、部門別に違うシステムを導入しており、他の部門の情報がブラックボックス化してしまうことがあります。
生産管理システムを導入すれば部門の垣根がなく「工数」「実績」「販売」「製造」といった状況を一元管理し、リアルタイムに情報にアクセスできます。
リードタイム短縮につながる
生産管理システムを導入すれば、発注から納品までのリードタイムを短縮できます。
滞留在庫や生産性、業務効率など工場全体の状況を分析できるため、不良品率の原因の解明や改善に役立ちます。
適切な改善策を行えるため、作業工数の無駄削減などリードタイムの短縮にもつながります。
適正在庫の管理が可能
生産管理システムによって、適正在庫を常に保てることもメリットです。
必要な在庫を確保しながら過剰在庫を防ぎ、在庫管理のコストを最小限に抑えられます。
生産管理システムでは販売・生産・在庫といった情報を一元管理でき、製品の在庫状況が可視化されます。
結果として、適正在庫の判断が容易になるため、機会損失を防ぎつつ、在庫管理コストを抑えられます。
適切な原価管理が行える
適切な原価管理に役立つことも生産管理システムを導入するメリットです。
製品ごとの詳細な原価計算を行えるため、工場全体の正確なコスト把握と分析が可能です。
収入と支出の合計額だけで管理するよりも、より正確にコスト管理が行えるため、収益性の改善や競争力の強化につながります。
品質管理を適正化できる
生産管理システムを導入すれば品質管理の適正化が行えます。
例えば、不良品発生の傾向分析や、工程ごとの品質データの収集・分析も可能です。
品質に問題があれば早期の発見と迅速な対応が行えるようになり、全体的な品質向上につながります。
以下の記事でも、生産管理システムについて詳しく解説しております。ぜひご一読ください。
生産管理システムとは?主な機能や導入メリット、選び方をご紹介 | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社
予実管理のための生産管理システム導入ステップ
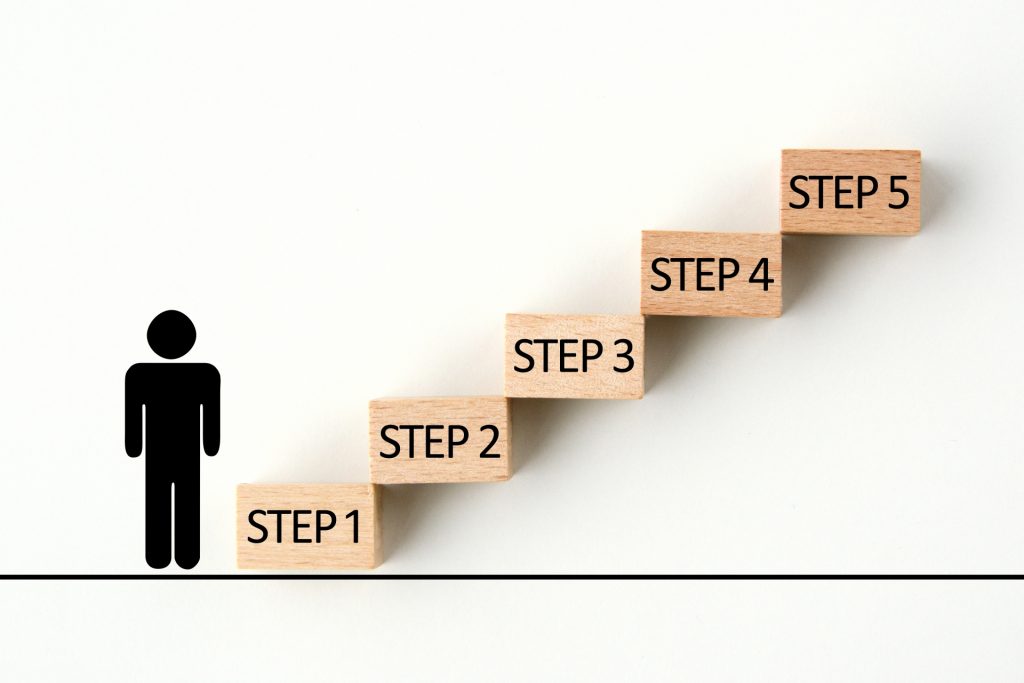
前章では、予実管理をより効率的に行うためには生産管理システムの導入が有効であることを解説しました。
本章では、予実管理のための生産管理システムの導入ステップについて解説します。
せっかく導入したにもかかわらず、現場作業の性質と合わずに定着しない例も少なくありません。
具体的には、以下のステップで導入するとより効果的な導入が可能です。
- 導入の目的を明確にする
- 全社で取り組む
- 自社に合ったシステムを選定する
- 全社で継続的に効果測定を行う
- 業務フローの見直しや改善を行う
詳しく見ていきましょう。
導入の目的を明確にする
まず、生産管理システム導入にあたって、目的を明確化しましょう。
目的が定まっていないと、システム選定に長期間掛けてしまったり、導入後に度重なるカスタマイズが必要となり時間とコストが掛かってしまうリスクがあります。
目的の明確化のためには、各業務のフローを整理し、現状の課題の洗い出しを行います。
そして業務ごとの課題を整理し、導入目的と求める機能を把握できれば、無駄のない導入計画を立てられます。
全社で取り組む
次に、全社プロジェクトとして取り組む体制を作ります。
経営陣だけで決めてしまうと、現場に即していないシステムの導入が行われてしまうこともあります。
生産管理システムは一部の部門や作業者だけが利用しても効果を最大化できません。
したがって、経営陣の意向と現場の課題を基に全体最適を目標としてプロジェクトを進めていく必要があります。
自社に合ったシステムを選定する
さらに、自社に合ったシステムを選定するのも重要なステップです。
自社の製品の特性や生産方式、特性に合ったシステムを選定します。
導入コストや実績だけにとらわれず、導入企業の事例や同業他社の導入状況などを分析、比較しながら検討を進めましょう。
全社で継続的に効果測定を行う
無事に生産管理システムを選定し、導入できれば、導入後はKPIを設定し、継続的に効果測定を行いましょう。
導入コストを回収するためにも、生産効率を上げて効果を出さなければ意味がありません。
さらに、継続的に効果測定を行うことで、導入効果だけでなく、生産性を上げるための改善策の精度も高まります。
業務フローの見直しや改善を行う
生産管理システムを導入し、無事に定着ができれば、実際の生産工程のフローの見直しや改善活動につなげます。
導入が目的ではないので、定着後には、選定時に挙げた課題を解決するためのヒント探しとして活用します。
顕在していた課題を解決し、さらにシステム導入の結果見えてきた課題も分析し、改善を行い常に利益を出せるように生産性向上のためのサイクルを回しましょう。
製造業において予実管理を効率化するその他の方法
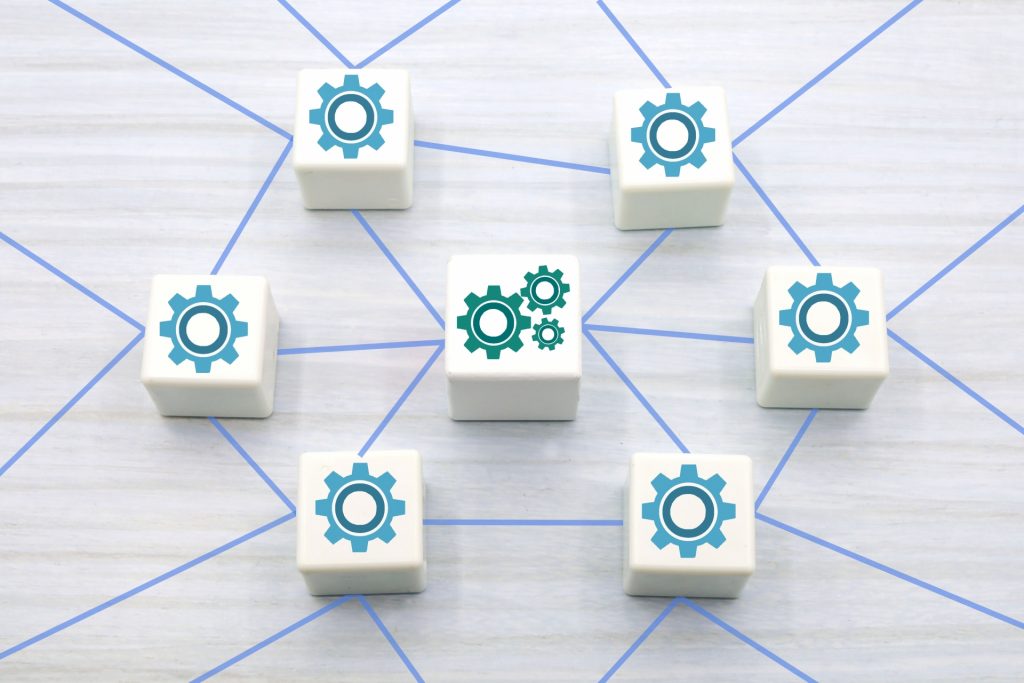
本章では、生産管理システムだけでなく予実管理を効率化する方法について解説します。
具体的には以下の方法があります。
- ボトルネック工程の洗い出しと改善
- IoTツールを活用したリアルタイムデータの活用、共有
- BIツールの活用
以降でご紹介します。
ボトルネック工程の洗い出しと改善
予実管理を効率化するためには、ボトルネック工程の洗い出しと改善も効果的です。
生産プロセスにおいてボトルネックを特定し、改善できれば、予実管理と相互的に生産効率向上につながります。
ボトルネック工程の見つけ方については、以下の記事でも詳しく解説しております。
IoTツールを活用したリアルタイムデータの活用、共有
予実管理をより効率的に、かつ正確に行うためにはIoTツールによるリアルタイムデータの活用が有効です。
現場のデータをタイムリーに収集し、即座に分析できれば、異常の早期発見や迅速な対応が行えます。
具体例を挙げると以下の通りです。
- IoTセンサー導入により、機械の稼働状況や温度、振動などを常時モニタリングし、異常値を検知
- デジタルディスプレイやダッシュボードを活用し、現場の状況をリアルタイムで表示
- アラートシステムにより、異常検知されたら即時通知を可能にする
- データ分析ツール活用により、パターン認識や異常検知を自動化する
リアルタイムデータを活用できれば、生産ラインの状況を常にモニタリングし、問題が発生した場合の影響も最小限にして効率的な予実管理が可能です。
BIツールの活用
BIツールの活用も、予実管理を効率化できます。
IoTツールを活用した現場データを取得、蓄積できる体制を作ったとしても、分析のための時間が取れずに改善につながらない企業も少なくありません。
データをBIツールで可視化すれば、現場だけでなく経営層まで同じ情報を共有できます。
現場の分析作業を待つことなく、迅速で正確な意思決定にもつながります。
適切な予実管理のためには生産システム導入が有効

本記事では、製造業における予実管理について、生産管理の業務についても踏まえながらメリットや課題、適切な管理を行うための生産管理システム導入などを解説しました。
予実差異を的確に把握し、改善につなげることで、生産性向上や品質向上、コスト削減を同時に実現できます。
しかし、需要の変動や部門間の連携不足など、現場では多くの課題が存在します。
解決のためには生産システムの導入が有効ですが、目的を明確にし、全社的に継続して改善を進めることも重要です。
以下のホワイトペーパーでは、生産システムの導入や乗り換えのポイントについて解説しておりますので、ぜひご一読ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
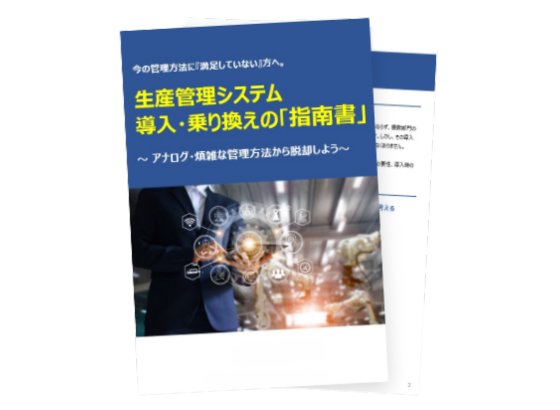
今の生産管理方法に不満がある、という方へ。
生産管理システム 導入・乗り換えの「指南書」