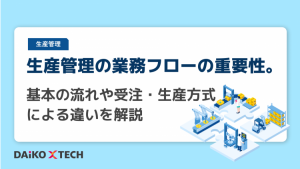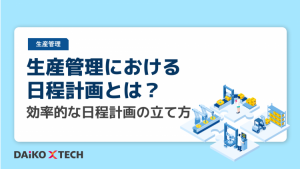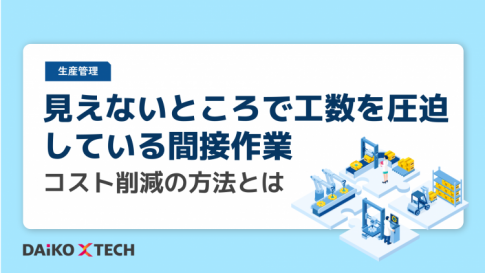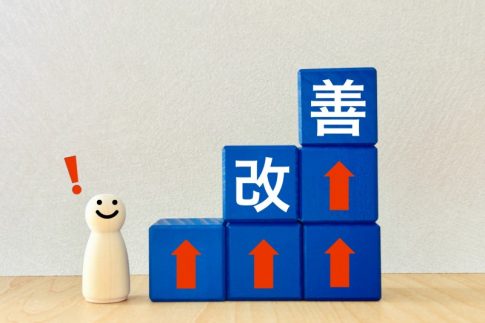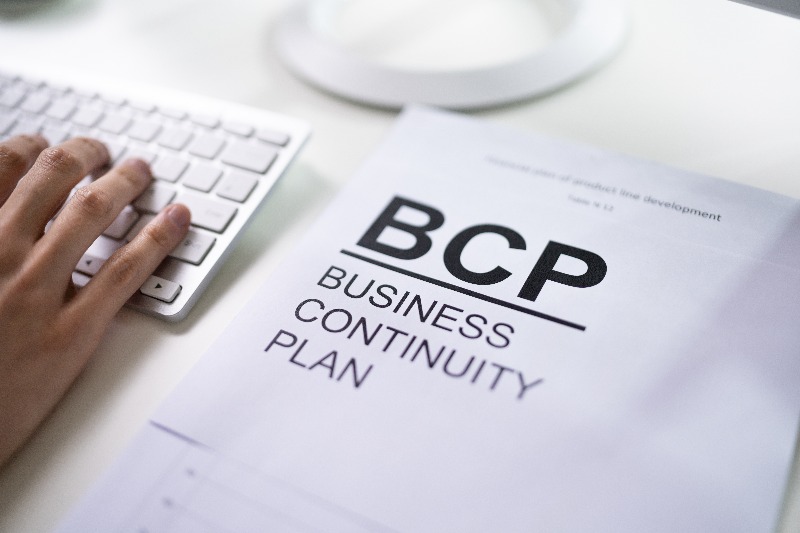工程管理とは、製造工程に関わる「製品づくりの進行を管理すること」を指します。多くの製品を効率的に生産するためには、工程管理の見直しが必要です。本記事では、工程管理の概要だけでなく、管理の方法や効率化のポイント、システム導入時のメリットなどもご紹介します。
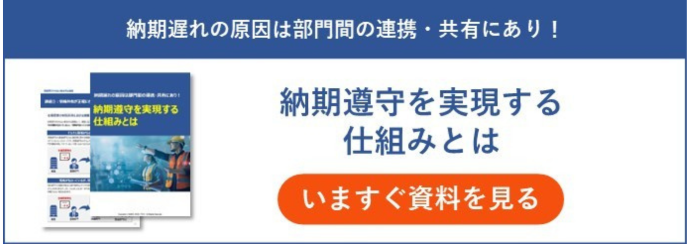
目次
製造業における工程管理とは

工程管理とは、製造工程に関わる「製品づくりの進行を管理すること」を意味します。材料の加工・運搬・検査など製造工程のすべてが対象です。そして、これらの工程は、作業員・機械・作業方法の三要素によって成り立っています。
以下では、工程管理の目的や、重要な理由、よく似た概念である生産管理との違いについて、ご紹介しています。内容の違いを明確にして工程管理を理解しましょう。
工程管理の目的
工程管理の目的とは、製品の品質・数量・製造期間などを適切に保ち、効率的に製造することです。
具体的には、管理の進捗状況や生産計画に関する情報が部署間やチーム間で常に共有されることで、人員の配置や工程の段取りを最適化することが可能になります。これにより、製品の品質を保持しつつ、作業に必要な期間の短縮が可能となり、さらに無駄な在庫(製造途中の在庫)をコントロールすることで、管理にかかるコスト削減も可能となります。
工程管理が重要な理由
進捗状況や計画に関する情報が部署間やチーム間で常に把握・共有できていない場合、納期の遅れによる信頼の低下や人手不足といった現場課題を認識することができず、社内外に悪影響を及ぼす可能性があります。また、昨今はお客さまや株主などから、企業活動が厳しく監視されているため、品質の維持や適切な作業配分を行うことが重要です。
そのため、生産計画を立て、進捗状況や計画に関する情報を部署間やチーム間で共有し合い、生産活動を円滑に進めることが求められています。
生産管理との違い
工程管理と生産管理では、管理している範囲に違いがあります。両者ともに製造に関わる内容ですが、工程管理は納期の管理を中心にしているのに対し、生産管理は生産ライン全体といったより広い工程範囲をカバーします。生産管理の扱う範囲は、販売計画から材料の仕入・製品の出荷・売上管理まで、製品に関わるすべての流れを管理します。つまり、生産管理の範囲の一部に工程管理が含まれています。
生産管理については以下記事でご紹介しています。ぜひご覧ください。
製造業において工程管理の可視化が求められる理由

上記でご紹介した、工程管理を行うためには、工程の「見える化」が必要となります。
見える化が必要になる理由は「情報の共有」「納期やスケジュールの把握」「トラブルへの迅速な対応」の3つです。以下ではそれぞれの詳細についてご紹介します。
情報の共有
生産や受注案件は複数のメンバーで進められているため、作業状況を各チームが報告し、情報を共有することで、進行状況を把握することができます。また、情報の共有ができることで、遅れているチームに人員を増やすなどの対策を立てることができます。
納期やスケジュールの把握
各メンバーが何時間かけて作業を行っているのかを把握することができます。これにより、計画していたスケジュールから遅れがある場合、早めに調整・対策を行うことが可能です。また、立案したスケジュールに無理や無駄がないか目視で確認できるため、遅延を防止することも可能です。
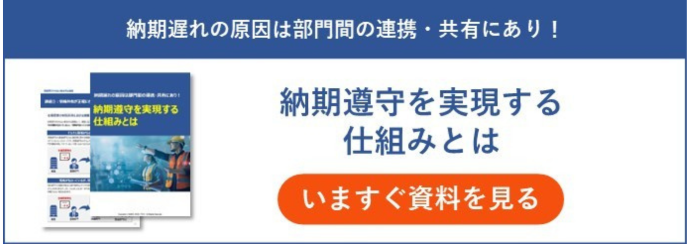
トラブルへの迅速な対応
設備の故障や仕入の遅延などのトラブルにスムーズに対応するためには、現場の状況や進捗状況を常に把握し、各工程を管理することが重要になるため、工数管理を見える化することが求められています。
トラブルにはさまざまな種類がありますが、他にも、手戻り作業発生による特急対応があります。工程を可視化しておくことで、手戻り作業の発生を防いだり、早い段階で手戻りがありそうかを予測したりすることが可能です。
製造業の工程管理の基本手順

工程管理を効率化していくためには、PDCAサイクルを徹底することが重要です。PDCAとは、Plan=計画、Do=実行、Check=確認、Action=実施であり、各4つの段階について注意するべきポイントをご紹介します。
1.計画を立てる
工程管理を効率的に行うためには、データに基づいて事前に計画を立てることが重要です。過去の製造にかかった期間・得られた生産数・発生した不具合とその解決にかかった時間などを総合的に考慮して、計画を立てましょう。
2.計画に基づき実施する
計画に従い、段取りを整えて製造を進めます。個々の段階では、計画通りに進めることに加え、計画外の問題を見つけ出すことも重要なポイントです。計画を実施していく中で、事前の想定と違っていた箇所や、新たに発生した問題を書きとめて、次の評価工程に役立てましょう。
3.結果を評価する
計画を実行に移した結果、計画通りに進行できたかどうか、総合的な評価を行います。できなかった場合は、何が原因だったのかを調査し、改善案を作成することが必要です。この段階では、現在の進捗を把握し、遅延などの不具合が発生している工程はないか、状況を正確に認識することがポイントとなります。システム導入による情報の一元化など、現場の状況を集約できる仕組みを整えておきましょう。
4.改善案を実施する
改善点を発見し、改善案を実行に移します。実行した後は、改善した結果を次の計画に取り入れましょう。最初に立てた計画にこだわり過ぎず、状況に合わせて柔軟に対応していくことが重要です。ポイントとしてPDCAサイクルは一度だけ行うのではなく、繰り返し行うことで継続的に作業を見直していく必要があります。改善案を基に、新たな計画を立て、作業工程をより効率化していきましょう。
工程管理の3つの手法

工程管理を行うためには、進捗状況を把握できる仕組みが必要です。
以下では、工程管理の3つの方法とそれぞれの特徴についてご紹介します。
方法①:紙やホワイトボードを使用する
紙やホワイトボードなどにチャート形式で貼りだす方法は、専用のツールやシステムを使わないため、コストを低く抑えやすいことがメリットです。その代わりに、リアルタイムでの正確な情報共有には不向きであり、過去データとの比較が行いにくい点がデメリットです。
方法②:Excelやクラウドを使用した管理
ExcelやGoogleのスプレッドシートで管理する方法は、上記同様に、専用のツールやシステムを使わないためコストが抑えられることや、テンプレートを制作することで効率化を図ることがメリットとして挙げられます。スプレッドシートでの管理の場合、リアルタイムに情報共有ができることが挙げられます。
一方で、Excelは同時編集ができないため同じチームのメンバーが編集をしていないかを確認しながら進めたり、ファイルを別で保存したりと手間がかかります。
自動化には限界があるため、プロジェクトの規模が大きくなるほど収集や集計が困難になります。
特に、多数のタスクや長期的なスケジュールを含むプロジェクトで使われるのが、「バーチャート工程表」と「ガントチャート工程表」です。詳しくは以下のリンクも参考にしてください。
参照記事:工程管理をエクセルで行う方法|工程表の種類から作成方法を徹底解説
バーチャート工程表
バーチャート工程表は、プロジェクトの各工程や作業を縦軸に、時間経過を横軸に配置した棒グラフ形式の工程表です。作業の開始から完了までの期間を横棒で表示し、シンプルな視覚化で全体の進捗状況を把握できます。
バーチャート工程表の特徴は、作業の進捗状況が一目で分かりやすく、シンプルで理解しやすい形式である点です。また、複数の工程が同時に進行する並行作業の状況も容易に理解できます。
ガントチャート工程表
ガントチャートは、バーチャートを発展させた形式で、タスク間の関連性や依存関係も表現できる工程表です。
特徴として、タスク間の依存関係を矢印で表現でき、各作業の進捗率も表示可能です。重要な節目となるマイルストーンの設定もでき、ある作業に遅延が生じた場合に、他の工程にどのような影響が及ぶのかを視覚的に把握できます。
参考情報:工程管理を劇的に変えるガントチャート!基本から応用までを徹底解説
方法③:工程管理のシステム化
工程管理のシステム化では、機能単体で工程管理システムが販売されていることもあれば、生産管理システムなど上位システムの一機能として販売されていることもあります。工程管理をシステム化することで、タスクの進捗状況が目視で確認できたり、アラート機能や権限設定などの多様な機能を使用したりできます。
工程管理表とは違い、過去のデータから現在の進捗状況までの管理について一元化が可能なため、正確に状況を把握することができます。また、信頼できるシステムや、権限設定を行えば、セキュリティ面でも安心できます。
このように、工程管理をシステム化すれば、紙やExcel、クラウドでのデメリットをカバーすることが可能です。
次章では、工程管理システムを導入することで得られるメリットについて、より詳しく説明します。
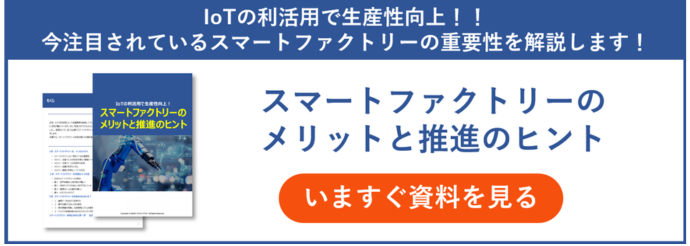
製造業が工程管理システムを導入するメリット

製造業が工程管理システムを導入するメリットは次の3点です。
- 計画の変更やイレギュラーに対応しやすい
- 人的ミスの回避につながる
- 業務効率化につながる
以上について解説します。
メリット①:計画の変更やイレギュラーに対応しやすい
工程管理システムを使用することで、複数のタスクのスケジュールや担当者、現在の進行状況など多くの情報を可視化することが可能です。計画に変更があったり、イレギュラーが発生したりした場合でも、すぐに「いつまでに、誰が、なにをする」といった詳細情報を共有ができるため、対応がしやすいです。
また、メンバーが休んでいるときや、急な退職をしてしまった場合でも、タスクの引継ぎが行いやすいです。
メリット②:人的ミスの回避につながる
工程管理では、小さなミスが大幅な遅れや大きな失敗につながる可能性があるため、人の手で管理する箇所を減らすことが重要です。工程管理システムを使用して、複数メンバーで全工程の管理表を共有できていれば、誤入力や入力漏れにいち早く気づくことが可能です。
そういったミスをなくしていくことで、チームのパフォーマンス向上や顧客満足度の向上にもつながります。
メリット③:業務効率化につながる
工程管理システムの構築時に、細かいタスクまで洗い出せれば、「あるけど、なくてもよい」慣行作業を減らすことができます。また、大規模なプロジェクトに取り掛かる場合や、社内のメンバー数やクライアント、外注先と関与者が多くなる場合には、メール・FAX・電話でのやり取りを減らし、ムダな業務時間を削減することが可能です。
これにより、組織全体の生産性向上につながります。
システム化のメリット・デメリットについては以下の記事もご覧ください。
工程管理ツールの選び方|導入するメリット・デメリットを徹底解説
製造業の工程管理における課題と解決策

製造業の工程管理において、多くの企業が「進捗状況の把握が難しい」「品質とスピードにばらつきがある」といった課題に直面しています。これらの工程管理の課題を放置すると、生産性の低下や納期遅延、品質のムラなど、さまざまな問題を引き起こす原因になりかねません。ここでは、工程管理における主な課題と解決策について、具体的に解説します。
品質とスピードにばらつきがある
製造業において、作業者によって品質とスピードにばらつきが生じることは、生産性と製品品質に大きな影響を及ぼします。作業手順が明確に標準化されていないことや、従業員間での技術レベルの差異によって発生する場合が多く、結果として生産効率の低下や品質のムラを引き起こしています。
従来の管理方法では、各作業者の経験や判断に依存する部分が大きく、同じ工程であっても作業者によって作業時間や完成品の品質に差が出るのは避けられません。特に熟練作業者と新人作業者の間での技術格差は、生産ラインの安定性を損なう要因です。全体の生産計画にも支障をきたす場合があります。
これらを解決するためには、まず作業手順の標準化が不可欠です。誰が作業を行っても同じ品質とスピードで生産できるよう、作業手順を明確に文書化し、それに基づいた教育・訓練を実施することが重要です。標準化された手順の導入により、作業者間のばらつきを最小限に抑え、安定した生産活動を実現できます。
現場にとって生産プロセス全体の最適化も重要な取り組みとなります。各工程でのボトルネックを特定し、改善策を実施すれば、生産ライン全体の効率を向上できます。例えば、作業の難易度が高い工程を特定し、作業補助システムの導入や治具の改良を行うと、熟練度に関係なく安定した作業が可能です。
生産管理システムを活用すると、各工程での作業時間や品質データをリアルタイムで収集・分析できるようになり、問題が発生した際にはすぐに原因を特定して対策を立てられます。製品の品質を一定に保ちながら、生産効率の向上が可能です。また、収集したデータを基に継続的な改善活動を行えば、さらなる品質とスピードの安定化を図れます。
次章では、工程管理システムを選定する際に気を付けるべきポイントをご紹介します。
製造業向けの工程管理システムを選ぶ際のポイント

工程管理システムを選ぶ際には、次のポイントをおさえましょう。
- 人と設備の負荷状況を管理できるか
- 複数プロジェクトを横断的に管理できるか
- カスタマイズが可能か
- 他のシステムと連携できるか
各項目を詳しく解説します。
人と設備の負荷状況を管理できるか
製造業の現場では、納期に目が奪われがちですが、「人や設備に負荷がかかりすぎていないか」「負荷の偏りがないか」を確認することも重要です。ある程度の時間が経過すると、忙しい人と時間に余裕のある人に差が出てきてしまうため、負荷の状況を可視化・分散化できる機能があるとよいでしょう。
複数プロジェクトを横断的に管理できるか
リソースが偏っている時は、優秀な人材や高性能な設備が取り合いになっている状態、つまり複数のプロジェクトが同時に進行していることが多いです。そのため、複数のプロジェクトを横断的に確認できる機能があるとよいでしょう。プロジェクトごとの負荷状況を確認して、分散化を行うことが可能です。
カスタマイズが可能か
工程管理システムを導入する際は、始めはシンプルな機能を選択し、必要に応じて機能を追加するとよいでしょう。そのため、カスタマイズ度が高いシステムを選定すると、導入がスムーズに行いやすいです。
他のシステムと連携できるか
工程管理システムを運用する際は、生産管理や販売管理、購買管理、在庫管理など既存の他システムと連携できるものを選択すると、効率化が期待できます。特に製造業では、サプライチェーンにおける一連の流れを管理することが重要になるので、システム連携できるかどうかは大事です。
ただ、既存システムが古いと連携できない可能性があります。その場合、工程管理システムを提供する会社が、他の管理システムを同時に提供していたり、システムが統合されたものを販売していたりするので、一括で新しいシステムを導入するのもおすすめです。
製造業向けの工程管理システムは、rBOMにお任せください

ここまで、工程管理の基礎知識から、システム選定のポイントまで詳しくご紹介しました。
製造業において業務を効率化させ、お客さまの満足度を向上させるためには、第一歩として工程管理システムの導入が欠かせません。
工程管理だけでなく、生産管理・購買管理・在庫管理などさまざまなシステムを包含または連携できる「rBOM」がおすすめです。製品を製造するために必要な部品表に、部品ごとや製品ごとの制作工程を追記できます。工程ごとに納期情報を与えることができるため、進捗を簡単に確認することができます。
また、納期の設定時にはガントチャートを使用することができるため、従来の管理でガントチャートを使用していた方でも早く慣れることができます。負荷の把握も一緒に行えるため、管理も簡単です。
「社内で紙やExcelを使用して工程管理を行っており、自動化したい…」
「社内システムのカスタマイズが複雑化しており、属人化している…」
「業務を効率的にして、価値ある業務に人員を割きたい」などの課題をお持ちの方は、ぜひ以下資料から「rBOM」の詳細をご覧ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
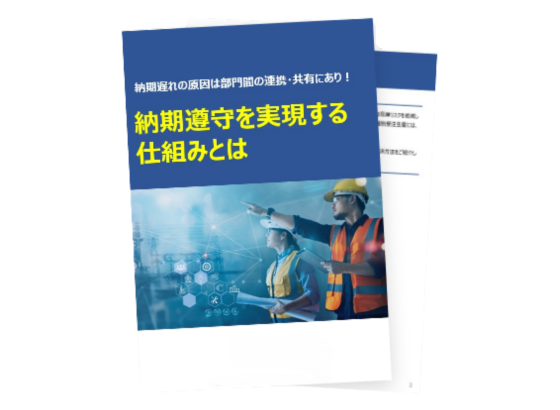
納期遅れの原因は部門間の連携・共有にあり!
納期遵守を実現する仕組みとは

- この記事を監修した人
- 入社後15年間、長野支店にてシステムエンジニアとして活動。
運送業、倉庫業のお客さまを中心に担当し、業務システム構築からインフラ環境構築等の経験を積む。
その後、製造業のお客さまも担当し、rBOM導入のプロジェクトにも関わるように。
16年目に現部門に異動し、rBOM全国支援の担当者となる。
現在はrBOMだけではなく、製造業全般のソリューション提案を手掛けている。
料理が趣味、これからお菓子作りにも挑戦しようか迷っている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部 - 田幸 義則