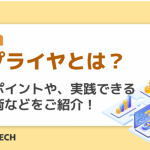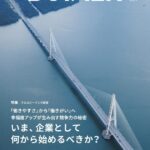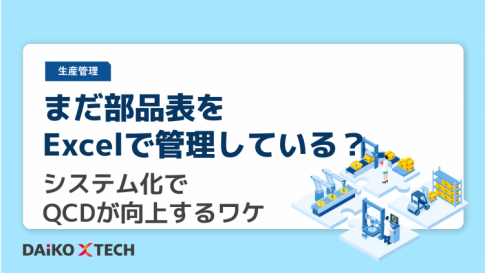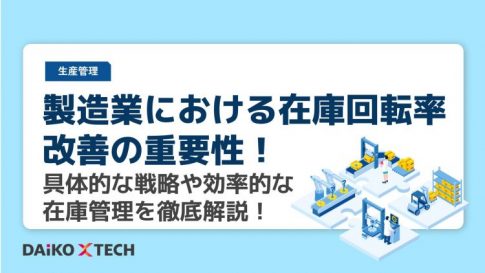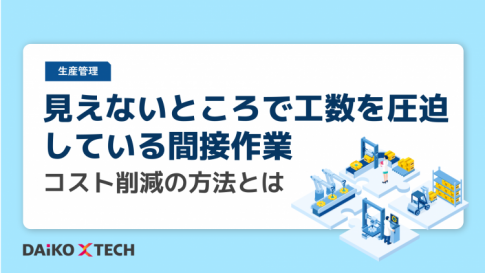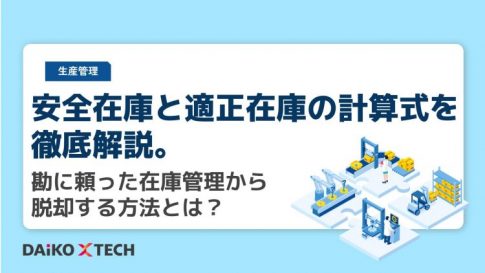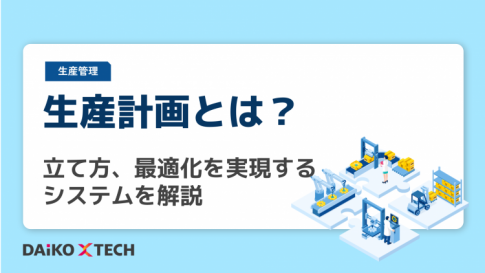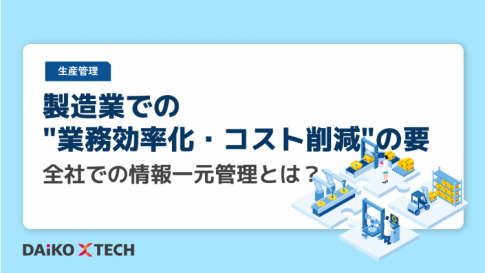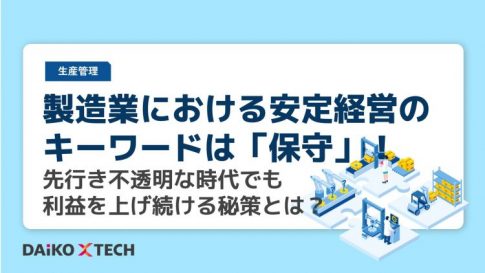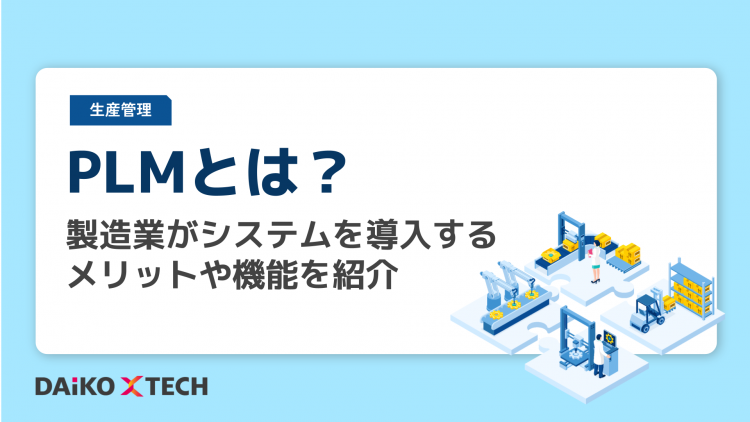
PLM(Product Lifecycle Management)とは、製造業において製品のライフサイクル全体を管理する手法のことです。労働人口の減少や景気悪化など、製造業界を取り巻く現状が厳しくなっている中でPLMは企業の競争力や売上向上に有効な取り組みとして注目を集めています。
本記事では、PLMの概要や機能に加え、PDMとの違い、導入で得られるメリットをご紹介します。
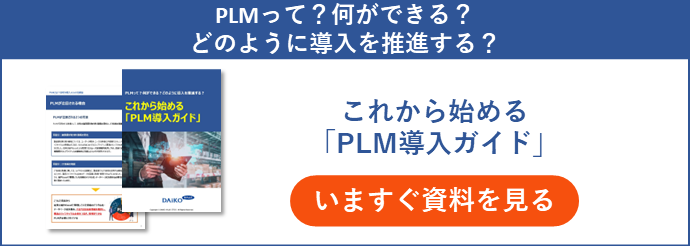
目次
PLMとは
 ここではPLMの概要や目的、注目される背景について解説します。
ここではPLMの概要や目的、注目される背景について解説します。
PLMの概要
PLMとは、自社製品の企画から設計開発、製造、販売、保守までのライフサイクル全体を一体的に管理する手法です。
企画や生産、販売といった各プロセスを相互に関連付け、共有することで業務プロセスの効率化やモノづくり体制の強化を図ることができます。またPLMに取り組むことで、製造の前段階から製品の解体や廃棄、もしくはリサイクルまで考慮した設計・開発を行えます。
航空・宇宙産業や自動車産業からはじまり、電機産業や産業機器業界などを含め、幅広い業界で導入が進んでいます。
PLMの目的
PLMの目的は、市場の変化やニーズの変容に対応した高付加価値の製品を他社に先駆けて創出、市場投入することで、業務効率や開発力、企業競争力の強化をすることにあり、企業の存在価値を高めるために重要な役割を果たしています。
企業力強化のためには、常にQCDの改善により利益を最大化させたり、市場やニーズの変化に対応して短期間かつ低コストで高品質の製品を生産したりする必要があります。これらは、ライフサイクル全体を一元管理し、各部門の連携を促すことができるPLMによって実現できます。
QCDとは
PLMによって企業力を強化する際にカギとなるのが、QCDです。QCDとは、PLMを向上させるキーファクターである品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)の頭文字を取った言葉です。
|
品質(Quality) |
・不良品発生率を低減して品質基準を遵守する ・顧客満足度を満たす商品を提供する ・従業員の意識品質を向上させる |
|
コスト(Cost) |
・製造原価を低減して原材料費を最適化する ・工程の自動化・効率化により人件費を最適化する ・在庫の管理適正により時間のムダを排除する |
|
納期(Delivery) |
・予測の精度を向上させた上で生産計画を立てる ・リードタイムを短縮してサプライチェーンを効率化する ・突発的な注文への柔軟な対応力を強化する |
QCDはトレードオフの関係を持ちます。例えば、品質向上のために製造ラインの設備に投資するにはコストが必要です。
また、納期短縮のために検品コストを割くと、不良品発生率が上がり顧客満足度の低下を招きます。PLMの体制を強化するには、QCDのバランスを最適化することが重要です。
PLMシステムによって製品のライフサイクル全体を効率的に管理することは、QCDを改善する手助けにつながります。
PLMが必要とされる背景
先述したようにPLMが必要とされる背景には、近年の製造業を取り巻く環境の変化と、IT技術の発展があります。
製品の品質向上やブランド価値が、製造業にとってますます重要になっており、消費者の多様なニーズや急速に変わるトレンドに対応するため、効率的で一貫したプロセスが求められています。
従来の紙やExcelによる管理では、これらの変化に迅速に対応することが困難であり、製品ライフサイクルの短縮が進む中、製品の各段階での情報共有や品質管理がさらに重要になってきています。
こうした状況下で、製品開発から製造、市場投入、廃棄までの全ての段階でデータを一元的に管理し、品質を維持しながらブランドを強化できるPLM(製品ライフサイクル管理)システムの導入に注目が集まっています。
PLMは、情報のデジタル化とデータベース化を通じて、製品情報を集約し、一貫した品質管理と迅速な市場対応を実現します。
PLMでは、設計・開発部門や製造部門など、部署間でのデータ連携・情報共有を進めることで、入力の二度手間や情報のタイムラグを減らしつつ、データや状況を正確に共有することが可能です。
上記のように、情報を正確かつ迅速に伝えられる環境を整えることで、品質向上やコスト削減につながり、国内製造業の製品開発力強化を図ることができます。
PLMとPDMの違い

PLM(ProductLifecycleManagement)とPDM(ProductDataManagement)はいずれも製品情報を管理する仕組みですが、その対象範囲と役割には明確な違いがあります。
PDMは主に設計・開発部門の情報管理に特化しているのに対し、PLMは製品の企画から設計、製造、販売、保守・廃棄に至るライフサイクル全体をカバーします。
つまり、PDMは設計データの一元管理手法であり、PLMは事業全体を支えるライフサイクル管理基盤として進化したものです。
PDMとは
PDM(製品データ管理)は、1990年代に普及した製品設計情報の一元管理手法です。CADデータや設計部品表(BOM)、図面、技術ドキュメントといった設計開発部門の情報をまとめて管理し、流用設計やチーム設計を容易にしました。
主な機能には以下が含まれます。
- CADやBOMデータの同期
- 変更管理・ワークフロー管理
- データ検索機能
これにより、設計業務の効率化やプロセスの標準化が実現し、製造現場のリードタイム短縮やコスト削減に貢献してきました。
PDMが普及した背景
PDMが広く普及した背景には、当時の製造業が直面していた課題があります。1990年代は大量生産・大量消費が前提であり、企業にとっていかに安く、速く、多く生産し、安定供給できるかが重要でした。
そのため、開発・設計の効率化とリードタイム短縮を実現するPDMは大きな役割を果たしました。設計データの再利用や設計変更管理が容易になり、製造業全体でのQCD(品質・コスト・納期)改善に直結しています。
PDMからPLMへ
2000年代に入ると、製造業を取り巻く環境は大きく変化しました。グローバル化の進展や消費者ニーズの多様化により、単なる設計効率化だけでなく、市場変化への迅速な対応や製品ライフサイクル全体の最適化が求められるようになっています。
この流れの中で、PDMの枠を超えて各部門の情報を横断的に統合する仕組みとしてPLMが登場しました。結果として、企業は部門間の連携を強化し、QCD改善や顧客満足度向上を通じて競争力を高められるようになりました。
PLMシステムとは

PLMシステムとは、製品の企画、設計、調達、製造、販売、廃棄に至るまでのライフサイクル全体にわたる情報を、社内で一元的に管理・共有するための仕組みです。品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)を最適化し、製造業の競争力を高めるために活用されます。
従来のPDMが主に設計・開発段階のデータに特化していたのに対し、PLMシステムは対象範囲を拡大しています。製品ライフサイクル全体をカバーすることで、業務効率化、品質向上、コスト削減、さらには顧客満足度の向上まで実現できるのが大きな特徴です。
また、PLMシステムは部門間の情報共有不足やスキルの属人化といった課題を解消し、グローバルな市場における競争力強化を支援します。企業全体での情報の見える化や連携を促進することで、迅速かつ柔軟な意思決定を可能にし、DXを推進する重要な基盤となります。
PLMシステムの導入によるメリット

PLMシステムを導入することで、以下の4つのメリットが期待できます。
- 品質向上
- リードタイムの短縮
- コスト削減
- 信頼性の向上
それぞれ解説します。
品質向上
PLMシステムでは各プロセスで取得・収集したデータを分析し、情報を一元的に管理・共有することができます。一元的な管理によって不具合をすぐに発見・修正でき、更にワークフロー全体を最適化できるため、製品の品質向上につながります。
リードタイムの短縮
PLMシステムによって製品に関するデータを一元的に管理することで、全体のリードタイム短縮が可能です。
全てのデータと情報がシステム上で管理されるため、調達や発注の適切なタイミングを把握するだけでなく、見積業務を短縮したり、部品やアセンブリなどの標準化を促すきっかけになったりと、製造工程全体の効率化が図られます。
例えば、実際に車を衝突させる実機検証をシミュレーションで行ったり、手書きの図面設計を3次元CADに置き換えたりすることで、効率化を図ることができます。
消費者の多様化や市場のトレンドの変化に対応するためには、PLM活用によるリードタイムの短縮で、生産から製造、納品までのオペレーションを頻繁に変更できることが必要です。
コスト削減
PLMシステムを導入することで、製品開発から生産に至るまでの各プロセスにおける人件費や原材料費などのコストを詳細に把握することが可能になります。また、他部門との情報共有、過去の不具合などの製品の品質情報や製品構成データ、原価実績の把握を通じて、次回の製品開発に生かすこともできます。これにより、長期的な視点でのコスト削減が実現します。
さらに、PLMシステムによるバーチャル環境での施策展開やシミュレーション機能を活用することで、業務プロセスの効率化が進み、時間短縮はもちろん、人件費の削減も図れます。
信頼性の向上
PLMシステムの導入はトレーサビリティの体制の強化につながります。これにより、商品・サービスの品質が高まり、取引先から自社への信頼性向上につながります。例えば、システム上でシリアルナンバーを共有すると、製品ごとの設計変更履歴や試験データを即時抽出することが可能です。
万が一不良品が発生した時には、追跡と改善に必要な時間も短縮できます。したがって、PLMシステムを導入している企業は、顧客満足度を高められ、競合他社との差別化につながることがメリットと言えます。
市場ニーズの反映
製造業では市場変化のスピードが年々加速しており、需要の高まりに合わせて迅速に製品を供給する力が求められています。従来の開発プロセスでは、製品企画から市場投入までに時間がかかり、投入時にはすでに市場ニーズが変化しているケースも少なくありませんでした。
PLMを導入することで、製品に関する情報が企画から設計、製造、販売まで一元的に管理されます。営業部門が収集した市場動向や顧客の声を速やかに設計部門へ共有できるため、市場が求める製品をタイムリーに反映した開発が可能です。
リードタイムの短縮によって、需要が高いときに需要のある製品を投入できる体制を整えられる点も大きな強みです。市場ニーズに応じた柔軟な製品開発と供給の実現が、競争力の向上につながります。
PLMシステムの機能

PLMシステムは、製品ライフサイクルの各工程で必要となる多様な機能を持っています。
今回は、製造業の設計部門を中心とした、「企画構想・開発」、「製品設計」、「工程設計」、「設備設計」、「生産準備」までを含めたエンジニアリングチェーンに着目し、各業務における主なシステム機能をご紹介します。
CAD
CADとは、「ComputerAidedDesign」の略で、従来ドラフターなどを用いて手書きしていた製図の設計作業を、コンピューターで効率的に設計できる機能です。
2次元だけでなく3次元で行うこともでき、3次元設計データは組み立て業務や生産ラインシミュレーションにも活用することが可能です。
CADソフトウェアは、分野別に機械用、電気用、建築用、建築設備用、土木用向けなどの専用CADがあります。
CADは図面をデータとして扱えるため、これまでの紙図面では難しかった膨大な図面の中から類似図面情報を検索することが容易になりました。
2DCAD、3DCADそれぞれにメリット、デメリットがありますが、製造業のDX推進が求められる近年では、3DCAD設計及び3Dデータ活用がデジタルエンジニアリングの中核になります。
3D設計の基本やメリット、導入時の注意点を確認しておきたい方は、以下の記事をご覧ください。
自動設計
自動設計は、製品やユニットの標準化を図ることにより、製品仕様を入力するだけで見積図面や3Dモデル、見積書などの設計成果物を自動生成できます。そのため、設計の業務効率化を図ることが可能です。
また設計業務では、「図面での要求事項の打合せで、認識や仕様に齟齬が生じてしまう」「業務が属人的になっており、設計品質にバラツキができてしまう」といった課題が生じやすいですが、自動設計では製品仕様を入力すると自動的に成果物を出せるため、正確な図面による業務の効率化が期待できます。
このように、CADを応用させた最新技術である自動設計は、スピード設計や仕様の早期確定、均一品質・見積、そして短期納品などを実現できます。
解析
解析(CAE)は、「ComputerAidedEngineering」の略で、従来手計算で行われていたものをコンピューターで各種解析を行うエンジニアリング機能です。
解析の種類には構造解析、流体解析、数値解析などがあり、構造解析には主に、応力解析、振動解析、熱伝導解析などがあります。
以前は、解析専任者が業務を主に対応していましたが、現在では「設計者向け構造解析」が登場しており、設計者自身が製品の強度、振動、熱に関する評価を行えます。
これらの性能確認は、実際に試作や試験を行わなくても計算・シミュレーションによって結果を得られるため、開発期間の短縮やコスト削減、環境負荷軽減といったメリットがあります。
CADデータ管理
CADデータ管理は、単にデータを整理するのではなく、管理を行うことで設計時に必要な対象データの検索が容易になりムダな工数・時間を省けます。
従来の2D図面の管理はWindowsエクスプローラのフォルダで対応可能でしたが、3D設計が進むにつれ、データの整合性や版数管理など管理が複雑化し、Windowsエクスプローラのフォルダ管理では限界がきています。
また、コンカレント開発が重視される中、設計データの早期共有、チーム設計、部品共通化、標準化が必要とされ、取引先毎の複数のCADシステムを管理する必要性が更に高まっています。
設計部品表管理(BOM管理)
設計開発業務を進める上で技術情報の核となるものが、設計部品表(E-BOM)です。E-BOMを中心に部門毎に最適化されたBOM(M-BOM:製造部品表、S-BOM:保守BOM)などを統合的に管理できます。
設計部品表は紙やExcelで管理されることが多く、情報の二重入力が発生する、検索に時間がかかる、属人化する、情報の利活用が進まないといった課題に直面しているケースも多くみられます。
このような場合は、設計部品表をデータベース化することで、部品表を中心に技術情報を一元的に管理でき、設計業務の効率化や関連部門とのシームレスな情報連携が可能となります。
またこれにより、リードタイムの短縮やコストダウン、高品質なモノづくりにもつながります。
3Dデジタルデータを活用したデジタル生産準備
デジタル生産準備業務で3Dデジタルデータを活用すると、使用する工具や組み立て作業の手順や工数など詳細な製造情報を集約することが可能です。
従来の生産準備業務は、試作機などの実機を使って、組立性検証、組立プロセス検討、作業指示書作成等を実施していました。しかし、3Dデジタルデータを用いることで詳細で正確な製造情報を視覚的に理解し実施できるため、品質向上・属人化防止を実現できます。
また、製品開発のプロセスにおいては複数部門の業務を同時に進行させることができるため開発業務の効率化や納期短縮につながります(コンカレントエンジニアリング)。
製造業向けVRシステム
VRとは、「VirtualReality」の略で、コンピューター上で人工的な世界を作りだし、実体験に近い体験を得ることができる仕組みです。
機械設備開発では、機械設備ができあがった後に不具合によって再設計が発生することがあり、納期の延長や費用の増加が起こりえます。そこで、製造業向けのVRを活用することで、2Dのディスプレイ上では気付くことができなかった不具合を、3Dの中に入り込んで検証・検討・発見することができます。
PLMシステムの基本の選び方

PLMシステムは製造業の競争力を左右する基盤です。適切に選定すれば、設計から製造、販売までの一連の業務効率が大幅に改善されます。しかし、製品ごとに特徴や機能が異なるため、導入前に自社に合うシステムを見極めることが重要です。
以下では、基本となる選び方のポイントを解説します。
自社の課題解決につながるシステムを選ぶ
PLMシステムを選ぶ第一歩は、自社が抱える課題を明確にし、その課題を解決できる仕組みを選定することです。
PLMシステムには「パッケージ型」と「半製品型」があり、パッケージ型は低コストかつ短期導入が可能、半製品型は自社の要望に合わせて柔軟にカスタマイズできます。例えば、早期導入を優先するならパッケージ型、自社仕様に最適化したいなら半製品型が適しています。
必要な機能が標準仕様で搭載されているシステムを選ぶ
PLMシステムの中には、PDM機能のみを中心とした製品や、多機能を備えた製品があります。そのため、自社が利用したい機能が標準仕様に含まれているかの確認が欠かせません。
標準搭載されている機能が自社のニーズと一致していれば、追加開発や拡張に余分なコストをかける必要がなく、導入後の満足度が高まります。
処理スピードの速いシステムを選ぶ
PLMで扱うデータは、BOMや3Dデータなど大容量のものが中心です。処理スピードの遅いシステムでは、作業効率が低下し、リードタイム短縮の効果が薄れてしまいます。
大規模なデータを迅速に展開・分析できるシステムであれば、業務の生産性を向上させ、QCD改善につなげられます。
サポート体制が整っているシステムを選ぶ
PLMシステムは操作が複雑であり、導入後には従業員への教育が不可欠です。そのため、サポート体制が整っているベンダーを選ぶことが重要です。
日本語の操作マニュアルや導入支援が不足していると、現場での習熟に時間がかかり、導入効果を十分に得られません。安心して利用を続けるためには、サポートの充実度を重視する必要があります。
予算の範囲内で選ぶ
PLMシステムは拡張やカスタマイズの度に追加費用が発生する場合があります。予算を超えてしまうと、導入そのものが負担になりかねません。
そのため、事前に自社の課題や導入目的を整理し、予算を明確にしたうえでベンダーに伝えることが大切です。予算に収まるシステムを選べば、費用対効果を実感しやすくなります。
製造業における目的別PLMシステムの選び方

続いて、システム導入の目的別にPLMシステムの選び方を紹介します。
図面やBOM管理を中心に効率化したい場合
図面やBOM管理の効率化が目的の場合は、設計データの一元管理機能に着目することが重要です。特に、CADデータの統合管理や、部品表(BOM)のバージョン管理機能が充実したシステムを選定することで、設計変更の追跡や履歴が容易になります。
例えば、設計部門で作成したCADから規格や数量を特定できれば、CADを持たない部署や提携企業ともスムーズな連携が可能です。自社の既存システムを補填する形で、PLMシステムを導入することが望ましいと言えます。
BOP(製造工程情報)を導入して製造業全体を効率化したい場合
BOPを導入した製造業全体の効率化が目的の場合は、図面やBOM管理を効率化するケースよりも多様な機能を持つPLMシステムの導入を検討しましょう。
例えば、製造現場の作業手順や工程管理、設備情報などのデータを統合したPLMシステムを選択することで、設計から製造までの業務フローが可視化され、部門間での連携が深まります。導入コストと運用の負荷を考慮して、最初は設計データの一元管理、段階的にBOP管理まで拡張することも視野に入れて、PLMシステムを選ぶことが重要です。
PLMシステム導入の流れ

PLMシステム選定時に考慮すべき主要なポイントは、以下の6つです。
- 自社の課題解決に必要な機能を洗い出す
- 必要な機能が入っているPLMシステム選定する
- 導入計画を策定する
- PLMシステムを導入する
- 社員教育を行う
- 評価と改善を行う
それぞれ解説します。
自社の課題解決に必要な機能を洗い出す
PLMシステムを導入する際には、まず自社が直面している課題や必要とする機能を明確にすることが重要です。企業の規模や業務内容に応じたニーズを正確に把握することで、適切なシステム選定が可能となります。
例えば、設計部門では、設計プロセスの効率化やミスの削減が求められる場合があります。これらの要望に応えるためには、高度なCAD機能やデータ管理機能が必要になることが多いです。
一方で、製造部門では、生産プロセスの最適化やコスト削減を目的とした機能が求められることが一般的です。特に、作業の標準化と効率化が重視され、最近ではデジタルツールやVR(仮想現実)の活用も普及しています。
これらの課題を解決するためには、各部門の意見を集約し、どの機能が必要か、どのプロセスにおいて効果を発揮するかを検討する必要があります。また、コンサルタントを活用してRFP(提案依頼書)を作成し、具体的な要望を整理することも有効な手段です。
必要な機能が入っているPLMシステムを比較・検討する選定する
最適なPLMシステムを選ぶためには、システムの標準機能、カスタマイズ性、サポート期間の3つに着目して比較・検討する必要があります。
まず、システムの標準機能が自社の課題や業務プロセスにマッチするかどうかを評価します。標準機能が豊富であれば、追加のカスタマイズや拡張が少なくて済み、結果的に導入後の運用がスムーズに進む可能性が高まります。ただし、多機能すぎると不要なコストが発生する場合があるため注意が必要です。
次に、カスタマイズ性です。標準機能だけではニーズを満たせない場合、業務要件に合わせてシステムをカスタマイズする必要があります。カスタマイズが容易であれば、将来的に発生するかもしれない新たなニーズにも柔軟に対応できます。
最後に、長期的な視点でサポート期間を検討することも欠かせません。システムのサポートが長期にわたって保証されているか、また、アップデートやバージョンアップがどのように提供されるかは、システムを持続的に安定して使用する上で重要です。
導入計画を策定する
PLMシステムの導入を成功させるには、まず明確な計画を立てることが欠かせません。自社の課題を洗い出し、解決すべき優先事項を整理したうえで、導入の目的・スケジュール・予算を定義します。
さらに、社内の関係部門を巻き込み、どのように業務へ適用していくのかを合意形成することで、導入後の定着がスムーズになります。
PLMシステムを導入する
計画が固まったら、実際のシステム導入に進みます。サーバー構築やクラウド環境設定、既存データの移行などを段階的に実施します。必要に応じてベンダーの支援を受けることが可能です。
導入時には小規模からテスト運用を始め、問題点を洗い出したうえで全社展開へと広げると、リスクを最小限に抑えられます。
社員教育を行う
PLMシステムは操作が複雑であるため、導入後に社員教育の徹底が重要です。基本的な操作方法に加え、業務フローに沿った活用方法を習得できるように研修を設計します。
マニュアルやサポート窓口を活用しながら教育を継続すれば、システムが現場に根づきやすくなり、効果的に運用できます。
評価と改善を行う
システムを稼働させた後は、導入効果を定期的に評価し、改善を繰り返すことが必要です。例えば、設計リードタイムがどれだけ短縮したか、部門間の情報共有が円滑になったかなどの観点で効果を測定します。
その結果を踏まえて設定や運用ルールを見直すことで、PLMシステムを継続的に最適化し、投資効果を最大化できます。
PLMシステム導入時の注意点

PLMシステム導入時の注意点は、以下の2つです。
- スモールスタートで導入する
- PLMシステムに精通しているベンダーに依頼する
それぞれ解説します。
スモールスタートで導入する
PLMシステムを導入する際に、まずは特定の部門や製品ラインに限定することで、スムーズなDX化が進められます。
PLMシステムを全工程で導入することは理想的ですが、全社規模で一斉に開始すると、従業員の混乱や業務の停止を招く可能性があるためです。また、システムが業務に適合しなかった場合、大きな機会損失を招くリスクがあります。
そのため、例えば、機械装置向け3次元CADや、製品仕様を入力するだけで設計成果物を自動生成するソリューションなど、部門内で完結する範囲からスモールスタートすることが重要です。小さい範囲からPLMシステムを導入して、運用状況や課題を確認しながら、段階的にスケールアップする方法が効果的です。
PLMシステムに精通しているベンダーに依頼する
PLMシステムの導入を成功させるには、製造業の業務フローとPLMの専門的な知識を深く理解したベンダーに依頼することが重要です。
PLMシステムは、製造業の業務プロセス全体を最適化するための重要な取り組みであり、失敗が許されません。適切なベンダー選びが今後の運用効率を大きく左右します。
例えば、類似業界での導入実績、業界特有の課題解決の実績は、ベンダー選びの重要なポイントです。また、PLMシステムの運用支援や自社ニーズに合わせたカスタマイズ、従業員教育など、包括的にサービスを提供しているベンダーは、安心して導入を依頼できます。
自社に適切なベンダーを選ぶことで、PLMシステムの投資対効果の最大化を目指すことが出来ます。
PLMシステムを導入して業務改善を実現

PLMシステムを導入することで、品質向上、リードタイムの短縮、コスト削減、信頼性の向上が期待できます。当社では、製造業においてPLMを進めるための各種ソリューションを提供しています。
営業、設計、製造など、製品のライフサイクルに関わる全部門のデータ連携、また3Dデータを活用したモノづくりを推進するPLMソリューションについてご関心のある方は、以下の資料をご覧ください。
また、PLMの導入やモノづくり現場の業務改善に関するお悩みは、以下よりお気軽にご相談ください。
PLMの実現にご興味のある方は、以下リンクよりご相談ください。
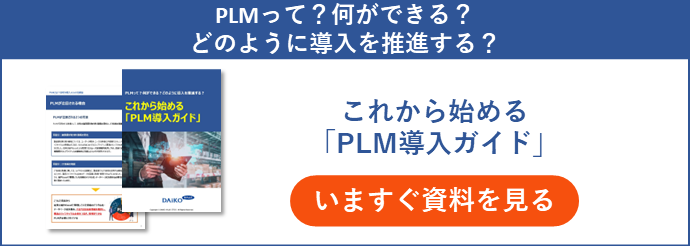
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
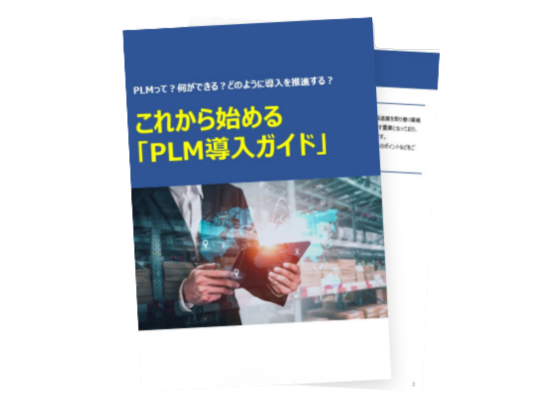
PLMって?何ができる? どのように導入を推進する?
これから始める 「PLM導入ガイド」

- この記事を監修した人
- 前職では、SEとしてCAD/CAMシステムのパッケージ開発に携わり、
お客さまのシステム構築なども経験しました。
それらの経験を活かし、PLM領域の専門営業として、大手企業から
中堅・中小企業まで幅広く提案経験を積んできました。
現在は当社にて、製造業全般のソリューション提案にも携わっています。
週末は趣味の草野球を楽しんでいます。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部 - 北島 靖夫