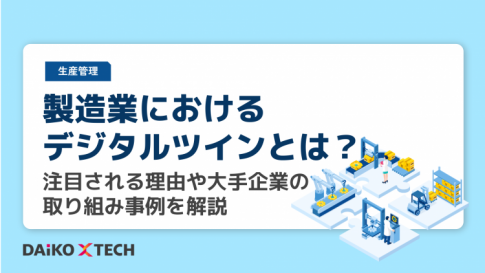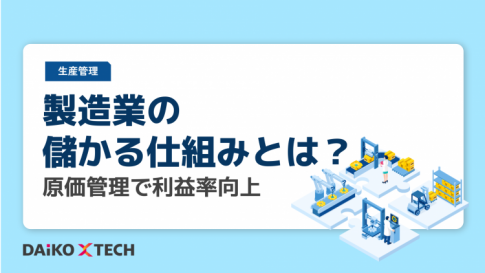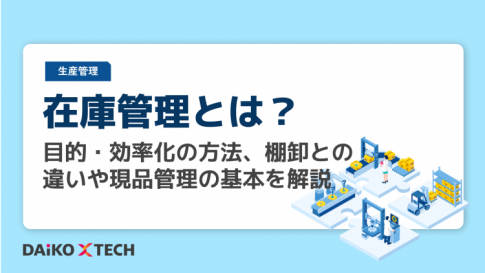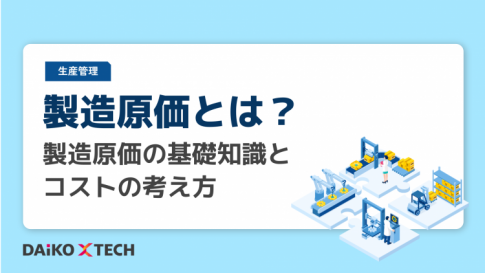TPMとは、製造プロセスにおける無駄をなくし、生産性を向上させるために重要な取り組みです。製造現場全体で生産保全を進めることで、生産性の向上だけでなく、不良率の低下や品質の改善にもつながります。
「TPMとは何か?」「なぜ今、TPMが注目されているのか?」と疑問をお持ちの方は、まずTPMにおける16大ロスや自主保全の7ステップを確認しておくとよいでしょう。
本記事では、TPMの基本的な概要と、注目されている理由について詳しく解説します。
モノづくりの問題・課題を解決するPLMについての資料はこちらからダウンロードできます。
目次
TPMとは

TPM(Total Productive Maintenance/全員参加の生産保全)とは、製造現場を中心に生産性の最大化を目指す生産改善手法です。
設備保全だけにとどまらず、組織全体の企業体質そのものを変革する「全員参加の生産保全」が特徴です。
TPMでは、以下のような幅広い観点から生産保全を実施します。
- 設備の稼働効率向上
- 不良品や事故、災害の未然防止
- 生産ラインの安定稼働
- コスト削減
- 従業員のスキル向上
なお、TPMの定義については、公益社団法人日本プラントメンテナンス協会(JIPM)が以下のように示しています。
「生産システム効率化の極限追求(総合的効率化)をする企業の体質づくりを目標にして、生産システムのライフサイクルを対象とし、“災害ゼロ・不良ゼロ・故障ゼロ”などあらゆるロスを未然防止する仕組みを現場現物で構築し、生産部門をはじめ、開発、営業、管理などの全部門にわたって、トップから第一線従業員に至るまで全員が参加し、重複小集団活動によって、ロス・ゼロを達成すること」
一部の管理職だけでなく、現場で働く従業員まで含む組織全体で生産保全を行う点が、TPMの特徴です。
TPMの歴史
TPMは、1970年代に日本で体系化されました。TPMのルーツは、戦後日本の高度経済成長期にまでさかのぼります。
当時の日本企業は、限られた資源の中で高品質・高効率な生産を実現する必要がありました。限られた資源を有効活用するために、設備の停止や故障を減らす「事後保全」から「予防保全」へと保全の概念が進化していったのです。
1960年代、日本の日本能率協会(現:JMAC)や日本プラントメンテナンス協会(現:JIPM)が中心となり、単なる保全にとどまらない「全員参加の生産保全(TPM)」という新しい管理手法を提唱しました。
1971年にはJIPMがTPM賞制度を創設し、トヨタ自動車や日産自動車などをはじめとする企業がTPMを導入し、世界トップクラスの生産効率と品質を実現しています。
その後、TPMは製造現場だけでなく、物流・医療・建設・ITシステム管理など、設備を活用するさまざまな分野で応用されています。
世界中で広がるTPM
日本で生まれたTPMは、現在ではアジア・欧米・中南米など世界中の製造業で導入されてきました。
主に、自動車・半導体・食品・医薬品・化学工業など、高度な設備を要する産業分野で広く活用されています。
JIPMが、TPMで優れた成果を達成した企業を称える「TPM優秀賞」は、世界約60のエリアで約4,000の事業場が受賞しています。
日本の製造現場の高品質・高効率の裏側にはTPMが大きく貢献しており、世界中の企業からも注目が集まりました。
アメリカやヨーロッパでも、リーン生産方式(Lean Production)やシックスシグマ(Six Sigma)と並んでTPMが取り入れられ、グローバルな競争力を強化する生産管理手法として取り入れられています。
世界中にTPMが広がり、日本産業規格(JIS Z8141:2001)において定義されただけでなく、国際規格であるIATF16949:2016では、TPMの考え方を取り入れたシステム構築が求められています。
TPMが注目されている理由

TPMが注目されている背景には、従来の製造現場を取り巻く環境の変化が関係しています。
設備管理や生産効率向上だけでなく、企業経営全体の競争力を高める手段としてTPMが注目を集めているのです。
TPMが注目されている理由は、主に下記です。
- テクノロジーの発展による競争市場の激化
- 高経年化・多様化した設備への対応
- サステナビリティへの対応
- DX促進の必要性増加
- 人材育成・モチベーション管理の重視
それぞれの理由を確認して、TPMを導入すべきか検討しましょう。
テクノロジーの発展による競争市場の激化
グローバル化やテクノロジーの進化によって、製造業を取り巻く市場環境は急速に変化しています。
AI・IoT・ロボティクスなどの最新技術が製造現場に導入され、生産スピードや品質の競争が激化しています。
DXにより、生産効率が急激に向上した現代では、設備トラブルや品質不良が競合他社との差を広げる大きな要因となるので注意しなければなりません。
TPMは、設備の突発的な故障や品質不良を未然に防ぎ、安定した生産を維持できます。また、TPMを導入すれば、技術革新による新たな設備管理の課題にも柔軟に対応できるため、各企業が注目しているのです。
高経年化・多様化した設備への対応
多くの製造現場では、長年使用され続けた高経年の設備が数多く稼働しています。最新設備だけでなく、20年以上使い続けているレガシーシステムが重要な生産ラインの一部を担っているケースも少なくありません。
レガシーシステムは、故障するリスクが高く、突発的なダウンタイムを引き起こせば、生産性が低下してしまいます。さらに、製造品目の多様化や小ロット生産の増加により、設備の使用状況はより複雑化しました。
TPMは、老朽設備や多品種生産に伴う保全管理を体系的に行う手法なので、高経年化・多様化した設備に対応できます。定期的な点検や予知保全を通じて、高経年設備でも安定した生産を実現できるのがTPMの強みです。
サステナビリティへの対応
企業の社会的責任(CSR)や環境配慮が求められる中、サステナビリティ経営の一環としてTPMは重要性を増しています。
設備の安定稼働を維持し、ムダな廃棄物やエネルギー消費を減らせば、環境負荷の低減につながります。
例えば、故障や不良品を削減し、原材料のムダを減らせば、修理や交換に伴う資源消費も抑制できるのです。
また、TPMによる安定した生産は、エネルギー効率の向上にもつながるため、CO2排出削減や持続可能な生産体制を構築できます。
TPMを導入すれば、企業価値の向上や国際的なESG評価にも好影響を与えられるため、環境・社会への貢献が求められる現代において、企業の競争優位性を高める要素として注目されています。
DX促進の必要性増加
製造業において、DXの推進は避けて通れない課題です。設備から収集されるビッグデータを活用して、故障予知やメンテナンス計画を最適化するスマートファクトリー化が進む中、TPMはDXと密接に結びついています。
TPMの基本である「現場現物主義」「データに基づく改善活動」は、DXで活用されるAI・IoTと親和性が高いです。TPM活動を通じて蓄積された保全データや故障履歴をAIに学習させれば、より精度の高い予防保全や自律的な設備管理が実現できます。
DX促進が求められる現代では、TPMを活用した予防保全や設備管理による、生産管理が推奨されています。
人材育成・モチベーション管理の重視
設備管理の高度化が進む現代において、設備を扱い管理する人材の育成も重要な課題です。TPMでは「全員参加型」の生産保全が基本にあり、現場作業者自らが設備の正常状態を把握し、改善提案を積極的に行います。
ただ作業を繰り返すオペレーターから、設備を守る管理者へと成長を促せるため、組織力の向上が期待できるのです。
また、現場主体の改善活動は、従業員の自己成長意欲や職場の一体感を高める効果もあります。TPMは、経験の少ない若年層や現場作業員にも、設備管理や生産保全の一端を担わせるため、若手人材の定着率向上や提案力・管理能力の向上にもつながります。
技術承継が課題となる現代において、TPMは貴重な人材育成プラットフォームとして注目されているのです。
TPMにおける16大ロスとは

TPMでは、生産現場で発生する「ロス」を徹底的に分析・排除することを重要視しています。
TPMにおける16大ロスは、下記の3つに分類されます。
- 設備の効率化を阻害する8大ロス
- 人の効率化を阻害する5大ロス
- 原単位の効率化を阻害する3大ロス
それぞれのロスを確認して、生産現場で発生するムダを徹底的に排除しましょう。
設備の効率化を阻害する8大ロス
TPMでは、設備の効率化を阻害する下記の8大ロスを定義しています。
- 故障ロス
- 段取り・調整ロス
- 刃具交換ロス
- 立上がりロス
- チョコ停・空転ロス
- 速度低下ロス
- 手直し・不良ロス
- シャットダウン(SD)ロス
上記の8大ロスは、設備稼働率や生産性を低下させる要因です。それぞれのロスを確認して、設備稼働率を維持・向上させる対策を実施しましょう。
故障ロス
故障ロスとは、設備が突然故障して停止してしまうロスです。突発的な機械トラブルや部品の破損が原因となり、生産計画が滞るだけでなく修理コストも発生します。
故障ロスを削減するためには、予防保全や設備点検を徹底しましょう。
段取り・調整ロス
段取り・調整ロスは、製品切り替え時の段取り作業や、設備の調整作業に要する時間のロスです。
生産品種が多い工場ほど、段取り・調整ロスは増え、生産性を低下させてしまいます。ロスを削減するには、段取り作業の標準化や段取り時間短縮(SMED活動)が効果的です。
刃具交換ロス
刃具交換ロスは、工具や刃具の交換に要する時間的なロスです。刃具の寿命管理や交換タイミングを最適化すれば、ロスを減らせます。
一方で、適切な管理がされていない場合、刃具の交換頻度が増え、生産性が低下します。
立上がりロス
立上がりロスとは、生産開始直後や設備停止後の再立ち上げ時にかかるタイムラグです。
設備の温度変化や条件調整ミスなどが原因であり、生産活動を再開するまでにかかる時間がロスとして加算されます。
立上がりロスを削減するには、設備停止を防止する対策や作業手順の見直しなど、再立ち上げにかかる時間をムダにしない対策が必要です。
チョコ停・空転ロス
チョコ停・空転ロスは、短時間で繰り返し発生する小停止(チョコ停)や空転(無駄な動作)によるロスです。
主に、センサー異常やワーク供給ミス、材料不良などが原因になるケースが多く、現場での現物確認がロス削減につながります。
速度低下ロス
速度低下ロスは、設備が本来の設計速度よりも低い速度で運転している場合に発生するロスです。
安全マージンの過剰設定や設備の経年劣化が原因となるケースが多く、適切な保全と設備改良が求められます。
手直し・不良ロス
手直し・不良ロスは、不良品の発生や手直し作業に要するロスです。加工精度や組立ミス、部品不良などが主な要因であり、品質管理の徹底と工程内検査の強化がロス削減に役立ちます。
シャットダウン(SD)ロス
シャットダウン(SD)ロスは、法定点検や計画停止など、生産計画上で発生する設備停止時間によるロスです。
事前準備の徹底や点検作業の効率化が、ロスの最小化につながります。
人の効率化を阻害する5大ロス
人の効率化を阻害する5大ロスは、下記のとおりです。
- 管理ロス
- 動作ロス
- 編成ロス
- 自働化置き換えロス
- 測定調整ロス
上記の5大ロスは、作業効率や労働生産性の低下につながります。人的要因によるロスであるため、作業員が注意を払ったり手順を改良したりすれば、ロスを削減できます。
管理ロス
管理ロスとは、生産計画のミスや指示不足、段取り替えの遅れなど、管理業務に起因して発生するロスです。
例えば、部品が間に合わない、必要な工具が準備されていない、作業手順が不明確などの状況が該当します。
作業の開始が遅れたり待機時間が発生したりすれば、管理ロスが発生するため、生産計画の精度向上・情報共有の徹底・作業指示書の整備などの対策を実施しましょう。
また、現場と管理部門の連携を密にすれば、計画と実行のギャップを縮められます。
動作ロス
動作ロスとは、作業員が本来必要のない動作を行い発生するロスです。例えば、部品を探す、工具を取りに行く、姿勢を何度も変えるなどのムダな動作が該当します。
動作ロスが積み重なると、大きな時間的損失につながるため、生産性が低下するのです。動作ロスの削減には、作業場の5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動を実施し、必要な物がすぐ取り出せる環境を整備しましょう。
編成ロス
編成ロスとは、作業員の配置が適切でない場合に発生するロスです。作業に対して人手が多すぎたり、反対に足りなかったり、スキルミスマッチがある場合に発生します。
また、複数作業を担当する際の役割分担が不明確な場合も、編成ロスが起きる可能性があります。
編成ロスを防ぐには、適切な人員配置計画とスキルマップの作成・活用が効果的です。作業員の教育訓練を強化し、多能工化を進めれば、柔軟な人員配置を実現し、編成ロスを最小化できます。
自働化置き換えロス
自働化置き換えロスとは、作業を自動化する設備を導入した結果、人が介入しなければならない付随作業や監視作業が残り、発生するロスです。
例えば、設備の異常を監視する、材料補給を手作業で行う、完成品の検査を目視で行うなどが該当します。
自働化置き換えロスを減らすには、自動補給装置や自動監視システムの導入、異常発生時のアラート機能の強化などが効果的です。
測定調整ロス
測定調整ロスとは、製品の品質測定や機械の調整作業に要する時間によるロスです。主に、頻繁な測定作業、長時間の条件出し、調整後の再確認などが作業時間を圧迫します。
測定調整ロスを削減するには、測定手順の標準化、事前準備の徹底、測定機器の自動化・デジタル化が効果的です。さらに、作業者の技能向上も重要で、経験を積んだ作業員は迅速かつ正確な測定・調整を行えます。
原単位の効率化を阻害する3大ロス
原単位の効率化を阻害する3大ロスは、下記のとおりです。
- 歩留まりロス
- エネルギーロス
- 型・治工具ロス
原単位とは、製造のため費やした原料や素材の総量に対する成果を図る指標です。上記の3大ロスは、原単位の効率化を阻害するため、製造のために費やした原料や素材に対する成果物の量を減少させる要因です。
歩留まりロス
歩留まりロスとは、投入した原材料のうち、製品として使えずに廃棄や再処理が必要になる部分に起因するロスです。
主に、加工ミス、寸法不良、材料の欠陥などが原因となり、製品化されない材料が発生します。歩留まりが低い場合、多くの原材料を消費する必要があり、コストが増大します。
歩留まりロスを削減するには、設備の精度向上、作業手順の標準化、原材料の品質管理強化などが必要です。また、工程内品質保証を徹底し、不良が発生する前に予防する体制を整える対策も効果的です。
エネルギーロス
エネルギーロスとは、電力・燃料・水などの使用エネルギーの無駄使いによって発生するロスを指します。
例えば、不要な待機運転、空調や照明の過剰使用、配管からの蒸気漏れなどが代表的です。エネルギーロスが大きいと、製品1個あたりに必要なエネルギーコストが増え、収益性を圧迫します。
エネルギーロスの削減には、省エネ機器の導入、エネルギー使用量の見える化、設備の定期保守、従業員の省エネ意識向上が有効です。また、IoTやAIを活用したエネルギー管理システムも効果的です。
型・治工具ロス
型・治工具ロスとは、型や治具、工具類の摩耗や不良、交換の遅れなどによって発生するロスを指します。
型が劣化すると寸法精度が保てず不良品が発生しやすくなるのです。また、治工具の破損や摩耗により作業停止や品質低下が生じます。
型・治工具ロスの削減には、定期的な保守点検、寿命管理、工具の標準化・共有化、交換作業の効率化が必要です。さらに、工具の摩耗状況を監視するセンシング技術の導入も、ロスの最小化に役立ちます。
TPMのロスを防ぐ8本の柱

TPMでは、先ほどご紹介した16大ロスを防ぐ8本の柱を定義付けています。
- 個別改善
- 自主保全
- 計画保全
- 品質保全
- 教育・訓練
- 安全・衛生・管理
- 設備初期管理
- 管理・間接
8本の柱をバランス良く推進すれば、設備効率を最大化し、不良・故障・災害ゼロを目指せます。
それぞれの柱を確認して、ロスを最小化する体制を整えましょう。
1.個別改善
個別改善は、現場で発生しているムダ・ムラ・ムリを洗い出し、重点課題を設定して改善活動を行う取り組みです。
機械停止や品質不良の原因を分析し、ロスの真因にアプローチしていきます。小集団活動(QCサークルなど)を通じて、現場の自主性を尊重しながら改善を進めるのが特長です。
現場の「気づき」を重視し、現物・現場・現実を基にPDCAサイクルを回しましょう。
2.自主保全
自主保全は、設備を使用するオペレーターが主体的に日常点検・清掃・注油などの基本保全を行う活動です。
現場作業員が設備の状態を常に把握し、小さな異常を早期に発見・対応して、大きなトラブルを未然に防ぎます。自主保全では、設備の「初期劣化を防ぐ」「異常の早期発見」「自己管理能力の向上」が主な目的です。
3.計画保全
計画保全は、保全部門が主体となり、設備の故障を未然に防ぐために、定期的な点検・整備・部品交換を計画的に実施する活動です。
設備の故障履歴や寿命データに基づいてメンテナンス計画を立て、突発故障の発生を最小化します。予防保全や予知保全も計画保全につながる生産保全です。
4.品質保全
品質保全は、設備の不具合が製品不良につながらないように、品質を守るための保全活動です。設備の精度維持や治工具の管理、加工条件の最適化などを行い、品質の安定を図ります。
「設備条件と品質条件の標準化」と「工程異常の早期発見」が品質保全における重要なポイントです。
5.教育・訓練
教育・訓練は、TPM活動を推進する上で必要な知識・技能・意識を身につけるための人材育成活動です。
オペレーターから保全部門、管理職まで、役割に応じた教育プログラムを整備し、全員参加型の改善活動を支えます。主に、技能教育、安全教育、改善手法教育などが含まれます。
6.安全・衛生・管理
安全・衛生・管理は、作業中の事故や災害を未然に防ぎ、安全で快適な職場環境を作る活動です。
設備の危険源の排除、安全教育の徹底、作業環境の改善、ヒヤリハット活動などが主な活動です。
TPMの基本方針には、安全ゼロ災害の達成が含まれており、安全・衛生・管理を重要視する必要があります。
7.設備初期管理
設備初期管理は、新たに導入する設備の立ち上げ段階から高い保全性・操作性・品質安定性を確保する活動です。
設備の設計・製造段階から保全性・操作性を考慮すれば、立上げ後の故障や不具合発生を未然に防ぎます。設備初期管理を実現するには、製造現場だけでなく開発・設計部門との連携が必要です。
8.管理・間接
管理・間接は、事務部門・管理部門でもTPM活動に参画し、事務効率や間接業務の改善を進める取り組みです。
間接部門のロス低減、事務作業の標準化、IT活用による業務効率化などを推進します。管理・間接は、生産現場だけでなく、組織全体の効率化を支える重要な柱です。
TPMにおける自主保全の7ステップ

自主保全とは、生産効率を高めるために、設備を使用する作業員自身が行う保全活動です。TPMにおける自主保全では、下記の7ステップを定めています。
- 初期清掃(清掃点検)
- 発生源・困難個所対策
- 自主保全仮基準の作成
- 総点検
- 自主点検
- 標準化
- 自主管理の徹底
TPMにおいて自主保全は、基本的な活動であり、製造現場におけるムダをなくす重要な活動です。設備維持を効率的に進めるため、上記の7ステップを意識して自主保全を行いましょう。
ステップ①初期清掃(清掃点検)
TPMの自主保全では、まず設備を徹底的に清掃し、汚れや異常箇所を発見する作業です。汚れは劣化や故障の発生源となるため、設備を徹底的に清掃しながら、油漏れ・ガタ・ゆるみ・摩耗・ひび割れなどの異常を洗い出しましょう。
清掃を通じて「設備の現状を知ること」が目的であり、オペレーターの設備への関心も高まります。
ステップ②発生源・困難個所対策
次は、清掃で発見された異常箇所の中で、特に汚れや不具合の「発生源」を突き止め、根本的に改善しましょう。
また、清掃や点検がしにくい「困難個所」には改善策を講じ、作業しやすく安全な状態に改良します。発生源対策は、設備の汚れ・劣化・故障の予防に直結する重要なステップです。
ステップ③自主保全仮基準の作成
清掃・点検の習慣を定着させるために、日常的に行う点検項目や清掃箇所をまとめた「自主保全仮基準」を作成します。
仮基準は、現場の状況に合わせて柔軟に作成し、日々の活動を標準化する土台です。点検頻度、点検ポイント、異常時の対応なども明確に定めます。
ステップ④総点検
設備の各部品や構造に関する基礎知識を習得し、オペレーター自身が設備の総点検を実施します。
軸受け、潤滑系統、締結部、電気系統など幅広い項目を理解し、点検技術を身につけるのが目的です。総点検を実施するための学習と実践が、設備トラブルの早期発見・早期対応能力を高めます。
ステップ⑤自主点検
仮基準を見直し、より実践的で精度の高い「本格的な自主点検」を日常業務として定着させます。自主点検では、作業員が点検技能を活かし、設備の状態を常に把握することが大切です。
自主点検を徹底すれば、設備の初期劣化を未然に防ぎ、安定した稼働を維持できる状態が作れます。
ステップ⑥標準化
清掃・点検・注油・整備などの手順を、誰でも正確に実施できるように標準化しましょう。
標準書やチェックリストを整備し、教育訓練によって作業のバラつきを防ぎます。自主保全を一部の従業員が担当する属人化が起きると、急な休職や異動があった際に、設備維持が困難になるため要注意です。
属人化を防止するために、品質と安全性を確保しつつ、属人的な作業を排除するためにも、標準化が必要不可欠です。
ステップ⑦自主管理の徹底
TPMにおける自主保全の最終ステップは、作業員が自ら設備の状態を管理し、安定した稼働を継続できる体制を確立する段階です。
異常の兆候を察知する「感性」を磨き、問題発生を未然に防ぐ自主保全文化が職場に根付く状態を指します。
自主管理を徹底すれば、改善提案も積極的に行われ、継続的な改善活動へと進化させられます。
TPMは保全だけでなく生産性向上につながる取り組み

TPMは、保全だけでなく生産性向上につながる取り組みなので、組織力・売上増加へと起因します。
TPMでは、作業員全体が参加し製造現場におけるムダをなくす取り組みが求められます。
まずは、TPMで定められている16大ロスを理解したうえで、ロスを防ぐ8本の柱と自主保全の7ステップを実施しましょう。
TPMの概要や注目されている理由を理解したうえで、製造現場のロスを改善する取り組みを実行してください。