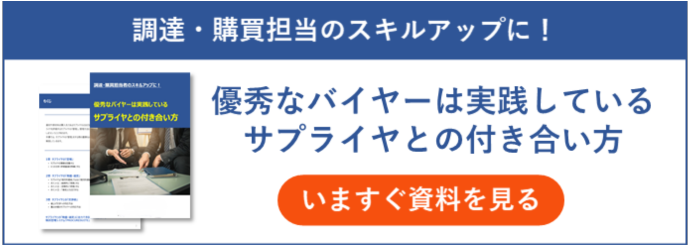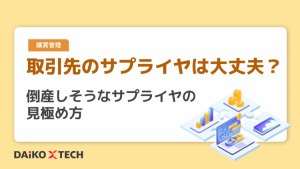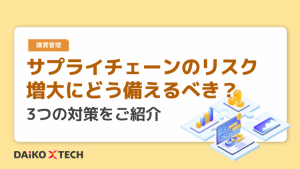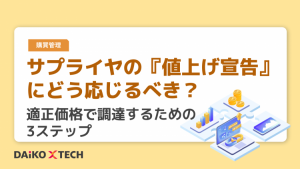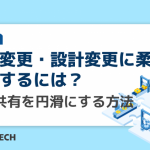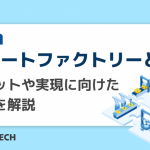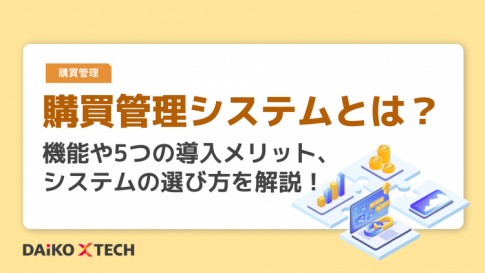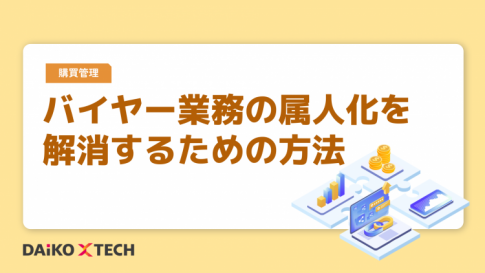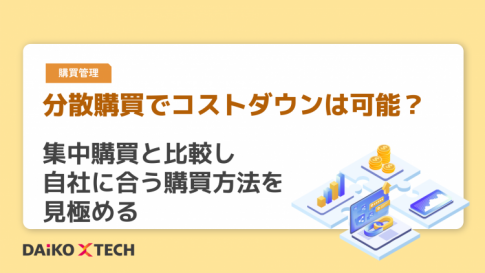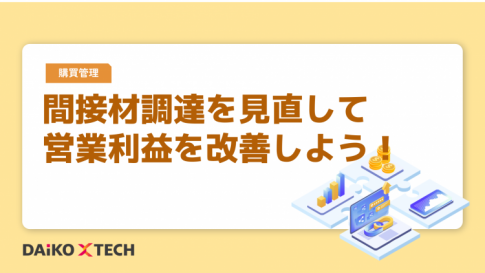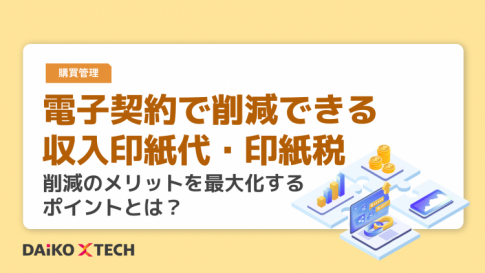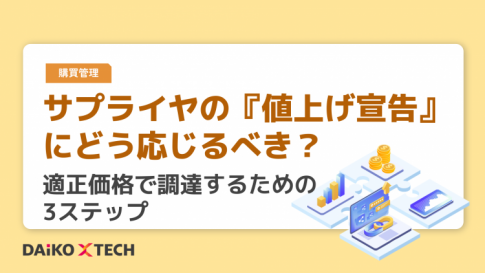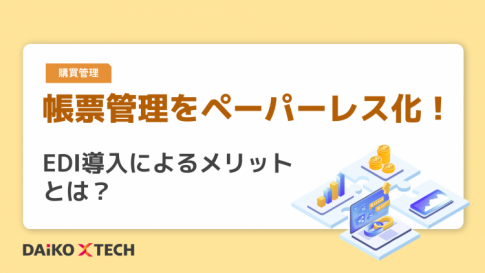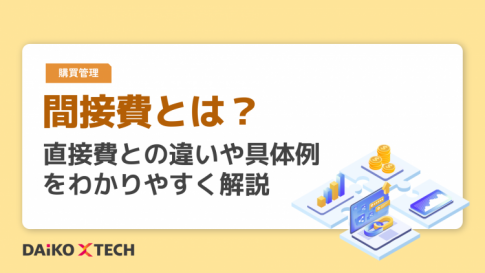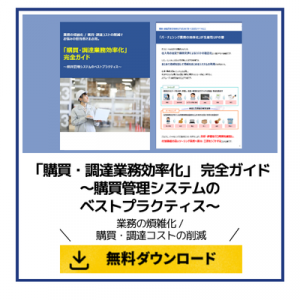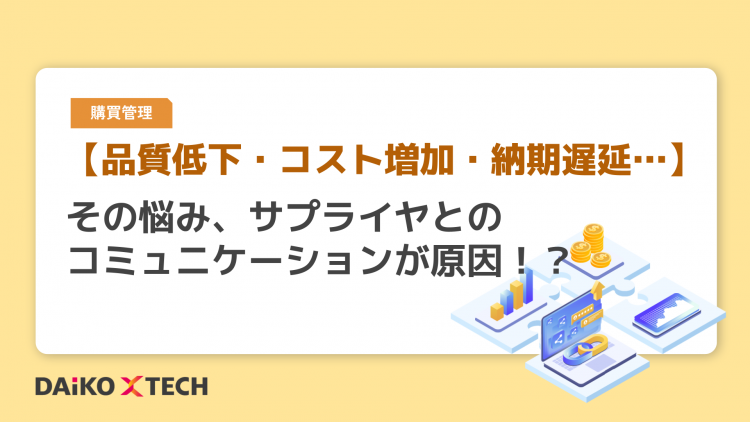
購買・調達部門はサプライヤとの取引でさまざまな課題に直面しています。このような事態に陥らないためにはサプライヤとの十分なコミュニケーションが重要ですが、実際は不足している状態です。
そこで本記事では、サプライヤとのコミュニケーションが不十分になってしまう原因やコミュニケーションを円滑にする方法をご紹介します。
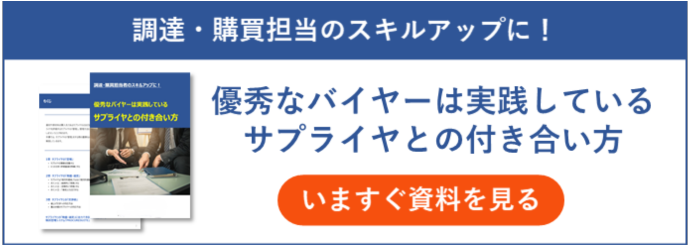
目次
サプライヤとの取引で購買・調達部門が陥りがちな課題
品質の高い製品を納期通りに納品するために、購買・調達部門はサプライヤとの円滑な取引を行うことが重要です。しかし、サプライヤとの連携が上手くいっていない場合、課題が発生します。
以下ではサプライヤとの取引で購買・調達部門が陥りがちな課題をご紹介します。
サプライヤの倒産危機に気づけない
サプライヤとコミュニケーションが上手く取れていない場合、サプライヤの倒産危機に気づけない可能性があります。
購買・調達部門のバイヤが気づかずにサプライヤが突然倒産してしまった場合、部品や材料が調達できず、リードタイムの遅れにつながります。昨今では新型コロナウイルスの影響で打撃を受けているサプライヤも多く存在しているため、特に注意を払う必要があります。
以下記事では取引先のサプライヤの状態を見極める方法をご紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。
サプライチェーンのリスクヘッジが困難
サプライヤが突然倒産してしまったり、予期せぬ事態によって供給停止に陥ってしまったりした場合、サプライチェーンが停滞・途絶してしまいます。このようなサプライチェーンリスクは昨今増加の傾向にあり、リスクヘッジを行うことが困難になってきています。
サプライチェーンリスクへの対策は以下記事でご紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。
このような課題は、表面化するまでに時間がかかったり、表面化してからは応急措置の対応をしたりするため見過ごされがちです。しかし、これらの課題に向き合わなければ悪影響を及ぼす恐れもあります。
サプライヤとの取引課題を放置すると?無視できぬ副作用
購買・調達部門の重要なミッションはサプライヤとの取引において、スケジュール通りに資材をできるだけ安く仕入れることです。しかし、サプライヤとの取引課題をリスクヘッジできていなければ、ミッションを達成できない可能性があります。
本章では、前述の課題から引き起こされる悪影響をご紹介します。
コスト増加
取引サプライヤの倒産や、サプライチェーンの影響で供給が停滞すると、急遽他のサプライヤから仕入れを行わなければならず、コストが増加することがあります。
また、サプライヤは外的環境を踏まえ、原材料価格やエネルギーコスト、労務費などの価格を設定しており、経済的要因により値上げをすることもあります。サプライヤとの連携が取れていない場合はこのような要因に気づかず、値上げ前の価格で仕入れられる別のサプライヤを探すなどしてコスト増加を防ぐ行動ができません。
さらに、連携不足であると価格査定時に最適な価格を導き出せず、コスト増加につながる可能性があります。
サプライヤに値上げの報告をされたときでも、適正価格で調達する方法は以下記事で詳しく解説しています。こちらもあわせてご覧ください。
納期・デリバリーの遅延
資材の供給が困難になってしまうと、代替サプライヤを探す必要があります。この場合、通常よりも遠方からの資材調達を行わなければならず納期に間に合わないという事態が起こりえます。
また、サプライヤとの連携ができていないために、納品期日に間に合わないという遅延連絡がバイヤに適切に伝わらず、社内からは資材の調達進捗を確認する問い合わせが発生してしまう事態にも陥ってしまいます。この納期・デリバリーの遅延は最終的な製品の納品日に影響するため、顧客からの信頼を損なう原因となります。
品質低下
サプライヤから納入されてくる資材の品質が低下するといった影響もあります。例えば、サプライヤ変更により扱う資材の質が変化するケースや、原材料費の高騰などの理由から、資材の価格自体は変わらないものの、品質を落とすケースがあります。
下記の記事では、このような悪影響を及ぼさない「優良なサプライヤ」と出逢うための方法をご紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。
ではなぜ、サプライヤとの取引でこのような問題が発生するのでしょうか。その原因を次章でご紹介します。
原因はサプライヤとの不十分なコミュニケーション?なぜ起こるのか
サプライヤとの連携が上手くいかない原因は、不十分なコミュニケーションにあります。コミュニケーション不足によって、購買・調達部門の要望をサプライヤが正確に認識できなかったり、サプライヤに関する情報や状況をバイヤが認識できていなかったりするため、課題が生じてしまいます。
また、ビジネスのスピードが加速し市場変化の振れ幅が大きい昨今では、サプライヤと円滑なコミュニケーションが取れなければ変化に対応することができません。
ではコミュニケーションが十分に取れない理由にはどのようなものがあるのでしょうか。以下では3つの原因についてご紹介します。
メールや電話によるコミュニケーションの属人化
サプライヤとの連絡をメールやFAX・電話などのアナログな手段で行っている企業は多く存在します。
アナログなコミュニケーション手法を取っていると、部門内で連絡内容を共有することが難しく、細かな交渉ナレッジやサプライヤとの関係構築、業界の動向など幅広い経験や知識が求められる購買・調達業務は属人化してしまう傾向にあります。
属人化による偏った伝達内容
購買・調達業務が属人化してしまった場合、網羅的な内容のコミュニケーションができず他部門の要求が反映されなかったり、内容に偏りが生じたりします。
また、属人化してしまっているせいで内容に齟齬や偏りがあっても誰も気づけず、間違った認識でコミュニケーションが進行してしまい、気づいた頃には問題が起きている場合が多いです。
サプライヤの管理が煩雑で情報共有・連携が困難
サプライヤの情報管理が煩雑となってしまっていることも、コミュニケーション不足に陥ってしまう理由の一つです。
購買・調達業務では取引先のサプライヤとのやり取りをメールやExcelを駆使してツール単位に行っていたり、サプライヤごとの見積書のフォーマットがバラバラであったりします。そのため、情報管理が複雑化してしまい、社内の情報共有やサプライヤとの連携が難しくなってしまいます。
上述のような理由からサプライヤとの不十分なコミュニケーションが発生してしまいます。次章では、サプライヤとのコミュニケーションを円滑にする方法についてご紹介します。
サプライヤとのコミュニケーションを円滑にする方法
以下ではサプライヤとのコミュニケーションを円滑化し、情報収集を強化するための方法についてご紹介します。
柔軟なコミュニケーション基盤の構築
サプライヤとのコミュニケーションを円滑化するためには、サプライヤの情報を収集・蓄積できるコミュニケーション基盤の構築が必要です。また、担当者同士による1対1の属人的なコミュニケーションではなく、1対N、N対Nのように、複数人でのコミュニケーションにも柔軟に対応できる状態であることも重要です。
このような基盤により、過去の調達資材のコスト情報や保有設備などの情報を部門内で共有できるようになるため、先述したような課題への対策ともなります。
定期的に網羅的な情報収集を行う
サプライヤの突然の倒産リスクや価格引き上げに対応するためには、常日頃からサプライヤに関する情報を収集することが大切です。
サプライヤの情報を収集する際には、都度知りたい情報を収集するだけではなく、網羅的な情報収集を行う必要があります。網羅的な情報収集を実現するためにはヒアリングフォーマットやアンケートを用いることをおすすめします。また、これらの情報を定期的に収集できるような仕組みを構築することも重要です。
情報の一元管理
定期的かつ網羅的にサプライヤ情報を収集・蓄積できたとしても、管理が煩雑だと共有が難しくなってしまい、コミュニケーションを円滑に進めることはできません。そのため、情報を一元管理できる仕組みを構築することも必要となってきます。
次章では、情報の一元管理を実現するシステムについてご紹介します。
システムを導入することでサプライヤとのコミュニケーションを円滑に
購買・調達部門が陥りがちな課題を解決するためには、バイヤとサプライヤのコミュニケーションを円滑に行えるような仕組みを構築する必要があります。
これを実現するのが購買管理システム「PROCURESUITE」です。「PROCURESUITE」は、見積や発注、承認処理といった、購買業務における社内情報から取引先の情報まであらゆる情報の一元化・可視化が可能です。サプライヤ情報を一元管理することで、収集した情報を共有しやすくなります。
バイヤとサプライヤのコミュニケーションを円滑にできるPROCURESUITEについては
以下からご確認いただけます。
本記事でご紹介したような課題にお悩みの方はぜひご覧ください。