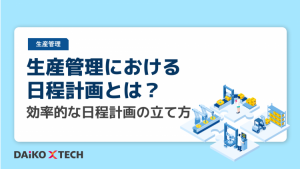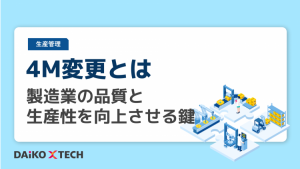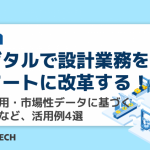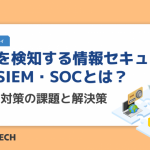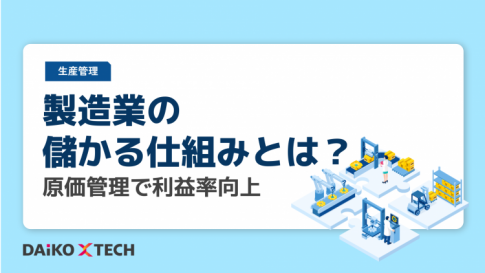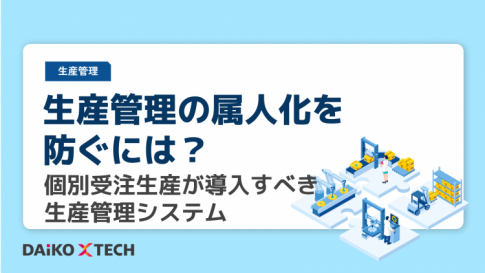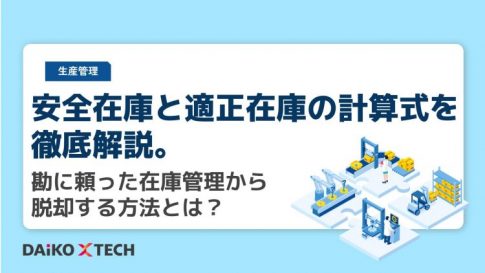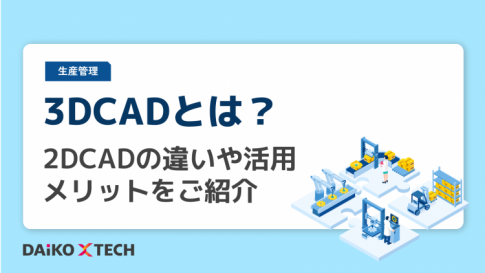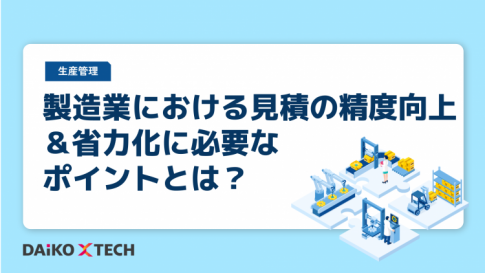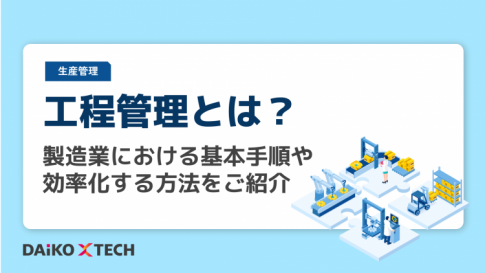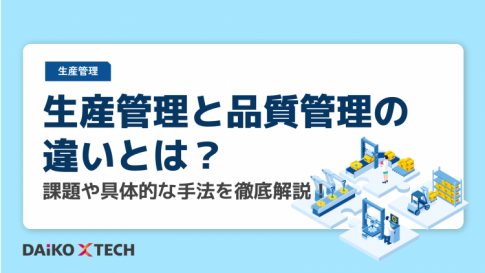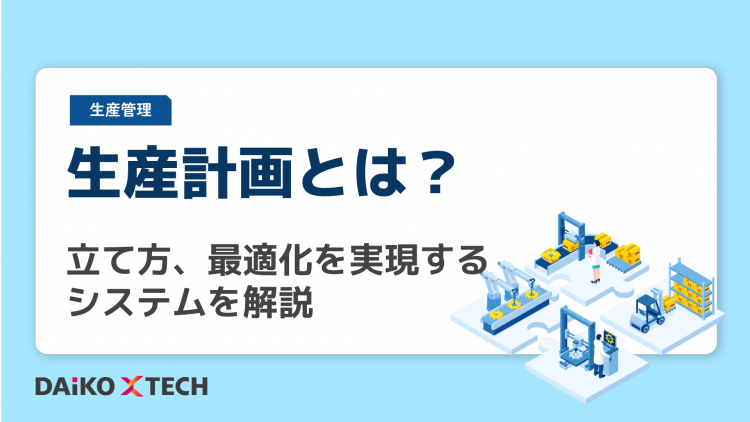
製造業において効率的に製品を生産・販売していくためにも適切な生産計画は非常に重要です。では、具体的にどのように生産計画を立て、何に注意する必要があるのでしょうか?
本記事では、生産計画の立て方や運用方法、運用をスムーズにするためのポイントについてご紹介します。
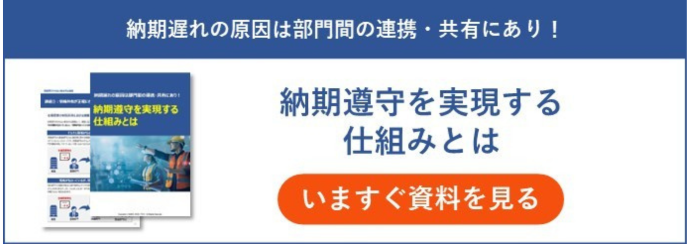
目次
生産計画とは

生産計画とは、製品の生産量・生産時期に関する計画のことで、「何を」「いつ」「どれほど」生産し、「いつまでに」出荷するかを定めるものです。
生産計画には、製品の原材料や部品の管理、製造から出荷までの工程が含まれます。これは、効率的な生産業務に不可欠であり、品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)の維持・向上に貢献し、資金計画や人事計画にも大きく影響します。
生産計画の特徴
生産計画の特徴は、企業の生産活動全体を包括的に管理できる点です。製造業における生産活動の根幹として、以下の4つの要素を統合的に管理します。
|
1.生産品目と数量の管理 |
市場需要の予測に基づき、製品の種類ごとの最適な生産数量を決定 |
|
2.生産タイミングの設定 |
受注状況や市場動向を考慮し、各製品の生産開始時期を決定 |
|
3.資材調達の最適化 |
必要な原材料や部品の調達計画を立案 |
|
4.スケジュール管理 |
設備稼働率や人員配置を考慮した具体的な生産日程を策定 |
生産計画におけるこれら4つの要素を適切にコントロールすることで、製造現場の生産性向上と経営効率の最適化を実現します。また、各要素は相互に関連しており、一体的な管理を実施することが重要です。
生産計画の手法
生産計画の手法は、大きく「押し出し方式(PUSH型)」と「引っ張り方式(PULL型)」の2つに分類されます。それぞれの特徴を理解することで、企業の生産形態に適した方式を選択できます。
押し出し方式
押し出し方式は、過去の実績データや市場分析をもとに年間計画を策定し、前工程から順次生産を進行させる手法です。生産ラインの稼働率向上に効果的ですが、需要予測と実需の乖離が生じた場合に在庫過剰リスクが発生します。 自動車部品や家電製品など規格化された製品の生産に適しています。
引っ張り方式
引っ張り方式では、顧客の実際の注文を受けてから生産指示を発行します。カンバン方式を採用したトヨタ生産システムが代表例で、部品調達から組み立てまでのリードタイム短縮が可能です。医療機器やオーダーメイド製品など、個別仕様に対応する生産形態で効果を発揮します。ただし、生産計画の頻繁な変更に対応できる柔軟な供給体制が前提条件となります。
|
方式 |
特徴 |
生産の流れ |
適している環境 |
|
押し出し方式(PUSH型) |
事前に策定した計画に基づき生産を進める |
前工程から後工程へ |
需要予測が安定している大量生産型 |
|
引っ張り方式(PULL型) |
実需に基づいて必要な分だけ生産する |
後工程から前工程へ |
多品種少量生産や需要変動が大きい環境 |
製造計画との違い
生産計画と製造計画は、よく混同されますが、該当する範囲や内容に違いがあります。
| 生産計画 | 製造計画 | |
| 計画範囲 | 製造に至るまでの全体的な戦略を扱う。生産に関わる広範な計画。 | 生産計画に基づき、実際の製造プロセスの細部を定めるもの。生産計画の一部。 |
| 例 | 製品の需要予測、資材の調達、工程計画など | 作業の割り当て、機械の稼働スケジュール、品質管理など |
生産計画は、生産に関わる広範な計画を指し、生産管理、購買管理、在庫管理、品質管理、工程管理などを含みます。一方、製造計画は生産計画の製造に関わる計画を指しており、製造現場での作業進捗や工程の管理を主に扱います。
生産計画がすべての生産活動を包含する大きな枠組みであれば、製造計画はその中の製造工程に特化した部分を扱うと覚えておきましょう。
生産計画の立て方【期間別】
生産計画の策定と管理は、製造業の効率的な業務サイクルを確保し、品質の維持と業務の最適化を実現するために不可欠です。ムリ・ムダのない生産計画を立てるために、ここでは大日程・中日程・小日程の3つの期間に分け、生産計画の立て方についてご紹介します。
大日程計画の作成
大日程計画は、3カ月から1年間の長期計画で、生産活動の全体の方向性を定めるものです。過去の実績に基づいて受注量や納品量を予測し、それに基づいて設備や人員の計画を行います。さらに、市場の動向とビジネスの長期目標を分析し、それに沿った生産目標を設定します。新製品開発や製品改良もここで計画し、状況の変化に応じて随時見直しを行いましょう。
中日程計画の作成
中日程計画は、1〜3カ月の中期計画で、月単位または四半期単位で生産活動を計画します。実際に受注した内容を基に、生産量や生産ペースを決定し、生産能力計画、人員計画、月別生産計画、原材料や部品の調達計画を立てましょう。市場の変動や受注の追加に応じて、計画の調整が行われます。
小日程計画の作成
小日程計画は、1週間から1カ月の短期計画で、日々の生産活動を管理し、計画通りに生産が進むようにするために立てられます。大日程計画・中日程計画とは異なり、小日程計画は計画通りに作業を進めなくてはなりません。作業完了期限までの具体的な作業スケジュール、機械の稼働計画、品質管理の手順などを細かく計画する必要があり、高度な知識と経験が要求されます。毎日または毎週、頻度の高いペースで見直しを行い、計画と現場の進捗状況とのズレを調整しましょう。
ここまでご紹介したように、生産計画は定期的な見直しが必要です。大日程計画は1〜3カ月ごと、中日程計画は毎週または毎月、小日程計画はほぼ毎日見直されるのが理想です。
効率的な日程計画の立て方の詳細は、下記記事をご覧ください。
生産計画の立て方【生産方式別】
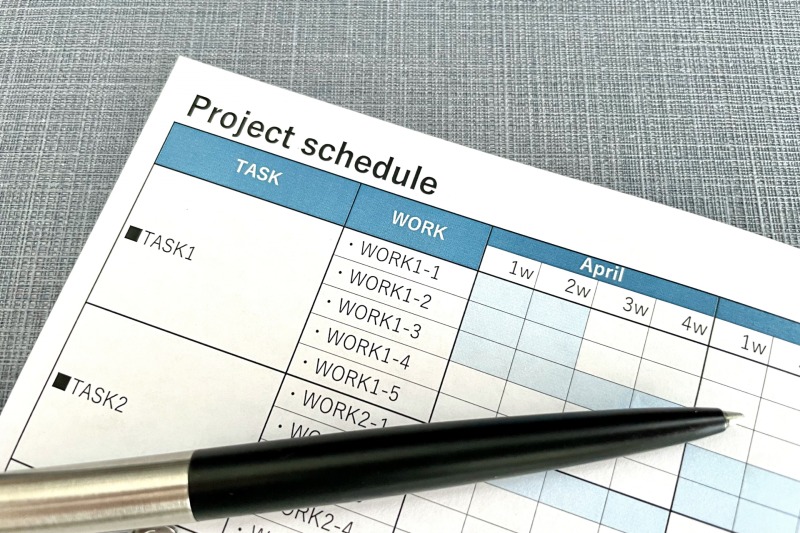
製造業における生産計画の立案方法は、企業が採用する生産方式によって異なります。生産方式は主に「受注生産」と「見込み生産」の2つに分類され、それぞれの特性に応じた計画立案アプローチが必要です。
以下では、それぞれの生産方式における効果的な計画立案の方法について詳しく解説します。
受注生産の場合
受注生産における生産計画は、顧客からの発注内容に基づいて立案します。 製品の特性によって、計画立案のアプローチは大きく「繰り返し生産型」「個別受注生産」の2つに分類されます。
繰り返し生産型
繰り返し生産型は、製品の標準化が進んでおり、同じ仕様で複数回生産することです。この場合、部品調達のリードタイムを考慮し、共通部品の在庫確保を大日程計画や中日程計画に組み込みます。 これにより、受注から納品までの期間短縮と生産効率の向上を実現できます。
個別受注生産
個別受注生産は、顧客ごとに異なる仕様で生産することです。生産計画の立案では、以下の点に注意が必要です。
- 共通部品や半製品の戦略的な在庫保有
- 調達リードタイムの長い部材の事前発注検討
- 生産能力の柔軟な調整体制の確保
特に、個別受注生産では工程や業務フローが複雑化するため、部門間の緊密な連携と情報共有が不可欠です。 生産管理システムを活用し、受注から出荷までの一連の工程を統合的に管理することで、効率的な生産計画の実現が可能です。
見込み生産の場合
見込み生産における生産計画は、精度の高い需要予測を基盤として策定します。 需要予測では、過去の販売実績データや市場のトレンド、顧客の注文傾向などを分析し、将来の需要を予測しましょう。需要予測の手法は主に以下の5つがあります。
- 算術平均法:過去データの単純平均による予測
- 移動平均法:一定期間のデータ平均を移動させる予測
- 指数平滑法:直近データを重視した予測
- 回帰分析法:傾向を数式化する予測
- 加重移動平均法:重要度に応じた重み付け予測
また、需要予測を基に生産計画を立案する際は、以下の要素を考慮しましょう。
- 生産能力と供給体制の整備
- 在庫保管コストの最適化
- 原材料の調達リードタイム
- 生産ラインの稼働率
- 人員配置と稼働時間
特に見込み生産では、需要と供給のバランスが重要です。過剰在庫や在庫不足を防ぐため、市場動向や顧客ニーズの変化に応じて柔軟に計画を修正できる体制を整えることが成功のポイントです。
生産計画を立てるメリット

生産計画の戦略的な立案は、企業の収益性向上と持続的な成長を実現する重要な施策です。適切な生産計画の導入により、以下のように収益向上と経費削減の両面から利益の最大化を達成できます。
|
メリット |
内容 |
効果 |
|
売上向上 |
・納期遵守による顧客満足度向上 ・小ロット生産への柔軟な対応 ・生産能力の最適化による受注機会の拡大 |
売上高の増加 |
|
原価低減 |
・適正在庫による保管コスト削減 ・効率的な人員配置による労務費削減 ・材料調達の最適化による仕入コスト削減 |
製造原価の低減 |
|
品質管理 |
・計画的な設備保全による不良率低減 ・作業標準化による品質安定化 ・トレーサビリティの向上 |
品質コストの削減 |
|
経営効率 |
・経営資源の効率的な活用 ・キャッシュフローの改善 ・意思決定の迅速化 |
経営効率の向上 |
これらのメリットを活かすことで、企業は競争力を高め、市場での優位性を確立できます。特に、需要予測の精度向上と生産リソースの最適配分により、持続的な利益創出が可能です。
生産計画を立てる際に起こりうるリスク・課題

生産を効率的に進めていくためにも生産計画は不可欠です。しかし、業務を効率化し精度も高い生産計画を立案することは簡単ではありません。適切な生産計画を立てるためにも、立案する際のリスク・課題について把握しておくことが重要です。
ここでは生産計画を立てる際に起こりうる2つのリスクと課題についてご紹介します。
適切な資材調達ができず、在庫に過不足が生じる
生産計画を立てる際に起こりうるリスクの1つは、在庫に過不足が生じてしまうことです。
例えば、無理のある販売計画を立ててしまうと、在庫過多に陥ってしまいます。また、低く見積もりすぎてしまった際には在庫が不足してしまい、お客さまへの納品に支障をきたしてしまう可能性もあります。
こういった在庫の過不足を無くすためにも、綿密な生産計画を立てる必要があります。
スケジュールにムリ・ムダが生じる
リスクの2つ目はスケジュールにムリ・ムダが生じてしまうことです。
スケジュールが共有されておらず、工場の生産能力を上回る受注を受けてしまうと、結果納期に間に合わなくなってしまいます。
また、余裕を持たせすぎた標準工程を持っていた場合は、工場のリソースが余ってしまう可能性があります。
工程スケジュールのムリ・ムダを解決する方法は下記記事からご覧ください。
生産計画を最適化するポイント

ムリのない生産計画を立案した後に重要となってくるのはその運用です。ここでは、運用を最適化するポイントについて解説します。
4Mの管理
生産計画を着実に実施するためには、「4M」を確保することが大切です。4Mとは、製造における重要な4つのリソースを指します。
| 人員(Man) | 人的要素のこと。計画通りの生産を実現するために必要な人員数や、求められる技能、工数を把握し、必要に応じて採用や育成を行う。 |
| 設備(Machine) | 製造設備やツール。機械の性能、保守、更新が生産プロセスに直結するため、最適な設備状態を保つための見直しを定期的に行う。 |
| 手順(Method) | 生産プロセスや手順、機械設備の操作方法。生産性を高め、品質を保証するため、効率的で無駄のない作業方法を考え、決定する。 |
| 材料(Material) | 製品の生産に必要な原材料や部品の種類・数量・規格のこと。材料の品質、コスト、供給の安定性が、最終製品の品質とコストに影響を与える。 |
これらのリソースは互いに関連し合っており、一つのリソースの変化が他のリソースに影響を与える可能性があります。したがって、これら4つのリソースをバランス良く管理することが、生産計画において重要です。
生産計画に余裕を持たせる
生産計画においては、常に余裕を設けておくことが重要です。特に製造現場では、設備の不具合や、需要の急激な変動、急な欠員、部品の配送遅延といった、想定外の事態が度々発生します。想定外のトラブルに備えて、生産計画には余裕を持たせましょう。
【在庫のバッファ】
● 目的:供給の遅延や需要の急増に対応するため。
● 設定方法:過去のデータを分析し、通常の需要より若干多めに在庫を持つ。ただし、過剰在庫には注意が必要。
【時間のバッファ】
● 目的:機械の故障や人的エラーなどの予期せぬ遅延に対応するため。
● 設定方法:予定納期よりも前に、余裕を持ったスケジュールを設定。例えば、納期の数日前を目標にする。
【能力のバッファ】
● 目的:急な注文増加や機械のダウンタイムに対応するため。
● 設定方法:生産設備や人員の最大能力を100%とせず、ある程度の余裕を持たせる。例えば、最大能力の80%程度で運用する。
これらのバッファは、リスク管理の一環として設けることが大切です。しかし、先述の通り、バッファを大きくしすぎるとコストが増加する可能性もあるため、適切なバランスを見極めることが重要です。過去のデータ分析や市場動向の把握を通じて、柔軟かつ効率的な生産計画を立てましょう。
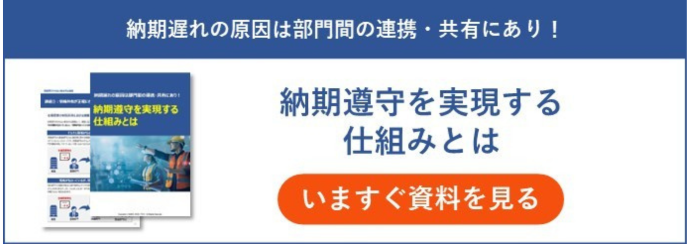
中長期的な計画を定期的に見直す
中長期的な生産計画を定期的に見直すことは、計画の精度を高め、変化する市場環境や生産現場の状況に柔軟に対応するために不可欠です。中長期的な計画を周期的に見直して部分的に修正する、このプロセスは「ローリングプラン」と呼ばれ、以下のポイントが重要です。
ローリングプランの実施方法
1.周期的な見直し
大日程計画(3カ月〜1年)を例えば毎月または2カ月ごとに見直します。これにより、計画と実態のズレを防ぎます。
2.修正の反映
大日程計画の修正は、中日程計画(1〜3カ月)や小日程計画(1週間〜1カ月)にも反映されます。これにより、全体の計画の連続性が保たれます。
3.柔軟な対応
市場の変化や需要の変動に迅速に対応できる体制を整えます。例えば、新製品の導入や既存製品の改良計画を修正する際に、ローリングプランが役立ちます。
ローリングプランのメリット
|
メリット |
内容 |
|
計画の精度向上 |
定期的な見直しにより、計画と実態のズレを防ぎ、精度を高める |
|
柔軟な対応能力 |
市場や需要の変化に迅速に対応できる体制を整えられる |
|
リスク低減 |
不確実性に対するリスクを低減し、安定した生産活動が可能 |
|
効率的なリソース配分 |
修正された計画に基づいて、人員や設備の最適な配分が可能 |
このように、ローリングプランを活用することで、生産計画はより現実的かつ柔軟なものとなり、企業の競争力を高められます。
工場内サイネージを活用する
生産目標や進捗情報、伝達事項の共有などを効率的に行いたい場合には、工場内サイネージの活用がおすすめです。サイネージとは、ディスプレイに情報を発信できるシステムで、情報発信のツールとして使用されます。
工場では、従業員が個別にPCを持たず、情報の伝達が朝礼や掲示物に限られがちです。しかし、サイネージを利用することで、リアルタイムでの情報共有が可能になり、工程の前後の情報など、作業員が常に最新の情報を得られる状態になります。緊急事態が発生した際にも、即座に重要な指示や警告を全従業員に伝えることができ、迅速な対応ができます。
ツールを活用する
生産計画の最適化には、専門的なツールの活用が不可欠です。2025年において、生産計画ツールは年率8%で市場が拡大しており、製造業のデジタル化を加速させています。生産計画ツールの活用により、以下の効果が期待できます。
- リアルタイムでの進捗管理と可視化
- 需要予測の精度向上
- リソース配分の最適化
- 作業負荷の平準化
- データに基づく意思決定の実現
特に近年は、AIを活用した生産計画ツールの導入が進んでおり、熟練作業員の経験やノウハウをデジタル化することで、労働環境の改善や業務効率の向上を実現可能です。また、生産スケジューラの導入により、受注状況や在庫状況、製造リソースの可用性を考慮した最適な生産計画の自動作成が可能です。
製造業における人手不足や需要変動への対応が求められる中、生産計画ツールの活用は企業の競争力強化に直結します。次章では、具体的な生産管理システムやツールの種類と、その選定方法について詳しく解説します。
生産計画の管理に活用できるツール

生産計画の管理には、さまざまなツールが活用されています。これらのツールは、計画の精度を高め、効率的な運用を実現するために不可欠です。特に、現代の製造業では、技術の進化に伴い、生産計画ツールも多様化し、企業のニーズに応じた選択肢が増えています。
以下では、各ツールの特徴や活用方法について詳しく解説します.。自社の生産体制に最適なツールを選択する際の参考にしてください。
生産スケジューラ
生産スケジューラは、製造工程の詳細な日程計画や資源配分の立案などをするためのツールです。製造現場の複雑な要件を考慮しながら、以下のような効率的な生産計画の立案を支援します。
|
支援内容 |
詳細 |
期待される効果 |
|
計画立案 |
・自動スケジューリング ・ドラッグ&ドロップでの調整 ・制約条件の考慮 |
・計画作成時間の短縮 ・人的ミスの削減 ・最適な工程設計 |
|
リソース管理 |
・設備稼働状況の把握 ・作業者の配置管理 ・負荷状況の可視化 |
・設備稼働率の向上 ・人員配置の最適化 ・過負荷の防止 |
|
時間管理 |
・工程別所要時間の算出 ・リードタイムの予測 ・ボトルネックの特定 |
・納期精度の向上 ・生産性の向上 ・工程改善の促進 |
特に、AIを活用した最新の生産スケジューラでは、過去の実績データを分析し、より精度の高い計画立案が可能です。 生産スケジューラを活用することで、製造現場のデジタル化と生産効率の向上を同時に実現できます。
生産管理システム
生産管理システムは、製造業の基幹システムとして、原材料の調達から製品の出荷まで、生産活動全体を包括的に管理するプラットフォームです。以下のような生産に関わるさまざまな業務プロセスを統合し、経営効率の向上を実現します。
|
管理内容 |
機能 |
業務効果 |
|
生産計画 |
・需要予測 ・資材所要量計画 ・工程計画 |
・計画精度の向上 ・リードタイムの短縮 ・生産効率の向上 |
|
在庫管理 |
・原材料管理 ・仕掛品管理 ・製品在庫管理 |
・在庫の適正化 ・保管コストの削減 ・欠品リスクの低減 |
|
原価管理 |
・製造原価計算 ・コスト分析 ・収益管理 |
・コスト削減 ・利益率の向上 ・経営判断の迅速化 |
生産スケジューラが製造現場の詳細な工程管理に特化しているのに対し、生産管理システムは製造プロセスの計画、実行、監視に特化したシステムです。生産現場のリアルタイムデータを活用し、製造工程の最適化と品質管理の強化を実現します。
PERT図
PERT図は、生産工程の関連性と所要時間を視覚的に表現する管理ツールです。複数の順序が決まっている作業を、アローダイアグラムを用いて可視化し、最適な工程計画を立案するためのツールです。PERT図は、以下のような効果が期待できます。
|
管理内容 |
効果 |
業務改善への貢献 |
|
工程管理 |
・工程間の依存関係の明確化 ・所要時間の可視化 ・ボトルネックの特定 |
・生産効率の向上 ・リードタイムの短縮 ・工程改善の促進 |
|
進捗管理 |
・リアルタイムの状況把握 ・完了予定時期の予測 ・遅延リスクの早期発見 |
・生産計画の最適化 ・納期管理の精度向上 ・問題の早期対応 |
PERT図の特徴は、3つの時間見積もり(最早開始時刻、最遅開始時刻、余裕時間)を用いることで、より現実的な工程計画を立案できる点です。この手法により、生産現場の不確実性を考慮した精度の高い計画策定が可能です。
特に複数の工程が並行して進行する複雑な生産活動において、PERT図は効果を発揮します。工程間の相互依存関係を明確にし、最適な生産スケジュールの策定を支援することで、生産効率を向上させましょう。
ガントチャート
ガントチャートは、生産計画の進捗状況を視覚的に表現する棒グラフ形式の管理ツールです。縦軸に生産リソース、横軸に時間軸を配置し、作業の流れを棒グラフで表現します。1910年代にヘンリー・ガントによって考案され、現在では製造業における標準的な生産管理ツールとして広く活用されています。ガントチャート活用によるメリットは以下のようなものが挙げられます。
- 生産工程の全体像を一目で把握
- リソースの効率的な配分が可能
- 工程間の依存関係を明確化
- スケジュール調整の柔軟性向上
- チーム間のコミュニケーション促進
特に近年は、デジタル化によりリアルタイムでの更新や複数プロジェクトの統合管理が可能となり、より効果的な生産計画の立案と実行を支援しています。
生産管理システム活用のメリット

生産管理システムは、製造業において生産活動全体を効率的に管理するための重要なツールです。このシステムを活用することで、企業は多くのメリットが得られます。以下では、生産管理システムの主なメリットについてご紹介します。
情報を一元管理できる
生産管理システムを導入することで、工数、実績、販売、製造などの情報をリアルタイムで部門を超えて共有することが可能です。これにより、組織全体の効率化と基盤強化が図られ、リードタイムの短縮につながります。
生産計画の精度が向上する
生産管理システムは、販売計画や受注予測に基づいて、生産能力を考慮した効率的な計画を立案します。受注生産計画機能を使えば、受注データと在庫データを基にして、必要な量を正確に生産計画に反映することも可能です。また、見込み生産計画機能を使えば、過去の生産実績を分析し、将来の需要を予測して計画を立てられます。
生産管理システムは多角的なデータを活用して精密な計画を作成できるため、無駄な生産を減らし、需要に即応する生産体制を築けます。
属人化を防げる
最適な生産計画を立てるには知識や経験が必要です。そのため、生産計画は属人化しているケースが多いです。しかし、生産管理システムを導入することで、計画業務が自動化され、個人の知識や経験に依存することなく、適切な計画を立案できます。
これにより、担当者が不在でも業務の継続が可能になり、組織全体の生産効率と安定性が向上します。人手不足に悩まされる製造業には、特に属人化解消は必須です。
生産管理システムの選び方については、下記記事をご覧ください。
生産管理システムの選び方

生産管理システムの導入は、製造業の生産性向上と競争力強化において重要な戦略的投資です。しかし、システムの選定には慎重な検討が必要です。以下では、生産管理システム選定の重要なポイントについて詳しく解説します。
自社にあった形態を選ぶ
生産管理システムの導入形態は、企業の規模や業務特性、投資予算に応じて適切に選択する必要があります。主要な導入形態には以下の3つがあります。
|
導入形態 |
特徴 |
適している企業 |
|
オンプレミス型 |
・自社サーバーでの運用 ・高度なカスタマイズ性 ・完全な管理権限 |
・大規模製造業 ・セキュリティ要件が厳格な企業 ・特殊な業務要件がある企業 |
|
クラウド型 |
・低い初期投資 ・迅速な導入 ・柔軟なスケーリング |
・中小規模製造業 ・複数拠点での利用 ・コスト重視の企業 |
|
パッケージ型 |
・導入期間が短い ・実績のある機能を利用可能 ・カスタマイズに制限あり |
・中規模製造業 ・標準的な業務フローの企業 ・早期導入を目指す企業 |
特に製造業のDX推進において、クラウド型システムの採用が増加傾向です。これは、初期投資の抑制とともに、リモートワークへの対応やデータ活用の容易さが評価されているためと言われています。
機能で選ぶ
個別受注生産における生産管理システムの機能選定は、顧客ごとの仕様に合わせた柔軟な対応が可能なシステムを選ぶことが重要です。個別受注生産では、多種多様な製品を少量生産するため、特に以下の機能を重視する必要があります。
|
項目 |
重要機能 |
重視する項目 |
|
設計情報管理 |
・BOM(部品表)の柔軟なカスタマイズ ・設計変更への迅速な対応 ・部品表(BOM)管理 |
顧客ごとの仕様変更に柔軟に対応できること |
|
工程管理 |
・個別案件ごとの進捗管理 ・リアルタイムな情報共有 |
各案件の状況を正確に把握し、遅延を防止できること |
|
原価管理 |
・案件ごとの正確な原価計算 ・収益性の分析 |
個別案件の収益性を正確に把握できること |
システム選定時は、基本機能(受注管理、在庫管理、工程管理)に加え、業界特有の要件に対応できる機能の有無を確認しましょう。特に、設計情報管理機能は、顧客ごとの細かな仕様変更に柔軟に対応するために不可欠です。これらの機能を確認することで、個別受注生産におけるより効果的な生産管理が実現できます。
サポート体制で選ぶ
生産管理システムの成功的な導入と運用には、充実したサポート体制が不可欠です。システムの機能性だけでなく、導入後の継続的なサポートを重視した選定が重要です。システム選定時には、以下のような項目に注目して選定しましょう。
- 24時間対応の可否
- 現地サポート体制の有無
- リモートサポートの充実度
- 定期的な運用診断の実施
- カスタマイズ要望への対応力
特に製造業では、システム停止が生産活動に直接影響するため、迅速な問題解決と安定的な運用を支えるサポート体制の確保が重要です。
生産管理システムの活用でムリ・ムダのない生産計画を立てよう

これまで紹介したポイントを押さえ、ムリ・ムダのない生産計画を立案しても、想定外の事態に見舞われてしまうことが多いです。
全体の納期をしっかり守り、生産計画にもムリ・ムダがないよう都度調整をかけるためには、いま各工程・部署で何がおこなわれているのかを、リアルタイムに・正確に把握できている状態が必要です。
当社では、生産管理システム「rBOM」を提供しています。ムリ・ムダのない生産計画を属人化することなく正確に立てたい企業様はぜひ製品資料や詳細ページをご覧ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓
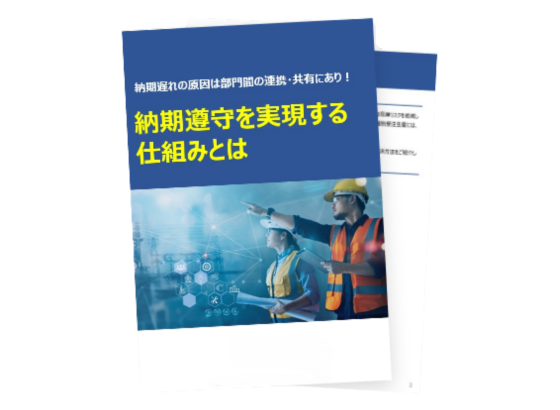
納期遅れの原因は部門間の連携・共有にあり!
納期遵守を実現する仕組みとは

- この記事を監修した人
- 入社後15年間、長野支店にてシステムエンジニアとして活動。
運送業、倉庫業のお客さまを中心に担当し、業務システム構築からインフラ環境構築等の経験を積む。
その後、製造業のお客さまも担当し、rBOM導入のプロジェクトにも関わるように。
16年目に現部門に異動し、rBOM全国支援の担当者となる。
現在はrBOMだけではなく、製造業全般のソリューション提案を手掛けている。
料理が趣味、これからお菓子作りにも挑戦しようか迷っている。 - DAIKO XTECH株式会社
ビジネスクエスト本部
インダストリー推進部 - 田幸 義則