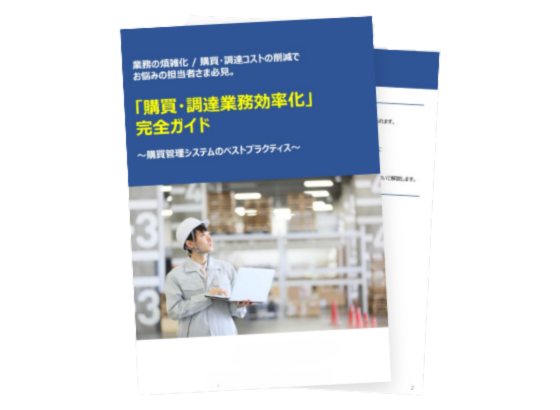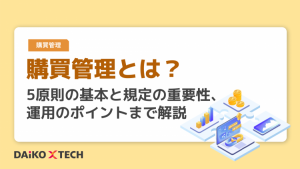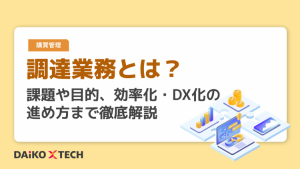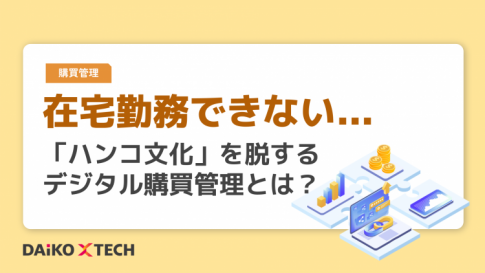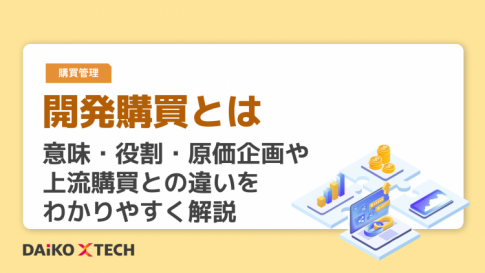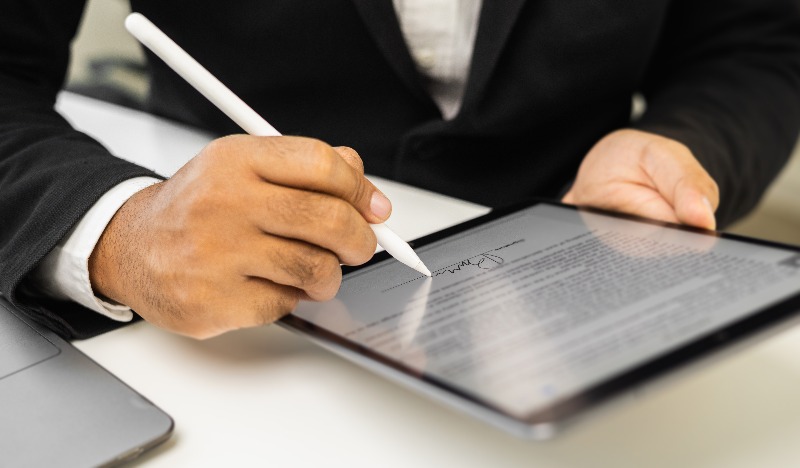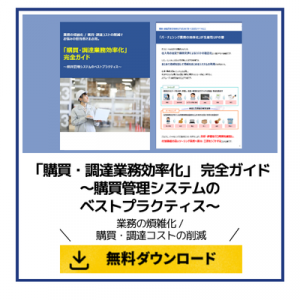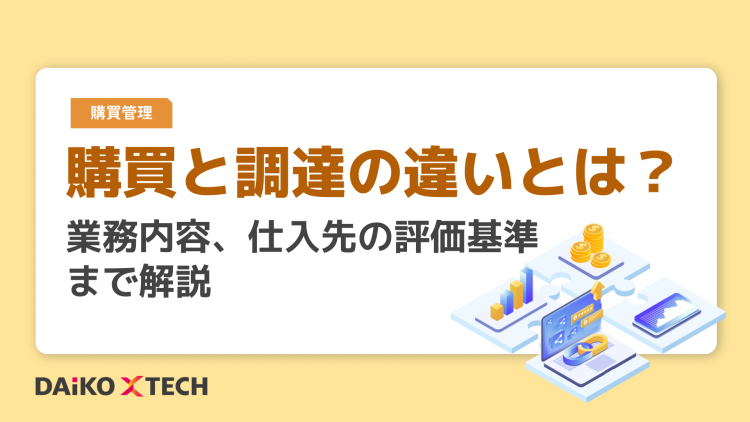 製造業では「部品を購入する」「部品を調達する」というように、購買と調達が似た言葉としてよく使われます。普段何気なく使われている2つの言葉ですが、厳密には意味合いが異なる言葉です。今回は、製造業において「購買」と「調達」が指す意味範囲の違いや現場の業務内容の違いを説明し、最後に、購買・調達業務双方で重要な「仕入先評価基準(選定基準)」について解説します。
製造業では「部品を購入する」「部品を調達する」というように、購買と調達が似た言葉としてよく使われます。普段何気なく使われている2つの言葉ですが、厳密には意味合いが異なる言葉です。今回は、製造業において「購買」と「調達」が指す意味範囲の違いや現場の業務内容の違いを説明し、最後に、購買・調達業務双方で重要な「仕入先評価基準(選定基準)」について解説します。

目次
購買と調達とは

企業活動において、必要な資材やサービスを効率的に入手することは不可欠です。本章では、この重要な機能を担う「購買」と「調達」について詳しく解説します。両者の定義や役割、そして企業経営における重要性を理解することで、ビジネスの効率化と競争力向上につなげましょう。
購買とは
購買とは、生産に必要な資材を外部から効率的に入手する活動です。
JIS規格(日本産業規格)の定義では、購買(管理)は「生産活動にあたって、外部から適正な品質の資材を必要量だけ、必要な時期までに経済的に調達するための手段の体系」※と説明されています。
つまり、必要な品質、量、タイミング、コストで資材を入手することが購買の目的です。
そのため、購買業務では、製品の資材の購買計画立案から、仕入先(サプライヤ)選定、発注、受入といった一連の調達業務が管理の対象となります。これらを最適化することで、製品の品質担保や納期通りの生産、業務効率化、そして利益率の向上などが期待できます。
※出所:日本規格協会「JIS Z8141:2001 生産管理用語」
購買管理の重要性や効果については、以下の記事で詳しく解説しています。
調達とは
調達という用語には「必要なものを整える、要求者に届ける」という意味があり、購買も含め、要求者に届けるまでが業務にあたります。したがって、調達は購買を包括する表現だといえます。
調達業務では、モノを購入する業務だけでなく、資材の発注から納入までに関わる「ヒト」「カネ」を適切に管理する業務も含まれます。適切な仕入先を選定したり、資材の発注から納入までのサイクルが円滑に進むよう各部門の業務のタイミングを調整したりするなど、購買活動を包括した幅広い業務を行うことが特徴です。そのため、生産計画を滞りなく進めるために非常に重要です。
以上、購買業務と調達業務の違いについて解説しました。次に、購買部門の基本的な業務内容について詳しく見ていきましょう。
また、調達業務の内容や、調達管理の効果を高めるためのポイントについては、以下の記事でも取り上げています。
購買部の基本業務

購買部門の基本となる業務は、見積、発注、検収の3つです。これらの業務を適切に遂行することで、企業の経営効率を高め、コスト削減や品質管理に貢献します。各業務の詳細と重要性について、以下で説明します。
見積
見積は購買の第一歩であり、適切な仕入先と価格を決定する重要な過程です。
見積業務では、複数の仕入先から見積書を取得し、比較検討を行います。この際、単に価格だけでなく、品質、納期、アフターサービスなども考慮に入れます。
見積の精度を高めるために、仕入先との交渉スキルも重要です。また、市場動向や原材料価格の変動なども把握し、適切な見積評価を行うことが求められます。正確な見積は、後の発注や予算管理の基礎となるため、慎重に行わなければいけません。
発注
発注は、見積で決定した内容を実際の購買行動に移す重要なステップです。
発注業務では、必要な物品やサービスの詳細を明確に指定し、正式な発注書を作成します。発注書には、品目、数量、価格、納期、支払条件などの重要事項を漏れなく記載します。
また、発注のタイミングも重要で、在庫状況や生産計画を考慮して適切なタイミングで行わなければいけません。緊急発注や定期発注など、状況に応じた発注方法を選択することも大切です。
発注後は、進捗管理を行い、納期遅延などの問題が発生しないよう注意を払います。
検収
検収は、発注した物品やサービスが適切に納入されたかを確認する最終段階です。
検収業務では、納入された物品が発注時の仕様や品質基準を満たしているかを厳密にチェックします。数量、品質、納期などを確認し、問題がある場合は速やかに仕入先に連絡し、対応を求めなければいけません。
また、検収結果を正確に記録し、支払いの根拠とするとともに今後の仕入先評価にも活用します。適切な検収は不良品の混入を防ぎ、製品品質の維持に貢献します。さらに、検収データの分析により、仕入先の信頼性評価や購買プロセスの改善にも役立てることができます。
購買・調達の業務の違い
 調達は購買を内包している表現であること、また購買部の基本的な業務が理解できたかと思います。それでは、実際に購買管理と調達管理では、業務内容にどのような違いがあるのでしょうか。
調達は購買を内包している表現であること、また購買部の基本的な業務が理解できたかと思います。それでは、実際に購買管理と調達管理では、業務内容にどのような違いがあるのでしょうか。
それぞれの役割を理解することで、業務上のコミュニケーションエラーを減らすことにもつながります。
購入以外の手段で物品を入手するか
購買業務では資材の購入を前提としていますが、調達業務では、機材のリースなどを行うこともあります。調達業務では、生産計画を滞りなく進行させるという目的があるため、購入に限らず、複数の調達手段を視野に入れ、その時々に合った方法を選定します。
納品物の品質や期日を管理するか
調達業務は、購買業務よりも広い範囲を管理します。
購買業務は、モノの購買が滞りなくできるよう管理するのに対し、調達業務では納品物が調達し終わるまでを管理することが不可欠です。納品までの責任を負うため、「購入したモノが欠陥なく、期日通りに納品されているか」までを気にかけて仕事を行います。
本章では、購買業務と調達業務の違いについて解説しました。次章では、どちらの業務でも重要な指標となる「仕入先の評価基準」についてご紹介します。
購買・調達業務における仕入先の評価基準
 仕入先の選定・評価は、購買・調達部門の重要な業務の一つです。
仕入先の選定・評価は、購買・調達部門の重要な業務の一つです。
製造業では良い資材を低価格で継続的に仕入れることが不可欠であり、購買・調達部門はそのために新規仕入先の選定や、既存仕入先との価格交渉を行います。
しかし、この調達プロセスや評価基準が担当者によって異なる場合があり、仕入先の選定によって生産プロジェクトが左右されるため、調達プロセスや評価基準は内部で一貫性をもたせることが大切です。
本章では、仕入先の選定で重要な3つの指標と、それらの評価基準をご紹介します。誰が担当しても最適な仕入先を選定できるよう、以下の3つを評価基準としてマニュアル化しましょう。
品質
新規仕入先を開拓する際に、品質を慎重に検討するご担当者様は多いはずです。しかし、品質面に関しては、既存の取引先から新しい部品を仕入れる場合も注意が必要です。
「いつもお願いしているから大丈夫だろう」と判断するのではなく、部品ごとに品質保証部門と掛け合い、仕様書を作成してもらうことで、品質を担保してもらうことも重要です。
部品や資材の品質を見極める際は、どのような製造プロセスを辿っているのか、品質管理体制はどうなっているかまで、しっかりと確認するようにしましょう。
価格
仕入れの際は、部品すべてに100%の品質を求めると同時に、コストを抑えることが重要です。
一般的に「高品質で低コスト」の仕入れは実現しにくい傾向にあります。しかし、価格交渉を行うことで少しでも仕入れコストを下げることができれば、企業の利益獲得に貢献することが可能となります。
一方で、品質が担保されていない部品を使用すると、後に欠陥等のトラブルを誘発する恐れがありますので、そのような仕入れは避けましょう。
納期
購買・調達管理部門では、仕入先の生産状況を把握、管理し、仕入先と協業して納期短縮を目指すことも大切です。
大量生産で製品機械を製造する場合は、毎回決まった部品を仕入れることが多いため、納期も安定しやすいと言えます。しかし、個別受注生産で製造する場合、扱う部品の種類がその時々で変わるため、より注意して調達しなければ納期に間に合わなくなる可能性が生じてしまいます。
納期に間に合わせるためには、調達業務が滞りなく行われる以外に、仕入先の生産能力も関わってきます。納期が遅い仕入先は生産能力が不足している可能性があり、不足分を外注しているケースもあります。その場合は、品質が均一でないなど、納期以外の問題も発生するリスクがあるため、同じコストをかけるのであれば、一か所で生産を完結させられる仕入先を選ぶ方が賢明といえます。
このような仕入先の評価基準をはじめ、サプライヤ管理を行ううえでのポイントについては、以下の資料で詳しく解説しています。
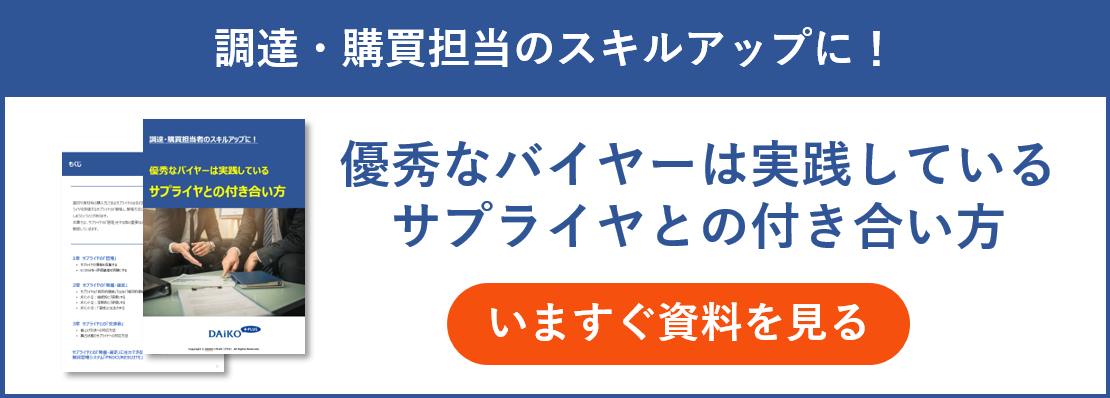
購買・調達業務の違いを理解して正しく管理しましょう
 今回は、購買と調達の意味や違い、仕入先の評価基準について解説しました。
今回は、購買と調達の意味や違い、仕入先の評価基準について解説しました。
購買と調達は用語としての意味合いは異なりますが、業務上で意識すべき点は共通しています。どちらもお客さまに品質や納期を保証することが業務の核であり、また業務の無駄をなくすことで、コスト削減、納期短縮、品質向上を期待できます。
しかし、購買・調達業務は単に工数が多いだけでなく、煩雑化していることが多く、なかなか抜本的な体制変更や効率化といった改善を行えないケースも多くみられます。そのような場合は、購買・調達業務を効率化するシステムの導入がおすすめです。
以下の資料では、製造業における購買・調達管理業務の効率化をサポートする、DAIKO XTECHの購買管理システム「PROCURESUITE」について紹介しています。具体的な機能や導入効果を一度確認してみたい方は、ぜひご覧ください。
おすすめのお役立ち資料はこちら↓